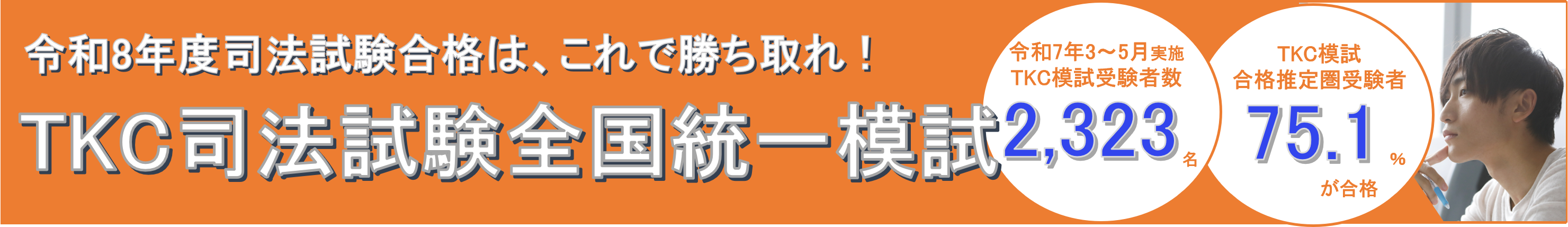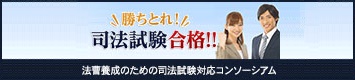- 模試チャレンジ成績
-
「模試チャレンジ」で出題中の全問題を母数に、科目別・正解率別で今の自分の実力を確認できます
成績表示: -
科目別憲法民法刑法
-
模試受験生の正解率別(80%以上)(79.9~50%)(49.9%以下)
昨年度のTKC模試を解いて現状の実力確認
「 形式」で出題します。
模試受験生の正解率と照らして、今の自分の実力をぜひお試しください
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第14条第2項は、華族その他の貴族の制度を禁止しているが、これは同条第1項後段の列挙事由の1つである、「門地」による差別禁止の当然の帰結であるといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 62.3%結果正解解説憲法14条2項は、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と規定して、華族をはじめとする貴族制度を禁止している。従来の華族は、爵位が付与され、また貴族院議員に就任するなどの特権を付与されていた。同項は、これらの貴族制度を廃止することを明確にしたものであり、将来にわたり、その名称を問わず華族をはじめとする貴族制度を創設することを禁止する趣旨である。そして、貴族は、先天的な原因によって認められる特権的身分であるため、「門地」(同条1項後段)に当たることになり、貴族制度の廃止は、「門地」による差別禁止の当然の帰結であるとされる。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)145頁。
佐藤幸(日本国憲法論)232頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)300頁。
芦部(憲法学Ⅲ)53~54頁。
注解憲法Ⅰ322頁、330頁。 -
民法債権の売主は、特約がなくても、契約の時における債務者の資力を担保する責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 58.3%結果正解解説債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定される(民法569条1項)。債権が売買の目的とされた場合において、売主は、債権の存在については責任を負うが、債務者の資力については、当然に契約の内容になっているとはいえず、当事者間に債務者の資力を担保する旨の特約がある場合にのみ責任を負うという考え方を基礎として、資力の担保の特約がされた場合に関する推定規定を設けたものである。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)110頁。
中田(契約)316頁。
新・コンメ民法(財産法)976頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、強盗事件を犯して逃亡中のAを、その事情を知りながら自宅にかくまったが、かくまった時点では、既にその強盗事件の公訴時効が完成していた。この場合、甲には犯人蔵匿罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 67.6%結果正解解説犯人蔵匿罪(刑法103条前段)は、刑事司法作用を妨害する行為の処罰を目的とするものであるから、無罪や免訴判決のあった者、公訴時効の完成によって訴追又は処罰の可能性がなくなった者は同罪の客体とはならない。したがって、甲には犯人蔵匿罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考西田(各)481~482頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)497頁。
条解刑法335~336頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所は、市町村長は、原則として転入届を受理しなければならないが、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合には、これを受理しないことが許されるとした。憲法この問題の模試受験生正解率 31.4%結果正解解説判例は、ある宗教団体の信者が転入届を政令指定都市内の区の区長に提出したが、区長が受理しなかったため、当該不受理処分の取消し及び国家賠償を請求した事例において、「住民基本台帳は、これに住民の居住関係の事実と合致した正確な記録をすることによって、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするものであるから」、区長は、転入届が提出された場合には、その者に新たに当該区の区域内に住所を定めた事実があれば、法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されないとした上で、上告人(区長)の「地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合には、転入届を受理しないことが許される」という主張は「実定法上の根拠を欠く」としている(最判平15.6.26 地方自治百選〔第5版〕16事件)。よって、本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)332頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、見ず知らずの他人から盗み出した印章と登記関係書類を用いて委任状を偽造し、その他人の代理人と称して行為をした場合、代理権授与の表示による表見代理が成立し得る。民法この問題の模試受験生正解率 81.8%結果正解解説代理権授与の表示による表見代理の成立には、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した」こと(民法109条1項本文)が必要である。見ず知らずの他人から印章や登記関係書類を盗み出し、委任状を偽造している本記述においては、第三者に対して他人に代理権を与えた旨の表示がないので、代理権授与の表示による表見代理は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)271頁。
平野(総則)320頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、宝石数十点が入っている施錠された丙所有のアタッシュケースを乙に届けるように丙に依頼され手渡されたが、自分の生活費のために同ケースに入っている宝石数点を換金しようと考え、丙に無断で同ケースの施錠を解き、宝石数点を取り出してポケットに入れた。この場合、甲には、窃盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 61.6%結果正解解説判例は、他人所有の施錠されたバッグの保管を依頼されるも、在中している衣服を盗んだ被告人の行為が何罪となるか問題となった事例において、「被告人が他人からその所有の衣類在中の繩掛け梱包した行李1個を預り保管していたような場合は、所有者たる他人は行李在中の衣類に対しその所持を失うものでないから、被告人が他から金借する質種に供する目的で擅に梱包を解き右行李から衣類を取出したときは、衣類の窃盗罪を構成し横領罪を構成しない」としている(最決昭32.4.25 刑法百選Ⅱ〔第2版〕26事件)。本記述では、アタッシュケースに在中する宝石について、丙の占有を失われないところ、甲はこれを自分のものにしようと考え、丙に無断で同ケースの施錠を解き、宝石を取り出しポケットに入れている。したがって、甲には、窃盗罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考西田(各)160頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)130~140頁。
条解刑法738頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法には閣議に関する明文の規定はなく、その運営の仕方は内閣の自主的判断に委ねられているところが大きいものの、内閣の一体性を図る趣旨から、会合しないで文書を大臣間で持ち回って署名を得る、いわゆる持回り閣議は認められないとされている。憲法この問題の模試受験生正解率 64.4%結果正解解説憲法は、内閣の職権行使の手続について明示しておらず、内閣法4条1項が「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と規定しているものの、閣議の定足数及び議決方法については、内閣法上も規定がなく内閣の自主的判断に委ねられている。そして、一般に、閣議の議決については、内閣の一体性や国会に対する連帯責任(憲法66条3項)を根拠に、全員一致によるという慣習が成立しているとされる。また、閣議の形態としては、定例閣議、臨時閣議、持回り閣議(閣僚が実際に会同することなく、閣議案件を記した閣議書を各閣僚に回覧してその押印をもって閣議決定とする方法)がある。よって、本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)218~219頁。
佐藤幸(日本国憲法論)539頁。
新・コンメ憲法571~572頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、債務不履行があっても、債権者がその債務に係る強制執行をしない旨の合意は、有効である。民法この問題の模試受験生正解率 75.5%結果正解解説債務者の財産が債務の引当てになることを責任といい、債務は、責任を伴うのが原則である。もっとも、判例は、強制執行をしない旨の特約がある場合、その債権に基づいて給付判決を得ることはできるが、強制執行をすることはできないとして、強制執行をしない旨の合意の有効性を認め、いわゆる責任なき債務の成立を肯定している(最判平5.11.11 民訴法百選〔第3版〕A30事件、最決平18.9.11 執行・保全百選〔第3版〕1事件参照)。よって、本記述は正しい。
なお、前掲最決平18.9.11は、「強制執行を受けた債務者が、その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には、執行抗告又は執行異議の方法によることはできず、請求異議の訴えによるべき」としている。参考内田Ⅲ131頁。
潮見(新債総Ⅰ)359頁。
中田(債総)82頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を積極的に利用する意思が必要である。刑法この問題の模試受験生正解率 84.5%結果正解解説判例は、不作為による現住建造物等放火罪(刑法108条)の成否が問題となった事例において、不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思が必要だとの被告人側の上告趣意に対し、既発の火力により建物が焼損することを認容する意思で足りるとし、本件では、被告人に消火措置を採るべき法的作為義務があったこと、及び消火措置を採ることが容易であったことを理由に、同罪の成立を認めている(最判昭33.9.9 刑法百選Ⅰ〔第8版〕5事件)。したがって、既発の火力を積極的に利用する意思が認められなくても不作為による放火罪は成立し得る。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)83~84頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)87~88頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法は、政教分離規定を設けるに当たり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 60.9%結果正解解説判例は、市の主催する体育館の起工式が、神社の神職主宰の下、神式にのっとって挙行され、その費用が公金から支出されたことが、憲法20条3項、89条に違反するか否かが争われた事例において、「憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである」としている(最大判昭52.7.13 津地鎮祭事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕42事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合において、Bの承認後にAが相続財産に属する不動産を売却し、その代金を遊興費に充てて費消したときは、Aは単純承認をしたものとみなされる。民法この問題の模試受験生正解率 50.3%結果正解解説相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産を私に消費した場合には、その相続人は単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認 民法921条3号本文)。このような相続人に限定承認や相続放棄の利益を受けさせる必要がないからである。もっとも、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでないとされる(同号ただし書)。新たに相続人となった者の保護を図る必要性があるからである。したがって、Aの相続放棄により相続人となったBが相続の承認をした後に、Aが相続財産に属する不動産を売却し、その代金を遊興費に充てて費消している本記述においては、Aは単純承認をしたものとみなされない。よって、本記述は誤りである。参考潮見(詳解相続法)107~109頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)274~275頁。
新基本法コメ(相続)166~167頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、他人を教唆して自己が犯した強盗被疑事件に関する証拠を偽造させた。この場合、甲には証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 67.6%結果正解解説証拠偽造罪(刑法104条前段)の客体は、「他人の刑事事件に関する証拠」であるところ、本記述において、甲は、自己が犯した強盗被疑事件に関する証拠を偽造させていることから問題となる。判例は、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を偽造させた場合、証拠偽造罪の教唆犯(同条前段、61条1項)が成立するとしている(最決昭40.9.16)。したがって、甲には証拠偽造罪の教唆犯が成立する。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)602頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)508~509頁。
条解刑法340頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば、地方議会にも国会と同様の広範な自律権が認められているから、地方議会議員の発言についても、国会議員と同様、憲法上免責特権が保障されている。憲法この問題の模試受験生正解率 84.1%結果正解解説判例は、地方議会の議事進行に関し公務執行妨害罪の成否が問題となった事例において、「憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといって、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」としている(最大判昭42.5.24 地方自治百選〔第4版〕69事件)。よって、本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)105頁。
-
民法配偶者短期居住権が成立するためには、配偶者が相続開始前から、被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居していたことが必要である。民法この問題の模試受験生正解率 30.6%結果正解解説配偶者短期居住権は、配偶者が、被相続人所有の建物に相続開始時に無償で居住していた(かつ現在も居住している)場合に認められる(民法1037条1項柱書本文)。配偶者の居住権を短期的に保護するために認められた権利であることから、長期的な保護を目的とする配偶者居住権が遺産分割や遺贈によって取得される(同1028条1項)のと異なり、要件を満たす限り、相続開始時に当然に発生する。
配偶者短期居住権は、相続開始の時に配偶者が無償で居住し、かつ、現在も居住している被相続人所有の建物について成立する(民法1037条1項)。配偶者が被相続人死亡時に被相続人が所有していた居住建物に居住していることが認められれば足り、同建物において被相続人と同居していたことは要件とされていない。よって、本記述は誤りである。
なお、平成30年民法改正により配偶者短期居住権が創設される前の判例は、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される」としている(最判平8.12.17 民法百選Ⅲ〔第3版〕63事件)。配偶者短期居住権が創設された現在においては、上記推定は、配偶者以外の相続人について適用されることになる。参考前田陽ほか(民法Ⅵ)366~368頁。
窪田(家族法)550頁。
潮見(詳解相続法)398~399頁、403頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、罰則を定めた特別法上の法条に、「過失により」との明文の規定がない場合であっても、過失犯として処罰されることがある。刑法この問題の模試受験生正解率 68.6%結果正解解説過失犯は、「法律に特別の規定がある場合」に限り処罰される(刑法38条1項ただし書)。もっとも、判例は、罰則を定めた特別法上の法条に、「過失により」との明文がなくても、過失犯を処罰する趣旨が読み取れる場合には、過失犯として処罰することを認めている(最決昭57.4.2 刑法百選Ⅰ〔第6版〕49事件参照)。よって、本記述は正しい。
なお、学説上は、罪刑法定主義の要請から、法文解釈から導き出すことができるものであることが必要であるとするものが多い。参考山口(総)242頁。
今井ほか(総)147~148頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国会の発議した憲法改正案を国民が承認することにより、憲法改正は成立するが、この承認は、国民が特定の規範内容について直接賛否の意思を表明する機会であり、ことのついでに行うものではないことから、国政選挙の際に行われる投票ではなく、特別の国民投票においてなされなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 60.4%結果正解解説国会の発議した憲法改正案を国民が承認することによって、憲法改正は成立する。国民の承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる(憲法96条1項後段)。つまり、「特別の国民投票」、「国会の定める選挙の際行はれる投票」のいずれの方式で行ってもよい。よって、本記述は誤りである。
なお、日本国憲法の改正手続に関する法律は、専ら前者の「特別の国民投票」を前提としている。参考芦部(憲法)421頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)157頁。
新基本法コメ(憲法)503頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、Aの所有する甲建物が未登記のままAからBに譲渡された場合、Bは、Aに対し、所有権移転登記手続を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説判例は、未登記の建物所有権が売買によって他人に移転した場合においては、所有権取得者は判決を得て自己の所有権を証明して単独で保存登記をすることができるが(不動産登記法74条1項2号)、また従来の所有者に対して移転登記の請求をすることもできるのであって、この場合には従来の所有者は、まず保存登記をした上で所有権取得者に対して移転登記手続をすべき義務を負担するとしている(最判昭31.6.5 不動産取引百選〔増補版〕32事件)。したがって、本記述のように、甲建物が未登記のまま譲渡された場合であっても、譲受人Bは、譲渡人Aに対し、所有権移転登記手続を請求することができる。よって、本記述は正しい。参考新版注釈民法(6)474頁。
論点体系判例民法(2)57頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、新聞記者が公務員を唆して秘密文書を漏示させたとしても、その取材活動が真に報道の目的から出たものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし社会通念上是認されるものである場合には、実質的に違法性を欠き、正当な業務行為となる。刑法この問題の模試受験生正解率 91.7%結果正解解説判例は、「報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではな」いとした上で、報道機関の取材活動が、「真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである」としている(最決昭53.5.31 刑法百選I〔第8版〕18事件)。よって、本記述は正しい。参考山口(総)113頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法労働基本権の保障の目的は、資本主義経済体制の下で、経済的に劣位にある者を保護することにあり、農漁業や小売商工業等の自営業を営む者などの自己の計算によって業を営む者は、憲法第28条の「勤労者」に該当する。憲法この問題の模試受験生正解率 61.7%結果正解解説労働基本権の保障の目的は、資本主義経済体制の下で、使用者に対して不利な立場に立たざるを得ない労働者を、使用者と対等の立場に立たせることにある。そして、憲法28条の「勤労者」とは、労働組合法にいう「労働者」がそれに当たり、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」(同3条)をいう。すなわち、自己の労働力を提供して対価を得て生活する者のことである。したがって、自己の計算によって業を営む者、例えば、農漁業、小売商工業等の自営業を営む者は、「勤労者」に該当しない。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)300頁。
毛利ほか(憲法Ⅱ)383頁。
新・コンメ憲法341~342頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、胎内にある子については、嫡出否認の訴えを提起することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 51.6%結果正解解説嫡出否認の訴えの出訴期間については、父又は前夫が原告になる場合については、父又は前夫が子の出生を知った時から3年以内(民法777条1号、4号)、子又は母が原告になる場合については、子の出生の時から3年以内(同条2号、3号)とされており、子の出生前に嫡出否認の訴えを提起することは認められていない。よって、本記述は正しい。
なお、胎内にある子について、母の承諾を得て、認知することはできる(同783条1項)。参考前田陽ほか(民法Ⅵ)129~131頁、144頁。
高橋ほか(民法7)135~136頁、142~143頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、私人である甲は、行使の目的で、虚偽の記載をした証明書発行申請書を提出し、情を知らない公務員をして内容虚偽の証明書を作成させた。甲は、作成権限のある公務員を利用して内容虚偽の公文書を作成させたので、この場合、甲には、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 71.1%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「刑法は、いわゆる無形偽造については公文書のみに限ってこれを処罰し、……公文書の無形偽造についても同法156条の他に特に公務員に対し虚偽の申立を為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法157条の処罰規定を設け、しかも右156条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない点から見ると公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない趣旨と解する」としている(最判昭27.12.25)。したがって、甲には、虚偽公文書作成罪(刑法156条)の間接正犯は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)386~387頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)405頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば、普通地方公共団体が課することができる租税の税目、課税客体、課税標準、税率その他の事項については、憲法上、租税法律主義の原則の下で、法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており、これらの事項について法律において準則が定められた場合には、普通地方公共団体の課税権は、これに従ってその範囲内で行使されなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 80.1%結果正解解説判例は、法人事業税の課税標準について、欠損金額の繰越控除を認める規定が地方税法に設けられているところ、ある県の課税条例がこの繰越控除を排除しているため、地方税法に違反するかが争われた事例において、「普通地方公共団体は、地方自治の本旨に従い、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有するものであり(憲法92条、94条)、その本旨に従ってこれらを行うためにはその財源を自ら調達する権能を有することが必要であることからすると、普通地方公共団体は、地方自治の不可欠の要素として、その区域内における当該普通地方公共団体の役務の提供等を受ける個人又は法人に対して国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されている」とした上で、「憲法は、普通地方公共団体の課税権の具体的内容について規定しておらず、普通地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律でこれを定めるものとし(92条)、普通地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるものとしていること(94条)、さらに、租税の賦課については国民の税負担全体の程度や国と地方の間ないし普通地方公共団体相互間の財源の配分等の観点からの調整が必要であることに照らせば、普通地方公共団体が課することができる租税の税目、課税客体、課税標準、税率その他の事項については、憲法上、租税法律主義(84条)の原則の下で、法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており、これらの事項について法律において準則が定められた場合には、普通地方公共団体の課税権は、これに従ってその範囲内で行使されなければならない」としている(最判平25.3.21 神奈川県臨時特例企業税事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕201事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、無効な売買契約を締結した当事者が、その無効であることを知ってこれを追認したときは、売買契約は初めから有効であったものとみなされる。民法この問題の模試受験生正解率 51.4%結果正解解説無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる(民法119条)。よって、本記述は誤りである。
なお、追認により新たな行為として有効となるためには、新たな行為として有効要件を充足しなければならないから、契約が公序良俗に反し無効であるような場合(同90条)、これをそのまま追認しても有効とはならない。参考佐久間(総則)220頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)245~246頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、偽造通貨であることを知りつつ、装飾にする目的で同通貨を収得したが、後になって気が変わり、飲食店での支払に同通貨を使った。この場合、甲には、同通貨の収得後知情行使罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 38.6%結果正解解説収得後知情行使罪(刑法152条)は、通貨を収得した後にそれが偽造通貨であることを知って行使した場合に成立する。したがって、偽造通貨であることを知って同通貨を収得した後に、これを流通に置いた甲には同罪は成立しない。よって、本記述は誤りである。
なお、本記述の場合、甲には、偽造通貨行使罪(同148条2項)が成立する。参考西田(各)354頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)428頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第26条第2項前段は保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めているが、これは、子どもが普通教育を受ける義務を負うことをも意味する。憲法この問題の模試受験生正解率 65.6%結果正解解説憲法26条2項前段は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と定めている。同項前段は、同条1項の教育を受ける権利の保障を受けて、子どもに普通教育を受けさせる国民の義務を定めたものであって、子どもが普通教育を受ける義務を負うのではない。よって、本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅰ)563頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)28頁。
新・コンメ憲法332頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと、婚姻が取り消された場合、当事者の一方は、他方に対して、財産の分与を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 65.9%結果正解解説離婚における財産分与を定めた民法768条が婚姻の取消しに準用されている(同749条)。婚姻の取消しは、将来に向かってのみ効力が生じるものとされており(同748条1項)、この点において離婚との共通点があることから、離婚の規定が準用されているのである。よって、本記述は正しい。参考窪田(家族法)48~49頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)58頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、休日の朝に、エンジンキー付きの乙所有の自動車が駐車してあるのを見付け、数時間ドライブした後、元の場所に戻す意思で、乙に無断で同車に乗り込み、ドライブしていたが、その日の夕方、無免許運転で検挙された。この場合、甲には、窃盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 61.6%結果正解解説窃盗罪が成立するためには、判例・通説は、故意のほかに、条文に明記されていない要件として不法領得の意思が必要であるとしている。その内容について、判例は、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」であるとしている(最判昭26.7.13 刑法百選〔初版〕90事件)。判例は、本記述と同様の事例において、不法領得の意思を認め、窃盗罪の成立を肯定している(最決昭55.10.30 刑法百選Ⅱ〔第8版〕32事件)。本記述では、甲は、乙所有の自動車を返還する意思を有しているが、同車を数時間にわたり利用する予定であったことから、自動車という価値の高い物を数時間にわたり利用することは、被害者の自動車に対する利用可能性を相当程度侵害する意思があるといえ、不法領得の意思が認められる。したがって、甲には、窃盗罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考西田(各)170頁、173~175頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)135~137頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国又はその機関が、宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対してそれらへの参加を強制することは、その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項に違反する。憲法この問題の模試受験生正解率 60.9%結果正解解説最大判昭52.7.13は、憲法20条2項の規定と同条3項の規定との関係につき、「両者はともに広義の信教の自由に関する規定ではあるが、2項の規定は、何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという、多数者によっても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定であるのに対し、3項の規定は、直接には、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障し、もって間接的に信教の自由を保障しようとする規定であって、……後者の保障にはおのずから限界があり、そして、その限界は、社会生活上における国家と宗教とのかかわり合いの問題である以上、それを考えるうえでは、当然に一般人の見解を考慮に入れなければならないものである。右のように、両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、2項の宗教上の行為等と3項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、2項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて3項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、2項に違反することとなるのはいうまでもない」としている。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、代理権を与えられた者が、その代理権が消滅した後に、第三者との間でその代理権の範囲内の行為をした場合において、その第三者が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときでも、代理権消滅後の表見代理が成立し得る。民法この問題の模試受験生正解率 81.8%結果正解解説判例は、「民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまる」としている(最判昭44.7.25 昭44重判民法2事件)。したがって、第三者が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときでも、代理権消滅後の表見代理が成立し得る。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)295頁。
平野(総則)344頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、人に暴行を加えた後、結果として死亡させるまでの間に傷害致死罪の法定刑を軽くする改正法が施行された場合、新法は適用されない。
(参照条文)刑法
第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。刑法この問題の模試受験生正解率 39.4%結果正解解説「犯罪後」とは、実行行為終了時を基準とする。傷害致死罪(刑法205条)は、結果的加重犯であるため、暴行の時点で実行行為は終了している。したがって、同罪の実行行為である暴行の終了後に法定刑を軽くする改正法が施行された場合、同6条の適用対象となり、新法が適用される。よって、本記述は誤りである。参考条解刑法12頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、皇居外苑などの国民公園は、国が直接公共の用に供した財産であるとしても、集会のために設置されたものではないため、公園を集会に使用するための許可の申請について、公園の管理権者は、その許否を自由に決することができ、不許可処分を行っても憲法第21条に反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 62.0%結果正解解説判例は、皇居外苑をメーデーに使用するための許可申請が不許可とされた事例において、「国有財産法(注:事件当時のもの)によれば、公共福祉用財産は、国が直接公共の用に供した財産であって、国民は、その供用された目的に従って均しくこれを利用しうるものであ」る。しかし、「国民がこれを利用しうるのは、当該公共福祉用財産が公共の用に供せられる目的に副い、且つ公共の用に供せられる態様、程度に応じ、その範囲内においてなしうるのであって、これは、皇居外苑の利用についても同様である。……公共福祉用財産をいかなる態様及び程度において国民に利用せしめるかは右管理権の内容であるが、勿論その利用の許否は、その利用が公共福祉用財産の、公共の用に供せられる目的に副うものである限り、管理権者の単なる自由裁量に属するものではなく、管理権者は、当該公共福祉用財産の種類に応じ、また、その規模、施設を勘案し、その公共福祉用財産としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであり、若しその行使を誤り、国民の利用を妨げるにおいては、違法たるを免れない」として公共福祉用財産についての一般論を述べた上で、「これは、皇居外苑の管理についても同様であって、……国民が同公園に集合しその広場を利用することは、一応同公園が公共の用に供せられている目的に副う使用の範囲内のことであり、唯本件のようにそれが集会又は示威行進のためにするものである場合に、同公園の管理上の必要から、これを厚生大臣(注:当時)の許可にかからしめたものであるから、その許否は管理権者の単なる自由裁量に委ねられた趣旨と解すべきでなく、管理権者たる厚生大臣は、皇居外苑の公共福祉用財産たる性質に鑑み、また、皇居外苑の規模と施設とを勘案し、その公園としての使命を十分達成せしめるよう考慮を払った上、その許否を決しなければならない」としている(最大判昭28.12.23 皇居前広場事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕80事件)。したがって、公共福祉用財産である公園使用の許可申請の許否は、公園の管理権者の自由裁量に属するものとはいえず、その許否を自由に決することはできない。よって、本記述は誤りである。
-
民法A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関して、判例の趣旨に照らした場合、Aが死亡し、相続人の不存在が確定し、かつ、清算手続が終了した場合において、Aの特別縁故者であるFが存在するときであっても、Aが有していた甲土地の持分は、Fに対する財産分与の対象となり得ず、B及びCに帰属する。民法この問題の模試受験生正解率 69.2%結果正解解説判例は、民法255条と同958条の2の優先関係につき、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3(現:958条の2)の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属する」としている(最判平元.11.24 民法百選Ⅲ〔第3版〕57事件)。その理由として、同判決は、同255条が同958条の2に優先すると解すると、共有持分でない相続財産は財産分与の対象となるのに対して、共有持分である相続財産は財産分与の対象にならないことになり、同じ相続財産でありながら取扱いに差異が生じ不合理であること等を挙げている。本記述においては、特別縁故者であるFが存在している以上、Aが有していた甲土地の持分は、まずはFに対する財産分与の対象となるのであって、直ちに共有者であるB及びCに帰属するわけではない。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(物権)208頁。
松井(物権)197~198頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)389頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、刑の一部の執行猶予は、被告人の再犯防止と改善更生を図るため、宣告刑の一部についてその執行を猶予するという新たな選択肢を裁判所に与える趣旨のものであり、特定の犯罪に対して科される刑の種類又は量を変更するものではない。刑法この問題の模試受験生正解率 49.4%結果正解解説刑の一部執行猶予制度(刑法27条の2~27条の7)は、平成25年の刑法一部改正により新設されたものであり、言い渡された刑の一部の期間のみを実際に刑に服させ、残りの期間は刑の執行が猶予されるという制度である(同27条の2第2項)。同制度について、判例は、被告人が実刑判決を受けた後に、刑の一部執行猶予制度を定める法律が施行されたことから、同制度の新設が判決のあった後の「刑の……変更」(刑訴法411条5号)に当たるかが問題となった事例において、「刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は、被告人の再犯防止と改善更生を図るため、宣告刑の一部についてその執行を猶予するという新たな選択肢を裁判所に与える趣旨と解され、特定の犯罪に対して科される刑の種類又は量を変更するものではない」としている(最決平28.7.27 平28重判刑法4事件)。よって、本記述は正しい。参考西田(総)463~464頁。
井田(総)67頁、632~633頁。
条解刑法69頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、信教の自由の保障は、自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対して、当該行為が強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきであるから、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益を、直ちに法的利益として認めることはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 70.7%結果正解解説判例は、社団法人隊友会山口県支部連合会と自衛隊山口地方連絡部が共同して亡夫を山口県護国神社に合祀申請したことは、宗教上の人格権の侵害であるなどとして、亡夫の妻が合祀手続の取消しなどを請求した事例において、「私人相互間において……信教の自由の侵害があり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは、……法的保護が図られるべきである」が、「人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし、そのことに不快の感情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にでも保障されているからである」とし、「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない」としている(最大判昭63.6.1 憲法百選Ⅰ〔第7版〕43事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法Aの所有する土地をBCDが共同で購入した場合において、BCDが売買契約の解除をするためには、BCD全員がAに対して解除の意思表示をする必要がある。民法この問題の模試受験生正解率 34.0%結果正解解説当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(解除権の不可分性 民法544条1項)。これは、一部の当事者についてのみ解除の効果を認めることで法律関係が複雑化するのを防止する趣旨である。したがって、本記述の場合、BCDが売買契約の解除をするためには、BCD全員がAに対して解除の意思表示をする必要がある。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)55~56頁。
中田(契約)219~220頁。
新・コンメ民法(財産法)924頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙、丙及び丁が、Aの身体に対し共同して害を加える目的でそれぞれ凶器を準備して公園に集合していることを知って、甲もAの身体に対し乙らと共同して害を加える目的で同公園に赴き集合したが、甲自身は、凶器を持参しなかった。この場合、甲に凶器準備集合罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 52.8%結果正解解説凶器準備集合罪(刑法208条の2第1項)は、2人以上の者が、他人の生命・身体・財産に対する共同加害の目的で、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合したときに成立する。準備があることを知って集合したとは、既に凶器の準備がなされていることを認識して共同加害の目的で参集するという意味である。本記述では、甲は乙らが凶器を準備していることを認識しながらAの身体に対する共同加害の目的で集合している。したがって、甲自らが凶器を準備していなくても、甲に凶器準備集合罪が成立する。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)66~68頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)35~36頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法天皇及び皇族が憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれると考える立場によると、憲法第24条第1項が保障する婚姻の自由については、必然的に、国民と同等に保障されることになる。憲法この問題の模試受験生正解率 46.3%結果正解解説天皇及び皇族は日本国籍を有するが、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれるかについては、争いがある。この点、天皇及び皇族が「国民」に含まれるとする見解(肯定説)も、皇位の世襲(憲法2条)と職務の性質から、一般国民と異なった取扱いがなされることを認めている。例えば、天皇は、「国政に関する権能を有しない」(同4条1項)し、また「象徴」(同1条)であるから、国民であれば当然有する政治活動の自由(同21条1項)は認められない。さらに、皇族男子の婚姻は皇室会議の議を経ることを要するが(皇室典範10条)、これは憲法24条1項が国民に保障する婚姻の自由に対する制限である。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)90~91頁。
佐藤幸(日本国憲法論)160頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)230~232頁。
渋谷(憲法)114~115頁。 -
民法Aが甲土地を所有し、Bが甲土地に隣接する乙土地を所有しており、甲土地上にAが所有し居住する丙建物が、乙土地上にBが所有し居住する丁建物がある場合に関して、A及びBは、共同の費用で境界標を設けることができ、境界標の設置及び保存の費用は、A及びBが甲土地及び乙土地の広狭に応じて分担する。民法この問題の模試受験生正解率 60.3%結果正解解説土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(民法223条)。そして、境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する(同224条本文)。相隣者は境界標の設置・保存の利益を平等に受けることから、その費用も等しい割合で負担すべきことを定めたものである。よって、本記述は誤りである。
なお、境界が不明な場合に境界を確定するために必要となる相隣地の測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する(同条ただし書)。参考平野(物権)316~317頁。
新注釈民法(5)432頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、緊急避難の要件である「現在の危難」は、法益に対する侵害が現実に存在することを意味し、侵害が差し迫っているだけでは足りない。刑法この問題の模試受験生正解率 85.7%結果正解解説緊急避難の要件である「現在の危難」には、法益侵害が現実に存在する場合のみならず、法益侵害の危険が切迫している場合も含まれる。判例は、正当防衛にいう「急迫」(刑法36条1項)とは、「法益の侵害が間近に押し迫ったことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味する」とした上で、緊急避難の要件である「現在の危難」についてもこれと同様に解するとしている(最判昭24.8.18 刑法百選〔初版〕11事件)。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)123頁、149頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)209頁。
条解刑法138~139頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第70条にいう「内閣総理大臣が欠けたとき」には、死亡、失踪などのほか、病気や一時的な生死不明のような暫定的とみられる性質の故障も含まれる。憲法この問題の模試受験生正解率 36.7%結果正解解説憲法70条は、内閣が総辞職しなければならない場合として、「内閣総理大臣が欠けたとき」と規定している。これは、内閣総理大臣が内閣の首長的地位を占めることの帰結として、内閣の一体性を保障することに趣旨がある。そして、同条の「欠けたとき」には、内閣総理大臣が死亡、失踪した場合や国会議員たる地位を失った場合を含むが、病気や一時的な生死不明のような、暫定的性質の故障の場合はこれに含まれず、「内閣総理大臣に事故のあるとき」として、内閣総理大臣の臨時代理が置かれることになる(内閣法9条)と解されている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)354頁。
佐藤幸(日本国憲法論)533~534頁、537~538頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)194頁。
新・コンメ憲法588~590頁。 -
民法家庭裁判所は、被補助人がする特定の法律行為について、その補助人に同意権を付与する旨の審判をすることができるが、その特定の法律行為は、民法第13条第1項に規定されている被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する行為の一部に限られる。民法この問題の模試受験生正解率 68.7%結果正解解説家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするには、その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるが(民法17条1項本文)、同意を得なければならないものとすることができる行為は、同13条1項に規定する行為の一部に限られる(同17条1項ただし書)。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)101~102頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)45頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、身の代金目的誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。刑法この問題の模試受験生正解率 72.6%結果正解解説刑法228条の2は、身の代金目的略取誘拐罪(同225条の2第1項)等の犯人が、「公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。この規定は、身の代金目的略取誘拐罪等は、被拐取者の生命が危険にさらされる極めて危険な犯罪であることから、犯人が自発的、積極的に被拐取者を解放した場合にその刑を必要的に減軽することにより、被拐取者の解放を促し、重大な結果の発生を少しでも防止しようとした政策的な規定である。よって、本記述は正しい。参考西田(各)95頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)62頁。
条解刑法692頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法第13条の趣旨に反し許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 89.9%結果正解解説判例は、旧外国人登録法が定める在留外国人についての指紋押なつ制度(平成11年に廃止)が憲法13条等に反しないかが争われた事例において、「指紋は、指先の紋様であり、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。このような意味で、指紋の押なつ制度は、国民の私生活上の自由と密接な関連をもつものと考えられる」とした上で、「憲法13条は、……個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許され」ないとしている(最判平7.12.15 憲法百選Ⅰ〔第7版〕2事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法根抵当権の極度額を増額するには、利害関係を有する者の承諾を得ることを要するが、減額するには、利害関係を有する者の承諾を得ることを要しない。民法この問題の模試受験生正解率 34.5%結果正解解説根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない(民法398条の5)。そして、極度額を増額するときは、抵当不動産の後順位担保権者・差押債権者等の承諾が必要となり、減額するときは、転抵当権者等の根抵当権自体に権利を有している者の承諾が必要となる。したがって、増減どちらの場合であっても、利害関係を有する者の承諾が必要となる。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ580頁。
松井(担物)120頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、Aら数名が殴り合いのけんかをしている現場に偶然出くわし、「もっとやれ。」と叫んではやし立てた。Aらけんかの当事者は誰も怪我をせず、Aらの暴行がいずれもけんかの相手に対する暴行罪にとどまっていた場合、甲に現場助勢罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 52.8%結果正解解説現場助勢罪(刑法206条)は、「前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者」について成立する。同206条の「前2条の犯罪」は傷害罪と傷害致死罪を指し、本犯が暴行罪にとどまった場合には、本罪は成立しない。したがって、甲に現場助勢罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考山口(各)48頁。
条解刑法620~621頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができず、その結果、宗教活動上の地位に基づく宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができない。この場合には、宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。憲法この問題の模試受験生正解率 59.0%結果正解解説判例は、宗教団体の代表役員及び管長の地位にないことの確認が求められた事例において、「特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている場合には、裁判所は、原則として、右の者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断すべきものであるが、他方、宗教上の教義ないし信仰の内容にかかわる事項についてまで裁判所の審判権が及ぶものではない」ため、「特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができず、その結果、宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができないことになるが、この場合には、特定の者の宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所が法令の適用によって終局的な解決を図ることができない訴訟として、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらない」としている(最判平5.9.7 憲法百選Ⅱ〔第7版〕185事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、法人の構成員に対して金銭債権を有する債権者は、その構成員が法人に出資した財産を差し押さえることができる。民法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説団体に法人格が付与されると、構成員から独立した権利義務の帰属主体となるため、法人と構成員個人の財産関係は遮断される。したがって、法人の構成員に対して金銭債権を有する債権者は、その構成員が法人に出資した財産を差し押さえることができない。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)334頁。
平野(総則)57頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、行使の目的で、銀行預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は、私文書の偽造ではなく、変造である。刑法この問題の模試受験生正解率 57.6%結果正解解説文書偽造罪にいう「変造」とは、文書の非本質的部分に不法に変更を加えることをいう。そして、判例は、郵便貯金通帳の貯金受入年月日を改ざんした場合は、変造になるとしている(大判昭11.11.9)。本記述の銀行預金通帳の預金受入年月日も、同様に考えることができる。したがって、行使の目的で、銀行預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は、私文書の変造である。よって、本記述は正しい。参考山口(各)444頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法「主権」の概念は多義的であり、①国家権力(統治権)そのもの、②国家権力の属性としての最高独立性(対外的独立性と対内的最高性)、③国政についての最高決定権という三つの異なる意味で用いられる。「主権」に関して、憲法第1条にある「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」との部分における「主権」は、①の意味であるとされている。憲法この問題の模試受験生正解率 71.4%結果正解解説「主権」の概念は多義的であり、①国家権力(統治権)そのもの、②国家権力の属性としての最高独立性(対外的独立性と対内的最高性)、③国政についての最高決定権という三つの異なる意味に分類されている。①の「国家権力そのもの」とは、立法権・司法権・行政権等の複数の「国家の権利」ないし「統治活動をなす権力」を総称する観念であり、伝統的に統治権と呼ばれる。②の「国家権力の属性としての最高独立性」とは、国家権力が、対外的には他のいかなる権力主体からも意思形成において制限されず独立であり、対内的には他のいかなる権力主体にも優越して最高であることを意味している。③の「国政についての最高決定権」とは、国内における最高権力、あるいは「国の政治の在り方を最終的に決定する力又は権威」を意味する。
「主権」の概念の分類において、憲法1条の「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」との部分における「主権」は、③国政についての最高決定権を意味するとされている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)39~40頁。芦部(憲法学Ⅰ)220~223頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、債務者のした相続の放棄は、詐害行為取消権の対象とならない。民法この問題の模試受験生正解率 56.7%結果正解解説財産権を目的としない行為は、詐害行為取消権の対象とならない(民法424条2項)。婚姻や養子縁組などの身分行為によって債務者の財産状態が悪化したとしても、詐害行為取消権を行使することはできない。しかし、本記述の相続放棄などのように、身分行為の中には、財産の管理や処分の性質を有するものもある。この点について、判例は、「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない」としている(最判昭49.9.20 家族法百選〔第5版〕103事件)。その理由として、同判決は、詐害行為取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、消極的に既得財産の増加を妨げる行為にすぎないとみるのが妥当であり、また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消し得るものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となって不当であることを挙げている。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ367~368頁。
潮見(プラクティス債総)237~238頁。
中田(債総)291~292頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚醒剤を注射したところ、その場でVが錯乱状態に陥った。甲は、覚醒剤を注射した事実の発覚を恐れ、そのままVを放置して立ち去り、Vは数時間後覚醒剤中毒により死亡した。Vが錯乱状態に陥った時点で甲が直ちに救急医療を要請していれば、僅かであるがVを救命できた可能性があった。この場合、甲がVを放置した行為とVの死亡の結果との間に、因果関係がある。刑法この問題の模試受験生正解率 82.3%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、被告人が立ち去った時点で直ちに「救急医療を要請していれば」、「十中八九」被害者の「救命が可能であった」ときは、「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置」を採らず放置した行為と同女の死亡との間には因果関係が認められるとしている(最決平元.12.15 刑法百選Ⅰ〔第8版〕4事件)。したがって、本記述において、Vが錯乱状態に陥った時点で甲が直ちに救急医療を要請していても、Vを救命できた可能性が僅かであった以上、甲がVを放置した行為とVの死亡の結果との間に、因果関係はない。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)79~80頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)61~62頁。
条解刑法96~97頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法法の支配の内容としては、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容・手続の公正を要求する適正手続、裁判所の役割に対する尊重などが重要であると考えられている。憲法この問題の模試受験生正解率 89.5%結果正解解説法の支配とは、専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理をいう。この原理の内容として重要なものは、①憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容・手続の公正を要求する適正手続、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などである。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)13~14頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、売買の目的物が他人の物であるため、直ちにその物の所有権を取得することができないことを知りながら買主がその物の占有を開始した場合、その占有は、所有の意思をもってする占有とはいえない。民法この問題の模試受験生正解率 69.8%結果正解解説取得時効の成立には、所有の意思をもってする占有が、民法所定の期間継続することが必要である(民法162条)。そして、判例は、「占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものであり、土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、右売買が他人の物の売買であるため売買によって直ちにその所有権を取得するものではないことを買主が知っている事実があっても、買主において所有者から土地の使用権の設定を受けるなど特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもってするものとすべきであって、右事実は、占有の始め悪意であることを意味するにすぎない」としている(最判昭56.1.27)。よって、本記述は誤りである。参考我妻・有泉コメ327頁。
論点体系判例民法(1)505~506頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、わいせつの目的をもって未成年者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪は成立せず、わいせつ目的誘拐罪のみが成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 72.6%結果正解解説判例は、刑法225条所定の目的をもって未成年者を誘拐したときは、同条の罪のみが成立するとしている(大判明44.12.8)。よって、本記述は正しい。参考山口(各)94頁。
条解刑法680頁。
大コメ(刑法・第3版)(11)539頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われる結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されるため、解散命令は、これらを用いて行っていた信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を伴う。憲法この問題の模試受験生正解率 70.7%結果正解解説判例は、宗教法人に対する解散命令が、信者の信教の自由を不当に制約し許されないのではないかが争われた事例において、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われ……、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから……、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る」としている(最決平8.1.30 憲法百選Ⅰ〔第7版〕39事件)。同決定によれば、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、相殺を禁じる当事者の意思表示は、第三者がこれを知り、又は過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。民法この問題の模試受験生正解率 51.5%結果正解解説当事者が相殺を禁止し、又は制限をする旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる(民法505条2項)。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ307~308頁。
潮見(プラクティス債総)432~433頁。
中田(債総)473頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙が所有し、管理している乙名義の更地を、自己が経営する工場の倉庫の敷地として利用しようと考え、乙に無断でその更地の登記名義を自己名義に変更したが、その上に倉庫を建築するには至らなかった。この場合、甲には不動産侵奪罪の実行の着手が認められる。刑法この問題の模試受験生正解率 35.1%結果正解解説不動産侵奪罪(刑法235条の2)の「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいう。窃盗罪(同235条)との対比上、不動産を占拠する積極的な事実行為を要するので、登記簿上の名義変更をしただけでは、「侵奪」したとは認められない。本記述では、甲は、乙名義の土地の登記名義を自己名義に変更したにすぎない。したがって、甲に不動産侵奪罪の実行の着手は認められない。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)177頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)141頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関し、その懲罰を受けた議員が取消しを求める訴えは、法令の適用によって終局的に解決し得る法律上の争訟に当たるところ、議会により出席停止の懲罰処分を科されると、その議員は、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなるから、当該処分が議会の自律的な権能に基づいてなされたものとして、議会に一定の裁量が認められるとしても、裁判所は、常にその適否を判断することができ、司法審査の対象となる。憲法この問題の模試受験生正解率 59.0%結果正解解説判例は、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰処分が司法審査の対象になるかが問題となった事例において、「普通地方公共団体の議会は、地方自治法並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる(同法134条1項)ところ、懲罰の種類及び手続は法定されている(同法135条)。これらの規定等に照らすと、出席停止の懲罰を科された議員がその取消しを求める訴えは、法令の規定に基づく処分の取消しを求めるものであって、その性質上、法令の適用によって終局的に解決し得るものというべきである」とした上で、「議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、……議事に参与し、議決に加わるなどして、住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである」「出席停止の懲罰は、上記の責務を負う公選の議員に対し、議会がその権能において科する処分であり、これが科されると、当該議員はその期間、会議及び委員会への出席が停止され、議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」「そうすると、出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである」「したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきである」としている(最大判令2.11.25 令3重判憲法2事件)。よって、本記述は正しい。参考市川(憲法)305頁。
毛利ほか(憲法Ⅰ)276頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、法人は、受遺者となることができる。民法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説夫婦、親子、兄弟姉妹といった身分を前提とする相続については、法人に認めることはできないが、法人が遺贈を受けることは可能であると解されている。よって、本記述は正しい。参考平野(総則)79頁。
新注釈民法(1)729頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、私文書偽造罪の客体である「事実証明に関する文書」とは、法律関係についての事実を証明する文書に限られ、求職のための履歴書はこれに含まれるが、私立大学入学試験の答案はこれに含まれない。刑法この問題の模試受験生正解率 57.6%結果正解解説判例は、私文書偽造罪の「事実証明に関する文書」について、「社会生活に交渉を有する事項……を証明するに足る文書」と広く解しており(最決昭33.9.16)、求職のための履歴書(最決平11.12.20 刑法百選Ⅱ〔第7版〕95事件)のみならず、私立大学入学試験の答案についても、「試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書……に当たる」としている(最決平6.11.29 刑法百選Ⅱ〔第8版〕89事件)。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)394頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)398頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、参議院議員の選挙において、都道府県を各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、むしろ、都道府県を各選挙区の単位として固定する結果、投票の価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続されてきた状況の下では、各選挙区の区域を定めるに当たり、都道府県という単位を用いることは不合理なものとして許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 63.1%結果正解解説判例は、平成28年7月施行の参議院議員選挙に対する選挙無効訴訟において、選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否かが争われた事例において、「平成24年大法廷判決(注:最大判平24.10.17)及び平成26年大法廷判決(注:最大判平26.11.26 平26重判憲法1事件)は、……選挙制度の構築についての国会の裁量権行使の合理性を判断するに当たって、長年にわたる制度及び社会状況の変化を考慮すべき必要性を指摘し、その変化として、参議院議員と衆議院議員の各選挙制度が同質的なものとなってきており、国政の運営における参議院の役割が増大してきていることに加え、衆議院については投票価値の平等の要請に対する制度的な配慮として選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする旨の区割りの基準が定められていることなどを挙げて、これらの事情の下では、昭和58年大法廷判決(注:最大判昭58.4.27 憲法百選Ⅱ〔第3版〕156事件)が長期にわたる投票価値の大きな較差の継続を許容し得る根拠として挙げていた諸点につき、数十年間にもわたり5倍前後の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっている旨を指摘するとともに、都道府県を各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、むしろ、都道府県を各選挙区の単位として固定する結果、上記のように長期にわたり大きな較差が継続していた状況の下では」、都道府県の意義や実体等をもって都道府県を単位とする「選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっていたとしたものである。しかし、この判断は、都道府県を各選挙区の単位として固定することが投票価値の大きな不平等状態を長期にわたって継続させてきた要因であるとみたことによるものにほかならず、各選挙区の区域を定めるに当たり、都道府県という単位を用いること自体を不合理なものとして許されないとしたものではない」としている(最大判平29.9.27 平29重判憲法1事件)。よって、本記述は誤りである。参考平29最高裁解説(民事)419~420頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、入会集落の慣習に基づく入会集団の会則中、入会権者の資格要件を原則として男子孫に限定し、当該入会集落の住民以外の男子と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り資格を認めないとする部分は、入会集落の団体としての統制の維持という点からも、入会権の行使における各世帯間の平等という点からも何ら合理性を有しないため、公序良俗に反する。民法この問題の模試受験生正解率 78.3%結果正解解説判例は、入会権者の資格を世帯主及び男子孫に限り、入会集落の住民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り資格を認めないとする慣習(慣習に基づいて定められた会則を含む。)の効力が争われた事例において、「本件慣習のうち、男子孫要件は、専ら女子であることのみを理由として女子を男子と差別したものというべきであり、……性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である」としている(最判平18.3.17 平18重判民法1事件)。その理由として、同判決は、「男子孫要件は、世帯主要件とは異なり、入会団体の団体としての統制の維持という点からも、入会権の行使における各世帯間の平等という点からも、何ら合理性を有しない」こと等を挙げている。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)192頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)140頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、営利目的略取誘拐罪において、拐取者が一旦被拐取者を自己の実力的支配内に置いたにもかかわらず、営利目的を遂げることができなかった場合、営利目的略取誘拐罪は未遂にとどまる。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、条例中に罰則を設けるには法律の授権が必要であるが、条例は地方公共団体の議会によって制定される民主的立法であり実質的に法律に準ずるものであるから、条例への罰則の委任は一般的・包括的委任で足りる。憲法この問題の模試受験生正解率 90.7%結果正解解説判例は、罰則を定める条例によって処罰された者が、当該条例は憲法31条に違反するとして争った事例において、「条例は、法律以下の法令といっても、……公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である」としている(最大判昭37.5.30 憲法百選Ⅱ〔第7版〕208事件)。したがって、条例への罰則の委任は、一般的・包括的なものでは足りない。よって、本記述は誤りである。
-
民法AのBに対する100万円の金銭債務(以下「本件債務」という。)についての代物弁済に関して、判例の趣旨に照らした場合、AB間で、本件債務について、AのDに対する80万円の金銭債権を代物弁済の目的とする契約を締結するに当たり、当該代物弁済により、本件債務の全部ではなく、80万円の限度で消滅させる合意をすることはできない。民法この問題の模試受験生正解率 65.8%
-
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、客を集めて有料でわいせつな映画を観覧させて利益を得る目的で、自宅付近の人通りの多い路上で、通行人に声を掛け、これに応じた5名の客に対し、外部との交通を厳重に遮断した自宅の一室においてわいせつな映画を観覧させて利益を得た。この場合、甲にわいせつ図画公然陳列罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 90.4%結果正解解説わいせつ図画公然陳列罪(刑法175条1項前段)の「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいう。判例は、本記述と同様の事例において、わいせつな映画を上映した部屋が、外部との交通が遮断されていて、観客も5名程度に限られていても、その5名が不特定多数人を勧誘して集められた者であれば、結果としてわいせつな映画を不特定の者に観覧可能な状態にしたといえるとした原審の判断を是認している(最決昭33.9.5)。したがって、本記述において、甲にわいせつ図画公然陳列罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考山口(各)512頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)442頁。
条解刑法510頁、519頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第13条後段の保障する幸福追求権の内容について、人格的生存に必要不可欠な利益に限定する見解によれば、人格的生存に必要不可欠ではない利益は、同条後段の保障の範囲外であるので、かかる利益に対するいかなる規制も許容されることになる。憲法この問題の模試受験生正解率 67.9%結果正解解説幸福追求権の内容(保障範囲)をめぐっては、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。このうち、人格的利益説は、憲法の基底的原理を自律的個人としての尊重と解し、幸福追求権の内容を人格的生存にとって必要不可欠である利益に限定する説である。この説によれば、人格的生存にとって必要不可欠とはいえない利益は憲法13条後段の保障する幸福追求権の内容には含まれないことになる。もっとも、このような利益に対するいかなる規制も当然に許されるというわけではなく、平等原則や比例原則との関わりで、憲法上問題になることがある。したがって、人格的利益説による場合に、当該利益が同条後段の保障範囲に含まれない利益であるからといって、いかなる規制も許されるということにはならない。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)122頁。
安西ほか(読本)90頁。
新井ほか(憲法Ⅱ)43~44頁。
注釈日本国憲法(2)105頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、他人所有の土地の上に通路の開設が必要であるが、その開設は、要役地の所有者によってなされる必要はない。民法この問題の模試受験生正解率 58.3%結果正解解説判例は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する」としている(最判昭30.12.26)。したがって、要役地の所有者が、通行地役権を時効により取得するためには、通路の開設は、要役地の所有者によってなされる必要がある。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(物権)270頁。
松井(物権)235~236頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)212頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙がAとBを殺害しようとしていることを知り、これを幇助するために、凶器となるナイフを乙に渡したところ、乙はこのナイフを用いてAとBを刺殺した。この場合、甲にはAに対する殺人罪の幇助犯とBに対する殺人罪の幇助犯が成立し、これらは併合罪となる。刑法この問題の模試受験生正解率 81.7%結果正解解説判例は、幇助罪の個数と罪数処理について、「幇助罪は正犯の犯行を幇助することによって成立するものであるから、成立すべき幇助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定されるものと解するのが相当である」とした上で、「幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かについては、幇助犯における行為は幇助犯のした幇助行為そのものにほかならないと解するのが相当であるから、幇助行為それ自体についてこれをみるべきである」としている(最決昭57.2.17 刑法百選Ⅰ〔第8版〕107事件)。したがって、本記述において、甲には、AとBに対する2個の殺人罪の幇助犯(同199条、62条1項)が成立するが、幇助行為はナイフの交付という1個の行為であるから、これらは観念的競合となる。よって、本記述は誤りである。参考山中(総)1072~1073頁。
大コメ(刑法・第3版)⑷294頁、367~368頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けている。憲法この問題の模試受験生正解率 55.8%結果正解解説判例は、国税犯則取締法(国税通則法に編入されることにより、平成30年廃止)に基づく質問調査に憲法38条1項の供述拒否権の保障が及ぶかどうかが問題となった事例において、「国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則嫌疑者については、自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供述を認めることになる」ので、「憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶ」とするものの、「同項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解される」としている(最判昭59.3.27 憲法百選Ⅱ〔第7版〕119事件)。したがって、同項は、供述拒否権の告知を義務付けていない。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、内縁の夫婦の一方が運転する自動車に同乗していた他方が、第三者の運転する自動車に衝突されて負傷したため、その第三者に対して損害賠償を請求したときは、賠償額を算定するに当たり、運転をしていた内縁の夫婦の一方の過失を被害者側の過失として考慮することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 78.8%結果正解解説判例は、「不法行為に基づき被害者に対して支払われるべき損害賠償額を定めるに当たっては、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失についても、民法722条2項の規定により、いわゆる被害者側の過失としてこれを考慮することができる」とした上で、「内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていないが、男女が相協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものであり、身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとみることができる。そうすると、内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し、それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において、その損害賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができると解するのが相当である」としている(最判平19.4.24)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅱ)128~129頁。
橋本ほか(民法Ⅴ)231~232頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、客観的に刑法第175条第1項前段の「わいせつな文書」に該当する文書を、その意味内容を理解しつつも、その文書が同項前段の「わいせつな文書」には該当しないと信じて販売した場合、わいせつ文書頒布罪の故意は阻却されない。刑法この問題の模試受験生正解率 95.4%結果正解解説判例は、「刑法175条の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、……かりに主観的には刑法175条の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として犯意を阻却しない」としている(最大判昭32.3.13 チャタレー事件 刑法百選Ⅰ〔第8版〕47事件)。よって、本記述は正しい。参考山口(総)205頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法は、内閣が総辞職すべき場合を定めているが、憲法が定める場合以外に、内閣はその存続が適当でないと考えるときは、いつでも総辞職することができる。憲法この問題の模試受験生正解率 62.5%結果正解解説憲法69条及び70条は、内閣が総辞職すべき場合を規定している。もっとも、当該規定は、内閣が必ず総辞職すべき場合を定めるものであり、内閣は、これらの憲法が定める場合に限られず、その存続が適当でないと考えるときは、いつでも総辞職することができる。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)354頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)193頁。 -
民法AとBは、Aが所有する建物甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結した。この事例に関して、判例の趣旨に照らした場合、Aが、Bに甲の引渡し及び所有権移転登記をする約定の期日の前に、甲をCに売却してCへの所有権移転登記をした場合、当該所有権移転登記がされたことにより、AのBに対する甲の引渡債務及び所有権移転登記をする債務は履行不能となるから、Bは、催告をすることなく直ちに本件契約を解除することができる。民法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説判例は、不動産の二重売買がされた場合、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のない限り、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるとしている(最判昭35.4.21 不動産取引百選〔第2版〕67事件)。そして、債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、履行の催告をすることなく契約の全部の解除をすることができる(民法542条1項1号)。本記述においても、Aが、Bに甲の引渡し及び所有権移転登記をする約定の期日の前に、甲をCに売却してCへの所有権移転登記がされた場合、当該所有権移転登記がされた時に、AのBに対する甲の引渡債務及び所有権移転登記をする債務は履行不能となるから、Bは、催告をすることなく直ちに本件契約を解除することができる。よって、本記述は正しい。参考潮見(プラクティス債総)72頁。
中田(債総)124頁。
新基本法コメ(債権2)54頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙の財布を自己のものにしようと考え、乙に対し、社会通念上一般に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加え、その反抗を抑圧された乙が気付かないうちに、同人の財布をポケットから抜き取った。この場合、甲に強盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.8%結果正解解説強盗罪の「強取」といえるためには、「暴行又は脅迫」と財物・財産上の利益の奪取との間に、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要である。したがって、被害者に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加え、その反抗の抑圧中に財物を奪取すれば、その奪取行為がたまたま被害者の気付かない間にされたものであっても、強盗罪が成立する(最判昭23.12.24)。したがって、本記述において、甲に強盗罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考西田(各)182頁、184頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)149~150頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例は、憲法第14条は差別すべき合理的理由なくして区別することを禁止する趣旨であるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる区別をすることは許されるとしている。憲法この問題の模試受験生正解率 97.1%結果正解解説判例は、高齢者であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分が憲法14条1項及び地方公務員法13条に反するかどうかが争われた事例において、憲法14条1項及び地方公務員法13条は、「国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない」としている(最大判昭39.5.27 公務員百選21事件)。よって、本記述は正しい。参考長谷部(憲法)168頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅱ)72頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)140~141頁。 -
民法未成年者Aが法定代理人の同意を得ることなく法律行為をした場合において、法定代理人が当該法律行為を知った時から5年が経過したときは、Aが成年に達する前であっても、Aの取消権も時効により消滅する。民法この問題の模試受験生正解率 74.2%結果正解解説取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法126条前段)。本記述においては、A及びその法定代理人は、Aのした法律行為について、それぞれ制限行為能力を理由とする取消権を有するところ(同120条1項)、これらの取消権は、同一人を当事者とする同一の法律行為について同一の取消原因によって発生しており、目的を同じくしている。このような場合には、一人の取消権者につき取消権の消滅時効が完成すると、他方の取消権も時効により消滅すると解されている。よって、本記述は正しい。参考新版注釈民法(4)544~545頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合、A国に居住する日本国民である甲は、A国において、A国民である友人乙から、「旅行に行っている間、預かっていてほしい。」と頼まれて預かっていた宝石を、乙に無断で売却し、受け取った代金を自己の遊興のために費消した。甲に刑法(単純横領罪)が適用される。刑法この問題の模試受験生正解率 57.1%結果正解解説刑法1条1項は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と規定し、場所的適用範囲について、原則として、属地主義を定めている。したがって、日本国内で犯罪を行った国内犯に対しては、その国籍を問わず、刑法の適用がある。また、日本国外で犯罪を行った国外犯であっても、同2条以下に当たるときは、刑法が適用される。
本記述において、日本国民である甲が乙から預かった宝石を売却した行為は、単純横領罪(刑法252条1項)に当たるが、当該行為を行ったのは、A国であり、日本国民の国外犯について定める同3条に単純横領罪は規定されていない。したがって、甲に刑法(単純横領罪)は適用されない。よって、本記述は誤りである。
なお、日本国民が、日本国外において業務上横領罪(同253条)を犯した場合には、刑法の適用がある(同3条16号)。参考山口(総)416~417頁。
刑法総論講義案25~27頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)461~466頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法議院の自律権を確保するためには財政的基盤が必要であり、憲法は、両議院の経費は、独立して、国の予算に計上しなければならない旨規定している。憲法この問題の模試受験生正解率 53.3%結果正解解説衆参両議院は、相互に独立して審議議決を行う機関であり、その前提として、他の機関や院の干渉を排除して行動できる自律権がある。この議院の自律権は、①自主組織権、②自律的運営権、③財政自律権の三つに大別できるところ、①自主組織権及び②自律的運営権については憲法上の規定が存在するものの(同58条1項、2項)、③財政自律権については国会法に規定が存在するのみで(同32条)、憲法は特に規定していない。よって、本記述は誤りである。
なお、国会法は、予備金を含む「両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。」(同32条1項)と規定している。両議院の所要経費は、一般会計歳出予算における独立した「国会所管」として計上・議決される。参考佐藤幸(日本国憲法論)507~508頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、共同相続人の一人は、他の共同相続人に自己の相続分を譲渡することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 67.1%結果正解解説相続分の譲渡については、明文規定があるわけではないが、民法905条に可能であることを前提とした規定が置かれていることから、当然に許容されると解されている。そして、判例は、「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり、分割が実行されれば、その結果に従って相続開始の時にさかのぼって被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。このように、相続分の譲受人たる共同相続人の遺産分割前における地位は、持分割合の数値が異なるだけで、相続によって取得した地位と本質的に異なるものではない。そして、遺産分割がされるまでの間は、共同相続人がそれぞれの持分割合により相続財産を共有することになる」としている(最判平13.7.10)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(詳解相続法)277~278頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)330頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、わいせつの目的をもって未成年者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪は成立せず、わいせつ目的誘拐罪のみが成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 73.8%結果正解解説判例は、刑法225条所定の目的を持って未成年者を誘拐したときは、同条の罪のみが成立するとしている(大判明44.12.8)。よって、本記述は正しい。参考山口(各)94頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)58頁。
条解刑法680頁。
大コメ(刑法・第3版)(11)539頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するように根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的から出たものであれば、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れない限り、国家公務員法との関係では実質的に違法性を欠き、正当な業務行為となる。憲法この問題の模試受験生正解率 60.7%結果正解解説判例は、いかなる取材活動が公務員に対する秘密漏示の「そそのかし」として国家公務員法111条によって処罰されるかが争われた事例において、「報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない」としている(最決昭53.5.31 外務省秘密電文漏洩事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕75事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、土地について設定されていた抵当権が実行され、当該土地上の建物について法定地上権が成立した場合、当該建物の所有者は、その法定地上権の登記をしていなくても、抵当権実行により当該土地の買受人となった者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。民法この問題の模試受験生正解率 90.0%結果正解解説競売によって法定地上権が成立する場合(民法388条前段)、法定地上権成立の当事者である土地の買受人と、建物所有者である法定地上権者との間においては、対抗要件は問題にならないから登記は不要である。したがって、本記述の場合、建物の所有者は、その法定地上権の登記をしていなくても、法定地上権の取得を抵当権の実行により土地の買受人となった者に対抗することができる。よって、本記述は正しい。
なお、法定地上権成立後に土地所有権を取得した者と法定地上権者、又は、法定地上権を譲り受けた者と土地所有者は、対抗関係に立つため、登記が必要であると解されている。参考道垣内(担物)226頁。
松井(担物)87~88頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙が所有し、管理している乙名義の更地を、自己が経営する工場の倉庫の敷地として利用しようと考え、乙に無断でその更地の登記名義を自己名義に変更したが、その上に倉庫を建築するには至らなかった。この場合、甲には不動産侵奪罪の実行の着手は認められない。刑法この問題の模試受験生正解率 44.6%結果正解解説不動産侵奪罪(刑法235条の2)の「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいう。窃盗罪との対比上、不動産を占拠する積極的な事実行為を要するので、登記簿上の名義変更をしただけでは、「侵奪」したとは認められない。したがって、本記述において、甲が更地の登記名義を自己名義に変更しても、不動産侵奪罪の実行の着手は認められない。よって、本記述は正しい。参考西田(各)177頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)141頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法行政機関が裁判官の懲戒処分を行うことはできないが、司法権の独立を実効的に保障するためには、司法権以外の権力が懲戒処分を行うことは一切避けなければならないとして、国会も裁判官の懲戒処分を行うことはできないと解されている。憲法この問題の模試受験生正解率 55.0%結果正解解説憲法は、同78条後段で、「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」と定めている。裁判官も公務員として身分関係の秩序を維持するために懲戒処分の対象となることは当然のことであるところ、その半面で司法権の独立の実効性確保のためには、司法権以外の権力が懲戒処分を行うことは避けるべきである。そこで、同条後段は、単に行政機関が裁判官の懲戒処分を行ってはならないということにとどまらず、それが裁判所によってなされるべきであること、すなわち行政機関だけでなく国会も処分機関として認めないものと解されている。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)667~668頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)247頁。
新基本法コメ(憲法)413頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、履行の場所が債権者の住所とされた種類債権の目的物は、債務者が物を取り分け、債権者に送付するため運送人に交付した時に特定する。民法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説債権の目的物を種類のみで指定した場合(種類債権)において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときは、当該債権の目的物の特定が認められる(民法401条2項)。判例は、種類債権の目的物の給付場所が債権者の住所とされている場合(持参債務の場合)は、債務者が債権者の住所において履行の提供をしない限り、物の給付に必要な行為を完了したとはいえないとした上で、債務者が物を取り分け、債権者に送付するため運送人に交付したのみでは、いまだ物の給付に必要な行為を完了したとはいえず、目的物が特定しないとしている(大判大8.12.25 民法百選Ⅱ〔初版〕1事件)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(新債総Ⅰ)219頁。
中田(債総)48頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、窃盗行為を目撃した警ら中の制服警察官に追跡されている窃盗犯人に、その事情を知りつつ特定の地域に逃走するよう勧告した場合、犯人隠避罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 84.2%結果正解解説判例は、犯人隠避罪における「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいうとしている(大判昭5.9.18)。そして、「隠避」には、逃走のための資金調達等の有形的方法だけでなく、犯人に逃走するよう勧告する(大判明44.4.25)といった無形的方法も含まれる。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)483頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)498頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、市が町内会に対し、無償で市有地を氏子集団によって管理運営されている神社の敷地としての利用に供している状態が、憲法第89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する。憲法この問題の模試受験生正解率 92.9%結果正解解説判例は、市が町内会に対し、無償で市有地を氏子集団によって管理運営されている神社の敷地としての利用に供している状態が政教分離規定違反となるかが争われた事例において、「憲法89条も、公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするもの」とした上で、「国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、前記の見地から、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべき」としている(最大判平22.1.20 空知太神社事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕47事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法根抵当権はあくまで抵当権の一形態であるから、根抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は、抵当権と同じである。民法この問題の模試受験生正解率 40.0%結果正解解説根抵当権は、抵当権の一形態として民法上規定されており、設定契約をもって定めるところに基づいて、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の範囲で負担することになるのみである(同398条の2第1項)。したがって、根抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は通常の抵当権(同370条、371条)と同じである。よって、本記述は正しい。参考道垣内(担物)239~240頁。
我妻・有泉コメ681頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙の財布を自己のものにしようと考え、乙に対し、社会通念上一般に相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行を加えたところ、乙が極度の小心者であったためにその反抗を抑圧されたことから、乙の反抗抑圧状態に乗じて同人から財布を奪った。この場合、甲に強盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.8%結果正解解説判例は、強盗罪(刑法236条)と恐喝罪(同249条)の区別について、暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかという客観的基準によって決せられるのであって、具体的事案の被害者の主観を基準として、その被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかによって決せられるものではないとした上で、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫が加えられた場合において、強盗罪の成立を認めている(最判昭24.2.8)。したがって、本記述において、甲は、乙に対し、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行を加えたにすぎないから、当該暴行により乙がその反抗を抑圧されたとしても、甲に強盗罪(同236条1項)は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)182頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)149頁、151頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば、自己に適用される法令や処分等が、特定の第三者の憲法上の権利・利益を侵害するから自己に適用すべきでないという形での違憲の主張は許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 72.5%結果正解解説判例は、貨物の密輸を企てた被告人が有罪判決を受けた際に、その付加刑として貨物の没収判決を受けた事例において、告知・弁解・防御の機会を与えることなく第三者の所有物を没収することは違憲であるとした上で、被告人がそのことを理由に上告することを、没収は被告人に対する付加刑であることに加え、「被告人としても没収に係る物の占有を剥奪され、またはこれが使用、収益をなしえない状態におかれ、更には所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかである」ということを理由として認めている(最大判昭37.11.28 第三者所有物没収事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕107事件)。したがって、自己に適用される法令や処分等が、特定の第三者の憲法上の権利・利益を侵害するから自己に適用すべきでないという形での違憲の主張が許されることがある。よって、本記述は誤りである。参考市川(憲法)337~339頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)356~357頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、財産分与をする際に、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提としていたが、その旨を黙示的に表示していたにすぎない場合には、財産分与契約について錯誤による取消しをすることはできない。民法この問題の模試受験生正解率 70.8%結果正解解説協議離婚に伴う財産分与(民法768条)において、分与者が自己に譲渡所得税が課されることを知らず、そのことを前提として意思表示をした場合、意思表示に対応する内心の意思自体を欠いてはいない以上、それはいわゆる動機の錯誤である。ウの解説で述べたように、動機の錯誤による意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができるが(同95条1項2号)、同号による取消しが認められるためには、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている必要がある(同条2項)。そして、ここにいう表示は黙示的なものでもよく、判例も、平成29年改正前民法下における本記述と同様の事例において、分与者の錯誤の主張を認めている(最判平元.9.14 民法百選Ⅰ〔第7版〕24事件)。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)155頁、160~161頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)173~175頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)22~23頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、A国民である甲は、A国で、日本国民である乙に対して腹部を蹴るなどの暴行を加えた。その後、乙は、乗船したB国船舶において公海を航行中、その船舶内で、甲の暴行によって生じた内臓の損傷が原因で死亡した。甲に刑法(傷害致死罪)が適用される。刑法この問題の模試受験生正解率 57.1%結果正解解説刑法1条1項は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と規定し、場所的適用範囲について、原則として、属地主義を定めている。したがって、日本国内で犯罪を行った国内犯に対しては、その国籍を問わず、刑法の適用がある。また、日本国外で犯罪を行った国外犯であっても、同2条以下に当たるときは、刑法が適用される。
本記述において、A国民である甲の暴行は、A国において、日本国民である乙に対して行われており、当該暴行に起因する傷害により乙は死亡しているので、甲の行為は傷害致死罪(刑法205条)に当たる。したがって、国民以外の者の国外犯の規定(同3条の2第3号)により、甲に刑法(傷害致死罪)が適用される。よって、本記述は正しい。参考山口(総)417頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)465頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法労働基本権は、使用者に対する民事上の権利という側面を有しており、この側面においては、当該権利は、私人間にも直接適用されるから、争議行為の民事免責を定める労働組合法第8条は、憲法第28条の確認規定であるといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 59.2%結果正解解説労働基本権は、社会権的側面、自由権的側面及び使用者に対する民事上の権利という側面を有する複合的な性格を有している。そして、これらのうち、使用者に対する民事上の権利という側面において、労働基本権は、私人間にも直接適用されると解されている。このことから、労働組合法8条が、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」と規定し、労働組合又はその組合員の民事免責を認めていることは、使用者労働者間という私人間の民事上の責任関係について、憲法28条が適用されることを確認するものであるといえる。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)299~301頁。
佐藤幸(日本国憲法論)414頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)527~528頁。 -
民法賃貸借契約において敷金が差し入れられていた場合に関して、判例の趣旨に照らした場合、賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を第三者に譲り渡した場合、敷金に関する権利義務関係は、敷金交付者である旧賃借人と賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務の担保とすることを合意し、又は、旧賃借人が新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなどの特段の事情がない限り、新賃借人に承継されない。民法この問題の模試受験生正解率 78.8%結果正解解説賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない(民法622条の2第1項2号)。このように、同号は、賃借人が賃貸人の承諾(同612条1項)又は裁判所による許可(借地借家法19条、20条)を得て賃借権を譲渡する場合のように適法に賃借権を譲渡したときは、その時点で賃貸人と旧賃借人(敷金交付者)との間の敷金契約は終了し、賃貸人に敷金返還債務が発生するので、敷金に関する権利義務関係は、新賃借人に当然には承継されない。そして、適法に賃借権を譲渡した賃借人が、賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務不履行の担保とすることを約し、又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなどの事情があるときは、民法622条の2第1項2号の適用はないと解されている(最判昭53.12.22 民法百選Ⅱ〔第8版〕66事件)。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)228頁。
中田(契約)417~418頁。
平野(債各Ⅰ)304頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙から、Vの殺害に用いるための猛毒の青酸ソーダを入手するよう依頼されてこれを承諾し、致死量の青酸ソーダを入手してこれを乙に渡した。しかし、乙は、この青酸ソーダを使用せず、別途調達した睡眠薬をVに服用させた上、Vを絞殺した。この場合、甲に殺人予備罪の共同正犯は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 82.1%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、殺人予備罪の共同正犯(刑法201条本文、60条)の成立を認めた原審の判断を是認している(最決昭37.11.8 刑法百選Ⅰ〔第8版〕80事件)。したがって、本記述において、甲に殺人予備罪の共同正犯が成立する。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)423頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)337頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第3条の内閣の「助言と承認」の意味について、これを一体的なものとして捉え、「助言と承認」という一つの行為が、国事行為に際して要求されるとする見解によれば、国事行為について天皇からの積極的な発議が認められることになる。憲法この問題の模試受験生正解率 83.6%結果正解解説憲法3条は、天皇の国事行為に際して「内閣の助言と承認」を必要とする旨規定している。この「助言と承認」の意味について、「助言と承認」を一体的に捉え、天皇に対して事前の指示を与えさえすればよい(事前の1回の閣議決定で足りる。)と解する見解がある。この見解は、同条の助言と承認の制度について、天皇が単独の意思によって行動することを禁じ、天皇の行動が全て内閣の意思に基づくことを要求する趣旨であるとする。この見解は、天皇からの積極的な発議を認めないため(事後の承認はない。)、事前の閣議決定があれば足りるとする。よって、本記述は誤りである。参考渡辺ほか(憲法Ⅱ)95~96頁。
毛利ほか(憲法Ⅰ)111頁。
新基本法コメ(憲法)30頁。 -
民法家庭裁判所が特定の法律行為について補助人Bに代理権を付与する旨の審判をした場合、被補助人Aは、自ら当該法律行為を単独で有効に行うことはできない。民法この問題の模試受験生正解率 52.4%結果正解解説代理権付与の審判(民法876条の9第1項)は、補助人に代理権を与えるものにすぎず、補助人が代理権付与の審判により代理権を与えられた行為について、被補助人の行為能力は制限されない。したがって、家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、自ら当該法律行為を単独で有効に行うことができる。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)100~101頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)44~45頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、A名義の預金口座から現金を引き出す目的で、AからA名義のキャッシュカードをだまし取るとともに、暗証番号を聞き出した。その後、甲は銀行に向かい、同銀行の現金自動預払機で同キャッシュカードを使用し、聞き出した暗証番号を入力して現金を引き出した。この場合、甲には、詐欺罪と窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。刑法この問題の模試受験生正解率 64.6%結果正解解説判例は、消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させた上、これを利用して同社の現金自動入出機から現金を引き出した行為について、詐欺罪(刑法246条1項)と窃盗罪(同235条)が成立し、これらは併合罪(同45条前段)となるとしている(最決平14.2.8)。甲は、AからA名義のキャッシュカードをだまし取り、同キャッシュカードを使用して、銀行の現金自動預払機から現金を引き出している。したがって、甲には、詐欺罪と窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。よって、本記述は正しい。参考山口(各)278頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)226頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり、病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させた行為が一種の宗教的行為としてなされたものであったとしても、信教の自由の保障は絶対無制限ではなく、当該行為が著しく反社会的なものであることは否定できないから、当該行為は信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかない。憲法この問題の模試受験生正解率 58.0%結果正解解説判例は、病者の平癒のために行った加持祈祷行為により、被害者が急性心臓麻痺により死亡したため、当該行為を行った僧侶(注:被告人)が傷害致死罪で起訴されたところ、当該行為が正当業務行為に当たるとして、違法性が阻却されないかが問題となった事例において、「信教の自由の保障も絶対無制限のものではない」とした上で、被告人の当該行為が、「一種の宗教行為としてなされたものであったとしても、それが……他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであって、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはな」いとしている(最大判昭38.5.15 憲法百選Ⅰ〔第7版〕38事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、物の引渡しを要する請負において、請負人が仕事を完成した後は、注文者は、物の引渡しを受ける前であっても、損害を賠償して契約の解除をすることができない。民法この問題の模試受験生正解率 75.2%結果正解解説請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。すなわち、請負人の債務不履行が認められない場合においては、同条に基づいて注文者が損害を賠償して請負契約の解除をすることができるのは、請負人が仕事を完成しない間に限られるので、物の引渡しを要する請負において、仕事が完成しているが引渡しがされていない場合には、同条による解除は認められない。よって、本記述は正しい。参考中田(契約)522頁。
曽野ほか(民法Ⅳ)339~340頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、単純遺棄罪(刑法第217条)が成立するには、老年、幼年、身体障害等のために扶助を必要とする者を故意に遺棄した結果、現実に生命・身体に対する危険が発生したことが必要である。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、尊属殺人に関し、普通殺人と区別して特別の罪を設け、刑罰を加重すること自体は憲法第14条第1項に抵触しないものの、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得べき根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして同項に違反する。憲法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説判例は、尊属殺人を普通殺人と区別して刑を加重する刑法200条(注:当時)の合憲性が争われた事例において、「通常、卑属は父母、祖父母等の直系尊属により養育されて成人するのみならず、尊属は、社会的にも卑属の所為につき法律上、道義上の責任を負うのであって、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するものといわなければならない」とした上で、「このような点を考えれば、尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきである」から、被害者が尊属であることを「法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもってただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず」、憲法14条1項に違反するということもできないとしている(最大判昭48.4.4 尊属殺重罰規定判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕25事件)。したがって、前段は正しい。また、同判決は、刑罰の「加重の程度が極端であって、……立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理なものといわなければならず、かかる規定は憲法14条1項に違反して無効であるとしなければならない」としている。したがって、後段も正しい。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることもできない。民法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説判例は、「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがって、登記請求権を有するものではないと解すべきであ」るから、権利能力なき社団が不動産登記の申請人となることは許されないとしている(最判昭47.6.2 民訴法百選〔第4版〕9事件)。また、同判決は、登記簿上、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義の記載が許されるかについて、「かような登記を許すことは、実質において社団を権利者とする登記を許容することにほかならないものであるところ、不動産登記法は、権利者として登記せらるべき者を実体法上権利能力を有する者に限定し、みだりに拡張を許さないものと解すべきである」から、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義の登記は許されないとしている。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)385~386頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)100頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、息子乙が犯した殺人事件につき、逮捕を免れさせるため、乙の犯行に関わる証拠を隠滅した。この場合、甲に証拠隠滅罪が成立するが、刑法第105条の適用によりその刑が必要的に免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 41.6%結果正解解説犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のために証拠隠滅等の罪を犯したときは、その刑を免除することができるとして、刑の任意的免除を認めている(刑法105条)。本記述では、甲に自己の息子乙が犯した殺人事件に関する証拠を隠滅したとして、証拠隠滅罪が成立するが、甲は乙の「直系血族」であるので、同条適用によって、その刑を任意的に免除することができる。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)589頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)512頁。
条解刑法341頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法予算は、内閣によって作成され、国会の審議・議決を受けるが、国会が、内閣によって作成された予算の原案の款項を削除し、又は款項の金額を削減する減額修正は、内閣の予算提出権を侵すものであり許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 84.5%結果正解解説予算は、内閣によって作成され、国会に提出してその審議を受け議決を経なければならない(憲法86条)。予算の議決権を有する国会が予算に対してどこまで修正権を持つかについて、増額修正が認められるかについては争いがあるものの、大日本帝国憲法67条のような国会の予算審議権を制限する規定が現行憲法にないこと、財政国会中心主義の原則(憲法83条)が確立していることから、予算の減額修正については国会が自由になし得ると解されている。したがって、国会は、予算の議決に際し、内閣によって作成された予算の原案の款項を削除し、又は款項の金額を削減する減額修正をすることができる。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)374~375頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)351頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)410~411頁。
新基本法コメ(憲法)456頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、甲建物の賃借人Aが、甲建物について留置権を行使している場合において、Aが、甲建物の所有者である債務者Bの承諾を得ないで甲建物をCに転貸した場合、Aの留置権は消滅する。民法この問題の模試受験生正解率 64.3%結果正解解説留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を賃貸することができず(民法298条2項本文)、これに違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる(同条3項)。もっとも、債務者は留置権の消滅請求権を取得するだけであり、賃貸により当然に留置権が消滅するのではない。また、留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅するが(同302条本文)、留置物を賃貸しても、留置権者は間接占有を保持し、占有を失うわけではないので、留置権は消滅しない。したがって、本記述においても、Aの留置権は消滅しない。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ671~673頁。
道垣内(担物)43~44頁。
松井(担物)153~154頁。
安永(物権・担物)524~525頁。
我妻・有泉コメ546~548頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、過失犯の成立には、構成要件的結果を回避する義務に違反したことが必要であるところ、たとえ行為者が結果回避義務を尽くしても結果を回避することができなかった場合には、行為者が結果回避義務に従った行動をとらなかったとしても、過失犯は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 77.7%結果正解解説判例は、行為者が結果回避義務に従った行動をとらなかった場合において、仮に行為者が結果回避義務を尽くしても結果が発生したといえる場合(結果回避義務を尽くしていれば結果が発生しなかったと立証できなかった場合)には、過失犯の成立を否定している(最判平15.1.24 刑法百選Ⅰ〔第8版〕7事件)。よって、本記述は正しい。参考山口(総)248~249頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)140頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国会の各会期は独立しており、会期中に議決されなかった案件は後会に継続しないとする原則を会期不継続の原則というが、この原則については憲法には明文の規定はなく、国会法において規定されている。憲法この問題の模試受験生正解率 39.9%結果正解解説国会の各会期は独立しており、会期中に議決されなかった案件は後会に継続しないとする原則を会期不継続の原則という。憲法にはこの原則を定めた明文の規定は存在しないが、国会法は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」(同68条本文)とし、この原則を定めている。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)334頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)253頁。
新・コンメ憲法508頁。 -
民法Aが、Bの代理人としてBが所有する甲土地を売却する代理権を有していないのに、Bの代理人と称して甲土地をCに売る契約(以下「本件契約」という。)を締結した場合に関して、判例の趣旨に照らした場合、Aは、過失なく自己に代理権があると信じて本件契約を締結したときであっても、Cに対する無権代理人の責任を免れることはできない。民法この問題の模試受験生正解率 62.0%結果正解解説判例は、民法117条による無権代理人の責任は、「無権代理人が相手方に対し代理権がある旨を表示し又は自己を代理人であると信じさせるような行為をした事実を責任の根拠として、相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持のために、法律が特別に認めた無過失責任であ」るとしている(最判昭62.7.7 民法百選Ⅰ〔第9版〕31事件)。したがって、本記述において、Aは、過失なく自己に代理権があると信じて本件契約を締結したときであっても、Cに対する無権代理人の責任を免れることはできない。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)299~300頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)224~226頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、近所に引っ越してきた乙に対し、町内会の活動に協力してくれるよう依頼するため乙宅を訪問したところ、乙から「5分ほど出掛けてくるので、この部屋で待っていてほしい。」と言われ、乙宅の1階にある応接間に通されたが、乙が出掛けて誰もいなくなったのをいいことに、2階に上がり、書斎や寝室に立ち入った。この場合、甲に住居侵入罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 54.0%結果正解解説住居侵入罪の「侵入」とは、住居への住居権者の意思に反した立入りをいい(最判昭58.4.8 刑法百選Ⅱ〔第8版〕16事件)、住居権者が立入りについて許諾がある場合には、住居侵入罪は成立しない。この立入りについての許諾は、住居の一部に限定して行うことが可能であるから、許諾された領域外に立ち入った場合には、住居侵入罪が成立する。本記述において、乙は、甲に対して、「この部屋で待っていてほしい。」と言って、甲を乙宅の1階にある応接間に通したのであるから、立入りについての許諾は、応接間に限定されたものであるといえる。それにもかかわらず、甲は、勝手に書斎や寝室に立ち入っており、この立入りは、乙の許諾の範囲を超え、乙の意思に反するものといえる。したがって、甲に住居侵入罪が成立する。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)122~123頁、125頁。
井田(各)184頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法恩赦の決定は内閣の事務であるが、恩赦が裁判によって確定した刑罰の効果を消滅させる行為であり、権力分立原理の例外的措置であることから、恩赦の内容及びその手続については法律で定める必要がある。憲法この問題の模試受験生正解率 62.8%結果正解解説内閣の事務の一つには、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権という5種のいわゆる恩赦の決定がある(憲法73条7号)。そして、恩赦が立法権及び司法権の作用を変動させる効果を持ち、権力分立原理の例外的措置であることから、恩赦の内容とその手続については、法律で定めることが必要と解され、実際に恩赦法が制定されている。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)545~546頁。
渋谷(憲法)612頁。 -
民法Aが所有する甲土地を建物所有目的でAから賃借したBが、甲土地上に乙建物を建築して所有している場合に関して、判例の趣旨に照らした場合、Bが乙建物について、Bの子であるC名義で所有権保存登記をしている場合において、DがAから甲土地を譲り受けたときは、AD間に甲土地の賃貸人たる地位を移転する旨の合意がなければ、甲土地の賃貸人たる地位はDに移転しない。なお、甲土地の賃借権の登記はされていないものとする。民法この問題の模試受験生正解率 44.6%結果正解解説不動産の賃貸借が、登記(民法605条)又は借地借家法10条、31条の規定により対抗要件を備えている場合には、目的不動産の譲渡人と譲受人との間で、目的不動産の譲渡の合意があれば、賃貸人たる地位の移転の合意がなくても、賃貸人たる地位が譲受人に移転する(民法605条の2第1項)。もっとも、判例は、借地借家法10条の対抗要件について、建物所有目的の土地の賃借人が、借地上に所有する建物につき、同居している家族の名義で所有権保存登記をしても、その建物の登記をもって、土地の賃借権を第三者に対抗することはできないとしている(最大判昭41.4.27 民法百選Ⅱ〔第9版〕51事件)。したがって、乙建物についてBの子であるC名義で所有権保存登記がされている本記述においても、甲土地の賃貸借は対抗要件を備えていないから、AD間で甲土地の賃貸人たる地位の移転の合意(民法605条の3前段)がなければ、甲土地の賃貸人たる地位はAからDに移転しない。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)184~185頁、208頁。
中田(契約)449頁、451頁、485頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪の「損壊」とは、電子計算機や電磁的記録を物理的変更、滅失させ、あるいは、その効用を害することをいうから、それらの物を物質的に変更、滅失させる場合のほか、電磁的記録の消去も「損壊」に含まれる。刑法この問題の模試受験生正解率 82.6%結果正解解説電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)における「損壊」とは、毀棄罪の場合と同じく、電子計算機や電磁的記録を物理的変更、滅失させ、あるいは、その効用を害することをいうと解されている。したがって、それらの物を物質的に変更、滅失させる場合のほか、電磁的記録の消去も「損壊」に含まれる。裁判例も、放送会社に設置されたサーバーコンピューターのハードディスク内に記憶されていた天気予報画像のデータファイルを消去した行為を「損壊」に当たるとしている(大阪地判平9.10.3)。よって、本記述は正しい。参考大塚ほか(基本刑法Ⅱ)106頁、346頁。
条解刑法725頁。
大コメ(刑法・第3版)⑿249頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法第37条第2項は、刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する旨規定するところ、同項は、被告人が有罪の判決を受けた場合、その被告人に証人尋問の費用の負担を命ずることを禁止する趣旨ではないが、被告人の費用負担への不安から十分な証人喚問をためらうことのないよう、少なくとも、その費用のうち強制にかかる費用については国家が負担すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 59.2%結果正解解説憲法37条2項後段は、被告人に「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」(証人喚問権)を保障している。ここにいう「公費で」について、判例は、「証人訊問に要する費用、すなわち、証人の旅費、日当等は、すべて国家がこれを支給するのであって、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨」であって、有罪判決を受けた場合になお被告人に対しそれを訴訟費用として負担させてはならないという趣旨ではないとしている(最大判昭23.12.27)。したがって、同判決は、被告人の費用負担への不安から十分な証人喚問をためらうことのないよう、少なくとも、その費用のうち強制にかかる費用については国家が負担すべきであるとはしていない。よって、本記述は誤りである。
なお、同判決のように考えても、有罪となりそうであれば、被告人は費用の最終的な負担を恐れて証人喚問権を行使しないことが予想され、同条の趣旨にそぐわないのではないかという懸念から、被告人が有罪となったとしても強制にかかる費用のみを国家が負担すると解する方が同条の文言に適合的だとする見解もある。参考注釈日本国憲法⑶396~397頁。
新基本法コメ(憲法)281頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、土地の所有者は、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けるために必要な範囲内で他人が所有する設備を使用することができる場合、その利益を受ける割合に応じて、その設備の改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 72.9%結果正解解説土地の所有者は、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他人が所有する設備を使用することができる(民法213条の2第1項)。例えば、他人の所有する給排水設備を使用しなければ給排水ができない宅地がある場合に、その宅地の所有者に、宅地の給排水のために必要な範囲内で、他人の給排水設備を使用する権利が認められる。そして、土地の所有者は、同項により他人の所有する設備を使用することができる場合においては、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならないものとされている(同条7項)。よって、本記述は正しい。参考山野目(物権)195~197頁。
平野(物権)310~311頁。
Q&A令和3年改正民法33~34頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、暴力団組員である甲と乙は、記者であるXが、甲と乙が所属する暴力団の資金源であるフロント企業を誹謗中傷する記事を書いたことに対して憤激し、Xに対して暴行を加えて傷害を負わせる旨を共謀し、共にXに暴行を加えたが、その際におけるXの言動が気に食わず激高した乙が、殺意をもって護身用に所持していたピストルをXに向けて発砲しXを殺害した。この場合、甲には傷害致死罪の共同正犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 78.0%結果正解解説判例は、暴行ないし傷害を共謀した者のうち1名が未必的故意をもって被害者を殺害したという事例において、「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから」、殺意のなかった者らについては、「殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」としている(最決昭54.4.13 刑法百選Ⅰ〔第8版〕92事件)。したがって、本記述において、殺意をもってXを殺害した乙には殺人罪(刑法199条)の単独犯が成立し、殺意のなかった甲との間では傷害致死罪の限度で共同正犯(同205条、60条)となる。したがって、甲には傷害致死罪の共同正犯が成立する。よって、本記述は正しい。参考大谷(講義総)413頁、464頁。
井田(総)510~511頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)379~380頁。
条解刑法160頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法摂政は、天皇の法定代理機関であり、天皇の名で国事行為を行い、摂政への就任については、皇室典範が定めるが、皇位の場合と同様、女性が就任することはできない旨規定されている。憲法この問題の模試受験生正解率 83.6%結果正解解説摂政は、天皇の法定代理機関であり、天皇の名で国事行為を行う(憲法5条前段)。摂政は、①天皇が成年に達しないとき、②天皇が精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事行為を自ら行えないような状態にあるときに(皇室典範16条)、置かれる。摂政への就任は、皇位の場合(同2条)とは異なり、皇后や皇太后といった女性も資格を有する(同17条)。よって、本記述は誤りである。
なお、憲法2条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定し、皇室典範1条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定している。参考佐藤幸(日本国憲法論)568頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)83頁、102~103頁。
青井・山本(憲法Ⅱ)41頁、44頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、人格的利益を侵害する不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者がその行使の意思を表示すれば、具体的な金額の請求権が当事者間で客観的に確定していなくても、代位行使することができる。民法この問題の模試受験生正解率 78.9%結果正解解説「債務者の一身に専属する権利」は、債権者代位権行使の対象とならない(民法423条1項ただし書)。人格的利益を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権について、判例は、被害者がその行使の意思を表示しただけでなく、具体的な金額の請求権が当事者間で客観的に確定した場合には代位行使することができるが、その前の段階では、代位行使の対象とはならないとしている(最判昭58.10.6 倒産百選〔第6版〕23事件)。したがって、具体的な金額の請求権が当事者間で客観的に確定していなければ、代位行使することはできない。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ341頁。
潮見(プラクティス債総)195~196頁。
中田(債総)251~252頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、心神耗弱とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が著しく減退した状態を指す。刑法この問題の模試受験生正解率 41.8%結果正解解説刑法39条1項の心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、同条2項の心神耗弱とは、精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には至っていないが、その能力が著しく減退した状態をいう(大判昭6.12.3 刑法百選Ⅰ〔第4版〕33事件)。したがって、心神耗弱に該当するのは、精神の障害により弁識能力が著しく減退した状態と精神の障害により行動制御能力が著しく減退した状態のいずれかが認められる場合である。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)298頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)223頁。
条解刑法167頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、宗教法人に対する解散命令は、宗教法人の法人格をはく奪するなどの法人としての活動に対する規制を行うにすぎず、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあることからすると、解散命令は、その宗教団体や信者の精神的・宗教的側面をも対象としているといえるので、信教の自由の重要性に鑑み、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 58.0%結果正解解説判例は、裁判所による宗教法人に対する解散命令が、当該法人の構成員たる信者の信教の自由を不当に制約し許されないのではないかが争われた事例において、宗教法人「法による宗教団体の規制は、専ら宗教団体の世俗的側面だけを対象とし、その精神的・宗教的側面を対象外としているのであって、信者が宗教上の行為を行うことなどの信教の自由に介入しようとするものではない……。……宗教法人の解散命令の制度も、……司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめることが可能となるようにしたものであ」るとした上で、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも、……宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない」としている(最決平8.1.30 宗教法人オウム真理教解散命令事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕39事件)。さらに、同決定は、当該事例における解散命令の合憲性の判断において、宗教法人「法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではな」いとしている。したがって、同決定によれば、宗教法人に対する解散命令は、その宗教団体や信者の精神的・宗教的側面を対象とするものではない。よって、本記述は誤りである。
-
民法債権者Aが債務者Bに対して有する預貯金債権でない金銭債権甲(以下「甲債権」という。)をCとDに二重譲渡した場合に関して、判例の趣旨に照らした場合、Aが第一譲渡について確定日付のある証書による通知をしてこれがBに到達した後に、第二譲渡についても確定日付のある証書による通知をしてこれがBに到達した場合において、甲債権が、第一譲渡及びその通知の時点においては現に発生していなかったが、第二譲渡の時点においては発生していたときは、BがCに対して弁済をしても、甲債権は消滅しない。
なお、本問では、Cに対する債権譲渡を「第一譲渡」といい、Dに対する債権譲渡を「第二譲渡」という。民法この問題の模試受験生正解率 83.9%結果正解解説本記述において、第一譲渡は、将来債権の譲渡であるところ、民法は、債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(同466条の6第1項)として、将来債権の譲渡が有効であることを認めている。将来債権が譲渡された場合は、将来債権につき具体的な債権の成立後、改めて譲渡の意思表示などを要せず、譲受人は、発生した債権を当然に取得する(同条2項)。そして、債権譲渡の対抗要件を定める同467条1項は、「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」として、現に発生していない債権の譲渡についても、債権譲渡の時点で債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備し得る旨明記している。したがって、本記述においては、Cは、発生した甲債権を取得し、第三者対抗要件も具備していることとなる。そして、判例は、債権が二重に譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付のある証書による通知がされた場合においては、「譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日附の先後によって定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時又は確定日附のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであ」るとしている(最判昭49.3.7 民法百選Ⅱ〔第9版〕23事件)。本記述においては、第一譲渡についての通知が第二譲渡についての通知よりも先にBに到達しているので、Cが甲債権の債権者となる。したがって、BがCに対して弁済をすれば、甲債権は消滅する。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ254頁、267~268頁。
潮見(プラクティス債総)465~467頁、520頁。
中田(債総)645頁、648頁、667~668頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、Aを恐喝してAから財物の交付を受け、その恐喝の手段として用いられた暴行によりAに傷害を負わせた。この場合、甲には恐喝罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。刑法この問題の模試受験生正解率 64.6%結果正解解説判例は、恐喝の手段として暴行が用いられ、その暴行により、被害者に傷害を負わせた場合には、恐喝罪(刑法249条)と傷害罪(同204条)の観念的競合(同54条1項前段)となるとしている(最判昭23.7.29)。したがって、甲には、恐喝罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。よって、本記述は正しい。
なお、恐喝の手段として用いられた暴行により傷害が生じていない場合は、その暴行は恐喝罪において評価し尽くされているから、恐喝罪とは別に暴行罪は成立しない。参考大塚ほか(基本刑法Ⅱ)263頁。
大コメ(刑法・第3版)⒀529頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法裁判官が法律を事案に適用して判決を下す場合には、当該法律の合憲性が前提となることから、理論的には当該法律の違憲審査が先行すべきであり、訴訟において違憲の争点が適法に提起されている場合には、裁判官は憲法審査義務を負っているとする見解に対しては、我が国が採用している付随的違憲審査制においては、裁判所は必要以上に政治部門の判断に介入すべきではないと批判することができる。憲法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説訴訟において違憲の争点が適法に提起されている場合、裁判官が当該法律を適用して判決を下す場合には当該法律の合憲性が前提となることからすれば、理論的には当該法律の違憲審査が先行すべきであり、裁判官は憲法審査義務を負っているとする見解がある。これに対しては、付随的違憲審査制においては、当該事件の解決に必要な限りで憲法判断が行われるのが建前であり、裁判所は必要以上に政治部門の判断に介入すべきではないというのを主たる論拠として、訴訟において違憲の争点が適法に提起されている場合でも、裁判所はその争点に触れずに事件を解決することができるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきでもないという憲法判断回避原則が一般に主張されている。よって、本記述は正しい。参考野中ほか(憲法Ⅱ)310~311頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)363~364頁。
憲法百選Ⅱ〔第7版〕359頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、Aが甲土地をBに譲渡した後に死亡し、Aを単独相続したCが限定承認をした場合、Bは、その後に甲土地について所有権移転登記をしても、甲土地の所有権の取得を相続債権者に対抗することができない。民法この問題の模試受験生正解率 58.3%結果正解解説判例は、被相続人が不動産を第三者に譲渡したが、所有権移転登記をすることなく相続が開始し、限定承認がされた場合、限定承認によって所有権移転登記がされていない財産が相続財産及び受遺者に対する弁済のための引当財産であるという性質が確立することを理由に、第三者は、後日登記を具備したとしても相続債権者及び受遺者に対抗することができないとしている(大判昭9.1.30)。したがって、本記述においても、Bは、Cが限定承認をした後に、甲土地について所有権移転登記をしても、甲土地の所有権の取得を相続債権者に対抗することができない。よって、本記述は正しい。
なお、判例は、「不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない」としている(最判平10.2.13 民法百選Ⅲ〔第3版〕83事件)。参考吉田(物権Ⅱ)887頁。
新注釈民法(19)639頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、単純遺棄罪(刑法第217条)が成立するには、老年、幼年、身体障害等のために扶助を必要とする者を故意に遺棄した結果、現実に生命・身体に対する危険が発生したことが必要である。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、職業の許可制は、職業の自由に対する強力な制限であるから、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置である場合であっても、許可制と比べてより緩やかな規制によってはその目的を十分に達することができない場合でなければ、合憲性を肯定し得ない。憲法この問題の模試受験生正解率 47.5%結果正解解説判例は、スーパーマーケット等を経営する原告が、店舗内での医薬品の一般販売業の許可を申請したところ、許可の条件である旧薬事法の適正配置規制に抵触するとして不許可とされたため、当該規制が憲法22条1項に違反すると主張し、その不許可処分の取消しを求めた事例において、「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」としている(最大判昭50.4.30 薬事法距離制限違憲判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕92事件)。したがって、同判決は、職業の許可制は、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するとしつつも、職業の許可制が社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置である場合、許可制と比べてより緩やかな規制によってはその目的を十分に達することができない場合でなければ、その合憲性を肯定し得ないとはしていない。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、買戻しの特約のある不動産の買主が、買い受けた不動産を第三者に譲渡し、所有権移転登記をした場合、売主が買戻しの意思表示をすべき相手方は、転得者ではなく、買主である。民法この問題の模試受験生正解率 74.2%結果正解解説判例は、買戻しの特約付きの売買契約により不動産を買い受けた者が、特約所定の買戻期間中に、更にその不動産を第三者に売り渡し、かつ所有権移転登記を経由した場合は、その不動産の売主が買戻権を行使するには、転得者に対してすべきであるとしている(最判昭36.5.30 不動産取引百選〔第3版〕82事件)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(新契各Ⅰ)227頁。
平野(債各Ⅰ)204頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙に対して、Xに傷害を負わせることを唆したところ、乙はその旨決意し、深夜、帰宅するXを襲撃するために、Xの自宅付近で待ち伏せしていたが、Xと同居する双子の弟Yがこちらに向かってくるのを見て、YをXと誤認し、Yに傷害を負わせた。この場合、甲には、Yに対する傷害罪の教唆犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 78.0%結果正解解説判例によれば、教唆者の認識内容と、被教唆者の実行行為及び結果との間に食い違いがあっても、それが同一構成要件の範囲内にとどまる限り、教唆者の故意は阻却されない。判例は、A方に侵入して金銭を窃取することを教唆したところ、被教唆者が誤って隣家のB方に侵入して衣類を窃取した事例において、窃盗罪の教唆犯が成立するとしている(大判大9.3.16)。本記述において、甲は、乙に対して、Xに傷害を負わせるように教唆し、その旨決意した乙が、YをXと誤認して、Yに傷害を負わせている。これは、乙にとっては客体の錯誤であるが(Yに対する傷害罪の故意犯が成立する。)、甲にとっては方法の錯誤であると考えられる。そのため、法定的符合説によると、構成要件的に符合する限りで認識していなかった客体に対する故意が認められるため、甲のYに対する傷害の故意が認められる。したがって、甲にはYに対する傷害罪の教唆犯が成立する。よって、本記述は正しい。参考大谷(講義総)464~465頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)374~375頁。
大コメ(刑法・第3版)(5)18頁、614~615頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第73条第6号本文は、「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」を内閣の事務として規定しているところ、この「憲法及び法律」について一体として読む必要があるとの見解によれば、法律に定めのない事項を定める独立命令は許されないことになる。憲法この問題の模試受験生正解率 62.8%結果正解解説憲法73条6号本文は、「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」を内閣の事務として規定している。「憲法及び法律の規定を実施」するためという文言から、内閣は憲法を直接実施するための政令を制定し得ると解する余地もあるとする見解もある。このような見解からは、法律に定めのない事項を定める独立命令は許されることになる。しかし、憲法を直接実施する権限を持つのは、唯一の立法機関(同41条後段)である国会のみであるから、政令は直接的には法律を実施するものであり、同73条6号本文の「憲法及び法律」は一体として読む必要があると解されている。したがって、このように解した場合、内閣は憲法を直接実施するための政令を制定し得ず、法律の存在を前提としない独立命令は許されないことになる。よって、本記述は正しい。参考野中ほか(憲法Ⅱ)210~211頁。
高橋(立憲主義と日本国憲法)408頁。
毛利ほか(憲法Ⅰ)233頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、地役権者は、承役地を不法に占有する者がいる場合であっても、地役権に基づき承役地の自己への明渡しを請求することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 92.0%結果正解解説地役権は物権であるから、地役権者は、その侵害に対して直接に物権的請求権を行使することができる。もっとも、地役権は承役地を占有すべき権能を当然には含まないため、返還請求は認められない。したがって、地役権者は、承役地を不法に占有する者に対し、地役権に基づき承役地の自己への明渡しを請求することはできない。よって、本記述は正しい。参考佐久間(物権)271頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)215~216頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であれば足り、必ずしもその行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものであることを要しない。刑法この問題の模試受験生正解率 77.7%結果正解解説判例は、業務上過失致死傷罪(刑法211条1項前段)にいう「業務」について、「人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為」であって、「他人の生命身体等に危害を加える虞あるもの」としている(最判昭33.4.18 刑法百選Ⅰ〔第2版〕62事件)。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)68頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)39頁。
条解刑法636頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、日本国籍は重要な法的地位であり、父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子自身の意思や努力によっては変えられない事柄であるため、こうした事柄により国籍取得に関して区別することが憲法第14条第1項に違反しないというためには、立法目的が重要であり、立法目的と手段との間に実質的関連性が存することを要する。憲法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説判例は、日本人の父が生後認知した婚外子について、父母がその後婚姻していることを国籍取得の要件としていた国籍法(平成20年法律88号による改正前のもの)3条1項の規定の合憲性が争われた事例において、国籍取得に関する要件をどのように定めるかについては、立法府の裁量判断に委ねられるとした上で、かかる「裁量権を考慮しても、なおそのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない場合」、又はその具体的な区別と「立法目的との間に合理的関連性が認められない場合」には、当該区別は、合理的な理由のない差別として、憲法14条1項に違反するとしている。そして、同判決は、「日本国籍は、……我が国において……重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻……は、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である」から、「このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である」としている(最大判平20.6.4 国籍法違憲判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕26事件)。よって、本記述は誤りである。
なお、同判決の泉徳治裁判官の補足意見は、差別の対象となる権益が日本国籍という基本的な法的地位であり、差別の理由が憲法14条1項に差別禁止事由として掲げられている社会的身分及び性別であるから、それが同項に違反しないというためには強度の正当化事由が必要であって、国籍法3条1項の立法目的が国にとって重要であり、この立法目的と手段との間に事実上の実質的関連性が存することが必要であるとしている。 -
民法申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。民法この問題の模試受験生正解率 79.8%結果正解解説契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立するが(民法522条1項)、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する(同527条)。例えば、申込みを受けた者が、指定された第三者に商品を発送したときや、目的物の製造に着手したとき等に、それぞれの時点で契約が成立したことになる。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)18頁。
中田(契約)92~93頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、医師甲は、乙の同意を得ずに堕胎手術を行った。この場合、甲に業務上堕胎罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 44.9%結果正解解説業務上堕胎罪(刑法214条)は、医師等が「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたとき」に成立するものであり、女子の嘱託又は承諾は構成要件要素である。そして、不同意堕胎罪(同215条1項)は、女子の嘱託又は承諾がないのに堕胎を行う行為を処罰するものであり、身体に対する一方的な攻撃として違法性が高い類型の行為であるといえることから、堕胎罪中最も法定刑が重い。同罪は、その主体には制限がなく、業務上堕胎罪の主体である医師等も不同意堕胎罪の主体となり得る。そのため、医師等が、女子の嘱託又は承諾がないのに堕胎を行えば、不同意堕胎罪が成立し、女子の嘱託又は承諾を得て堕胎を行えば、軽い業務上堕胎罪が成立することとなる。したがって、甲に不同意堕胎罪が成立する。よって、本記述は誤りである。参考条解刑法653~654頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法予算の議決方法は、原則として、法律案に関する憲法第59条第1項で示されており、憲法第60条は、その例外的な方法のみを示したものであると解しているのは、予算の法的性格について、予算を法律であるとする見解(予算法律説)である。憲法この問題の模試受験生正解率 84.5%結果正解解説予算の法的性格について、予算を法律であるとする予算法律説によれば、憲法60条が予算に関する原則的な議決要件を示さずに、予算先議権及び議決における衆議院の優越のみを定めているのは、「法律案」である予算案の原則的な議決方法が同59条1項で示されていることを前提に、同項にいう「憲法に特別の定のある場合」として、例外的な方法のみを示したものという説明がなされる。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)581頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)350頁。
大石(憲法概論Ⅰ)456頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、連帯債務者の一人について時効が完成した場合においても、当事者が別段の意思表示をしていないときは、他の連帯債務者は、その一人の負担部分を含めて履行する義務を負い、これを履行したときにも、時効の完成した連帯債務者に対して求償権を行使することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 40.2%結果正解解説連帯債務者の一人について消滅時効が完成しても、消滅時効の効力は他の連帯債務者に及ばない(民法441条本文参照)。これは、消滅時効の完成を絶対的効力事由としたのでは、債権者が全ての連帯債務者に対して時効の進行を止める措置を執っておかないと債務が縮減することになり、債権の効力を強化するという連帯債務の性質に反するからである。したがって、本記述前段は正しい。もっとも、この場合であっても、弁済した連帯債務者は、消滅時効が完成した連帯債務者に対し、その負担部分について求償することが認められている(同445条、442条1項)。したがって、本記述後段は誤っている。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ462~463頁、469頁。
潮見(プラクティス債総)580~581頁。
中田(債総)534頁、539~540頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、過失犯の成立には、構成要件的結果を回避する義務に違反したことが必要であるところ、たとえ行為者が結果回避義務を尽くしても結果を回避することができなかった場合には、行為者が結果回避義務に従った行動をとらなかったとしても、過失犯は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 77.7%結果正解解説判例は、行為者が結果回避義務に従った行動をとらなかった場合において、仮に行為者が結果回避義務を尽くしても結果が発生したといえる場合(結果回避義務を尽くしていれば結果が発生しなかったと立証できなかった場合)には、過失犯の成立を否定している(最判平15.1.24 刑法百選Ⅰ〔第8版〕7事件)。よって、本記述は正しい。参考山口(総)248~249頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)140頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第14条第1項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには、合憲性の推定は排除され、裁判所は厳格な基準によってその差別が合理的であるかどうかを審査すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 49.2%結果正解解説判例は、憲法14条1項後段列挙事由(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)は例示的なものと解しており、当該事由に本記述のような意味における特段の効果を認めていない(最大判昭25.10.11、最大判昭39.5.27等)。よって、本記述は誤りである。
なお、本記述は、最大判昭60.3.27(サラリーマン税金訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕31事件)の伊藤正己裁判官の補足意見である。参考佐藤幸(日本国憲法論)225~226頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)286~287頁。
渋谷(憲法)202~203頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、抵当不動産の一部が、抵当不動産の所有者の過失によって損傷した場合、その損傷による抵当権者の損害賠償請求権は、抵当権を実行する前においては行使することができない。民法この問題の模試受験生正解率 76.0%結果正解解説抵当不動産の所有者が、抵当不動産を損傷し、その価値を下落させた場合、抵当権者は、損害の賠償を請求することができる。この点に関し、判例は、抵当不動産の価値が下落したため、被担保債権の満足が得られなくなったときに限り損害があるといえるとし(大判昭3.8.1)、損害の有無及びその額については、抵当権実行時又は被担保債権の弁済期到来後で抵当権実行前における損害賠償請求権行使時を基準に判断されるとしており(大判昭7.5.27 民法百選Ⅰ〔初版〕92事件)、抵当権の実行前における損害賠償請求権の行使を認めている。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ540~541頁。
道垣内(担物)190頁。
松井(担物)61~62頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、相手方の加害行為に対し、憤激又は逆上して反撃を加えた場合、直ちに防衛の意思の要件を欠き、正当防衛は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 84.2%結果正解解説判例は、「刑法36条の防衛行為は、防衛の意思をもってなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」としている(最判昭46.11.16 刑法百選Ⅰ〔初版〕36事件)。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)128~129頁。
西田(総)182~183頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)189頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用されるが、信教の自由や学問の自由は、自然人である個人の精神的活動の自由であるから、法人には適用されない。憲法この問題の模試受験生正解率 71.8%結果正解解説憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用される(最大判昭45.6.24 八幡製鉄事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕8事件参照)。つまり、自然人に固有なものは法人には保障されないが、その他の人権規定は、法人固有の性格と矛盾しない範囲内で適用される。精神的活動の自由については、争いがあるが、宗教法人には信教の自由(同20条)が、学校法人には学問の自由(同23条)が保障されると考えられている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)90~91頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)42~44頁。
毛利ほか(憲法Ⅱ)33~35頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、債権者代位権を行使するためには、債務者が無資力であることが必要でない場合があるが、詐害行為取消権を行使するためには、債務者が無資力であることが必要である。民法この問題の模試受験生正解率 56.6%結果正解解説債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる(民法423条1項本文)。そして、判例は、「債権者は、債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合にかぎり、自己の金銭債権を保全するため、民法423条1項本文の規定により当該債務者に属する権利を行使しうる」としているが(最判昭40.10.12)、特定債権の履行が債務者の有する権利を代位行使することによって確保される場合には、当該特定債権の保全のために債権者代位権の行使を認めており(債権者代位権の転用)、この場合には無資力要件を不要としている(大判明43.7.6 民法百選Ⅱ〔第7版〕14事件、大判昭4.12.16 民法百選Ⅱ〔第5版新法対応補正版〕12事件等)。一方、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるところ(同424条1項本文)、ここにいう「債権者を害する」とは、債務者の行為によって債務者の資産総額が債権額を弁済するのに不十分(無資力)となることをいうから、債務者が無資力でない場合には、債務者の処分行為は「債権者を害する」ものではなく、詐害行為にはならない。よって、本記述は正しい。
なお、同423条の7は、登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権を認めているが、これは、平成29年民法改正により、判例によって認められた債権者代位権の転用の具体例の一つを明文化したものである。参考内田Ⅲ339~340頁、351~352頁、366頁。
潮見(プラクティス債総)211頁、213頁、230~231頁。
中田(債総)248頁、264~267頁、293頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、緊急避難は、避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に成立するから、前者と後者が同等の場合には成立し得ない。刑法この問題の模試受験生正解率 73.0%結果正解解説緊急避難が成立するためには、避難行為から生じた害が、避けようとした害の程度を超えないことが必要である(法益の均衡)。したがって、侵害法益と保全法益が等しい場合にも、緊急避難は成立し得る。よって、本記述は誤りである。参考井田(総)334頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)211頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法「主権」について、国の政治の在り方を最終的に決定する権力又は権威の意味で使われることがあるが、その例として、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」というときの「主権」が挙げられる。憲法この問題の模試受験生正解率 79.7%結果正解解説「主権」の概念は多義的であり、①国家権力(統治権)そのもの、②国家権力の属性としての最高独立性(対外的独立性と対内的最高性)、③国政についての最高決定権という三つの異なる意味で使われることがある。このうち、③国政についての最高決定権としての主権とは、国の政治の在り方を最終的に決定する権力又は権威という意味である。例えば、「日本国民は、(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し」(憲法前文第1項)というときの「主権」がこれに当たる。他方、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」というときの「主権」は、上記①から③のうち、①国家権力(統治権)そのものを表すものとして使われている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)39~40頁。
芦部(憲法学Ⅰ)220~223頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、協議上の離婚は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ、判決による離婚は、離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生じる。民法この問題の模試受験生正解率 53.8%結果正解解説協議上の離婚は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じる(民法764条・739条1項)。これは、協議上の離婚成立の形式的要件であり、創設的届出となる。また、判決による離婚は、離婚判決が確定した時にその効力を生じる。よって、本記述は正しい。参考親族相続講義案72~73頁、81頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙とAが殴り合いのけんかをしているのを見掛け、一方的に乙に肩入れして、「いっそのことAを叩きのめしてしまえ。」などと申し向けたところ、これにより乙は、犯罪意思を強固にして、Aの腹部を強く蹴るなどして傷害を負わせた。この場合、甲には現場助勢罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 44.9%結果正解解説現場助勢罪(刑法206条)は、傷害又は傷害致死の行為が行われる際、その現場において勢いを助ける行為を処罰対象としている。勢いを助けるとは、本犯の気勢を高め、又は刺激すべき性質の行為をいい、例えば、「やれやれ。」、「もっとやれ。」などの声援がこれに当たる。もっとも、同条が、傷害の現場でなされた助勢行為を処罰する規定である以上、特定の正犯者の犯行を容易にする従犯とは異なる(大判昭2.3.28参照)。すなわち、傷害現場での声援であっても、双方がけんか状態になっている現場で、一方を加勢するために助勢した場合は、正犯者を幇助するものといえる。本記述では、甲は、傷害の現場において、一方的に乙に肩入れして、「いっそのことAを叩きのめしてしまえ。」などと申し向け、既に暴行ないし傷害の故意があった乙の犯意を強固にしている。したがって、甲には現場助勢罪は成立せず、傷害罪の従犯(同204条、62条1項)が成立する。よって、本記述は正しい。参考西田(各)47頁。
井田(各)65~66頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)32頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会に復興支援拠出金を寄付するために、会員から負担金を徴収することは、強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想、信条の自由を害するものではない。憲法この問題の模試受験生正解率 79.3%結果正解解説判例は、司法書士会が大震災により被災した他県の司法書士会に対する復興支援拠出金(以下「本件拠出金」という。)を寄付することが司法書士会の定める会の目的の範囲内といえるか、また、強制加入団体である司法書士会がその寄付のために負担金(以下「本件負担金」という。)を会員から徴収することができるかが争われた事例において、司法書士会が本件拠出金を寄付することは、司法書士会の権利能力の範囲内にあるとした上で、司法書士会は「本件拠出金の調達方法についても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づき自ら決定することができる」から、司法書士会が「いわゆる強制加入団体であること……を考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではな」いとしている(最判平14.4.25 平14重判憲法2事件)。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)93頁。
-
民法AがBに対して動産甲を売却した場合における民法上の留置権と同時履行の抗弁権に関して、判例の趣旨に照らした場合、BがCに対して甲を譲渡したが、Aが甲を占有し続けている場合、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求に対し、Aは、留置権を行使することはできるが、同時履行の抗弁権は行使することができない。なお、Aの代金債権に関して留置権と同時履行の抗弁権が競合的に成立するものとする。民法この問題の模試受験生正解率 53.8%結果正解解説留置権は、物権であるから誰に対しても主張することができる。本記述においても、Aは、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求に対し、留置権を行使することができる。これに対し、同時履行の抗弁権は、双務契約の牽連性から認められる抗弁権であるから、契約の当事者間でのみ主張することができ、第三者に対しては主張することはできない。本記述においても、Aは、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求に対し、同時履行の抗弁権は行使することができない。よって、本記述は正しい。参考平野(担物)253頁。
松井(担物)144頁。
中田(契約)161頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、偽造有価証券を行使して相手方から金品をだまし取った場合、偽造有価証券行使罪が成立し、詐欺罪は偽造有価証券行使罪に吸収される。刑法この問題の模試受験生正解率 61.8%結果正解解説判例は、偽造有価証券を行使して相手方から金品をだまし取った場合、偽造有価証券行使罪(刑法163条1項)と詐欺罪(同246条1項)が成立し、両罪は牽連犯となるとしている(大判大3.10.19)。よって、本記述は誤りである。参考高橋(各)572頁。
新基本法コメ(刑法)347頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第81条は、「一切の法律、命令、規則又は処分」と規定しているところ、憲法第58条第2項に規定されている議院規則は、議院の自律権を尊重するという観点から、憲法第81条の「規則」には含まれないと解されている。憲法この問題の模試受験生正解率 53.9%結果正解解説憲法81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定しており、このうちの「規則」には、憲法の定める議院規則(同58条2項)や裁判所規則(同77条)が含まれる。よって、本記述は誤りである。参考新基本法コメ(憲法)430頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、被相続人の占有により取得時効が完成した場合、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。民法この問題の模試受験生正解率 45.2%結果正解解説判例は、「時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎない」としている(最判平13.7.10)。よって、本記述は正しい。参考平野(総則)383~384頁。
論点体系判例民法⑴459頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が、懲役5年の刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、その刑の一部の執行を猶予することができる。刑法この問題の模試受験生正解率 51.3%結果正解解説刑法27条の2第1項柱書は、「次に掲げる者が3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において……その刑の一部の執行を猶予することができる。」としており、懲役5年の刑の言渡しを受けた場合は、これに当たらない。よって、本記述は誤りである。参考大塚ほか(基本刑法Ⅰ)450頁。
新基本法コメ(刑法)62頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるところ、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれる。憲法この問題の模試受験生正解率 90.5%結果正解解説最大判昭51.5.21(旭川学テ事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕136事件)は、教育内容決定権の所在につき、「親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられる」としている。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、雇用契約上の安全配慮義務に違反したことによって死亡した者の遺族は、雇用契約ないしこれに準ずる法律関係の当事者として、使用者に対して遺族固有の慰謝料請求権を有する。民法この問題の模試受験生正解率 69.9%結果正解解説判例は、被用者の遺族が使用者に対して、雇用契約上の安全保証義務(安全配慮義務と同義)違反を理由とする損害賠償等を請求した事例において、亡被用者と使用者との間の雇用契約ないしこれに準ずる法律関係の当事者でない被用者の遺族が雇用契約ないしこれに準ずる法律関係上の債務不履行により固有の慰謝料請求権を取得するものとは解し難いとしている(最判昭55.12.18 労働百選〔第10版〕50事件、昭55重判民法9事件)。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ154頁。
中田(債総)140頁。
平野(債総)112頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、資力が乏しく回収を見込めない債務者に対して、金銭の貸付けをした場合、その後に債務者の宝くじが当たり、債務者が当該貸付金について弁済できた場合であっても、「財産上の損害」が認められる。刑法この問題の模試受験生正解率 78.5%結果正解解説判例は、「財産上の損害」について、「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」としている(最決昭58.5.24 刑法百選Ⅱ〔第8版〕72事件)。そして、資力が乏しいなどの事情から返済が見込まれない債務者に金銭を貸し付けた場合、その債権は、実際に返済時期が到来して回収不能の事態に至らなくても、貸し付けた時点において既に額面どおりに評価をすることはできず、その時点で経済的見地からは損害が生じたということができる。また、宝くじが当たったという事情は、犯罪後の情状にすぎない。したがって、本記述の場合にも、「財産上の損害」が認められる。よって、本記述は正しい。参考西田(各)280~281頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)309~310頁。
条解刑法810~811頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国会議員は、国庫から相当額の歳費を受けるものとされ、その歳費は、その在任中減額されないことが憲法上保障されている。憲法この問題の模試受験生正解率 71.5%結果正解解説憲法49条は、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と規定している。しかし、国会議員の歳費について、その在任中減額されないことは憲法上保障されていない(同79条6項、80条2項参照)。よって、本記述は誤りである。
なお、国会法35条は、「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額……より少なくない歳費を受ける。」と定めている。参考佐藤幸(日本国憲法論)516頁、668頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)109頁、245頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、Aの所有する土地をBCDが共同で購入した場合において、BCDが売買契約の解除をするためには、BCD全員がAに対して解除の意思表示をする必要がある。民法この問題の模試受験生正解率 58.1%結果正解解説当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(解除権の不可分性 民法544条1項)。これは、当事者が知らないうちに契約が終了することを防ぐとともに、一部の当事者についてのみ解除の効果を認めることで法律関係が複雑化するのを防止する趣旨である。したがって、本記述の場合、売買契約の買主が数人いるから、買主が売買契約の解除をするためには、BCD全員がAに対して解除の意思表示をする必要がある。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)55~56頁。
中田(契約)219~220頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、信書開封罪及び秘密漏示罪は、いずれも告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。刑法この問題の模試受験生正解率 85.5%結果正解解説信書開封罪及び秘密漏示罪は、ともに親告罪である(刑法135条)。両罪の保護法益は個人の秘密であり、両罪は、比較的軽微な法益侵害行為であることから、あえて被害者の意思に反してまで訴追する必要はないとして、親告罪となっている。よって、本記述は正しい。参考大塚ほか(基本刑法Ⅱ)88~89頁。
条解刑法418頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、個々の事件において法律の誤解又は事実の誤認等により、被告人にとって不利益な裁判が行われても、それが構成その他において偏ぱのおそれのない裁判所の裁判である以上、憲法第37条第1項にいう「公平な裁判所」の裁判でないとはいえない。憲法この問題の模試受験生正解率 70.5%結果正解解説判例は、虚偽公文書作成罪等で起訴された被告人が、各審級において、繰り返し主張していた弁解事由について、上告審であった高裁段階においても、何ら判断が示されなかったことから、憲法の保障する公平な裁判ではないと主張して、再上告をした事例において、憲法37条の「「公平なる裁判所の裁判」というのは構成其他において偏頗の惧なき裁判所の裁判という意味である。かかる裁判所の裁判である以上個々の事件において法律の誤解又は事実の誤認等により偶被告人に不利益な裁判がなされてもそれが一々同条に触れる違憲の裁判になるというものではない」としている(最大判昭23.5.5 憲法百選〔初版〕44事件)。よって、本記述は正しい。参考野中ほか(憲法Ⅰ)439頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)320頁。 -
民法物権も債権も、その内容を当事者において自由に定めることができる。民法この問題の模試受験生正解率 82.3%結果正解解説債権においては、契約の内容の自由の原則(民法521条2項)が妥当し、その種類及び内容は、契約により原則として自由に定めることができる。これに対して、物権は、民法その他の法律に定めるもののほかは創設することができない(物権法定主義 同175条)。同条にいう「創設することができない」とは、法律が認めない新しい種類の物権を設定することができないというだけではなく、法律が認める物権であっても、その法律の定める内容又は効力を変更して、これと異なる内容又は効力を持たせることも許されないことを意味する。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(物権)4頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)4頁。
我妻・有泉コメ368頁、734頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、知人乙から依頼されて、荷物を預かったが、その荷物の中身は覚醒剤であった。甲は、同荷物の中身が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたが、覚醒剤や麻薬ではないと認識していた。この場合、甲には、覚醒剤取締法違反(覚醒罪所持)の罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 71.8%結果正解解説判例は、「化粧品」と称する物を日本に運ぶように頼まれ、これを隠匿して日本国内に持ち込んだが、その中身は覚醒剤であったという事例において、覚醒剤輸入罪(覚醒剤取締法41条1項)、同所持罪(同41条の2第1項)で起訴された被告人が、被告人には当該物が覚醒剤であることの認識がなかったのであるから、覚醒剤輸入罪、同所持罪の故意は認められないと主張したのに対し、対象物が覚醒剤であるとの確定的な認識まではなくとも、「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識」が被告人にあったことから、同罪の故意を認めている(最決平2.2.9 刑法百選Ⅰ〔第8版〕40事件)。すなわち、同決定は、覚醒剤輸入罪、同所持罪の故意が認められるためには、認識の対象から覚醒剤が除外されておらず、「覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれない」という認識が必要であるとしたものであり、覚醒剤ではないと認識していた場合には、覚醒剤輸入罪、同所持罪の故意は否定される。本記述では、甲は、乙から預かった荷物の中身が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたが、覚醒剤や麻薬ではないと認識していたのであるから、覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の罪の故意は認められない。したがって、甲には、覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考西田(総)229頁。
山口(総)202頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)96頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法第26条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。憲法この問題の模試受験生正解率 90.5%結果正解解説判例は、全国中学校一斉学力調査に対して実力阻止活動を行った労組役員らが公務執行妨害罪等で起訴された事例において、憲法26条の「規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」としている(最大判昭51.5.21 旭川学テ事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕136事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、委任者が受任者に対し、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に支払わなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 64.6%結果正解解説民法648条の2第1項は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならないとしている。成果完成型の委任において、報酬の支払に関しては請負に類似することを考慮し、請負(同633条本文)に準じた規律が設けられたものである。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)276頁。
中田(契約)538頁。
平野(債各Ⅰ)379頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、事後強盗罪を犯す目的は、強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」に含まれない。刑法この問題の模試受験生正解率 76.2%結果正解解説強盗予備罪(刑法237条)が成立するためには、「強盗の罪を犯す目的」でその予備行為をすることが必要である。判例は、同条にいう「強盗の罪を犯す目的」には、事後強盗の目的を含むとしている(最決昭54.11.19 刑法百選Ⅱ〔第7版〕43事件)。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)230頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者がした投票について、その投票が何人に対して行われたのかを取り調べることは、投票の秘密を侵害するものとはいえず、認められる。憲法この問題の模試受験生正解率 60.9%結果正解解説判例は、議員の当選の効力を決定する手続において、選挙権のない者の投票及び正当な選挙人でない者が選挙人の名で行ったいわゆる代理投票が何人に対して行われたのかを調べることが、秘密選挙との関係で許されるかが争われた事例において、「選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならない」としている(最判昭25.11.9 憲法百選Ⅱ〔第7版〕159事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法Aは、Bと通謀して自己の所有する甲土地をBに仮装譲渡し、Bへの所有権移転登記をした。この場合に関して判例の趣旨に照らした場合、その後、Bの一般債権者Cが、仮装譲渡の事実を知らずに甲土地を差し押さえた場合、Aは、Cに対し、AB間の譲渡の無効を主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 66.9%結果正解解説判例は、民法94条2項にいう第三者とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいうとしている(大判大9.7.23、最判昭45.7.24 不動産取引百選〔第2版〕31事件)。そして、判例は、仮装譲渡された不動産を差し押さえた一般債権者は、同項の第三者に該当するとしている(最判昭48.6.28)。これは、差押えにより、目的物の所有権の所在と債権回収の可能性との関係が密接化するためである。したがって、本記述において、AB間で仮装譲渡された甲土地を差し押さえたCは、同項の第三者に該当するため、Aは、Cに対し、AB間の譲渡の無効を主張することができない。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)124~126頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)159~160頁。
論点体系判例民法(1)239~240頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、真正不作為犯と不真正不作為犯は、刑罰法規そのものが構成要件要素として明文で不作為を規定しているかどうかによって区別される。刑法この問題の模試受験生正解率 90.2%結果正解解説真正不作為犯とは、不作為を明示的に構成要件要素として規定し、それが犯罪となる条件を法文上明定しているものである。不真正不作為犯とは、不作為が明示的に構成要件要素として規定されてはいない犯罪であって、通常は作為により実現される構成要件を不作為で実現する場合である。よって、本記述は正しい。参考山口(総)74~75頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)79頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法前文第3段は、他国との共存の必要性・国際協調主義を謳い、主権国家として国際協調主義の立場に立つことを定めており、このことは憲法本文で具体化されている。憲法この問題の模試受験生正解率 75.6%結果正解解説憲法前文第3段では、他国との共存の必要性と政治道徳の普遍性を謳い、主権国家として国際協調主義の立場に立つことを定めている。そして、国際協調主義は同98条2項によって具体化されている。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)87頁。
新・コンメ憲法25頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知った時から5年間行使しないときには、時効によって消滅する。民法この問題の模試受験生正解率 55.8%結果正解解説人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには、時効によって消滅する(民法724条の2、724条1号)。このように、不法行為による損害賠償請求権の短期の消滅時効期間は、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者のいずれをも知った時から進行する。よって、本記述は誤りである。参考窪田(不法行為)500~501頁、507~508頁。
潮見(基本講義・債各Ⅱ)138~140頁。
橋本ほか(民法Ⅴ)243~244頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合には、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに限り、第三者供賄罪(刑法第197条の2)が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 55.8%結果正解解説第三者供賄罪(刑法197条の2)は、「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたとき」に成立し、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことは不要である。よって、本記述は誤りである。
なお、第三者供賄罪を犯し、「よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった」場合、加重収賄罪(同197条の3第1項)が成立する。参考西田(各)528~529頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)458~459頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法条約締結後に国会が当該条約を修正して承認することができるかについて、これを肯定する見解によれば、当該条約は、その内容を修正して承認する旨の国会の議決により、当該修正議決に従った内容どおりに改訂されたことになる。憲法この問題の模試受験生正解率 55.5%結果正解解説憲法73条3号ただし書の「承認」をめぐり、国会が条約を修正して承認することができるかについて、肯定説(さらに、事前承認の場合に限って認められるとする説と、事後承認の場合にも認められるとする説とに分かれる。)と否定説に分かれている。肯定説は、同61条・60条2項が両院協議会の手続を要求しているのは、両院の妥協により条約を修正して承認する可能性のあることを想定したものと解されることなどを根拠としている。もっとも、肯定説に立ったとしても、条約は、その内容を修正して承認する旨の国会の議決によって、その修正議決に従った内容どおりに改訂されたことになるのではなく、国会が修正した内容のものを締結するよう内閣に対して交渉を義務付けるという効果が生じるだけである。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)325~326頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)206~208頁、426~428頁。
新基本法コメ(憲法)388~389頁。 -
民法A、B及びCが甲土地を共有している場合に関して、Aは、甲土地の自己の持分を第三者に対して譲渡する場合、B及びCの同意を得る必要はない。民法この問題の模試受験生正解率 83.4%結果正解解説明文の規定はないが、共有持分権は所有権と同様の性質を有すること及び処分を認めても他の共有者の持分権に影響を与えないことから、各共有者は、自己の持分権を自由に処分することができるとされている。よって、本記述は正しい。参考佐久間(物権)206~207頁。
平野(物権)358頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)158頁。
新基本法コメ(物権)118頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、従犯の刑は、正犯の刑を減軽すると規定されているが、従犯に言い渡される具体的宣告刑が、正犯に言い渡される具体的宣告刑より常に軽くなるとは限らない。刑法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説刑法63条は、「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。」と規定しているところ、同条にいう「正犯の刑を減軽する」とは、正犯に対する法定刑に法律上の減軽を施した上で、従犯の処断刑を定めるという趣旨であると解されている。したがって、従犯には、正犯に言い渡される具体的宣告刑より重い刑が言い渡されることもあり得る(大判昭13.7.19)。よって、本記述は正しい。参考大谷(講義総)450頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)356~357頁。
条解刑法265頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、公職選挙における立候補の自由は、憲法第15条第1項の保障する重要な基本的人権の一つであるから、労働組合が、公職選挙における統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進している場合であっても、組合の方針に反して立候補をしようとしている組合員に対し、立候補を思いとどまるよう、勧告又は説得することは許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 75.6%結果正解解説判例は、労働組合が市議会議員選挙に向けて統一候補を決定したところ、その決定に反して当該選挙に立候補した組合員を、当該労働組合の執行部役員が統制違反者として権利停止処分にしたことなどが公職選挙法違反に当たるとして起訴された事例において、「憲法28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有」するが、この「労働組合が行使し得べき組合員に対する統制権には、当然、一定の限界が存するものといわなければならない。殊に、公職選挙における立候補の自由は、憲法15条1項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利であるから、これに対する制約は、特に慎重でなければならず、組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であっても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して、その許否を決すべきであ」るとした上で、「統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、組合が所期の目的を達成するために、立候補を思いとどまるよう、勧告または説得をすることは、組合としても、当然なし得るところである。しかし、当該組合員に対し、勧告または説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない」としている(最大判昭43.12.4 三井美唄労組事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕144事件)。したがって、労働組合は、組合の方針に反して立候補をしようとしている組合員に対し、立候補を思いとどまるよう、勧告又は説得することは許される。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、建物の賃貸借契約が期間の満了によって終了した場合において、賃借人が造作買取請求権を行使し、賃貸人が賃借人に対して建物の引渡しを請求したときは、賃借人は、造作代金の支払と建物引渡しとの同時履行を主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説判例は、建物と造作代金とは対価関係にないことを理由として、建物の引渡しと造作代金の支払とは同時履行の関係にないとしている(大判昭7.9.30、最判昭29.7.22)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)220~221頁。
平野(債各Ⅰ)271頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、警察官から提示を求められたときに備え、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車を運転した場合、偽造公文書行使罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 33.7%結果正解解説判例は、偽造公文書行使罪の「行使」について、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」とした上で、「自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、未だこれを他人の閲覧に供しその内容を認識しうる状態においたものというには足りず、偽造公文書行使罪にあたらない」としている(最大判昭44.6.18 刑法百選Ⅱ〔第8版〕99事件)。よって、本記述は正しい。参考西田(各)391~392頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)391~392頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、集合住宅でのビラの戸別配布のために、一般に人が自由に出入りすることが予定されていない当該集合住宅の共用部分及びその敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、たとえ表現の自由の行使のためであるとしても、管理権者の管理権及びそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものであるから、このような立入りについて刑法第130条前段の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説判例は、政治的意見を記載したビラを公務員宿舎の共用部分である各室の玄関ドアの新聞受けに投函する目的で管理権者及び居住者の承諾を得ずに当該宿舎内に立ち入り、当該ビラを投函した行為について、刑法130条前段を適用することの合憲性が問題となった事例において、「被告人らが立ち入った場所は、防衛庁(現:防衛省)の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない」としている(最判平20.4.11 憲法百選Ⅰ〔第7版〕58事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、Aは、その所有する甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記が未了の間に、Bは、甲土地をCに売却した。その後、A及びBがAB間の売買契約を合意解除した場合、Cは、所有権移転登記をしなければ、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。民法この問題の模試受験生正解率 70.4%結果正解解説判例は、A名義の登記がなされているA所有の土地が、AからB、BからCへと順次売買され、いずれについても所有権移転登記がなされていない間にAB間の売買が合意解除された事例において、遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することができないことは民法545条1項ただし書の定めるところであり、合意解除は、同項の解除ではないが、それが契約の時にさかのぼって効力を有する趣旨であるときは法定解除と別に扱う理由もないから、そのような合意解除も第三者の権利を害することはできないが、その第三者を同177条にいう第三者の範囲から除外し別に扱うべき理由もないから、その第三者が不動産の所有権を取得した場合は、その所有権について不動産登記を経由していることを要し、もし登記を経由していないときは第三者として保護されないとしている(最判昭33.6.14)。よって、本記述は正しい。参考佐久間(物権)91~94頁。
平野(物権)116頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)48~49頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙の同意を得て、差押えを受けている乙所有の自動車に放火してこれを焼損したが、公共の危険は生じなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 58.7%結果正解解説他人が所有する自動車を放火する場合は、刑法110条1項の成立が問題となるところ、その者の同意がある場合には、財産権侵害がなく、自己所有物との均衡を考えて、同条2項が適用される。ただし、その物が差押えを受けている場合には、同115条により同110条1項の成立が問題となる。もっとも、建造物等以外放火罪(同条)が成立するためには、その客体が他人所有物(同条1項)、自己所有物(同条2項)のいずれであっても、「公共の危険」の発生が必要である。本記述では、甲は乙所有の自動車に放火してこれを焼損したが、公共の危険が生じていない。したがって、甲には、建造物等以外放火罪は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)329~330頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)362頁。
条解刑法367~369頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法内閣は法律を誠実に執行する義務を負うが、他方、内閣の構成員である国務大臣は、憲法尊重擁護義務を負うため、内閣が違憲と判断する法律が成立した場合には、その執行を免れる。憲法この問題の模試受験生正解率 76.0%結果正解解説憲法73条1号は、内閣が「法律を誠実に執行」する旨定めている。これは、たとえ内閣の賛成できない法律であっても、法律の目的にかなった執行を行うことを義務付ける趣旨である。他方、内閣の構成員である国務大臣は、憲法尊重擁護義務を負う(同99条)。しかし、法律が違憲かどうかについては、国会の判断が内閣のそれに優先するとされている。すなわち、国会で合憲であるものとして制定した以上、内閣はその判断に拘束される。したがって、内閣が違憲と判断する法律が成立した場合でも、その執行を免れることはない。よって、本記述は誤りである。
なお、最高裁判所が法律を違憲と判断した場合には、内閣はその法律の執行を停止することができると解されている。参考佐藤幸(日本国憲法論)541~542頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)205頁。 -
民法留置権者及び抵当権者は、いずれもその目的である不動産の競売を申し立てることができる。民法この問題の模試受験生正解率 43.3%結果正解解説留置権は、優先弁済的効力を有しないため、留置権者は、担保権の実行としての競売手続(民事執行法180条1号、190条1項)をとることはできないが、競売手続をとることは認められている(形式的競売 同195条)。また、抵当権は、優先弁済的効力を有することから、抵当権者は、担保権の実行としての競売手続をとることができる。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ554~555頁、667頁。
道垣内(担物)40頁、200頁。
松井(担物)151~152頁。 -
刑法ある刑罰法規につき、条文の文言を、語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈することは、許されることがある。刑法この問題の模試受験生正解率 74.8%結果正解解説刑罰法規で規定されていない事項に対し、これと類似する性質を有する事項に関する刑罰法規を適用することは、罪刑法定主義の派生原理である法律主義及び事後法の禁止に反するものであり許されない(類推解釈の禁止)。もっとも、このことは、文理解釈しか許されないことを意味するものではなく、法の予想し得る限度まで、いかにあるべきかを考えて実質的な解釈をすることまで禁止するものではない。そのため、ある刑罰法規につき、条文の文言を、語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈することが許されることがある(拡張解釈)。よって、本記述は正しい。参考山口(総)13~14頁。
大谷(講義総)64~66頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)21~22頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であったことに鑑みると、憲法は、政教分離規定を設けるに当たり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものと解すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 55.0%結果正解解説判例は、市が体育館建設に当たり、神式による起工式(地鎮祭)を行い、そのための費用を市の公金から支出したことが、憲法20条3項、89条に違反するか否かが争われた事例において、「憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき……種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至ったのである。元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであって、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であった。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである」としている(最大判昭52.7.13 津地鎮祭事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕42事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合において、第三者がその選択権を有するときは、その選択の意思表示は、債権者及び債務者の双方に対してしなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 52.9%結果正解解説選択債権とは、2個以上の異なった給付を選択的に目的としている債権であって、選択によってそのうちの1つが債権の目的となるものをいう。そして、民法409条1項は、第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするとしている。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ78~79頁。
潮見(プラクティス債総)50頁、52頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、中止犯が成立する場合は、必ずその刑が免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 90.9%結果正解解説中止犯とは、犯罪の実行に着手したが「自己の意思」によって中止した場合をいい、その刑は必要的に減軽又は免除される(刑法43条ただし書)。よって、本記述は誤りである。参考大谷(講義総)382頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)281~282頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法第34条前段の弁護人依頼権は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまり、被疑者が弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障するものではない。憲法この問題の模試受験生正解率 82.7%結果正解解説判例は、刑訴法39条3項の規定(接見指定)が憲法34条等に違反するかどうかが争われた事例において、「憲法34条前段は、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と定める。この弁護人に依頼する権利は、身体の拘束を受けている被疑者が、拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり、人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的とするものである。したがって、右規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障している」としている(最大判平11.3.24 憲法百選Ⅱ〔第7版〕120事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、重婚の場合において、後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚に当たることを理由としてその取消しを請求することができない。民法この問題の模試受験生正解率 55.8%結果正解解説重婚の禁止の違反は婚姻の取消原因である(民法744条1項、732条)。もっとも、判例は、「重婚の場合において、後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されないものと解するのが相当である」としている(最判昭57.9.28 民法百選Ⅲ〔第3版〕4事件)。その理由として、同判決は、「婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法748条、749条)、離婚後、なお婚姻の取消を請求することは、特段の事情がある場合のほか、法律上その利益がない」ことを挙げている。よって、本記述は正しい。参考窪田(家族法)35~36頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)56頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、わいせつの目的をもって未成年者を誘拐した場合、わいせつ目的誘拐罪のみが成立し、未成年者誘拐罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 59.9%結果正解解説判例は、刑法225条所定の目的をもって未成年者を誘拐したときは、同条の罪のみが成立するとしている(大判明44.12.8)。よって、本記述は正しい。参考山口(各)94頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)58頁。
大コメ(刑法・第3版)(11)539頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、学生は、大学における不可欠の構成員として、学問を学び、教育を受けるものとして、その学園の環境や条件の保持及びその改変に重大な利害関係を有する以上、大学自治の運営について要望し、批判し、あるいは反対する当然の権利を有する。憲法この問題の模試受験生正解率 59.6%結果正解解説最大判昭38.5.22(ポポロ事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕86事件)は、「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。もとより、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである」としている。したがって、同判決は、学生を単なる施設の利用者として捉えているにすぎない。よって、本記述は誤りである。
なお、仙台高判昭46.5.28(東北大学事件 教育百選〔第2版〕4事件)は、「学生は、大学における不可欠の構成員として、学問を学び、教育を受けるものとして、その学園の環境や条件の保持およびその改変に重大な利害関係を有する以上、大学自治の運営について要望し、批判し、あるいは反対する当然の権利を有し、教員団においても、十分これに耳を傾けるべき責務を負う」としている。参考芦部(憲法)177~178頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、Aが、Bからその所有する甲土地を譲り受け、引渡しを受けて占有を開始した後、BがCにも甲土地を譲渡し、Cへの所有権移転登記をした場合において、Aは、その後も甲土地の占有を継続し、甲土地の占有を開始した時から民法所定の時効期間を経過したときは、甲土地の所有権を時効取得することができる。民法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説判例は、不動産が売主から第一の買主に譲渡され、その登記がされない間に、その不動産が売主から「第二の買主に二重に売却され、第二の買主に対し所有権移転登記がなされたときは、……登記の時に第二の買主において完全に所有権を取得するわけであるが、その所有権は、売主から第二の買主に直接移転するのであり、売主から一旦第一の買主に移転し、第一の買主から第二の買主に移転するものではなく、第一の買主は当初から全く所有権を取得しなかったことになる」とし、「したがって、第一の買主がその買受後不動産の占有を取得し、その時から民法162条に定める時効期間を経過したときは、同法条により当該不動産を時効によって取得しうる」としている(最判昭46.11.5 民法百選Ⅰ〔第9版〕53事件)。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)405頁。
我妻・有泉コメ328頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、名誉毀損罪は、公知の事実を摘示した場合でも、成立し得る。刑法この問題の模試受験生正解率 55.3%
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、企業者は、雇用の自由を有し、労働者の思想、信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないため、労働者の採否決定に当たり、その思想、信条を調査し、労働者にその思想、信条に関連する事項の申告を求めることも許される。憲法この問題の模試受験生正解率 77.8%結果正解解説最大判昭48.12.12(三菱樹脂事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕9事件)は、企業者が労働者の雇入れに当たりその思想、信条に関連する事項を調査することは許されるかにつき、「企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない」としている。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、家屋の所有者である賃貸人の地位と転借人の地位が同一人に帰属した場合、転貸借契約の当事者間に転貸借契約を存続させる特別の合意が成立しない限り、転借権は混同により消滅する。民法この問題の模試受験生正解率 61.1%結果正解解説判例は、「家屋の所有権者たる賃貸人の地位と転借人たる地位とが同一人に帰した場合は民法613条1項の規定による転借人の賃貸人に対する直接の義務が混同により消滅するは別論として、当事者間に転貸借関係を消滅させる特別の合意が成立しない限りは転貸借関係は当然には消滅しない」としている(最判昭35.6.23)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(プラクティス債総)452~453頁。
中田(債総)496頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、Vの後頸部に割れたビール瓶を突き刺し、Vに重篤な頸部の血管損傷の傷害を負わせたところ、Vは、直ちに病院で手術を受け、一旦は容体が安定したが、医師の指示に従わず、安静に努めなかったため、容体が悪化し、上記傷害による脳機能障害により死亡した。この場合、甲がVの後頸部に割れたビール瓶を突き刺した行為とVの死亡の結果との間には、因果関係はない。刑法この問題の模試受験生正解率 86.8%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「被害者の受けた……傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、……被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」としている(最決平16.2.17 平16重判刑法1事件)。したがって、本記述において、甲がVの後頸部に割れたビール瓶を突き刺した行為とVの死亡の結果との間には、因果関係がある。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)64頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)76~77頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争について、国際法上の用例を尊重し、「国家の政策としての戦争」、すなわち侵略戦争を意味するならば、同条全体により自衛戦争を含めた全ての戦争が放棄されているという結論を導くことはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 50.5%結果正解解説憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争について、国際法上の用例を尊重し、「国家の政策としての戦争」、すなわち侵略戦争を意味するならば、同項で放棄されているのは侵略戦争ということになり、自衛戦争は放棄されていないことになる。もっとも、この見解に立っても、同条2項の「前項の目的を達するため」にいう「前項の目的」について、戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すものと解釈し、同項で戦力の保持が無条件で禁止され、また、交戦権まで否認されていると解釈するならば、同条1項で留保された自衛戦争も事実上不可能となり、同条全体で自衛戦争を含めた全ての戦争が放棄されているという結論を導くことができる。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)57~58頁。
佐藤幸(日本国憲法論)106~107頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)164~168頁。
芦部(憲法学Ⅰ)255~259頁。 -
民法Aが家出をして行方不明になり、その生死が10年間明らかでなかったため、Aについて失踪宣告がされた場合に関して、判例の趣旨に照らした場合、Aが失踪宣告により死亡したものとみなされた時と異なる時に死亡していたことが判明した場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、Aの失踪宣告を取り消さなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説失踪宣告を受けた者が生存していること又は失踪宣告により死亡したものとみなされる時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない(民法32条1項前段)。本記述においては、Aは、生死不明となってから7年の期間が経過した時に死亡したものとみなされるところ、これと異なる時に死亡していたことが判明しているから、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、Aの失踪宣告を取り消さなければならないこととなる。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)26頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)53頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を要求した後、公務員になったが、結局、賄賂を収受しなかった場合、事前収賄罪(刑法第197条第2項)は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 55.8%結果正解解説事前収賄罪(刑法197条2項)は、「公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした」場合、公務員になったときに成立する。したがって、公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を要求している以上、公務員になった後、結局、賄賂を収受しなかったとしても事前収賄罪が成立する。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)527頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)457~458頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、そのうちに実質上は、無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがある場合には、その部分の抑留又は拘禁は憲法第40条の適用対象となり得る。憲法この問題の模試受験生正解率 52.4%結果正解解説判例は、覚醒剤取締法違反の事実につき無罪判決を得た者が、当該被疑事実の取調べが、不起訴となった別の事実に基づく勾留中に不法に行われたとして、その身柄拘束期間についての刑事補償を請求した事例において、「憲法40条は「……抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき……」と規定しているから、抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となった場合は同条の補償の問題を生じないことは明らかである」としているが、しかし、「憲法40条にいう「抑留又は拘禁」中には、……たとえ不起訴となった事実に基く抑留または拘禁であっても、そのうちに実質上は、無罪となった事実についての抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁もまたこれを包含する」としている(最大決昭31.12.24 憲法百選Ⅱ〔第7版〕129事件)。したがって、抑留又は拘禁の理由となった被疑事実が不起訴となった場合であっても、そのうちに実質上は、無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留又は拘禁は、同条の適用対象となり得る。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、自筆証書遺言が数葉にわたる場合でも、一通の遺言書として作成されているときは、その日付、署名、捺印は一葉にされることで足りる。民法この問題の模試受験生正解率 60.1%結果正解解説自筆証書遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)。本記述のように、自筆証書遺言が数葉にわたる場合、毎葉ごとに日付、署名及び捺印をしなければならないのかが問題となる。この点につき、判例は、「遺言書が数葉にわたるときであっても、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日附、署名、捺印が適法になされている限り、右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする」としている(最判昭36.6.22 家族法百選〔第2版〕113事件)。よって、本記述は正しい。参考窪田(家族法)465頁。
新基本法コメ(相続)184頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙が覚醒剤を密輸することを知りながら、同人に対して覚醒剤購入資金を交付したところ、乙は、これを用いて2回の密輸を行った。この場合、甲には、2個の覚醒剤取締法違反幇助の罪が成立し、これらは併合罪となる。刑法この問題の模試受験生正解率 57.5%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「幇助罪は正犯の犯行を幇助することによって成立するものであるから、成立すべき幇助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定される」ところ、「幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かについては、幇助犯における行為は幇助犯のした幇助行為そのものにほかならないと解するのが相当であるから、幇助行為それ自体についてこれをみるべきである」としている(最決昭57.2.17 刑法百選Ⅰ〔第8版〕107事件)。したがって、本記述において、甲には2個の覚醒剤取締法違反幇助の罪が成立するが、覚醒剤購入資金を交付する幇助行為は1個であるから、観念的競合(刑法54条1項前段)として科刑上一罪となる。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)453~454頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)415頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、最高裁判所裁判官の国民審査は、一種の国民解職制度であるが、裁判官の任命を完成させる事後審査の意味をも含んでいる。憲法この問題の模試受験生正解率 58.9%結果正解解説判例は、最高裁判所裁判官の「国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度と見ることが出来る」とした上で、憲法79条2項と同条3項の字句を照らし合わせてみると、「国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であって、……任命そのものを完成させるか否かを審査するものでない」としている(最大判昭27.2.20 憲法百選Ⅱ〔第7版〕178事件)。したがって、国民審査は、裁判官の任命を完成させる事後審査の意味を含まない。よって、本記述は誤りである。
-
民法売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。民法この問題の模試受験生正解率 38.6%結果正解解説売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される(民法573条)。売買契約は双務契約であり、両当事者は、同時履行の抗弁権(同533条本文)を有し、目的物の引渡しについて期限がある場合には、買主の代金支払についても同一の期限を定めるのが通常であると考えられることから、推定規定を設けたものである。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)87頁。
中田(契約)336頁。
我妻・有泉コメ1242頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、Vの頭部を多数回殴打した結果、恐怖心による心理的圧迫によりVの血圧を上昇させ、Vに脳出血を発生させてVを意識消失状態に陥らせた。甲は、意識を消失したままのVを建材会社の資材置場まで自動車で運搬し、同所に放置して立ち去ったところ、Vは、甲とは無関係な何者かから角材で頭頂部を殴打され、死亡するに至ったが、Vの死因は甲の殴打行為により形成された脳出血であり、資材置場で受けた殴打行為は、既に発生していた脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合、甲の上記殴打行為とVの死亡の結果との間には、因果関係はない。刑法この問題の模試受験生正解率 95.3%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ」るとしている(最決平2.11.20 刑法百選Ⅰ〔第8版〕10事件)。したがって、本記述においても、甲の殴打行為とVの死亡の結果との間には、因果関係がある。よって、本記述は誤りである。参考大塚ほか(基本刑法Ⅰ)71~72頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、労働組合の活動が多様化して組合による統制範囲が拡大していることに加え、事実上組合員の脱退の自由が大きな制約を受けていることからすれば、労働組合の目的の範囲内の活動であっても直ちに組合員の協力義務を肯定することができず、具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることを要する。憲法この問題の模試受験生正解率 73.8%結果正解解説判例は、労働組合が他の労働組合の闘争支援資金、安保反対闘争により不利益処分を受けた組合員の救援費用等のための臨時組合費の納付を組合員に強制できるかどうかが争われた事例において、「労働組合の活動が……多様化するにつれて、組合による統制の範囲も拡大し、組合員が一個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が増大し、しかも今日の社会的条件のもとでは、組合に加入していることが労働者にとって重要な利益で、組合脱退の自由も事実上大きな制約を受けていることを考えると、労働組合の活動として許されたものであるというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは、相当でないというべきである。それゆえ、この点に関して格別の立法上の規制が加えられていない場合でも、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である」としている(最判昭50.11.28 国労広島地本事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕145事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、他の一方の相続権は認められないが、当該他の一方は、特別の寄与の制度により、死亡した一方の財産を取得することができる。民法この問題の模試受験生正解率 60.7%結果正解解説被相続人の配偶者は常に相続人となるが(民法890条前段)、同条の「配偶者」は、戸籍でその存在を確認し得る法律婚の配偶者を指し、内縁配偶者を含まない。また、相続人以外の者であっても、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者に対し、相続財産から分配を受けることを認める制度として、特別の寄与の制度(同1050条)があるが、この制度により相続財産から分配を受けることができるのは、被相続人の親族に限られ(同条1項)、内縁配偶者には認められない。よって、本記述は誤りである。参考窪田(家族法)141頁、444頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)243頁、310頁。
一問一答(新しい相続法)181~182頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、ある犯罪が行われた後、その罪の法定刑に懲役刑のほかに禁錮刑を新たに加える法改正が行われて施行された場合、新法が適用される。(参照条文)刑法 第6条(刑の変更)犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法政党が党議拘束に従わない国会議員を懲戒処分に付することは、その効果が政党内にとどまるか否かにかかわらず、国会議員が憲法第43条第1項にいう「全国民を代表する」ことと矛盾抵触することになる。憲法この問題の模試受験生正解率 84.3%結果正解解説国会議員は、全国民の代表であり、支持母体等の具体的指示に法的に拘束されることなく、議会において自己の信念に基づいてのみ発言・表決する(自由委任の原則 憲法43条1項)。他方、政党は国会内で一体として行動するために、その所属議員に対して党議拘束を加えることがある。そこで、同項と党議拘束との関係が問題となるが、国会議員は、所属政党の決定に従って行動することにより国民の代表者としての実質を発揮できるといえるし、また、政党が、党議拘束に従わない国会議員を懲戒処分に付することは、本来その政党により自律的に決せられるべき内部事項である。したがって、懲戒処分の効果が、党からの除名をもって議員資格を喪失させるものであるならともかく、その効果が政党内にとどまるものである限り、党議拘束に従わない国会議員を懲戒処分に付することは、国会議員が同項にいう「全国民を代表する」ことと矛盾抵触しないということができる。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)302~304頁。
佐藤幸(日本国憲法論)462~463頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)62~63頁、108頁。
市川(憲法)251頁。 -
民法共有物の管理者が、共有者間において決定された共有物の管理に関する事項に反してその職務を行った場合、その行為は共有者に対して効力を有しないが、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。民法この問題の模試受験生正解率 63.9%結果正解解説共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならず(民法252条の2第3項)、同項に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない(同条4項本文)。ただし、このような内部事項を知り得ない第三者を保護するため、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができないとされている(同項ただし書)。よって、本記述は正しい。参考平野(物権)364頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)163頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、遺棄罪の保護法益には、生命のみならず身体の安全も含まれ、生命及び身体に対する具体的な危険が発生しない限り、遺棄罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 52.3%結果正解解説参考山口(各)30~31頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)21~22頁。
新基本法コメ(刑法)468~469頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、公務員の地位の特殊性と職務の公共性に鑑みると、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむを得ない限度の制限を加えることができるが、当該制限が必要やむを得ない限度か否かを検討するに当たっては、個々の公務員の職務上の地位や職務の内容などの個別的事情を考慮しなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 53.0%結果正解解説判例は、非現業の国家「公務員は、私企業の労働者と異なり、国民の信託に基づいて国政を担当する政府により任命されるものであるが、憲法15条の示すとおり、実質的には、その使用者は国民全体であり、公務員の労務提供義務は国民全体に対して負うものである。もとよりこのことだけの理由から公務員に対して団結権をはじめその他一切の労働基本権を否定することは許されないのであるが、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである」としている(最大判昭48.4.25 全農林警職法事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕141事件)。このように、同判決は、公務員の労働基本権に対する制限が必要やむを得ない限度かどうかを判断するに当たり、個々の公務員の職務上の地位や職務の内容などの個別的事情を考慮しなければならないとはしていない。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)288~291頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)243~244頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、詐害行為取消請求をするためには、債務者は当該行為時に無資力であれば足り、詐害行為取消権を行使した時点において無資力である必要はない。民法この問題の模試受験生正解率 81.0%結果正解解説判例は、債務者は詐害行為時に無資力であることを要するだけでなく、詐害行為取消権を行使する時においても無資力であることを要し、詐害行為取消権行使時に債務者が資力を回復したときには、詐害行為取消権の行使は認められないとしている(大判大15.11.13)。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ366頁。
潮見(プラクティス債総)232頁。
中田(債総)296頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙所有の動産に質権の設定を受けた丙の委託により同動産を保管していたところ、乙の求めに応じて、丙に無断で、同動産を乙に対して交付した。この場合、甲には、横領罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 51.4%結果正解解説横領罪の成立には、他人の所有権に対する侵害が必要であり、質権を侵害しても、横領罪は成立しない。判例も、本記述と同様の事例において、横領罪の成立を否定している(大判明44.10.13)。したがって、甲に横領罪は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)288頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)320頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与する場合、一定の場合を除き、国会の議決に基づかなければならないが、ここでの「国会の議決」には、憲法上、衆議院の優越は認められていない。憲法この問題の模試受験生正解率 74.8%結果正解解説憲法8条は、「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と規定している。これは、皇室の財産授受を国会のコントロールの下に置くことによって、再び大きな財産が皇室に集中し、皇室が特定の個人ないし団体と経済的に特別な関係を結ぶことを防止することを目的とする。同条の「国会の議決」には、衆参両院の一致した議決を要し、衆議院の優越は認められていない。よって、本記述は正しい。
なお、皇室経済法は、相当の対価による売買等通常の私的経済行為、外国交際のための儀礼上の贈答、公共のためになす遺贈又は遺産の賜与、年間に一定の価額内の財産の賜与又は譲受については、「その度ごとに国会の議決を経なくても」よいとしている(同2条)。参考芦部(憲法)53頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)119頁。
新・コンメ(憲法)64~65頁。 -
民法消費寄託契約は、目的物の引渡しがなければ成立しない。民法この問題の模試受験生正解率 50.2%結果正解解説消費寄託とは、受寄者が代替物である寄託物を消費することができ、寄託された物自体ではなく、これと同種・同等・同量の物を返還することを約束する寄託をいう(民法666条1項)。消費寄託は、通常の寄託と同様、当事者の合意のみで成立する諾成契約である(同657条)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)285頁、293頁。
中田(契約)556頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、住居の賃貸人が、賃貸借契約が終了したので、直ちに賃借人を追い出すため、同住居に立ち入った場合、賃貸人には住居侵入罪が成立し得る。刑法この問題の模試受験生正解率 81.0%結果正解解説判例は、「住居侵入罪は故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物等に侵入し又は要求を受けてその場所より退去しないことによって成立するのであり、その居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない」とし、住居侵入罪の客体である住居が不適法に占有されている場合であっても、同罪の成立を認めている(最決昭28.5.14)。よって、本記述は正しい。参考山口(各)120頁。
西田(各)111頁。
条解刑法407頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、筆記行為の自由は、様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限りにおいては、憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるといえるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求される。憲法この問題の模試受験生正解率 75.7%結果正解解説判例は、一般の傍聴者が法廷でメモを取ることを禁止しながら、司法記者クラブ所属の報道記者に対してはこれを許可していた裁判長の措置の合憲性が争われた事例において、「筆記行為は、一般的には人の生活活動の一つであり、生活のさまざまな場面において行われ、極めて広い範囲に及んでいるから、そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない」とした上で、「筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない」としている(最大判平元.3.8 レペタ事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕72事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、保証が付された債権が譲渡され、主たる債務者に対して債権譲渡の通知がされたときは、保証人に対して債権譲渡の通知がされていなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、保証債務の履行を求めることができる。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、A及びBが殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり、「A、もっと頑張れ。」などとAに一方的に肩入れするような声援を送ったところ、その声援を聞いたAは、いっそう犯意を強固にし、更に強度の暴行を加え続けたことにより、Bに鼻骨骨折等の傷害を負わせた。この場合、甲に現場助勢罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 49.2%結果正解解説現場助勢罪(刑法206条)は、傷害又は傷害致死の行為が行われる際、その現場において勢いを助ける行為を処罰対象としている。勢いを助けるとは、本犯の気勢を高め、又は刺激すべき性質の行為をいい、例えば、「やれやれ。」、「もっとやれ。」などの声援がこれに当たる。もっとも、同条が、傷害の現場でなされた助勢行為を処罰する規定である以上、特定の正犯者の犯行を容易にする従犯とは異なる(大判昭2.3.28参照)。したがって、傷害罪又は傷害致死罪(同205条)の現場での声援であっても、双方がけんか状態になっている現場で、一方を加勢するために助勢した場合は、幇助行為であって、同206条に該当しない。本記述では、甲の行為は、既に暴行ないし傷害の故意があったAの犯意を強固にしているから、甲には傷害罪の従犯(同204条、62条1項)が成立し、現場助勢罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考西田(各)47頁。
高橋(各)55~56頁。
井田(各)65~66頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)34~35頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国民と議会とを媒介する組織として発達した政党は、国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じており、権力分立制の在り方を機能的に変容させる結果をもたらしたといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 84.3%結果正解解説政党は、国民と議会とを媒介する組織として発達してきており、国家意思の形成に際して事実上主導的な役割を演じるに至っている。このような現象は、「政党国家」現象と呼ばれ、権力分立制における伝統的な議会と政府との関係は、政党・与党と野党といった対抗関係に機能的に変容している。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)299頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、法人は、一般社団法人の役員となることができる。民法この問題の模試受験生正解率 57.3%結果正解解説法人の権利能力は、法令による制限を受ける(民法34条)。一般社団法人の役員の資格について定める一般法人法65条1項は、法人は一般社団法人の役員となることはできないとしている(同項1号)。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)356頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)77~78頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、元妻Aに対する嫌がらせとして、5階建て市営住宅のA居室の出入口に設置された玄関ドアを金属バットで叩いてへこませたが、同ドアは適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であった。この場合、甲に建造物損壊罪が成立する余地はない。刑法この問題の模試受験生正解率 57.0%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものであるところ、……本件ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ、適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても、この結論は左右されない。そうすると、建造物損壊罪の成立を認めた原判断は、結論において正当である」としている(最決平19.3.20 刑法百選Ⅱ〔第8版〕79事件)。つまり、同決定は、建造物に接合する物が当該建造物の一部といえるかについて、当該物と建造物との接合の程度のみならず、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して判断している。したがって、本記述では、甲に建造物損壊罪(刑法260条前段)が成立する余地がある。よって、本記述は誤りである。参考大谷(講義各)367~368頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)357頁。
条解刑法360頁、854~855頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更した場合には、財産権に対する侵害の程度が強度であることから、かかる財産権の事後的変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかについては、変更の目的が失われる利益を上回るほどに重要であり、また、その目的達成のために必要性があると認められるか否かによって判断すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 55.8%結果正解解説判例は、改正前農地法によって著しい廉価で農地を買い受けられることとなっていた買収農地の旧所有者が、国有農地等の売払いに関する特別措置法及び同法施行令の制定、施行により売払いの対価が時価の7割に増額されたことから、同人が買収の対価相当額での売払いを求めた事例において、「憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定しているが、同条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがって、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということができないことは明らかである。そして、右の変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、いったん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって、判断すべきである」としている(最大判昭53.7.12 憲法百選Ⅰ〔第7版〕99事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、遺留分は、相続開始前には放棄することができないが、相続開始後は放棄することができる。民法この問題の模試受験生正解率 49.8%結果正解解説相続開始後の遺留分の放棄は、既に自分に帰属した権利を処分することだから、自由にできると解されている。これに対して、相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる(民法1049条1項)。これは、無制限の放棄を許すならば、遺留分権利者が被相続人の圧迫によって遺留分を放棄するよう強要されるおそれがあるため、相続開始前の遺留分の放棄を家庭裁判所の許可にかからしめたものである。したがって、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分を放棄することができる。よって、本記述は誤りである。参考窪田(家族法)579頁。
潮見(詳解相続法)642~643頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)428頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、甲の債務者Aに対する債権をBに譲渡したが、その後、Aに対して譲渡通知をする前に、債務の弁済としてAから金銭を受領した。甲は、同金銭を譲受人Bに渡さず自己のために費消した。この場合、甲には、横領罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 51.4%結果正解解説横領罪は、「自己の占有する他人の物」を客体として、それを「横領した」場合に成立する。そこで、本記述のように、債権譲渡人が、債務者への譲渡通知前に、債務者から当該債権の弁済として金銭を受け取った場合、弁済が譲受人に対する債務の履行であるとして、同金銭が「他人の物」に当たるかが問題となる。判例は、債権譲渡人が、債務者への譲渡通知前に、同人から債権の弁済として受け取った金銭を費消した場合、債権は既に譲渡行為により譲受人に移転し、通知は債務者に対する対抗要件にすぎないから、同金銭は譲受人に帰属し、譲渡人の行為は横領罪を構成するとした原審の判断を是認している(最決昭33.5.1)。したがって、甲には横領罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考西田(各)253頁。
昭33最高裁解説(刑事)296~299頁。
条解刑法831頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第43条第1項の規定する「選挙」には間接選挙も含まれるとする見解によっても、地方議会の議員など既に選挙されて公職にある者が国会議員を選挙する、いわゆる複選制は、被選挙人と選挙人との関係が間接的にすぎるから、同項の規定する「選挙」に含まれないと解されている。憲法この問題の模試受験生正解率 50.2%結果正解解説間接選挙には、選挙人がまず選挙委員を選び、その選挙委員が国会議員を選挙する制度である狭義の間接選挙制と、地方議会の議員など既に選挙されて公職にある者が国会議員を選挙する制度である複選制とがある。そして、憲法43条1項の規定する「選挙」には間接選挙も含まれるとする見解においても、国会議員の選挙において、狭義の間接選挙制は許容されるが、複選制は、被選挙人(代表)と選挙人との関係が間接的にすぎ、もはや公選とはいえないから、同項の「選挙」に含まれないと解されている。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)276頁。
佐藤幸(日本国憲法論)443~444頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)30~32頁。
渋谷(憲法)474頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、債務の消滅時効期間が経過する前に、債務者が債権者に対し債務の承認をした場合、その債務のために自己の所有する土地に抵当権を設定した物上保証人が、被担保債権について生じた時効の更新の効力を否定することは許されない。民法この問題の模試受験生正解率 74.1%結果正解解説時効期間が経過する前に、債務者が債権者に対し債務の承認をすることは、民法152条1項の「承認」に該当し、時効の更新事由に当たる。もっとも、同153条3項は、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」としているため、物上保証人が、債務者の承認による時効の更新の効力を否定することができるか否かについて問題となる。この点について、判例は、他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定した物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、同396条の趣旨にも反し、許されないという立場に立っている(最判平7.3.10)。したがって、物上保証人が、被担保債権について生じた債務者の承認による時効の更新の効力を否定することは許されない。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)427~429頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)312頁、316頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、傷害を犯した後、労役場留置の期間を短くする改正法が施行された場合であっても、旧法が適用される。(参照条文)刑法 第6条(刑の変更)犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。刑法この問題の模試受験生正解率 59.2%結果正解解説刑法6条は、遡及処罰の禁止の趣旨を推し進めて、犯罪後に刑の変更があったときは、最も軽い刑によるべきことを定めたものである。遡及処罰の禁止により遡及適用が排除されるものには、主刑又は付加刑自体の加重のみならず、労役場留置期間の延長等も含まれる。判例も、労役場留置の期間の変更については、同条の趣旨が妥当することを理由に「刑の変更」に当たるとして、期間を短くする改正法が施行された場合には、新法が適用されるとしている(大判昭16.7.17)。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)416頁。
条解刑法13頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所は、憲法第22条第1項の「移転」とは、短期的な移動一般を意味するため、一時的な海外渡航の自由は、同項により保障されるとした。憲法この問題の模試受験生正解率 60.6%結果正解解説判例は、旅券発給拒否処分の憲法適合性が争われた事例において、「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含む」としている(最大判昭33.9.10 帆足計事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕105事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法AB間の契約の終了に関して、AB間の契約が使用貸借契約である場合、貸主Aが死亡したときであっても、当該使用貸借契約は終了しない。民法この問題の模試受験生正解率 61.4%結果正解解説使用貸借は、借主の死亡によって終了する(民法597条3項)。これは、使用貸借が当事者の信頼関係に基づいて行われるものであるためである。これに対し、貸主の死亡の場合、使用貸借はその効力を失わない。したがって、本記述の場合、貸主Aが死亡したときであっても、使用貸借契約は終了しない。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)145~146頁。
中田(契約)384頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、自己が所有する高額な自転車Aに保険を掛けていたことを思い出し、保険金を詐取して新車を購入しようと考え、Aをハンマーで叩いて修理不能な状態にした。この場合、甲に器物損壊罪が成立する余地はない。刑法この問題の模試受験生正解率 57.0%結果正解解説器物損壊等罪(刑法261条)の客体は、「他人の物」であるから、自己の所有物は同罪の客体にはならない。また、自己の物に保険を掛けていた場合に、その物を損壊したときは他人の物を損壊したとする旨の規定もない(同262条参照)。したがって、本記述では、甲に器物損壊罪(同261条前段)が成立する余地はない。よって、本記述は正しい。参考大谷(講義各)370~371頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)357~358頁。
条解刑法857頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法の規範内容が踏みにじられたり不当に変質させられたりしないようにする様々な国法上の工夫は、広く「憲法の保障」といわれるが、その代表的な方法や考え方に関して、憲法第99条で規定される憲法尊重擁護義務の主体として、国民が挙げられていないのは、国民に憲法に対する忠誠を要求することにより、国民の権利自由が侵害されることを恐れた結果であると考えることができる。憲法この問題の模試受験生正解率 44.9%結果正解解説憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定しており、憲法尊重擁護義務の主体として国民を挙げていない。そして、同条の主体として国民を挙げていない点について、国民に憲法に対する忠誠を要求することにより、国民の権利自由が侵害されることを恐れた結果であるとする見解などがある。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)386頁。
佐藤幸(日本国憲法論)57~59頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)400頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができるほか、身上監護権又は管理権の一方のみを辞することもできる。民法この問題の模試受験生正解率 55.1%結果正解解説親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(民法837条1項)。辞任の対象は、親権全部又は財産管理権に限られ、身上監護権のみの辞任は認められない。よって、本記述は誤りである。参考新基本法コメ(親族)269頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合、証人等威迫罪における「威迫」とは、勢力を示す言葉や動作を用いて相手を困惑させ不安感を生じさせることをいうが、それは直接相手と相対する場合に限られず、不安の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合も含まれる。刑法この問題の模試受験生正解率 95.6%結果正解解説証人等威迫罪(刑法105条の2)における「威迫」とは、他人に対し言語挙動によって気勢を示し、不安の念を生じさせる行為をいう。そして、判例は、「威迫」には、「不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない」としている(最決平19.11.13 平20重判刑法12事件)。よって、本記述は正しい。参考山口(各)593頁。
条解刑法345頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国政調査権は議院に強制的権限を付与するものではないため、議院は、国政調査のため、刑罰による制裁をもって証人の出頭を強制することはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 55.1%結果正解解説憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定し、同条後段は、議院に証人の出頭・証言、記録の提出を求める権限があることを明示している。これを受けて、現行法は、刑事司法手続を通じた処罰によってこの権限に強制力を与えている。すなわち、「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出……を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。」(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律1条)と定め、さらに、「正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と定めている(同7条1項)。したがって、議院は、国政調査のため、刑罰による制裁をもって証人の出頭を強制することができる。よって、本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)143~144頁、152頁。
毛利ほか(憲法Ⅰ)199~200頁。
新基本法コメ(憲法)355頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、代理人が本人の名において権限外の行為をした場合であっても、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合に限り、権限外の行為についての表見代理の規定が類推適用され、本人がその責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 85.4%結果正解解説民法110条は、代理人がその権限の範囲外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は、当該行為について責任を負うとし、権限の範囲外の行為の表見代理について規定している。そして、同条をはじめとする表見代理は、代理権が存在することへの信頼を保護する制度であり、行為を行う者が本人であることへの信頼を保護する制度ではない。したがって、本記述のように、代理人が本人になりすまして本人の名で権限外の行為をしたことにより、取引の相手方が代理人のした行為が本人自身の行為であると信じた場合には、同条の規定を適用することができないとする見解もある。もっとも、判例は、「代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、代理人の代理権を信じたものではないが、その信頼が取引上保護に値する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはないから、本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合にかぎり、民法110条の規定を類推適用して、本人がその責に任ずる」としている(最判昭44.12.19)。よって、本記述は正しい。参考平野(総則)341~342頁。
新・コンメ民法(財産法)170頁。
昭44最高裁解説(民事)630~631頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、単純遺棄罪の客体は、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」と規定されているが、扶助を必要とする原因として挙げられている「老年、幼年、身体障害又は疾病」は、例示列挙であるから、老年、幼年、身体障害又は疾病の者以外で扶助を必要とする者も、単純遺棄罪の客体となり得る。刑法この問題の模試受験生正解率 52.3%結果正解解説単純遺棄罪(刑法217条)の客体は、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」であり、これらの扶助を要する原因は制限列挙であると解されている。したがって、老年、幼年、身体障害又は疾病の者以外で扶助を必要とする者は、単純遺棄罪の客体となり得ない。よって、本記述は誤りである。
なお、この点については、保護責任者遺棄等罪(同218条)の客体についても同様に解されている。参考山口(各)32頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)19~20頁。
新基本法コメ(刑法)468頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、普通殺人罪と別個に尊属殺人罪という刑罰を加重する特別な罪を設けるその目的自体は、尊属に対する尊重報恩という社会生活上の基本的道義の維持として、合理性が認められるが、刑罰加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得べき根拠を見いだし得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして違憲である。憲法この問題の模試受験生正解率 90.2%結果正解解説判例は、実父を殺害し、削除前の刑法200条の尊属殺人罪で起訴された者に関する刑事事件につき、同条が憲法14条1項に反しないかが問題となった事例において、刑法200条の立法目的は、尊属殺を特に禁圧するためであり、「尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義」であるから、「このような自然的情愛ないし普遍的倫理」を維持しようとするために、尊属殺という特別の罪を設け、刑罰を加重すること自体は直ちに合理的な根拠を欠くものとはいえず違憲ではないが、「加重の程度が極端であって、……立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理なものといわなければならず、かかる規定は憲法14条1項に違反して無効である」としている(最大判昭48.4.4 尊属殺重罰規定判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕25事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定があり、当該契約が中途で解除された場合であっても、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したときは、当該出来形部分の所有権は下請負人に帰属する。民法この問題の模試受験生正解率 76.1%結果正解解説判例は、「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である」としている(最判平5.10.19 民法百選Ⅱ〔第8版〕69事件)。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)257頁。
中田(契約)518頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、飲食店Aにおいて飲食後、同店従業員乙から飲食代金の請求を受けたところ、乙を脅迫して当該請求を断念させようと考え、乙に対し反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加え、同脅迫に畏怖した乙は、飲食代金の請求を一時断念した。この場合、甲に恐喝罪が成立することはない。刑法この問題の模試受験生正解率 69.9%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「原裁判所が、被告人が一審判決判示の脅迫文言を申し向けて被害者等を畏怖させ、よって被害者側の請求を断念せしめた以上、そこに被害者側の黙示的な少くとも支払猶予の処分行為が存在するものと認め、恐喝罪の成立を肯定したのは相当である」として、恐喝罪(刑法249条2項)の成立を認めている(最決昭43.12.11 刑法百選Ⅱ〔第8版〕62事件)。同決定は、恐喝罪における処分行為の内容として、必ずしも積極的な処分行為は必要なく黙示的な処分行為で足りるとしている。本記述では、乙は少なくとも黙示的な支払猶予の処分行為を行っているといえる。したがって、甲には恐喝罪が成立し得る。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)244~245頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)271~272頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、国民が最高裁判所の法解釈を踏まえて自己の行動を定めることは当然であるから、憲法第39条前段の遡及処罰の禁止の規定は、行為当時の最高裁判所の判例が示す法解釈に従えば無罪となるべき行為をした者を、判例変更後の法令解釈に基づき処罰してはならないことを要求している。憲法この問題の模試受験生正解率 64.3%結果正解解説判例は、行為当時は最高裁判所の判例上適法とされた行為について、判例変更をして処罰をすることが憲法39条前段に違反するかが争われた事例において、「行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することが憲法39条に違反する旨をいう点は、そのような行為であっても、これを処罰することが憲法の右規定に違反しない」としている(最判平8.11.18 平8重判刑法2事件)。したがって、同条前段の遡及処罰の禁止の規定は、行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為をした者を、判例変更後の法令解釈に基づき処罰してはならないことまでを要求しているわけではない。よって、本記述は誤りである。参考長谷部(憲法)279頁。
市川(憲法)197頁。 -
民法委任による代理人が適法に選任した復代理人が、代理行為をするに当たり金銭その他の物を受け取ったときは、本人に対し直接これを引き渡す義務を負う。民法この問題の模試受験生正解率 45.9%結果正解解説復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し義務を負う(民法106条2項)。したがって、委任による代理人が適法に選任した復代理人は、代理行為を行うに当たって受け取った金銭その他の物を直接本人に引き渡す義務を負う。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)244~245頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)200~202頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪における「人の業務に使用する電子計算機」には、全ての公務に使用される電子計算機を含む。刑法この問題の模試受験生正解率 88.8%結果正解解説電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2第1項)にいう「人の業務に使用する電子計算機」とは、全ての公務に使用される電子計算機を含むと解されている。電子計算機による情報処理の業務が強制力を行使する権力的公務であることを想定し難いからである。よって、本記述は正しい。参考西田(各)143~144頁。
高橋(各)212頁。
条解刑法724頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法は、地方公共団体の長、その議会の議員につき、当該地域の住民による直接選挙を要請しているが、地方公共団体にその議事機関としての議会を設けることは要請していないため、町村については、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会、いわゆる町村総会を設けることができる旨を法律で規定することは、憲法に反しないといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 21.6%結果正解解説憲法93条は、地方公共団体に議事機関として議会を設置すること、議会が住民の直接選挙する議員によって構成されるべきことを要請している。したがって、同条は、議事機関として議会を設置することも要請している。よって、本記述は誤りである。
なお、地方自治法は、町村は、条例で、住民の選挙による議員からなる議会(同89条)を置かず、選挙権を有する者の総会(町村総会)を設けることができるとしている(同94条)。町村総会は、より住民自治の原則に適合するものであるから、憲法93条1項にいう議事機関としての「議会」に当たると解されている。参考市川(憲法)375~376頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)426頁。 -
民法債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた後、Aは甲をCに譲渡し、Cへの所有権移転登記がされた。この場合に判例の趣旨に照らした場合、その後、AはBに被担保債務を弁済し、甲に対するBの抵当権が消滅したが、設定登記はそのままになっていたところ、これをA及びBの合意で、BのAに対する新たな貸付債権の担保として流用することとした場合であっても、Cは、甲に対するBの抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 70.3%結果正解解説弁済によっていったん消滅した抵当権の登記を他の同額の債権の担保のために流用することの可否について、流用までに現れた正当な利害関係のある第三者(第三取得者、後順位抵当権者等)に対しては流用による抵当権の対抗力を否定するというのが判例の立場である(大判昭8.11.7、最判昭49.12.24参照)。したがって、本記述において、登記の流用の前に甲を買い受け、所有権移転登記をしているCは、正当な利害関係のある第三者に当たるので、Bの抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ480頁。
道垣内(担物)137~139頁。
松井(担物)21~23頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、外国人Aは、外国において日本人Bに対し、外国人Xを殺害するよう唆し、その旨決意したBが、日本国内においてXを殺害した。この場合、Aには日本の刑法は適用されないから、Aは殺人罪の教唆犯として処罰されない。刑法この問題の模試受験生正解率 76.6%結果正解解説教唆犯の犯罪地については、正犯行為及びその結果発生場所、教唆行為の場所が含まれると解されている。判例も、幇助の事例であるが、幇助行為が国外、正犯行為が国内で行われた覚醒剤輸入罪の事例において、幇助行為をした者を国内犯としている(最決平6.12.9 平6重判刑法1事件)。したがって、日本国内においてBがXを殺害しているから、Bを教唆したAにも日本の刑法が適用され(同1条)、Aは殺人罪の教唆犯として処罰される。よって、本記述は誤りである。参考高橋(総)51頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)462頁。
大コメ(刑法・第3版)⑸563頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所は、裁判所法第3条第1項にいう「法律において特に定める権限」である客観訴訟の裁判をするに当たって違憲審査権を行使したことがあるが、非訟事件の裁判をするに当たって違憲審査権を行使したことはない。憲法この問題の模試受験生正解率 69.0%結果正解解説最高裁判所は、主観訴訟以外の「法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)である客観訴訟の裁判をするに当たって違憲審査権(憲法81条)を行使している。例えば、公職選挙法における選挙無効訴訟(同204条、205条)において、議員定数の不均衡が争われた場合(最大判昭51.4.14 憲法百選Ⅱ〔第7版〕148事件等)や、地方公共団体の住民が提起する住民訴訟(地方自治法242条の2)において、地方公共団体の公金支出等の政教分離原則違反が争われた場合(最大判昭52.7.13 津地鎮祭事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕42事件等)において、最高裁判所は違憲審査権を行使している。また、近年では、最高裁判所は、非訟事件の裁判をするに当たり、違憲審査権を行使している。例えば、最高裁判所は、家事審判手続における特別抗告を受けて、婚外子法定相続分差別規定を違憲としている(最大決平25.9.4 憲法百選Ⅰ〔第7版〕27事件等)。したがって、最高裁判所は、客観訴訟の裁判のほか、非訟事件の裁判をするに当たっても違憲審査権を行使したことがある。よって、本記述は誤りである。参考市川(憲法)332頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)349頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、Aからその所有する建物を賃借しているBが増築をした場合、当該増築部分が取引上の独立性を有しないときは、Bは、増築についてAの承諾を得ていたとしても、当該増築部分の所有権を取得しない。民法この問題の模試受験生正解率 85.5%結果正解解説所有権の対象となるには、その物が独立性を有していることが必要である。判例は、本記述と同様の事例において、当該増築部分に独立性がないため、賃借人は当該増築部分の所有権を取得しないとしている(最判昭44.7.25 民法百選Ⅰ〔第8版〕73事件)。よって、本記述は正しい。参考松井(物権)185~186頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)149~150頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、けんか闘争は、ある瞬間においては、正当防衛を行っているように見えることがあっても、全般的に見れば、闘争者双方が攻撃及び防御を繰り返す一団の連続的闘争行為であり、法律秩序に反する行為であるから、正当防衛が成立する余地はない。刑法この問題の模試受験生正解率 66.8%結果正解解説判例は、当初、けんか闘争について、いわゆる「喧嘩両成敗」の考え方によって正当防衛の成立を否定していたが(大判昭7.1.25など)、その後、正当防衛が成立する余地を認めている(最判昭32.1.22 刑法百選Ⅰ〔初版〕39事件)。例えば、手拳で殴り合っていたところ、突然一方がナイフを持って切り掛かってきた場合のように、闘争を全体的に観察し、局面が変わったような場合には、正当防衛の要件を満たし得ると解されている。したがって、いわゆるけんか闘争における相手方に対してした暴行行為について、事態を全体的に観察した場合、正当防衛が成立する余地がある。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)172頁。
高橋(総)314~315頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)199~200頁。
大コメ(刑法・第3版)(2)590~591頁、593~594頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法は、第94条によって各地方公共団体に条例制定権を認めているものの、地域によって差別が生じることまでも認めているものではないから、当該条例によって生じる地域差の故をもって、憲法第14条に反し違憲であると主張することができる。憲法この問題の模試受験生正解率 90.2%結果正解解説判例は、条例による地域的取扱いの差異が、憲法14条1項に反しないかが争われた事例において、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。それ故、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあっても、……地域差の故をもって違憲ということはできない」としている(最大判昭33.10.15 憲法百選Ⅰ〔第7版〕32事件)。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合、解除条件付売買契約における買主の占有は、所有の意思をもってする占有であるが、現に解除条件が成就して当該売買契約が失効すれば、その占有は所有の意思をもってする占有ではなくなる。民法この問題の模試受験生正解率 66.7%結果正解解説判例は、「売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が附されている場合であっても、民法162条にいう所有の意思をもってする占有であるというを妨げず、かつ、現に右の解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもってする占有でなくなるというものではないと解するのが相当である」としている(最判昭60.3.28 昭60重判民法2事件)。よって、本記述は誤りである。参考論点体系判例民法(1)506頁。
新版注釈民法(7)50頁。
新・コンメ民法(財産法)373頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、支払督促制度を悪用して乙の財産を不正に差し押さえるなどして金銭を得ようと考え、乙を債務者とする内容虚偽の支払督促を簡易裁判所に申し立て、乙宛ての支払督促正本、仮執行宣言付支払督促正本を送達してきた郵便配達員に対し、乙を装い、甲を乙と誤信した同郵便配達員から支払督促正本等の交付を受け廃棄した。甲は、当初から乙宛ての支払督促正本等を何らかの用途に利用するつもりはなく速やかに廃棄する意図であった。この場合、甲に詐欺罪が成立することはない。刑法この問題の模試受験生正解率 69.9%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、詐欺罪の成立のためには、故意のほか不法領得の意思が必要であるとする見解に立つことを前提に、「郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について、廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかった場合には、支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできないというべきであり、このことは、郵便配達員からの受領行為を財産的利得を得るための手段の一つとして行ったときであっても異ならない」としている(最決平16.11.30 刑法百選Ⅱ〔第8版〕31事件)。したがって、乙宛てに送達された支払督促正本等を廃棄するために、乙に成り済まして郵便配達員から同正本等を受け取った甲には不法領得の意思が認められず、詐欺罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考山口(各)202頁。
高橋(各)243~244頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)149頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条本文は、議員の資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる趣旨のものであるが、議員の資格争訟も法律上の争訟である以上、この裁判について、不服のある議員は、裁判所に出訴することが認められる。憲法この問題の模試受験生正解率 75.5%結果正解解説憲法44条本文は、「両議院の議員……の資格は、法律でこれを定める。」とし、同55条本文は、「その議員の資格に関する争訟」が生じたときは、各議院がその「争訟を裁判する」とする。この趣旨は、議院自身の自律性・独自性に配慮したものである。そして、この議員の資格に関する裁判権は、同76条の定める司法権独占という原則の例外として規定されており、議院の判断に不服があっても、裁判所に救済を求めることはできない。よって、本記述は誤りである。参考渡辺ほか(憲法Ⅱ)264頁。
毛利ほか(憲法Ⅰ)213頁。
新・コンメ憲法516~517頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、AB間で、Aが所有する宝石甲を目的とする売買契約が締結されたが、引渡しも代金の支払もされない間に、BがCに甲を譲渡し、指図による占有移転をもって引き渡した。Aは、Cからの甲の引渡請求に対し、同時履行の抗弁を主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 63.5%結果正解解説同時履行の抗弁は、双務契約の当事者間において先履行の不公平を避けるためのものであるから、第三者に対しては主張することができない。したがって、本記述において、Aは、宝石甲を譲り受けたCに対し、同時履行の抗弁を主張することはできない。よって、本記述は誤りである。
なお、Aは、Cに対し、Bに対する代金債権を被担保債権とする留置権(民法295条1項本文)を行使することはできる。参考中田(契約)161頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、犯行当時の行為者が、心神喪失状態にあった場合は処罰されないが、心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 66.5%結果正解解説心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する(刑法39条2項)。したがって、犯行当時の行為者が、心神耗弱状態にあった場合、その刑は免除されない。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)298~299頁。
松原(総)235~236頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)222頁。
条解刑法184頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合、憲法第37条第2項後段は、被告人に公費で証人を召喚できる権利を規定しているため、有罪判決を受けた被告人に証人喚問に要した費用を負担させることはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 64.3%結果正解解説憲法37条2項後段は、被告人に「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」(証人喚問権)を保障している。ここにいう「公費」について、判例は、「被告人は、裁判所に対して証人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない、証人訊問に要する費用、すなわち、証人の旅費、日当等は、すべて国家がこれを支給するのであって、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることはしない」としている(最大判昭23.12.27)。これは、被告人が有罪判決を受けた場合、その被告人に証人喚問の旅費、日当等の証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁止する趣旨ではない。したがって、有罪判決を受けた被告人に証人喚問に要した費用を負担させても同項に違反しない。よって、本記述は誤りである。参考市川(憲法)196~197頁。
新・コンメ憲法411~412頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡して、AからBへの所有権移転登記がされた後に、BがCとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した。予約完結権行使の時にCが仮装譲渡について悪意であったときは、予約成立の時に善意であったとしても、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。民法この問題の模試受験生正解率 92.2%結果正解解説判例は、「民法94条2項所定の第三者の善意・悪意は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として決すべき」であるとしており(最判昭55.9.11 昭55重判民法5事件)、通謀虚偽表示の売買契約における買主が、当該契約の目的物について第三者と売買予約を締結した場合については、「その目的物の物権取得の法律関係につき、予約権利者が民法第94条第2項にいう善意であるかどうかは、その売買予約成立の時ではなく、当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるべきである」としている(最判昭38.6.7)。したがって、本記述において、Cは、予約完結権行使の時に悪意である以上、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。よって、本記述は正しい。参考平野(総則)160頁。
論点体系判例民法(1)239~240頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,偽造文書行使罪の「行使」とは、偽造文書を真正な文書として使用することをいうから、行使の相手方は、当該文書が偽造されたものであることを知らないことが必要である。刑法この問題の模試受験生正解率 69.8%結果正解解説偽造文書行使罪(刑法158条1項、161条1項)の「行使」とは、偽造文書を真正な文書として使用することをいう。したがって、相手方は、当該文書が偽造されたものであることを知らない者でなければならない。よって、本記述は正しい。参考西田(各)392頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)401頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの)第3条第1項が、日本国民を父に持つ非嫡出子についてのみ、父母の婚姻という、子にはどうすることもできない身分行為が行われない限り、生来的にも届出によっても日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段であり、不合理な差別を生じさせている。憲法この問題の模試受験生正解率 90.2%結果正解解説判例は、日本人の父が生後認知した婚外子について、父母がその後婚姻していることを国籍取得の要件としていた国籍法(平成20年法律88号による改正前のもの)3条1項の規定の合憲性が争われた事例において、「国籍法3条1項は、同法の基本的な原則である血統主義を基調としつつ、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて、これらを満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。このような目的を達成するため準正その他の要件が設けられ、これにより本件区別が生じたのであるが、本件区別を生じさせた上記の立法目的自体には、合理的な根拠があるというべきであ」り、「国籍法制の傾向にかんがみても、同項の規定が認知に加えて準正を日本国籍取得の要件としたことには、上記の立法目的との間に一定の合理的関連性があった」ものの、「非嫡出子についてのみ、父母の婚姻という、子にはどうすることもできない父母の身分行為が行われない限り、生来的にも届出によっても日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用しているものというほかなく、その結果、不合理な差別を生じさせているもの」として、同項の規定がかかる区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反しているとしている(最大判平20.6.4 国籍法違憲判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕26事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,AB間でAが所有する自動車甲の売買契約が締結され、Bはその代金をCに支払うこととされ、Cがこれを承諾した場合、その後、A及びBの合意により当該売買契約の目的物を自動車乙に変更することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 59.0%結果正解解説契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約した場合、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(第三者のためにする契約 民法537条1項)。この場合における第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生し(同条3項)、第三者の利益を享受する意思表示により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない(同538条1項)。したがって、本記述において、第三者Cが取得した権利はBに対する代金債権であり、A及びBの合意により、売買の目的物を自動車乙に変更することは、Cの取得した権利を変更するものではないから許される。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)46~47頁。
中田(契約)176~177頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,14歳未満の少年は、事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていたとしても、責任能力が認められることはない。刑法この問題の模試受験生正解率 66.5%結果正解解説14歳に満たない者の行為は、不可罰とされている(刑法41条)。これは、年少者の可塑性及び少年保護の理念に鑑みて、画一的に14歳未満の者を責任無能力者とするものである。よって、本記述は正しい。参考西田(総)299~300頁。
松原(総)241~242頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)222頁。
条解刑法189頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,裁判所が命ずる謝罪広告について、その内容によってはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限することとなり、強制執行に適さない場合もあるが、その広告の内容が単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものは、強制執行によることが可能である。憲法この問題の模試受験生正解率 63.6%結果正解解説判例は、名誉毀損の加害者に対しその意思に反して謝罪広告の掲載を裁判所が命じることが、加害者の良心の自由の侵害に当たらないかが争われた事例において、「謝罪広告を命ずる判決にもその内容上、これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定に委ねるを相当とし、これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替作為として民訴734条(現:民事執行法172条)に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく、時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さない場合に該当することもありうるであろうけれど、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあっては、これが強制執行も代替作為として民訴733条(現:民事執行法171条)の手続によることを得るものといわなければならない」としている(最大判昭31.7.4 憲法百選Ⅰ〔第7版〕33事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法Aには死亡した妻との間に子B、Cがおり、Bには妻子がおらず、Cには死亡した妻との間に実子であるD、Eがいる場合における相続に関して,判例の趣旨に照らした場合,Aが死亡する前にCが死亡していた場合において、Cが生前、Dを相続人から廃除していたときは、Dは、Cを代襲してAの相続人とならない。民法この問題の模試受験生正解率 51.5%結果正解解説代襲相続人となるためには、代襲者自身も、被相続人との関係で欠格事由がなく、かつ、被相続人から廃除されていないことが必要である。もっとも、代襲者に被代襲者との関係で欠格事由が存在することや、代襲者が被代襲者から廃除されていたとしても、被相続人の代襲相続人となる資格には影響がない。したがって、本記述において、代襲者Dが、被代襲者Cから廃除されていても、Aとの関係で代襲相続人となる資格を失わない。よって、本記述は誤りである。参考潮見(詳解相続法)33頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)247頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は、住宅街の中にある駐車場に駐車されていた乙所有の自動車にガソリンをまいて放火したところ、同自動車が勢いよく炎上し、同自動車の両隣りに駐車されていた所有者の異なる自動車2台に火が燃え移りかねない状態となったが、同駐車場の付近の建造物に燃え移る危険は生じなかった。この場合、甲には、他人所有建造物等以外放火罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 66.1%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、他人所有建造物等以外放火罪(刑法110条1項)の「公共の危険」について「必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定または多数の人の生命、身体又は……建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である」としている(最決平15.4.14 刑法百選Ⅱ〔第8版〕85事件)。本記述において、甲の放火行為により第三者が所有する自動車2台に燃え移る危険が生じているから、「公共の危険」が生じたといえる。したがって、甲には、他人所有建造物等以外放火罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考今井ほか(各)306~309頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)381~384頁。
条解刑法365~367頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,憲法第84条が直接適用されるのは、国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当する全ての者に対して課する金銭給付の場合である。憲法この問題の模試受験生正解率 73.7%結果正解解説判例は、市の実施する国民健康保険事業の経費を保険税方式ではなく保険料形式で徴収する旨を規定した条例が、具体的な保険料を定めず、告示に委任していたことから、当該条例が憲法84条に違反しないか等が争われた事例において、国民健康保険の保険料が同条の「租税」に当たるかにつき、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである」としている(最大判平18.3.1 旭川市国民健康保険条例事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕196事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割においては、原則として特別受益及び寄与分は考慮されない。民法この問題の模試受験生正解率 52.1%結果正解解説相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、具体的相続分の算定に関する民法903条から同904条の2までの規定は適用されない(同904条の3本文)。したがって、この場合の遺産分割は、法定相続分又は指定相続分によって行われ、特別受益及び寄与分は考慮されない。所有者不明土地の発生予防の観点から、遺産分割をできる限り早期に実施し、遺産共有関係を円滑に解消するため、令和3年民法改正により、具体的相続分による遺産分割に時的限界を設けたものである。よって、本記述は正しい。参考潮見(詳解相続法)300頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)298頁。
Q&A令和3年改正民法245~247頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,業務妨害罪における「業務」は、職業その他社会生活上の地位に基づくものであることを要し、個人的な活動や家庭生活上の活動は、たとえそれが反復継続されるものであっても「業務」に当たらない。刑法この問題の模試受験生正解率 88.8%結果正解解説業務妨害罪(刑法233条、234条、234条の2)における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいうと解されている(大判大10.10.24など)。職業としての経済活動をその典型とする社会生活上の活動であることが必要であり、学生の学習活動や、レジャーでの自動車の運転といった個人的活動や、料理、掃除、洗濯などの家庭生活上の活動は、たとえそれが継続して行われるものであったとしても、除外される。よって、本記述は正しい。参考西田(各)138頁。
山口(各)155~156頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)110頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が、20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく、任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思に委ねることとした措置について、著しく合理性を欠くものであるかどうかは、あくまで保険方式を基本とする国民年金制度の趣旨に照らして判断すべきであって、生活保護法に基づく生活保護制度のような別の社会保障制度が存在しているという事情を考慮することはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 52.6%結果正解解説大学在学中に障害を負った学生らが障害基礎年金の支給裁定を申請したところ、国民年金未加入(当時は、強制加入ではなかった。)を理由に不支給処分を受けたため、憲法25条等の違反を主張して、当該処分の取消訴訟等を提起した事例において、「国民年金制度は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるところ、同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない」とした上で、「世帯主が学生の学費、生活費等の負担に加えて保険料納付」を行い、「他方、障害者については障害者基本法等による諸施策が講じられており、生活保護法に基づく生活保護制度も存在している」など「の事情からすれば、平成元年改正前の法が、20歳以上の学生の保険料負担能力、国民年金に加入する必要性ないし実益の程度、加入に伴い学生及び学生の属する世帯の世帯主等が負うこととなる経済的な負担等を考慮し、保険方式を基本とする国民年金制度の趣旨を踏まえて、20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく、任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は、著しく合理性を欠くということはでき」ないから、同法が「20歳以上の学生について国民年金の強制加入被保険者とするなどの……措置を講じなかったことは」、憲法25条に反しないとしている(最判平19.9.28 学生無年金障害者訴訟 憲法百選Ⅱ〔第7版〕134事件)。したがって、同判決は、平成元年改正前の国民年金法の措置が著しく合理性を欠くものかどうかについて、生活保護法に基づく生活保護制度の存在等の事情を考慮している。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,Aが運転する自動車と、Bが運転する自動車とが衝突する交通事故により、Aの自動車に同乗していたCが負傷した場合において、AがCの被用者であり、Cの業務中に自動車を運転していたときは、CのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求において、その損害額を定めるにつきAの過失を被害者側の過失として斟酌することができる。民法この問題の模試受験生正解率 60.4%結果正解解説不法行為の被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(民法722条2項)。同項の文言上は、被害者本人の過失に限定されているようにみえるが、判例は、被害者本人と一定の関係にある者の過失(被害者側の過失)をも考慮することを認めており、本記述のように、被害者の被用者の過失も、同項の「過失」に含まれるとして、損害額の算定につき、被害者の被用者の過失を考慮することを認めている(大判大9.6.15、大判昭12.11.30)。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅱ)130頁。
橋本ほか(民法Ⅴ)233頁。
新注釈民法(16)482~483頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は、実弟とその配偶者乙と同居していたが、乙が親族関係のない丙から窃取した高級腕時計を、盗品であると知りつつ、乙から有償で譲り受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪が成立し、その刑は免除されない。刑法この問題の模試受験生正解率 32.4%結果正解解説甲は、盗品である高級腕時計を、盗品であると知りつつ、乙から有償で譲り受けているため、甲には盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)が成立する。もっとも、配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等に関する罪を犯した場合、その刑が免除される(同257条1項)。そして、同条が適用されるためには、親族関係は、本犯と盗品等関与罪の犯人との間に存在することが必要である(最決昭38.11.8)。本記述では、窃盗犯人乙は、甲の実弟の配偶者であり、いずれも甲と同居しており、同条にいう親族関係が認められるため、同条1項が適用される。したがって、甲は盗品等有償譲受け罪の刑が免除される。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)350~351頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)352~353頁。
条解刑法849頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所は、下級裁判所が、天皇の国事行為に対する内閣の「助言と承認」について、助言と承認の両者が必要であるという見解に立ちつつ、衆議院の解散の効力について判示した事例において、「助言と承認」について、同様の見解に立ちつつ、解散は有効であるとして、上告を棄却した。憲法この問題の模試受験生正解率 39.6%結果正解解説天皇の全ての国事行為には、内閣による「助言と承認」が必要とされる(憲法3条)。この助言と承認の両者が必要であるかについては見解が分かれている。この点、解散の効力が争われた苫米地事件においてこれが一つの争点とされたが、第一審(助言を欠くから解散は無効とした。)、控訴審(助言も存在したとした上で、解散を有効とした。)ともに、助言と承認の両者が必要であるとした。これに対し、最高裁判所は、解散を統治行為と捉え、助言と承認の論点について立ち入ることを回避して、上告を棄却している(最大判昭35.6.8 苫米地事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕190事件)。したがって、最高裁判所は、「助言と承認」について、両者が必要であるとする見解に立つかについて判示していない。よって、本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)540~541頁、561~562頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)120~121頁。
毛利ほか(憲法Ⅰ)111頁。 -
民法A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合に関して,A及びBの合意により、甲土地について、第三者のために建物所有目的の賃借権を設定することができる。民法この問題の模試受験生正解率 54.0%結果正解解説共有物である土地に対する賃借権の設定は、その賃借権が樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権である場合には10年、それ以外の土地の賃借権である場合には5年を超えない期間であれば、各共有者の持分の価格に従い、その過半数の賛成によりすることができる(民法252条4項1号、2号、1項前段)。建物の所有を目的とする賃借権は、その存続期間は30年以上とされるので(借地借家法3条)、持分の価格の過半数により設定することはできない。令和3年民法改正前において、共有物に賃借権を設定することは、基本的には共有物の管理に関する事項に当たり、管理行為として持分の価格の過半数で決することができるが(最判昭39.1.23)、長期間の賃借権の設定は、共有者に与える影響が大きいため、共有者全員の同意が必要であると解されていた。しかし、その区別の基準が明確でないため、実際の運用の場面においては、慎重を期して共有者全員の同意を求めざるを得ず、共有物の利用が阻害されているとの指摘がされていたことから、同改正により、共有物に一定の期間を超えない短期の賃借権を設定するには、持分の価格の過半数で決することができることを明らかにしたものである。よって、本記述は誤りである。参考平野(物権)363~364頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)162頁。
Q&A令和3年改正民法59~60頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,Aが、Bに対し、「刑務所に入ると箔がつくから、何かやってこい。」と唆したところ、その気になったBは、この機会にかねてから折り合いの悪かった隣人Xに対する恨みを晴らしてやろうと思い、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に、Xを誹謗中傷する書き込みをして、Xを侮辱した。この場合、Aは、漠然と犯罪を唆したにすぎないから、Aに侮辱罪の教唆犯は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 76.6%結果正解解説教唆とは、他人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせることをいう。正犯者に対し、特定の犯罪を実行する決意を生じさせることを要し、「何か悪いことをやれ。」というように、漠然と犯罪を唆すことだけでは足りない(最判昭26.12.6 刑法百選Ⅰ〔第2版〕78事件)。したがって、Bに対し、「刑務所に入ると箔がつくから、何かやってこい。」と漠然と犯罪を唆したにすぎないAには、侮辱罪の教唆犯(刑法231条、61条1項)は成立しない。よって、本記述は正しい。
なお、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられたことから、侮辱罪についても教唆犯及び幇助犯が成立し得ることとなった(刑法64条参照)。参考高橋(総)523頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)346頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,信教の自由の保障は、何人も他者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものであり、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は法的利益として認められない。憲法この問題の模試受験生正解率 63.0%結果正解解説判例は、社団法人隊友会A県支部連合会と自衛隊A地方連絡部が共同して亡夫をA県護国神社に合祀申請したことは、宗教上の人格権の侵害であるなどとして、亡夫の妻が、合祀手続の取消しなどを求めた事例において、「人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし、そのことに不快の感情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである」とした上で、「信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである」とし、「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである」としている(最大判昭63.6.1 憲法百選Ⅰ〔第7版〕43事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,A及びBが甲土地を共有している場合において、Bからその持分を譲り受けたCは、登記を備えていなければ、Aに対し、甲土地の持分の取得を主張することができない。民法この問題の模試受験生正解率 65.2%結果正解解説判例は、「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当するから、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもって他の共有者に対抗することができない」としている(最判昭46.6.18)。したがって、本記述において、Cは、登記を備えていなければ、Aに甲土地の持分の取得を主張することができない。よって、本記述は正しい。参考我妻・有泉コメ391頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段として持つ社会的機能を保護するものであるから、公文書偽造罪の客体である「文書」は、公務員による意識内容を直接保有伝達し証明するものとして、公務員がその権限に基づいて作成する文書たる原本に限られる。刑法この問題の模試受験生正解率 69.8%結果正解解説判例は、「公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段としてもつ社会的機能を保護し、社会生活の安定を図ろうとするものであるから、公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、これに含まれるものと解するのが相当である」としている(最判昭51.4.30 刑法百選Ⅱ〔第8版〕88事件)。よって、本記述は誤りである。参考高橋(各)526~527頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)412~413頁。
条解刑法454~455頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法嫡出でない子の相続分に関する削除前の民法第900条第4号ただし書前段の規定(以下「本件規定」という。)について、憲法第14条第1項に違反するとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成25年9月4日大法廷決定、民集67巻6号1320頁)に関して,前記決定は、本件規定で問題となる区別の合理性の判断は、単なる合理性の存否によってなされるべきではなく、立法目的自体の合理性及びその手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否が検討されるべきであるとした。憲法この問題の模試受験生正解率 60.5%結果正解解説本問の最高裁判所決定(最大決平25.9.4 憲法百選Ⅰ〔第7版〕27事件)は、被相続人の嫡出である子が、嫡出でない子に対し、当該被相続人の遺産について、遺産の分割の審判を申し立てた事例において、「憲法14条1項は、……事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものである」ところ、相続制度をどのように定めるかは、種々の事柄を総合的に考慮した上で、「立法府の合理的な裁量判断に委ねられている……。この事件で問われているのは、……相続制度全体のうち、本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、立法府に与えられた……裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反する」としている。したがって、同決定は、本件規定の憲法適合性を判断するに際し、立法目的自体の合理性及びその手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否が検討されるべきであるとはしていない。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,Aが所有する甲土地上に、権原なく乙建物を建築して所有することにより甲土地を不法占拠するBが、第三者Cとの合意により、乙建物の所有権をCに移転していないにもかかわらず、乙建物につきC名義で所有権保存登記をした場合、Aは、Cに対して建物収去土地明渡請求をすることができない。民法この問題の模試受験生正解率 64.9%結果正解解説判例は、「建物の所有権を有しない者は、たとえ、所有者との合意により、建物につき自己のための所有権保存登記をしていたとしても、建物を収去する権能を有しないから、建物の敷地所有者の所有権に基づく請求に対し、建物収去義務を負うものではない」としている(最判昭47.12.7)。したがって、本記述において、甲土地所有者Aは、乙建物の所有権を有しないCに対して建物収去土地明渡請求をすることはできない。よって、本記述は正しい。参考佐久間(物権)310頁。
松井(物権)34頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、公道を歩いているAに対し殺意をもって拳銃を発射したところ、銃弾はAの身体に命中せず、予期しなかったAが散歩中に連れていたAの犬に命中し、これを死なせた。この場合、甲には、器物損壊罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 57.2%結果正解解説判例は、異なった構成要件間における錯誤があった場合、構成要件が実質的に重なり合う限度において軽い罪の成立を認めている(最決昭61.6.9 刑法百選Ⅰ〔第8版〕43事件等)。そして、保護法益の共通性は構成要件の重なり合いが認められるための最低限度の要件であると解されるところ、殺人罪は個人の生命を保護法益とするのに対し、器物損壊罪(刑法261条)は個人の財産としての物ないし物の効用を保護法益とするものであり、両罪間に保護法益の共通性は認められない。したがって、甲に器物損壊罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考山口(総)236~241頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法改正についての国民の承認は、ことのついでに行う性質のものではないから、「特別の国民投票」によって行わなければならない旨憲法上規定されている。憲法この問題の模試受験生正解率 56.5%結果正解解説憲法改正は国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない(憲法96条1項前段)。そして、この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる(同項後段)。したがって、憲法改正についての国民の承認は、特別の国民投票のほか、国会の定める選挙(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)の際行われる投票によっても行われる。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)407頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)409頁。 -
民法買主は、売買の目的物の引渡しを受けていても、代金の支払をしていない限り、その目的物から生ずる果実を収取することができない。民法この問題の模試受験生正解率 84.4%結果正解解説売買の目的物が売主の所有する特定物である場合、目的物の所有権は、売買契約成立と同時に買主に移転すると解されているところ(最判昭33.6.20 民法百選Ⅰ〔第8版〕52事件)、いまだ引き渡されていない売買の目的物から果実が生じたときは、本来、売主は生じた果実を所有者である買主に引き渡さなければならず、他方、買主は、売買目的物の所有者として、管理費用を売主に支払わなければならないはずである。しかし、このような事態は複雑であるから、民法は、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属するものとし(同575条1項)、他方、買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負うものとして(同条2項本文)、このような関係を画一的に解決することとしている。このように、同条1項が適用されるのは、売買目的物が引き渡される前に限られるから、売買目的物が引き渡されれば、代金の支払を受けているか否かを問わず、売主は果実収取権を失う。したがって、本記述において、目的物の引渡しを受けた買主は、代金の支払の有無を問わず、目的物から生じる果実を収取することができる。よって、本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)87~88頁。
中田(契約)297~298頁。
新・コンメ民法(財産法)982~983頁。
新基本法コメ(債権2)145頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、民事事件の当事者として、口頭弁論期日において、乙の刑事事件の証拠として使用されることを認識しながら、虚偽の請求を認諾し、情を知らない裁判所書記官をして、内容虚偽の口頭弁論調書を作成させた。この場合、甲に証拠偽造罪が成立しない。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第30条の定める納税の義務は、国家の存立と国政の運営に必要となる国家の財政を支えるため、国民が税金を納めるのは当然であるという考えに基づくものであり、この義務は、租税法律主義の観点から、法律の規定により内容が具体化される。憲法この問題の模試受験生正解率 89.5%結果正解解説憲法30条は、国民の納税の義務を定めているが、この規定は、国家の存立には国民が能力に応じてその財政を支えなければならないのは当然の義務であることを明示すると同時に、国民の納税の義務は「法律の定めるところにより」具体化されるとしたものである。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)191~192頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)565頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,夫婦の一方が知らない間に、他方が離婚の届出をしこれが受理された場合であっても、協議上の離婚の効力を生じない。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合、信書開封罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪であるが、秘密漏示罪は非親告罪である。刑法この問題の模試受験生正解率 65.7%結果正解解説信書開封罪及び秘密漏示罪(刑法134条)は、ともに親告罪である(同135条)。両罪の保護法益は個人の秘密であり、両罪は、比較的軽微な法益侵害行為であることから、あえて被害者の意思に反してまで訴追する必要はないとして、親告罪となっている。よって、本記述は誤りである。参考大塚ほか(基本刑法Ⅱ)96~97頁。
条解刑法418頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは、事前抑制に該当するものであって、とりわけ出版物が公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることに鑑みると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 75.9%結果正解解説判例は、知事選挙への立候補を予定していた者が、その名誉を毀損する内容の記事が掲載された雑誌の販売等を差し止める仮処分を申請し、無審尋でこれを認める仮処分決定がなされたことについて、憲法21条に違反するかが争われた事例において、「表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない」とした上で、「出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、……憲法21条1項の趣旨……に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない」としている(最大判昭61.6.11 「北方ジャーナル」事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕68事件 )。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,虚偽表示の目的物である土地を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者は、民法第94条第2項にいう「第三者」に当たらない。民法この問題の模試受験生正解率 76.8%結果正解解説判例は、仮装譲渡された不動産を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者は、民法94条2項の「第三者」に当たるとしている(最判昭48.6.28)。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)126頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)160頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、公務執行妨害罪にいう「職務を執行するに当たり」とは、公務員が職務の遂行に直接必要な行為を現に行っている場合に限られない。刑法この問題の模試受験生正解率 88.3%結果正解解説判例は、公務執行妨害罪における「職務を執行するに当たり」について、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲及びまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離しえない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為をいう」とした上で、「職務の性質によっては、その内容、職務執行の過程を個別的に分断して部分的にそれぞれの開始、終了を論ずることが不自然かつ不可能であって、ある程度継続した一連の職務として把握することが相当と考えられるものがあ」るとして、一時中断中の職務に対する公務執行妨害罪の成立を認めている(最判昭53.6.29)。したがって、「職務を執行するに当たり」とは、公務員が職務の遂行に直接必要な行為を現に行っている場合だけを指すのではなく、公務員が職務執行のため勤務に就いている状態にある場合も含まれる。よって、本記述は正しい。参考西田(各)446~447頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)493~495頁。
大コメ(刑法・第3版)(6)138頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法上の人権規定には、未成年者に対して成年者とは異なった特別な保護を与えているものがある。憲法この問題の模試受験生正解率 53.6%結果正解解説未成年者は、心身ともに発達途上であることから、憲法は、同26条2項前段で、「子女」に「普通教育」を受ける権利を保障し、同27条3項で、「児童は、これを酷使してはならない。」と規定して特別な保護を与えている。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)88頁。
佐藤幸(日本国憲法論)155~157頁。
渋谷(憲法)110頁。
新基本法コメ(憲法)81頁。 -
民法弁済期が到来した利息債権は、元本債権に対して独立性を有するから、元本債権から分離して譲渡することができる。民法この問題の模試受験生正解率 49.9%結果正解解説利息債権は、「基本権としての利息債権」と「支分権としての利息債権」とに分けられ、元本に対して、一定の利息を生じさせることを内容とする債権である「基本権としての利息債権」の効果として、一定期間の経過により一定の率による利息を支払うことを内容とする「支分権としての利息債権」が生じるという関係にある。「基本権としての利息債権」は、元本債権が消滅すれば消滅し、元本債権が譲渡されればこれに随伴するなど、元本債権に対して付従性が強いのに対し、「支分権としての利息債権」は、元本債権に対する付従性が弱く、一度発生すれば元本債権から独立して存在するから、これのみを処分することができる。弁済期が到来した利息債権は、「支分権としての利息債権」であるから、元本債権と分離して処分することが可能である。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ68頁。
中田(債総)61頁。 -
刑法刑法が定める刑の種類の中には、懲役、禁錮、拘留及び労役場留置があるが、そのいずれもが自由刑である。刑法この問題の模試受験生正解率 55.5%結果正解解説刑の種類については、刑法9条は「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と規定している。このうち、懲役、禁錮、拘留は、対象者を刑事施設に拘置することにより、その身体の自由をはく奪する刑罰であり(同12条2項、13条2項、16条)、これを自由刑という。これに対して、労役場留置は、罰金又は科料を言い渡されたが、これらを完納できない者について、一定の期間刑事施設に付設された労役場に留置するものである(同18条)。その性格については、これを罰金又は科料に換えて自由刑を科する換刑処分とみるか、罰金又は科料の特別な執行方法とみるか争いがあるが、いずれと解するにしても、労役場留置は、同9条に挙げられておらず、刑法が定める刑の種類に含まれない。よって、本記述は誤りである。参考条解刑法23頁、31~32頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第40条は、刑事手続において身体を拘束された者が後に無罪判決を受けた場合における刑事補償請求権を定めている。同様の規定は、大日本帝国憲法にもあったが、現実になされる補償は極めて不十分という問題があった。憲法この問題の模試受験生正解率 25.7%結果正解解説憲法40条は、刑事手続において身体を拘束された者が後に無罪判決を受けた場合の損失を塡補するために、刑事補償請求権を定めている。しかし、大日本帝国憲法には、この種の規定はなく、国の恩恵的施策としての性格を有する刑事補償法が制定されていたにすぎず、現実になされる補償も極めて不十分という問題があった。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)269頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)557頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、賃貸借契約を解除することができる。民法この問題の模試受験生正解率 57.1%結果正解解説賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない(民法606条2項)。そして、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借した目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約を解除することができる(同607条)。よって、本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)161頁。
中田(契約)401頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、公務員が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、公務員の身分を失った後に賄賂を収受した場合には、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 60.0%結果正解解説事後収賄罪(刑法197条の3第3項)は、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する。よって、本記述は正しい。参考山口(各)626~627頁。
大塚ほか(刑法Ⅱ)472~473頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国会議員には当然に憲法改正原案を国会に提出する権利が認められるが、国会議員が当該原案を国会に提出するには、各議院においてそれぞれ一定数の賛成を要するものとする旨を法律で定めても、直ちに違憲とはいえないと解されている。憲法この問題の模試受験生正解率 56.5%結果正解解説憲法96条は、憲法改正手続について、国会の発議と国民の承認という二段階の要件を定め、天皇による公布を予定している。国会による発議の前提として、憲法改正原案の提出(発案)がなされなければならないが、両議院の議員には発案権が当然に認められている。もっとも、国会法68条の2は、議員が憲法改正原案を国会に提出するためには「衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」として、一定数の国会議員の賛成を要する旨を定めており、このような要件を課すことも憲法改正の重要性から直ちに違憲とはいえないと解されている。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)405頁。
佐藤幸(日本国憲法論)48頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)408頁。
新基本法コメ(憲法)502頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について、当該期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加えるものであるなどの特段の事情の認められる場合には、当該将来債権譲渡契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定される場合がある。民法この問題の模試受験生正解率 76.8%結果正解解説将来債権譲渡契約の締結時において譲渡の目的債権の発生の可能性が低かったことは、当該契約の効力を当然に左右するものではない。しかし、最判平11.1.29 民法百選Ⅱ〔第8版〕26事件 は、契約締結時における譲渡人の資産状況や、契約当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み、契約内容、契約が締結された経緯等を総合的に考慮し、将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について、当該期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであるとみられるなどの特段の事情の認められる場合には、当該将来債権譲渡契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されることがあることを認めている。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ253~254頁。
潮見(プラクティス債総)467頁。
中田(債総)642~644頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、誰かが怪我をすればいいと思って歩道橋から石を投げ落としたところ、下を歩いていた小学生の頭部に当たったため、同人は脳内出血を起こし、早期に治療を受けなければ死亡する危険のある状態となった。行為者が、悔悟の念を生じて同人を病院に運んだところ、手当てが早かったため死亡するに至らなかった場合、行為者には中止犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 42.8%結果正解解説中止犯は、自己の意思により犯罪を「中止した」場合であって、犯罪の完成に至っていないことが必要である。本記述においては、行為者が誰かに怪我を負わせようと思って、現実に小学生に死亡の危険のある傷害を負わせており、既に傷害罪(刑法204条)が成立している。したがって、中止犯は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考大コメ(刑法・第3版)(4)119~120頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したことの合憲性は、当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保護を目的とすることから、当該仕組みより緩やかな規制によってはその目的を達成することができないか否かによって判断されるべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 74.5%結果正解解説判例は、農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という。)が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組み(以下「当然加入制」という。)を採用したことの合憲性が問題となった事例において、「法が、水稲等の耕作の業務を営む者でその耕作面積が一定の規模以上のものは農業共済組合の組合員となり当該組合との間で農作物共済の共済関係が当然に成立するという仕組み……を採用した趣旨は、国民の主食である米の生産を確保するとともに、水稲等の耕作をする自作農の経営を保護することを目的」とするものであるとした上で、「当然加入制の採用は、公共の福祉に合致する目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまる措置ということができ、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であることが明白であるとは認め難い」から、「上記の当然加入制を定める法の規定は、職業の自由を侵害するものとして憲法22条1項に違反するということはできない」としている(最判平17.4.26 平17重判憲法8事件)。このように、同判決は、農業災害補償法が当然加入制を採用したことの合憲性について、最大判昭47.11.22(小売市場事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕91事件)を引用し、明白の原則を適用して合憲の判断を下している。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)245頁。
毛利ほか(憲法Ⅱ)296頁。 -
民法16歳の未成年者Aの法定代理人が、Aが法定代理人の同意を得ずに自己が所有する不動産の売買契約を締結したのを知ってから5年間、取消権を行使しなかった場合であっても、Aは、固有の取消権を行使することができる。民法この問題の模試受験生正解率 68.4%結果正解解説未成年者の法定代理人は、未成年者の行為を知った時から、追認をなし得るようになり(民法124条1項、2項1号参照)、その時から5年で取消権が時効によって消滅する(同126条前段)。そして、未成年者の法定代理人の取消権が時効によって消滅すれば、本人の取消権も消滅すると解されている。これは、どちらの取消権も発生原因が同一である上、法律関係を可及的速やかに安定させるという同条の趣旨に沿うからである。したがって、本記述において、未成年者Aの法定代理人が、Aが売買契約を締結したのを知ってから5年間、取消権を行使しなかった場合、法定代理人の取消権が消滅するのに伴い、Aの固有の取消権も消滅する。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)228~229頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)257~258頁。
平野(総則)228頁、230~231頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙の財物を強取しようと考え、乙に対して客観的に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えたところ、乙は、畏怖したものの反抗抑圧状態にはならず、下手に抵抗して怪我でもしたらつまらないと思い、甲に財布を手渡した。この場合、甲には、強盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 70.5%結果正解解説判例は、強盗罪(刑法236条)と恐喝罪(同249条)の区別は、財物奪取の手段たる暴行・脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度かという客観的基準によるとしている(最判昭24.2.8)。そして、同判決は、被害者に対し反抗抑圧に足りる程度の暴行を加えれば、実際には被害者の反抗抑圧に至らなくても、強盗既遂罪が成立するとしている。したがって、本記述において、甲が客観的に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その結果財物が交付された以上、甲には、強盗既遂罪が成立する。よって、本記述は正しい。参考山口(各)217頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)161頁。
条解刑法756頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国務大臣の任命は天皇により認証されるが、認証は効力要件ではないから、内閣総理大臣が国務大臣を任命した時点で、合議体としての内閣が成立する。憲法この問題の模試受験生正解率 69.3%結果正解解説内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣により構成される合議体である(憲法66条1項)。そして、国務大臣の任命(同68条1項本文)は、天皇により認証されるが(同7条5号)、認証は効力要件ではないから、内閣総理大臣による国務大臣の任命によって、合議体としての内閣は成立する。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)531頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)192頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,Aの単独親権に服するBが、Aから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aに無断でAの代理人と称して、A所有の甲土地につき、Bの代理権の不存在について善意無過失のCと売買契約を締結した場合において、その後、Aの追認を得られなかったときは、Bは、Cに対し、無権代理人の責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 41.7%結果正解解説無権代理人は、本人の追認がなければ、無権代理であることにつき善意無過失の相手方に対し履行又は損害賠償の責任を負うが(民法117条1項、2項1号、2号本文)、無権代理人が制限行為能力者である場合は、その責任を負わない(同項3号)。したがって、本記述において、Aの単独親権に服するBは、未成年者であり(同818条1項参照)、制限行為能力者であるから(同5条1項参照)、Cに対し、無権代理人の責任を負わない。よって、本記述は誤りである。
なお、制限行為能力者が法定代理人の同意を得て無権代理行為をした場合には、無権代理人の責任を負うと解されている。参考佐久間(総則)298~299頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)224~225頁。
我妻・有泉コメ256頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、犯罪行為の重さと法定刑が著しく均衡を失する刑罰法規は、罪刑法定主義に反する。刑法この問題の模試受験生正解率 58.9%結果正解解説罪刑法定主義には、刑罰法規の適正性が含まれる。そして、その具体的内容の1つとして、罪刑の均衡が要請される。判例も、「刑罰規定が罪刑の均衡その他種々の観点からして、著しく不合理なものであって、とうてい許容し難いものであるときは、違憲の判断を受けなければならない」として、罪刑均衡の原則を認めている(最大判昭49.11.6 猿払事件上告審 憲法百選Ⅰ〔第7版〕12事件)。よって、本記述は正しい。参考大谷(講義総)63頁。
高橋(総)41頁。
今井ほか(刑法総論)24~25頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)18頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,集会の用に供される公の施設において、当該公の施設の管理者が、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に当該公の施設の利用を拒むことができるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。憲法この問題の模試受験生正解率 84.8%結果正解解説判例は、死亡した労働組合連合体の幹部について、合同葬を行うために、当該組合連合体が市の福祉会館(以下「本件会館」という。)の使用許可申請をしたところ、内ゲバ殺人である可能性がある旨の報道に照らして、当該組合連合体と対立する者らの妨害による混乱のおそれがあることなどを理由に不許可処分となったことから、当該組合連合体が市に対して国家賠償請求訴訟を提起した事例において、地方自治法「244条に定める普通地方公共団体の公の施設として、本件会館のような集会の用に供する施設が設けられている場合、住民等は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので、管理者が正当な理由もないのにその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれがある」とした上で、「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、……公の施設の利用関係の性質に照らせば、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」としている (最判平8.3.15 上尾市福祉会館事件 地方自治百選〔第4版〕57事件、平8重判憲法6事件)。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)322~323頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)368頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の子に対して扶養義務を負うことはあるが、他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。民法この問題の模試受験生正解率 57.8%結果正解解説直系血族及び兄弟姉妹は、相互に扶養義務を負う(民法877条1項)。また、3親等内の親族間においては、家庭裁判所の審判により扶養義務が生じることがある(同条2項)。夫婦の一方からみて、他方の兄弟姉妹の子は、他方の兄弟姉妹の血族であり3親等の姻族に当たるので、3親等内の親族である(同725条3号)。そのため、他方の兄弟姉妹の子に対しては、家庭裁判所の審判によって扶養義務を負うことがある。これに対して、夫婦の一方からみて、他方の兄弟姉妹の配偶者は、他方の配偶者の血族ではなく、また、本人の血族の配偶者でもないため、姻族に当たらない。そのため、他方の兄弟姉妹の配偶者に対しては扶養義務を負うことはない。よって、本記述は正しい。参考窪田(家族法)42~43頁、341頁。
前田陽ほか(民法Ⅵ)24~26頁、216~217頁。
新基本法コメ(親族)17頁、351~352頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局、賄賂を収受しなかった場合、事前収賄罪(刑法第197条第2項)は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 60.0%結果正解解説事前収賄罪(刑法197条2項)は、「公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合」に成立する。したがって、公務員になった後、賄賂を収受しなかったとしても、賄賂の収受を約束している以上、事前収賄罪が成立する。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)624頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)472頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法形式的意味の憲法とは、憲法としての法形式に着目した憲法概念であるが、最低限度、その内容が国家の統治の基本を定めたものでなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 53.3%結果正解解説形式的意味の憲法とは、憲法制定権者が制定した法には「憲法」という形式が与えられるという、法形式に着目した憲法概念であり、その内容がどのようなものであるかには関わらない。したがって、その内容が国家の統治の基本を定めたものでなければならないわけではない。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)4頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)7~8頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務については、社団の財産が第一次的な責任財産となり、構成員各自は、第二次的な責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 57.5%結果正解解説判例は、「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、1個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない」としている(最判昭48.10.9 民法百選Ⅰ〔第8版〕9事件)。したがって、構成員は、第二次的な責任も負わない。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)385頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)99頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、強盗殺人被告事件の被告人の弁護人が、上告審係属中に、「真犯人は、被告人ではなく被害者の兄である。」旨の上告趣意書を提出した上、記者会見でそれを発表し、さらに、同内容の本を執筆して出版する行為は、正当な弁護活動であり、正当業務行為として違法性が阻却される。刑法この問題の模試受験生正解率 90.0%結果正解解説判例は、刑事事件の弁護人による真犯人の指摘や公表は訴訟外救援活動であって弁護目的との関連も著しく間接的であり、正当な弁護活動の範囲を超えるものというほかはないとして、名誉毀損罪(刑法230条1項)の成立を認めている(最決昭51.3.23 刑法百選Ⅰ〔第2版〕27事件)。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)113頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)157~158頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所が具体的事件についてある法律を違憲無効と判断した場合の違憲判決の効力について、一般的効力説によると、法的安定性が害され、憲法第14条の平等原則に反する事態も生じるおそれがあり、他方、個別的効力説によると、一種の消極的立法を認めることになるので、国会のみが立法権を行使するという憲法第41条の原則に反するおそれがある。憲法この問題の模試受験生正解率 72.1%結果正解解説最高裁判所が具体的事件において、ある法律を違憲無効と判断した場合の違憲判決の効力について、①違憲無効とされた法律は、客観的無効となるとする一般的効力説と、②違憲無効とされた法律は、当該事件に限って適用が排除されるとする個別的効力説、③違憲無効とされた法律の効力については、法律の定めるところによるとする法律委任説がある。そして、①説に対しては、裁判所が一種の消極的立法を行うことになり、憲法41条に違反するおそれがあるとの批判が、②説に対しては、法的安定性ないし予見可能性が害され、同14条の平等原則に反するおそれがあるとの批判がある。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)401~402頁。
佐藤幸(日本国憲法論)719~721頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)319~323頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,債務の不履行について当事者が損害賠償の額を予定している場合であっても、裁判所は、過失相殺により賠償額を減額することができる。民法この問題の模試受験生正解率 72.1%結果正解解説当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができ(民法420条1項)、当事者が損害賠償の額を予定している場合、裁判所は、実際の損害が予定賠償額より過大であったり、過小であったりしても、予定賠償額を増減することは認められない。もっとも、判例は、「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である」としている(最判平6.4.21)。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ201頁。
潮見(プラクティス債総)164頁。
中田(債総)223頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、バスの中で乗客の手提げかばんから財布を窃取した直後、その犯行状況を目撃して甲を逮捕しようとした警察官乙に対し、逮捕を免れる目的で、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えたが、乙に逮捕された。この場合、甲には、事後強盗未遂罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 70.5%結果正解解説事後強盗罪(刑法238条)の既遂・未遂は、先行する窃盗の既遂・未遂によって決定される(最判昭24.7.9)。また、暴行・脅迫の対象は、窃盗の被害者に限られず、追跡・逮捕しようとした第三者や警察官も含まれる。本記述において、甲は、バスの乗客の財布を窃取し、窃盗が既遂に達した後、甲を逮捕しようとした警察官乙に対して反抗抑圧に足りる程度の暴行を加えているから、事後強盗既遂罪が成立する。したがって、甲には、事後強盗未遂罪(同243条、238条)は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)192~193頁、195頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)189頁、191~192頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,尊属殺という特別の罪を設け、刑罰を加重すること自体、一種の身分制道徳の見地に立つものというべきであって、個人の尊厳と人格価値の平等を基本的立脚点とする民主主義の理念と抵触するものであるから、憲法第14条第1項に違反する。憲法この問題の模試受験生正解率 74.0%結果正解解説判例は、削除前の刑法200条所定の尊属殺人罪で起訴された被告人が、同条は憲法14条1項に違反すると主張した事例において、「尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値する」とし、「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない」としながらも、「刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である」としている(最大判昭48.4.4 尊属殺重罰規定判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕25事件)。したがって、同判決は、尊属殺という特別の罪を設けること自体、個人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする民主主義の理念と抵触するとはしていない。よって、本記述は誤りである。
なお、同判決の田中二郎裁判官の意見は、「尊属殺人に関する特別の規定を設けることは、一種の身分制道徳の見地に立つもの」であって、「個人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする民主主義の理念と牴触するものとの疑いが極めて濃厚である」とし、「尊属殺人に関し、普通殺人と区別して特別の規定を設けること自体が憲法14条1項に抵触する」としている。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,抵当権設定者Aは、抵当権の被担保債権に係る債務を弁済した場合、抵当権設定登記の抹消登記をしなければ、第三者に対し、その抵当権の消滅を主張することができない。民法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説参考道垣内(担物)233~234頁。
新基本法コメ(物権)309頁。
我妻・有泉コメ649頁。
新版注釈民法(6)646~647頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、公証人である甲は、乙の承諾を得て、業務上取り扱ったことによって知った乙の秘密を、これを知らなかった丙に告知した。この場合、甲には、秘密漏示罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 70.3%結果正解解説秘密漏示罪(刑法134条1項)は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立するところ、秘密を他人に知らせることにつき、秘密の主体たる本人の承諾を得ていた場合には、正当な理由が存するといえる。したがって、本記述において、甲には、秘密漏示罪は成立しない。よって、本記述は正しい。参考大谷(講義各)165頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)96~97頁。
条解刑法417頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,公立図書館は、そこで閲覧に供された図書の著作者にとっては、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができるから、公立図書館の職員が著作者の思想・信条を理由とする不公正な取扱いによって既に閲覧に供された図書を廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 80.7%結果正解解説判例は、公立図書館の職員が、当該図書館における図書館資料の除籍基準に該当しないにもかかわらず、独断で、蔵書の一部を廃棄したことが、著作者の人格的利益等を侵害しないかが問題となった事例において、「公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場」であり、「他方、公立図書館が、……住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる」から、「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない」としている(最判平17.7.14 憲法百選Ⅰ〔第7版〕70事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法A、B及びCが甲土地を共有している場合,判例の趣旨に照らすと,Aは、その持分割合にかかわらず、単独で甲土地の分割を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 48.0%結果正解解説各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(共有物分割請求自由の原則 民法256条1項本文)。持分割合は、共有物分割請求の要件となっていない。よって、本記述は正しい。参考佐久間(物権)214~215頁。
松井(物権)203頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)172頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、重過失とは、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。刑法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、通常の過失に比べ、わずかな注意で結果を予見でき、かつ容易に結果の発生を回避し得るのに、その注意義務を怠った場合をいう。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)294頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)131~132頁。
条解刑法153頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法「主権」の概念は多義的であり、①国家権力(統治権)そのもの、②国家権力の属性としての最高独立性(対外的独立性と対内的最高性)、③国政についての最高決定権という三つの異なる意味で用いられる。「主権」に関して,ポツダム宣言8項にある「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」との部分における「主権」は、②の意味であるとされている。憲法この問題の模試受験生正解率 61.4%結果正解解説「主権」の概念は多義的であり、①国家権力(統治権)そのもの、②国家権力の属性としての最高独立性(対外的独立性と対内的最高性)、③国政についての最高決定権という三つの異なる意味に分類されている。①の「国家権力そのもの」とは、立法権・司法権・行政権等の複数の「国家の権利」ないし「統治活動をなす権力」を総称する観念であり、伝統的に統治権と呼ばれる。②の「国家権力の属性としての最高独立性」とは、国家権力が、対外的には他のいかなる権力主体からも意思形成において制限されず独立であり、対内的には他のいかなる権力主体にも優越して最高であることを意味している。③の「国政についての最高決定権」とは、国内における最高権力、あるいは「国の政治の在り方を最終的に決定する力又は権威」を意味する。ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」との部分における「主権」は、①国家権力(統治権)そのものを意味するとされている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)39~40頁。
芦部(憲法学Ⅰ)220~223頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,民法第724条第1号にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。民法この問題の模試受験生正解率 56.2%結果正解解説判例は、民法724条は、不法行為に基づく法律関係が、未知の当事者間に、予期しない事情に基づいて発生することがあることに鑑み、被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて、消滅時効の起算点に関して特則を設けたのであるから、同条1号にいう「損害及び加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時を意味するとした上で、同号にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとしている(最判平14.1.29 平14重判民法9事件)。よって、本記述は正しい。参考窪田(不法行為)501頁。
潮見(基本講義・債各Ⅱ)138~139頁。
橋本ほか(民法Ⅴ)244頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙との間でVを殺害することを共謀し、その後、乙がVを殺害した。甲と乙の共謀の内容が、仮にVとけんかになる等の事態になればVの殺害もやむを得ないというものであった場合でも、甲には、殺人罪の共同正犯が成立し得る。刑法この問題の模試受験生正解率 82.8%結果正解解説判例は、本記述と同様の事例において、「謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする被告人の意思そのものは確定的であったのであり、被告人は被害者の殺害の結果を認容していたのであるから、被告人の故意の成立に欠けるところはない」として、殺人罪の共同正犯の成立を認めている(最決昭56.12.21 刑法百選Ⅰ〔第2版〕46事件)。したがって、甲には、殺人罪の共同正犯が成立し得る。よって、本記述は正しい。参考高橋(総)188頁。
新基本法コメ(刑法)118頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けている。憲法この問題の模試受験生正解率 56.9%結果正解解説判例は、国税犯則取締法(国税通則法に編入されることにより、平成30年廃止)に基づく質問調査に憲法38条1項の供述拒否権の保障が及ぶかどうかが問題となった事例において、「国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則嫌疑者については、自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供述を認めることになる」ので、「憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶ」とするものの、同「項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解される」としている(最判昭59.3.27 憲法百選Ⅱ〔第7版〕119事件)。したがって、同項は、供述拒否権の告知を義務付けていない。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において、相手方がその事実を知ることができたときは、その意思表示を取り消すことができる。民法この問題の模試受験生正解率 64.3%結果正解解説ある者に対する意思表示につき、第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。詐欺を行っていない意思表示の相手方の信頼を保護するため、取消しの範囲を限定したものである。よって、本記述は正しい。参考佐久間(総則)170~171頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)184頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、身の代金目的略取誘拐罪を犯した者が、公訴が提起される前に被拐取者を安全な場所に解放した場合、その刑は必要的に減軽される。刑法この問題の模試受験生正解率 24.1%結果正解解説身の代金目的略取誘拐罪を犯した者が、公訴提起される前に、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その刑は必要的に減軽される(刑法228条の2)。同条は、同罪においては、被拐取者の生命、身体の危険が大きいことから、その安全を図るために政策的に必要的減軽を定めたものである。よって、本記述は正しい。参考西田(各)95頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)68頁。
条解刑法692頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法愛媛県玉串料訴訟判決(最高裁判所平成9年4月2日大法廷判決、民集51巻4号1673頁)に関して,この判決は、一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際し、県が公金を支出して玉串料等を奉納することは、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえないとした。憲法この問題の模試受験生正解率 80.9%結果正解解説本問の判決は、問題となった県の公金支出行為について、「県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかである」とした上で、「一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難い」としている。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,債務者が弁済の準備ができない経済状態にあり、口頭の提供ができない場合であっても、債権者が契約の存在を否定するなど、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は、口頭の提供をしなくても債務不履行の責任を免れる。民法この問題の模試受験生正解率 47.4%結果正解解説判例は、債務者が口頭の提供をしても、債権者が契約の存在を否定するなど弁済を受領しない意思を明確にしている場合には、口頭の提供をしなくても債務不履行責任を負わないが(最大判昭32.6.5)、「弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められるときでも、弁済の提供をしないことによって債務不履行の責を免かれない」としている(最判昭44.5.1 民法百選Ⅱ〔初版〕37事件)。よって、本記述は誤りである。参考内田Ⅲ106~107頁。
潮見(プラクティス債総)291~292頁。
中田(債総)368頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、現行刑法上、過失犯の未遂を処罰する規定は存在しない。刑法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説刑法典上、過失犯については、未遂を処罰する規定は存在しない。過失犯についてその未遂犯を処罰することは著しい処罰の拡張となり妥当でないからである。よって、本記述は正しい。参考山口(総)280頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,裁判所によるテレビフィルムの提出命令が許されるか否かを判断するに当たり、当該フィルムを証拠として提出させられることによる報道機関の不利益が考慮されるが、既に放映されたものを含む放映のために準備されたフィルムが証拠として使用されることで報道機関が受ける不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる。憲法この問題の模試受験生正解率 78.3%結果正解解説判例は、テレビ放送会社が学生と機動隊との衝突事件の現場を撮影したテレビフィルム(以下「本件フィルム」という。)に対して裁判所が発した提出命令が表現の自由を保障した憲法21条に違反するか否かが争われた事例において、同条の精神に照らし十分尊重に値する取材の自由も「公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない」とした上で、公正な刑事裁判の実現のために報道機関が取材活動によって得たものに対して提出命令を発することにより取材の自由を制限することが許されるか否かは、「審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させられることによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべき」であるとし、本件フィルムは、「すでに放映されたものを含む放映のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることによって報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる」としている(最大決昭44.11.26 博多駅事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕73事件)。よって、本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,留置権者が留置権を主張して目的物の返還を拒むとともに、被担保債権について履行を求めた場合、被担保債権の消滅時効の完成が猶予される。民法この問題の模試受験生正解率 62.3%結果正解解説留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない(民法300条)。留置権を行使して、目的物の留置を継続していても、被担保債権を行使していることにはならないからである。しかし、留置権を主張して、目的物の返還を拒むと同時に、被担保債権の履行を求めれば、「催告」として時効の完成が猶予される(同150条1項)。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ672~673頁。
道垣内(担物)35頁。
松井(担物)152頁。
新・コンメ民法(財産法)463頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでなければ、成立する余地はない。刑法この問題の模試受験生正解率 64.0%結果正解解説判例は、「シャクティ治療」と称する独自治療を唱導していた被告人が、その信奉者から重篤な患者である親族に対する「シャクティ治療」を依頼され、同患者を入院中の病院から運び出させた上、必要な医療措置を受けさせないまま放置した事例において、「被告人は、自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上、患者が運び込まれたホテルにおいて、被告人を信奉する患者の親族から、重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際、被告人は、患者の重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである」とし(最決平17.7.4 刑法百選Ⅰ〔第8版〕6事件)、先行行為、保護の引受け、排他的支配を根拠に、作為義務(直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務)があったとしており、法律上の規定から作為義務を導いてはいない。したがって、不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合であっても、成立する余地がある。よって、本記述は誤りである。参考西田(総)126~129頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)85~86頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,憲法第8章の地方自治に関する規定の趣旨に鑑みれば、憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民のみを意味するものとは解されないことから、法律をもって、その居住する地域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った外国人に地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。憲法この問題の模試受験生正解率 53.0%結果正解解説判例は、定住外国人に地方公共団体の選挙権を認めない地方自治法の規定が、憲法前文、14条、15条、93条2項に反するかが問題となった事例において、同15条1項の「規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」とした上で、「前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」としている(最判平7.2.28 憲法百選Ⅰ〔第7版〕3事件)。よって、本記述は誤りである。
なお、同判決は、「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」としている。 -
民法本人が後見開始の審判を受けた場合、委任による代理権は消滅する。民法この問題の模試受験生正解率 68.1%結果正解解説本人に生じた事由により代理権が消滅するのは、本人が死亡した場合のみであり(民法111条1項1号)、本人が後見開始の審判(同7条)を受けても代理権は消滅しない。また、委任による代理権は、委任の終了によって消滅するところ(同111条2項)、委任者(本人)が後見開始の審判を受けたことは、委任の終了事由とはされていない(同653条参照)。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)256頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)198頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、緊急避難の要件である「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」には、避難行為によって生じた害が、避けようとした害と同程度の場合も含まれる。刑法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説緊急避難の要件である「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」(刑法37条1項本文)とは、避けようとした害が避難行為によって生じた害と同程度であるか、又は、優越する場合をいう。よって、本記述は正しい。参考山口(総)154~155頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)211頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例は、政党がその所属党員に対してした除名その他の処分の当否について、裁判所は、原則として適正な手続にのっとってされたか否かを審査して判断すべきであり、一般市民としての権利利益を侵害する場合に限り処分内容の当否を審査することができるとしている。憲法この問題の模試受験生正解率 42.4%結果正解解説判例は、政党が除名処分を受けた元党役員に対し、当該党役員に利用させてきた家屋の明渡しを求めた事例において、「政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」とした上で、「右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られる」としている(最判昭63.12.20 憲法百選Ⅱ〔第7版〕183事件)。したがって、政党がその所属党員に対してした除名その他の処分の当否については、一般市民法秩序と直接の関係を有しない限り、裁判所の審判権は及ばず、当該処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合でも、処分内容の当否を審査することはできない。よって、本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する訴訟においては、原告が、その義務内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 52.3%結果正解解説判例は、「国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反し、右公務員の生命、健康等を侵害し、同人に損害を与えたことを理由として損害賠償を請求する訴訟において、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、国の義務違反を主張する原告にある、と解するのが相当である」としている(最判昭56.2.16 民法百選Ⅱ〔第2版〕3事件)。よって、本記述は正しい。参考内田Ⅲ154頁。
中田(債総)139頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、日本国外で販売しようと考え、日本国内において、わいせつな写真を保管し、所持した。この場合、甲には、わいせつ図画有償頒布目的所持罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.7%結果正解解説判例は、刑法175条2項にいう「有償で頒布する目的」とは、国内における有償頒布目的を意味するとした上で、わいせつ図画等を国内で所持していた場合でも、国外での有償頒布目的があったにすぎないときには、同項の罪は成立しないとしている(最判昭52.12.22 刑法百選Ⅱ〔第5版〕100事件)。したがって、本記述において、甲にわいせつ図画有償頒布目的所持罪(同項)は成立しない。よって、本記述は誤りである。参考山口(各)514頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)456頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し、国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め、その執行を監督し、更にその人事に関与するなど、その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することを要すると解する見解は、同条後段の趣旨を私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとするところに求める立場と結び付く。憲法この問題の模試受験生正解率 60.2%結果正解解説憲法89条後段の趣旨については、必ずしも明確ではなく、学説上も見解が分かれている。本記述の見解は、同条後段の趣旨について、私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとするところに求める立場(自主性確保説)である。この見解は、同条後段の「公の支配」の意義について、国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め、その執行を監督し、更にその人事に関与するなど、その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することを要すると解する見解(厳格説)に立つとされる。これにより、国が財政的援助をする以上は事業の自主性を認めず、事業の自主性を認める以上は援助しないと憲法が割り切っていると解することになる。よって、本記述は正しい。参考芦部(憲法)375~376頁。
佐藤幸(日本国憲法論)573~574頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)343~346頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,Bは、Aから甲動産を詐取してCに売却し、Cは、甲動産がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲動産を詐取された時から2年以内であれば、Cに対し、甲動産の返還を求めることができる。民法この問題の模試受験生正解率 53.9%結果正解解説民法193条は、同192条が定める要件を満たした場合であっても、占有物が「盗品又は遺失物」である場合、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、その物の回復請求をすることができるとしている。これは、「盗品又は遺失物」のように、被害者又は遺失者の意思によらないで占有を離れた物について、特に同人の権利を保護するためのものである。詐欺により物の占有を失った場合には、あくまで占有者がその意思に基づいて物の占有を移転していることから、同193条の適用又は類推適用は認められないと解されており、判例も、同条の適用を否定している(大判明35.11.1)。したがって、本記述において、Aは、甲動産を詐取された時から2年以内であっても、Cに対し、同条に基づく回復請求として甲動産の返還を求めることはできない。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(物権)156頁。
松井(物権)143頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)103~104頁。
新注釈民法(5)187頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、精神に障害のない場合、心神喪失とは認められない。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,現在、学校教育法に規定する小学校、中学校などの義務教育諸学校においては、法律により、教科書は無償で配布されているが、当該法律を改正して教科書を有償としても、義務教育の無償を規定する憲法第26条第2項後段に違反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 61.1%結果正解解説判例は、公立小学校に子を在学させている親が、義務教育期間中の教科書代金の徴収行為の取消し等を求めた事例において、「憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」としつつ、「国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではない」としている(最大判昭39.2.26 教科書費国庫負担請求事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕A11事件)。現在、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等によって、義務教育に係る教科書も無償で配布されているが、同判決によれば、これは憲法上の要請ではないから、当該法律を改正して有償としても、義務教育の無償を規定する憲法26条2項後段に違反しない。よって、本記述は正しい。参考渡辺ほか(憲法Ⅰ)393~394頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,袋地を買い受けた者は、所有権移転登記を経由していなくても、袋地を囲んでいる土地(以下「囲繞地」という。)の所有者ないし利用権者に対し、公道に至るため、その囲繞地の通行権を主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 74.2%結果正解解説判例は、「袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないしこれにつき利用権を有する者に対して、囲繞地通行権を主張することができる」としている(最判昭47.4.14 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕56事件)。その理由として、同判決は、民法の相隣関係の規定(同209条~238条)は、いずれも、相隣接する不動産相互間の利用の調整を目的とする規定であって、同210条の囲繞地通行権も、相隣関係にある所有権共存の一態様として、囲繞地の所有者に一定の範囲の通行受忍義務を課し、袋地の効用を高めようとするもので、「このような趣旨に照らすと、袋地の所有者が囲繞地の所有者らに対して囲繞地通行権を主張する場合は、不動産取引の安全保護をはかるための公示制度とは関係がない」ことを挙げている。よって、本記述は正しい。参考佐久間(物権)168頁。
松井(物権)167頁。
石田剛ほか(民法Ⅱ)137頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、乙が覚醒剤の密輸入を企てていることを知りながら、その資金として、同人に対し金員を供与した。その後、乙は、当該金員を用いて、2度にわたり覚醒剤を密輸入した。この場合、甲には、2個の覚醒剤輸入罪の幇助犯が成立し、両罪は併合罪となる。刑法この問題の模試受験生正解率 60.6%結果正解解説判例は、「幇助罪は正犯の犯行を幇助することによって成立するものであるから、成立すべき幇助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定される」とした上で、「幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かについては、……幇助行為それ自体についてこれをみるべき」としている(最決昭57.2.17 刑法百選Ⅰ〔第8版〕107事件)。したがって、本記述において、甲には2個の覚醒剤輸入罪の幇助犯(覚醒剤取締法13条、41条1項、刑法62条1項)が成立し、幇助行為は金員供与1個であるから、両罪は観念的競合(同54条1項前段)となる。よって、本記述は誤りである。参考山口(総)409~410頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)415頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らした場合,インターネットには、利用者の対等性と反論の容易性という特徴があるということに加え、個人利用者がインターネット上で発信した情報の信頼性は一般に低いものと受け止められていることにも鑑みると、個人利用者がインターネットを使って名誉毀損的表現に及んだ場合には、当該個人利用者が、摘示した事実が真実でないことを知りながら発信したか、あるいは、インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行わず真実かどうか確かめないで発信したといえるときに初めて名誉毀損罪が成立する。憲法この問題の模試受験生正解率 80.7%結果正解解説判例は、個人が、インターネット上に自己が開設したホームページにおいて、ある会社につきその名誉を毀損する記載をしたとして起訴された事例において、「所論は、被告人は、一市民として、インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行った上で、本件表現行為を行っており、インターネットの発達に伴って表現行為を取り巻く環境が変化していることを考慮すれば、被告人が摘示した事実を真実と信じたことについては相当の理由があると解すべきであって、被告人には名誉毀損罪は成立しない」と主張するが、「個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって、おしなべて、閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって、相当の理由の存否を判断するに際し、これを一律に、個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして、インターネット上に載せた情報は、不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり、これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること、一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく、インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると、インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」としている(最決平22.3.15 ラーメンフランチャイズ事件 メディア百選〔第2版〕111事件)。したがって、同決定は、インターネットの個人利用者による表現行為についても、他の場合と同様の名誉毀損法理(相当性の理論)が妥当するとしている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)194~195頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)401頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,建物の賃借人が、造作引渡債務との同時履行の抗弁権の付いた賃貸人に対する造作代金支払債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権として相殺をすることは、許されない。民法この問題の模試受験生正解率 54.3%結果正解解説自働債権に抗弁権が付着している場合には、相殺を認めると自働債権の債務者が有する抗弁権を一方的に奪うことになるから、相殺は許されない。判例は、建物の賃借人が造作買取請求権(借地借家法33条1項)を行使することによって発生する造作代金支払債務は、造作引渡債務と対価的関係に立つとして、賃貸人は賃借人に対して、造作の引渡しがあるまで造作代金の支払を拒むことができる同時履行の抗弁権を有するとした上で、賃借人が賃貸人に対し、造作代金支払債権を自働債権、賃料その他の債権を受働債権として相殺することは許されないとしている(大判昭13.3.1)。よって、本記述は正しい。参考中田(債総)473~474頁。
潮見(新債総Ⅱ)283頁。
論点体系判例民法(5)302~303頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、甲は、妻乙が殺人罪を犯したことを知り、逮捕を免れさせるため、同人を自己の所有する別荘にかくまった。この場合、甲には、犯人蔵匿罪が成立するが、親族による犯罪に関する特例の適用により、甲は、必ずその刑を免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 48.8%結果正解解説犯人蔵匿罪(刑法103条前段)の行為は、犯人等を蔵匿することであるが、「蔵匿」とは場所を提供してかくまうことをいう。本記述では、甲は殺人罪(同199条)を犯した乙を自己が所有する別荘にかくまっており、蔵匿したといえる。そのため、甲には犯人蔵匿罪が成立する。もっとも、乙は甲の妻であるから、親族による犯罪に関する特例(同105条)が適用され、その刑を免除することができる(裁量的免除)。したがって、甲は必ずその刑を免除されるわけではない。よって、本記述は誤りである。参考西田(各)483頁、490頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)515~516頁、530頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法内閣は、憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負うから、たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても、その法律を執行しなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 65.2%結果正解解説憲法73条1号は、内閣が「法律を誠実に執行」する旨を規定している。「誠実に執行」とは、たとえ内閣の賛成できない法律であっても、法律の目的にかなった執行を行うことを義務付ける趣旨である。つまり、法律が違憲かどうかについては、国会の判断が内閣のそれに優先し、国会で合憲であるものとして制定した以上、内閣はその判断に拘束されるということである。したがって、内閣は、自らが違憲と判断する法律であっても、その法律を執行しなければならない。よって、本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)541~542頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)285~286頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,建物の賃借人は、当該建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。民法この問題の模試受験生正解率 68.1%結果正解解説判例は、係争地の所有権を時効取得すべき者又はその承継人から、その土地上に同人らが所有する建物を賃借しているにすぎない者は、当該土地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではないから、当該土地の所有権の取得時効を援用することはできないとしている(最判昭44.7.15)。よって、本記述は誤りである。参考佐久間(総則)434頁。
佐久間ほか(民法Ⅰ)322~323頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、「自己若しくは第三者の利益を図る目的」は、本人の利益を図る目的が併存する場合であっても認められ得る。刑法この問題の模試受験生正解率 80.6%結果正解解説背任罪が成立するためには、他人のためにその事務を処理する者が、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(図利・加害目的)をもって、その任務に背く行為をすることが必要である。図利・加害目的と本人図利目的とが併存する場合には、両目的の主従によって背任罪の成否が決定されると解されており、判例も、両者が併存する事例において、本人の利益を図る目的が「決定的な動機」ではなかったとして、図利・加害目的を認めている(最決平10.11.25 刑法百選Ⅱ〔第8版〕73事件)。したがって、「自己若しくは第三者の利益を図る目的」は、本人の利益を図る目的が併存する場合であっても認められ得る。よって、本記述は正しい。参考西田(各)278~279頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)326~329頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法会計年度開始前までに予算が成立しない場合,内閣は,前年度の予算を施行することができるし,暫定予算を作成し,国会に提出することもできる。憲法この問題の模試受験生正解率 45.3%結果正解解説憲法86条は,国の収入及び支出が,毎年,予算という形式で国会に提出され審議・議決されなければならないという近代国家に通ずる大原則を定めたものである。もっとも,国会での審議が遅れ議決されないなどの事情により,会計年度開始前までに本予算が成立しない場合があり得る。大日本帝国憲法は,予算が会計年度開始前までに成立しない場合に備えて,前年度の予算の施行を認めていたが(同71条),これでは財政における国会中心主義に反する。そこで,日本国憲法の下では,内閣は,必要に応じて,一会計年度のうちの一定期間を対象とする暫定予算を作成し,国会に提出することができるとする,暫定予算制を採用している(財政法30条1項)。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)373~375頁。
佐藤幸(日本国憲法論)581頁,585頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)413~414頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権は,代位弁済者の債務者に対する求償権である。民法この問題の模試受験生正解率 56.4%結果正解解説判例は,「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために,法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり,したがって,代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権として扱うべきものは,原債権であって,保証人の債務者に対する求償権でないことはいうまでもない」としている(最判昭59.5.29 民法百選Ⅱ〔第8版〕36事件)。よって,本記述は誤りである。参考潮見(プラクティス債総)360~361頁。
中田(債総)417~418頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合,当該盗品等有償譲受け罪の犯人について,その刑は免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 53.4%結果正解解説配偶者との間又は直系血族,同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等に関する罪を犯した者は,その刑が免除されるところ(刑法257条1項),判例は,同項の適用について,当該親族関係は,本犯の犯人と盗品等関与罪の犯人との間に存在することが必要であるとしている(最決昭38.11.8)。したがって,盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合,その刑は免除される。よって,本記述は正しい。参考西田(各)299頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)353頁。
条解刑法849頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法両議院は,各々国政に関する調査を行うことができるが,この国政調査権は,各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので,個々の国会議員も行使することができる。憲法この問題の模試受験生正解率 59.7%結果正解解説両議院は,「各々国政に関する調査を行」うことができる(憲法62条前段)。これが議院の国政調査権と呼ばれるものである。この国政調査権は,あくまで議院に認められる権能であって,議院を構成する個々の議員の権能ではない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)328頁。
佐藤幸(日本国憲法論)508頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)143頁。
新基本法コメ(憲法)355頁。 -
民法Aは,Bとの間で,自己が所有する別荘用の木造建物(以下「甲」という。)を,1か月後に引渡し及び所有権移転登記,その5日後に代金支払の約定でBに売却する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。この事例に関して,本件契約が締結された1か月後に,Aは,Bに甲を引き渡すとともに,Bへの所有権移転登記をしたが,その3日後に,甲は落雷によって滅失した。この場合,Bは,Aからの代金支払請求を拒むことができない。民法この問題の模試受験生正解率 90.6%結果正解解説売主が買主に目的物を引き渡した場合において,その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し,又は損傷したときは,買主は,代金の支払を拒むことができない(民法567条1項後段)。同項は,公平の観点から,売主から買主への目的物滅失の危険の移転の基準時を,目的物の引渡しの時点としたものである。よって,本記述は正しい。参考一問一答(民法(債権関係)改正)287頁。
平野(新債権法の論点と解釈)349頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙が居住する家屋に隣接する乙所有の無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,予想に反して乙居住の家屋に延焼した。この場合,甲には延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.1%結果正解解説刑法111条1項の延焼罪は,自己所有非現住建造物等放火罪(同109条2項)又は自己所有建造物等以外放火罪(同110条2項)を犯したときにのみ成立する。本記述において,甲が放火したのは乙所有の無人の倉庫であり,他人所有の非現住建造物である。したがって,甲には延焼罪は成立せず,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)331頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)387~388頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,無拠出制の年金給付の実現が国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右されるところが大きいこと等に鑑みると,無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範囲,支給要件等をどうするかの決定についての立法府の裁量は,拠出制の年金の場合に比べて更に広範である。憲法この問題の模試受験生正解率 59.0%結果正解解説判例は,大学在学中に障害を負った者が障害基礎年金の支給裁定を申請したが,国民年金に任意加入しておらず被保険者資格がないことを理由に不支給処分を受けたため,当該処分の取消訴訟と国家賠償請求訴訟を提起した事例において,20歳以上の学生に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかった立法不作為が憲法14条及び25条に違反するという原告の主張に対して,「無拠出制の年金給付の実現は,国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右されるところが大きいこと等にかんがみると,立法府は,保険方式を基本とする国民年金制度において補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範囲,支給要件等をどうするかの決定について,拠出制の年金の場合に比べて更に広範な裁量を有している」とした上で,上記の立法措置を講じなかったことは同条,14条1項に違反しないとしている(最判平19.9.28 学生無年金障害者訴訟 憲法百選Ⅱ〔第7版〕134事件)。よって,本記述は正しい。参考安西ほか(読本)234頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,A及びBが甲土地を共有している場合において,AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合,Aは,甲土地を単独で使用することができるが,その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。民法この問題の模試受験生正解率 55.6%結果正解解説判例は,「共有者は,共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり,他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし,共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には,右合意により単独使用を認められた共有者は,右合意が変更され,又は共有関係が解消されるまでの間は,共有物を単独で使用することができ,右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わない」としている(最判平10.2.26 平10重判民法13事件)。よって,本記述は誤りである。参考平野(物権)323~324頁。
松井(物権)198頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,法人事業主は,その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について,両罰規定が定められている場合には,選任監督上の過失がなかったとの証明がなされない限り,刑事責任を免れることができない。刑法この問題の模試受験生正解率 58.1%結果正解解説両罰規定とは,従業者が業務に関して違法行為をした場合に,その従業者と共に事業主をも罰する旨の規定をいう。そして,判例は,「事業主が人である場合の両罰規定については,その代理人,使用人その他の従業者の違反行為に対し,事業主に右行為者らの選任,監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定したものであって,事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り,事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする」とした上で,「右法意は,……事業主が法人(株式会社)で,行為者が,その代表者でない,従業者である場合にも,当然推及されるべきである」としている(最判昭40.3.26 刑法百選Ⅰ〔第8版〕3事件)。このように,判例は,両罰規定は,選任監督上の過失を推定した規定であり,無過失の証明がなされない限り,事業主は処罰されるとして責任主義との調和を図っている。よって,本記述は正しい。参考西田(総)82~83頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)53~54頁。
条解刑法20~21頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の規則制定権は,司法部内における最高裁判所の統制権と監督権を強化するために,国会が国の唯一の立法機関であるとする憲法第41条の例外として憲法上認められたものであるから,最高裁判所は,下級裁判所に関する規則を定める権限であっても,当該権限を下級裁判所に委任することはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 68.9%結果正解解説最高裁判所の規則制定権(憲法77条1項)は,①権力分立の見地から裁判所の自主性を確保し,司法部内における最高裁判所の統制権と監督権を強化すること,さらに,②裁判実務に通じた裁判所の専門的知見を尊重するために認められている。そして,同条3項は,最高裁判所が下級裁判所に関する規則制定権を下級裁判所に委任することを認めている。同項は,②の趣旨からすれば,当然の規定である。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)363頁。
佐藤幸(日本国憲法論)661頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)252~254頁。
新基本法コメ(憲法)409頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,AがB所有の甲土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが甲土地をBから譲り受け,その取得時効の完成後にCが甲土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を時効取得したことを対抗することができない。民法この問題の模試受験生正解率 55.6%結果正解解説判例は,不動産の取得時効完成前に,原所有者から当該不動産の所有権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が,取得時効完成後に所有権移転登記を経由した事例において,取得時効完成当時の当該不動産の所有者は譲受人であり,時効取得者と譲受人は,当該不動産の所有権の得喪のいわば当事者の立場に立つから,時効取得者は,その時効取得を登記なくして譲受人に対抗することができ,このことは,その後譲受人が当該不動産につき所有権移転登記をしたとしても変わりはないとしている(最判昭42.7.21)。したがって,Cは「第三者」に当たらず,AはCに対し,甲土地の所有権を時効取得したことを対抗することができる。よって,本記述は誤りである。参考松井(物権)85頁。
論点体系判例民法(2)77頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,窃盗事件を犯して逃走中のAを,その事実を知りながら自宅にかくまった。甲は,Aが窃盗事件を犯したことは知っていたが,窃盗罪が罰金以上の刑に当たる罪であるとの認識はなかった。この場合,甲には犯人蔵匿罪が成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 88.9%結果正解解説判例は,密入国者をかくまった事例において,犯人蔵匿罪の故意について,密入国者であることを認識すれば足り,密入国罪の刑が罰金以上であることまで認識する必要はないとしている(最決昭29.9.30)。したがって,窃盗罪の刑が罰金以上である限り,その刑が罰金以上であることの認識がなくても,窃盗犯人であると認識してAをかくまった甲には犯人蔵匿罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)581頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)516~517頁。
条解刑法337頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法前文第3段は,他国との共存の必要性・政治道徳の普遍性を謳い,主権国家として国際協調主義の立場に立つことを定めており,このことは憲法本文で具体化されている。憲法この問題の模試受験生正解率 75.8%結果正解解説憲法前文第3段では,他国との共存の必要性と政治道徳の普遍性を謳い,主権国家として国際協調主義の立場に立つことを定めている。そして,国際協調主義は同98条2項によって具体化されている。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)87頁。
新・コンメ憲法25頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,債権者代位権を行使するためには,保存行為の場合を除き,債権者代位権を行使する時点で被保全債権の弁済期が到来している必要があるが,詐害行為取消権を行使するためには,詐害行為の時点で被保全債権の弁済期が到来している必要はない。民法この問題の模試受験生正解率 45.7%結果正解解説債権者は,保存行為を除き,自己の債権(被保全債権)の期限が到来しない間は,債務者に属する権利を行使することができない(民法423条2項)。すなわち,原則として,債権者代位権を行使する時点で,被保全債権の弁済期が到来している必要がある。一方,判例は,債務者の財産が一般債権者の共同担保であり,詐害行為取消権は債権者が債務者の財産に対して有するその担保の利益が害されるのを防止することを目的とするから,被保全債権の弁済期がいまだ到来していない場合においても,弁済の資力に乏しい債務者がその所有する財産を処分するときは,被保全債権の弁済期が既に到来している場合と同様に債権者に不利益が及ぶことを理由に,詐害行為当時に被保全債権の弁済期が到来していなくても,債権者は,詐害行為取消権を行使することができるとしている(大判大9.12.27)。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ338頁,364頁。
潮見(プラクティス債総)182~183頁,226頁。
中田(債総)249頁,285~286頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,外国人甲は,某外国において日本人Vから財物を窃取した。この場合,甲の行為について刑法(窃盗罪)が適用される。刑法この問題の模試受験生正解率 64.1%結果正解解説日本国外において日本国民を被害者とする一定の重大な罪を犯した者には,その者が日本国民でなくても,刑法が適用される(刑法3条の2)。もっとも,これらの罪には,窃盗罪(同235条)は含まれていない(同3条の2各号参照)。したがって,甲の行為について刑法は適用されない。よって,本記述は誤りである。参考大塚ほか(基本刑法Ⅰ)465頁。
条解刑法8~9頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第39条前段にいう「実行の時に適法であつた行為」には,行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為が含まれるから,当該行為をした被告人を処罰することは,同条に違反する。憲法この問題の模試受験生正解率 82.9%結果正解解説判例は,行為当時は最高裁判所の判例上適法とされた行為について,判例変更をして処罰をすることが憲法39条前段に違反するかが争われた事例において,「行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することが憲法39条に違反する旨をいう点は,そのような行為であっても,これを処罰することが憲法の右規定に違反しない」としている(最判平8.11.18 平8重判刑法2事件)。よって,本記述は誤りである。参考長谷部(憲法)275頁。
市川(憲法)207~208頁。
新基本法コメ(憲法)287頁。 -
民法甲土地の所有者Aが隣接するB所有の乙土地を通行する権利(以下「本件通行権」という。)を有している場合に関して,本件通行権が通行地役権に当たる場合,Aは,乙土地に通路を開設することができるが,本件通行権が囲繞地通行権に当たる場合,Aは,乙土地に通路を開設することはできない。
なお,袋地とは,他人の土地に囲まれて公道に通じない土地を,囲繞地とは,袋地を囲んでいる土地をいい,囲繞地通行権とは,公道に至るための他の土地の通行権をいう。民法この問題の模試受験生正解率 64.1%結果正解解説地役権は,承役地を要役地の便益に供する目的で設定されるものであるから,地役権者は,地役権の内容を実現するのに必要な付随行為をすることができる。この付随行為は,地役権の内容によって異なるが,通行地役権の場合,通行に必要な通路を開設することが挙げられる。また,囲繞地通行権者も,必要な場合には通路を開設することができる。したがって,本件通行権が囲繞地通行権に当たる場合,Aは,乙土地に通路を開設することはできないとする点において,本記述は誤っている。よって,本記述は誤りである。参考新版注釈民法(7)338頁,947頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,所持金を全く有していなかったため,当初から運賃を支払うことなくタクシーで目的地へ行こうと考え,乙の運転するタクシーに乗車するやいなや,乙の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた上で,行き先を告げ,乙の意に反してタクシーを目的地まで走行させた後,運賃を支払うことなく逃走した。この場合,甲には強盗利得罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 63.7%結果正解解説刑法236条2項の強盗利得罪の客体である「財産上……の利益」とは,同条1項の財物以外の全ての財産上の利益をいい,そこには財産的価値のある役務(輸送サービス等)の提供が含まれる。そして,相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加えた結果,相手方が事実上債務の弁済請求ができない状態に陥った場合には,強盗利得罪が成立する(最判昭32.9.13等)。本記述において,甲はタクシーの運転手である乙に対し,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて,目的地まで走行させた後,運賃を支払うことなく逃走している。したがって,甲には強盗利得罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考アクチュアル刑法(各)188頁。
条解刑法759~760頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除及び復権を決定する。憲法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,「大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証する」(憲法7条6号)。これら恩赦の決定は,内閣の権能である(同73条7号)。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)545頁,566頁。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,Aが所有する甲土地にBのための第一順位の抵当権が設定され,その後,甲土地上にA所有の乙建物が建てられ,さらに,甲土地にCのための第二順位の抵当権が設定された後,Cの申立てに基づいて抵当権が実行された結果,Dが甲土地の所有者になった場合,甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。民法この問題の模試受験生正解率 58.5%結果正解解説民法388条前段は,「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において,その土地又は建物につき抵当権が設定され,その実行により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなす。」と規定する(法定地上権)。そこで,同条から,法定地上権の成立要件としては,①抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること,②その土地と建物とが同一の所有者に属すること(以下「同一所有者要件」という。),③土地又は建物に抵当権が設定されたこと,及び,④競売の結果,土地と建物とが異なる所有者に属するに至ったことが必要である。
判例は,「土地について一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なり,法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には,土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても,その後に抵当権が実行され,土地が競落されたことにより一番抵当権が消滅するときには,地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である」としている(最判平2.1.22 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕89事件)。したがって,抵当権が実行された結果,第一順位のBの抵当権が消滅している本記述においても,甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ215~216頁。
内田Ⅲ521~522頁。
道垣内Ⅲ224頁。
松井(担物)79~80頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,深夜,市街地にある幅員の狭い道路上に無灯火のまま駐車していた普通乗用自動車の後部トランク内にVを監禁したところ,数分後,たまたま普通乗用自動車で通り掛かった乙が居眠り運転をして同車を甲の自動車の後方に衝突させ,Ⅴは全身打撲の傷害を負い死亡した。この場合,甲の監禁行為とⅤの死亡の結果との間に,因果関係がある。刑法この問題の模試受験生正解率 91.9%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている(最決平18.3.27 刑法百選Ⅰ〔第8版〕11事件)。したがって,甲がVをトランクに監禁した行為とVの死亡の結果との間に,因果関係がある。よって,本記述は正しい。参考山口(総)66頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)77頁。
条解刑法100頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第99条が公務員の憲法尊重擁護義務を規定していることに鑑み,公務員に対して憲法尊重擁護の宣誓を課すことは許されるが,公務員に対して特定の憲法解釈を内容とする宣誓を課すことは,憲法第19条に反し,許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 72.4%結果正解解説公務員は,憲法尊重擁護義務を負う(憲法99条)から,公務員に憲法尊重擁護の宣誓を課すこと自体は違憲とはいえない。ただし,公務員に対して特定の憲法解釈を内容とする宣誓や,人の政治的関係や信条を推知し,又は許容される政治的信条を枠付けた上でそれに従った行動を強要するような内容の宣誓をさせることは,同19条に違反すると解されている。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)247頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)310~311頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,債権者代位権を行使するためには,債務者が無資力であることが必要でない場合があるが,詐害行為取消権を行使するためには,債務者が無資力であることが必要である。民法この問題の模試受験生正解率 45.7%結果正解解説債権者は,自己の債権を保全するため,債務者に属する権利を行使することができる(民法423条1項本文)。そして,判例は,「債権者は,債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合にかぎり,自己の金銭債権を保全するため,民法423条1項本文の規定により当該債務者に属する権利を行使しうる」としているが(最判昭40.10.12),特定債権の履行が債務者の有する権利を代位行使することによって確保される場合には,当該特定債権の保全のために債権者代位権の行使を認めており(債権者代位権の転用),この場合には無資力要件を不要としている(大判明43.7.6 民法百選Ⅱ〔第7版〕14事件,大判昭4.12.16 民法百選Ⅱ〔第5版新法対応補正版〕12事件等)。一方,債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができるところ(同424条1項本文),ここにいう「債権者を害する」とは,債務者の行為によって債務者の資産総額が債権額を弁済するのに不十分(無資力)となることをいうから,債務者が無資力でない場合には,債務者の処分行為は「債権者を害する」ものではなく,詐害行為にはならない。よって,本記述は正しい。
なお,同423条の7は,登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権を認めているが,これは,平成29年民法改正により,判例によって認められた債権者代位権の転用の具体例の一つを明文化したものである。参考内田Ⅲ339~340頁,351~352頁,366頁。
潮見(プラクティス債総)211頁,213頁,230~231頁。
中田(債総)248頁,264~267頁,293頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできないが,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。刑法この問題の模試受験生正解率 58.1%結果正解解説刑法38条3項本文は,「法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定している。したがって,前段は正しい。一方,同項ただし書は,「情状により,その刑を減軽することができる」と規定しており,刑の免除をすることはできない。したがって,後段は誤りである。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法143頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,選挙区割り及び議員定数の配分は,議員総数と関連させながら決定されるのであって,その決定内容は,相互に有機的に関連し,一つの部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有し,その意味において不可分一体をなすので,議員定数配分規定の一部について投票価値の不平等が認められ,違憲と評価される場合,当該議員定数配分規定は,単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく,全体として違憲の瑕疵を帯びる。憲法この問題の模試受験生正解率 65.2%結果正解解説判例は,昭和47年12月10日施行の衆議院議員選挙について,投票価値の較差が憲法に違反するかどうかが争われた事例において,「選挙区割及び議員定数の配分は,議員総数と関連させながら,……複雑,微妙な考慮の下で決定されるのであって,一旦このようにして決定されたものは,一定の議員総数の各選挙区への配分として,相互に有機的に関連し,一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ,その意味において不可分の一体をなすと考えられるから,……配分規定は,単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく,全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである」としている(最大判昭51.4.14 憲法百選Ⅱ〔第7版〕148事件)。よって,本記述は正しい。参考長谷部(憲法)176頁,180頁。
新・コンメ憲法474~475頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は,抵当権者の同意を得ることなく単独でその抵当権を行使することができるが,その抵当権が実行された場合には,競売代金の配当については,当該抵当権者が当該第三者に優先する。民法この問題の模試受験生正解率 56.4%結果正解解説債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその権利を行使することができる(民法502条1項)。したがって,抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は,抵当権者の同意を得ることなく単独でその抵当権を行使することができるわけではない。よって,本記述は誤りである。
なお,代位者が権利行使したことによって得られる金銭については,同条3項は,債権者が行使する権利が,代位者が行使する権利に優先するとしており,この点については,本記述は正しい。参考内田Ⅲ89~90頁。
潮見(プラクティス債総)371~373頁。
中田(債総)431~433頁。
平野(債総)391頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,盗品等無償譲受け罪が成立するためには,無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず,盗品等が現実に移転されることが必要であるが,盗品等有償譲受け罪は,有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 53.4%結果正解解説盗品等無償譲受け罪(刑法256条1項)が成立するためには,無償で盗品等の交付を受け,事実上の処分権を取得することが必要であると解されている。したがって,前段は正しい。また,判例は,盗品等有償譲受け罪(同条2項)が成立するためには,単に契約が成立しただけでは足りず,盗品等の現実の受領が必要であるとしている(大判大12.1.25)。したがって,後段は誤りである。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)345頁,347頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)346頁。
条解刑法845~846頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。憲法この問題の模試受験生正解率 69.7%結果正解解説判例は,夫婦が夫又は妻の氏を称すると定める民法750条が,憲法13条,14条1項,24条に反するかが争われた事例において,「氏は,個人の呼称としての意義があり,名とあいまって社会的に個人を他人から識別し特定する機能を有するものであることからすれば,自らの意思のみによって自由に定めたり,又は改めたりすることを認めることは本来の性質に沿わないもの」であり,また,「氏に,名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることからすれば,氏が,親子関係など一定の身分関係を反映し,婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは,その性質上予定されている」とした上で,「現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえ」ず,民法750条の規定は,「憲法13条に違反するものではない」としている(最大判平27.12.16 憲法百選Ⅰ〔第7版〕29事件)。よって,本記述は正しい。参考渡辺ほか(憲法Ⅰ)119頁。
安西ほか(読本)99頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,甲土地を所有するAが,遺言を残さないで死亡し,Bが唯一の相続人として甲土地を相続したが,Aは生前に甲土地をCに譲渡していた場合において,Cは,所有権移転登記をしなければ,Bに対し,甲土地の所有権の取得を対抗することができない。民法この問題の模試受験生正解率 55.6%結果正解解説判例は,民法177条にいう第三者とは,当事者及びその包括承継人以外の者で,登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいうとしている(大連判明41.12.15 不動産取引百選〔第3版〕46事件)。本記述において,Bは唯一の相続人として,Aの権利義務の一切を承継するのであるから(同896条本文),Aの包括承継人に当たり,同177条にいう第三者に当たらない。したがって,Cは登記がなくても,Bに甲土地の所有権の取得を対抗することができる。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)62頁。
松井(物権)101頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)甲は,某外国において,行使の目的で,通用する日本銀行券を偽造した。この場合,甲の行為について刑法(通貨偽造罪)が適用される。刑法この問題の模試受験生正解率 64.1%結果正解解説日本国外において我が国の国家的・社会的法益を害する一定の重大な罪を犯した者には,その者が日本国民であるか否かを問わず,刑法が適用される(刑法2条)。そして,これらの罪には,通貨偽造罪(同148条1項)が含まれる(同2条4号)。したがって,甲の行為について刑法が適用される。よって,本記述は正しい。参考大塚ほか(基本刑法Ⅰ)464頁。
条解刑法5~6頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,インターネット上の利用者は相互に情報の発受信に関して対等の地位に立ち言論を応酬し合える点に加え,個人利用者がインターネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いものと受け止められていることからすると,インターネットの個人利用者による表現行為に名誉毀損罪が成立するかどうかを判断するに当たっては,個人が他の表現手段を利用した場合とは異なった特別の配慮を要する。憲法この問題の模試受験生正解率 86.9%結果正解解説判例は,被告人自らが開設したホームページにおいて,同人がある株式会社の名誉を毀損する内容の文章を掲載したなどとして起訴された事例において,「個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」とし,インターネットの個人利用者による表現行為について特別な配慮をしない姿勢を示している(最決平22.3.15 平22重判憲法8事件)。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)194~195頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)257~258頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,契約により,承役地の所有者が,自己の費用で地役権者の地役権行使のために承役地に工作物を設ける義務を負担した場合であっても,承役地の所有者は,いつでも,地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで,当該義務を免れることができる。民法この問題の模試受験生正解率 56.0%結果正解解説契約によって承役地の所有者が負担した地役権行使のために工作物を設ける義務は,いつでも,地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで,免れることができる(民法287条,286条)。これは,本来義務は放棄することができないが,地役権行使のために工作物を設ける義務は,いわば土地の所有者が負担するものであるから,土地の所有権を放棄して地役権者に移転することで,その義務を免れると考えられるためである。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)250頁。
松井(物権)238頁。
我妻・有泉コメ515頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,窃盗の目的で,深夜,乙宅に侵入しようと乙宅玄関のガラスを割ったところで乙に発見されたため,逮捕を免れる目的で,同人に対し,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え,その反抗を抑圧し,逃走した。甲には事後強盗未遂罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 63.7%結果正解解説事後強盗罪(刑法238条)の「窃盗」とは,窃盗罪(同235条)の実行に着手した者をいう。住居侵入窃盗の場合,住居に侵入しただけでは窃盗罪の実行の着手は認められないと解されており,判例も,窃盗の目的で人の家屋に侵入し,財物を物色した時に窃盗罪の実行の着手が認められるとしている(最判昭23.4.17)。本記述において,甲は,乙宅への侵入すら遂げていないから,窃盗罪の実行の着手は認められず,事後強盗罪の「窃盗」には当たらない。したがって,甲には事後強盗未遂罪(同243条,238条)は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)162頁,195頁。
条解刑法746頁,767頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法合憲限定解釈には,立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまう可能性があり,立法権の簒奪につながりかねないという問題や,当該解釈が不明確であると,犯罪構成要件の保障的機能を失わせ,憲法第31条違反の疑いを生じさせるという問題があるとされる。憲法この問題の模試受験生正解率 72.2%結果正解解説合憲限定解釈とは,違憲性が争われている法文について,広い意味で解釈すれば違憲となり,狭い意味で解釈すれば合憲となる場合に,狭い意味の解釈を採用することにより違憲判断を回避する手法をいう。合憲限定解釈には,無理な解釈によって合憲限定解釈をした場合,かかる合憲限定解釈によって立法者の意思に反して事実上法文の意味を書き換えてしまう可能性があり,裁判所が司法の権限を逸脱して立法権を簒奪してしまう可能性がある,また,法文について不明確な合憲限定解釈をしてしまうと,犯罪構成要件の保障的機能を失わせてしまい,憲法31条違反の疑いを生じさせるという問題点があるとされる。後者について,判例も,公務員が争議行為のあおり行為を行ったため逮捕・起訴された事例において,「不明確な限定解釈は,かえって犯罪構成要件の保障的機能を失わせることとなり,その明確性を要請する憲法31条に違反する疑いすら存する」としている(最大判昭48.4.25 全農林警職法事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕141事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)394頁。
佐藤幸(日本国憲法論)702~705頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)315頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)367~370頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,AのBに対する甲債権を担保する目的で,BがCに対して有する乙債権の代理受領をAに委任し,Cが,Aに対しその担保の事実を知りつつ代理受領権限を承認したにもかかわらず,Bに対して弁済したため,AがCからの弁済を受領することにより甲債権の満足を得る利益を失った場合,Aは,Cに対し,不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。民法この問題の模試受験生正解率 59.8%結果正解解説本記述のように,甲債権を担保する目的で,債務者Bが債権者Aに対し,乙債権の弁済をBに代わって受領する権限を与えてこれを委任し,CがAに対し,それを承認することを「代理受領」という。本記述において,代理受領の承認がされれば,Aは,CのBに対する債務の弁済を受領する権限を取得するが,CがBに弁済してしまった場合におけるAの救済について,判例は,代理受領の「承認」は,単に代理受領を承認するというにとどまらず,代理受領によって甲債権の満足を得るというAの利益を承認し,正当の理由がなくその利益を侵害しないという趣旨をも当然包含するから,Cとしては,承認の趣旨に反し,Aの利益を害することのないようにすべき義務があるとした上で,Cが承認の際担保の事実を知っていたなどの事情がある場合には,Aは,Cに対し不法行為に基づく損害賠償請求をすることができるとしている(最判昭44.3.4 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕100事件)。よって,本記述は正しい。
なお,Cの承認によって,ABC間の三面契約が成立したと構成することができる場合には,Aは,Cに対し,不法行為責任以外に債務不履行責任を追及することもできると解されている。参考内田Ⅲ662~663頁。
道垣内Ⅲ350頁。
松井(担物)232頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Aから金銭を喝取しようと考え,Aの店の前で連日怒声を上げるなどして客足を遠のかせてAの業務を妨害し,金銭を支払わなければ引き続き妨害行為を続ける旨の態度を示しAを畏怖させ,金銭を交付させた。この場合,甲には,威力業務妨害罪と恐喝罪が成立し,これらは牽連犯となる。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,職業の許可制が,自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的, 警察的措置である場合には,許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められれば,当該措置を導入したことの合憲性が肯定される。憲法この問題の模試受験生正解率 34.6%結果正解解説最大判昭50.4.30(薬事法距離制限違憲判決 憲法百選I 〔第7版〕92事件)は,職業の自由に対する規制の合憲性判断枠組みにつき,「一般に許可制は,単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので,職業の自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定しうるためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し,また,それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく,自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的,警察的措置である場合には,許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの, というべきである」としている。同判決は,職業の自由に対する規制の合憲性は,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるかという判断に加えて,許可制が消極目的から導入される場合には,許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められることを要するとしている。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,Aに代理権を与えたBは,Aが自己の利益を図る目的で,Cとの間でその代理権の範囲内の行為をした場合において,CがAの目的を過失なく知らなかったときは,その行為についての責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 87.8%結果正解解説代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合,その行為は,原則として本人にその効力を生ずるが,相手方がその目的を知り,又は知ることができたときは,その行為は,無権代理行為とみなされる(民法107条)。したがって,CがAの目的を過失なく知らない本記述においては,Bは,原則どおりAがした行為についての責任を負う。よって,本記述は正しい。参考佐久間(総則)250~251頁。
リーガルクエスト(総則)204~205頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,強盗致傷罪において必要とされる反抗を抑圧するに足りる程度の暴行からは多少の傷害が生じるのが通常であって,軽微な傷害は強盗の手段としての暴行に評価し尽くされているから,強盗致傷罪における傷害は,傷害罪における傷害よりも重大なものでなければならない。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法日本国憲法の改正手続に関する法律は,公職選挙法が18歳未満の者の選挙運動を禁止しているのとは異なり,18歳未満の者の国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないように勧誘する行為)を禁止していない。憲法この問題の模試受験生正解率 64.5%結果正解解説日本国憲法の改正手続に関する法律は,憲法改正案に対する国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないように勧誘する行為同100条の2)について規定するが,選挙運動と比較すると規制が緩和されている。例えば,選挙では,18歳未満の者の選挙運動は禁止されているが(公職選挙法137条の2第1項),国民投票運動には年齢制限はない。その理由としては,選挙と比べて不当な利益誘導のなされる危険が少ないといった説明がなされている。したがって,日本国憲法の改正手続に関する法律は,18歳未満の者の国民投票運動を禁止していない。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)407~408頁。
渡辺ほか(憲法I)429頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)158頁。
リーガルクエスト(憲法I)36頁。 -
民法A男(17歳)とB女(18歳)との間に子Cが生まれた場合,Aは,成年に達すれば,Cを養子とする普通養子縁組をすることができる。民法この問題の模試受験生正解率 61.0%結果正解解説普通養子縁組の養親となることができる者の年齢は,20歳である(民法792条)。したがって,Aは,成年(18歳)に達しただけではCの養親となることはできない。よって,本記述は誤りである。
なお,平成30年民法改正前においては,普通養子縁組の養親となることができる者の年齢について,「成年に達した者」とされていたが,同改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことから,養親年齢については,「20歳に達した者」と改められた。成年年齢を引き下げても,養親となる者については,一定の成熟度が求められるという観点から,同改正前の年齢が維持されたものである。参考窪田(家族法)246~247頁。
リーガルクエスト(親族・相続)151頁。
新基本法コメ(親族)164頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,自宅の前の道路を通勤のため毎日通行しているA女に一方的に好意を抱き,Aを自宅の一室に連れ込んで閉じ込めようと考え,甲の自宅前の道路上においてAを待ち伏せた上,歩いてきたAを自宅に連れ込むため,Aの顔面を手拳で殴打し顔面に傷害を負わせたが,Aが逃げたため,自宅に連れ込むことはできなかった。この場合,甲には,監禁致傷罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 75.6%結果正解解説監禁致死傷罪(刑法221条)は,監禁罪を犯し,よって人を死傷させた場合に成立する結果的加重犯であるから,監禁致死傷罪が成立するためには,基本犯としての監禁罪が成立すること,及び監禁行為と人の死傷との間に因果関係が存在することが必要である。本記述においては,Aは,甲宅に連れ込まれる前に逃げているため,甲には基本犯としての監禁罪が成立しない。したがって,甲に監禁致傷罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)84頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)57頁。
条解刑法667頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,国が,難民条約の批准等及びこれに伴う国会審議を契機として,外国人に対する生活保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めたことからすると,一定の範囲の外国人は,生活保護法に基づく保護の対象となり得る。憲法この問題の模試受験生正解率 76.5%結果正解解説判例は,永住外国人が,市に対して生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ,当該申請を違法に却下する処分を受けたとして,その取消し等を求めた事例において,「旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれ」ず,「現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない」ため,「生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない」,また,行政庁の通達等に基づく「行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても,そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく」,これは,我が国が難民の地位に関する条約等に加入した際の経緯を勘案しても変わらないとし,結論として,「外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しない」としている(裁判平26.7.18 平26重判憲法11事件)。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決の原審(福岡高判平23.11.25 平23重判国際法3事件)は,「国は,難民条約の批准等及びこれに伴う国会審議を契機として,外国人に対する生活保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めたものということができる。すなわち,行政府と立法府が,当時の出入国管理令との関係上支障が生じないとの認定の下で,一定範囲の外国人に対し,日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを是認したものということができるのであって,換言すれば一定範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである」から,生活保護法の文言にかかわらず,一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるとしている。参考佐藤幸(日本国憲法論)167頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅱ)30頁。
新井ほか(憲法Ⅱ)24頁。 -
民法AB夫婦が離婚し,その1か月後にBがCを出産した場合に判例の趣旨に照らすと,Cが嫡出の推定が及ばない子であると認められるときは,Cは,血縁上の父に対して認知の請求をすることができる。民法この問題の模試受験生正解率 44.4%結果正解解説嫡出でない子について,法律上の父子関係を成立させるには,認知による必要がある。認知には,父の側からその子について父子関係があることを認める任意認知(民法779条)と,父が任意に認知しない場合に,子の側が訴えによって認知を求め,判決により父子関係を成立させる強制認知(同787条)がある。そして,婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は,夫の子と推定されるが(同772条),判例は,形式的に同条の嫡出推定を受ける子であっても,子の懐胎時に夫が不在であったり,事実上の離婚状態があったなど妻と夫の間に同棲や実質的な夫婦生活が存在せず,外観上夫による懐胎でないことが明らかな場合には,同条の推定が及ばないとしている(推定の及ばない子 最判昭44.5.29 家族法百選〔第5版〕30事件,最判平10.8.31など)。したがって,推定の及ばない子Cは,真実の父に対して認知請求をすることができる。よって,本記述は正しい。参考窪田(家族法)176~177頁,193~197頁。
リーガルクエスト(親族・相続)125~126頁,134頁。
新・コンメ民法(家族法)91頁,101頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,実父乙がその友人である丙から借り受け,自室で管理していた丙所有の腕時計を,乙の所有物であると誤信し,それを自分のものにしようと思い,乙の部屋から持ち出した。この場合,甲には,窃盗罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 66.9%結果正解解説刑法244条1項は,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者について,刑の免除を認める規定である。判例は,同「244条1項は,親族間の一定の財産犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき,その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず,その犯罪の成立を否定したものではない」として(最決平20.2.18 刑法百選Ⅱ〔第8版〕35事件),同項を政策的な理由に基づいて,人的処罰阻却事由を定めた規定であると解している。同項の親族関係の錯誤については,同項について人的処罰阻却事由を定めた規定と解する以上,犯罪事実に関する錯誤とはいえず,故意あるいは犯罪の成否に影響を及ぼさない。したがって,本記述では,甲には,窃盗罪(同235条)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考井田(総)183~184頁。
条解刑法778~779頁。
大コメ(刑法・第3版)(12)572~574頁。
大コメ(刑法・第3版)(13)700頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法立法権が議会に,司法権が裁判所に分化帰属して,残ったものが行政権になったという歴史的経緯に適合することなどを理由として,行政権とは,全ての国家作用のうちから立法権と司法権を除いた残余の権力であるとする見解に対しては,弾劾裁判所の設置権も裁判所規則制定権も行政権になってしまいかねないとの批判が妥当する。憲法この問題の模試受験生正解率 32.9%結果正解解説憲法65条は,「行政権は,内閣に属する。」と規定し,行政権は内閣の権限であるとする。そして,本記述の見解は,行政権とは,全ての国家作用のうちから立法権と司法権を除いた残余の権力であるとする(控除説)。控除説を前提にすると,立法権・司法権以外の国家作用は,全て行政権ということになる。そこで,控除説に対しては,国会の権限である弾劾裁判所の設置権(同64条1項),また,最高裁判所の権限である裁判所規則制定権(同77条1項)も行政権ということになりかねないとの批判が妥当する。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)333~334頁。
佐藤幸(日本国憲法論)523~525頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)196~197頁。
安西ほか(憲法学読本)300頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)282~283頁。 -
民法売買の目的物として買主に引き渡された物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において,買主が代金減額請求権を行使したときは,買主は,その後,その不適合を理由とする履行の追完に代わる損害の賠償を請求することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 58.5%結果正解解説民法564条は,同562条及び同563条の規定は,同415条の規定による損害賠償の請求並びに同541条及び同542条の規定による解除権の行使を妨げないとしている。同564条は,同562条が買主の追完請求権を規定し,同563条が代金減額請求権を規定していることは,同415条所定の損害賠償請求権の行使及び同541条,542条の解除権の行使を妨げないことを定めたものであり,両立しない請求を認めるものではない。例えば,本記述のように,代金減額請求権が行使されると,契約の内容に適合しなかった部分について,代金債務の減額と引換えに,引渡債務の内容も現実に引き渡された目的物の価値に応じて圧縮され,契約の内容に適合した物が引き渡されたとみなされることになるので,さらに,当該不適合を理由とする履行の追完に代わる損害賠償請求を認めることはできない。よって,本記述は正しい。参考潮見(新契約各論I)150頁。
中田(契約)310~312頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)279頁。
新基本法コメ(債権2)130~131頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,責任能力の有無・程度について,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠として提出され,裁判所がその証拠を採用する場合には,裁判所は,その意見に従い認定しなければならない。刑法この問題の模試受験生正解率 87.2%結果正解解説判例は,責任能力の判断は専ら裁判所に委ねられるべき法律的判断であることを前提としつつ,「生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである」としている(最判平20.4.25 平20重判刑法4事件)。したがって,裁判所は上記のような証拠を採用した場合でも,専門家である鑑定人の意見に従い認定しなければならないわけではない。よって,本記述は誤りである。参考西田(総)301~302頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)224頁。
条解刑法168頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,放送事業者又は放送事業者が制作に協力を依頼した関係業者から素材収集のための取材を受けた取材対象者が,取材担当者の言動等によって,当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,あるいは信頼したとしても,その期待や信頼は原則として法的保護の対象とはならない。憲法この問題の模試受験生正解率 59.6%結果正解解説判例は,テレビ局の番組について,番組制作会社等が当初説明した内容とは異なる趣旨で番組を制作・放送して,期待や信頼を侵害したなどとして,取材対象者が損害賠償を求めた事例において,「放送事業者がどのように番組の編集をするかは,放送事業者の自律的判断にゆだねられており,番組の編集段階における検討により最終的な放送の内容が当初企画されたものとは異なるものになったり,企画された番組自体放送に至らない可能性があることも当然のことと認識されているものと考えられることからすれば,放送事業者又は制作業者(注:放送事業者が制作に協力を依頼した関係業者)から素材収集のための取材を受けた取材対象者が,取材担当者の言動等によって,当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,あるいは信頼したとしても,その期待や信頼は原則として法的保護の対象とはならない」としている(最判平20.6.12 メディア百選〔第2版〕98事件)。よって,本記述は正しい。参考辻村(憲法)212頁。
アルマ(憲法1)182~183頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,Aがその所有する甲建物をBに賃貸し,BがAの承諾を得てCに甲建物を転貸した場合において,AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは,特段の事情のない限り,AB間の賃貸借契約が終了した時点で,BC間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能となる。民法この問題の模試受験生正解率 59.6%結果正解解説賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合は,賃貸借は,これによって終了する(民法616条の2)。そして,適法に転貸借がなされた場合において,原賃貸借契約が債務不履行を理由に終了したときは,転借人は原賃貸人に対して転借権を対抗することはできないから,転貸借契約は消滅することになるが,その終了時期がいつなのかについて争いがある。平成29年民法改正前の事例であるが,判例は,「賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合,賃貸人の承諾のある転貸借は,原則として,賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に,転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する」としている(最判平9.2.25 民法百選Ⅱ〔第8版〕64事件)。その理由として,同判決は,「賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上,転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして,転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは,もはや期待し得ないものというほかはなく,転貸人の転借人に対する債務は,社会通念及び取引観念に照らして履行不能というべき」ことを挙げている。同判決は,同改正後においても妥当すると解されている。したがって,本記述において,AがCに甲建物の返還を請求した時に,BC間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能となる。よって,本記述は誤りである。参考潮見(新契約各論I)478~482頁。
中田(契約)429頁。
論点体系判例民法(6)110頁。
新債権法の論点と解釈482頁。
新基本法コメ(債権2)221頁。
新・コンメ民法(財産法)1046~1047頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,複数名が殴り合いのけんかをしている場所でその暴行をはやし立てた者には,けんかの当事者に傷害の結果が生じなかった場合,現場助勢罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 77.2%結果正解解説現場助勢罪(刑法206条)は,傷害罪,傷害致死罪(同205条)が行われるに当たり,はやし立てたり,無責任な声援を送ったりするなど,現場において勢いを助ける行為を処罰の対象としている。現場助勢罪は,傷害又は傷害致死の犯罪が行われていることを要するから,暴行の段階で助勢したがこれらの結果が生じなかった場合には,現場助勢罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)47頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)221頁。
条解刑法621頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法上,地方政治では,執行権の担い手である長と,議決機関である議会が,それぞれ直接に住民に対し責任を負う体制が採られているため,法律上,議会が長の不信任決議をしたり,長が議会の解散権を持つといった制度は設けられていない。憲法この問題の模試受験生正解率 70.7%結果正解解説憲法93条は,地方公共団体の機関として,公選の長と議会を規定する。それを受けて,地方自治法は,普通地方公共団体の長と地方公共団体の議会の議員との兼職禁止を定める(同141条2項)等,執行権の担い手としての長と,議決機関である議会が,それぞれ直接に住民に対して責任を負う二元的代表制が採られている。もっとも,議院内閣制的仕組みとして,同法は,議会の特別多数決による長に対する不信任決議と,長による議会の解散権について規定している(同178条1項)。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)372~373頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)425頁。
リーガルクエスト(憲法I)375頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がなされた場合,その登記の存在のみをもって,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 54.9%結果正解解説法人が金銭債権を譲渡した場合において,当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは,当該債権の譲受人において民法467条の第三者対抗要件が具備されたものとみなされる(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)4条1項前段)。すなわち,債権譲渡登記ファイルへの譲渡の登記は,あくまで第三者対抗要件にすぎない。そして,同項における登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において,当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし,又は当該債務者が承諾をしたときは,債務者対抗要件が具備されたものとみなされる(同条2項)。したがって,本記述において,CがBに対して自己が債権者であることを主張するためには,債権譲渡登記に加え,債権譲渡及び債権譲渡登記がされたことについて,A若しくはCがBに登記事項証明書を交付して通知をするか,又はBがそのことを承諾する必要がある。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ261~262頁。
潮見(プラクティス債総)531~532頁。
中田(債総)681頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,現行犯逮捕され,最寄りの警察署に連行された後,取調べを受けていたが,トイレ休憩の際に,隙を見てトイレの窓から中庭に出て,警察署の敷地外へ逃走しようとしたが,それを果たすことなく警察官に拘束された。この場合,甲には,逃走罪の未遂犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 33.8%結果正解解説逃走罪(刑法97条)の主体は,「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」である。「裁判の執行により拘禁された」という文言は,逮捕された者を除く趣旨を明確にするために入れられたものである。裁判の執行により拘禁された未決の者とは,勾留状によって,刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条)又は留置施設(同14条)に拘禁されている被告人又は被疑者をいい,逮捕された者は含まれない(札幌高判昭28.7. 9)。本記述では,甲は現行犯逮捕された者であり,刑法97条の主体にはならない。したがって,甲には,逃走罪の未遂犯(同97条,102条)は成立しない。よって,本記述は誤りである。
なお,同罪が既遂に達するのは,同罪の主体が,刑事施設等の外に脱出するなどして,看守者の実力的支配を脱した時である。参考山口(各)565頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)540~541頁。
条解刑法323~324頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われる結果,宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されるため,解散命令は,これらを用いて行っていた信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を伴うものといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 57.8%結果正解解説判例は,宗教法人に対する解散命令が,信者の信教の自由を不当に制約し許されないのではないかが争われた事例において,「解散命令によって宗教法人が解散しても,信者は,法人格を有しない宗教団体を存続させ,あるいは,これを新たに結成することが妨げられるわけではなく,また,宗教上の行為を行い,その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち,解散命令は,信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも,宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われ・・・・・・,その結果,宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから・・・・・・,これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る」としている(最決平8.1.30 憲法百選I〔第7版〕39事件)。同決定によれば,解散命令は,信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない。よって,本記述は誤りである。
なお,同決定は,「宗教法人に関する法的規制が,信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても,これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば,憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し,憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない」としている。参考芦部(憲法)164頁。
渡辺ほか(憲法I)176頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人は,仕事の完成前であれば,請負契約を解除することができる。民法この問題の模試受験生正解率 86.4%結果正解解説注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人又は破産管財人は,契約の解除をすることができる(民法642条1項本文)。このうち,請負人の解除権の行使については,仕事の完成前に限って認められる(同項ただし書)。仕事の完成前に限って請負人の解除権が認められた趣旨は,注文者が破産手続開始決定を受けた場合,請負人が仕事の完成までに投人する労力に応じた報酬を確保できない危険性があることによるところ,注文者が破産手続開始決定を受けた時点で仕事が完成している場合には,請負人がそれ以上の損害を被る危険性がないことによる。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各I)254頁。
中田(契約)523~524頁。
新・コンメ民法(財産法)1088~1089頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,製薬会社に勤務し経理部に所属していたが,同社の研究開発部が開発中の薬剤に係る情報を他の製薬会社に売り渡そうと考え,研究開発部に所属し,同薬剤の開発に携わっていた乙のパソコンに保存されていた当該情報を甲が所有するUSBメモリに転送し,当該USBメモリを金銭と引換えに丙社に引き渡した。この場合,甲には,窃盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 67.7%結果正解解説窃盗罪の客体は,「他人の財物」である。情報は,財物ではないので,情報自体を盗んでも窃盗罪とはならない。裁判例も,情報それ自体を財物とは解しておらず,情報が化体した媒体につき財物性を肯定している(東京地判昭59.6.28 刑法百選Ⅱ〔第8版〕33事件)。本記述では,甲は,自己の所有するUSBメモリに開発中の薬剤に係る情報を転送したにすぎない。したがって,当該USBメモリを引き渡しても,甲には,窃盗罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考高橋(各)218~219頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)122頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とした民法の法定相続分規定は,遺言によっても侵害し得ない遺留分の計算において明確な法律上の差別というべきであるとともに,当該規定の存在自体がその出生時から嫡出でない子に対する差別意識を生じさせかねないことをも考慮すれば,当該規定が補充的に機能する規定であることは,その合理性判断において重要性を有しない。憲法この問題の模試受験生正解率 16.1%結果正解解説判例は,民法900条(平成25年法律第94号による改正前のもの)は法定相続分について規定し,同条4号は被相続人に子が数人あるときは各自の相続分を相等しいものとした上で,同号ただし書で非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていた(以下「本件規定」という。)ところ,これが憲法14条1項に反するかどうかが争われた事例において,最大決平7.7.5(憲法百選I〔第5版〕31事件)においては,「本件規定を含む法定相続分の定めが遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能する規定であることをも考慮事情としている。しかし,本件規定の補充性からすれば,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とすることも何ら不合理ではないといえる上,遺言によっても侵害し得ない遺留分については本件規定は明確な法律上の差別というべきであるとともに,本件規定の存在自体がその出生時から嫡出でない子に対する差別意識を生じさせかねないことをも考慮すれば,本件規定が上記のように補充的に機能する規定であることは,その合理性判断において重要性を有しない」としている(最大決平25.9.4 憲法百選I〔第7版〕27事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)140~142頁。
渡辺ほか(憲法I)150~151頁。 -
民法A男(17歳)とB女(18歳)との間に子Cが生まれた場合,AがCを認知していない場合,Cに対する親権は,Bが行使する。民法この問題の模試受験生正解率 61.0%結果正解解説嫡出でない子に対する親権は,その子を認知した父と母の協議で,父を親権者と定めたときを除き(民法819条4項),母が行う。したがって,本記述において,Cに対する親権は,母であるBが行う。よって,本記述は正しい。
なお,親権を行う者は,その親権に服する子に代わって親権を行うこととされているが(同833条),本問において,Cの親権者であるBは18歳であり,成年に達しているから(同4条),同833条の適用はない。参考窪田(家族法)305頁。
リーガルクエスト(親族・相続)172頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,妊娠中の甲は,医者である乙に嘱託し,堕胎を行わせた。この場合,甲には,業務上堕胎罪の教唆犯が成立する。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法特別会は,衆議院の解散又は衆議院議員の任期満了による総選挙後に召集される国会であり,その目的は,内閣総理大臣の指名であるから,内閣総理大臣の指名が終われば,直ちに会期は終了する。憲法この問題の模試受験生正解率 58.1%結果正解解説特別会とは,衆議院の解散後,総選挙が行われた後に召集される国会をいう。衆議院議員の任期満了による総選挙後に召集される国会は,特別会ではなく,臨時会である。また,特別会の主たる目的は,内閣総理大臣の指名(憲法67条1項前段)であるが,その審議事項について,特に制約はない。そのため,会期中であれば,内閣総理大臣の指名以外の事項について審議することは可能であって,内閣総理大臣の指名がされたからといって,直ちに特別会の会期が終了するわけではない。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)116頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)253頁。
注釈日本国憲法(3)662頁。 -
民法多数当事者の債権及び債務に関して,数人の債権者がいる場合に,可分な債権の目的を当事者の意思表示によって不可分とすることができる。民法この問題の模試受験生正解率 38.7%結果正解解説不可分債権とは,一個の不可分な給付について多数の債権者がいる場合に,同一の不可分給付を目的とする債権が債権者の数だけ生じる債権関係をいう。平成29年民法改正前は,債権の目的が性質上不可分であるもののほか,意思表示により不可分とされるものも,不可分債権に含まれていた。しかし,連帯債権との区別が不明瞭であり,また,同改正によりあえて性質上可分な場合を不可分債権とする実益がなくなったため,意思表示による不可分債権は廃止し,同改正前の意思表示による不可分債権に相当するものは,連帯債権として扱うこととされた(民法428条・432条参照)。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ473頁,475頁。
潮見(プラクティス債総)596頁。
中田(債総)515~516頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲と乙は,裁判所に提出する目的で,市立病院の医師丙を教唆して内容虚偽の診断書を作成させる共謀をし,乙は,丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲と相談することなく,当初と同一の目的で,医師でない丁を教唆して市立病院医師丙名義の診断書を作成させた。この場合,甲には,有印公文書偽造教唆罪の共同正犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 52.5%結果正解解説判例は,保釈の請求に使用するため,刑務所医師をして虚偽内容の診断書を作成せしめることを共謀した者のうちの一人が,他の共犯者に謀ることなく同一の目的のため他人をして刑務所医師名義の診断書を作成せしめたという事例において,本件の故意の内容は虚偽公文書作成罪(刑法156条)の教唆であり,結果は公文書偽造罪(同155条)の教唆であるところ,「この両者は犯罪の構成要件を異にするもその罪質を同じくするものであり且法定刑も同じである。而して右両者の動機目的は全く同一である」から,他の共謀者について,「法律上本件公文書偽造教唆につき故意を阻却しない」として有印公文書偽造教唆罪の共同正犯(同条1項,61条1項,60条)の成立を認めている(最判昭23.10.23 刑法百選I〔初版〕53事件)。したがって,本記述において,甲には,有印公文書偽造教唆罪の共同正犯が成立する。よって,本記述は正しい。参考大谷(講義総)465~466頁。
井田(総)556~557頁。
大塚ほか(基本刑法I)347頁。
条解刑法160頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法法律で,「町村は,条例で,議会を置かず,選挙権を有する住民の総会を設けることができる。」と定めることは,違憲ではないと解されているが,これまでにこのような町村総会が設置された例はない。憲法この問題の模試受験生正解率 70.7%結果正解解説直接選挙で選ばれる議員によって構成される議決機関としての議会の設置は,憲法93条の要求するところである。そして, 地方自治法も「普通地方公共団体に議会を置く。」と規定する(同89条)。この規定にかかわらず,町村は,条例で,議会を置かず,選挙権を有する者の総会を設けることができる(同94条)。そして,このような町村総会も憲法上の「議会」に当たると解されている。地方自治法下において,町村総会を設置した例としては,東京都八丈支庁管内宇津木村がある。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)373頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)426頁。
リーガルクエスト(憲法I)374頁。 -
民法Aが所有する甲土地とBが所有する乙土地が隣接している場合,判例の趣旨に照らすと,乙土地上に生えている樹木の枝が,境界線を越えて甲土地上に伸びてきたときは,Aは,Bの承諾なくその枝を切り取ることができる。民法この問題の模試受験生正解率 73.7%結果正解解説隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる(民法233条1項)。したがって,本記述において,Aは,Bの承諾なく自ら乙土地上の樹木の枝を切り取ることはできない。よって,本記述は誤りである。参考松井(物権)175頁。
新注釈民法(5)445頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,違法な業務も,業務妨害罪の客体になり得る。刑法この問題の模試受験生正解率 66.5%結果正解解説業務妨害罪における「業務」は,職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務のことをいう(大判大10.10.24)。同罪は,事実上平穏に行われている人の社会的活動の自由を保護しようとするものであるから,その業務の適法性については,刑法的な保護に値するものであれば足り,違法なものでも同罪の業務に含まれると解されている(東京高判昭27.7.3,東京高判昭24.10.15等参照)。判例も,行政代執行の手続をとるべきであったが,相手方や目的物の特定等の点で困難があるので,そのような手続を踏まずに東京都の職員が路上生活者の段ボール小屋を撤去した事例において,「やむを得ない事情に基づくものであって,業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法的瑕疵があったとは認められない」としている(最決平14.9.30 刑法百選Ⅱ〔第8版〕24事件)。よって,本記述は正しい。参考西田(各)138頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)110~111頁。
条解刑法715~716頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対して学校長が行った原級留置処分や退学処分が,当該生徒がそれら各処分による不利益を避けるために剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくされるという性質を有する場合には,当該生徒の信教の自由を直接的に制約するものであるから,学校長はそれらの処分をするに当たり,当然そのことに相応の考慮を払う必要がある。憲法この問題の模試受験生正解率 57.8%結果正解解説判例は,公立の高等専門学校での剣道実技の履修を信仰上の理由から拒否したため,学校長(注:上告人)から原級留置処分及び退学処分を受けた生徒(注:被上告人)が,当該処分は信教の自由を侵害するものとしてその取消しを求めた事例において,「被上告人は,信仰上の理由による剣道実技の履修拒否の結果として,他の科目では成績優秀であったにもかかわらず,原級留置,退学という事態に追い込まれたものというべきであり,その不利益が極めて大きいことも明らかである。また,本件各処分(注:原級留置処分及び退学処分)は,その内容それ自体において被上告人に信仰上の教義に反する行動を命じたものではなく,その意味では,被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえないが,しかし,被上告人がそれらによる重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である」ところ,「上告人の採った措置が,信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなく,教育内容の設定及びその履修に関する評価方法についての一般的な定めに従ったものであるとしても,本件各処分が右のとおりの性質を有するものであった以上,上告人は,・・・・・・当然そのことに相応の考慮を払う必要があった」としている(最判平8.3.8 憲法百選I〔第7版〕41事件)。同判決によれば,信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対して学校長が行った原級留置処分及び退学処分は,生徒の信教の自由を直接的に制約するものではない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)163~164頁。
渡辺ほか(憲法I)180~181頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,Aは,Bとの間で,真実その所有する動産を売却する意思がないのに,Bにその動産を売却し,その代金をBがCに支払う旨の契約を締結したが,BがAの真意を知っていた場合,受益の意思表示をしたCがAの真意につき善意無過失であっても,Bは,Cに対して売買契約の無効を主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 31.3%結果正解解説諾約者は,第三者のためにする契約に基づく「抗弁」をもって,受益者に対抗することができる(民法539条)。この「抗弁」には,同時履行の抗弁権のほか,契約の無効,取消し,解除の効果を主張することも含まれる。また,無効又は取消しを主張する場合,第三者のためにする契約における受益者は善意の第三者(同93条2項,94条2項,95条4項,96条3項)として保護されることはない。本記述の場合,Aの売却の意思表示は,心裡留保(同93条1項本文)に当たるが,BがAの真意を知っているためAB間の売買契約は無効となる(同項ただし書)。そして,この場合,意思表示をした者の真意を知らない第三者は同条2項により保護されるが,受益者であるCについては,同項の適用はない。そのため,Bは,AB間の売買契約の無効をCに対して主張することができる。よって,本記述は正しい。参考新基本法コメ(債権2)41頁。
論点体系判例民法(6)92頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙の同意を得て,差押えを受けている乙所有の自動車に放火してこれを燃やしたが, 公共の危険が生じなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 80.9%結果正解解説他人が所有する自動車を放火する場合は,刑法110条1項の成立が問題となるところ,その者の同意がある場合には,財産権侵害がなく,自己所有物との均衡を考えて,同条2項が適用される。しかし,その物が差押えを受けている場合には,同115条より同110条1項の成立が再び問題となる。もっとも,建造物等以外放火罪(同条)は,他人所有・自己所有いずれの場合も,「よって公共の危険を生じさせた」場合にのみ処罰される。本記述では,公共の危険が生じなかった以上,同罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)329~330頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)371~372頁。
条解刑法367~369頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法天皇の国事行為は,憲法によって限定列挙されているから,法律によって,新たに国事行為を創設することはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 74.5%結果正解解説天皇の国事行為は,憲法6条,7条が列挙するもの「のみ」(同4条1項)に限定される。したがって,法律によって新たに国事行為を創設することはできない。よって,本記述は正しい。
なお,国事行為の具体的内容は,同6条,7条に列挙されているが,同4条2項の国事行為の委任も国事行為の一つに数えられることがある。参考野中ほか(憲法I)123頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)90~91頁。
新井ほか(憲法I)66頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,.Aに代理権を与えたBは,AがCとの間でしたその代理権の範囲内の行為が,Aの詐欺を理由としてCにより取り消された場合であっても,Aの詐欺について善意無過失であるときは,Cに対し,その行為の効果が自己に帰属することを主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 87.8%結果正解解説判例は,代理人の詐欺によって相手方が意思表示をした場合,民法101条1項の適用を認めている(大判明39.3.31,大判昭7.3.5)。すなわち,代理人の詐欺は本人の詐欺と同視され,相手方は,本人が代理人の詐欺を知っているか否かにかかわらず,本人に対して詐欺による意思表示の取消しを対抗することができる。したがって,本記述において,Bは,代理人であるAの詐欺について善意無過失であっても,Cに対し,その行為の効果が自己に帰属することを主張することはできない。よって,本記述は誤りである。
なお,学説は,代理人は,本人が契約締結のために用いた者であり,同96条2項の「第三者」に含まれないとして同項の適用を排除することで,同条1項の原則どおり詐欺による取消しを可能として,判例と同じ結論を導いている。参考平野(総則)293~294頁。
リーガルクエスト(総則)196~197頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Aが所有する絵画を手に入れたいと思い,乙に対し,Aから絵画を盗んでくれは高値で買ってやると申し向け,乙がAから盗んできた絵画を買い受けた。甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,これらは牽連犯となる。刑法この問題の模試受験生正解率 72.1%結果正解解説判例は,盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)と窃盗教唆罪(同61条1項,235条)とは,各別個独立の犯罪であるから,同一人が盗品を買い受ける目的をもって他人に対して窃盗を教唆し,その窃取してきた物を有償で譲り受けたときでも,窃盗教唆罪とは別に盗品等有償譲受け罪が成立するとしている(大判大5.6.15)。そして,この両罪の関係について,判例は,牽連犯(同54条1項後段)が成立するためには,「ある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって,被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りない」とした上で,窃盗教唆と盗品有償譲受けとの間には通常手段又は結果の関係はないのであるから,被告人が盗品有償譲受けの手段として窃盗教唆を行ったものであっても,牽連犯に当たるものではなく,両者は併合罪の関係に立つとしている(最判昭25.11.10)。したがって,本記述において,甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,これらは併合罪となる。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)298頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)348頁。
大コメ(刑法・第3版)(13)751~752頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第13条後段の保障する幸福追求権は,それ自体一つの権利としての性格を持つ個別的基本権を包括する基本権であるが,個別の権利条項が妥当しない場合に限り,補充的に同条後段が適用される。憲法この問題の模試受験生正解率 69.3%結果正解解説憲法13条後段は,幸福追求権について規定しており,かかる権利は,具体的権利性を有すると考えられている。そして,他の人権規定と同条後段との関係については,幸福追求権が個人の尊重にとって必要な権利を包括的に保障したものであることから,個別の権利条項と幸福追求権の保障とは,特別法と一般法の関係に立ち,前者の保障の及ばない範囲を同条後段がカバーするものとされている。よって,本記述は正しい。参考野中ほか(憲法I)271頁。
渋谷(憲法)179頁。
新・コンメ(憲法)151頁。 -
民法売買の目的物として買主に引き渡された物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において,その不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものであれば,買主は,売主に対して,代金の減額を請求することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 58.5%結果正解解説売買の目的物の種類,品質,数量に関する契約不適合における代金減額請求権(民法563条)の要件として,契約不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものであることは要求されない。したがって,同条の要件を備える限り,売主の帰責事由の有無にかかわらず,代金減額請求をすることができる。よって,本記述は誤りである。参考潮見(新契約各論I)146頁。
新基本法コメ(債権2)126頁。
新・コンメ民法(財産法)963頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙が運転する自動車との接触事故により,全治3日間の軽傷を負ったが,乙から多額の賠償金を得ようと考え,行使の目的で,真正な市立病院丙医師作成名義の診断書から切り取った丙医師の署名及び押なつ部分を,甲が当該事故により全治1か月の傷害を負った旨の虚偽の事実を記入した診断書と題する書面の下方に接続させた上で,複写機を使用してこれをコピーし,あたかも真正な丙医師作成の診断書の写しであるかのような外観を呈する文書を作成した。この場合,甲には,有印公文書偽造罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 45.0%結果正解解説判例は,真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押なつ部分を,虚偽の供託事実を記入した供託所用紙の下方に接続させてこれを電子複写機で複写する方法により作成された写真コピーの文書性が争われた事例において,「公文書偽造罪の客体となる文書は,これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく,たとえ原本の写であっても,原本と同一の意識内容を保有し,証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り,これに含まれる」とした上で,写真コピーは,原本と同様の機能と信用性を有し得ない場合を除き,公文書偽造罪の客体たり得るとしている(最判昭51.4.30 刑法百選Ⅱ〔第8版〕88事件)。また,同判決は,「原本の作成名義を不正に使用し,原本と異なる意識内容を作出して写真コピーを作成するがごときことは,もとより原本作成名義人の許容するところではなく,また,そもそも公文書の原本のない場合に,公務所または公務員作成名義を一定の意識内容とともに写真コピーの上に現出させ,あたかもその作成名義人が作成した公文書の原本の写真コピーであるかのような文書を作成することについては,右写真コピーに作成名義人と表示された者の許諾のあり得ないことは当然であって,行使の目的をもってするこのような写真コピーの作成は,その意味において,公務所または公務員の作成名義を冒用して,本来公務所または公務員の作るべき公文書を偽造したものにあたる」とし,さらに,写真コピーが有印であるか無印であるかについて,「作成名義人の印章,署名の有無についても,写真コピーの上に印章,署名が複写されている以上,これを写真コピーの保有する意識内容の場合と別異に解する理由はないから,原本作成名義人の印章,署名のある文書として公文書偽造罪の客体たりうるものと認めるのが相当である」としている。したがって,本記述では,甲には,有印公文書偽造罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(各)378頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)412~413頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,議員の当選の効力を定める手続において,選挙権のない者がした投票について,その投票が何人に対して行われたのかを取り調べることは,投票の秘密を侵害するものとはいえず,認められる。憲法この問題の模試受験生正解率 42.2%結果正解解説判例は,議員の当選の効力を決定する手続において,選挙権のない者の投票及び正当な選挙人でない者が選挙人の名で行ったいわゆる代理投票が何人に対して行われたのかを調べることが秘密選挙との関係で許されるかが争われた事例において,「選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても,その投票が何人に対しなされたかは,議員の当選の効力を定める手続において,取り調べてはならない」としている(最判昭25.11.9 憲法百選Ⅱ〔第7版〕159事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,AがBに300万円を貸すが,Aの気が向いたらBに請求し,請求を受けるとBは返済しなければならないという契約は無効である。民法この問題の模試受験生正解率 74.7%結果正解解説停止条件付法律行為は,その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,無効とされる(民法134条)。同条は,債権者の意思のみに係る条件には適用はない。本記述の契約は,条件が債権者たるAの意思のみに係るので,同条の適用はなく,有効である。よって,本記述は誤りである。
なお,解除条件付法律行為においては,条件が債権者の意思のみに係る場合はもちろん,債務者の意思のみに係る場合も,当該法律行為は有効であると解されている。参考四宮・能見(総則)401~402頁。
リーガルクエスト(総則)267頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,わいせつの目的をもって未成年者を誘拐した場合,未成年者誘拐罪は成立せず,わいせつ目的誘拐罪のみが成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 56.7%結果正解解説判例は,刑法225条所定の目的をもって未成年者を誘拐したときは,同条の罪のみが成立するとしている(大判明44.12.8)。よって,本記述は正しい。参考山口(各)94頁。
条解刑法208頁,680頁。
大コメ(刑法・第3版)⑾539頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても,未決拘禁者は,刑事施設という営造物を利用する関係において,特別の法律上の原因に基づく,一般の統治関係とは異なる特別権力関係に属し,国家は未決拘禁者を包括的に支配することができるため,未決拘禁者について喫煙の自由を一般に認めないのはやむを得ない措置というべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 55.5%結果正解解説判例は,刑事施設の被収容者の喫煙を禁止した旧監獄法施行規則の合憲性が争われた事例において,「未決勾留は,刑事訴訟法に基づき,逃走または罪証隠滅の防止を目的として,被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ,監獄内においては,多数の被拘禁者を収容し,これを集団として管理するにあたり,その秩序を維持し,正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには,被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく,右の目的に照らし,必要な限度において,被拘禁者のその他の自由に対し,合理的制限を加えることもやむをえないところである」とした上で,未決拘禁者の喫煙の自由を認めることは,通謀とそれに伴う罪証隠滅のおそれ及び火災発生による被拘禁者の逃走のおそれを生じさせること,煙草が嗜好品にすぎず,喫煙の禁止が人体に直接障害を与えるものではないことからすれば,喫煙の自由は憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても,あらゆる時,所において保障されなければならないものではないこと等を総合考察すると,「喫煙禁止という程度の自由の制限は,必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり,(旧)監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえない」としている(最大判昭45.9.16 憲法百選Ⅰ〔第7版〕A4事件)。したがって,同判決は,在監関係には特別権力関係が成立し,特別権力関係の下では,国家が未決拘禁者を包括的に支配することができるため,未決拘禁者の喫煙を禁止することも許されると判断しているわけではない。よって,本記述は誤りである。
-
民法債務者の交替による更改は,債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができるが,更改前の債務者が承諾をしなければその効力を生じない。民法この問題の模試受験生正解率 35.0%結果正解解説債務者の交替による更改は,債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができ,この場合において,更改は,債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に,その効力を生ずる(民法514条1項)。したがって,債権者と更改後に債務者となる者は,更改前の債務者の意思に反しても,債務者の交替による更改をすることができるのであって,その承諾は要しない。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ119~120頁。
潮見(新債権総論Ⅱ)334~335頁。
中田(債総)493頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,秘密漏示罪の「秘密」にいわゆる公知の事実は含まれない。刑法この問題の模試受験生正解率 90.3%結果正解解説秘密漏示罪(刑法134条)における「秘密」は,少数者にしか知られていない事実で,他人に知られることが本人の不利益となるものである。いわゆる公知の事実は秘密たり得ない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)119頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)97頁。
条解刑法417頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,憲法第81条の規定は,最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であって,下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨ではなく,下級裁判所も違憲審査権を行使し得る。憲法この問題の模試受験生正解率 91.4%結果正解解説判例は,「憲法は国の最高法規であってその条規に反する法律命令等はその効力を有せず,裁判官は憲法及び法律に拘束せられ,また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定するところである」から,「裁判官が,具体的訴訟事件に法令を適用して裁判するに当り,その法令が憲法に適合するか否かを判断することは,憲法によって裁判官に課せられた職務と職権であって,このことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問わない。憲法81条は,最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であって,下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨をもっているものではない」としている(最大判昭25.2.1 憲法百選Ⅱ〔第4版〕200事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)396頁。
佐藤幸(日本国憲法論)675頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)277頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,Aの所有する甲土地にAのBに対する債務を担保するために抵当権が設定され,その旨の登記がされていたが,Cの申請によりその登記が不法に抹消された場合であっても,抵当権の対抗力は失われない。民法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説判例は,有効になされた抵当権設定登記が第三者の申請によって不法に抹消された事例において,「登記は物権の対抗力発生の要件であって,この対抗力は法律上消滅事由の発生しないかぎり消滅するものではないと解すべきである」から,「抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には,抵当権者は対抗力を喪失するものでない」としている(最判昭36.6.16)。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)122頁。
リーガルクエスト(物権)85頁。
論点体系判例民法(2)60~61頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,客を集めて有料でわいせつな映画を観覧させて利益を得る目的で,自宅付近の人通りの多い路上で,通行人に声を掛け,これに応じた5名の客に対し,外部との交通を厳重に遮断した自宅の一室においてわいせつな映画を観覧させて利益を得た。この場合,甲には,わいせつ物公然陳列罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 54.7%結果正解解説わいせつ物公然陳列罪(刑法175条1項前段)の「公然と」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいう。判例は,わいせつな映画を上映した部屋が,外部との交通が遮断されていて,観客も5名程度に限られていても,その5名が不特定多数人を勧誘して集められた者であれば,結果としてわいせつな映画を不特定の者に観覧可能な状態にしたといえるとした原審の判断を是認している(最決昭33.9.5)。したがって,甲には,わいせつ物公然陳列罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)512頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)455頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,憲法第32条は,国民が憲法又は法律によって定められた裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障するのみならず,訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利についても保障するものである。憲法この問題の模試受験生正解率 50.5%結果正解解説判例は,管轄違いの裁判所によって言い渡された判決が原審によって是認されたため,被告人等が憲法32条の保障する正当な裁判所で裁判を受ける権利を侵害されたと主張した事例において,「憲法第32条は,何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれないと規定しているが,同条の趣旨は凡て国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し,裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障したものであって,訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない」としている(最大判昭24.3.23 憲法百選Ⅱ〔第4版〕131事件)。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅰ)550頁。
新基本法コメ(憲法)262頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,法人は,受遺者となることができる。民法この問題の模試受験生正解率 84.2%結果正解解説夫婦,親子,兄弟姉妹といった身分を前提とする相続については,法人に認めることはできないが,法人が遺贈を受けることは可能であると解されている。よって,本記述は正しい。参考平野(総則)79頁。
新注釈民法(1)729頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,自己が所有する不動産について,Aを権利者とする抵当権を設定したが,その抵当権設定登記が完了する前に,同不動産について,Bを権利者とする抵当権を設定し,その抵当権設定登記を完了した。この場合,甲には,横領罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 35.2%結果正解解説横領罪(刑法252条1項)は,「自己の占有する他人の物」を客体として,それを「横領した」場合に成立する。本記述において,甲は,当該不動産の所有者であって,他人の物の占有者ではないから,同罪が成立することはない。したがって,甲には,横領罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。
なお,判例は,本記述と同様の事例において,本来2番抵当権者となるべき者に1番抵当権を設定してその登記をした行為は,本来1番抵当権者となるべき者に対する背任罪(同247条)を構成するとしている(最判昭31.12.7 刑法百選Ⅱ〔第8版〕70事件)。参考西田(各)219頁,256頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)280頁,324頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,公職選挙における立候補の自由は,憲法第15条第1項の保障する重要な基本的人権の一つであるから,労働組合が,公職選挙における統一候補を決定し,組合を挙げて,その選挙運動を推進している場合であっても,組合の方針に反して立候補をしようとしている組合員に対し,立候補を思いとどまるよう,勧告又は説得することは許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 58.1%結果正解解説判例は,労働組合が市議会議員選挙に向けて統一候補を決定したところ,その決定に反して当該選挙に立候補した組合員を,当該労働組合の執行部役員が統制違反者として権利停止処分にしたことなどが公職選挙法違反に当たるとして起訴された事例において,「憲法28条による労働者の団結権保障の効果として,労働組合は,その目的を達成するために必要であり,かつ,合理的な範囲内において,その組合員に対する統制権を有」するが,この「労働組合が行使し得べき組合員に対する統制権には,当然,一定の限界が存するものといわなければならない。殊に,公職選挙における立候補の自由は,憲法15条1項の趣旨に照らし,基本的人権の一つとして,憲法の保障する重要な権利であるから,これに対する制約は,特に慎重でなければならず,組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であっても,その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して,その許否を決すべきであ」るとした上で,「統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し,組合が所期の目的を達成するために,立候補を思いとどまるよう,勧告または説得をすることは,組合としても,当然なし得るところである。しかし,当該組合員に対し,勧告または説得の域を超え,立候補を取りやめることを要求し,これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは,組合の統制権の限界を超えるものとして,違法といわなければならない」としている(最大判昭43.12.4 三井美唄労組事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕144事件)。したがって,労働組合は,組合の方針に反して立候補をしようとしている組合員に対し,立候補を思いとどまるよう,勧告又は説得することは許される。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,下請会社の労働者が,元請会社の作業現場で事故に遭った場合,元請会社と下請会社の労働者との間には直接の契約関係がない以上,元請会社が当該事故について,債務不履行責任を負うことはない。民法この問題の模試受験生正解率 60.8%結果正解解説元請会社の労働者が,事故に遭った場合,元請会社が安全配慮義務違反による債務不履行責任を負う。これに対して,下請会社の労働者が,元請会社の作業現場で事故に遭った場合には,元請会社と下請会社の労働者との間には契約関係がないため,契約の効果として給付義務たる安全配慮義務が導かれるのであれば,債務不履行責任は認められないことになる。しかし,判例は,下請企業に雇用された社外工として元請企業の経営する造船所において勤務してきた者に対する元請企業の安全配慮義務の有無が争われた事例において,下請企業の労働者が元請企業の造船所で労務の提供をするに当たっては,元請企業の管理する設備,工具等を用い,事実上元請企業の指揮,監督を受けて稼働し,その作業内容も元請企業の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり,このような事実関係の下においては,元請企業は,「下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので,信義則上,右労働者に対し安全配慮義務を負う」としている(最判平3.4.11 民法百選Ⅱ〔第4版〕4事件)。したがって,元請会社と下請会社の労働者との間には直接の契約関係がない場合であっても,元請会社が事故について,債務不履行責任を負うことがある。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ152頁。
中田(債総)138~139頁。
平野(債総)105頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Vを眠らせてVの財布から現金を抜き取るつもりで,コーヒ-の入ったコップに一時的に意識喪失を生じさせるのに十分な量の睡眠薬を入れて,Vに飲むようすすめたが,Vは,これを飲まなかった。この場合,甲には昏酔強盗罪の実行の着手が認められる。刑法この問題の模試受験生正解率 64.6%結果正解解説昏酔強盗罪(刑法239条)における「昏酔させる」とは,一時的又は継続的に相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の障害を生じさせて,財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることをいう。そして,財物を盗取する目的で相手方を昏酔させる行為を開始した時点で実行の着手が認められる。本記述では,甲は,Vを眠らせてVの財布から現金を抜き取るつもりで,コーヒ-の入ったコップに一時的に意識喪失を生じさせるのに十分な量の睡眠薬を入れて,Vに飲むようすすめており,その時点で昏酔強盗罪の実行の着手が認められる。よって,本記述は正しい。参考条解刑法768~769頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法大日本帝国憲法には,平等原則に関する一般的な定めはなく,ただ公務就任資格に関する平等の規定が置かれているにすぎなかった。憲法この問題の模試受験生正解率 32.9%結果正解解説大日本帝国憲法は,平等原則に関する一般的な規定は置かず,公務就任資格に関する個別の規定しか置いていなかった(同19条)。他方,日本国憲法では,同14条1項により,平等原則に関する一般的な規定を置いている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)130~131頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)281頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,賭博によって生じた債務の履行のために振り出された小切手の支払に関する和解は,無効である。民法この問題の模試受験生正解率 86.3%結果正解解説判例は,賭博によって生じた債務の履行のために交付された小切手の支払について和解がされた事例において,賭博に勝った者が賭博に負けた者に対して小切手金の支払を求めることは,公序良俗に違反するものとして許されないというべきであり,その支払についてされた和解上の金銭支払の約束も,実質上,その金額の限度で賭博に勝った者をして賭博による金銭給付を得させることを目的とするものであることが明らかであるから,同じく,公序良俗に違反するものとして,無効とされなければならないとしている(最判昭46.4.9 手形小切手百選〔第7版〕88事件)。よって,本記述は正しい。参考潮見(新契約各論Ⅱ)478頁。
中田(契約)601頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,他人の事務処理の用に供する権利義務に関する電磁的記録を不正に作った場合,目的のいかんにかかわらず,電磁的記録不正作出罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 69.1%結果正解解説人の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合,電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)が成立する。したがって,上記の目的がない場合には同罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)404頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)411頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法内閣は,行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負うが,この連帯責任は,個々の国務大臣の責任を否定するものではないから,衆議院において,国務大臣に対する不信任決議が可決された場合には,当該国務大臣は辞職すべき法的義務を負う。憲法この問題の模試受験生正解率 70.2%結果正解解説内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う(憲法66条3項)。内閣が内閣総理大臣の下に一体となって政治を行う原則から,内閣が負う責任も一体として負うこととされているが,国務大臣の単独責任を否定する趣旨ではないとされている。そのため,個々の国務大臣が,その所管事項に関して違法又は不当な行為をした場合などに,国会が当該国務大臣の責任を問うことは,憲法上否定されない。もっとも,国務大臣に対する衆議院の不信任決議については憲法に規定がないため,衆議院において当該国務大臣に対する不信任決議が可決されたとしても,法的効果は生じない。したがって,衆議院において不信任決議が可決されても,当該国務大臣は辞職すべき法的義務を負わない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)339~340頁。
佐藤幸(日本国憲法論)549~550頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)280頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,養子が尊属又は年長者であることを理由とする養子縁組の取消しは,縁組の当事者又はその親族から,いつでも家庭裁判所に請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 43.9%結果正解解説養子が尊属又は年長者であることを理由とする養子縁組の取消しについては,取消権の行使期間に制限がないと解されている(民法805条参照,大連判大12.7.7 家族法百選〔初版〕50事件)。これは,同条による取消しが公益的見地から規定されているためである。よって,本記述は正しい。参考新基本法コメ(親族)181頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,緊急避難は,避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に限り成立し,前者と後者が同等の場合には成立し得ない。刑法この問題の模試受験生正解率 63.3%結果正解解説緊急避難の要件である「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」(刑法37条1項本文)とは,避難行為により避けようとした害,すなわち保全法益が,避難行為から生じた害,すなわち侵害法益と同等か,又は侵害法益よりも大きい場合をいう。緊急避難の本質が,自己に降り掛かった危難を避けるため,その危難の発生とは無関係の他人の犠牲の下に避難行為を行う点にあるためである。したがって,保全法益と侵害法益とが同等の場合にも緊急避難は成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(総)155~156頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)211頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法付随的違憲審査制は,伝統的な司法の観念に立脚するものであり,個人の権利保護を第一の目的とする私権保障型の憲法保障制度であるから,事件・争訟として適切に裁判所に提起されている場合,その当事者は,特定の第三者の憲法上の権利を主張することは一切許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 91.4%結果正解解説付随的違憲審査制は,伝統的な司法の観念に立脚するものであり,個人の権利保護を第一の目的とする(私権保障型の憲法保障制度)。そのため,事件・争訟の当事者が特定の第三者の憲法上の権利を主張することは,原則として許されない。もっとも,違憲の主張をする者の利益の程度,援用される憲法上の権利の性格,違憲の主張をする者と第三者の関係,第三者が別の訴訟で自己の権利侵害につき違憲の主張をすることの可能性等の要素を考慮した上で,その主張を当事者にさせることが適切な状況があり,またそのことが第三者に実質的な不利益を与えない限り,その主張を認めてもよいとする等,これを認める見解が一般的である。判例も,憲法81条はこの付随的違憲審査制を規定するものであり(最大判昭27.10.8 警察予備隊違憲訴訟 憲法百選Ⅱ〔第7版〕187事件),当初,「他人の権利に容喙干渉」(最大判昭35.10.19)することは許されないとして,事件・争訟の当事者が特定の第三者の憲法上の権利を主張することを認めなかったが,その後,これを認めている(最大判昭37.11.28 第三者所有物没収事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕107事件)。したがって,付随的違憲審査制から直ちに,事件・争訟の当事者が,特定の第三者の憲法上の権利を主張することが一切許されないということにはならない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)392~393頁。
佐藤幸(日本国憲法論)682~684頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)298~301頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)322~326頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,建物が滅失した後,その跡地に同様の建物が新築された場合において,旧建物の既存の登記について表示の変更登記をすることにより,登記記録の表題部が新築建物の構造・坪数と合致するように変更されたときは,旧建物の既存の登記は,新建物の登記として有効となる。民法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説判例は,「建物が滅失した後,その跡地に同様の建物が新築された場合には,旧建物の登記簿は滅失登記により閉鎖され,新建物についてその所有者から新たな所有権保存登記がなさるべきものであって,旧建物の既存の登記を新建物の右保存登記に流用することは許されず,かかる流用された登記は,新建物の登記としては無効」であり,流用時に本記述のように変更がなされても,登記としての効力は認められないとしている(最判昭40.5.4 民法百選Ⅰ〔第4版〕84事件)。その理由として,同判決は,「旧建物が滅失した以上,その後の登記は真実に符合しないだけでなく,新建物についてその後新たな保存登記がなされて,1個の不動産に二重の登記が存在するに至るとか,その他登記簿上の権利関係の錯雑・不明確をきたす等不動産登記の公示性をみだすおそれがあり,制度の本質に反する」ことを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)124頁。
松井(物権)121頁。
リーガルクエスト(物権)86頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Aからパソコンを借りて保管していたが,同パソコンを売却してその代金を自己の借金の返済に充てるつもりで,無断で,同パソコンの買取りをBに持ち掛けたが,Bはいまだ買受けの意思表示をしていなかった。この場合,甲には,横領罪は成立する。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,条例中に罰則を設けるには法律の授権が必要であるが,条例は,行政府の命令と異なり,地方公共団体の議会によって制定される民主的立法であり実質的に法律に準ずるもので,条例への罰則の委任は一般的・包括的委任で足りる。憲法この問題の模試受験生正解率 56.3%結果正解解説判例は,罰則を定める条例によって処罰された者が,当該条例は憲法31条に違反するとして争った事例において,「条例は,法律以下の法令といっても,……公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にし,むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから,条例によって刑罰を定める場合には,法律の授権が相当な程度に具体的であり,限定されておればたりると解するのが正当である」としている(最大判昭37.5.30 憲法百選Ⅱ〔第7版〕208事件)。したがって,条例への罰則の委任は,一般的・包括的なものでは足りない。よって,本記述は誤りである。
-
民法債権者の交替による更改は,更改前の債権者,更改後に債権者となる者との二者間の契約によってすることができる。民法この問題の模試受験生正解率 35.0%結果正解解説債権者の交替による更改は,債権の譲渡人と譲受人間の契約によってする債権譲渡と異なり,更改前の債権者,更改後に債権者となる者及び債務者の三面契約によってする(民法515条1項)。いずれの者の意思をも無視することができないことによる。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ120頁。
潮見(新債権総論Ⅱ)335頁。
中田(債総)493頁。
新・コンメ民法(財産法)869頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,A社の炭坑内にある同社所有の工業用掘削機械を自己の所有物であるとしてリサイクル業者Bに売却し,Bから転売を受けた情を知らない乙をして同機械を炭坑から搬出させた。この場合,甲には,窃盗罪の間接正犯が成立する。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,憲法第29条の規定に照らせば,法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し,特段の補償を行わないものとしても,それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り,これをもって違憲ということはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 69.6%結果正解解説判例は,国有農地等の売払に関する特別措置法によって,その制定前に農地の売払の申込みをしていた旧所有者に対する売却の価格を買収対価相当額から時価の7割に変更したことが,憲法29条に反しないかが争われた事例において,「法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても,それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り,これをもって違憲の立法ということができないことは明らかである。そして,右の変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは,いったん定められた法律に基づく財産権の性質,その内容を変更する程度,及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し,その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって,判断すべきである」としている(最大判昭53.7.12 憲法百選Ⅰ〔第7版〕99事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法甲土地を所有していたAが死亡し,Aには法定相続人として妻B,子C及びDがいるが,いまだ遺産分割はされていない。この場合に関して判例の趣旨に照らした場合,Aが遺産分割の方法の指定として甲土地をDに相続させる旨の遺言をしていた場合において,DがAの死亡以前に死亡したときであっても,AがそのときにはDの代襲者Eに甲土地を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情があると認められるときには,その遺言は効力を生じる。民法この問題の模試受験生正解率 52.1%結果正解解説判例は,「遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し,当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言」は,「当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない」としている(最判平23.2.22 平23重判民法14事件)。したがって,本記述においては,DがAの死亡以前に死亡したときにはDの代襲者Eに相続させる旨の意思をAが有していたと認められるから,その遺言は効力を生じる。よって,本記述は正しい。参考窪田(家族法)469頁。
潮見(詳解相続法)478~479頁。
リーガルクエスト(親族・相続)407~408頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,裁判所より,医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師が,その過程で知り得た人の秘密を漏示しても,その秘密は,医師の業務上知った秘密ではなく,鑑定人の業務上知った秘密であるから,秘密漏示罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 90.3%結果正解解説判例は,「医師が,医師としての知識,経験に基づく,診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には,その鑑定の実施は,医師がその業務として行うものといえるから,医師が当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当すると解するのが相当である」としている(最決平24.2.13 平24重判刑法6事件)。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)118~119頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)96~97頁。
条解刑法418頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,憲法第14条第1項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには,合憲性の推定は排除され,裁判所は厳格な基準によってその差別が合理的であるかどうかを審理すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 32.9%結果正解解説判例は,憲法14条1項後段列挙事由(人種,信条,性別,社会的身分又は門地)は例示的なものと解しており,当該事由に本記述のような特段の効果を認めていない(最大判昭25.10.11,最大判昭39.5.27等)。よって,本記述は誤りである。
なお,本記述は,最大判昭60.3.27(サラリーマン税金訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕31事件)の伊藤正己裁判官の補足意見である。参考芦部(憲法)135頁。
佐藤幸(日本国憲法論)225~226頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)286~287頁。
渋谷(憲法)202~203頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,A及びBは,Aを養親,Bを養子とする養子縁組の届出をしたが,Aは養子縁組を他の目的のために利用する意思であって,真にBと養親子関係の設定を欲する意思を有していなかった場合,BがAの真意を過失なく知らなかったとしても,AB間の養子縁組は無効である。民法この問題の模試受験生正解率 65.4%結果正解解説「当事者間に縁組をする意思がないとき」は,養子縁組は無効である(民法802条1号)。判例は,同号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは,当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであるから,たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても,それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたにすぎず,真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかった場合においては,養子縁組は効力を生じないとした上で,この無効は絶対的なものであって,同93条1項ただし書の適用を待って初めて無効となるものではないとしている(最判昭23.12.23 家族法百選〔第2版〕59事件)。よって,本記述は正しい。参考四宮・能見(民法総則)229頁。
論点体系判例民法⑴235頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,警察官乙から現行犯逮捕の現場で覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際,乙の面前で同注射器を足で踏み付けて壊した。この場合,甲には,公務執行妨害罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説公務執行妨害罪(刑法95条1項)における「暴行」とは,不法な有形力の行使をいい,直接に公務員の身体に向けられたものである必要はなく,職務執行を妨害するに足りる程度の暴行といえる限り,間接的に公務員に向けられたもの(間接暴行)で足りる(最判昭37.1.23 続刑法百選23事件)。判例は,司法巡査が現行犯逮捕の現場で差し押さえて整理のために同所に置いた覚せい剤入りのアンプルを,被告人が足で踏んで損壊した事例において,司法巡査の職務の執行中にその執行を妨害するに足りる暴行を加えたものであり,その暴行は間接的に司法巡査に対するものというべきであるとして本罪の成立を認めている(最決昭34.8.27)。したがって,甲には公務執行妨害罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)451頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)490~491頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,受刑者が国会議員あての請願書の内容についての取材・調査・報道を求める旨を記載した手紙を新聞社に送付しようとする場合,刑事施設の長がこれを制限し得るのは,具体的事情の下でそれを許可することにより刑事施設内の規律及び秩序の維持が害される明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られる。憲法この問題の模試受験生正解率 55.5%結果正解解説判例は,受刑者が国会議員あての請願書の内容についての取材・調査・報道を求める旨を記載した新聞社あての手紙の発信許可を刑事施設の長に求めたところ,当該刑事施設の長がこれを不許可としたことから,当該受刑者がそれにより精神的苦痛を被ったとして,国に対し国賠法1条1項に基づき慰謝料を請求した事例において,「表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨,目的にかんがみると,受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は,受刑者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該信書の内容その他の具体的事情の下で,これを許すことにより,監獄内の規律及び秩序の維持,受刑者の身柄の確保,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って,これを制限することが許される」としている(最判平18.3.23)。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)110頁。
佐藤幸(日本国憲法論)179頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)49頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,和解契約は当事者が互いに譲歩することを成立要件とするから,当事者ではなく第三者が対価を給付することを和解契約の内容とすることはできない。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙から,Vの殺害に用いるための猛毒の青酸ソーダを入手するよう依頼されてこれを承諾し,致死量の青酸ソーダを入手してこれを乙に渡した。しかし,乙は,この青酸ソーダを使用せず,別途調達した睡眠薬をVに服用させた上,Vを絞殺した。この場合,甲には,殺人予備罪の共同正犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 61.0%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,甲に殺人予備罪の共同正犯(刑法201条,60条)の成立を認めた原審の判断を是認している(最決昭37.11.8 刑法百選Ⅰ〔第8版〕80事件)。よって,本記述は正しい。参考西田(総)423頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)337頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争について,国際法上の用例を尊重し,国家の政策としての戦争,すなわち侵略戦争を意味すると解するとしても,同条全体により自衛戦争を含めた全ての戦争が放棄されているという結論を導くことはできる。憲法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争について,国際法上の用例を尊重し,「国家の政策としての戦争」,すなわち侵略戦争を意味するならば,同項で放棄されているのは侵略戦争ということになり,自衛戦争は放棄されていないことになる。もっとも,この見解に立っても,同条2項前段の「前項の目的を達するため」にいう「前項の目的」について,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すものと解釈し,同項で戦力の保持が無条件で禁止され,また,交戦権まで否認されていると解釈するならば,同条1項で留保された自衛戦争も事実上不可能となり,同条全体で自衛戦争を含めた全ての戦争が放棄されているという結論を導くことができる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)57~58頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)164~168頁。
芦部(憲法学Ⅰ)255~259頁。
辻村(憲法)68~70頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,占有者から動産を買い受けることによりその占有を取得した者は,即時取得を主張するために,当該動産について,取引の相手方が権利者であると信じたことについて自己に過失がなかったことを立証する必要がある。民法この問題の模試受験生正解率 72.0%結果正解解説判例は,民法192条にいう「過失がないとき」とは,「物の譲渡人である占有者が権利者たる外観を有しているため,その譲受人が譲渡人にこの外観に対応する権利があるものと誤信し,かつこのように信ずるについて過失のないことを意味するものであるが,およそ占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定される以上(民法188条),譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないものと推定され,占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しない」としている(最判昭41.6.9 昭41重判民法3事件)。したがって,本記述において,即時取得を主張する占有者は,自己の無過失について立証する必要はない。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)147頁。
松井(物権)142頁。
リーガルクエスト(物権)100頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,幇助行為が日本国外でなされた場合には,正犯が日本国内で実行行為をしたときでも,従犯として処罰することはできない。刑法この問題の模試受験生正解率 78.1%結果正解解説判例は,日本国外で幇助行為をした者であっても,正犯が日本国内で実行行為をした場合には,刑法1条1項の「日本国内において罪を犯した」者に当たるとしている(最決平6.12.9 平6重判刑法1事件)。したがって,幇助行為が日本国外でなされた場合であっても,正犯が日本国内で実行行為をしたときは,従犯として処罰することができる。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)417頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)462頁。
条解刑法259~260頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例は,内閣総理大臣は,閣議にかけて決定された方針が存在しない場合には,内閣の明示の意思に反しないとしても,行政各部に対し指導,助言等の指示を与える権限を有しないとしている。憲法この問題の模試受験生正解率 74.1%結果正解解説判例は,内閣総理大臣が当時の運輸大臣(現:国土交通大臣)に対して航空会社に特定の航空機の選定購入を勧奨するよう働きかけた行為が内閣総理大臣の職務権限に属するかが争われた事例において,「内閣総理大臣は,憲法上,行政権を行使する内閣の首長として(66条),国務大臣の任免権(68条),内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど,内閣を統率し,行政各部を統轄調整する地位にあるものである。そして,内閣法は,閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条),内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条),行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。このように,内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには,閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと,流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため,内閣総理大臣は,少なくとも,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有する」としている(最大判平7.2.22 ロッキード事件丸紅ルート 憲法百選Ⅱ〔第7版〕174事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法Aが所有する甲土地をBが不法に占有している場合に関して,判例の趣旨に照らすと,Aが第三者に甲土地を譲渡し,所有権移転登記をした場合,Aは,Bに対して所有権に基づいて甲土地の返還を請求することはできない。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,刑罰法規において,刑の種類も刑の分量も全く定めないことは罪刑法定主義に反するが,刑の種類のみを定めていれば,刑の分量を全く定めなくとも,罪刑法定主義に反しない。刑法この問題の模試受験生正解率 74.7%結果正解解説罪刑法定主義には,刑罰法規の適正性が含まれる。そして,その具体的内容の1つとして,絶対的不確定刑も禁止される。絶対的不確定刑とは,①「……した者は,刑に処する」というように,刑の種類と刑の分量をともに法定しない場合,及び②「……した者は,懲役に処する」というように刑の種類だけを定めて刑の分量を法定しない場合の法定刑をいう。よって,本記述は誤りである。参考井田(総)38~39頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)18頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第21条第2項前段の「検閲」の禁止は,表現の自由を保障するために定められているが,この検閲にも公共の福祉を理由とする例外が認められる場合がある。憲法この問題の模試受験生正解率 68.9%結果正解解説判例は,税関検査が憲法21条2項前段の「検閲」に当たるかどうか等が争われた事例において,「憲法21条2項前段は,「検閲は,これをしてはならない。」と規定する。憲法が,表現の自由につき,広くこれを保障する旨の一般的規定を同条1項に置きながら,別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは,検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ,これについては,公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法12条,13条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである」としている(最大判昭59.12.12 札幌税関検査訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕69事件)。したがって,同判決は,同21条2項前段の検閲の禁止は,公共の福祉を理由とする例外を許容しない,絶対的禁止と捉えている。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,引き渡された売買の目的物の品質が契約の内容に適合しない場合において,履行の追完の方法として目的物の修補と代替物の引渡しとが可能であるときは,買主は,売主に対し,どちらかを任意に選択して履行の追完を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 58.9%結果正解解説引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは,買主は,売主に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる(民法562条1項本文)。同項は,追完の方法の選択肢が複数存在する場合,そのうちいかなる方法を採るのかの選択権を第一次的に買主に委ねたものである。よって,本記述は正しい。
なお,売主は,買主に不相当な負担を課するものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(同項ただし書)。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)94頁。
中田(債総)318頁。
新・コンメ民法(財産法)961頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,拘禁中に逃走した者をその事情を知りつつこれを蔵匿した場合,犯人蔵匿罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.7%結果正解解説犯人蔵匿罪(刑法103条前段)の客体は,「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は「拘禁中に逃走した者」である。「拘禁中に逃走した者」とは,法令により拘禁中に逃走した者をいい,その範囲は,同99条の「法令により拘禁された者」と一致するものとされ,裁判の執行により拘禁された既決,未決の者や勾引状の執行を受けた者(同97条,98条)のほか,現行犯逮捕された者,緊急逮捕されて令状が発せられる前の者がこれに当たる。よって,本記述は正しい。参考西田(各)477頁,483頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)516頁,543頁。
条解刑法330頁,336頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法公の支配に属しない事業への,公金その他の公の財産の支出を禁止する,憲法第89条後段の規定の趣旨を,公費の濫用を防止することにあると解する立場は,「公の支配」の意義について,公権力が当該事業の運営,存立に影響を及ぼすことにより,当該事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正し得る途が確保されていれば足りるという見解と結び付く。憲法この問題の模試受験生正解率 63.9%結果正解解説憲法89条後段は,公金その他の公の財産は「公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。」と定めている。そして,この規定の趣旨に関しては,大別して①私的事業に対して公金支出を行う場合には,財政民主主義の観点から,公費の濫用を来さないように当該事業を監督すべきことを要求するものであるとする立場(公費濫用防止説)と,②私的事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止し,事業の自主性を確保するための規定と解する立場(自主性確保説)とがある。そのうち,①の立場は,公費が濫用されない程度に,事業についての監督が及んでいればよいと考えるから,「公の支配」に属するという意味を,「国又は地方公共団体の一定の監督が及んでいることをもって足りる」というように,緩やかに解している。具体的には,業務や会計の状況に関し報告を徴したり,予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権を持っていれば足りるとする。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)376~377頁。
佐藤幸(日本国憲法論)574~575頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)343~347頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,Aが家出をして行方不明になり,その生死が10年間明らかでなかったため,利害関係人の請求により,Aについて失踪宣告がされたが,その1年後に,Aの生存が明らかとなったので,失踪宣告が取り消された。この場合,失踪宣告によりAを単独相続したDは,Aの生存につき善意であったときは,当該相続によって得た財産を不当利得として返還する義務を負わない。民法この問題の模試受験生正解率 77.1%結果正解解説失踪宣告を受けた者が生存していることの証明があったときは,家庭裁判所は,本人又は利害関係人の請求により,失踪宣告を取り消さなければならない(民法32条1項前段)。取消しの結果,失踪宣告の効果として生じた身分上・財産上の変動はなかったものとされる。したがって,失踪宣告が取り消されると,失踪宣告を受けた者を被相続人とする相続は開始しなかったことになるから,この相続によって財産を得た者は,失踪者の生存について善意であったか悪意であったかにかかわらず,これを不当利得として返還しなければならない(同条2項本文)。よって,本記述は誤りである。
なお,同項ただし書は,返還の範囲について,特に善意・悪意を区別せず「現に利益を受けている限度」としているが,同項ただし書は善意者のみに適用があり,悪意者は,同704条の場合と同様,全部の利益に利息を付して返還しなければならないとする見解がある。参考佐久間(総則)31~33頁。
リーガルクエスト(総則)53~55頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,刑法第36条第1項における「自己又は他人の権利」は,個人的法益に限られる。刑法この問題の模試受験生正解率 81.3%結果正解解説刑法36条1項にいう「権利」には,個人的法益にとどまらず,国家的法益ないし社会的法益も含まれると解されている。判例も,「国家的,国民的,公共的法益についても正当防衛の許さるべき場合が存することを認むべきである」としている(最判昭24.8.18 刑法百選〔初版〕11事件)。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決は,国家的・公共的法益「のための正当防衛等は,国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容されるべきもの」としている。参考西田(総)166頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)185~186頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,法令の合憲性の審査に当たり,当該法令を制定する場合の基礎を形成し,かつその合理性を支える事実,いわゆる立法事実を検討することがあるが,立法事実はあくまで当該法令の制定時の事実が考慮されるのであって,当該法令の制定後の事実の変化は考慮されない。憲法この問題の模試受験生正解率 68.1%結果正解解説判例は,日本人の父と外国人の母との間に生まれた非嫡出子について,父からの認知だけでなく父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合のみ届出による日本国籍取得を認めるとする旧国籍法3条1項の合憲性が争われた事例において,日本国民である父の生後認知子が父母の婚姻による準正によって,我が国社会との密接な結び付きが生じ,国籍取得を認めるに足る状況が認められるために,準正を要件としたという立法目的自体には合理的な根拠があることを認めた上で,旧「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては,日本国民である父と日本国民でない母との間の子について,父母が法律上の婚姻をしたことをもって日本国民である父との家族生活を通じた我が国との密接な結び付きの存在を示すものとみることには相応の理由があったものとみられ,当時の諸外国における……国籍法制の傾向にかんがみても,同項の規定が認知に加えて準正を日本国籍取得の要件としたことには,……立法目的との間に一定の合理的関連性があったものということができる」として,同項の制定時の事実を考慮して,制定当時における立法目的と準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件とすることとの間に一定の合理的関連性を認めている(最大判平20.6.4 国籍法違憲判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕26事件)。もっとも,同判決は,「我が国を取り巻く国内的,国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると,準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件としておくことについて,……立法目的との間に合理的関連性を見いだすことがもはや難しくなっているというべきである」としている。つまり,同判決は,旧国籍法3条1項の制定後の事実の変化をも考慮している。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)303頁。
渋谷(憲法)710頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合,債務者が契約から生じた債務を履行期に履行しなかったため,債権者が相当の期間を定めて履行の催告をしたが,その期間内に履行がなかったため,解除権が発生した場合であっても,債権者は,契約を解除せずに債務者に対して履行に代わる損害賠償を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 57.0%結果正解解説債務の履行に代わる損害賠償の請求が認められる場合の一つとして,債務が契約によって生じたものである場合において,債務の不履行による契約の解除権が発生したとき(民法415条2項3号後段)がある。この場合,同541条,542条1項3号から5号までの規定により解除権が発生すれば,債権者は,解除をしなくても債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。よって,本記述は正しい。
なお,同542条1項1号,2号によっても解除権が発生するが,これらの場合には,同415条2項3号後段ではなく,同項1号,2号によって債務の履行に代わる損害賠償の請求が認められる。参考内田Ⅲ145~146頁。
潮見(プラクティス債総)131~132頁。
中田(債総)183頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,犯人の親族が,犯人を庇護する目的で,犯人との間に親族関係がない者を教唆して犯人を隠避させた場合,犯人隠避教唆罪が成立し,その刑は免除されない。刑法この問題の模試受験生正解率 74.7%結果正解解説罰金以上の刑に当たる罪を犯した者の親族が,犯人のために犯人蔵匿等罪(刑法103条)を犯したときは,適法行為の期待可能性が低く責任が減少することを考慮し,裁量的な刑の免除が認められているところ(同105条),判例は,犯人の親族が犯人を庇護する目的で他人を教唆して犯人を隠避させた場合には,犯人隠避教唆罪(同103条後段,61条1項)が成立するとしており(大判昭8.10.18),同105条の適用を否定している。よって,本記述は正しい。参考西田(各)491頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)531頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法1789年のフランス人権宣言第16条は,「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,すべて憲法を持つものではない」と規定していたが,これは「立憲的意味の憲法」の観念を典型的に表現したものと受け取られている。憲法この問題の模試受験生正解率 70.9%結果正解解説「立憲的意味の憲法」とは,権力を制限することにより自由を保障しようという考えを基本理念とする憲法をいう。そして,1789年のフランス人権宣言16条は,「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,すべて憲法を持つものではない」と規定していたところ,これは「立憲的意味の憲法」の観念を典型的に表現したものと受け取られている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)5頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)5~6頁。 -
民法Aが所有する甲土地をBが不法に占有している場合に関して,判例の趣旨に照らした場合,Bが,権原のない第三者との間で締結した使用貸借契約に基づいて20年以上にわたり甲土地の使用を継続している場合において,Aが,所有権に基づき,甲土地の返還を求めた場合,Bは,返還請求権の消滅時効を主張して甲土地の返還を拒むことができる。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,責任主義の観点から,結果的加重犯の成立には,基本となる犯罪についての故意のほか,重い結果についての過失を要する。刑法この問題の模試受験生正解率 66.7%結果正解解説結果的加重犯とは,基本となる犯罪から生じた結果を重視して,基本となる犯罪に対する刑よりも重い法定刑を規定した犯罪をいう。結果的加重犯の意義に関しては,重い結果について過失が必要か否かが問題となるところ,判例は,夫が妻に暴行を加え,その結果妻をショック死させた事例において,「傷害罪の成立には暴行と死亡との間に因果関係の存在を必要とするが,致死の結果についての予見を必要としない」としており(最判昭32.2.26 刑法百選Ⅰ〔第8版〕50事件),重い結果について過失がない場合にも結果的加重犯が成立するというのが判例の立場である。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義総)196~197頁。
条解刑法145頁,619頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,企業内においても,労働者の思想,信条は十分尊重されるべきであるから,企業秩序違反行為の調査をするために行われたことが明らかであったとしても,雇用者が労働者に対し,調査目的との関連性を明らかにしないまま,政党所属の有無を尋ねることや,特定の政党に所属していないことを書面にして交付するよう求めることは,強要にわたるものでなくても許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 58.8%結果正解解説判例は,企業の営業所の内部情報が特定政党の機関紙に記載されたことに関連して,当該営業所の所長Yが従業員Xに対し調査をした際,当該政党の党員かどうかを尋ねたこと,そして,これに対してそうではない旨の返答があったため,それを書面にするよう求めたことが,Xの思想・良心の自由を侵害するかどうかが争われた事例において,Yによる「話合いは企業秘密の漏えいという企業秩序違反行為の調査をするために行われたことが明らかであるから……本件話合いを持つに至ったことの必要性,合理性は,これを肯認することができる」とした上で,本件政党の機関紙の記事の取材源ではないかと疑われているXに対し,本件政党「との係わりの有無を尋ねることには,その必要性,合理性を肯認することができないわけではなく,また,本件質問の態様は,返答を強要するものではなかった」から,「本件質問は,社会的に許容し得る限界を超えてXの精神的自由を侵害した違法行為であるとはいえない」としている(最判昭63.2.5 憲法百選Ⅰ〔第7版〕35事件)。また,同判決は,本件政党の党員でないと返答したことについて書面交付を要求した行為についても,その要求が強要にわたるものではなく,「Xが本件書面交付の要求を拒否することによって不利益な取扱いを受ける虞のあることを示唆した」事実がないこと等から,本件書面交付の要求も,「社会的に許容し得る限界を超えてXの精神的自由を侵害した違法行為であるということはできない」としている。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らした場合,利息付きの消費貸借において,貸主は,借主が元本を受け取った日以後の利息を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 67.6%結果正解解説民法上,利息の支払は消費貸借の成立の要素とはされていないため(同587条,587条の2第1項),貸主は,特約がある場合に限り,借主に対し利息を請求することができる(同589条1項)。そして,利息は,元本使用の対価であるから,貸主は,借主に対し,借主が元本を使用できる状況に置かれた時,すなわち,借主が元本を受け取った日以後の利息を請求することができる(同条2項)。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)131頁。
中田(契約)365頁。
新基本法コメ(債権2)176頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,不作為犯は,結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでなければ,成立する余地はない。刑法この問題の模試受験生正解率 93.4%結果正解解説判例は,「シャクティ治療」と称する独自治療を唱導していた被告人が,その信奉者から重篤な患者である親族に対する「シャクティ治療」を依頼され,同患者を入院中の病院から運び出させた上,必要な医療措置を受けさせないまま放置した事例において,「被告人は,自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上,患者が運び込まれたホテルにおいて,被告人を信奉する患者の親族から,重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際,被告人は,患者の重篤な状態を認識し,これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから,直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである」とし(最決平17.7.4 刑法百選Ⅰ〔第8版〕6事件),先行行為,保護の引受け,排他的支配を根拠に,作為義務(直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務)があったとしており,法律上の規定から作為義務を導いてはいない。したがって,不作為犯は,結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合であっても,成立する余地がある。よって,本記述は誤りである。参考西田(総)128頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)86頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第9条第1項で放棄されている戦争とは侵略戦争であって,自衛戦争は放棄されていないとし,同条第2項前段の「前項の目的を達するため」を,侵略戦争放棄という同条第1項の目的を達するためとする見解によると,自衛のための戦力は保持できることになるが,この見解に対しては,自衛のための戦力と侵略のための戦力は実際上区別できないとの批判が当てはまる。憲法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説憲法9条1項で放棄されている戦争とは侵略戦争であって,自衛戦争は放棄されていないとし,同条2項前段の「前項の目的を達するため」の意味を,侵略戦争放棄という同条1項の目的を達するためとする立場に立つと,同条2項は,侵略のための戦力は保持せず(つまり,自衛のための戦力は保持できる。),また,交戦権の否認は交戦国が持つ諸権利は認めないとの意味にとどまることになる。この見解に対しては,憲法自体に内閣構成員の資格としての文民規定(同66条2項)以外に戦争・軍隊を前提とする他の規定がないこと,自衛のための戦力と侵略のための戦力を実際上区別できないことなどの批判がある。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)56~58頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)164~167頁。
渋谷(憲法)72~73頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,未分離の果実は,土地の定着物であり,土地と独立に所有権の対象とすることはできない。民法この問題の模試受験生正解率 59.1%結果正解解説未分離の果実は,本来,土地の定着物として(民法86条1項),土地又は樹木の一部とみるべきであるが,判例は,樹木又は土地とは別個独立して所有権の対象となり,明認方法によりその所有権を第三者に対抗することを認めている(大判大5.9.20 民法百選Ⅰ〔初版〕63事件,大判大9.5.5,大判昭13.9.28など))。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(総則)112~113頁。
新・コンメ民法(財産法)51頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙から商品を購入する際,偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として同通貨を交付し,商品を得た。この場合,甲には,偽造通貨行使罪が成立し,詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。刑法この問題の模試受験生正解率 41.5%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,詐欺罪(刑法246条1項)は,偽造通貨行使罪(同148条2項)に当然に吸収され,別罪を構成しないとしている(大判明43.6.30)。したがって,甲には,偽造通貨行使罪が成立し,詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。よって,本記述は正しい。参考西田(各)353頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)440頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,政党は,政治上の信条,意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって,内部的には,通常,自律的規範を有し,その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり,一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり,国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって,議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるということができる。憲法この問題の模試受験生正解率 63.1%結果正解解説判例は,政党が除名処分を受けた元党役員に対し,当該党役員に利用させてきた家屋の明渡しを求めた事例において,「政党は,政治上の信条,意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって,内部的には,通常,自律的規範を有し,その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり,一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり,国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって,議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在であるということができる」としている(最判昭63.12.20 共産党除名処分事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕183事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法Aが所有する甲土地をBが不法に占有している場合に関して,判例の趣旨に照らすと,Aが自己の債権者のために甲土地を譲渡担保に供した場合であっても,Aは,特段の事情のない限り,Bに対して甲土地の返還を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 84.7%結果正解解説判例は,譲渡担保契約による目的物件の所有権移転の効力は,債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるのであって,譲渡担保権設定者は,譲渡担保権者が目的物件の換価処分を完結するまでは,被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから,正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には,特段の事情のない限り,当該占有者に対してその返還を請求することができるとしている(最判昭57.9.28)。したがって,本記述において,Aは,特段の事情のない限り,Bに対して甲土地の返還を請求することができる。よって,本記述は正しい。参考松井(担物)191頁。
リーガルクエスト(物権)344頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,遺棄罪(刑法第217条)の客体は,「老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」と規定されているが,扶助を必要とする原因として挙げられている「老年,幼年,身体障害又は疾病」は,例示列挙である。刑法この問題の模試受験生正解率 55.6%結果正解解説遺棄罪(刑法217条)の客体は,「老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」であるところ,要扶助状態の原因として挙げられている「老年,幼年,身体障害又は疾病」は,制限列挙であるとされる。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)29頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)19~20頁。
新基本法コメ(刑法)468頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法泉佐野市民会館事件判決(最高裁判所平成7年3月7日第三小法廷判決,民集49巻3号687頁)に関して,この判決は,憲法第21条第1項が保障する集会の自由には,表現活動や集会に必要な場所の提供を公権力に請求し得る権利が当然に含まれるから,集会の用に供される施設が設けられている場合,当該施設の管理者がその利用を拒否し得るのは,利用の希望が競合する場合のほかは,施設をその集会のために利用させることによって,他の基本的人権が侵害され,公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるとした。憲法この問題の模試受験生正解率 42.8%結果正解解説本問の最高裁判所判決(最判平7.3.7 泉佐野市民会館事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕81事件)は,市民会館の使用許可の申請を,条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に該当するとして不許可にした処分の違憲性が争われた事例において,「地方自治法244条にいう普通地方公共団体の公の施設として,本件会館のように集会の用に供する施設が設けられている場合」,当該施設の管理者が,公共施設の管理の点から「利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは,利用の希望が競合する場合のほかは,施設をその集会のために利用させることによって,他の基本的人権が侵害され,公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる」としている。したがって,本記述の結論は正しい。もっとも,同判決は,公の施設について,「住民は,その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので,管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは,憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる」としているが,同21条1項が保障する集会の自由には,表現活動や集会に必要な場所の提供を公権力に請求し得る権利が当然に含まれるとはしていない。よって,本記述は誤りである。
-
民法AのBに対する意思表示に関して,AがBに対し,承諾の期間を定めて契約の申込みをし,Bがその期間内にAに対し承諾の通知を発したが,当該通知が期間経過後にAに到達した場合,Aがした申込みは,その効力を失う。民法この問題の模試受験生正解率 53.3%結果正解解説承諾の期間の定めのある契約の申込みをした者が,その期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込みは,その効力を失う(民法523条2項)。本記述において,Bの承諾の通知は,承諾の期間経過後にAに到達しているので,Aがした申込みはその効力を失う。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)23~24頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,右前方を歩行中の乙に自動車で接近し,運転席の窓から手を出して乙がひじに提げていたハンドバッグを奪い取ろうとして,そのさげひもを引っ張ったところ,乙がこれを離さなかったため,そのまま加速して自動車を走行させ,乙を同バッグもろとも引きずって転倒させて,同バッグを奪って逃走した。乙は引きずられたことにより,加療約1か月を要する傷害を負った。この場合,甲には,強盗致傷罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 64.3%結果正解解説強盗罪の「暴行又は脅迫」は,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要する。そして,いわゆるひったくりのように暴行が専ら財物を奪取する直接の手段として用いられている場合には,暴行が反抗の抑圧に向けられたものとはいえないから,通常は,「暴行」が認められず,窃盗罪が成立するにすぎない。もっとも,判例は,本記述と同様の事例において,「ハンドバックを離そうとしない女性を車もろとも引きずって転倒させたり,車体に接触させたり,また道路脇の電柱に衝突させて女性に暴行を加えてその反抗を抑圧し,その結果ハンドバックを奪取した」として強盗致傷罪(刑法240条前段)の成立を認めている(最決昭45.12.22 刑法百選Ⅱ〔第2版〕34事件)。したがって,甲には,強盗致傷罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(各)182~183頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)164~165頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第34条前段の弁護人依頼権は,単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく,被疑者に対し,弁護人を選任した上で,弁護人に相談し,その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障している。憲法この問題の模試受験生正解率 65.4%結果正解解説判例は,刑訴法39条3項の規定(接見指定)が憲法34条等に違反するかどうかが争われた事例において,「憲法34条前段は,「何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。」と定める。この弁護人に依頼する権利は,身体の拘束を受けている被疑者が,拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり,人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的とするものである。したがって,右規定は,単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく,被疑者に対し,弁護人を選任した上で,弁護人に相談し,その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障している」としている(最大判平11.3.24 憲法百選Ⅱ〔第7版〕120事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,責任能力のない未成年者の行為によって,第三者に傷害結果が生じた場合,当該行為について違法性がないときであっても,その未成年者の監督義務者は,民法第714条第1項に基づく監督義務者の責任を負うことがある。民法この問題の模試受験生正解率 73.6%結果正解解説判例は,責任能力のない未成年者の行為に違法性がない場合には,その未成年者の監督義務者は,監督義務者の責任(民法714条1項本文)を負わないとしている(最判昭37.2.27)。すなわち,同項の監督義務者の責任は,行為者本人が責任無能力であるがゆえに賠償責任を負わない場合に限り問題となるのであって,本人の行為が責任能力がないという理由以外の理由によって不法行為を構成しない場合には,問題となり得ない。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(事務管理・不当利得・不法行為)256頁。
論点体系判例民法(9)391頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,第三者供賄罪が成立するためには,賄賂として利益を供与された第三者において,供与された利益が賄賂であることの認識を有している必要はない。刑法この問題の模試受験生正解率 84.5%結果正解解説第三者供賄罪(刑法197条の2)が成立するためには,公務員の意思に基づいて賄賂が第三者に供与されていれば足り,第三者が,供与された利益が賄賂であることの認識を有している必要はない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)528頁。
リーガルクエスト(刑法各論)458頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは,我が国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力に限られず,我が国との安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の軍隊も,ここにいう戦力に該当し得る。憲法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説判例は,正当な理由がなく,米軍基地に侵入した者が,旧日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法2条違反で起訴された事例において,憲法9条2項「において戦力の不保持を規定したのは,わが国がいわゆる戦力を保持し,自らその主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためである……。従って……同条項がその保持を禁止した戦力とは,わが国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力をいうものであり,結局わが国自体の戦力を指し,外国の軍隊は,たとえそれがわが国に駐留するとしても,ここにいう戦力には該当しない」としている(最大判昭34.12.16 砂川事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕163事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,動産の所有者であって寄託者であるAが,その受寄者であるBに対して,以後第三者Cのために動産を占有することを命じたが,Bがこれを承諾しなかったときは,Cは,動産の占有権を取得することができない。民法この問題の模試受験生正解率 31.7%結果正解解説代理人によって占有をする場合において,本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ,その第三者がこれを承諾したときは,その第三者は,占有権を取得する(指図による占有移転 民法184条)。同条において,代理人の承諾は,占有移転の要件とされていない。したがって,本記述において,受寄者Bの承諾がなくても第三者Cは動産の占有権を取得し得る。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)132~133頁。
松井(物権)129頁。
リーガルクエスト(物権)93頁。
新基本法コメ(物権)50頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,重過失とは,注意義務違反の程度が著しく,かつ,それによって発生した構成要件的結果が重大なものをいう。刑法この問題の模試受験生正解率 66.7%結果正解解説重過失とは,通常の過失に比して,容易に結果の発生を予見することができ,かつ,容易に結果の発生を回避し得るのに,その注意義務を怠って結果を発生させた場合をいう。構成要件的結果が重大であることは,重過失が認められる要件ではない。よって,本記述は誤りである。参考刑法総論講義案159頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)131~132頁。
条解刑法153頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,大学の自治は,大学における学問の自由を保障するために認められるものであるから,大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるものであって,大学の施設及び学生の管理について認められるものではない。憲法この問題の模試受験生正解率 51.4%結果正解解説判例は,ある国立大学(現:国立大学法人)の公認学生団体である劇団が,大学の許可を得て一般公演(以下「本件集会」という。)を大学の教室で開催したところ,その観客の中に警察官が公安調査の目的で潜入していたことから,学生がその警察官に暴行を加えたとして,暴力行為等処罰二関スル法律違反で起訴された事例において,「大学における学問の自由を保障するために,伝統的に大学の自治が認められている。この自治は,とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ,大学の学長,教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また,大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ」るとしている(最大判昭38.5.22 ポポロ事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕86事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,当該賃借人が取得すべき転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。民法この問題の模試受験生正解率 59.4%結果正解解説判例は,「民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「債務者」には,原則として,抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれない」としている(最決平12.4.14 平12重判民法2事件)。その理由として,同決定は,「所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し,抵当不動産の賃借人は,このような責任を負担するものではなく,自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはない」ことなどを挙げている。もっとも,同決定は,「所有者の取得すべき賃料を減少させ,又は抵当権の行使を妨げるために,法人格を濫用し,又は賃貸借を仮装した上で,転貸借関係を作出したものであるなど,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には,その賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して抵当権に基づく物上代位権を行使することを許すべき」としている。したがって,抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,当該賃借人が取得すべき転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ503~504頁。
道垣内Ⅲ152頁。
松井(担物)43~44頁。 -
刑法死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合,その長期は30年となる。刑法この問題の模試受験生正解率 44.9%結果正解解説懲役と禁錮には無期及び有期があり,有期の懲役及び禁錮はそれぞれ1月以上20年以下とされるが(刑法12条1項,13条1項),死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合には,その長期は30年となる(同14条1項)。よって,本記述は正しい。参考新基本法コメ(刑法)34頁,36頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法前文が具体的な争訟における裁判所の判断につき直接の準拠となる規範としての性格(裁判規範性)を有するか否かについて,これを肯定する見解(肯定説)と否定する見解(否定説)がある。これらの見解に関して,憲法前文の法規範性を認める考え方は,肯定説及び否定説のいずれの見解とも矛盾しない。憲法この問題の模試受験生正解率 83.2%結果正解解説憲法前文の法規範性については,憲法前文が憲法典の内容の一部であることから,憲法本文の各条項と同じく,これを認める見解が一般的である。しかし,憲法前文の法規範性と裁判規範性は別個に考えられるものであり,憲法前文の法規範性から直ちに裁判規範性が認められることにはならない。したがって,憲法前文の法規範性を認める考え方は,裁判規範性についての肯定説はもとより,否定説とも矛盾しない。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)37~38頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)68~70頁。
芦部(憲法学Ⅰ)206~208頁。
新・コンメ憲法17頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合,当事者の一方が,その他方の債務の履行遅滞を理由として契約を解除するためには,自己の債務の履行の提供をした上で,相当の期間を定めて催告をした日から,解除権を行使する日まで履行の提供を継続する必要がある。民法この問題の模試受験生正解率 53.2%結果正解解説双務契約上の債務が同時履行の関係にある場合,同時履行の抗弁権(民法533条)を有している限り,債務者は履行遅滞にあるとはいえないから,債権者が履行遅滞を理由とする解除権を行使するためには自らの債務につき履行の提供をする必要がある。その際,相当の期間を定めて催告をした日から,解除権を行使する日まで,履行の提供を継続しなければならないのかが問題となるが,催告に当たって一度提供すれば足り,改めて提供しなくても解除することができると解されている。催告中も,履行されない契約からの解放を望む解除権者に履行の提供の継続を要求することは,過大な負担と考えられるからである。判例も,履行の提供の継続を不要としている(大判昭3.5.31)。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)152頁。
平野(債各Ⅰ)61~62頁。
我妻・有泉コメ1121頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,第三者供賄罪が成立するためには,賄賂として利益を供与された第三者において,供与された利益が賄賂であることの認識を有していることが必要である。刑法この問題の模試受験生正解率 92.1%結果正解解説第三者供賄罪(刑法197条の2)が成立するためには,公務員の意思に基づいて賄賂が第三者に供与されていれば足り,第三者が,供与される利益が賄賂であることの認識を有している必要はない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)625頁。
西田(各)528頁。
条解刑法588頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,麻薬の取扱いに関する事実の記帳義務を負う麻薬取扱者は,麻薬を取り扱うことを自ら申請して免許を得た者であり,麻薬取締関係法規による厳重な監査を受け,それによる命令に服することをあらかじめ承認しているものといえるから,正規の手続を経ていない麻薬の取扱いに関する事実についても記帳義務を負う。憲法この問題の模試受験生正解率 65.3%結果正解解説判例は,旧麻薬取締法14条1項(現:麻薬及び向精神薬取締法37条1項,50条の23参照)により記帳義務を負う麻薬取扱者が,正規の手続を経ていない麻薬の取扱いに関する事実の記帳義務まで負うのかが争われた事例において,同法が記帳義務を課しているのは,「麻薬取扱者による麻薬処理の実状を明確にしようとするにあるのであるから,いやしくも麻薬取扱者として麻薬を取扱った以上は,たとえその麻薬が正規の手続を経ていないものであっても,右帳簿記入の義務を免れ」ず,「麻薬取扱者たることを自ら申請して免許された者は,そのことによって当然麻薬取締法規による厳重な監査を受け,その命ずる一切の制限または義務に服することを受諾しているものというべきであ」り,「取締上の要請からいっても,かかる場合記帳の義務がないと解すべき理由は認められない」としている(最判昭29.7.16 憲法百選Ⅱ〔第7版〕118事件)。同判決は,いわば特権を受けるのと引換えに自己負罪拒否特権を事前に放棄したという考え方を採ったものといわれている。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,AがBに対して動産甲を売却したが,Bが甲の代金を支払わない場合において,その間に,Bが,甲をCに売却し,占有改定の方法によりこれを引き渡したため,Bが引き続き甲を占有しているときであっても,Aは,甲について動産売買の先取特権を行使することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 54.2%結果正解解説民法333条は,先取特権は,債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は,その動産について行使することはできないとしており,判例は,同条の引渡しには,占有改定も含まれるとしている(大判大6.7.26 民法百選Ⅰ〔初版〕83事件)。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ70~71頁。
内田Ⅲ679~680頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,正犯に中止犯が成立する場合には,教唆犯にも当然に中止犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 65.8%結果正解解説判例は,正犯者の中止行為の効果は共犯者に及ばないとしている(大判大2.11.18 刑法百選Ⅰ〔初版〕90事件)。すなわち,正犯に中止犯が成立する場合であっても,教唆犯(刑法61条1項)に当然に中止犯が成立するわけではない。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義総)469頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)282~283頁。
条解刑法255頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,県が公の立場で戦没者の慰霊を行うことを相当数の者が望んでいるならば,その希望に応えた県知事の玉串料等の奉納は,県と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えないものとして,憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」に当たらない。憲法この問題の模試受験生正解率 91.6%結果正解解説判例は,県知事が靖国神社及び県護国神社における恒例の宗教上の祭祀に際して,県の公金を用いて玉串料等を支出したことの合憲性が問題とされた事例において,「靖國神社及び護國神社に祭られている祭神の多くは第二次大戦の戦没者であって,その遺族を始めとする愛媛県民のうちの相当数の者が,県が公の立場において靖國神社等に祭られている戦没者の慰霊を行うことを望んでおり,そのうちには,必ずしも戦没者を祭神として信仰の対象としているからではなく,故人をしのぶ心情からそのように望んでいる者もいることは,これを肯認することができる。そのような希望にこたえるという側面においては,本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあることも否定できない。しかしながら,明治維新以降国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど……憲法制定の経緯に照らせば,たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても,そのことのゆえに,地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが,相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない」としている(最大判平9.4.2 愛媛県玉串料訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕44事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aが所有する甲土地を要役地,Bが所有する乙土地を承役地とする通行地役権が設定された後,Bが乙土地をCに売却した場合,売却の時に,乙土地がAによって継続的に通路として使用されていることがその物理的状況から客観的に明らかであるとしても,Cがそのことを認識していないときは,Aは,Cに対し,地役権設定登記なくして通行地役権を主張することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 90.0%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「譲受人は,通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても,特段の事情がない限り,地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない」としている(最判平10.2.13 民法百選Ⅰ〔第8版〕63事件)。その理由として,同判決は,第三者に登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合には,当該第三者は,登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者(民法177条)に当たらないとした上で,通行地役権の承役地の譲渡時に,承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,譲受人がそのことを認識又は認識可能であったときは,譲受人は,要役地の所有者が承役地について通行地役権等を有していることを容易に推認することができ,また,要役地の所有者に照会するなどして通行権の有無,内容を容易に調査することができるため,譲受人は,通行地役権の存在を知らないで承役地を譲り受けた場合であっても,何らかの通行権の負担があるものとしてこれを譲り受けたものとして,譲受人が地役権者に対して地役権設定登記の欠缺を主張することは,通常は信義に反することを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)83~84頁。
内田Ⅰ459~460頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,背任罪の主体である「他人のためにその事務を処理する者」には,独立の権限をもって単独の意思で事務を処理する者のみならず,事実上の補助者としてその事務の処理に当たる者も含まれる。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法「法の支配」の原理の内容としては,憲法の最高法規性の観念,権力によって侵されない個人の人権,法の内容・手続の公正を要求する適正手続,裁判所の役割に対する尊重などが重要であると考えられている。憲法この問題の模試受験生正解率 94.2%結果正解解説「法の支配」の原理とは,専断的な国家権力の支配を排斥し,権力を法で拘束することによって,国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理をいう。この原理の内容として重要なものは,①憲法の最高法規性の観念,②権力によって侵されない個人の人権,③法の内容・手続の公正を要求する適正手続,④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などである。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)13~14頁。
-
民法抵当権は目的である物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権が抵当目的物の価格を上回っている場合でも,物上保証人が目的物の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。民法この問題の模試受験生正解率 61.1%結果正解解説不可分性とは,担保物権者が,被担保債権全額の弁済を受けるまで,目的物の全部についてその権利を行使することができるという担保物権の性質をいい,民法に定める四つの担保物権全てに認められる(民法296条,305条,350条,372条)。したがって,抵当権においても,被担保債権全額の弁済を受けるまでは,抵当目的物の全部に対してその権利を行使することができるので,被担保債権が抵当目的物の価格を上回っている場合に,物上保証人が目的物の価格に相当する額を弁済しても,抵当権は消滅しない。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ9頁,234~235頁。
内田Ⅲ485頁,569頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,V女の顔面を拳で殴打するなどして,その反抗を抑圧してV女の金品を強取した直後に,V女を強いて性交し殺害しようと決意し,V女の首を絞めながら性交した。V女は,一時気を失ったが,死亡するには至らなかった。甲に強盗・強制性交等殺人未遂罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 46.8%結果正解解説平成29年法改正以前の旧刑法241条後段は,「よって……死亡させたとき」と規定されていたことから,同条は結果的加重犯である強盗強姦致死罪のみを定めており,殺意があっても強盗強姦殺人罪は成立しないと解されていた(大判昭10.5.13)。これに対して,現行の刑法241条3項は,「よって」という文言を用いない規定ぶりに改められ,殺意がある場合も含まれることが明らかにされた。同項に未遂犯処罰規定(同243条)が設けられているのも,強盗・強制性交等殺人罪が未遂に終わった場合を想定したものである。本記述では,甲は,強盗罪を犯した上で,さらに同一の機会に強制性交等罪を犯し,その行為として殺意をもってV女の首を絞めたが,V女は死亡するに至らなかったため,甲には強盗・強制性交等殺人未遂罪(同条,241条3項)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)203~204頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)230~232頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,条例は,住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的立法であり,実質的には法律に準じるものであるから,法律の授権がなくても条例に罰則を定めることができる。憲法この問題の模試受験生正解率 52.8%結果正解解説判例は,条例による罰則制定の可否が争われた事例において,「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく,法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで,このことは憲法73条6号但書によっても明らかである」としている。もっとも,法律の授権が不特定な白紙委任的なものであってはならないとした上で,「条例は……公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にし,むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから,条例によって刑罰を定める場合には,法律の授権が相当な程度に具体的であり,限定されておればたりる」としている(最大判昭37.5.30 憲法百選Ⅱ〔第7版〕208事件)。したがって,同判決は,条例に罰則を定める場合には,法律による授権が必要であるという前提に立っている。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aが,Bのためにその所有する甲土地に抵当権を設定した後に甲土地の上に乙建物を建築した場合,Bの抵当権が実行されたときは,甲土地とともに乙建物も競売することができる。民法この問題の模試受験生正解率 54.7%結果正解解説民法389条1項本文は,抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは,抵当権者は,土地とともにその建物を競売することができるとしている。更地に抵当権が設定された後,建物が築造された場合,法定地上権は成立しないから(同388条参照),建物所有者は,土地についての抵当権が実行されると,その買受人である新たな土地所有者から建物収去土地明渡請求を受け,それに応じざるを得ない。しかし,この結果は建物の取壊しという社会経済的損失を生じさせ妥当ではない。そこで,そのような事態を回避するために,土地抵当権者に,土地と建物の一括競売をする権利を認めたのである。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ526~528頁。
道垣内Ⅲ160~161頁。
松井(担物)88~89頁。
新基本法コメ(物権)294~295頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,罰則を定めた特別法上の法条に,「過失により」との明文の規定がない場合であっても,過失犯として処罰されることがある。刑法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説過失犯は,「法律に特別の規定がある場合」に限り処罰される(刑法38条1項ただし書)。もっとも,判例は,罰則を定めた特別法上の法条に,「過失により」との明文がなくても,過失犯を処罰する趣旨が読み取れる場合には,過失犯として処罰することを認めている(最決昭57.4.2 刑法百選Ⅰ〔第6版〕49事件参照)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)242頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法独立行政委員会は委員の任命や予算編成の上で内閣のコントロール下にあるから憲法第65条に違反しないとする見解に対しては,裁判所も独立行政委員会と同様に位置付けることになってしまうという批判が可能である。憲法この問題の模試受験生正解率 65.8%結果正解解説独立行政委員会は委員の任命や予算編成の上で内閣のコントロール下にあるから憲法65条に違反しないとする見解は,行政権を行使する組織の全てが内閣の下にあることが要求されることを前提としている。しかし,この見解に対しては,任命権と予算権だけで内閣のコントロール下にあるとすれば,裁判所も独立行政委員会と同様に内閣のコントロール下にあると解することが可能となってしまうという批判がある。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)334~335頁。
佐藤幸(日本国憲法論)529~530頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)202~204頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,Aが自ら所有する建物をBに賃貸し,Bに対して引き渡した場合,BがAの承諾を得て,建物の屋上に増築部分を建築したときは,当該部分について外部へ出入りするためには,建物内のはしご段を使用するほかない等の事情があったとしても,Bが増築部分の所有権を取得する。民法この問題の模試受験生正解率 84.2%結果正解解説民法242条本文は,不動産の所有者は,その不動産に従として付合した物の所有権を取得するものとするが,同条ただし書は,その物が権原によって附属させられたものである場合には,付合した動産の所有権は,附属させた者に留保されるとしている。そして,判例は,本記述と同様の事例において,建物賃借人が賃貸人兼所有者の承諾を得て,建物の2階部分を増築した場合,外部から増築部分へ立ち入るには,建物内のはしご段を使用するほかないときは,増築部分はその構造の一部をなすものであり,それ自体では取引上の独立性を有しないので,建物の区分所有権の対象たる部分には当たらないから,当該増築部分について賃借人名義の所有権保存登記がされていたとしても,同条ただし書の適用はなく,増築部分の所有権は,賃貸人兼所有者に帰属するとしている(最判昭44.7.25 民法百選Ⅰ〔第8版〕73事件)。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(物権)149~150頁。
論点体系判例民法(2)309頁,313頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,共同正犯者の一人について過剰防衛が成立する場合でも,他の共同正犯者について必ずしも過剰防衛が成立するとは限らない。刑法この問題の模試受験生正解率 51.1%結果正解解説判例は,「共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は,共同正犯者の各人につきそれぞれその要件を満たすかどうかを検討して決するべきであって,共同正犯者の一人について過剰防衛が成立したとしても,その結果当然に他の共同正犯者についても過剰防衛が成立することになるものではない」としている(最決平4.6.5 刑法百選Ⅰ〔第8版〕90事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)360頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)406~409頁。
条解刑法135~136頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第30条について,「法律の定めるところにより」という文言を重視して考えると,憲法第30条は,憲法第84条に規定されている租税法律主義を国民の義務の面から確認したものと解することができる。憲法この問題の模試受験生正解率 84.7%結果正解解説憲法30条は,「法律の定めるところにより」と規定していることから,租税法律主義(同84条)を国民の義務の面から確認したものと解されている。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)191~192頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)565頁。
新基本法コメ(憲法)252頁。 -
民法自筆証書遺言は,法定の法務局において保管することができる。民法この問題の模試受験生正解率 54.7%結果正解解説法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」という。)1条は,この法律は,法務局における自筆証書遺言の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに,その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとするとしている。そして,同2条1項は,遺言書の保管に関する事務は,法務大臣の指定する法務局が,遺言書保管所としてつかさどるとしている。よって,本記述は正しい。
なお,遺言書保管法は,自筆証書遺言が,作成後に紛失したり,相続人等によって隠匿又は変造されるおそれがあること,また,相続人が自筆証書遺言書の存在を知らないままに遺産分割が終了し,後になってその存在を知ったことにより,遺産分割協議が無駄になること,及び,自筆証書遺言書の作成の真正等をめぐって深刻な紛争が生じること等を考慮して,平成30年民法改正に伴い制定され,令和2年7月10日に施行された。参考潮見(詳解相続法)428~429頁。
窪田(家族法)459~460頁。
リーガルクエスト(親族・相続)379頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,客を集めて有料でわいせつな映画を観覧させて利益を得る目的で,自宅付近の人通りの多い路上で,通行人に声をかけ,これに応じた5名の客に対し,外部との交通を厳重に遮断した自宅の一室において,わいせつな映画を観覧させて利益を得た。この場合,甲にわいせつ物公然陳列罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 78.7%結果正解解説わいせつ物公然陳列罪(刑法175条1項前段)の「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいう。判例は,わいせつな映画を上映した部屋が,外部との交通が遮断されていて,観客も5名程度に限られていても,その5名が不特定多数人を勧誘して集められた者であれば,結果としてわいせつな映画を不特定の者に観覧可能な状態にしたといえるとした原審の判断を是認している(最決昭33.9.5)。したがって,本記述において,甲にわいせつ物公然陳列罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(刑法各論)384頁。
条解刑法510頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法朝日訴訟判決(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決,民集21巻5号1043頁)は,生活保護法第3条にいう「健康で文化的な生活水準」は,憲法第25条第1項に由来するものであるが,その具体的内容は,理論的には特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定すべきものであり,またし得るものであるとした。憲法この問題の模試受験生正解率 53.0%結果正解解説本記述の最高裁判所判決(最大判昭42.5.24 朝日訴訟 憲法百選Ⅱ〔第7版〕131事件)は,生活保護法に基づき厚生大臣(現:厚生労働大臣)の設定する生活保護基準が同法の規定に違反して違法であるかが争われた事例において,原告(上告人)が上告中に死亡したことから,相続人による訴訟承継を否定し,訴訟終了を宣言したが,「なお,念のため」として,「憲法25条1項は,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。この規定は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり,直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない……。具体的権利としては,憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって,はじめて与えられているというべきである。……右の権利は,厚生大臣が最低限度の生活水準を維持するにたりると認めて設定した保護基準による保護を受け得ることにあると解すべきである。もとより,厚生大臣の定める保護基準は,法(注:生活保護法)8条2項所定の事項を遵守したものであることを要し,結局には憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するにたりるものでなければならない。しかし,健康で文化的な最低限度の生活なるものは,抽象的な相対的概念であり,その具体的内容は,文化の発達,国民経済の進展に伴って向上するのはもとより,多数の不確定的要素を綜合考量してはじめて決定できるものである」としている。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決の第一審判決(東京地判昭35.10.19)は,生活保護法上の受給権と憲法25条の関係について,生活保護法は憲法25条を現実化・具体化し,生活保護法3条は保護請求権を付与したものであるとした上で,同条にいう「健康で文化的な生活水準」は,憲法25条1項に由来するものであるが,「健康で文化的な生活水準」の具体的な内容は,「決して固定的なものではなく通常は絶えず進展向上しつつあるものであると考えられるが,それが人間としての生活の最低限度という一線を有する以上理論的には特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定すべきものであり,またしうるものである」としている。 -
民法判例の趣旨に照らすと,債権者は,根保証契約の保証人に対して,元本確定期日前に,保証債務の履行を請求することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 16.8%結果正解解説根保証契約の元本確定前に,債権者が保証人に対して保証債務の履行を請求できるかについては,根保証の法的性質と関連して,争いがある。根保証の法的性質について,①期間中に生じる個々の被保証債権について個々の具体的保証債務が成立するとみる個別保証集積説からは,履行請求を肯定することに親和的であり,一方,②将来確定された時点で存在する債務を保証するものとみる根抵当類似説からは,履行請求を否定することに親和的であるとされる。判例は,「根保証契約を締結した当事者は,通常,主たる債務の範囲に含まれる個別の債務が発生すれば保証人がこれをその都度保証し,当該債務の弁済期が到来すれば,当該根保証契約に定める元本確定期日……前であっても,保証人に対してその保証債務の履行を求めることができるものとして契約を締結……しているものと解するのが合理的である」として,元本確定前の保証債務の履行請求を認めている(最判平24.12.14 民法百選Ⅱ〔第8版〕24事件)。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ451頁。
潮見(プラクティス債総)674~677頁。
中田(債総)611~612頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,賄賂罪の「賄賂」とは,公務員の職務行為と対価関係にある不正な報酬としての利益をいい,その利益には,人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含む。刑法この問題の模試受験生正解率 92.1%結果正解解説賄賂罪の「賄賂」とは,公務員の職務行為と対価関係にある不正な利益をいう。その利益には,有形・無形を問わず,人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含む(大判明43.12.19)。よって,本記述は正しい。参考山口(各)619~620頁。
西田(各)516頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)467~468頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,筆記行為の自由は,様々な意見,知識,情報に接し,これを摂取することを補助するものとしてなされる限りにおいては,憲法第21条第1項の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれるといえるから,その制限又は禁止には,表現の自由に制約を加える場合に,一般に必要とされる厳格な基準が要求される。憲法この問題の模試受験生正解率 81.9%結果正解解説最大判平元.3.8(レペタ事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕72事件)は,「筆記行為は,一般的には人の生活活動の一つであり,生活のさまざまな場面において行われ,極めて広い範囲に及んでいるから,そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが,さまざまな意見,知識,情報に接し,これを摂取することを補助するものとしてなされる限り,筆記行為の自由は,憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない」とした上で,「筆記行為の自由は,憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから,その制限又は禁止には,表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない」としている。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,善意の利得者が,利得に法律上の原因がないことを認識した後,利益が消滅した場合であっても,現存利益の範囲は,法律上の原因がないことを認識した時点において算定されるべきである。民法この問題の模試受験生正解率 57.9%結果正解解説利得者は,原則として,得た利益の全部を返還しなければならないが(民法704条),善意の利得者は,現存利益のみを返還すれば足りる(同703条)。そこで,善意の利得者が後に悪意に転じ,さらにその後に利益が消滅した場合,いつの時点で返還すべき利益を算定すべきかが問題となる。判例は,AがBと普通預金契約をしており,口座に入金がなかったにもかかわらず,Bが誤ってAに対して払戻しをし,その3時間後にBがAに対して返還請求をしたが,Aが本件払戻金を第三者に交付してしまったため,現存利益の有無が争われた事例において,「善意で不当利得をした者の返還義務の範囲が利益の存する限度に減縮されるのは,利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨に出たものであるから,利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は,返還義務の範囲を減少させる理由とはならない」として,当該事例では,AがBから返還請求を受け,払戻しに法律上の原因がないことを認識した時点での利益の存否を検討すべきであるとしている(最判平3.11.19 平3重判民法7事件)。よって,本記述は正しい。参考論点体系判例民法(7)474頁。
リーガルクエスト(事務管理・不当利得・不法行為)44~45頁。
平野(債各Ⅱ)35頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,新聞記者である甲による取材行為が国家公務員法上の守秘義務違反のそそのかし罪に該当したが,当該取材行為は,真に報道の目的から出たものであり,その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものであった。この場合,甲の取材行為の違法性は阻却される。刑法この問題の模試受験生正解率 64.2%結果正解解説判例は,報道機関の取材行為に秘密漏示そそのかし罪(国家公務員法100条1項,109条12号,111条)が成立するかが問題となった事例において,「報道機関の国政に関する取材行為は,国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり,時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから,報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって,そのことだけで,直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく,報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは,それが真に報道の目的からでたものであり,その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは,実質的に違法性を欠き正当な業務行為」であるとしている(最決昭53.5.31 外務省機密漏洩事件 刑法百選Ⅰ〔第8版〕18事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)113頁。
西田(総)213頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法公の支配に属しない事業への公金その他の公の財産の支出を禁止する憲法第89条後段の趣旨を,公費の濫用を防止することにあると解する立場は,「公の支配」の意義について,公の権力が当該事業の運営,存立に影響を及ぼすことにより,当該事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正し得る途が確保されていれば足りるという見解と結び付く。憲法この問題の模試受験生正解率 55.3%結果正解解説憲法89条後段は,公金その他の公の財産は「公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。」と定めている。この規定の趣旨に関しては,大別して①私的事業に対して公金支出を行う場合には,財政民主主義の観点から,公費の濫用を来さないように当該事業を監督すべきことを要求するものであると解する立場(公費濫用防止説)と,②私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止し,事業の自主性を確保するための規定と解する立場(自主性確保説)とがある。そのうち,①の立場は,公費が濫用されない程度に,事業についての監督が及んでいればよいと考えるから,「公の支配」に属するを,「国又は地方公共団体の一定の監督が及んでいることをもって足りる」というように,緩やかに解している。具体的には,業務や会計の状況に関し報告を徴したり,予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権を持っていれば足りるとする。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)376~377頁。
佐藤幸(日本国憲法論)574~575頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)343~347頁。 -
民法債務の履行について不確定期限が定められていた場合,債務者は,履行の請求を受ける前でも遅滞の責任を負うことがある。民法この問題の模試受験生正解率 62.1%結果正解解説民法412条2項は,債務の履行について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負うとしている。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ59頁。
潮見(プラクティス債総)125頁。
中田(債総)119頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,所持金を全く有しておらず,代金を支払う意思がないのに,乙の営業する飲食店で料理を注文し食事をした後,隙を見て同店から立ち去ったが,これに気付いた乙に追跡されたので,携帯していた拳銃を発砲し,乙を殺害した。この場合,甲には詐欺罪と殺人罪が成立し,強盗殺人罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 62.6%結果正解解説判例は,代金を支払う意思がないにもかかわらず,あるかのように装い,飲食店において注文をし,飲食物の提供を受けた行為について詐欺罪(刑法246条1項)が成立するとしている(最決昭30.7.7 刑法百選Ⅱ〔第8版〕53事件)。また,判例は,財物を窃取又は詐取した直後に被害者からの返還請求又は代金支払請求を免れるために,同人を殺害しようとしてこれを遂げなかった事例において,窃盗罪(同235条)又は詐欺罪と強盗殺人未遂罪(同243条,240条)のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべきであるとしている(最決昭61.11.18 刑法百選Ⅱ〔第8版〕40事件)。したがって,本記述において,甲には1項詐欺罪と強盗殺人罪(同条後段)が成立し,重い後者の包括一罪となる。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)225頁,258頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)182~183頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法思想の表明としての外部的行為によって現実的・具体的な害悪が生じたとしても,当該行為が思想内容の表明であることを理由として,当該行為を規制することは許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 38.1%結果正解解説特定の「思想」を有すること,又は有しないことを理由として刑罰その他の不利益を加えることは,憲法19条によって禁じられる。例えば,思想内容の表明としての外部的行為が現実的・具体的な害悪を生ぜしめた場合,思想内容とかかわりない現実的・具体的な害悪の発生を理由に当該行為を規制することは,許される。しかし,思想内容の表明であるということを理由として当該行為を規制することは,許されない。よって,本記述は正しい。参考野中ほか(憲法Ⅰ)312頁。
注解憲法Ⅰ381頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,妻が婚姻中に懐胎した子について,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかである場合,夫は,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存在を争うことができる。民法この問題の模試受験生正解率 54.2%結果正解解説妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定され(嫡出推定 民法772条1項),同条の推定を受ける子について父子関係の存否を争うには,夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することとされており(同774条,775条,777条),これと異なる方法により父子関係の存否を争う訴えは基本的に不適法とされる。もっとも,判例は,同772条2項の推定要件を満たしていても,妻がその子を懐胎すべき時期に既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,その子には実質的に同条の推定が及ばないとして,親子関係不存在確認の訴えなどにより父子関係の存否を争うことができる場合を認めている(最判平12.3.14 平12重判民法11事件など)。そこで,妻が婚姻中に懐胎した子ではあるが,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかである場合,実質的に同条の推定が及ばない場合に当たるのかが問題となる。判例は,「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえ」ないとした上で,前掲最判平12.3.14が判示した嫡出推定が及ばないと認められる事情の存否を検討して,本件ではそのような事情は認められないとして,親子関係不存在確認の訴えを却下している(最判平26.7.17 民法百選Ⅲ〔第2版〕28事件)。このように,判例は,夫婦の長期間の別居等で妻が夫の子を懐胎し得ないことが外観上明白な場合に嫡出推定が排除されるという外観説に立つものと考えられている。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(親族・相続)128~129頁。
窪田(家族法)196~200頁。
平26最高裁解説(民事)282~285頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,注意義務に違反して人を負傷させた場合,相手方に重大な過失があれば,過失の責任を免れることができる。刑法この問題の模試受験生正解率 80.5%結果正解解説刑法においては,過失相殺は適用されない(大判大11.5.11)。また,注意義務違反によって人を負傷させた以上,相手方に重過失があっても,行為者は過失の責任を免れることができない(最決昭33.4.18 交通事故百選〔初版〕88事件)。相手方にも重過失があったということは行為の際の具体的事情として,行為者の過失の有無を判断するための一資料となるにすぎない。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義総)194頁。
団藤(総)344頁。
大コメ(刑法・第3版)(3)107~108頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,公職選挙法が,衆議院議員選挙における小選挙区選挙につき候補者届出政党にのみ政見放送を認め,候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないとしたことは,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に,質量ともに大きな差異を設けたというべきであり,政見放送の持つ影響力の大きさなどを考慮すると,この差異は,合理性を有するとは到底いえない程度に達していると認めざるを得ない。憲法この問題の模試受験生正解率 83.7%結果正解解説判例は,公職選挙法に,平成6年に導入された小選挙区比例代表並立制の合憲性が争われた事例において,同法が「小選挙区選挙については候補者届出政党にのみ政見放送を認め候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないものとしたことは,政見放送という手段に限ってみれば,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差異を設ける結果となるものである。……このような差異が設けられた理由は,小選挙区制の導入により選挙区が狭くなったこと,従前よりも多数の立候補が予測され,これら多数の候補者に政見放送の機会を均等に提供することが困難になったこと,候補者届出政党は選挙運動の対象区域が広くラジオ放送,テレビジョン放送の利用が不可欠であることなどにあるとされているが,ラジオ放送又はテレビジョン放送による政見放送の影響の大きさを考慮すると,これらの理由をもってはいまだ右のような大きな差異を設けるに十分な合理的理由といい得るかに疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない。しかしながら,右の理由にも全く根拠がないものではないし,政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず,その余の選挙運動については候補者届出政党に所属しない候補者も十分に行うことができるのであって,その政見等を選挙人に訴えるのに不十分とはいえないことに照らせば,政見放送が認められないことの一事をもって,選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは断定し難いところであって,これをもって国会の合理的裁量の限界を超えているということはできない」としている(最大判平11.11.10 憲法百選Ⅱ〔第7版〕152②事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,使用者責任が成立するためには,他人を使用する関係の存在が必要であるが,この関係は,非営利的なものでもよく,また,一時的なものであってもよい。民法この問題の模試受験生正解率 86.3%結果正解解説民法715条1項本文は,ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとしている。そして,同項本文にいう事業とは,広い概念であり,一時的か継続的か,営利か非営利か,及び,適法か不適法かを問わないものと解されている。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅱ)145頁。
論点体系判例民法(9)410頁。
リーガルクエスト(事務管理・不当利得・不法行為)266~267頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙の両足をロープで縛り,5分間にわたり引きずり回した。この場合,甲の行為は継続して乙の場所的移動の自由を奪ったといえるから,甲に逮捕罪が成立する。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第14条第2項は,貴族制度を禁止しているが,これは,大日本帝国憲法下において存在した華族をはじめとする貴族制度を廃止するとともに,将来にわたって類似の制度が復活することのないように,改めてその廃止を明文で述べたものである。憲法この問題の模試受験生正解率 94.7%結果正解解説憲法14条2項は,「華族その他の貴族の制度は,これを認めない。」と規定して,華族をはじめとする貴族制度を禁止している。貴族は一般に世襲の特権階級をいうため,貴族制度を設けることは,同条1項後段列挙事由の「門地」による差別として禁止されるが,同条2項は,大日本帝国憲法下において存在した華族をはじめとする貴族制度を廃止するとともに,将来にわたって類似の制度が復活することのないように,改めてその廃止を明文で述べたものである。もっとも,今日の皇族については,皇室典範により定められた地位として,同項の例外とされる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)131頁,140頁。
佐藤幸(日本国憲法論)232頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)300頁。
新・コンメ憲法167頁。 -
民法質権の設定における目的である物の引渡しは,占有改定によることができる。民法この問題の模試受験生正解率 61.1%結果正解解説民法344条は,質権の設定の効力は,債権者に目的物を引き渡すことにより生ずるとしており,当事者が質権設定契約をするだけでは効力を生じない。そして,同345条は,質権設定者による目的物の代理占有を禁止していることから,占有改定(同183条)は,同344条の「引き渡す」には当たらない。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ85~86頁。
内田Ⅲ590頁。
我妻・有泉コメ557頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,有価証券虚偽記入罪の「虚偽の記入」とは,有価証券に真実に反する記載をする全ての行為をいう。刑法この問題の模試受験生正解率 54.7%結果正解解説判例は,「刑法162条2項にいわゆる「虚偽ノ記入」(現:「虚偽の記入」)とは,既成の有価証券に対すると否とを問わず……,有価証券に真実に反する記載をするすべての行為を指すものであって,手形にあっては基本的な振出行為を除いたいわゆる附属的手形行為の偽造等をいうものと解するを相当とする」としている(最決昭32.1.17 刑法百選〔新版〕80事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(各)482~483頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)444頁。
条解刑法470頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法内閣総理大臣は,国会議員,すなわち衆議院議員又は参議院議員であることが求められるが,参議院は衆議院と異なり,内閣との間に解散などの制度がなく,内閣は国会に対して連帯責任を負うとされていることなどからすれば,内閣総理大臣は衆議院議員でなければならないと解することとなる。憲法この問題の模試受験生正解率 72.5%結果正解解説内閣総理大臣は,国会議員,すなわち衆議院議員又は参議院議員の中から指名される(憲法67条1項前段)。文言上は衆参両議院のどちらの議員から指名してもよいとされている規定ぶりになっているが,内閣総理大臣は衆議院議員の中から指名されるべきであるとする見解がある。この見解は,参議院は衆議院と異なり,内閣との間には,解散などの制度がないことを根拠とする。他方,参議院議員が内閣総理大臣になることは排除されていないとする見解は,参議院議員も国民から直接選挙されており,また内閣は国会に対して連帯責任を負う(同66条3項)とされていることなどを根拠とする。したがって,内閣は国会に対して連帯責任を負うということを根拠とするのは,内閣総理大臣は衆議院議員でなければならないとする見解の根拠ではない。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)179~181頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)292頁。
新・コンメ憲法576~577頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,抵当権者は,抵当不動産の賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができない。民法この問題の模試受験生正解率 87.0%結果正解解説判例は,「民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「債務者」には,原則として,抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれない」としている(最決平12.4.14 平12重判民法2事件)。その理由として,同決定は,「所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し,抵当不動産の賃借人は,このような責任を負担するものではなく,自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはない」ことなどを挙げている。もっとも,同決定は,「所有者の取得すべき賃料を減少させ,又は抵当権の行使を妨げるために,法人格を濫用し,又は賃貸借を仮装した上で,転貸借関係を作出したものであるなど,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には,その賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して抵当権に基づく物上代位権を行使することを許すべき」としている。したがって,抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,当該賃借人が取得すべき転貸賃料債権を目的債権として物上代位権を行使することができない。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ152頁。
内田Ⅲ503~504頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,成年者に暴行を加える目的で略取誘拐しても,営利目的等略取誘拐罪として処罰されない。刑法この問題の模試受験生正解率 62.2%結果正解解説営利目的等略取誘拐罪は,未成年者,成年者共に客体となるところ,本罪は,営利,わいせつ,結婚又は生命若しくは身体に対する加害のいずれかの目的がなければ成立しない。本罪にいう生命若しくは身体に対する加害とは,被拐取者を殺害し,傷害し,又は暴行を加える目的をいう。したがって,成年者に暴行を加える目的で略取誘拐した場合であっても,営利目的等略取誘拐罪として処罰される。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)88~89頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)63頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法典中の規定は全て同一の形式的効力を有しており,効力に差のある規定が併存することを認める理論的根拠は存在しないとの見解は,憲法改正の限界を理論的に想定する立場の根拠となり得る。憲法この問題の模試受験生正解率 64.7%結果正解解説憲法改正について理論上限界があるか否か学説上争われている。憲法改正の限界を理論的に想定する立場(憲法改正限界説)は,その根拠として,憲法規範はその憲法体制の基本原理に関わるものとそうでないもの,すなわち改正を許さない部分と許す部分という価値の序列ないし効力を異にする2種類の規範群から成り立つ階層構造をなしていると主張する。これに対して,憲法改正に理論上限界はないとする立場(憲法改正無限界説)は,法実証主義の立場から,憲法という一つの法形式の内部に,改正不可能な部分と改正を許容する部分というように効力に差のある2種類の規定が併存することを認める理論的根拠は存在しないとして,憲法規範の階層構造ないし憲法規範内部の価値序列を否認する。したがって,憲法典中の規定は全て同一の形式的効力を有しており,効力に差のある規定が併存することを認める理論的根拠は存在しない,という見解は,憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠であり,限界を想定する立場の根拠とはなり得ない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)409~410頁。
佐藤幸(日本国憲法論)51頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)160頁。
憲法の争点328頁。 -
民法AがBに対し,Bとの間で締結した不動産の売買契約を解除する旨の意思表示をした当時,Bが被保佐人であったときは,Aのした解除の意思表示はその効力を生じない。民法この問題の模試受験生正解率 90.9%結果正解解説意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは,その意思表示をもって相手方に対抗することができない(民法98条の2本文)。制限行為能力者のうち,未成年者と成年被後見人に意思表示の受領能力がないことを定めた規定であり,被保佐人,被補助人には意思表示の受領能力が認められる。したがって,AがBに対し,Bとの間で締結した不動産の売買契約を解除する旨の意思表示をした当時,Bが被保佐人であっても,Aのした解除の意思表示はその効力を生じる。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)68頁。
リーガルクエスト(総則)154頁。
我妻・有泉コメ218頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲と乙が,それぞれ自動車を運転し,赤色信号を殊更に無視して交差点に進入し,Vが乗車する自動車に乙の自動車が衝突するなどして,Vを死亡させた。甲と乙が,互いに,同交差点において赤色信号を殊更に無視する意思であることを認識しながら,相手の運転行為にも触発され,速度を競うように高速度のまま同交差点を通過する意図の下に赤色信号を殊更に無視する意思を強め合い,時速100キロメートルを上回る高速度で一体となって甲の自動車を同交差点に進入させた。この場合,甲に危険運転致死罪の共同正犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 66.4%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,被害車両と衝突をせず,被害者に接触すらしなかった被告人にも,被害者に生じた死亡結果につき,危険運転致死罪の共同正犯(自動車運転死傷行為処罰法2条5号,刑法60条)が成立するかにつき,「被告人と乙は,本件交差点の2km以上手前の交差点において,赤色信号に従い停止した第三者運転の自動車の後ろにそれぞれ自車を停止させた後,信号表示が青色に変わると,共に自車を急激に加速させ,強引な車線変更により前記先行車両を追い越し,制限時速60kmの道路を時速約130km以上の高速度で連なって走行し続けた末,本件交差点において赤色信号を殊更に無視する意思で時速100kmを上回る高速度で乙車,被告人車の順に連続して本件交差点に進入させ,……事故に至ったものと認められる。上記の行為態様に照らせば,被告人と乙は,互いに,相手が本件交差点において赤色信号を殊更に無視する意思であることを認識しながら,相手の運転行為にも触発され,速度を競うように高速度のまま本件交差点を通過する意図の下に赤色信号を殊更に無視する意思を強め合い,時速100kmを上回る高速度で一体となって自車を本件交差点に進入させたといえる」とした上で,「以上の事実関係によれば,被告人と乙は,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上,共同して危険運転行為を行ったものといえるから,被告人には,乙車による死傷の結果も含め,法(注:自動車運転死傷行為処罰法)2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するというべきである」としている(最決平30.10.23 平30重判刑法7事件)。したがって,甲に危険運転致死罪の共同正犯が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(総)381~382頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,被害者が尊属であることを犯情の一つとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみならず,さらに進んでこのことを類型化し,法律上,刑の加重要件とする規定を設けても,このような差別的取扱いをもって直ちに合理的な根拠を欠くものと判断することはできず,憲法第14条第1項に反するということはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 58.4%結果正解解説判例は,削除前の刑法200条所定の尊属殺人罪で起訴された被告人が,同条は憲法14条1項に違反すると主張した事例において,「刑法200条の立法目的は,尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもって一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし,かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し,もって特に強くこれを禁圧しようとするにあるものと解される。ところで,およそ,親族は,婚姻と血縁とを主たる基盤とし,互いに自然的な敬愛と親密の情によって結ばれていると同時に,その間おのずから長幼の別や責任の分担に伴う一定の秩序が存し,通常,卑属は父母,祖父母等の直系尊属により養育されて成人するのみならず,尊属は,社会的にも卑属の所為につき法律上,道義上の責任を負うのであって,尊属に対する尊重報恩は,社会生活上の基本的道義というべく,このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は,刑法上の保護に値するものといわなければならない。しかるに,自己または配偶者の直系尊属を殺害するがごとき行為はかかる結合の破壊であって,それ自体人倫の大本に反し,かかる行為をあえてした者の背倫理性は特に重い非難に値するということができる」とした上で,「このような点を考えれば,尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして,このことをその処罰に反映させても,あながち不合理であるとはいえない。そこで,被害者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみならず,さらに進んでこのことを類型化し,法律上,刑の加重要件とする規定を設けても,かかる差別的取扱いをもってただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず,したがってまた,憲法14条1項に違反するということもできない」としている(最大判昭48.4.4 尊属殺重罰規定判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕25事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aが,Bの不注意により,Bの運転する自動車と接触して負傷し,Bに対して損害賠償債権を有していたが,当該債権をCに譲渡した場合において,BがCに対して既に弁済期にある貸金債権を有しているときであっても,Bは,Cに対して,貸金債権を自働債権とする相殺をもって対抗することができない。民法この問題の模試受験生正解率 56.7%結果正解解説悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務(民法509条1号)及び人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(同条2号)の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない。もっとも,同条柱書ただし書は,その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りではないとしている。本記述においても,Aは,Bに対して,負傷したことによる損害賠償債権を有しているが,CはこれをAから譲り受けた者であるので,Bは,Cに対して,相殺をもって対抗することができる。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ308~309頁。
潮見(プラクティス債総)434~436頁。
中田(債総)476~477頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,行為者が,犯行時に心神耗弱状態にあった場合,必ずその刑が減軽又は免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 93.1%結果正解解説刑法39条2項は,心神耗弱者の行為は,その刑を必要的に減軽すると定めているが,刑の免除までは認めていない。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)271頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)222頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,労働組合が労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のような政治的活動としての一面を持つ行為を行うことは,労働組合の目的の範囲外であるから,当該行為について組合員に協力を義務付けることは許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 69.5%結果正解解説労働組合が他の労働組合の闘争支援資金,安保反対闘争により不利益処分を受けた組合員の救援費用等のための臨時組合費の納付を組合員に強制できるかどうかが争われた事例において,「政治的活動は一定の政治的思想,見解,判断等に結びついて行われるものであり,労働組合の政治的活動の基礎にある政治的思想,見解,判断等は,必ずしも個々の組合員のそれと一致するものではないから,……労働組合としては,その多数決による政治的活動に対してこれと異なる政治的思想,見解,判断等をもつ個々の組合員の協力を義務づけることは,原則として許されない」が,「労働組合の活動がいささかでも政治的性質を帯びるものであれば,常にこれに対する組合員の協力を強制することができないと解することは,妥当な解釈とはいいがたい。例えば,労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のごときは,政治的活動としての一面をもち,そのかぎりにおいて組合員の政治的思想,見解,判断等と全く無関係ではありえないけれども,それとの関連性は稀薄であり,むしろ組合員個人の政治的立場の相違を超えて労働組合本来の目的を達成するための広い意味における経済的活動ないしはこれに付随する活動であるともみられるものであって,このような活動について組合員の協力を要求しても,その政治的自由に対する制約の程度は極めて軽微なものということができる。それゆえ,このような活動については,労働組合の自主的な政策決定を優先させ,組合員の費用負担を含む協力義務を肯定すべきである」としている(最判昭50.11.28 国労広島地本事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕145事件)。同判決は,労働組合の活動が政治的活動としての一面を持っていたとしても,そのことから,直ちに組合の目的の範囲外であるとはせずに,そのような活動も組合の目的の範囲内にあるとの理解を示しつつ,組合員の協力義務の範囲について検討している。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)175頁。
-
民法判例の趣旨に照らすと,賃貸借契約が期間の満了により終了したときは,賃貸人は,賃借人との間で,通常の使用及び収益から生じた賃借物の損耗についての原状回復費用は賃借人の負担とするとの特約を明確に合意していない限り,通常の使用及び収益から生じた賃借物の損耗についての原状回復費用を敷金から差し引くことはできない。民法この問題の模試受験生正解率 83.6%結果正解解説賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において,賃貸借が終了したときは,その損傷を原状に復する義務を負うが(民法621条本文),通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については原状回復義務を負わない(同条本文括弧書)。同条は,平成29年民法改正によって新設された規定であるが,同改正前における判例も,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであり,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われているから,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるとして,「賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約……が明確に合意されていることが必要である」としている(最判平17.12.16 平17重判民法8事件,消費者法百選〔第2版〕23事件)。したがって,賃借物の通常の使用及び収益によって生じた損耗についての原状回復費用は,これを賃借人が負担するという特約が当事者間で明確に合意されていない限り,賃借人に負担させることはできないから,賃貸人は当該費用を敷金から差し引くことはできない。よって,本記述は正しい。参考論点体系判例民法(6)428頁。
潮見(基本講義・債各Ⅰ)168頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Vに対して有している30万円の債権を喝取しようと企て,「俺の顔を立てろ。」などと申し向けて金員を要求し,Vが要求に応じないときにはVの身体に危害を加えるような態度を示したところ,Vはこれに応じなければ自己の身体に危害を加えられるかもしれないと畏怖し,現金50万円を甲に交付した。この場合,甲に現金50万円全額につき恐喝罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.2%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「他人に対して権利を有する者が,その権利を実行することは,その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り,何等違法の問題を生じないけれども,右の範囲程度を逸脱するときは違法となり,恐喝罪の成立することがある」とした上で,被告人の行為は,権利行使の手段として社会通念上,一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した手段であるとし,被告人の有する債権額のいかんにかかわらず,交付を受けた金額全部につき恐喝罪(刑法249条1項)が成立するとしている(最判昭30.10.14 刑法百選Ⅱ〔第8版〕61事件)。したがって,甲に現金50万円全額につき恐喝罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(各)246~247頁。
山口(各)284~285頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)276頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命するが,最高裁判所による指名過程に国民の意思を反映させる必要性があることを踏まえて,最高裁判所は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会を設置した。憲法この問題の模試受験生正解率 52.5%結果正解解説下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣でこれを任命する(憲法80条1項前段)。最高裁判所による指名過程に国民の意思を反映させる必要性があることを踏まえて,最高裁判所は2003年に,下級裁判所裁判官指名諮問委員会を設置した(下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則1条)。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)653頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)328~329頁。
新基本法コメ(憲法)420~422頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,Aの請求により家庭裁判所がBを廃除する審判をし,この審判がAの生前に確定した場合,Bは,Aから遺贈を受ける資格を失う。民法この問題の模試受験生正解率 72.7%結果正解解説廃除を求める審判が廃除を求めた被相続人の生前に確定すると,被廃除者はその時から相続権を失う。受遺者については,相続欠格の規定(民法891条)が準用されているが(同965条),廃除の規定は準用されていない。したがって,廃除により相続権を失った者も,被相続人から遺贈を受ける資格を失わない。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(親族・相続)250~251頁。
潮見(詳解相続法)51頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,医師甲は,妊娠している乙女の承諾を得た上で,胎児が母体外において生命を保続することのできない時期ではないにもかかわらず,薬物を使用して堕胎させた。この場合,甲に同意堕胎罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説医師や助産師などの業務者が女子の嘱託を受け,又はその承諾を得て堕胎させたときは,同意堕胎罪(刑法213条前段)ではなく,業務上堕胎罪(同214条前段)が成立する。したがって,甲には同意堕胎罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)22~23頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)16~17頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し,これに対する国民の信頼を維持するという目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は,国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。憲法この問題の模試受験生正解率 54.6%結果正解解説判例は,国家公務員が行った政党ビラの戸別配布に対し,国家公務員法が禁止する政治的行為を行ったとして起訴された事例において,「国の行政機関における公務は,憲法の定める我が国の統治機構の仕組みの下で,議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策を忠実に遂行するため,国民全体に対する奉仕を旨として,政治的に中立に運営されるべきものといえる。そして,このような行政の中立的運営が確保されるためには,公務員が,政治的に公正かつ中立的な立場に立って職務の遂行に当たることが必要となるものである。このように,本法(注:国家公務員法)102条1項は,公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し,これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される」とし,「他方,国民は,憲法上,表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており,この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって,民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると,上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は,国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである」としている(最判平24.12.7 堀越事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕13事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地の法律関係に関して,判例の趣旨に照らすと,甲土地を分割する場合,Bに対して債権を有するDがいるときは,分割によってDの利益が害されるおそれがあるので,A及びBは,Dに対して,分割に先立ち分割についての協議をする旨の通知をしなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 82.9%結果正解解説民法260条1項は,共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は,自己の費用で,分割に参加することができるとしている。これは,共有物の分割においては,共有物につき地上権,賃借権,担保物権等の権利を有する者及び各共有者の債権者が,分割方法によってはその利益を害されるおそれがあるから,分割に参加し意見を述べることを認めるものである。もっとも,各共有者は,共有物の分割に先立ち共有物について権利を有する者や各共有者の債権者に対して分割の協議をする旨の通知をする義務はない。よって,本記述は誤りである。参考新基本法コメ(物権)126頁。
論点体系判例民法(2)384頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,友人乙から粉末が入っているビニール袋を50個,数日間預かってほしいと頼まれたため,これを承諾し所持していたが,甲は同ビニール袋の中身が身体に有害な違法な薬物か何かであることは認識していたが,覚せい剤ではないと認識していた。この場合,甲に覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 69.2%結果正解解説判例は,覚せい剤取締法違反(覚せい剤輸入・所持)の罪で起訴された被告人が,日本国内に持ち込んで所持した薬物が,覚せい剤であることの認識がなかったとして,同罪の故意が認められるかが争われた事例において,「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があった」場合には,「覚せい剤かもしれないし,その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる」から,同罪の故意が認められるとしている(最決平2.2.9 刑法百選Ⅰ〔第8版〕40事件)。本記述では,甲は,ビニール袋の中身は覚せい剤ではないと認識しており,認識の対象から覚せい剤が除外されている。したがって,甲に覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪の故意は認められず,同罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考山口(総)202頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)96頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法改正権は,憲法により設立された権力であり,憲法制定権力とは質的に異なり区別されるとの見解は,憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得る。憲法この問題の模試受験生正解率 64.7%結果正解解説憲法改正権は,憲法により設立された権力であり,憲法制定権力とは質的に異なり区別されるという見解は,憲法改正権は憲法制定権力によって与えられた権能であるから,憲法制定権力によって樹立された根本原理に反するような改正,あるいは憲法の同一性を失わせるような改正は行い得ないとして,憲法改正限界説の根拠とされている。これに対して,憲法改正権と憲法制定権力を同視する見解は,憲法改正の内容は制定された憲法の枠には拘束されないとして,憲法改正無限界説の根拠となる。したがって,憲法改正権と憲法制定権力を区別する見解は,憲法改正限界説の根拠となるが,憲法改正無限界説の根拠とはなり得ない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)409頁。
高橋(憲法)474頁。
辻村(憲法)520頁。
松井(憲法)76~77頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)411頁。
渡辺ほか(憲法Ⅱ)160~161頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)30~32頁。
安西ほか(憲法学読本)362~363頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,代理人が本人の名において権限外の行為をした場合であっても,相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは,本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合に限り,権限外の行為についての表見代理の規定が類推適用され,本人がその責任を負う。民法この問題の模試受験生正解率 54.7%結果正解解説民法110条は,代理人がその権限の範囲外の行為をした場合において,第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは,本人は,当該行為について責任を負うとし,権限の範囲外の行為の表見代理について規定している。そして,同条をはじめとする表見代理は,代理権が存在することへの信頼を保護する制度であり,行為を行う者が本人であることへの信頼を保護する制度ではない。したがって,本記述のように,代理人が本人になりすまして本人の名で権限外の行為をしたことにより,取引の相手方が代理人のした行為が本人自身の行為であると信じた場合には,同条の規定を適用することができないとする見解もある。もっとも,判例は,「代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において,相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは,代理人の代理権を信じたものではないが,その信頼が取引上保護に値する点においては,代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはないから,本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合にかぎり,民法110条の規定を類推適用して,本人がその責に任ずる」としている(最判昭44.12.19)。よって,本記述は正しい。参考昭44最高裁解説(民事)630~631頁。
新・コンメ民法170頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,心神喪失とは,精神の障害により,事物の理非善悪を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力の両方を欠いている状態をいう。刑法この問題の模試受験生正解率 93.1%結果正解解説心神喪失(刑法39条1項)とは,精神の障害により,事物の理非善悪を弁識する能力(弁識能力)又はこの弁識に従って行動する能力(制御能力)のいずれかを欠く状態をいう(大判昭6.12.3 刑法百選Ⅰ〔第4版〕33事件)。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)272頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)223頁。
条解刑法167頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,参議院議員の選挙において,都道府県を各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ,都道府県を各選挙区の単位として固定する結果,投票の価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続されてきた状況の下では,各選挙区の区域を定めるに当たり,都道府県という単位を用いることは不合理なものとして許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 55.0%結果正解解説判例は,平成28年7月施行の参議院議員選挙に対する選挙無効訴訟において,選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否かが争われた事例において,「平成24年大法廷判決(注:最大判平24.10.17 憲法百選Ⅱ〔第7版〕150事件)及び平成26年大法廷判決(注:最大判平26.11.26 平26重判憲法1事件)は,……選挙制度の構築についての国会の裁量権行使の合理性を判断するに当たって,長年にわたる制度及び社会状況の変化を考慮すべき必要性を指摘し,その変化として,参議院議員と衆議院議員の各選挙制度が同質的なものとなってきており,国政の運営における参議院の役割が増大してきていることに加え,衆議院については投票価値の平等の要請に対する制度的な配慮として選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする旨の区割りの基準が定められていることなどを挙げて,これらの事情の下では,昭和58年大法廷判決(注:最大判昭58.4.27 憲法百選Ⅱ〔第3版〕156事件)が長期にわたる投票価値の大きな較差の継続を許容し得る根拠として挙げていた諸点につき,数十年間にもわたり5倍前後の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっている旨を指摘するとともに,都道府県を各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ,都道府県を各選挙区の単位として固定する結果,上記のように長期にわたり大きな較差が継続していた状況の下では」,都道府県の意義や実体等をもって都道府県を単位とする「選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっていたとしたものである。しかし,この判断は,都道府県を各選挙区の単位として固定することが投票価値の大きな不平等状態を長期にわたって継続させてきた要因であるとみたことによるものにほかならず,各選挙区の区域を定めるに当たり,都道府県という単位を用いること自体を不合理なものとして許されないとしたものではない」としている(最大判平29.9.27 平29重判憲法1事件)。よって,本記述は誤りである。参考平29最高裁解説(民事)419~420頁。
-
民法判例の趣旨に照らすと,一般債権者が物上代位の目的となる賃料債権を差し押さえて転付命令が第三債務者に送達された後であっても,抵当権者は,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。民法この問題の模試受験生正解率 87.0%結果正解解説判例は,「転付命令に係る金銭債権(以下「被転付債権」という。)が抵当権の物上代位の目的となり得る場合においても,転付命令が第三債務者に送達される時までに抵当権者が被転付債権の差押えをしなかったときは,転付命令の効力を妨げることはできず,差押命令及び転付命令が確定したときには,転付命令が第三債務者に送達された時に被転付債権は差押債権者の債権及び執行費用の弁済に充当されたものとみなされ,抵当権者が被転付債権について抵当権の効力を主張することはできない」としている(最判平14.3.12 執行・保全百選〔第3版〕78事件)。その理由として,同判決は,「転付命令は,……転付命令が第三債務者に送達された時に他の債権者が民事執行法159条3項に規定する差押等をしていないことを条件として,差押債権者に独占的満足を与えるものであり(民事執行法159条3項,160条),他方,……同法159条3項に規定する差押えに物上代位による差押えが含まれることは文理上明らかであることに照らせば,抵当権の物上代位としての差押えについて強制執行における差押えと異なる取扱いをすべき理由はなく,これを反対に解するときは,転付命令を規定した趣旨に反することになる」ことを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ158~159頁。
内田Ⅲ510~511頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,民事訴訟の証拠調べの期日において,証人として宣誓の上,虚偽の陳述をした。原告乙,被告丙ともに甲が虚偽の陳述をすることについてあらかじめ承諾をしていた。この場合,甲に偽証罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説法益主体の同意によって犯罪の成立が否定されるものは,同意の対象となる法益が法益主体にとって処分可能なものである。偽証罪(刑法169条)の保護法益は,国の審判作用の適正な運用であり,同罪は国家的法益に対する罪であるから,原告及び被告の同意があっても同罪の成立は否定されない。したがって,甲に偽証罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考大谷(講義総)252頁。
山口(総)162頁。
西田(各)495頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)545~547頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,教科書検定は,当該検定で教科書としての発表を禁じられた図書が一般図書として発行されることを妨げるものではなく,発表禁止目的や発表前の審査などの特質もないから,憲法第21条第2項前段にいう「検閲」には当たらない。憲法この問題の模試受験生正解率 63.4%結果正解解説判例は,高等学校用教科書を検定不合格処分とされたため,執筆者が国家賠償を求めた事例において,「憲法21条2項にいう検閲とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的とし,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指す」とした上で,教科書検定は,発表禁止目的や発表前の審査などの検閲の特質がないから,「検閲に当たらず,憲法21条2項前段の規定に違反するものではない」としている(最判平5.3.16 第1次家永教科書事件上告審 憲法百選Ⅰ〔第7版〕88事件)。同判決は,教科書検定が同項前段の検閲に該当しないとした理由として,教科書検定で不合格とされた図書は,教育委員会が開催する教科書展示会にその見本を出品することができるなどの特別な取扱いを受けることができず,教科書としての発行の道が閉ざされることになるが,「右制約は,普通教育の場において使用義務が課せられている教科書という特殊な形態に限定されるのであって,不合格図書をそのまま一般図書として発行し,教師,児童,生徒を含む国民一般にこれを発表すること,すなわち思想の自由市場に登場させることは,何ら妨げられるところはない」とし,また,「一般図書として発行済みの図書をそのまま検定申請することももとより可能である」ことなどを挙げている。よって,本記述は正しい。
-
民法AとBは,Aが所有する建物甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結した。この事例に関して,判例の趣旨に照らすと,Aが,Bに甲の引渡し及び所有権移転登記をする約定の期日の前に,甲をCに売却してCへの所有権移転登記をした場合,当該所有権移転登記がされたことにより,AのBに対する甲の引渡債務及び所有権移転登記をする債務は履行不能となるから,Bは,催告をすることなく直ちに本件契約を解除することができる。民法この問題の模試受験生正解率 86.8%結果正解解説判例は,不動産の二重売買がされた場合,売主の一方の買主に対する債務は,特段の事情のない限り,他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるとしている(最判昭35.4.21 不動産取引百選〔第2版〕67事件)。そして,債務の全部の履行が不能であるときは,債権者は,履行の催告をすることなく契約の全部の解除をすることができる(民法542条1項1号)。本記述においても,Aが,Bに甲の引渡し及び所有権移転登記をする約定の期日の前に,甲をCに売却してCへの所有権移転登記がされた場合,当該所有権移転登記がされた時に,AのBに対する甲の引渡債務及び所有権移転登記をする債務は履行不能となるから,Bは,催告をすることなく直ちに本件契約を解除することができる。よって,本記述は正しい。参考潮見(プラクティス債総)72頁。
新基本法コメ(債権2)54頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,営利目的等略取誘拐罪にいう「結婚の目的」とは,被拐取者を自己又は第三者と結婚させる目的をいい,法律婚のみならず,事実婚を含む。刑法この問題の模試受験生正解率 62.2%結果正解解説営利目的等略取誘拐罪における結婚の目的とは,自己又は第三者と結婚させる目的をいうが,法律婚だけでなく,事実婚も含むとされている。よって,本記述は正しい。参考西田(各)89頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)62頁。
条解刑法681頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,大学が個人識別を行うための単純な情報であって,秘匿の必要性が高くはないから,それ自体はプライバシーに係る情報として法的保護の対象にならないが,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるから,慎重に取り扱われる必要がある。憲法この問題の模試受験生正解率 55.2%結果正解解説判例は,私立大学が講演会の参加を申し込んだ学生らの氏名や学籍番号等の記載された名簿を警察に提出したことが不法行為に当たるか否かが問題になった事例において,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,当該私立大学が「個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」が,「このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,……プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」とした上で,「このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要がある」としている(最判平15.9.12 江沢民早大講演会訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕18事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aが所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地上に乙建物を建築した上で乙建物をCに賃貸した後,Cが,乙建物について工事を施して,Bに対して工事費用の償還請求権を有している場合,AB間の甲土地の賃貸借契約が有効に解除された後,AがCに対して乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを求めたときは,Cは,工事費用の償還を受けるまで乙建物を留置する結果として甲土地を留置することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 65.2%結果正解解説判例は,「借地上にある家屋の賃借人がその家屋について工事を施したことにもとづくその費用の償還請求権は,借地自体に関して生じた債権でもなければ,借地の所有者に対して取得した債権でもないから,借地の賃貸借契約が有効に解除された後,その借地の所有者が借家人に対して右家屋からの退去およびその敷地部分の明渡を求めた場合においては,その借家人には右費用の償還を受けるまでその家屋の敷地部分を留置しうる権利は認められない」としている(最判昭44.11.6)。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ669頁。
論点体系判例民法(3)9~10頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,緊急避難は,避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に成立するから,前者と後者が同等の場合には成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 86.4%結果正解解説緊急避難が成立するためには,避難行為から生じた害が,避けようとした害の程度を超えないことが必要である(法益の均衡)。したがって,侵害法益と保全法益が等しい場合にも,緊急避難は成立し得る。よって,本記述は誤りである。参考井田(総)334頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)211頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所は,罰則規定の内容をなしている税務調査の規定の意義が不明確であり,憲法第31条に違反するかが問われた川崎民商事件(最高裁判所昭和47年11月22日大法廷判決,刑集26巻9号554頁)において,当該事案において,税務署職員の職務上の地位及び行為が上記税務調査の規定の各要件を具備することは明らかであるから,この規定が当該事案に適用される場合には,その内容に何ら不明確な点は存在しないと判示した。憲法この問題の模試受験生正解率 73.9%結果正解解説本問の最高裁判所判決(最大判昭47.11.22 川崎民商事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕114事件)は,「所論は,昭和40年法律第33号による改正前の所得税法(以下,旧所得税法という。)70条10号の罪の内容をなす同法63条は,規定の意義が不明確であって,憲法31条に違反するものである旨主張する」とした上で,「しかし,第一,二審判決判示の本件事実関係は,被告人が所管川崎税務署長に提出した昭和37年分所得税確定申告書について,同税務署が検討した結果,その内容に過少申告の疑いが認められたことから,その調査のため,同税務署所得税第二課に所属し所得税の賦課徴収事務に従事する職員において,被告人に対し,売上帳,仕入帳等の呈示を求めたというものであり,右職員の職務上の地位および行為が旧所得税法63条所定の各要件を具備するものであることは明らかであるから,旧所得税法70条10号の刑罰規定の内容をなす同法63条の規定は,それが本件に適用される場合に,その内容になんら不明確な点は存しない」としている。よって,本記述は正しい。
なお,同判決に対しては,明確性とは法文自体の性格の問題であるから,ある事案との関係で明確であったり不明確であったりするわけがないとの批判がなされている。参考高橋(憲法訴訟)200頁。
野坂(憲法判例)382~384頁。
憲法判例の射程366頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,金銭消費貸借が書面によってされた場合,借主は,貸主から金銭を受け取るまでの間,契約を解除することができる。民法この問題の模試受験生正解率 50.3%結果正解解説民法上,消費貸借は,要物契約としての消費貸借(同587条)と,諾成的消費貸借(同587条の2)とが認められている。要物契約としての消費貸借は,目的物の交付がその成立要件とされており,諾成的消費貸借は,合意が書面でされることがその成立要件とされている。
民法587条の2は,諾成的消費貸借を認めており,書面でする消費貸借は,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその受け取った物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって,その効力が生ずるとされている(同条1項)。そして,書面でする消費貸借の借主は,貸主から金銭その他の物を受け取るまで,契約の解除をすることができるとされている(同条2項前段)。よって,本記述は正しい。
なお,同項後段は,契約の解除によって貸主が損害を受けた場合,貸主は,借主に対し,損害賠償請求をすることができるとしている。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)126~128頁。
新基本法コメ(債権2)172~173頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,A及びBが殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり,「A,もっと頑張れ。」などとAに一方的に肩入れするような声援を送ったところ,その声援を聞いたAはいっそう犯意を強固にし,更に強度の暴行を加え続けたことにより,Bに鼻骨骨折等の傷害を負わせた。この場合,甲に現場助勢罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 53.2%結果正解解説現場助勢罪(刑法206条)は,傷害又は傷害致死の行為が行われる際,その現場において勢いを助ける行為を処罰対象としている。勢いを助けるとは,本犯の気勢を高め,又は刺激すべき性質の行為をいい,例えば,「やれやれ。」,「もっとやれ。」などの声援がこれに当たる。もっとも,同条が,傷害の現場でなされた助勢行為を処罰する規定である以上,特定の正犯者の犯行を容易にする従犯とは異なる(大判昭2.3.28参照)。したがって,傷害罪又は傷害致死罪の現場での声援であっても,双方がけんか状態になっている現場で,一方を加勢するために助勢した場合は,幇助行為であって,本条に該当しない。本記述では,甲の行為は,既に暴行ないし傷害の故意があったAの犯意を強固にしているから,甲には傷害罪の従犯(同204条,62条1項)が成立し,現場助勢罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)47頁。
高橋(各)55~56頁。
井田(各)65~66頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)34~35頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法上,天皇が行う全ての国事行為には,内閣の助言と承認が必要であり,その責任は内閣が負うとされているが,ここでいう責任は,内閣が天皇に代わって負うものではなく,助言と承認に対する内閣の自己責任である。憲法この問題の模試受験生正解率 69.9%結果正解解説天皇の国事に関する全ての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣がその責任を負う(憲法3条)。天皇は内閣の助言と承認のとおり国事行為を行うのだから,ここでいう責任は,内閣が天皇に代わって負う責任ではなく,助言と承認に対する内閣の自己責任である。よって,本記述は正しい。参考渡辺ほか(憲法Ⅱ)96頁。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次売却されたが,登記名義がなおAに残っている場合,その登記は現在の権利関係に合致していないので,Cは,Aに対し,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 51.5%結果正解解説中間省略登記請求をする場合においては,物権変動の過程を忠実に反映すべきという不動産登記制度の原則が重視されている。判例は,「不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されない」としている(最判平22.12.16 平23重判民法4事件)。したがって,Cは,Aに対し,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができない。よって,本記述は誤りである。参考新基本法コメ(物権)32頁。
アルマ(民法2)291~293頁。
リーガルクエスト(物権)82頁。
論点体系判例民法(2)65頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,3000円の商品を購入する際,代金として5千円札を出したところ,7000円の釣銭を受け取った。帰宅する途中,甲は釣銭が多いことに気付いたが,これを自分のものにしようと考え,返還することなくそのまま帰宅した。この場合,甲に詐欺罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 74.2%結果正解解説詐欺罪(刑法246条)にいう「人を欺」く行為は,不作為によっても可能である。当該不作為が詐欺罪にいう欺く行為に当たるというためには,不作為犯が成立するための法的な告知義務が行為者に認められる場合であることを要する(大判昭8.5.4)。本記述において,甲は,釣銭を受け取った後,帰宅する途中,釣銭が多いことに気付いたにもかかわらず,これを自分のものにしようと考え,過分の釣銭を返還することなくそのまま帰宅しているが,このような場合,相手方の錯誤を利用して財物を取得したのではなく,偶然に自己の占有に属したものを領得したにすぎないとして,詐欺罪は成立せず,占有離脱物横領罪(同254条)が成立すると解されている。したがって,甲に詐欺罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義各)271頁。
西田(各)210頁。
条解刑法785頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第49条は,国会議員は国庫から相当額の歳費を受けるものとし,その歳費が在任中に減額されないことを定めている。憲法この問題の模試受験生正解率 29.4%結果正解解説憲法49条は,「両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。」と規定しているが,その歳費が在任中に減額されないことまでは定めていない。よって,本記述は誤りである。
なお,憲法は,最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は,全て定期に相当額の報酬を受け,この報酬が在任中に減額されないことを保障している(同79条6項,80条2項)。参考野中ほか(憲法Ⅱ)109頁,245頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)219~220頁。 -
民法AがBに対して有する弁済期の到来した甲債権の消滅時効に関して,AB間で,甲債権の額について争いが生じたことから,その額について協議を行う旨の合意を書面でした場合,その合意があった時から一定期間,甲債権の消滅時効の完成が猶予される。民法この問題の模試受験生正解率 50.9%結果正解解説権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは,①その合意があった時から1年を経過した時,②その合意において当事者が1年に満たない協議期間を定めたときは,その期間を経過した時,③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは,その通知の時から6か月を経過した時のいずれか早い時までの間は,時効の完成が猶予される(民法151条1項)。よって,本記述は正しい。参考佐久間(総則)426~427頁。
リーガルクエスト(総則)311~312頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,公務執行妨害罪の「職務」には,私企業的性格を有する公務も含まれる。刑法この問題の模試受験生正解率 84.0%結果正解解説判例は,公務執行妨害罪の「職務」は,権力的,強制的なものであることを要せず(大判明42.11.19),「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」としている(最判昭53.6.29)。よって,本記述は正しい。参考西田(各)446頁。
山口(各)542頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)493頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法信教の自由に関して,判例によれば,静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は,宗教上の人格権として保障されるべきであるから,人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたときには,損害賠償を請求することができる。憲法この問題の模試受験生正解率 67.2%結果正解解説判例は,社団法人隊友会A県支部連合会と自衛隊A地方連絡部が共同して亡夫をA県護国神社に合祀申請(以下「本件合祀申請」という。)したことは,宗教上の人格権の侵害であるなどとして,亡夫の妻が,合祀手続の取消しなどを請求した事例において,「人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし,そのことに不快の感情を持ち,そのようなことがないよう望むことのあるのは,その心情として当然であるとしても,かかる宗教上の感情を被侵害利益として,直ちに損害賠償を請求し,又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば,かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは,見易いところである」とした上で,「信教の自由の保障は,何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して,それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである」とし,「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは,これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである」としている(最大判昭63.6.1 憲法百選Ⅰ〔第7版〕43事件)。したがって,同判決は,静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は宗教上の人格権として保障されるべきであるとはしていない。よって,本記述は誤りである。
-
民法AがBに対して預貯金債権以外の金銭債権である甲債権を有し,AがCに対して甲債権を譲渡した。この場合に関して,判例の趣旨に照らすと,甲債権がAB間の特定物を目的とする売買契約により生じた代金債権である場合,甲債権の譲渡につきAがBに対して通知する前において,AのBに対する売買目的物の引渡債務が既に履行期が到来しているにもかかわらず履行されていないときは,Bは,Cからの甲債権の弁済請求に対して売買目的物の引渡債務との同時履行の抗弁を主張することができる。民法この問題の模試受験生正解率 85.8%結果正解解説民法468条1項は,債務者は,対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるとしている。ここでいう「譲渡人に対して生じた事由」とは,例えば,債務者が譲渡人に対して弁済した事実,債権を発生させた契約についての無効,取消し,解除が発生した事実,同時履行の抗弁などである。本記述の場合,甲債権は,AB間の売買契約により生じた代金債権であり,売買契約により生じたAのBに対する目的物引渡債務は,甲債権の譲渡につき債務者対抗要件となるAのBに対する通知(同467条1項)の前において,既に履行期が到来しているにもかかわらず履行されていない。したがって,Bは,債権譲渡の対抗要件具備時までにAに対して同時履行の抗弁権を有しており,甲債権の譲受人であるCからの弁済請求に対して,目的物引渡債務との同時履行の抗弁を主張することができる。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ277~278頁。
潮見(プラクティス債総)501頁。
中田(債総)653頁。
平野(債総)323頁。
平野(債各Ⅰ)56~62頁。
論点体系判例民法(5)18頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,住所不定である実弟乙がたまたま甲宅に来訪した際,乙がVから窃取したパソコンの保管を依頼され,同パソコンは乙が窃取したものであることを知りつつ,これを乙のために保管した。この場合,甲に盗品等保管罪が成立するが,その刑は免除される。刑法この問題の模試受験生正解率 32.8%結果正解解説同居の親族との間で盗品等保管罪を犯した者には,親族等の間の犯罪に関する特例(刑法257条1項)が適用され,その刑が免除されるところ,同項の「同居」とは,同一の場所で日常生活を共にし,定住性がある場合をいう(最決昭32.11.19)。本記述において,甲は,親族である乙との間で同罪を犯しているが,乙は,住所不定であり,たまたま甲宅を来訪したにすぎないことから,甲と同一の場所で日常生活を共にし,定住性があるとはいえず,甲と「同居」しているとはいえない。したがって,甲に盗品等保管罪が成立するが,同項は適用されないため,その刑は免除されない。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義各)363頁。
条解刑法825頁。
昭32最高裁解説(刑事)586~588頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法判例によれば,憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから,憲法は,政党の存在を当然に予定しているものというべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 80.4%結果正解解説判例は,株主が会社の代表取締役による政党への政治献金の責任を追及した事例において,「憲法は政党について規定するところがなく,これに特別の地位を与えてはいないのであるが,憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから,憲法は,政党の存在を当然に予定しているものというべきであり,政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである」としている(最大判昭45.6.24 八幡製鉄事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕8事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)に関して,個人根保証契約は,個人貸金等根保証契約に限り,書面又は電磁的記録で極度額を定めなければ効力が生じない。
なお,個人根保証契約とは,根保証契約であって保証人が法人でないものをいい,個人貸金等根保証契約とは,個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。民法この問題の模試受験生正解率 15.3%結果正解解説民法465条の2第1項は,一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負うとしている。そして,同条2項は,個人根保証契約は,同条1項に規定する極度額を定めなければ,その効力が生じないとしている。したがって,個人貸金等根保証契約に限らず,全ての個人根保証契約は,極度額を定めなければその効力が生じない。さらに,同条3項は,同446条2項,3項の規定を個人根保証契約における極度額の定めについて準用しているので,極度額は,書面又は電磁的記録により定めなければならない。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ434~435頁。
潮見(プラクティス債総)679頁。
中田(債総)606~607頁。
平野(債総)294頁。
論点体系判例民法(4)420頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙宅の居間の金庫に多額の現金が入っていることを知り,これを盗む目的で,乙宅の裏口の無施錠のドアから入ったが,乙にその場で発見されたため,慌てて逃走した。甲に窃盗罪の実行の着手が認められる。刑法この問題の模試受験生正解率 52.0%結果正解解説窃盗罪(刑法235条)の実行の着手(同43条本文)は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められる。具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,犯行の日時・場所等の諸般の事情を考慮することになるが,通常の住宅等への侵入窃盗の場合には,侵入しただけでは窃盗罪の実行の着手とは認められない(最判昭23.4.17)。したがって,甲は乙宅の裏口の無施錠のドアから入ったところ,その場で乙に発見されたため,逃走しているから,窃盗罪の実行の着手は認められない。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)162頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)256頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法では,憲法改正について国民の承認を得たときは,天皇は「国民の名で,この憲法と一体を成すものとして」公布すると規定されており,この公布により憲法改正が成立することになる。憲法この問題の模試受験生正解率 24.3%結果正解解説憲法改正について国民の承認があった場合,天皇は「国民の名で,この憲法と一体を成すものとして」公布する(憲法96条2項,7条1号)。公布は成立した国法を国民に広く知らせる行為で,国法の成立要件ではない。憲法改正は国民の承認を経た段階で確定的に成立している。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)408頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)410~411頁。
新基本法コメ(憲法)504頁。 -
民法贈与者は,贈与の目的である特定物を,贈与契約が締結された時の状態で引き渡すことを約したものと推定され,この推定が覆されない限り,担保責任を負わない。民法この問題の模試受験生正解率 60.2%結果正解解説民法551条1項は,贈与者は,贈与の目的である物又は権利を,贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し,又は移転することを約したものと推定するとしている。これは,贈与者の債務内容を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し,又は移転することを約したという推定をし,性能や品質に問題があってもその状態で引き渡すことを義務付けられているだけであり,この推定が覆されない限り担保責任を負うことはないものとしたものである。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)119~120頁。
平野(債各Ⅰ)145頁。
民法SⅣ75~76頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,公務執行妨害罪は,公務員を特別に保護する趣旨ではなく,公務員によって執行される公務そのものを保護するものである。刑法この問題の模試受験生正解率 84.0%結果正解解説判例は,「刑法95条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく公務員によって執行される公務そのものを保護するものである」としている(最判昭28.10.2)。よって,本記述は正しい。参考西田(各)444頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)488頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国家権力を単一の国家機関に集中させず,その性質に応じて異なる国家機関に担当させることで,相互の抑制と均衡を図る権力分立制は,憲法保障制度の一つといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説憲法の最高法規性は,法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ,ゆがめられるという事態が生じるので,このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し,又は事後に是正するための装置を,あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。そのような装置を憲法保障制度という。憲法保障制度の分類にもいくつかあるが,憲法自身に定められているものと憲法には定められていないが超法規的な根拠によって認められるものとに分ける分類がある。
権力分立とは,国家権力を単一の国家機関に集中させることなく,その性質に応じて,立法・行政・司法の異なる機関に担当させることで,相互の抑制と均衡を保たせる制度をいう。権力分立制度の採用(憲法41条,65条,76条)は,上記の分類によれば,憲法自身に定められている憲法保障制度の一つである。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)297~299頁,386頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)399頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)24頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,Aが所有し,Bのための通行地役権が設定されている甲土地を,Cが無断で占拠してBの通行を妨げている場合,Bは,Cに対し,甲土地を自己に明け渡すよう請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 40.9%結果正解解説地役権は,設定行為で定めた目的に従い,他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する用益物権である(民法280条本文)。地役権も物権であるから,地役権者は,その侵害者に対し,物権的請求権を行使することができる。もっとも,地役権は,承役地を占有すべき権利を含まないから,物権的請求権のうち妨害排除請求権及び妨害予防請求権のみ認められ,返還請求権は認められない。したがって,本記述において,Bは,Cに対し,甲土地を自己に明け渡すよう請求することはできない。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)249頁。
リーガルクエスト(物権)205頁。
新版注釈民法(6)126頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,公然と事実を摘示して乙に対し軽べつの意を表した。この場合,甲に侮辱罪が成立する余地はない。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第28条が保障する労働基本権は,国民一般ではなく,勤労者にだけ保障される権利であり,そこには団結権,団体交渉権,争議権が含まれる。もっとも,勤労者の中でも公務員については,その職務の性質上,法令により労働基本権が制限されており,労働三権全てについて否定されている職種も存在する。憲法この問題の模試受験生正解率 49.6%結果正解解説憲法28条が保障する労働基本権は,国民一般ではなく,「勤労者」にだけ保障される権利である。具体的には,団結権,団体交渉権,争議権の三つからなり,それは労働三権ともいわれる。同条にいう「勤労者」とは,自己の労働力を提供して対価を得て生活する者であり,公務員もこれに含まれるが,公務員の職務の性質上,法令により労働基本権について制限がなされている。例えば,警察職員,消防職員,自衛隊員,海上保安庁又は刑事施設に勤務する職員には,団結権,団体交渉権,争議権の全てが否定されている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)287~289頁。
安西ほか(憲法学読本)245頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,Aが,Bとの不倫関係を維持する目的で,その所有する登記されている甲不動産をBに贈与し,引き渡した場合,Bは,所有権移転登記手続がされていなくても,甲不動産の所有権を取得する。民法この問題の模試受験生正解率 73.9%結果正解解説不法な原因のために給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない(民法708条本文)。そして,判例は,不倫関係を継続する目的で未登記建物の贈与契約が締結され,当該建物が受贈者に引き渡された事例において,当該贈与が公序良俗に反して無効であり,したがって,贈与による所有権の移転が認められない場合であっても,当該贈与に基づく履行行為が同条本文にいわゆる不法原因給付に当たるときは,その建物の所有権は受贈者に帰属するに至ったものと解するとしている(最大判昭45.10.21 民法百選Ⅱ〔第8版〕82事件)。その理由として,同判決は,「同条は,みずから反社会的な行為をした者に対しては,その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を規定したものと認められるから,給付者は,不当利得に基づく返還請求をすることが許されないばかりでなく,目的物の所有権が自己にあることを理由として,給付した物の返還を請求することも許されない筋合であるというべきである。かように,贈与者において給付した物の返還を請求できなくなったときは,その反射的効果として,目的物の所有権は贈与者の手を離れて受贈者に帰属するにいたったものと解するのが,最も事柄の実質に適合し,かつ,法律関係を明確ならしめる所以と考えられる」ことを挙げている。また,判例は,既登記建物の贈与においては,引渡しだけでは同条本文における「給付」には当たらず,所有権移転登記がされて初めて「給付」があったといえるとしている(最判昭46.10.28)。したがって,本記述においては,贈与の目的物である甲不動産の所有権はBに帰属しない。よって,本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)354~355頁。
リーガルクエスト(事務管理・不当利得・不法行為)58~59頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,次の記述の正誤(〇・×)を答えなさい。甲は,自動車を運転中,自転車で通行中のVに自動車を過って衝突させてVを同車の屋根に跳ね上げ,その意識を喪失させたが,Vに気付かないまま同車の運転を続けるうち,同車の助手席に同乗していた乙がVに気付き,走行中の同車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転落させた。Vは,頭部打撲に基づくくも膜下出血等により死亡したところ,同傷害は,自動車と衝突した際に生じたものか,乙の引きずり降ろしによって生じたものかは不明であった。この場合,甲の衝突行為とVの死亡の結果との間には,因果関係がある。刑法この問題の模試受験生正解率 92.0%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者を引きずり降ろし,アスファルト舗装道路上に転落させる行為は,経験則上,普通,予想することができないものであり,加えて,被害者の死因となった頭部の傷害が,被告人の過失による衝突行為によるか,同乗者の上記行為によるか確定し難いという場合においては,被告人の上記過失行為から被害者の上記死の結果が発生することが,われわれの経験則上当然予想し得られるところであるとは到底いえないとして,被告人の衝突行為と被害者の死の結果との間の因果関係を否定している(最決昭42.10.24 刑法百選Ⅰ〔第7版〕9事件)。したがって,本記述において,甲の衝突行為とVの死亡の結果との間には,因果関係はない。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)36~37頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)77~78頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法刑事補償請求権に関して,判例によれば,刑事訴訟法上の手続における無罪の確定裁判だけでなく,少年審判の手続における不処分決定事件のうち,非行事実の不存在を理由とする不処分決定である場合には,憲法第40条の「無罪の裁判」に含まれる。憲法この問題の模試受験生正解率 57.9%結果正解解説判例は,少年審判手続において非行事実の不存在を理由として不処分決定を受けた者が刑事補償を請求した事例において,「刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」とは,同項及び関係の諸規定から明らかなとおり,刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ,不処分決定は,刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定である上,右決定を経た事件について,刑事訴追をし,又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから,非行事実が認められないことを理由とするものであっても,刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであり,このように解しても憲法40条及び14条に違反しない」としている(最決平3.3.29 憲法百選Ⅱ〔第7版〕130事件)。よって,本記述は誤りである。
なお,同決定を受けて,平成4年に「少年の保護事件に係る補償に関する法律」が制定され,審判が開始せず又は保護処分に付さない旨の判断が下され,その決定が確定した場合,補償が認められることになった。参考安西ほか(憲法学読本)227頁。
新基本法コメ(憲法)290~291頁。 -
民法AがBに対して預貯金債権以外の金銭債権である甲債権を有し,AがCに対して甲債権を譲渡した。この場合に関して,判例の趣旨に照らすと,甲債権の譲渡についてのBの承諾が,Aに対してされた場合でも,Cは,当該譲渡をBに対抗することができる。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙から,「Vの所有する掛け軸を盗んでくるので,売却先を探してほしい。」との依頼を受け,乙が将来窃取すべき掛け軸の売却をあっせんした。この場合,甲に盗品等有償処分あっせん罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 32.8%結果正解解説判例は,窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却をあっせんしても,盗品等有償処分あっせん罪(刑法256条2項)は成立しないとしている(最決昭35.12.13)。したがって,甲に盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)352頁。
条解刑法822~823頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法政党が党議拘束に従わない国会議員を懲戒処分に付することは,その効果が政党内にとどまるか否かにかかわらず,国会議員が憲法第43条第1項にいう「全国民を代表する」ことと矛盾抵触すると考えざるを得ないことになる。憲法この問題の模試受験生正解率 80.4%結果正解解説国会議員は,全国民の代表であり,支持母体等の具体的指示に法的に拘束されることなく,議会において自己の信念に基づいてのみ発言・表決する(自由委任の原則 憲法43条1項)。他方,政党は国会内で一体として行動するために,その所属議員に対して党議拘束を加えることがある。そこで,同項と党議拘束との関係が問題となるが,国会議員は,所属政党の決定に従って行動することにより国民の代表者としての実質を発揮できるといえるし,また,政党が,党議拘束に従わない国会議員を懲戒処分に付することは,本来その政党により自律的に決せられるべき内部事項である。したがって,懲戒処分の効果が,党からの除名をもって議員資格を喪失させるものであるならともかく,その効果が政党内にとどまるものである限り,党議拘束は国会議員が同項にいう「全国民を代表する」ことと矛盾抵触しないということができる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)302~304頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)93~96頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)62~63頁。
戸波(憲法)362頁。 -
民法債権者Aが,支払不能の状態にある債務者Bが受益者Cとの間でした行為につき詐害行為取消権を行使する場合に関して,Bが,その債権者を害することを知りながら,所有する不動産をCに贈与したが,その際,Cはその贈与がBの債権者を害することを知らなかった場合,Cが,BのCに対する贈与がBの債権者を害することを知っていたDに当該不動産を売却し,所有権移転登記をしたときであっても,Aは,Dに対し,当該贈与について,詐害行為取消請求をすることはできない。民法この問題の模試受験生正解率 26.4%結果正解解説債権者は,受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において,受益者に移転した財産を転得した者があるときは,その転得者が受益者から転得した者である場合には,その転得者が,転得の当時,債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限り,その転得者に対しても,詐害行為取消請求をすることができる(民法424条の5第1号)。このように,転得者に対する詐害行為取消請求をするためには,「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合」であること,すなわち,受益者に対する詐害行為取消請求の要件を満たす場合であることが必要である。本記述においては,受益者であるCは,Bから贈与を受けた当時,当該贈与がBの債権者を害することを知らなかったのであるから,AのCに対する詐害行為取消請求は認められない(同424条1項ただし書)。したがって,AのDに対する詐害行為取消請求も認められない。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ373~374頁。
潮見(プラクティス債総)251~252頁。
中田(債総)297~299頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙が所有し,管理している乙名義の更地を,自己が経営する工場の倉庫の敷地として利用しようと考え,乙に無断でその更地の登記名義を自己名義に変更したが,その上に倉庫を建築するには至らなかった。甲に不動産侵奪罪の実行の着手は認められない。刑法この問題の模試受験生正解率 52.0%結果正解解説不動産侵奪罪(刑法235条の2)の「侵奪」とは,不動産に対する他人の占有を排除し,これを自己又は第三者の占有に移すことをいう。窃盗罪との対比上,不動産を占拠する積極的な事実行為を要するので,登記簿上の名義変更をしただけでは,「侵奪」したとは認められない。したがって,甲が登記を自己名義に変更しても,同罪の実行の着手は認められない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)177頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)151頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法知る権利は,国民が情報を収集することを国家によって妨げられないという自由権にとどまらず,積極的に政府に対し情報の公開を求める権利でもあるところ,後者の権利が基本的に自由権を規定する憲法第21条によって保障されているとしても,個々の国民が裁判上当該権利を行使するためには,法律による具体化が必要であると解されている。憲法この問題の模試受験生正解率 64.3%結果正解解説表現の自由は,単に表現の送り手の自由だけでなく,表現の受け手の自由をも含むものであり,この表現の受け手の自由が「知る権利」として捉えられている。そして,知る権利は,国民が情報を収集することを国家によって妨げられないという自由権にとどまらず,積極的に政府に対し情報の公開を求める権利でもある。後者のような情報公開請求権が,基本的に自由権を規定するものである憲法21条から導かれるかどうかについては,疑問も提起されている。仮に情報公開請求権が同条によって保障されているとしても,個々の国民が裁判上情報公開請求権を行使するためには,法律による具体化が必要であると解されている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)180~181頁。
安西ほか(憲法学読本)158~160頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)353頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)246頁。 -
民法民法第1050条が定める特別の寄与に関して,特別寄与料を請求するためには,労務の提供が無償で行われたか,有償で行われたかを問わない。民法この問題の模試受験生正解率 14.8%結果正解解説相続人ではないが,被相続人の親族であって,被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(特別寄与者)は,相続が開始した後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる(民法1050条1項)。相続とは別の枠組みで,相続人以外の者による貢献を考慮するものであり,平成30年7月の改正によって新設された制度である。なお,被相続人に対して療養看護等の貢献をした者が相続財産から分配を受けることを認める制度として寄与分の制度があるが,寄与分は,相続人にのみ認められるものであり(同904条の2第1項),遺産分割手続の中で考慮されるなど,特別の寄与の制度とは様々な違いがある。
特別寄与料の請求が認められるためには,「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが必要である(民法1050条1項)。したがって,労務の提供が有償で行われていたときは,特別寄与料の請求は認められない。よって,本記述は誤りである。参考潮見(詳解相続法)349~350頁。
潮見(詳解相続法)352頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは,公務員が職務の遂行に直接必要な行為を現に行っている場合に限られる。刑法この問題の模試受験生正解率 32.8%結果正解解説判例は,公務執行妨害罪における「職務を執行するに当たり」について,「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲及びまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離しえない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為をいう」とした上で,「職務の性質によっては,その内容,職務執行の過程を個別的に分断して部分的にそれぞれの開始,終了を論ずることが不自然かつ不可能であって,ある程度継続した一連の職務として把握することが相当と考えられるものがあ」るとして,一時中断中の職務に対する公務執行妨害罪の成立を認めている(最判昭53.6.29 刑法百選Ⅱ〔第2版〕104事件)。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)446~447頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)493~495頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国会議員は,院外における現行犯の場合を除いては,国会の会期中逮捕されないことが憲法上保障されている。憲法この問題の模試受験生正解率 29.4%結果正解解説憲法50条前段は,「両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕され」ない旨規定している。いわゆる国会議員の不逮捕特権である。したがって,憲法上,国会議員は,院外における現行犯の場合を除いては,国会の会期中逮捕されないとされているわけではない。よって,本記述は誤りである。
なお,現行法が定める不逮捕特権の例外は,「院外における現行犯罪の場合」並びに「院の許諾」がある場合である(国会法33条)。参考芦部(憲法)318~319頁。
安西ほか(読本)292~293頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)101~103頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,契約の申込みを受けた者が,その申込みに条件を付してこれを承諾し,これが相手方に到達した後に,改めて条件を付さずに承諾したとしても,契約は成立しない。民法この問題の模試受験生正解率 61.2%結果正解解説承諾者が,申込みに条件を付し,その他変更を加えてこれを承諾したときは,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる(民法528条)。同条によって申込みの拒絶とみなされた場合,第一次の申込みの効力は失われるから,条件を付した承諾をした後に改めて無条件の承諾をしたとしても,契約は成立しない。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)20頁。
平野(債各Ⅰ)42頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙から,「Vから窃取した宝石を売却したい。」との相談を受け,宝石商であるAを乙に紹介した。この場合,実際に乙とAとの間に同宝石の売買契約が締結されなかったとしても,甲に盗品等有償処分あっせん罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 32.8%結果正解解説判例は,盗品等に関する罪の本質は,盗品等を転々とさせて被害者の返還請求権の行使を困難若しくは不可能にさせる点にあるので,盗品と知りながら盗品の売買を仲介又はあっせんした事実があれば,あっせんに係る盗品の売買が成立しなくても,盗品等有償処分あっせん罪が成立するとしている(最判昭23.11.9 刑法百選Ⅱ〔第5版〕69事件)。したがって,甲に盗品等有償処分あっせん罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(刑法)355頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)350頁。
条解刑法822~823頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法国家緊急権とは,戦争・内乱や自然災害等の非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が憲法秩序を一時停止して非常措置を執る権限とされるが,日本国憲法に国家緊急権についての規定は存在しない。憲法この問題の模試受験生正解率 80.3%結果正解解説憲法の最高法規性は,法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ,ゆがめられるという事態が生じるので,このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し,又は事後に是正するための装置を,あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。そのような装置を憲法保障制度という。憲法保障制度の分類にもいくつかあるが,憲法自身に定められているものと憲法には定められていないが超法規的な根拠によって認められるものとに分ける分類がある。後者の例としては,抵抗権と国家緊急権が挙げられる。そのうち,国家緊急権とは,戦争・内乱や自然災害等の非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が憲法秩序を一時停止して非常措置を執る権限のことである。大日本帝国憲法には,緊急命令権(同8条),戒厳大権(同14条),非常大権(同31条)などの規定があったが,日本国憲法には国家緊急権についての規定は存在しない。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)186頁。
安西ほか(憲法学読本)361~362頁。
新・コンメ憲法773頁,775頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,Aが所有する甲土地上に,Bが無断で樹木の苗木を植栽した場合,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づき当該苗木を収去するよう請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 40.9%結果正解解説判例は,苗木を植え付けてこれを維持管理するにつき正当な権原を有することなく,苗木を植え付けて原告の所有する土地を占有している被告に対して,原告が,苗木を抜去して当該土地を明け渡すことを求めた事例において,「権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は,民法242条本文の規定に従い,土地に附合し,土地所有者がその所有権を取得するものと解される」から,上記苗木は被告の所有に属するものではなく,したがって,被告において原告に対しこれを収去する義務を負うものではないというべきであるとしている(最判昭46.11.16)。したがって,本記述において,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づいて,Bが甲土地に植栽した樹木の苗木を収去するよう請求することはできない。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)178頁。
平野(物権)300頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,公然と公知の事実を摘示して乙の社会的評価を害した。この場合,甲に名誉毀損罪が成立する余地はない。刑法この問題の模試受験生正解率 58.4%結果正解解説名誉毀損罪(刑法230条1項)にいう摘示される事実は,必ずしも非公知のものに限らない。公知の事実であっても,それを摘示することにより,更に名誉を低下させるおそれがある限り,同罪が成立する(大判大5.12.13)。したがって,甲には名誉毀損罪が成立する余地がある。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)124頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)99頁。
条解刑法675~676頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第14条第1項の平等の要請は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨であると解され,特に同項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには,合憲性の推定は排除され,裁判所は厳格な基準によってその差別が合理的であるかどうかを審査すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 41.1%結果正解解説判例は,削除前の刑法200条所定の尊属殺人罪で起訴された被告人が,同条は憲法14条1項に違反すると主張した事例において,「憲法14条1項は,国民に対し法の下の平等を保障した規定であって,同項後段列挙の事項は例示的なものであること,およびこの平等の要請は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり,差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき」であるとしている(最大判昭48.4.4 尊属殺重罰規定判決 憲法百選Ⅰ〔第7版〕25事件)。同判決は,同条の意義を相対的平等であると理解している。しかし,同条1項後段列挙の事項は例示にすぎないとして,本記述のような特別な法的意味を認めていない。よって,本記述は誤りである。
なお,後掲最大判昭60.3.27の伊藤正己裁判官補足意見は,「憲法14条1項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには,合憲性の推定は排除され,裁判所は厳格な基準によってその差別が合理的であるかどうかを審査すべきであ」るとしている。 -
民法債権が差し押さえられ,差押命令が第三債務者に送達された場合において,第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,差押債権者は,その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 54.8%結果正解解説民法481条1項は,差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,差押債権者は,その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができるとしており,差押命令は債務者及び第三債務者に送達され(民事執行法145条3項),第三債務者に送達された時に差押えの効力が生じる(同条5項)。民法481条1項は,第三債務者が差押債務者に対してした弁済は,差押債務者に対する関係では弁済として有効であるが,これを差押債権者には対抗することができず,差押債権者は,差押債務者の債権が存在するものとしてこれを取り立てることができる旨を規定したものである。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ40~41頁。
潮見(プラクティス債総)328頁。
中田(債総)384頁。
平野(債総)356頁。
新・コンメ民法818頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,次の記述の正誤(〇・×)を答えなさい。
甲は,夜明け前の暗い高速道路を走行中,同方向に進行していた大型トレーラーを運転するAの運転態度に腹を立てたため,Aの車両(以下「A車」という。)を相応の交通量のある第3通行帯(追越し車線)に停止させ,A車から降りてきたAに暴行を加えた。甲が自車で走り去ってから7,8分後までAがその場にA車を停車させ続けたところ,後続車がA車に衝突し,後続車の運転手Vが死亡した。AがA車を直ちに発進させなかったことが,甲から暴行を受けた際にエンジンキーを紛失したと勘違いし周囲を探していたという事情によるものであった場合であっても,甲がA車を停止させた行為とVの死亡の結果との間には,因果関係がある。刑法この問題の模試受験生正解率 92.0%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,高速道路の第3通行帯(追越し車線)上に自車及びA車を停止させたという被告人の過失行為は,「後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有していたというべきである」とした上で,「本件事故は,被告人の上記過失行為の後,Aが,自らエンジンキーをズボンのポケットに入れたことを失念し周囲を捜すなどして,被告人車が本件現場を走り去ってから7,8分後まで,危険な本件現場に自車を停止させ続けたことなど,少なからぬ他人の行動等が介在して発生したものであるが,それらは被告人の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったといえる」として,被告人の過失行為と被害者の死傷との間には因果関係があるとしている(最決平16.10.19 平16重判刑法2事件)。したがって,本記述において,甲がA車を停止させた行為とVの死亡の結果との間には,因果関係がある。よって,本記述は正しい。参考山口(刑法)38頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)77~78頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所裁判官国民審査は,現行法上,審査人が罷免を可とする裁判官の欄に「×」印を付けるという投票方法を定めているが,判例によれば,国民審査制度は解職の制度であるから,何も記載されていない投票全てについて罷免を可とするものではないとの効果を生じさせても憲法に反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 65.3%結果正解解説最高裁判所裁判官国民審査は,現行法上,罷免を可とすべき裁判官の欄に×印を付け,そうでない場合には何も記入しないという投票方法を採用している(最高裁判所裁判官国民審査法14条,15条)が,この方法には,罷免の可否について不明な者の票を罷免を可としない票に数えるなどの問題点が指摘されている。この点について,判例は,「国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度」であって,「積極的に罷免を可とするもの」が,「そうでないもの」よりも多数であるか否かを知ろうとする制度であるとした上で,「罷免する方がいいか悪いかわからない者は,積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから,そういう者の投票は……後者の方に入るのが当然である。それ故法が連記投票にして,特に罷免すべきものと思う裁判官にだけ×印をつけ,それ以外の裁判官については何も記さずに投票させ,×印のないものを「罷免を可としない投票」……の数に算えたのは……,憲法の規定する国民審査制度の趣旨に合するものである」としている(最大判昭27.2.20 憲法百選Ⅱ〔第7版〕178事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)361~362頁。
安西ほか(憲法学読本)319頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)251頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)286頁。 -
民法AがBに対して預貯金債権以外の金銭債権である甲債権を有し,AがCに対して甲債権を譲渡した。この場合に関して,判例の趣旨に照らすと,AがCに甲債権を譲渡した後,Dにも甲債権を譲渡し,AがBに対してそれぞれの譲渡につき確定日付のある証書によって通知をした場合,これらの通知が同時にBに到達したときは,Bは,Dからの請求に対して同順位の譲受人であるCが存在することを理由として弁済を拒むことができる。民法この問題の模試受験生正解率 85.8%結果正解解説債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには,確定日付のある証書による通知又は承諾があることが必要である(民法467条2項)。債権が二重に譲渡された場合,複数の確定日付のある証書による通知が債務者に到達することがあり得るが,この場合の優劣の判断基準について,判例は,確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時の先後によって決すべきであるとしている(最判昭49.3.7 民法百選Ⅱ〔第8版〕29事件)。そうすると,本記述のように,確定日付のある証書による複数の通知が同時に債務者であるBに到達した場合には,譲受人であるCD間の優劣を決することができないことになるが,この点について,別の判例は,「指名債権が二重に譲渡され,確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは,各譲受人は,第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ,譲受人の一人から弁済の請求を受けた第三債務者は,他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り,単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできない」としている(最判昭55.1.11 民法百選Ⅱ〔第4版〕33事件)。したがって,本記述においても,Bは,Dからの請求に対して同順位の譲受人であるCが存在することを理由として弁済を拒むことはできない。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ267~270頁。
潮見(プラクティス債総)520~522頁。
中田(債総)669~671頁。
平野(債総)330~331頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙が1年前にV宅から窃取した自転車を善意無過失の丙に売却したことを知り,同自転車は乙が窃取したものであることを知りつつ,これを丙から買い受けた。この場合,甲に盗品等有償譲受け罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 32.8%結果正解解説判例は,盗品等に関する罪は,被害者の財産権の保護を目的とするものであることを理由に,被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない期間内においては,盗品等に関する罪が成立するとしている(最決昭34.2.9)。そして,盗品については,被害者は盗難の時から2年間その盗品の回復を請求することができるため(民法193条),その期間内であれば盗品性は失われず,その物について盗品等に関する罪が成立する。したがって,乙が1年前にV宅から窃取した自転車の盗品性は失われておらず,甲に盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)352頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)345頁。
条解刑法819頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法閣議の決定は,慣例上全員一致でなければならないとされており,一部の国務大臣が閣議の決定に反対した場合には,内閣は総辞職しなければならない。憲法この問題の模試受験生正解率 83.7%結果正解解説内閣の運営方法,すなわちその意思決定及び活動方法について,憲法に規定はない。内閣法によれば,「内閣がその職権を行うのは,閣議によるものとする。」(同4条1項)。そして,大日本帝国憲法下からの慣例により,閣議の議事は全員一致で決められる。内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負い(憲法66条3項),閣議の決定に反対する国務大臣であっても閣内にとどまる限り,連帯して責任を負うところ,当該国務大臣が内閣と一体となって行動できない場合には,自ら辞職するか内閣総理大臣による罷免(同68条2項)が考えられる。しかし,一部の国務大臣が閣議の決定に反対したからといって,内閣が総辞職しなければならないことになるわけではない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)339~340頁。
佐藤幸(日本国憲法論)495~496頁,504~505頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)218~222頁。 -
民法売主が契約の内容に適合しない権利を買主に移転した場合において,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,買主は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。民法この問題の模試受験生正解率 26.4%結果正解解説売主が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものを買主に引き渡したときは,買主は,売主に対し,履行の追完の請求(民法562条),代金の減額の請求(同563条),損害賠償の請求及び契約の解除(同564条)をすることができ,これらの規定は,売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合についても準用される(同565条)。そして,売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合については,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,買主は,その不適合を理由として履行追完請求,代金減額請求,損害賠償請求,契約の解除をすることができなくなる(同566条本文)。このような期間制限が設けられたのは,目的物の引渡し後は履行が終了したとの期待が売主に生じ,この期待を保護する必要があると考えられること,物の種類・品質面での不適合の有無は目的物の使用や時間経過による劣化等により比較的短期間で判断が困難となるから,短期の期間制限を設けて法律関係を早期に安定させる必要があることによる。しかし,引き渡された目的物が数量に関して契約の内容に適合しない場合及び移転した権利が契約の内容に適合しない場合における不適合責任については,上記のような期間制限は設けられていない。数量についての不適合は,引渡しをする売主にとっては比較的容易に判断できることから,なすべきことを完了したことについての売主の期待を特に保護する必要はないと考えられることによる。また,権利に関する不適合については,売主が契約の趣旨に適合した権利を移転したという期待を抱くことは想定しがたく,また,短期間で契約不適合の判断が困難になるともいいがたいことによる。したがって,売主が契約の内容に適合しない権利を買主に移転した場合には,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなくても,買主は,履行追完請求等をすることができる。よって,本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)105~106頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,偽造通貨行使罪にいう「行使」に当たるためには,偽造通貨の使用方法が適法である必要はないから,偽造通貨を賭博の賭金として使用した場合も,「行使」に当たる。刑法この問題の模試受験生正解率 61.8%結果正解解説偽造通貨行使罪(刑法148条2項)にいう「行使」とは,偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことをいい(大判明37.5.13),真正な通貨として流通に置くものであれば,使用方法の適法・違法は問わない。判例も,偽造通貨を賭博の賭金として使用した場合に,偽造通貨行使罪が成立するとしている(大判明41.9.4)。よって,本記述は正しい。参考山口(各)424頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)439~440頁。
条解刑法414頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法参議院の緊急集会で採られた措置は,臨時のものであって,次の国会開会後,10日以内に衆議院の同意がない場合には,その効力を失う。憲法この問題の模試受験生正解率 25.8%結果正解解説参議院の緊急集会とは,衆議院が解散されて総選挙が施行され,新たな国会(特別会)が召集されるまでの間に,緊急に国会の議決を必要とする事態が生じたとき,それに応えて国会の権能を代行するという制度である(憲法54条2項ただし書)。この緊急集会で採られた措置は,「臨時のものであつて,次の国会開会の後10日以内に,衆議院の同意がない場合には,その効力を失ふ。」(同条3項)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)321~322頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)119~122頁。 -
民法16歳の未成年者Aの法定代理人が,Aが法定代理人の同意を得ずに自己が所有する不動産の売買契約を締結したのを知ってから5年間,取消権を行使しなかった場合であっても,Aは,固有の取消権を行使することができる。民法この問題の模試受験生正解率 59.8%結果正解解説未成年者の法定代理人は,未成年者の行為を知った時から,追認をなし得るようになり(民法124条1項,2項1号参照),その時から5年で取消権が時効によって消滅する(同126条前段)。そして,未成年者の法定代理人の取消権が時効によって消滅すれば,本人の取消権も消滅すると解されている。これは,どちらの取消権も発生原因が同一である上,法律関係を可及的速やかに安定させるという同条の趣旨に沿うからである。したがって,本記述において,未成年者Aの法定代理人が,Aが売買契約を締結したのを知ってから5年間,取消権を行使しなかった場合,法定代理人の取消権が消滅するのに伴い,Aの固有の取消権も消滅する。よって,本記述は誤りである。参考平野(総則)228頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,12歳の乙女の承諾を得て,同女に対してわいせつな行為をした。この場合,甲には強制わいせつ罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 80.0%結果正解解説13歳未満の者にわいせつな行為をした場合,被害者の承諾の有無にかかわらず,強制わいせつ罪が成立する(刑法176条後段)。したがって,甲には強制わいせつ罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(刑法)244頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)159頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,道路交通法上の規定に基づく警察官の呼気検査は,飲酒運転を防止することを目的としてアルコール保有の程度を調査するものであって,運転者から供述を得ようとするものではないから,これを拒んだ者を処罰する旨の道路交通法の規定は,憲法第38条第1項に違反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 87.3%結果正解解説判例は,酒気帯び運転のおそれがあるとして,警察官から,道路交通法上の呼気検査に応じるよう要求された者が,これを拒否したため,同法上の呼気検査拒否罪に問われた事例において,呼気検査の手続が憲法38条1項の禁止する「自己に不利益な供述」の強要に当たるか否かにつき,「憲法38条1項は,刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ,右検査は,酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって,その供述を得ようとするものではないから,右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は,憲法38条1項に違反するものではない」としている(最判平9.1.30 刑訴法百選〔第10版〕A9事件)。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)346頁。
渋谷(憲法)246~247頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合,債権者と代位者は,特段の事情がない限り,その債権を被担保債権とする抵当権の実行による売却代金につき,債権者が有する残債権額と代位者が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。民法この問題の模試受験生正解率 41.3%結果正解解説債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその権利を行使することができ(民法502条1項),又は,債権者は単独でその権利を行使することができる(同条2項)。そして,これらの場合に債権者が行使する権利は,その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について,代位者が行使する権利に優先する(同条3項)。したがって,一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合,債権者と代位弁済者は,その債権を被担保債権とする抵当権の実行による売却代金につき,債権者が代位者に優先して弁済を受ける。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ89~90頁。
潮見(プラクティス債総)371~373頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,脅迫罪において告知される加害行為は,犯罪を構成することを要する。刑法この問題の模試受験生正解率 69.8%結果正解解説判例は,加害の内容が告訴する意思がないのに告訴すると通知することでもよいとしており(大判大3.12.1),脅迫罪(刑法222条)において告知される加害行為が犯罪を構成することを要しないとの前提をとっている。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)230頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)49頁。
大コメ(刑法・第3版)(11)463頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法両議院の会議及び両院協議会は公開が原則であるが,いずれも出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会とすることができる。憲法この問題の模試受験生正解率 25.8%結果正解解説憲法57条1項は,「両議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。」と規定している。したがって,両議院の会議(本会議)は公開が原則であり,秘密会とするためには,出席議員の3分の3以上の多数による議決が必要である。他方,両院協議会とは,両院の議決が異なる場合に,両院間の妥協を図るために設けられる協議機関であるところ,両院協議会はその性質上一切の傍聴が許されず(国会法97条),当然に秘密会となる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)323頁。
佐藤幸(日本国憲法論)451頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)134~135頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,抵当権設定者と譲渡担保権設定者は,いずれも被担保債権の弁済と担保権の設定登記の抹消登記手続ないし目的物の返還との同時履行を主張することができない。民法この問題の模試受験生正解率 56.9%結果正解解説判例は,抵当権,譲渡担保権のいずれにおいても,被担保債権の弁済と担保権の設定登記の抹消登記手続ないし目的物の返還とは,被担保債権の弁済が先履行であり,同時履行の関係には立たないとしている(抵当権につき最判昭57.1.19,譲渡担保権につき最判平6.9.8)。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ233頁,333頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,不真正不作為犯の因果関係が認められるためには,期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが,合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。刑法この問題の模試受験生正解率 80.7%結果正解解説判例は,覚せい剤の常用者である被告人が,ホテルの客室において13歳の少女に多量の覚せい剤を注射して,同女を錯乱状態に陥れたにもかかわらず,同女を同室に1人で放置したまま立ち去った事例において,「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った……時点において,直ちに被告人が救急医療を要請していれば,……同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる」場合には,被告人が救急医療の要請をすることなく同女をホテル客室に放置した行為と,同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には,因果関係が認められるとしている(最決平元.12.15 刑法百選Ⅰ〔第7版〕4事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(刑法)46~47頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)89~90頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第22条第2項後段は,国籍離脱の自由を保障しているところ,法律で外国の国籍を有することを日本の国籍離脱の条件とすることは,国籍離脱の自由に対する制約に当たると解されている。憲法この問題の模試受験生正解率 79.9%結果正解解説憲法22条2項後段は,国籍離脱の自由を保障している。この点,国籍法は外国の国籍を有することを日本の国籍離脱の条件としていること(同11条~13条)は,国籍離脱の自由の制約に当たらないと解されている。なぜなら,国際法において,無国籍の防止が望まれていること,国籍唯一の原則が理想とされていることから,憲法22条2項後段は,無国籍になる自由を保障するものではないと解されているからである。したがって,上記国籍法の規定は,同項後段で保障している国籍離脱の自由の制約に当たらない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)241頁。
佐藤幸(日本国憲法論)109~110頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)470頁。
注解憲法Ⅱ116頁。
注釈日本国憲法(2)479頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,債権の消滅時効が完成した場合であっても,債務者が時効完成前に時効の利益を放棄していたときは,債務者は,その時効を援用することができない。民法この問題の模試受験生正解率 85.1%結果正解解説時効の利益は,あらかじめ放棄することができない(民法146条)。これは,債権者が債務者に時効の利益の放棄を強制することを防ぎ,永続する事実状態の尊重という時効制度の趣旨を貫くためである。そして,同条にいう「あらかじめ」とは,時効完成前を意味する。したがって,債権の消滅時効が完成した場合,債務者が時効完成前に時効の利益を放棄していたときであっても,その放棄は無効であるから,債務者は,その時効を援用することができる。よって,本記述は誤りである。
なお,時効完成前になされた時効の利益の放棄が,相手方の権利を承認するものであれば,時効の更新の効力を生じる(同152条1項)。参考佐久間(総則)439頁。
我妻・有泉コメ293頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙から金銭が入っている封かんされた封筒を一時的に預かっていたが,乙に無断で封を開けて,その中に入っていた金銭の一部を遊興費として費消した。この場合,甲には,横領罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 33.7%結果正解解説判例は,委託された封かん物について,封かん物全体の占有は受託者にあるが,内容物の占有は委託者にあるとしている(最決昭32.4.25 刑法百選Ⅱ〔第2版〕26事件)。本記述において,封かんされた封筒に入っていた金銭の占有は,委託者である乙にあるといえ,これを乙に無断で遊興費として費消した甲には窃盗罪(刑法235条)が成立する。したがって,甲に横領罪(同252条1項)は成立しない。よって,本記述は正しい。参考大谷(講義各)221頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)140~141頁。
条解刑法716頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有するものであり,その本旨に従ってこれらを行うためにその財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから,地方自治の不可欠の要素として,課税権の主体となることが憲法上予定されている。憲法この問題の模試受験生正解率 31.1%結果正解解説判例は,一定規模の法人に対して地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)上の規定に基づく道府県法定外普通税を課する旨定める県条例が,地方税法の趣旨に反し無効とされるかが争われた事例において,「普通地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有するものであり(憲法92条,94条),その本旨に従ってこれらを行うためにはその財源を自ら調達する権能を有することが必要であることからすると,普通地方公共団体は,地方自治の不可欠の要素として,その区域内における当該普通地方公共団体の役務の提供等を受ける個人又は法人に対して国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているものと解される」としている(最判平25.3.21 神奈川県臨時特例企業税事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕201事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法消費貸借は,書面をもって,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその受け取った物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約した場合,目的物の授受がされなくてもその効力を生じる。民法この問題の模試受験生正解率 51.6%結果正解解説消費貸借には,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによりその効力を生じる要物契約としての消費貸借と(民法587条),書面ですることを要件として,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその受け取った物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約することによりその効力を生じる諾成契約としての消費貸借(同587条の2第1項)の二種類がある。よって,本記述は正しい。参考潮見(基本講義・債各Ⅰ)126頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,不作為による放火罪は,作為義務違反に加え,既発の火力を積極的に利用する意図が認められなければ成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 80.7%結果正解解説判例は,不作為による現住建造物等放火罪(刑法108条)の成否が問題となった事例において,不作為による放火罪が成立するためには,既発の火力を利用する意思が必要だとの被告人側の上告趣意に対し,既発の火力により建物が焼損することを認容する意思で足りるとし,本件では,被告人に消火措置を採るべき法的作為義務があったこと,及び消火措置を採ることが容易であったことを理由に,同罪の成立を認めている(最判昭33.9.9 刑法百選Ⅰ〔第7版〕5事件)。したがって,既発の火力を積極的に利用する意図が認められなくても不作為による放火罪は成立し得る。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)49~50頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)87~88頁。
昭33最高裁解説(刑事)592頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,喫煙の自由は,憲法第13条の保障する基本権の一つに含まれるとしても,未決の者として拘禁された者に対する喫煙禁止という程度の自由の制限は,必要かつ合理的なものであるため,同条に違反するものとはいえない。憲法この問題の模試受験生正解率 82.4%結果正解解説判例は,公職選挙法違反の容疑で刑事施設(旧監獄)に収容された未決拘禁者が,当該刑事施設内において喫煙を許可されなかったことから(旧)在監者に対する喫煙を禁止した旧監獄法施工規則96条が憲法13条に違反するとして国家賠償を請求した事例において,「未決勾留は,刑事訴訟法に基づき,逃走または罪証隠滅の防止を目的として,被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ,監獄内においては,多数の被拘禁者を収容し,これを集団として管理するにあたり,その秩序を維持し,正常な状態を保持するよう配慮する必要がある」とした上で,「煙草は生活必需品とまでは断じがたく,ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず,喫煙の禁止は,煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても,それが人体に直接障害を与えるものではないのであり,かかる観点よりすれば,喫煙の自由は,憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても,あらゆる時,所において保障されなければならないものではない」とし,「このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容,制限の必要性などの関係を総合考察すると,前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は,必要かつ合理的なものであると解するのが相当であ」るとしている(最大判昭45.9.16 憲法百選Ⅰ〔第7版〕A4事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aがその所有する土地に,債権者Bのために第1順位の抵当権を,さらに,債権者Cのために第2順位の抵当権を設定し,その後に,Aが死亡し,BがAを単独で相続した場合,Bの抵当権は消滅しない。民法この問題の模試受験生正解率 48.4%結果正解解説混同とは,相対立する2つの法律上の地位ないし資格が同一人に帰属した場合において,双方を存続させておく意味がないときに,一方が他方に吸収されて消滅することをいう。そして,同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは,当該他の物権は,消滅する(民法179条1項本文)。ただし,その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは,消滅しない(同項ただし書)。
抵当目的物の所有者と抵当権者が同一人となった場合であっても,後順位抵当権者がいるときは,抵当権は消滅しない(民法179条1項ただし書)。しかし,本記述のように,抵当権者が債務者を相続することにより,抵当目的物の所有者と抵当権者が同一人となった場合には,抵当権の被担保債権が混同によって消滅し(同520条本文),付従性により抵当権も消滅する。よって,本記述は誤りである。参考我妻・有泉コメ390頁。
注釈民法(12)507頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,心神耗弱者の行為については,死刑を科すことができない。刑法この問題の模試受験生正解率 60.9%結果正解解説心神耗弱者の行為については,その刑は減軽される(刑法39条2項)。これは,心神耗弱者の行為に対しては,正常な人の行為に対するのと比べて低度の非難しかできないからである。そして,死刑を減軽するときは,無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮となる(同68条1号)。したがって,心神耗弱者の行為については,死刑を科すことができない。よって,本記述は正しい。参考大塚ほか(基本刑法Ⅰ)222頁,442頁。
条解刑法151頁,255~256頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法皇位の継承につき世襲制を採用すること及び皇位継承の資格につき男系男子主義を採用することについて,憲法は何ら規定しておらず,専ら皇室典範の定めるところに委ねている。憲法この問題の模試受験生正解率 40.4%結果正解解説憲法2条は,「皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する。」とし,皇位の継承につき世襲制を採用している。よって,本記述は誤りである。
なお,皇位継承の資格者については,憲法は定めておらず,皇室典範が「皇統に属する男系の男子」(同1条)の「皇族」(同2条1項柱書)が皇位を継承する(男系男子主義)旨定めている。参考芦部(憲法)46頁。
佐藤幸(日本国憲法論)512~514頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)113頁。 -
民法成年後見人は,成年被後見人に代わって親権を行う。民法この問題の模試受験生正解率 61.6%結果正解解説未成年後見人は,未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条1項)。親権者は,未婚の未成年者に代わって未成年者の子の親権を行うが(代行親権 同833条),同867条1項は未婚の未成年者に親権者がおらず,そのために未成年後見人が選任されている場合の規定である。しかし,成年被後見人に関して,同様の規定はない。よって,本記述は誤りである。
なお,未成年の子がいる成年の親権者に後見開始の審判(同7条)が開始されると,当該親権者はその子への親権を行うことができなくなるため(大判明39.4.2),その子に未成年後見が開始する(同838条1号前段)。参考リーガルクエスト(親族・相続)194頁。
新版注釈民法(25)251頁,451~452頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,刑法第104条にいう「証拠」には,捜査段階における参考人も含まれ,これを隠匿すれば証拠隠滅罪が成立する。(参照条文)刑法 第104条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。刑法この問題の模試受験生正解率 85.8%結果正解解説判例は,捜査段階における参考人にすぎない者も刑法104条にいう「他人の刑事事件に関する証拠」であることに変わりはなく,これを隠匿すれば証拠隠滅罪が成立するとしている(最決昭36.8.17 刑法百選Ⅱ〔第7版〕121事件)。したがって,第三者が捜査段階における参考人を隠匿した場合,当該第三者には,証拠隠滅罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(各)487頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)522頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有する。憲法この問題の模試受験生正解率 83.7%結果正解解説判例は,内閣総理大臣が当時の運輸大臣(現:国土交通大臣)に対して航空会社に特定の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けた行為が内閣総理大臣の職務権限に属するか争われた事例において,「内閣総理大臣は,憲法上,行政権を行使する内閣の首長として(66条),国務大臣の任免権(68条),内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど,内閣を統率し,行政各部を統轄調整する地位にあるものである。そして,内閣法は,閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条),内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条),行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。このように,内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには,閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと,流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため,内閣総理大臣は,少なくとも,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有する」としている(最大判平7.2.22 ロッキード事件丸紅ルート 憲法百選Ⅱ〔第7版〕174事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権として扱うべきものは,代位弁済者の債務者に対する求償権ではなく原債権である。民法この問題の模試受験生正解率 41.3%結果正解解説判例は,保証人と債務者との間で代位弁済による求償権の内容につき法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約をした場合,代位弁済をした保証人が当該特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として,弁済による代位により取得した担保権を行使することができるかが問題となった事例において,その前提として,「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために,法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり,……代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権として扱うべきものは,原債権であって,保証人の債務者に対する求償権でない」としている(最判昭59.5.29 民法百選Ⅱ〔第8版〕36事件)。よって,本記述は正しい。参考潮見(プラクティス債総)360~361頁。
平野(債総)379~380頁。 -
刑法有期の禁錮と有期の懲役とでは,前者の長期が後者の長期の2倍を超えるときでも,後者が重い刑である。刑法この問題の模試受験生正解率 63.6%結果正解解説主刑の軽重は,刑法9条の規定する順序によるものとされており(同10条1項本文),懲役と禁錮では,懲役の方が重いとされている。ただし,有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときは,禁錮が重い刑とされる(同項ただし書後段)。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)196頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)441頁。
条解刑法24頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争について,国際法上の用例を尊重し,「国家の政策としての戦争」,すなわち侵略戦争を意味するならば,同条全体により自衛戦争を含めた全ての戦争が放棄されているという結論を導くことはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 66.6%結果正解解説憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争について,国際法上の用例を尊重し,「国家の政策としての戦争」,すなわち侵略戦争を意味するならば,同項で放棄されているのは侵略戦争ということになり,自衛戦争は放棄されていないことになる。もっとも,この見解に立っても,同条2項前段の「前項の目的を達するため」にいう「前項の目的」について,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すものと解釈し,同項で戦力の保持が無条件で禁止され,また,交戦権まで否認されていると解釈するならば,同条1項で留保された自衛戦争も事実上不可能となり,同条全体で自衛戦争を含めた全ての戦争が放棄されているという結論を導くことができる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)56~58頁。
佐藤幸(日本国憲法論)93~98頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)164~168頁。
芦部(憲法学Ⅰ)255~259頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,代理権を与えられた者が,その代理権が消滅した後に,第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした場合,表見代理が成立し得る。民法この問題の模試受験生正解率 81.8%結果正解解説他人に代理権を与えた者は,代理権の消滅後に,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば,代理権消滅後の表見代理の規定(民法112条1項)によりその責任を負うべき場合において,その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは,第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為についての責任を負う(同条2項)。したがって,代理権を与えられた者が,その代理権が消滅した後に,第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした場合,表見代理が成立し得る。よって,本記述は正しい。参考佐久間(総則)270頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙の業務を妨害するため,乙に関する風説を虚偽のものであると思いつつ流布したが,その風説はたまたま真実に合致するものであった。この場合,甲には偽計業務妨害罪は成立し得ない。刑法この問題の模試受験生正解率 36.2%結果正解解説偽計業務妨害罪にいう「虚偽の風説」につき,「行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実」であるとする見解もあるが(東京地判昭49.4.25 昭50重判刑法4事件参照),判例は,虚偽とは,客観的真実に反することとしている(大判明44.12.25)。したがって,流布した風説が客観的真実に合致している限り,同罪は成立し得ない。よって,本記述は正しい。参考条解刑法691頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法臨時会とは,衆議院の解散による総選挙後に召集される国会をいい,総選挙の日から30日以内に召集される。憲法この問題の模試受験生正解率 25.8%結果正解解説衆議院の解散による総選挙後に召集される国会は,特別会(憲法54条1項)である。臨時会とは,常会のほかに,必要に応じ臨時に召集される国会のことをいう(同53条)。よって,本記述は誤りである。
なお,特別会は,解散による総選挙の日から30日以内に召集される(同54条1項)。参考芦部(憲法)320頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)115~116頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,Aは,Bと婚姻後,協議離婚し,Fと婚姻した場合において,Bとの協議離婚が無効であることが判明したときであっても,既にAとFとの婚姻が離婚によって解消されていれば,Bは,特段の事情のない限り,重婚を理由としてAとFとの婚姻の取消しを請求することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 50.7%結果正解解説判例は,「重婚の場合において,後婚が離婚によって解消されたときは,特段の事情のない限り,後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されない」としている(最判昭57.9.28 民法百選Ⅲ〔第2版〕4事件)。その理由として,同判決は,「婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法748条,749条),離婚後,なお婚姻の取消を請求することは,特段の事情がある場合のほか,法律上その利益がないものというべき」ことを挙げている。よって,本記述は正しい。参考リーガルクエスト(親族・相続)56頁。
窪田(家族法)36頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,刑務所の看守者である公務員甲は,18歳の被拘禁者乙女の承諾を得て,勤務時間中に同女にわいせつな行為をした。この場合,甲には特別公務員暴行陵虐罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 80.0%結果正解解説特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)における被害者の承諾は,無効であると解されている(大判大15.2.25参照)。これは,同罪は,一面において職務の適正を保護するものであるところ,この法益は,暴行・陵虐の相手方個人の同意によって放棄される性質のものではないからである。したがって,甲の行為が乙女の承諾を得て行われたとしても,同条2項にいう「陵辱若しくは加虐」に当たり,甲には特別公務員暴行陵虐罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考大塚ほか(基本刑法Ⅱ)556頁。
条解刑法551頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,報道機関が国政に関する取材目的で,公務員に対し秘密を漏示するように根気強く執ように説得を続けることは,それが真に報道の目的から出たもので,その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは,正当な取材行為として処罰の対象とはならない。憲法この問題の模試受験生正解率 71.3%結果正解解説判例は,新聞記者が,国家公務員である外務審議官付女性事務官と情を通じ,これを利用して,秘密文書又はその写しの持出しを執ように迫り,職務上知ることのできた秘密を漏らすことを唆したとして,国家公務員法111条,109条12号,100条1項違反に問われた事例において,「報道機関の国政に関する取材行為は,国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり,時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから,報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって,そのことだけで,直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく,報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは,それが真に報道の目的からでたものであり,その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは,実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである」としている(最決昭53.5.31 外務省秘密電文漏洩事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕75事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,Aが土地の工作物をBから買い受けたが,その工作物の設置又は保存に瑕疵があり,その瑕疵によって第三者Cに損害を生じさせた場合,その瑕疵がBの下で生じたものであるときは,Aは,Cに対して,損害を賠償する責任を負わない。民法この問題の模試受験生正解率 83.8%結果正解解説民法717条1項ただし書の所有者の土地工作物責任は,危険責任の原理に基づく無過失責任と解されており,そうである以上,所有者の過失(行為義務違反)は問題とならないのであるから,瑕疵が前所有者の下で生じたか,現所有者の下で生じたかは,責任の成否に影響しない。判例も,AがBから宅地を買い受けたが,Bが設置した当該宅地の擁壁に瑕疵があったために擁壁が崩壊し,当該宅地の崖下のCの木造家屋が破壊され,CがAに対して,土地工作物責任に基づく損害賠償請求(同条1項)をしたという事例において,占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを立証すれば免責されるが,所有者は,瑕疵のある工作物を所有すること自体が賠償責任の根拠であり,瑕疵が生じたことについて無過失であることをもって免責されないことは,同714条1項,715条1項,718条1項の各ただし書には免責規定が存在するのに対して,同717条には存在しないこととの対比から明らかであるとし,工作物の所有者は,設置又は保存による瑕疵が前所有者の所有していた時期に生じた場合でも,現に当該工作物を所有するということだけで損害を賠償する責任を負うとしている(大判昭3.6.7)。よって,本記述は誤りである。参考潮見(基本講義・債各Ⅱ)163~164頁。
我妻・有泉コメ1544頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙からパソコンを借りて保管していたところ,その売却代金を自己の借金の返済に充てるつもりで,乙に無断で,同パソコンの買取りを丙に持ち掛けたが,丙はいまだ買受けの意思表示をしていなかった。この場合,甲には,横領罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 33.7%結果正解解説判例は,業務上自己の占有する他人の動産を第三者に売却した事例において,自己の占有する他人の動産を不法に第三者に売り渡そうとする行為がなされた場合には,不法領得の意思の実現があるといえるので,第三者がこれを買い受ける意思表示をすることを待たずに業務上横領罪(刑法253条)が成立するとしている(大判大2.6.12)。したがって,甲が丙に買取りを持ち掛けた時点で,不法領得の意思の実現があり,甲には横領罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)306頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)282頁。
条解刑法809頁,818頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法通信に関する情報は,通信の内容と,受発信者の住所,氏名,送信日時などの通信の存在自体に関する事実に分類されるところ,通信の秘密の保障の主要な目的が私生活の秘密の保護にあるとする見解によれば,前者のみならず後者の情報も,通信の秘密の保護を受ける。憲法この問題の模試受験生正解率 84.7%結果正解解説憲法21条2項後段は,「通信の秘密は,これを侵してはならない。」と規定している。この点,通信の秘密の保障の主要な目的が私生活の秘密ないしプライバシーの保護にあると考える見解からは,通信の秘密の保障は,通信の内容だけではなく,受発信者の住所,氏名,送信日時などの通信の存在自体に関する事実にも及ぶものとされている。よって,本記述は正しい。
参考芦部(憲法)230頁。
佐藤幸(日本国憲法論)320~321頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)397頁。
新・コンメ憲法273頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,同一不動産上に,不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権とが存在し,かつ,それらが適法に登記されているときは,不動産保存の先取特権が優先する。民法この問題の模試受験生正解率 23.8%結果正解解説同一の不動産について,不動産保存の先取特権は,不動産工事の先取特権に優先する(民法331条1項,325条1号,2号)。これは,工事より後に保存行為がされたときは,保存行為により工事の先取特権者も利益を受けるためである。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ80頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,暴行・脅迫を用いて乙のかばんを強取する犯意の下,まず当該かばんを隙を突いて乙の手から取り上げ,かばんを取り戻そうとして追いすがる乙に対して財物の取り返しを抑圧するに足りる程度の暴行を加えてその奪取を確保した。この場合,甲には事後強盗罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 62.0%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に先づ財産を奪取し,次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は強盗罪を構成するのであって,窃盗がその財物の取還を拒いで暴行をする場合の準強盗ではない」としている(最判昭24.2.15)。したがって,甲に事後強盗罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)221頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅱ)166頁。
条解刑法736頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,憲法第14条第1項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには,合憲性の推定は排除され,裁判所は厳格な基準によってその差別が合理的であるかどうかを審査すべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 29.2%結果正解解説判例は,憲法14条1項後段列挙事由(人種,信条,性別,社会的身分又は門地)は例示的なものと解しており,当該事由に本記述のような特段の効果を認めていない(最大判昭25.10.11,最大判昭39.5.27等)。よって,本記述は誤りである。
なお,本記述は,最大判昭60.3.27(サラリーマン税金訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕31事件)の伊藤正己裁判官の補足意見である。参考芦部(憲法)135頁。
佐藤幸(日本国憲法論)199~201頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)286~287頁。
渋谷(憲法)202~203頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,A(東京在住)がB(京都在住)に対し,Bによる契約の申込みを承諾する旨の通知を,手紙によって発した場合,AB間の契約は,当該通知を発した時に成立する。民法この問題の模試受験生正解率 62.5%結果正解解説意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民法97条1項)。したがって,本記述においても,AB間の契約は承諾の通知がBに到達した時に成立することになる。よって,本記述は誤りである。
なお,平成29年改正前民法526条1項では,隔地者間契約は,承諾の通知を発した時に成立するものとされていた(発信主義)。これは,承諾の発信後直ちに契約を成立させることにより,承諾者がいち早く契約の履行準備に取り掛かれるようにすることが取引の迅速化の要請にかなうと考えられたことによる。しかし,電子媒体を用いた通信手段が主流となった現在においては,発信主義を維持する合理性は失われたため,同改正において,同改正前民法526条1項は削除された。参考佐久間(総則)63頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)221頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,通常の意思能力もなく,死の意味を理解することができない乙の承諾を得て,乙の頭を拳銃で撃ち抜き,これにより乙は死亡した。この場合,甲には,殺人罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 100%結果正解解説被害者の承諾に基づく行為につき違法性阻却が認められるためには,その承諾自体が有効なものでなければならないところ,通常の意思能力を欠く者の承諾は無効である(最決昭27.2.21 宗教百選91事件)。したがって,乙の承諾は無効であるから,甲には,同意殺人罪(刑法202条後段)ではなく,殺人罪(同199条)が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(総)204頁。
基本刑法Ⅰ161頁。
条解刑法99頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法裁判を受ける権利に関して,憲法第32条の保障する裁判を受ける権利は,民事事件及び行政事件については,何人も自ら裁判所へ訴訟を提起し,救済を求め得る権利を有することを意味し,国家にとっては裁判の拒絶の禁止を意味する。憲法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説憲法32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定し,裁判を受ける権利を保障している。裁判を受ける権利は,具体的には,民事事件及び行政事件については,何人も自ら裁判所へ訴訟を提起し,救済を求め得る権利,すなわち裁判請求権を有することを意味し,国家にとっては裁判の拒絶の禁止を意味する。よって,本記述は正しい。
なお,刑事事件については,裁判所による裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味する。これは,同31条の定める適正手続の当然の要請であり,同37条1項が重ねて規定している。参考芦部(憲法)267~268頁。
佐藤幸(日本国憲法論)353頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)548~549頁。
新基本法コメ(憲法)260頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,債務の不履行について当事者が損害賠償の額を予定している場合であっても,裁判所は過失相殺により賠償額を減額することができる。民法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説当事者は,債務の不履行について損害賠償の額を予定することができ(民法420条1項),当事者が損害賠償の額を予定している場合,裁判所は,実際の損害が予定賠償額より過大であったり,過小であったりしても,予定賠償額を増減することは認められない。もっとも,判例は,「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても,債務不履行に関し債権者に過失があったときは,特段の事情のない限り,裁判所は,損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき,これを斟酌すべきものと解するのが相当である」としている(最判平6.4.21)。よって,本記述は正しい。
なお,平成29年改正前民法では,当事者は,債務の不履行について損害賠償の額を予定することができ(同420条1項前段),この場合において,裁判所は,その額を増減することができない(同項後段)としていた。しかし,過大な賠償額の予定がされている場合などに,暴利行為を理由として裁判所が当該予定条項を無効としたり(同90条),予定賠償額を減額したりすることは認められると解されているところ,同420条1項後段の規定の存在により,このような処理が否定されるのか疑義が生じるため,規定文言上障害となり得る同項後段は削除された。参考平野(債総)139~140頁。
潮見(プラクティス債総)161頁。
民法(債権関係)改正法の概要74~75頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)69~70頁。
民法(債権法)改正のポイント123~128頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,公務員である甲は,自己の職務に関し,Xから賄賂として土地を収受した。この場合,当該土地は必ず没収しなければならない。刑法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説没収は,対象物を国庫に帰属させる処分であり,財産刑としての性質を有する。没収の対象となるのは,①犯罪行為を組成した物(犯罪組成物件 刑法19条1項1号),②犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(犯罪供用物件 同項2号),③犯罪行為によって生じた物,犯罪行為によって得た物,犯罪行為の報酬として得た物(犯罪生成・取得・報酬物件 同項3号),④③に掲げる物の対価として得た物(対価物件 同項4号)である。
刑法197条の5は,同19条及び同19条の2の特則として,犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂の必要的没収を規定している。没収の対象となる賄賂は,金銭その他の動産,不動産,株券や小切手等の有価証券などの有体物である。したがって,本記述のように,賄賂として収受した土地は,必ず没収しなければならない。よって,本記述は正しい。参考山口(総)420頁。
基本刑法Ⅰ438~439頁。
条解刑法33~42頁。
西田(各)534頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らして,司法書士以外の者が登記に関する手続の代理等の業務を行うことを原則として禁止する司法書士法の規定は,登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることを考慮したものであり,公共の福祉に合致した合理的な規定であるから,憲法第22条第1項には反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 83.3%結果正解解説判例は,司法書士以外の者が登記に関する手続の代理等の業務を行うことを原則として禁止する司法書士法19条1項(現:73条1項本文),25条1項(現:78条1項)の合憲性が争われた事例において,「司法書士法の右各規定は,登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ,法律に別段の定めがある場合を除き,司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が,他人の嘱託を受けて,登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し,これに違反した者を処罰することにしたものであって,右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法22条1項に違反するものでない」としている(最判平12.2.8 憲法百選Ⅰ〔第7版〕95事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,買戻しの期間は,10年を超えることができず,特約でこれより長い期間を定めたときは,その期間は10年とされる。民法この問題の模試受験生正解率 12.5%結果正解解説民法580条1項は,「買戻しの期間は,10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは,その期間は,10年とする。」と規定している。よって,本記述は正しい。
なお,買戻しについて期間を定めなかったときは,5年以内に買戻しをしなければならない(同条3項)。参考平野(債各Ⅰ)203頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,成年者を客体とする人身買受け罪は,買受けが,一定の目的をもってされた場合でなければ,成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説人身売買罪(刑法226条の2)は,目的のいかんを問わず人身買受け行為と人身売渡し行為を犯罪とした上で,その目的,客体,行為に応じて法定刑を加重する条文構造となっている。したがって,成年者の買受けについては,営利,わいせつ,結婚又は身体・生命加害,所在国外移送の目的がなくても,人身買受け罪(同条1項)が成立する。よって,本記述は誤りである。
なお,成年者の拐取については,一定の目的がある場合のみ処罰の対象とされている(同225条,225条の2第1項,226条)。参考西田(各)93頁。
条解刑法663~665頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第95条の特別法(以下「地方特別法」という。)に関して,憲法第95条にいう「一の地方公共団体」とは,一つの地方公共団体の意味であるから,複数の地方公共団体に適用される法律は,地方特別法に該当しない。憲法この問題の模試受験生正解率 12.5%結果正解解説憲法95条にいう「一の地方公共団体」とは,特定の地方公共団体という意味であり,実際に法律の適用される地方公共団体が一つである必要はないとされている。例えば,旧軍港市転換法は,旧軍港のあった横須賀,呉,佐世保,舞鶴の4市を適用対象とし,地方特別法に該当するものとして住民投票に付されている。したがって,複数の地方公共団体に適用される法律も,憲法95条の地方特別法に該当し得る。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)560頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)389~390頁。
新基本法コメ(憲法)499頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,複数の寄託者の同意を得て,各寄託者が寄託した種類及び品質が同一の物を混合して保管する場合,混合して保管されている寄託物の一部が滅失したときは,各寄託者は,受寄者に対し,混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還及び損害賠償の請求をすることができる。民法この問題の模試受験生正解率 62.5%結果正解解説民法665条の2第1項は,複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には,受寄者は,各寄託者の承諾を得たときに限り,これらを混合して保管することができるとし,いわゆる混合寄託を認めている。そして,同条2項は,混合寄託がなされた場合に,寄託者は,その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができるとし,同条3項は,寄託物の一部が滅失したときは,寄託者は,混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の返還を請求することができるとともに損害賠償請求もすることができるとしている。よって,本記述は正しい。
なお,平成29年改正前民法下でも,混合寄託は,実務上広く利用されていたが,明文の規定がなかった。そこで,同改正により混合寄託の要件効果が明文化された。参考一問一答(民法(債権関係)改正)336頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,覚せい剤を含有する粉末を所持していたが,同粉末が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたものの,覚せい剤や麻薬ではないと認識していた。この場合,甲には,覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説判例は,覚せい剤取締法違反(覚せい剤輸入・所持)の罪で起訴された被告人が,日本国内に持ち込んで所持した薬物が,覚せい剤であることの認識がなかったとして,故意の成立を争った事例において,「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があった」場合には,「覚せい剤かもしれないし,その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる」から,同罪の故意が認められるとしている(最決平2.2.9 刑法百選Ⅰ〔第7版〕40事件)。もっとも,甲は,その所持する粉末が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたものの,覚せい剤や麻薬ではないと認識しているから,甲に覚せい剤所持の罪の故意は認められない。したがって,甲には,同罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考前田(総)187~188頁。
基本刑法Ⅰ96頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に,音楽専科の教諭が「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,当該教諭にとって通常想定され期待されるものであり,当該伴奏を行う当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。憲法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説判例は,市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に音楽専科の教諭に対してピアノ伴奏を命じる職務命令が憲法19条に違反するか否かが問題となった事例において,「本件職務命令当時,公立小学校における入学式や卒業式において,国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり,客観的に見て,入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって,上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであ」るとしている(最判平19.2.27 平19重判憲法3事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)158頁。
佐藤幸(日本国憲法論)223頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)313~314頁。 -
民法特別養子縁組に関して,特別養子縁組の養親は,縁組を継続し難い重大な事由があれば,家庭裁判所に離縁を請求することができる。民法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説特別養子縁組の離縁に関しては,①養親による虐待,悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること及び②実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において,養子の利益のため特に必要があるときは,家庭裁判所は,養子,実父母又は検察官の請求により,当事者を離縁させることができ(民法817条の10第1項),同項の規定による場合のほかには離縁は認められないとされている(同条2項)。したがって,縁組を継続し難い重大な事由があることにより離縁をすることはできない。また,養親が離縁を申し立てることもできない。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅳ277頁。
基本法コメ(親族)200~201頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,中止行為に当たっては,他人の助力を得てもよいが,自らが結果発生を防止したと同視し得る程度の努力を払うことが必要である。刑法この問題の模試受験生正解率 100%結果正解解説判例は,刑法第43条ただし書にいわゆる中止犯は,犯人が犯罪の実行に着手したる後,その継続中任意にこれを中止し若しくは結果の発生を防止するにより成立するものにして,結果発生についての防止は必ずしも犯人単独にて之にあたるの要なきこと勿論なりといえども,その自ら之にあたらざる場合は,少なくとも犯人自身之が防止にあたりたると同視するに足るべき程度の努力を行うの要あるものとするとして,中止犯が成立するには,結果発生の防止は必ずしも犯人が単独で行う必要はないが,自ら防止しない場合は,少なくとも犯人自身が防止にあたったのと同視できるだけの努力が必要であるとしている(大判昭12.6.25)。よって,本記述は正しい。参考西田(総論)342頁。
山口(総)299~300頁。
基本刑法Ⅰ289頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法前文を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味での裁判規範性は認められないとする立場からは,憲法本文の各規定を解釈する際に,憲法前文の趣旨を拠りどころにすることも許されない。憲法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説憲法前文の裁判規範性を否定する見解の根拠は,前文は憲法の理想・原則を抽象的に宣明したものであって具体性を欠くこと,前文の内容は全て本文の各条項において具体化されているので,前文がそれらの解釈基準となり得るとしても,裁判所において実際の判断基準として用いられるのは本文の具体的規定であることなどに求められる。つまり,裁判規範性を否定する見解であっても,前文が憲法法典の一部を構成しその基本原理を示したものである以上,各条項はそれに従って解釈すべきという意味において,前文が憲法本文の各条項の解釈の基準となることを承認している。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅰ)70~71頁。
佐藤幸(日本国憲法論)31頁。
新・コンメ憲法17頁。憲法の争点14~15頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,遺言執行者は,その任務を開始したときは,遅滞なく,遺言の内容を相続人に通知しなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 62.5%結果正解解説民法1007条2項は,「遺言執行者は,その任務を開始したときは,遅滞なく,遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と規定している。よって,本記述は正しい。
なお,平成29年改正前民法下では,遺言執行者自らが就職した事実や遺言の内容を相続人に通知する義務についての規定はなかったものの,遺言の内容の実現は,原則として,遺言執行者がある場合には遺言執行者が,遺言執行者がない場合には相続人がすべきことになるため,相続人としては,遺言の内容及び遺言執行者の存否について重大な利害関係を有することになる。そこで,同改正後民法1007条2項が新設された。参考リーガルクエスト(親族・相続)415頁。
一問一答(新しい相続法)112頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Xが窃取した自動車を有償で譲り受け,その自動車を売却し,代金として現金50万円を得た。この場合,当該現金を没収することができる。刑法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説没収は,対象物を国庫に帰属させる処分であり,財産刑としての性質を有する。没収の対象となるのは,①犯罪行為を組成した物(犯罪組成物件 刑法19条1項1号),②犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(犯罪供用物件 同項2号),③犯罪行為によって生じた物,犯罪行為によって得た物,犯罪行為の報酬として得た物(犯罪生成・取得・報酬物件 同項3号),④③に掲げる物の対価として得た物(対価物件 同項4号)である。
④の対価物件を没収するに当たり,対価を取得する行為が犯罪を構成する必要はない(最判昭23.11.18)。本記述のように,有償で譲り受けた盗品を売却して得た現金は,③の犯罪取得物件の対価として得た物であるので,④の対価物件に当たり,没収の対象となる。よって,本記述は正しい。参考山口(総)420頁。
基本刑法Ⅰ438~439頁。
条解刑法33~42頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第73条が列挙する内閣の事務に関して,憲法第73条第4号は,「官吏」に関する事務を掌理することを内閣の事務として規定しているところ,この「官吏」には,国会や裁判所の職員のほか,地方公務員もこれに含まれる。憲法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説憲法73条4号は,「法律の定める基準に従ひ,官吏に関する事務を掌理すること。」を内閣の事務として規定している。この「官吏」に,国会や裁判所の職員が含まれるか学説上争いがあるも,地方公務員は,地方公共団体独自の地位に照らし,また,同93条2項の「吏員」に対応することから,「官吏」には含まれない。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)498~499頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)208~209頁。
新基本法コメ(憲法)389~390頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,主たる債務につき消滅時効が完成した場合において,主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても,保証人はその完成した時効を援用することができる。民法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説保証人は,主たる債務の消滅時効の援用権者に当たる(民法145条括弧書)。また,判例は,主たる債務者が時効の利益を放棄しても,保証人に対しては効力を及ぼさないとしている(大判大5.12.25)。したがって,主たる債務者が時効の利益を放棄しても,保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができる。よって,本記述は正しい。参考平野(総則)397頁。
潮見(プラクティス債総)627~628頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,略取誘拐罪において,略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は,保護者又は監護者に対して用いるのでは足りず,直接被拐取者に対して用いる必要がある。刑法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説略取誘拐罪(刑法224条以下)における略取とは,暴行又は脅迫を手段とする場合であり,誘拐とは,欺罔又は誘惑を手段とする場合をいう。この暴行,欺罔等は,他人を自己の支配下に置くための手段であるから,直接被拐取者に加えられることを要せず,保護者・監護者に対するものであってもよい(大判大13.6.19)。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)85頁。
基本刑法Ⅱ59頁。
条解刑法656~657頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法天皇及び皇族が憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれるとしても,天皇に象徴たる地位が認められ,皇位に世襲制が設けられていることからすると,一般の国民と異なる取扱いをすることも認められる。憲法この問題の模試受験生正解率 62.5%結果正解解説天皇及び皇族は日本国籍を有するが,憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれるか争いがある。これについては,日本国憲法下では,大日本帝国憲法下のような皇族と臣民の区別は存在しないはずであるとの基本的認識から,天皇及び皇族は人権享有主体である「国民」に含まれるとする見解がある。もっとも,この見解によっても,天皇に象徴たる地位が認められることや,皇位に世襲制が設けられていることから,一般の国民と異なった取扱いをすることも認められる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)87~89頁。
佐藤幸(日本国憲法論)141~142頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)230~232頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,二人以上の者が相互に関連する内容の遺言をする場合,同一の証書ですることができる。民法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説民法975条は,遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができないとして共同遺言を禁止している。これは,共同遺言を許すと,一方の遺言者の意思内容や撤回の自由が他方の意思によって制約されるおそれがあり,また,一方の遺言が失効した場合に他方の遺言の効力に疑義が生じることになるという理由によるものである。共同遺言として禁止されるのは,①同一の証書に複数の者が遺言を記載しており(形式的要素),②その証書で示された各遺言者の意思内容が相互に関連し,各自の意思表示を他から独立して抽出できない場合(実質的要素)である。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(親族・相続)387頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Xの妻が所有する果物ナイフで,Xを刺殺し,現在もその果物ナイフを所持している。この場合,当該果物ナイフを没収することができる。刑法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説没収は,対象物を国庫に帰属させる処分であり,財産刑としての性質を有する。没収の対象となるのは,①犯罪行為を組成した物(犯罪組成物件 刑法19条1項1号),②犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(犯罪供用物件 同項2号),③犯罪行為によって生じた物,犯罪行為によって得た物,犯罪行為の報酬として得た物(犯罪生成・取得・報酬物件 同項3号),④③に掲げる物の対価として得た物(対価物件 同項4号)である。
没収は,その物が犯人以外の者に属しない場合に限り,することができる(刑法19条2項本文)。犯人以外の者に属しない物とは,犯人以外の者がその物に対して所有権その他の物権を有しない物をいう。したがって,本記述の果物ナイフは,殺害行為に使用されているため,②の犯罪供用物件に当たるが,「犯人以外の者」であるXの妻が所有している物であるから,これを没収することはできない。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)420頁。
基本刑法Ⅰ438~439頁。
条解刑法33~42頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第14条第3項は,特権を伴う栄典の授与を禁止しているが,同項にいう「栄典」には,公に与えられるものが全て含まれる。憲法この問題の模試受験生正解率 29.2%結果正解解説憲法14条3項前段は,「栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。」と規定して,特権を伴う栄典の授与を禁止している。ここにいう「栄典」とは,名誉を表彰するために付与される特殊な地位をいい,天皇によって授与されるものに限らず,公に与えられるものを全て含む。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)129~130頁。
佐藤幸(日本国憲法論)207頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)300~301頁。
新基本法コメ(憲法)113頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,同一の法律行為について,代理権を授与された代理人が,自らを相手方としてした行為は,債務の履行行為又は本人があらかじめ許諾した行為を除き,無権代理行為とみなされ,効力を生じない。民法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説民法108条1項は,「同一の法律行為について,相手方の代理人として……した行為は,代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし,債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については,この限りでない。」と規定している。このような代理人が自ら契約の相手方となる場合を自己契約という。自己契約では,本人と代理人の利益が相反するが,法律行為の内容を一人の者が決められるとなると,内容の妥当性が確保されず,本人の利益が害される危険が大きいため,同項は,自己契約を原則として禁止し,禁止に反する行為を無権代理行為とみなしている。よって,本記述は正しい。参考佐久間(総則)246~247頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,ゴルフ場内の人工池に打ち込まれた後,そのまま放置されたロストボールは,ゴルフ場経営者が回収及び再利用を予定していた場合には,遺失物等横領罪における「占有を離れた他人の物」に当たらない。刑法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説遺失物等横領罪(刑法254条)における「占有を離れた他人の物」とは,占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物で,誰の占有にも属していないもの,及び委託関係に基づかずに行為者の占有に属したものをいう。判例は,本記述と同様の事例において,被告人がゴルフ場内における人工池の底から領得したロストボールは,ゴルフ場側において,その回収,再利用を予定していたのであるから,当該ロストボールは,ゴルフ場側の所有に帰していたのであり,かつ,ゴルフ場の管理者において占有していたものといえるとしている(最決昭62.4.10 昭62重判刑法6事件)。したがって,本記述におけるロストボールは,「占有を離れた他人の物」に当たらない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)154頁,270頁。
基本刑法Ⅱ125頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,市が町内会に対し,無償で市有地を氏子集団によって管理運営されている神社の敷地としての利用に供している状態が,憲法第89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断する。憲法この問題の模試受験生正解率 100%結果正解解説判例は,市が町内会に対し,無償で市有地を氏子集団によって管理運営されている神社の敷地としての利用に供している状態が政教分離違反となるかが争われた事例において,「憲法89条も,公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするもの」とした上で,「国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべき」としている(最大判平22.1.20 空知太神社事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕47事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法特別養子縁組に関して,家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,養親となろうとする夫婦がともに25歳に達していなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説民法817条の2第1項は,家庭裁判所は,同817条の3から同817条の7までに定める要件があるときは,特別養子縁組を成立させることができるとしている。特別養子縁組で,養親となる者は,配偶者のある者でなければならず,原則として配偶者とともに養親とならなければならない(同817条の3第1項,2項)。そして,25歳に達しない者は,養親となることができない(同817条の4本文)が,養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合であっても,その者が20歳に達していれば養親になることができる(同条ただし書)。したがって,夫婦の一方が25歳に達していない場合であっても,特別養子縁組の養親になることができる。よって,本記述は誤りである。
なお,養子となる者の年齢の上限については,令和元年6月改正(令和2年4月1日施行)により,原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられた(民法817条の5第1項)。参考リーガルクエスト(親族・相続)161頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,人を不法に監禁中に,監禁罪の法定刑を重くする改正法が施行された場合,新法は適用されない。刑法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説刑法6条は,刑の変更に関する規定であり,犯罪後に刑の変更があったときは,最も軽い刑によるべきことを定めたものである。「犯罪後」とは,実行行為終了時を基準とする。判例は,継続犯については,行為の継続中に刑の変更があった場合,常に行為の完結した時期における新法が適用されるとしている(最決昭27.9.25)。また,「刑の変更」は,改正法の施行時を基準とする。したがって,監禁罪(同220条)は継続犯であることから,常に新法が適用される。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法11~12頁,640頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法裁判を受ける権利に関して,最高裁判所の判例によれば,憲法第32条は,国民が憲法又は法律によって定められた裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障するのみならず,訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利についても保障するものである。憲法この問題の模試受験生正解率 50.0%結果正解解説判例は,管轄違いの裁判所によって言い渡された判決が原審によって是認されたため,被告人等が憲法32条の保障する正当な裁判所で裁判を受ける権利を侵害されたと主張した事例において,「憲法第32条は,何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれないと規定しているが,同条の趣旨は凡て国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し,裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障したものであって,訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない」としている(最大判昭24.3.23 憲法百選Ⅱ〔第4版〕131事件)。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅰ)550頁。
新基本法コメ(憲法)262頁。 -
民法根保証契約に関して,主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けた場合,個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は確定する。民法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説個人根保証契約における主たる債務の元本は,保証人が破産手続開始の決定を受けたときに確定する(民法465条の4第1項柱書本文,同項2号)。また,個人貸金等根保証契約の場合には特則が設けられており,個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,保証人が破産手続開始の決定を受けたときのほか,主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合にも確定する(同条2項柱書本文,同項2号)。これは,個人貸金等根保証契約以外の個人根保証契約の典型例である,不動産の賃借人の債務を主たる債務の範囲に含む個人根保証契約において,主たる債務者の破産手続開始の決定によって,個人根保証契約における主たる債務の元本が確定してしまうと,賃貸借契約は主たる債務者である賃借人の破産によっても終了しないため,賃貸人としては,保証契約の存在を前提として賃貸借契約を締結したにもかかわらず,以後は保証がないまま賃貸し続けることを強いられるという不都合が生じることを理由とする。よって,本記述は正しい。
なお,平成29年改正前においては,貸金等根保証契約の場合についてのみ元本確定事由が規定されていた(同改正前民法465条の4)。もっとも,同改正によって,予想外の事態が生じた後にも個人保証人の責任が拡大することを防止する観点から,個人根保証契約一般に元本確定事由の規律が及ぼされることとなった。ただし,例外的に,貸金等根保証契約の元本確定事由のうち,主たる債務者の財産について強制執行等の申立てがあったことと,主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたことについては,上記理由から個人根保証契約一般の元本確定事由とされなかった。参考潮見(プラクティス債総)673~674頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)138頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,自らが作成したX宅の合い鍵を使用してX宅に侵入し,金員を窃取したことにより窃盗罪で起訴された。住居侵入罪が窃盗罪と併せて起訴されていない場合,当該合い鍵を没収することはできない。刑法この問題の模試受験生正解率 37.5%結果正解解説没収は,対象物を国庫に帰属させる処分であり,財産刑としての性質を有する。没収の対象となるのは,①犯罪行為を組成した物(犯罪組成物件 刑法19条1項1号),②犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(犯罪供用物件 同項2号),③犯罪行為によって生じた物,犯罪行為によって得た物,犯罪行為の報酬として得た物(犯罪生成・取得・報酬物件 同項3号),④③に掲げる物の対価として得た物(対価物件 同項4号)である。
②の犯罪供用物件とは,犯罪行為の不可欠な要素となっている物ではないが,犯罪行為のために使用された物をいう。犯罪の実行行為に直接使用された物のみならず,実行行為や逃走を容易にするなど,犯罪の成果を確保する目的でなされた行為において使用された物も,当該行為と実行行為が密接な関連性を有する限り,犯罪供用物件ということができる。判例は,住居侵入窃盗の事犯で窃盗罪のみが起訴された事例において,被告人が住居侵入に当たり使用した鉄棒につき,これを窃盗の手段としてその犯罪行為の用に供した物と解することができるとして,没収を認めている(最判昭25.9.14)。したがって,本記述のように,窃盗のための住居侵入に使用した甲が作成したX宅の合い鍵は,②の犯罪供用物件に当たり,没収の対象となる。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)420頁。
基本刑法Ⅰ438~439頁。
条解刑法33~42頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,職業活動の自由についても精神的自由についても,国の積極的な社会経済政策の実施の一手段として,これに一定の合理的規制措置を講じるところ,当該規制措置が適切妥当であるかは,主として立法政策の問題として,立法府の裁量的判断に委ねられる。憲法この問題の模試受験生正解率 83.3%結果正解解説判例は,政令で指定する市の区域内の建物については,都道府県知事の許可を受けた者でなければ,特定の形態の小売市場を開設,経営してはならないとする小売商業調整特別措置法の規定が憲法22条1項に反しないかが争われた事例において,「右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は,個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に,消極的に,かような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない。のみならず,憲法の他の条項をあわせ考察すると,憲法は,全体として,福祉国家的理想のもとに,社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており,その見地から,すべての国民にいわゆる生存権を保障し,その一環として,国民の勤労権を保障する等,経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである。このような点を総合的に考察すると,憲法は,国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定しているものということができ,個人の経済活動の自由に関する限り,個人の精神的自由等に関する場合と異なって,右社会経済政策の実施の一手段として,これに一定の合理的規制措置を講ずることは,もともと,憲法が予定し,かつ,許容するところと解するのが相当であ」るとしている(最大判昭47.11.22 小売市場事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕91事件)。したがって,同判決は,精神的自由について国の積極的な社会経済政策の実施の一手段として,これに一定の合理的規制措置を講じることを認めていないといえる。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決は,「個人の経済活動に対する法的規制措置については,立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく,裁判所は,立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし,ただ,立法府がその裁量権を逸脱し,当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って,これを違憲として,その効力を否定することができる」としている。 -
民法判例の趣旨に照らすと,不動産の売買契約と同時に買戻しの特約を登記した場合において,買主が買い受けた不動産を第三者に売り渡し,所有権移転登記を経由した場合であっても,売主が買戻しの意思表示をすべき相手方は,その第三者ではなく,買主である。民法この問題の模試受験生正解率 12.5%結果正解解説判例は,買戻しの特約付きの売買契約により不動産を買い受けた者が,特約所定の買戻し期間中に,更にその不動産を第三者に売り渡し,かつ所有権移転登記を経由した場合は,その不動産の売主が買戻権を行使するには,転得者に対してすべきであるとしている(最判昭36.5.30 不動産取引百選〔第3版〕82事件)。よって,本記述は誤りである。参考平野(債各Ⅰ)204頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,証拠隠滅罪の「証拠」は,犯罪の成否に関するものでなければならず,情状証拠はこれに含まれない。刑法この問題の模試受験生正解率 75.0%結果正解解説証拠隠滅罪の「証拠」には犯罪の成否に関するものだけでなく,情状証拠も含まれる(大判昭7.12.10)。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)486~487頁。
基本刑法Ⅱ522頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第95条の特別法(以下「地方特別法」という。)に関して,特定の地方公共団体の地域を対象とする法律であっても,国の事務・事業や国の組織について規定し,地方公共団体の組織,運営,権能に関係のないものは,地方特別法には該当しない。憲法この問題の模試受験生正解率 12.5%結果正解解説憲法95条の立法趣旨は,①地方公共団体の個性の尊重,②地方公共団体の平等権の保障,③地方特別法による地方公共団体の自治権の侵害の防止,④地方行政における民意の尊重にあるが,その中心は,③の地方特別法による地方公共団体の自治権の侵害の防止にあるといわれている。そのため,特定の地方公共団体の地域を対象とする法律であっても,国の事務・事業や国の組織について規定し,地方公共団体の組織,運営,権能に関係のないものは,同条の地方特別法には該当しないと解されている。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)560頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)389~390頁。
新基本法コメ(憲法)499頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,債権の譲受人が,譲渡人から代理権を与えられて,譲渡人の代理人として債務者に債権譲渡の通知をしたとしても,その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。民法この問題の模試受験生正解率 62.5%結果正解解説債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。もっとも,判例は,譲受人が譲渡人の代理人として債務者に通知することは許されるとしている(最判昭46.3.25)。よって,本記述は誤りである。
なお,判例は,譲受人が,譲渡人に代位して,債権譲渡を債務者に通知しても,通知の効力は生じないとしている(大判昭5.10.10)。参考潮見(プラクティス債総)489頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Aを溺死させようとして橋の上から川に突き落としたところ,Aは,落下する途中で橋桁に頭部が激突して死亡した。この場合,甲には,殺人罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 87.5%結果正解解説法益侵害が生じた客体について行為者に錯誤はないが,侵害に至る因果経過に錯誤がある場合を因果関係の錯誤という。この点,判例は,法定的符合説の立場から,故意の要件として因果関係の認識が必要であるが,行為者が認識した因果経過と実際の因果経過との間に食い違い(錯誤)があっても,両者が当該構成要件の範囲内において一致するのであれば,その食い違いは構成要件的に重要でないので,故意を阻却しないとしている(最決平16.3.22 刑法百選Ⅰ〔第7版〕64事件参照)。本記述において,Aは橋桁に頭部が激突し死亡しているが,甲の認識した因果経過は橋から川に突き落とすことによる溺死であり,両者は食い違っている。しかし,両者は殺人罪(刑法199条)の構成要件の範囲内において一致しており,この食い違いは構成要件的に重要でないため故意は阻却されない。したがって,甲には,殺人罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考基本刑法Ⅰ114~116頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,公立学校において,学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に,学校が,その理由の当否を判断するため,単なる怠学のための口実であるか,当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。憲法この問題の模試受験生正解率 82.2%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「公立学校において,学生の信仰を調査せん索し,宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないものであるが,学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に,学校が,その理由の当否を判断するため,単なる怠学のための口実であるか,当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するとはいえない」としている(最判平8.3.8 エホバの証人剣道拒否事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕41事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,甲土地を所有するAが,その子である共同相続人B及びCのうち,Bに甲土地を「相続させる」旨の遺言を残して死亡し,この遺言が遺産分割方法の指定と解される場合において,Cの債権者Dが,甲土地についてCも共同相続したものとしてB及びCの共同相続登記をした上で,Cの持分を差し押さえ,その旨の登記がされたときであっても,Bは,Dに対し,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。民法この問題の模試受験生正解率 73.1%結果正解解説判例は,相続させる旨の遺言は,遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り,民法908条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり,「特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」としている(最判平3.4.19 民法百選Ⅲ〔第2版〕87事件)。次に,同899条の2第1項は,相続による権利の承継は,法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができないとしている。本記述の相続人は,Aの子BCの2人のみであることから,同900条4号本文より,相続分は各々1/2である。遺言によって甲土地の所有権全部を承継したBは,1/2の相続分を超える権利については,対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。そして,同899条の2第1項の第三者とは,不動産に関する権利であれば同177条の第三者と同義であり,当事者及びその包括承継人以外の者で,登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいうと解されている(大連判明41.12.15 不動産取引百選〔第3版〕46事件参照)。また,同判決は,不動産を差し押さえた債権者は同条の第三者に当たるとしている。Dは,Cの債権者として,Cの持分を差し押さえたのであり,当事者及び包括承継人に当たらず,登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者であり,同899条の2第1項の第三者に当たる。したがって,Bは,Dに対し,登記なくして甲土地の所有権の全部の取得を対抗することができない。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(親族・相続)313頁,404~405頁。
佐久間(物権)70頁,103~104頁。
一問一答(新しい相続法)162~163頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,遺棄致死傷罪は,単純遺棄罪・保護責任者遺棄罪と傷害罪・傷害致死罪の法定刑を比較して,重い刑により処断される。刑法この問題の模試受験生正解率 34.5%結果正解解説刑法219条は,「前2条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。」と規定する。「傷害の罪と比較して,重い刑により処断する」とされていることの意味は,傷害の罪における傷害罪(同204条)及び傷害致死罪(同205条)と比較して,上限・下限ともに重い方をもって法定刑とすることをいう。よって,本記述は正しい。
なお,致傷については,単純遺棄による場合は15年以下の懲役,保護責任者遺棄による場合は3月以上15年以下の懲役となり,致死については,いずれの場合も3年以上の懲役となる。参考西田(各)22頁,37頁。
山口(各)38頁。
条解刑法639頁。
基本刑法Ⅱ25頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第43条第1項の「全国民を代表」に関して,「代表」とは,本来的に意思能力を欠く国民の法定代表機関たる国会の表明する意思が国法上国民の意思とみなされるという法的意味と解する見解は,国民に主権者という地位を付与した日本国憲法と根本的に矛盾するといえる。憲法この問題の模試受験生正解率 29.3%結果正解解説「代表」の概念を,民法の法定代理又は法人の代表とのアナロジーで捉えて,本来的に意思能力を欠く国民の法定代表機関たる国会の表明する意思が国法上国民の意思とみなされるとみる見解(法的代表説)がある。この見解は,国民を政治的無能力者として扱う点で,参政権をはじめとする諸権利を保持し,選挙等の手続を通じて固有の意思を表明し得る国民主権下での国民の理解としては妥当でなく,また,国民を本来的に意思能力を欠くとしている点が,国民に主権者としての地位を付与した日本国憲法と根本的に矛盾すると批判されている。よって,本記述は正しい。参考野中ほか(憲法Ⅱ)60~61頁。
渋谷(憲法)535頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,無権代理行為の相手方が代理権の不存在について過失により知らなかった場合でも,無権代理人が自己の代理権の不存在について知っていたときには,相手方は無権代理人の責任を追及することができる。民法この問題の模試受験生正解率 88.3%結果正解解説他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得た場合を除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(無権代理人の責任 民法117条1項)。これに対して,相手方が,無権代理人に代理権が与えられていないことを過失により知らなかった場合には,無権代理人は免責される(同条2項2号本文)。もっとも,この場合であっても,無権代理人が自己に代理権が存在しないことを知っていた場合には,同号本文による無権代理人の免責は否定される(同号ただし書)。したがって,無権代理人が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときであっても,無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは,無権代理人は相手方に対し履行又は損害賠償の責任を負う。よって,本記述は正しい。
なお,平成29年改正前においては,相手方が無権代理について悪意・有過失の場合には,無権代理人は責任を負わないこととされていたが,無権代理人と取引の相手方の公平を図るため,同改正において民法117条2項2号が新設された。参考佐久間(総則)297~298頁。
平野(総則)301頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)29頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合,刑の言渡しに基づく法的効果は将来に向かって消滅するので,刑の言渡しを受けた事実を,その後の犯罪の量刑資料に参酌することは違法である。刑法この問題の模試受験生正解率 70.1%結果正解解説刑法27条は,「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。」と規定する。そして,「効力を失う」とは,刑の言渡しに基づく法的効果が将来に向かって消滅することを意味する(最判昭29.3.11)。もっとも,刑の言渡しが失効しても,刑の言渡しを受けた事実そのものが消滅するわけではないので,その事実をその後の犯罪の量刑資料に参酌しても違法ではないとされている(最決昭33.5.1)。よって,本記述は誤りである。参考新基本法コメ(刑法)61~62頁,80~81頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法改正に関して,憲法規範は,価値の序列又は効力を異にする規範群から成り立つ階層構造をなしているとする見解は,憲法改正手続に従えば,いかなる内容の改正も法的に許されるとの立場の根拠となる。憲法この問題の模試受験生正解率 61.2%結果正解解説憲法改正手続に従えば,いかなる内容の改正も法的に許されるとの見解(無限界説)は,憲法規範には価値の序列を認めることはできないとの考え方を根拠とする。これに対して,憲法改正に法的限界が存在するという見解(限界説)は,憲法典に記載された各条項相互間にはその法的効力において上下関係が存在し,最高位に根本規範,中間に憲法改正規範,最下位に普通の憲法規範が序列付けられるということを根拠の1つとする。したがって,憲法規範は,価値の序列又は効力を異にする規範群から成り立つ階層構造をなしているとする見解は,無限界説の根拠とはならない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)409頁。
高橋(立憲主義と日本国憲法)452頁。
憲法の争点328頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,受益者を被告とした詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,債務者に対しても,その効力を有する。民法この問題の模試受験生正解率 36.7%結果正解解説民法424条の7第1項は,債務者に詐害行為取消請求の被告適格が認められないとしつつ,同425条は,詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力が債務者に及ぶとしている。よって,本記述は正しい。
なお,債務者にも詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力を及ぼすことからその手続保障のため,債権者は,詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは,債務者に対して遅滞なく訴訟告知をしなければならないとされている(同424条の7第2項)。また,平成29年改正前において,判例は,詐害行為取消訴訟について債務者に被告適格が認められず,判決の効力は債務者に及ばないと解していた(大連判明44.3.24 民法百選Ⅱ〔第8版〕14事件)。参考潮見(新債権総論Ⅰ)734~735頁,814~816頁,826頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えた場合,過剰避難が成立する余地がある。刑法この問題の模試受験生正解率 91.4%結果正解解説避難行為が「その程度を超えた」(刑法37条1項ただし書)場合を過剰避難という。どのような場合に過剰避難が成立するかについては争いがあるが,避難行為が「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」という要件(法益権衡の原則)を充足しない場合に過剰避難が成立し得る点について争いはない。よって,本記述は正しい。参考基本刑法Ⅰ212頁。
リーガルクエスト(刑法総論)238頁。
条解刑法126頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法は,婚姻・家族に関する具体的制度の構築を合理的な立法裁量に委ねており,これを受けて民法は,いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用しているが,法律婚主義を採用しているからといって,非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする旨の規定の合理性が直ちに認められるわけではなく,当該規定の立法目的の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否が検討されるべきである。憲法この問題の模試受験生正解率 12.3%結果正解解説判例は,旧民法900条4号ただし書前段の規定(以下「本件規定」という。)が,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていることが憲法14条1項に反しているかが争われた事例において,「相続制度は,被相続人の財産を誰に,どのように承継させるかを定めるものであるが,相続制度を定めるに当たっては,それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども考慮されなければならない。さらに,現在の相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。この事件で問われているのは,このようにして定められた相続制度全体のうち,本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が,合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり,立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である」としている(最大決平25.9.4 憲法百選Ⅰ〔第7版〕27事件)。同決定は,本件規定の立法目的の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討せずに,端的に合理的根拠が認められるか否かを検討する旨述べている。よって,本記述は誤りである。
-
民法売買契約において,その目的物であるビールを種類のみで指定し,買主の住所で引き渡すこととされていた場合に関して,判例の趣旨に照らすと,売主が債務の本旨に従って買主の住所にビールを持参したが,買主がその受領を拒み,その後そのビールが保管されていた倉庫が地震によって倒壊し,ビールが滅失した場合であって,当該ビールが数量限定生産の特別ラベルであり,新たな調達が不可能なとき,買主は,ビールの代金債務を負わない。民法この問題の模試受験生正解率 81.5%結果正解解説債権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができない場合において,履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(民法413条の2第2項)。そして,債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことができない(同536条2項前段)。本記述においては,売主は債務の本旨に従って買主の住所にビールを持参しており,履行の提供(同493条本文)が認められるのに対し,買主が持参されたビールの受領を拒否している。そして,買主による受領拒否後に地震という当事者双方の責めに帰することができない事由によって,当該ビールが滅失している。さらに,当該ビールが限定ラベルであったため,新たな調達が不可能であることから,ビールの引渡債務は履行不能となり,その履行の不能につき買主に帰責性があるとみなされる。そのため,買主は,ビールの代金支払請求を拒むことができない。よって,本記述は誤りである。
なお,受領遅滞中の目的物の滅失・損傷について追完が可能である場合には,同567条2項が適用されるが,受領遅滞中の履行不能の場合には,同413条の2第2項の規定が適用される。すなわち,債権者が受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になった場合には,その不能は債権者の帰責事由によるものとみなされ(同項),その結果,反対債務の履行拒絶及び債権者からの解除の主張が排除される(同536条2項前段,543条)。参考潮見(プラクティス債総)283頁,294頁。
中田(契約)167頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)73頁。
詳解改正民法438頁。
部会資料75A31頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,小売店Vで買ったオレンジジュースに洗剤を注入し,警察官に対して異物が混入していた旨虚偽の申告をすることにより,警察職員からその旨の発表を受けた報道機関をして,V店で異物の混入されたオレンジジュースが陳列・販売されていたことを報道させた。この場合,甲には,信用毀損罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 68.7%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,信用毀損罪(刑法233条前段)にいう「信用」の意義につき,人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく,商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当とし,同罪の成立を認めている(最判平15.3.11)。したがって,甲には,信用毀損罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)153頁。
井田(各)175頁。
基本刑法Ⅱ109頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由と並んで,事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にある。憲法この問題の模試受験生正解率 82.9%結果正解解説判例は,報道機関の取材フィルムに対する裁判所の提出命令の合憲性が争われた事例において,「報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがって,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」としている(最大決昭44.11.26 博多駅事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕73事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,譲渡担保権者が,譲渡担保権の実行として,譲渡担保の設定者に対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起した場合に,譲渡担保の設定者が清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは,特段の事情のある場合を除き,目的不動産の引渡請求は,清算金の支払と引換えにのみ認容される。民法この問題の模試受験生正解率 52.3%結果正解解説譲渡担保権者は,譲渡担保権の実行により目的物の所有権を取得するが,目的物の価額が被担保債権額を超える場合には,その差額を設定者に返還しなければならない。この譲渡担保権者の差額返還義務を清算義務という。判例は,本記述と類似の事例において,「貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保形式の契約を締結し,債務者が弁済期に債務を弁済すれば不動産は債務者に返還するが,弁済をしないときは右不動産を債務の弁済の代わりに確定的に自己の所有に帰せしめるとの合意のもとに,自己のため所有権移転登記を経由した債権者は,債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合においては,目的不動産を換価処分し,またはこれを適正に評価することによって具体化する右物件の価額から,自己の債権額を差引き,なお残額があるときは,これに相当する金銭を清算金として債務者に支払うことを要するのである。そして,この担保目的実現の手段として,債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を求める訴を提起した場合に,債務者が右清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは,特段の事情のある場合を除き,債権者の右請求は,債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解する」としている(最判昭46.3.25 民法百選Ⅰ〔第8版〕97事件)。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ327頁。
松井(担物)197~198頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,住居侵入罪が成立した後,退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合には,更に不退去罪が成立し,これらは併合罪となる。刑法この問題の模試受験生正解率 49.1%結果正解解説住居侵入罪(刑法130条前段)と不退去罪(同条後段)の関係について,判例は,住居侵入罪が成立する場合には,同罪は退去するまで継続する継続犯であるとしている(最決昭31.8.22)。したがって,退去を求められ応じなかったとしても別に不退去罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)127頁。
大谷(講義各)147頁。
基本刑法Ⅱ93頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,国会議員は,憲法を尊重し擁護する義務を負っているので,違憲の法律を制定してはならないという行為規範の遵守義務が課されているから,国会において議決された法律が違憲であれば,直ちに,当該立法行為は,国家賠償法第1条第1項の適用上も違法の評価を受ける。憲法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説判例は,日本国内で行われる国会議員の選挙に際し,公職選挙法が在外日本人に選挙権の行使の機会を保障していなかったこと等の立法不作為に対して国家賠償が請求された事例において,「国会議員の立法行為又は立法不作為が同項(注:国家賠償法1条1項)の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。しかしながら,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである」としている(最大判平17.9.14 在外邦人選挙権違憲訴訟 憲法百選Ⅱ〔第7版〕147事件)。したがって,同判決によれば,国会において議決された法律が違憲であっても直ちに違法の評価を受けるものではなく,別途権利侵害の明白性等も考慮されて違法と評価されるかが検討される。よって,本記述は誤りである。
-
民法遺留分に関して,被相続人Aが相続人Bに対し,生計の資本として甲不動産を贈与していた場合において,当該贈与が相続開始の5年前の日よりも前にされたものであり,また,A及びBが,当該贈与が遺留分権利者に損害を加えるものであることを知らなかったときは,その価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入されない。民法この問題の模試受験生正解率 33.4%結果正解解説贈与は,相続開始前の1年間にしたものに限り,民法1043条の規定(遺留分を算定するための財産の価額)によりその価額を算入するが(同1044条1項前段),相続人に対する贈与についての同項の規定の適用については,同項中「1年」とあるのは「10年」と,「価額」とあるのは「価額(……生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする(同条3項)。したがって,生計の資本として相続人に対してした贈与については,相続開始前の10年間にしたものであれば,遺留分算定の基礎に含まれることになる。もっとも,同条1項後段は,「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,1年前の日より前にしたものについても,同様とする。」としている。そして,同条3項より,「1年」とあるのは「10年」とされるので,当事者双方が,遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,例外的に10年前の日より前のものであっても,遺留分算定の基礎に含まれる。しかし,本記述においては,A及びBは当該贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかったのであるから,同条1項後段の適用はない。したがって,本記述においては,原則どおり,被相続人Aの相続人Bへの贈与が相続開始の5年前の日よりも前のものであっても,相続開始から10年以内のものであれば,遺留分算定の基礎に含まれる。よって,本記述は誤りである。
なお,同条は,平成30年7月改正前の判例が,「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は,右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって,その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき,減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り,民法1030条(現:1044条1項に相当する。)の定める要件を満たさないものであっても,遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である」としていたことを受けたものである(最判平10.3.24 民法百選Ⅲ〔第2版〕94事件)。もっとも,同判決の法理では,被相続人が相続開始時の何十年も前にした相続人への贈与によって第三者である受遺者等の減殺の範囲が変わることになり得るが,当該第三者は被相続人の相続人に対する古い贈与の存在を知り得ないことが通常であり,当該第三者に不測の損害を与え,法的安定性を害するおそれがあった。そこで,相続人と第三者の調和を図るために,贈与の目的と期間を限定した。参考潮見(詳解相続法)535~536頁。
一問一答(新しい相続法)135~136頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,既に犯罪を決意している者に助言や激励を行うという方法により,その決意を強固にし,犯罪の実行を容易にする場合であっても,幇助犯が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 88.0%結果正解解説幇助の方法は,凶器の提供といった物理的方法(有形的方法)であると,激励や犯行方法の教示といった精神的方法(無形的方法)であるとを問わない。物理的方法による場合を物理的幇助といい,精神的方法による場合を精神的幇助という。したがって,本記述の場合には,精神的方法による幇助犯が成立する。よって,本記述は正しい。参考井田(総)543~544頁。
基本刑法Ⅰ350頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法憲法第89条後段の「公の支配」に関して,憲法第89条後段の趣旨を慈善・教育・博愛事業の自主性を確保し公権力の介入を防止することに求められるとする見解は,公権力が業務・会計について報告を求める程度の監督権を有していれば同条後段の「公の支配」に当たると解するから,現行の私学助成は同条後段に反しないことになる。憲法この問題の模試受験生正解率 42.7%結果正解解説憲法89条後段の趣旨が慈善・教育・博愛事業の自主性を確保し公権力の介入を防止することに求める見解(自主性確保説)は,同条後段の「公の支配」の意義について,公権力が事業を実施する団体に対して人事に関与するなどの強い権限を持つ場合に限られる(厳格説)と解しており,私立学校に対する国の監督が緩やかにとどまる中で行われている現行の私学助成は,同条後段に違反するとしている。よって,本記述は誤りである。
なお,同条後段の趣旨を公金の濫用防止に求める見解(公費濫用防止説)は,公権力が業務・会計について報告を求める程度の監督権を有していれば同条後段の「公の支配」に当たる(緩和説)と解し,現行の私学助成は同条後段に反しないとしている。参考芦部(憲法)376~377頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)345頁。
安西ほか(憲法学読本)351頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知ることができたときは,その意思表示を取り消すことができる。民法この問題の模試受験生正解率 80.9%結果正解解説ある者に対する意思表示につき,第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知り,又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。よって,本記述は正しい。
なお,平成29年改正前民法96条2項においては,詐欺による意思表示が取消し可能となるのは相手方が悪意である場合に限られていた。もっとも,同93条の心裡留保について,相手方が善意又は無過失でなければ意思表示が無効とされないこととの権衝上,相手方が有過失である場合にも,取消しを可能とするべきとの考えから,同96条2項は改められた。参考佐久間(総則)168頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,心神耗弱と認められるのは,精神の障害により,事物の理非善悪を弁識する能力が著しく減退した状態にあった場合に限られる。刑法この問題の模試受験生正解率 64.4%結果正解解説判例は,心神喪失とは,精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいい,心神耗弱とは,精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には至っていないが,その能力が著しく減退した状態をいうとしている(大判昭6.12.3 刑法百選Ⅰ〔第4版〕33事件)。したがって,心神耗弱(刑法39条2項)には,精神の障害により弁識能力が著しく減退した状態に限らず,精神の障害により行動制御能力が著しく減退した状態も含まれる。よって,本記述は誤りである。参考西田(総)298頁。
山中(総)644頁。
基本刑法Ⅰ223頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,筆記行為の自由は,憲法第21条から当然に導かれる派生原理である情報等に接し摂取する自由を補助するものとして,同条の精神に照らし尊重されるべきであるから,その制限又は禁止に対しては表現の自由の制約として厳格な基準が要求される。憲法この問題の模試受験生正解率 82.9%結果正解解説判例は,裁判所において刑事事件を傍聴した者が,裁判長にメモを取ることの許可を求めたところ,裁判長がこれを許可しなかったため,そのような措置は憲法21条1項等に反するとして,損害賠償を請求した事例において,「筆記行為は,一般的には人の生活活動の一つであり,生活のさまざまな場面において行われ,極めて広い範囲に及んでいるから,そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが,さまざまな意見,知識,情報に接し,これを摂取することを補助するものとしてなされる限り,筆記行為の自由は,憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきである」とした上で,「裁判の公開が制度として保障されていることに伴い,傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから,傍聴人が法廷においてメモを取ることは,その見聞する裁判を認識,記憶するためになされるものである限り,尊重に値し,故なく妨げられてはならない」としながらも,「筆記行為の自由は,憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから,その制限又は禁止には,表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない」としている(最大判平元.3.8 レペタ事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕72事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,通行地役権の承役地がAに譲渡された場合において,譲渡の時に要役地の所有者Bによって承役地が継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況からして客観的に明らかであり,Aがそのことを認識することが可能であったときは,Aが承役地を直接見ておらず,通行地役権の存在を認識していなかったとしても, 特段の事情のない限り,Bは,Aに対し,登記をしなくても当該地役権の存在を対抗することができる。民法この問題の模試受験生正解率 73.1%結果正解解説判例は,「通行地役権……の承役地が譲渡された場合において,譲渡の時に,右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが……物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,譲受人は,通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても,特段の事情がない限り,地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない」としている(最判平10.2.13 民法百選Ⅰ〔第8版〕63事件)。その理由として,同判決は,通路としての使用が客観的に明らかであり,かつ譲受人がそのことを認識し,又は認識できたときは,通行地役権の負担は適当な調査によって容易に知ることができ,通行地役権の存在を知らなかった場合であっても,地役権設定登記の欠缺を主張することは,通常は信義に反する点を挙げている。したがって,本記述におけるAは民法177条にいう第三者に当たらず,Bは,特段の事情がない限り,Aに対して,登記なくして通行地役権の存在を対抗することができる。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)80頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,住居侵入罪における「建造物」とは,屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で,人が出入りできるものをいうが,建造物に付属し,その利用に供される囲にょう地も建造物に含まれる。刑法この問題の模試受験生正解率 49.1%結果正解解説「建造物」(刑法130条前段)とは,屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し,人の起居出入りに適した構造をもった工作物のうち,住居・邸宅以外のものを指す。そして,囲にょう地とは,建物の周囲を囲む土地の境界を画する設備が施され,建物の付属地として建物利用に供されることが明示されている土地のことをいい(最判昭51.3.4 刑法百選Ⅱ〔第2版〕17事件),「建造物」の囲にょう地も「建造物」の一部とされる(最大判昭25.9.27)。よって,本記述は正しい。参考山口(各)122頁。
大谷(講義各)142~143頁。
基本刑法Ⅱ85~86頁。
条解刑法385頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,初等中等教育機関においては,教師が児童生徒に対して強い影響力・支配力を有すること,また教育の機会均等という点からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることから,教師に完全な教授の自由を認めることはできない。憲法この問題の模試受験生正解率 60.7%結果正解解説判例は,初等中等教育機関における教師に教授(教育)の自由が認められるかが争われた事例において,「学問の自由を保障した憲法23条により,学校において現実に子どもの教育の任にあたる教師は,教授の自由を有し,公権力による支配,介入を受けないで自由に子どもの教育内容を決定することができるとする見解も,採用することができない。確かに,憲法の保障する学問の自由は,単に学問研究の自由ばかりでなく,その結果を教授する自由をも含むと解されるし,更にまた,専ら自由な学問的探究と勉学を旨とする大学教育に比してむしろ知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においても,例えば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において,また,子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ,その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし,教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては,一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない。しかし,大学教育の場合には,学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し,普通教育においては,児童生徒にこのような能力がなく,教師が児童生徒に対して強い影響力,支配力を有することを考え,また,普通教育においては,子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく,教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは,普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは,とうてい許されない」としている(最大判昭51.5.21 旭川学テ事件 憲法百選Ⅱ〔第7版〕136事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法遺留分に関して,遺留分侵害額請求は,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること及び遺留分侵害額に相当する目的物の持分の返還を請求することの両者を含む。民法この問題の模試受験生正解率 33.4%結果正解解説遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(民法1046条1項)。遺留分侵害額に相当する目的物の持分の返還を請求することはできない。よって,本記述は誤りである。
なお,平成30年7月改正前においては,遺留分権利者が遺留分に関する権利を行使すると,当然に物権的効果が生じ,遺贈又は贈与の一部が無効となるものと解されており,遺留分権利者は,受遺者等に対して,遺留分相当の目的物の持分を回復してその返還を請求することができ,受遺者等は,遺留分相当の価額弁償をして目的物の返還を免れることができるとされていた。もっとも,共有関係の解消等の新たな紛争を生じさせるなどの不都合があった。そのため,同改正により,これらの点を改め,遺留分に関する権利の行使により,遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする債権が生じることとなった(民法1046条1項)。参考潮見(詳解相続法)510~511頁。
一問一答(新しい相続法)122~123頁。
リーガルクエスト(親族・相続)435頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,緊急避難の要件である「現在の危難」にいう「現在」とは,危難が現に存在している場合,すなわち被害の現在性を意味し,危難が間近に差し迫っているだけでは足りない。刑法この問題の模試受験生正解率 91.4%結果正解解説緊急避難(刑法37条1項本文)の要件である「現在の危難」にいう「現在」とは,正当防衛(同36条1項)における「急迫」と同義であり(最判昭24.8.18),危難が現に存在しているか,又は間近に押し迫っていることをいう(最判昭35.2.4 刑法百選Ⅰ〔第7版〕30事件参照)。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義総)297頁。
基本刑法Ⅰ209頁。
条解刑法122頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第94条が条例制定権を認めている以上,条例の制定により,地域ごとに取扱いの差異が生じることは憲法自ら容認しているが,これは無条件に当該条例を合憲とする趣旨ではなく,各地域の条例相互間の差異が平等原則を破るような結果を生じた場合には,当該条例を違憲とする趣旨である。憲法この問題の模試受験生正解率 12.3%結果正解解説判例は,売春取締りに関する罰則を条例で定めることが憲法14条に反するかが争われた事例において,「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから,かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである」としている(最大判昭33.10.15 憲法百選Ⅰ〔第7版〕32事件)。同判決の補足意見においては,「その各条例相互の内容の差異が,憲法14条の原則を破るような結果を生じたときは,やはり違憲問題を生ずるものというべき」とした上で,「無条件に地域的差別取扱を合憲とする趣旨であるとするならば,私どもの遽に賛同し得ない」と述べられている。これに対して,多数意見においては,上記判示部分がいかなる趣旨かについては何ら述べられていない。よって,本記述は誤りである。
-
民法制限行為能力者に関して,成年被後見人がした財産上の法律行為は,全て制限行為能力を理由とする取消しの対象となる。民法この問題の模試受験生正解率 80.4%結果正解解説民法9条本文は,「成年被後見人の法律行為は,取り消すことができる。」と規定している。もっとも,同条ただし書は,成年被後見人の法律行為の取消しについて,「日用品の購入その他日常生活に関する行為については,この限りでない。」と規定している。日常生活に関する行為としては,公共料金の支払,支払に必要な預貯金等の引出し等が挙げられている。本記述は,成年被後見人がした財産上の法律行為については,全て制限行為能力を理由として取り消すことができるとしている点で誤っている。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)92頁。
新注釈民法(1)507頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,恨みを抱いているVを貶めるため,誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に,「Vはもうすぐ破産しそうだ。」との嘘の書き込みをしたが,現実にVの経済面における社会的信用が低下することはなかった。この場合,甲には,信用毀損罪が成立する。刑法この問題の模試受験生正解率 68.7%結果正解解説信用毀損罪は,虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて人の信用を毀損することにより成立する。ここに「虚偽の風説を流布」とは,客観的真実に反することを不特定又は多数の人に伝播させることをいう。本記述では,甲は誰でも閲覧できるインターネットの掲示板に,「Vはもうすぐ破産しそうだ。」との嘘の情報を書き込んでいる。これは客観的真実に反することを不特定又は多数の人に伝播させるものといえ,「虚偽の風説を流布」したに当たる。また,同罪の成立には,信用を毀損する行為がされれば足り,現実に信用低下の結果が発生することを要しない(大判大2.1.27)。本記述では,現実にVの経済面における社会の信頼が低下することはなかったものの,信用を毀損する行為はなされている。したがって,甲には,信用毀損罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)154頁。
基本刑法Ⅱ109頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第17条は,公務員の不法行為について,「法律の定めるところにより」損害賠償を請求し得る旨を定めており,その保障する損害賠償請求権について,法律による具体化を予定しているが,同条は,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねるものであって,立法府に無制限の裁量権を付与したものではないから,非権力作用に属する公務員の行為についてであっても,無条件に国又は公共団体の賠償責任を否定する法律は,違憲無効となる。憲法この問題の模試受験生正解率 68.3%結果正解解説判例は,郵便業務従事者が書留郵便物や特別郵便物を滅失・毀損した際の損害賠償額を制限していた郵便法旧68条,73条の憲法17条適合性が問題となった事例において,同条の趣旨につき,「憲法17条は,……その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない」としている(最大判平14.9.11 郵便法違憲判決 憲法百選Ⅱ〔第7版〕128事件)。つまり,同条は,公務員の違法な行為について権力作用か非権力作用かを区別せずに,原則として国又は公共団体の不法行為責任を認めているといえる。そして,同条は,法律に対し白紙委任することを認めているわけではないから,法律が,無条件に国又は公共団体の賠償責任を否定する等,同条の保障の趣旨を没却するような場合には,その法律は違憲無効になると解されている。よって,本記述は正しい。参考精読憲法判例(人権編)609~616頁。
平14最高裁解説(民事)607~608頁。 -
民法ABCが,Dから2,000万円を借り入れ,その返還債務を連帯債務とする契約(負担部分は,Aが5分の3,B,Cがそれぞれ5分の1ずつとする。)を締結した場合,Aのために消滅時効が完成した場合でも,B及びCは,Dに対して2,000万円の連帯債務を負う。民法この問題の模試受験生正解率 41.9%結果正解解説民法441条本文は,「第438条,第439条第1項及び前条に規定する場合を除き,連帯債務者の一人について生じた事由は,他の連帯債務者に対してその効力を生じない。」としており,原則として,更改,相殺及び混同以外の事由については,相対的効力事由とされている。したがって,連帯債務者の一人であるAのために消滅時効が完成しても,その効力はB及びCに及ばず,B及びCは,Dに対して2,000万円の連帯債務を負ったままである。よって,本記述は正しい。
なお,Aのために消滅時効が完成しても,B又はCが,債務を履行した場合には,Aに対して求償権を行使することができ(同445条参照),この場合においては,Aは自己の負担部分について,時効による債務からの解放の利益を受けられない。また,平成29年改正前民法439条は,連帯債務者の一人についての時効の完成を絶対的効力事由であるとし,その負担部分については,他の連帯債務者もその義務を免れるとしていた。しかし,これでは債権者は,全ての連帯債務者との間でも消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければ,特定の連帯債務者との間でも債権の全額を保全することはできず,また,同改正後民法によれば,履行の請求についても相対的効力しか認められないので(同改正後民法441条本文参照),債権者に大きな負担となる。そこで,同改正によって,同改正前民法439条は削除され,時効の完成を相対的効力事由とした。参考潮見(新債権総論Ⅱ)598~600頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)123頁,125頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,無許可のデモ行進に参加していたところ,警察官らがこれを解散させようとしたため,警察官らに向けて石を一回投げ付け,その石は警察官乙の耳のあたりをかすめたが乙には命中しなかった。甲には公務執行妨害罪は成立しない。刑法この問題の模試受験生正解率 90.7%結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当りこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって,その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく,妨害となるべきものであれば足りうるものである」とした上で,「投石行為はそれが相手に命中した場合は勿論,命中しなかった場合においても本件のような状況の下に行われたときは,暴行であることはいうまでもなく,しかもそれは相手の行動の自由を阻害すべき性質のものであることは経験則上疑を容れないものというべきである」としている(最判昭33.9.30 刑法百選Ⅱ〔第7版〕115事件)。したがって,甲には公務執行妨害罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義各)582頁。
基本刑法Ⅱ492頁。
条解刑法278頁。
科目名
科目名
解答日・解答結果
設問
設問・解答
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,市が遺族会に対し,忠魂碑の敷地として市の敷地を無償貸与することは,小学校の校舎の建替えのため,公有地上に存する戦没者記念碑的な性格を有する施設をほかの場所に移設し,その敷地として利用することを目的とするものであり,専ら世俗的なものといえ,その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等にはならず,政教分離規定に反しない。憲法この問題の模試受験生正解率 82.2%結果正解解説判例は,市が遺族会に対し,忠魂碑の敷地として市の敷地を無償貸与することが政教分離規定に反するかが争われた事例において,「箕面市が旧忠魂碑ないし本件忠魂碑に関してした次の各行為,すなわち,旧忠魂碑を本件敷地上に移設,再建するため右公社から本件土地を代替地として買い受けた行為(本件売買),旧忠魂碑を本件敷地上に移設,再建した行為(本件移設・再建),市遺族会に対し,本件忠魂碑の敷地として本件敷地を無償貸与した行為(本件貸与)は,いずれも,その目的は,小学校の校舎の建替え等のため,公有地上に存する戦没者記念碑的な性格を有する施設を他の場所に移設し,その敷地を学校用地として利用することを主眼とするものであり,そのための方策として,右施設を維持管理する市遺族会に対し,右施設の移設場所として代替地を取得して,従来どおり,これを右施設の敷地等として無償で提供し,右施設の移設,再建を行ったものであって,専ら世俗的なものと認められ,その効果も,特定の宗教を援助,助長,促進し又は他の宗教に圧迫,干渉を加えるものとは認められない。したがって,箕面市の右各行為は,宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である」としている(最判平5.2.16 箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟 憲法百選Ⅰ〔第7版〕46事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,他主占有者の相続人が自らの占有のみに基づいて時効取得を主張する場合,占有者の所有の意思は推定されるため,相続人の時効取得を争う相手方が,その占有が自己の意思に基づくものでないことを立証しなければならない。民法この問題の模試受験生正解率 59.2%結果正解解説判例は,占有者の承継人は,その選択に従い,自己の占有のみを主張することができるとする民法187条1項は,相続のような包括承継にも適用されるとしている(最判昭37.5.18)。そして,別の判例は,「他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合において」,その「占有が所有の意思に基づくものであるといい得るためには,取得時効の成立を争う相手方ではなく,占有者である当該相続人において,その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当である」としている(最判平8.11.12 民法百選Ⅰ〔第8版〕67事件)。よって,本記述は誤りである。
なお,判例は,「占有者は所有の意思で占有するものと推定される」(暫定真実 同186条1項)ため,取得時効の成立を争う相手方が,その「占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う」としている(最判昭54.7.31)。参考佐久間(物権)279頁,281~284頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,単純遺棄罪の客体は,「老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」と規定されているが,扶助を必要とする原因として挙げられている「老年,幼年,身体障害又は疾病」は,例示列挙であるから,老年,幼年,身体障害又は疾病の者以外で扶助を必要とする者も,単純遺棄罪の客体となり得る。刑法この問題の模試受験生正解率 34.5%結果正解解説単純遺棄罪(刑法217条)の客体は,「老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」であり,これらの扶助を要する原因は制限列挙であると解されている。したがって,老年,幼年,身体障害又は疾病の者以外で扶助を必要とする者は,単純遺棄罪の客体となり得ない。よって,本記述は誤りである。
なお,この点については,保護責任者遺棄罪(同218条)の客体についても同様に解されている。参考新基本法コメ(刑法)468頁。
基本刑法Ⅱ19~20頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第31条は,刑罰を科す手続を法律で定めることを要求するのみであり,刑罰の実体要件を法律で定めなければならないという罪刑法定主義を要求していないとする見解によっても,憲法第73条第6号や憲法第39条の規定から,罪刑法定主義は憲法上当然の前提とされていると解することができる。憲法結果正解解説憲法31条は,刑罰を科す手続を法律で定めることを要求するのみであり,刑罰の実体要件を法律で定めることを要求していないとする見解によれば,いわゆる罪刑法定主義は,同条の要求するところではない。もっとも,罪刑法定主義の内容として挙げられる行政命令による罰則制定の禁止や,遡及処罰の禁止が,それぞれ同73条6号と同39条で定められているから,罪刑法定主義は憲法上当然の前提とされていると解することができる。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)330~331頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)410~411頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,不当利得として利得した財貨が金銭債権に変わった場合,特段の事情がない限り,現存する利得は,債権の額面額相当の価値であると推定される。民法結果正解解説利得した金銭が貸金債権,預金債権,非債弁済による不当利得返還請求権等に形を変えている場合であっても,利得は存在すると解されている。例えば,AがBから利得した金銭を法律上の原因なしにCに交付した場合には,AのCに対する不当利得返還請求権の形で利得が現存することとなる。そして,判例は,このことを前提として,「債権の価値は債務者の資力等に左右されるものであるが,特段の事情のない限り,その額面金額に相当する価値を有するものと推定すべき」としている(最判平3.11.19)。特段の事情として,同判決は,第三債務者が,受領した金銭を喪失し,又は金銭返還債務を履行するに足る資力を失った等の事情を挙げている。したがって,このような特段の事情がない限り,不当利得として利得した財貨が金銭債権に変わった場合,現存する利得は,債権の額面額相当の価値であると推定される。よって,本記述は正しい。参考平3最高裁解説(民事)457~458頁。
-
刑法罪刑法定主義に関して,判例の立場に従って検討した場合,被告人にとって有利な方向に働くのであれば,類推解釈も許容される。刑法結果正解解説類推解釈ないし類推適用とは,法文で規定されている内容と,その法文の適用が問題となっているがその法規には含まれない事実との間に,類似ないし共通の性質があることを理由として,前者に関する法規を後者に適用することをいう。そして,類推解釈は,行為後に裁判官により刑罰法規が創造されるに等しいので,法律主義の要請(犯罪行為の事前告知の要請)に反するため,許されない。もっとも,類推解釈の禁止は,主として当該行為を行った者又は行おうとする者の権利と自由の保護のための原則であるから,その者に有利な方向での類推解釈は許される。よって,本記述は正しい。参考井田(総)59頁。
大谷(講義総)64頁。
リーガルクエスト(刑法総論)17頁。
基本刑法Ⅰ21頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法司法権の範囲ないし限界に関して,最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,裁判所は,衆参両議院の自主性を尊重するため,両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布された法律に関しては,法律制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断することはできない。憲法結果正解解説判例は,昭和29年に制定された新警察法の成立手続の違憲性を主張する住民訴訟が提起された事例において,「同法は両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する……事実を審理してその有効無効を判断すべきでない」として,両院の議事手続に対する司法審査を否定している(最大判昭37.3.7 警察法改正無効事件 憲法百選Ⅱ〔第6版〕186事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,抵当不動産の第三取得者が,抵当不動産につき必要費又は有益費を支出して民法第391条に基づく優先償還請求権を有している場合,抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため,第三取得者が優先償還を受けられなかったときには,第三取得者は,当該抵当権者に対し,不当利得返還請求をすることができない。民法結果正解解説抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは,民法196条の区別に従い,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けることができる(同391条)。そして,判例は,「抵当不動産の第三取得者が,抵当不動産につき必要費または有益費を支出して民法391条にもとづく優先償還請求権を有しているにもかかわらず,抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため,第三取得者が優先償還を受けられなかったときは,第三取得者は右抵当権者に対し民法703条にもとづく不当利得返還請求権を有する」としている(最判昭48.7.12)。その理由として,同判決は,当該必要費又は有益費の優先償還請求権は,不動産の価値を維持・増加するために支出された一種の共益費であり,最先順位の抵当権にも優先するものであること,抵当権者は,第三取得者との関係で第三取得者が受けるべき優先償還金に相当する金員の交付を受けてこれを保有する実質的理由を有しないことなどを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考川井(2)361頁。
道垣内Ⅲ175頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙と共に,V方に侵入してVに暴行を加え,金品を強取しようと企て,深夜,2人でV方付近に赴き,付近の下見などをした。その後,乙がV方に侵入し,甲がV方の前に停めた自動車内で見張りをしていたところ,現場付近に人が集まって来たため,甲は,犯行の発覚を恐れて,屋内にいる乙に電話をかけ,「人が集まって来ている。早くやめて出てきた方がいい。」と告げたが,乙から,「もう少し待て。」などと言われたので,「危ないから待てない。先に帰る。」と乙に一方的に告げ,自動車でその場から立ち去った。乙はいったんV方を出て,甲が立ち去ったことを知ったが,V方に戻って強盗を実行し,その際加えた暴行によりVに傷害を負わせた。この場合,甲には,住居侵入罪及び強盗致傷罪の共同正犯が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「見張り役の共犯者が既に住居内に侵入していた共犯者に電話で「犯行をやめた方がよい,先に帰る」などと一方的に伝えただけで,被告人において格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく待機していた場所から見張り役らと共に離脱したにすぎず,残された共犯者らがそのまま強盗に及んだものと認められる。そうすると,被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり,たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識した上で離脱し,残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても,当初の共謀関係が解消したということはできず,その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基づいて行われたものと認めるのが相当である」としている(最決平21.6.30 刑法百選Ⅰ〔第7版〕94事件)。したがって,本記述では,当初の共謀に基づく因果性が遮断されたとはいい難く,甲には,住居侵入罪(刑法130条前段)及び強盗致傷罪の共同正犯(同240条前段,60条)が成立する。よって,本記述は正しい。参考高橋(総)515~516頁。
基本刑法Ⅰ399~401頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,文書が持つ芸術性・思想性が,文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて,刑法が処罰の対象とする程度以下にわいせつ性を解消させる場合があることは考えられるものの,そのような程度にわいせつ性が解消されない限り,芸術的・思想的価値のある文書であっても,わいせつな文書としての取扱いを免れることはできない。憲法結果正解解説判例は,マルキ・ド・サドの「悪徳の栄え」の翻訳者と出版社社長が,出版物がわいせつ文書に当たるとして刑法175条違反で起訴された事例において,わいせつ性と芸術性の関係についてチャタレイ事件(最大判昭32.3.13 憲法百選Ⅰ〔第6版〕56事件)の見解に従う旨を述べた上で,「文書がもつ芸術性・思想性が,文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて,刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが,右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり,芸術的・思想的価値のある文書であっても,猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。当裁判所は,文書の芸術性・思想性を強調して,芸術的・思想的価値のある文書は猥褻の文書として処罰対象とすることができないとか,名誉毀損罪に関する法理と同じく,文書のもつ猥褻性によって侵害される法益と芸術的・思想的文書としてもつ公益性とを比較衡量して,猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は,採用することができない」としている(最大判昭44.10.15 「悪徳の栄え」事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕57事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関して,判例の趣旨に照らすと,Bが単独で甲土地を占有している場合でも,A及びCは,その共有持分が過半数を超えていることを理由としては,Bに対して,甲土地全体の明渡しを求めることはできない。民法結果正解解説判例は,その有する共有持分の価格が共有物の価格の過半数を超える多数持分権者が,共有物を単独で占有している少数持分権者(その有する共有持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者をいう。)に対してその明渡しを求めた事例において,多数持分権者であっても,共有物を現に占有する「少数持分権者に対し,当然にその明渡を請求することができるものではない」としている(最判昭41.5.19 民法百選Ⅰ〔第8版〕74事件)。その理由として,同判決は,「少数持分権者は自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有し,これに基づいて共有物を占有する」ことが認められることを挙げている。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)208~209頁。
平野(総則)321~322頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,強制性交等未遂罪の犯人が,強制性交の実行に着手した直後に,強盗の犯意を生じ,同じ被害者に対して,強盗罪の手段に当たる脅迫を行ったが財物を強取するには至らなかった場合には,強制性交等未遂罪と強盗未遂罪の併合罪となる。刑法結果正解解説平成29年改正以前の強盗強姦罪(旧刑法241条前段)は,強盗犯人が強姦行為に及んだ場合に限って成立し,強姦の後に強盗の犯意を生じて財物を強取した場合には同罪は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪となるにすぎないと解されていた(最判昭24.12.24)。しかし,強盗と強姦の前後がいずれであっても重大犯罪であることに変わりはないことから,現行の強盗・強制性交等罪(刑法241条1項)は,強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が,強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した場合,又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が,強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した場合のいずれでも成立するものと改められた。つまり,同一の機会に強盗行為と強制性交等の行為を行った場合,その先後にかかわりなく,強盗・強制性交等罪は成立する。また,同項は,強盗罪と強制性交等罪がいずれも未遂の場合であっても,強盗・強制性交等罪が成立する旨規定しているから,強盗・強制性交等罪には未遂犯を観念することはできず,同43条も適用されない。したがって,本記述の場合には,強盗・強制性交等罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)201~203頁。
基本刑法Ⅱ226~229頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第81条の規定は,最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であって,下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨ではなく,下級裁判所も違憲審査権を行使し得る。憲法結果正解解説判例は,「憲法は国の最高法規であってその条規に反する法律命令等はその効力を有せず,裁判官は憲法及び法律に拘束せられ,また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定」していることから,「裁判官が,具体的訴訟事件に法令を適用して裁判するに当り,その法令が憲法に適合するか否かを判断することは,憲法によって裁判官に課せられた職務と職権であって,このことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問わない。憲法81条は,最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であって,下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨をもっているものではない」としている(最大判昭25.2.1 憲法百選Ⅱ〔第4版〕200事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法成年後見人が,成年被後見人が所有する甲不動産を売却する前に被保佐人となった場合,法定代理人として甲不動産を売却するためには,その保佐人の同意を得なければならない。民法結果正解解説被保佐人が,成年被後見人の法定代理人として,民法13条1項1号から9号までに規定する行為をするには,その保佐人の同意を得なければならない(同項10号)。本記述において,成年後見人は,被保佐人となっており,不動産の売却は,不動産に関する権利の得喪を目的とする行為(同項3号)であるから,成年被後見人の法定代理人としてする甲不動産の売却について,保佐人の同意を得なければならない。よって,本記述は正しい。
なお,同13条1項10号は,平成29年民法改正において新設された規定であり,制限行為能力者の法定代理人も制限行為能力者である場合に,代理される本人が法定代理人の行為により不利益を被ることを避けるために,取消しの根拠規定を設けたものである。参考佐久間(総則)95頁,235頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)30~31頁。
新版注釈民法(1)358~359頁。 -
刑法甲は,乙の経営する店の道路に面する部分の全面に物を一面に並べ立てた。このとき,乙の事業は知事の許可を得ていない違法なものであった。この場合,甲には,威力業務妨害罪が成立する余地はない。刑法結果正解解説業務妨害罪にいう「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいう。ここで,違法な業務が同罪で保護されるかが問題となる。この点,同罪は事実上平穏に行われている人の社会的活動の自由を保護しようとするものである。そのため,「偽計」や「威力」などの手段から刑法上保護されることが相当と認められるものであれば,違法な業務であっても「業務」に含まれる。よって,本記述は誤りである。
なお,裁判例は,知事の許可を受けていない者が行う浴場営業(東京高判昭27.7.3),風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に反するパチンコ遊技客からの景品の買入れ(横浜地判昭61.2.18)について,同罪の「業務」に当たるとしている。参考山口(各)157頁。
基本刑法Ⅱ110~111頁。
新基本法コメ(刑法)505頁。
条解刑法694~695頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,憲法第22条第1項の「移転」とは,短期的な移動一般を意味するため,一時的な海外渡航の自由は,同項により保障される。憲法結果正解解説判例は,旅券発給拒否処分の憲法適合性が争われた事例において,「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含む」としている(最大判昭33.9.10 帆足計事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕111事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法不動産の譲渡担保権者が,その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって求償債権を取得した場合,当該求償債権は,譲渡担保設定契約に特段の定めがない限り,譲渡担保権の被担保債権に含まれない。民法結果正解解説判例は,「不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権は,譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り,譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれない」としている(最判昭61.7.15 昭61重判民法6事件)。その理由として,同判決は,「抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)の負担のある不動産に譲渡担保権の設定を受けた債権者は,目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除した価額についてのみ優先弁済権を有するにすぎず,そのような地位に立つことを承認し,右価額を引き当てにして譲渡担保権の設定を受けたのであるから,先順位の抵当債務を弁済し,これによって取得すべき求償債権をも当然に譲渡担保の被担保債権に含ませることまでは予定していないのが譲渡担保設定当事者の通常の意思であると解される」ことを挙げている。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ330頁。
-
刑法責任能力に関して,判例の立場に従って検討した場合,犯行当時,行為者に重度の精神疾患があった場合には,心神喪失の状態にあったと判断されなければならない。刑法結果正解解説心神喪失とは,精神の障害により,行為の是非善悪を弁識する能力(弁識能力)がないか,又はその弁識に従って行動する能力(制御能力)がない状態をいう(大判昭6.12.3 刑法百選Ⅰ〔第4版〕33事件)。この定義のうち,精神の障害を生物学的要素,弁識能力・制御能力を心理学的要素と呼んでいる。この点,生物学的要素である精神の障害(疾病判断)が責任能力の判断にどのように関係するかについて,判例は,被告人が犯行当時精神分裂病にり患していたからといって,直ちに心神喪失の状態であったとされるものではなく,その責任能力の有無・程度は,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判断すべきであるとしている(最決昭59.7.3 刑法百選Ⅰ〔第6版〕33事件)。したがって,犯行当時,行為者に重度の精神疾患があった場合でも,必ずしも心神喪失の状態にあったと判断されるわけではない。よって,本記述は誤りである。参考高橋(総)356~357頁。
基本刑法Ⅰ223頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法「法の支配」における「法」とは,議会が制定する形式的な法律をいい,その中身の合理性は問題とされない。憲法結果正解解説「法の支配」における「法」とは,内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念である。よって,本記述は誤りである。
なお,戦前のドイツの「法治国家」の観念における「法」とは,内容とは関係のない形式的な法律にすぎず,そこでは,議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかった。参考芦部(憲法)15頁。 -
民法消滅時効に関して,判例の趣旨に照らすと,不法行為の時から20年が経過した場合,裁判所は,当事者からの主張がなくとも,不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅したものと判断すべきである。民法結果正解解説民法724条2号は,不法行為による損害賠償請求権は,不法行為の時から20年間行使しない場合には時効によって消滅すると規定している。そして,時効は,当事者が援用しなければ,裁判所がこれによって裁判をすることができない(同145条)。したがって,不法行為の時から20年が経過した場合であっても,裁判所は,当事者からの主張なく,損害賠償請求権が時効によって消滅したものと判断することはできない。よって,本記述は誤りである。
なお,平成29年改正前民法下における判例は,「民法724条後段の規定は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当である」とした上で,「裁判所は,除斥期間の性質にかんがみ,本件請求権が除斥期間の経過により消滅した旨の主張がなくても,右期間の経過により本件請求権が消滅したものと判断すべきであ」るとしていた(最判平元.12.21 平元重判民法9事件)。しかし,上述のように,同改正により,20年の期間も時効期間であることが明らかにされた。参考佐久間(総則)414頁,431~432頁。
平野(総則)438~441頁。
潮見(基本講義・債各Ⅱ)137頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)63~64頁。 -
刑法偽証の罪に関して,判例の立場に従って検討した場合,甲は,宣誓の上で偽証をしたが,その証言をした事件について,その裁判が確定する前に裁判所に対して偽証した事実を具体的に告白した。この場合,甲には,偽証罪が成立するが,その刑を減軽し,又は免除することができる。刑法結果正解解説刑法170条は,「前条の罪(注:偽証罪)を犯した者が,その証言をした事件について,その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。」と規定している。自白とは,偽証した事実を具体的に告白することであるところ,自白は,自ら積極的に申し立てる場合のほかに,尋問に応じて告白する場合でもよい。そして,自白の相手方は,裁判所,捜査機関,懲戒権者に限られる。本記述において,偽証をした甲は,その証言をした事件について,その裁判が確定する前に裁判所に対して自白している。したがって,甲には,偽証罪が成立するが,その刑を減軽し,又は免除することができる。よって,本記述は正しい。参考山口(各)597頁。
基本刑法Ⅱ550頁。
条解刑法480頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,未決拘禁者に喫煙を許すと,罪証隠滅のおそれや火災発生の場合の逃走も予想される一方で,たばこは嗜好品にすぎず,その禁止は人体に直接障害を与えるものではないことからすると,未決拘禁者について喫煙の自由を一般に認めないのはやむを得ない措置というべきである。憲法結果正解解説判例は,未決拘禁者の喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反するかが争われた事例において,「未決勾留は,刑事訴訟法に基づき,逃走または罪証隠滅の防止を目的として,被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ,監獄内においては,多数の被拘禁者を収容し,これを集団として管理するにあたり,その秩序を維持し,正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには,被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく,右の目的に照らし,必要な限度において,被拘禁者のその他の自由に対し,合理的制限を加えることもやむをえないところである」とした上で,未決拘禁者の喫煙の自由を認めることは,通謀とそれに伴う罪証隠滅のおそれ及び火災発生による被拘禁者の逃走のおそれを生じさせること,たばこが嗜好品にすぎず,喫煙の禁止が人体に直接障害を与えるものではないことからすれば,「喫煙の自由は,憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても,あらゆる時,所において保障されなければならないものではない。したがって,このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容,制限の必要性などの関係を総合考察すると,……喫煙禁止という程度の自由の制限は,必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり,(旧)監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえない」としている(最大判昭45.9.16 憲法百選Ⅰ〔第6版〕15事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法錯誤に関して,判例の趣旨に照らすと,他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,その旨が債権者に対して表示されていなくても,連帯保証契約について錯誤による取消しをすることができる。民法結果正解解説意思表示は,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(以下「動機の錯誤」という。)に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができるが(民法95条1項2号),同号による取消しが認められるためには,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている必要がある(同条2項)。判例は,平成29年改正前民法下における本記述と同様の事例において,「保証契約は,保証人と債権者との間に成立する契約であって,他に連帯保証人があるかどうかは,通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず,当然にはその保証契約の内容となるものではない」として,他に連帯保証人がいるとの誤信は,動機の錯誤であるとしている(最判昭32.12.19 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕17事件)。したがって,他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,その旨が債権者に対して表示されていない場合,連帯保証契約について錯誤による取消しをすることはできない。よって,本記述は誤りである。参考四宮・能見(民法総則)253頁。
我妻・有泉コメ205頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)22~23頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が,懲役5年の言渡しを受けた場合,その刑の全部の執行を猶予することはできない。刑法結果正解解説初度の刑の全部の執行猶予は,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間を定めて,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた者に対してすることができる(刑法25条1項柱書)。したがって,懲役5年の言渡しを受けた場合には,その刑の全部の執行を猶予することはできない。よって,本記述は正しい。参考西田(総)461~462頁。
松宮(総)350~351頁。
基本刑法Ⅰ448頁。
条解刑法52~54頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法日本国憲法が「法の支配」の原理に立脚していることは,憲法の最高法規性の明確化,不可侵の人権の保障,司法権の拡大強化等からみて明らかである。憲法結果正解解説日本国憲法は,①憲法の最高法規性の明確化(同98条1項),②不可侵の人権の保障(同3章),③適正手続の保障(同31条),④司法権の拡大強化(司法裁判所によるあらゆる法律上の争訟の裁判)(同76条),及び,⑤裁判所の違憲審査制の確立(同81条)からみて「法の支配」の原理に立脚していることが明らかであるといえる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)13~14頁。
佐藤幸(日本国憲法論)74頁。
芦部(憲法学Ⅰ)111頁。 -
民法安易な認知を防止し,また認知者の意思によって認知された子の身分関係が不安定となることを防止する必要があるので,血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,自らした認知の無効を主張することができない。民法結果正解解説子その他の利害関係人は,認知に対して反対の事実を主張することができる(民法786条)。判例は,同条の「利害関係人」に認知者自身が含まれるかが争われた事例において,「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができる」とし,「この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない」としている(最判平26.1.14 民法百選Ⅲ〔第2版〕33事件)。その理由として,同判決は,「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ,認知者が認知をするに至る事情は様々であり,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない」ことや,「認知を受けた子の保護の観点からみても,あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏し」いこと,及び,認知者が当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし,認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が,認知の取消しを禁止する同785条によって制限されると解することもできないことなどを挙げている。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決における大橋正春裁判官の反対意見は,認知者の意向によって被認知者の地位を不安定にすることを許してよいかという点で,「認知した父は子その他の利害関係人とは全く異なる立場に立つのであるから,他の利害関係人に認められるから当然に認知した父にも認めるべきであるということにはならない」こと等を理由として,認知者は,血縁上の父子関係が存在しないことを理由として認知の無効を主張することができないとしている。参考リーガルクエスト(親族・相続)140頁。 -
刑法甲は,乙から,乙が海中に取り落した腕時計の引き揚げを依頼されて,落下場所の大体の位置について指示を受けた。甲が,その腕時計をその付近で発見し,乙に知らせずに,自己のものとした場合,甲には窃盗罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,原判決の「海中に取り落した物件については,落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が,その落下場所の大体の位置を指示し,その引揚方を人に依頼した結果,該物件がその附近で発見されたときは,依頼者は,その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態とを有するものといえるから,依頼者は,その物件の現実の握持なく,現物を見ておらず且つその物件を監視していなくとも,所持すなわち事実上の支配管理を有するものと解すべき」旨の判示を正当としている(最決昭32.1.24)。したがって,甲には窃盗罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考高橋(各)242頁。
新基本法コメ(刑法)521頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法刑事補償に関して,最高裁判所の判例によれば,不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても,そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは,その部分は,憲法第40条の「抑留又は拘禁」に含まれる。憲法結果正解解説判例は,ある公訴事実について無罪を言い渡された被告人が,当該公訴事実において,不起訴処分となった別の被疑事実の勾留中に取り調べられた事実が内容とされているとして,その勾留に対する刑事補償請求をしたことにつき,その可否が争われた事例において,「憲法40条は,「……抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたとき……」と規定しているから,抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となった場合は同条の補償の問題を生じない」とした上で,しかし,「憲法40条にいう「抑留又は拘禁」中には,無罪となった公訴事実に基く抑留または拘禁はもとより,たとえ不起訴となった事実に基く抑留または拘禁であっても,そのうちに実質上は,無罪となった事実についての抑留または拘禁であると認められるものがあるときは,その部分の抑留及び拘禁もまたこれを包含する」としている(最大決昭31.12.24 憲法百選Ⅱ〔第6版〕134事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法契約の申込みの意思表示は,申込みの通知が相手方に到達した後に,申込者が死亡した場合において,相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったとしてもその効力を失わない。民法結果正解解説申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において,相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を生じない(民法526条)。そして,同条は,通知が相手方に到達した後に申込者が死亡した場合についても適用される。したがって,本記述において,相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡を知ったときは,申込みは,その効力を生じない。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)89~90頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)219~220頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,精神の障害により通常の判断能力のないVの殺害を計画し,Vに対し,首を吊ってもしばらくすれば生き返るとだまして,Vに首を吊らせて窒息死させた。この場合,甲には,自殺教唆罪が成立する。刑法結果正解解説殺人行為は,間接正犯の方法でも行うことができるところ,判例は,本記述と同様の事例において,「第一審判決は,本件被害者が通常の意思能力もなく,自殺の何たるかを理解しない者であると認定したのであるから,判示事実に対し刑法202条を以て問擬しないで同法199条を適用したのは正当であ」るとして,殺人罪の間接正犯の成立を認めている(最決昭27.2.21)。本記述においては,自殺教唆のような外形を呈しているものの,被害者に自殺の意味を理解する能力がない以上,甲には自殺教唆罪(同202条前段)ではなく殺人罪(同199条)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考高橋(総)437頁。
基本刑法Ⅰ161頁。
基本刑法Ⅱ13~14頁。
新基本法コメ(刑法)436頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,犯行当時少年であった者の経歴等に関する記事について,仮名を用いて週刊誌に掲載した場合,それが少年法第61条が禁止する推知報道に該当するか否かは,少年と面識を有する特定の読者が,その者が当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準として判断すべきである。憲法結果正解解説判例は,出版社が犯行時に少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことが,少年法61条が禁止する推知報道に該当するかどうかなどが争われた事例において,「少年法61条に違反する推知報道かどうかは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」としている(最判平15.3.14 長良川事件報道訴訟 憲法百選Ⅰ〔第6版〕71事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関して,判例の趣旨に照らすと,裁判所に請求して甲土地の分割をする場合,甲土地をA及びBの共有として,A及びBからCに対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。民法結果正解解説共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは,その分割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)。この裁判による分割においては,現物分割が原則であり,例外として共有物の競売による代金分割のみが認められている(同条2項)。しかし,同条は,これ以外の例外を否定する趣旨ではなく,最も適切な共有関係の解消方法を探るべきであると解されている。判例も,「当該共有物の性質及び形状,共有関係の発生原因,共有者の数及び持分の割合,共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値,分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し,当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ,かつ,その価格が適正に評価され,当該共有物を取得する者に支払能力があって,他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは,共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし,これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法,すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許される」としており(最判平8.10.31 民法百選Ⅰ〔第8版〕76事件),同条が予定していない分割方法を認めている。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)216~218頁。
平野(総則)335~337頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,罪刑法定主義は,民主主義の原理と自由主義の原理によって根拠付けられる。刑法結果正解解説罪刑法定主義とは,犯罪と刑罰は法律で事前に定めておかなければならないという原則である。民主主義の原理は,国民の代表である国会において法律を定めるという原理として理解されるところ,この原理は,犯罪と刑罰を定める刑法にも妥当する。つまり,刑罰法規は国民自身が議会を通じて法律で決定しなければならないことになる(法律主義)。また,自由主義の原理は,事前に何が禁止され,何が許されるかを国民に予告することによって,国民が予測可能性を持つことができるという自由主義的要請である。このことから,行為後に制定された刑罰法規を,制定前の行為に遡及的に適用して,その行為を犯罪として処罰することも禁止される(遡及処罰の禁止)。このように,罪刑法定主義は,民主主義の原理と自由主義の原理に根拠付けられる。よって,本記述は正しい。参考高橋(総)31~32頁。
基本刑法Ⅰ13~14頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,強制加入団体である税理士会が政治団体に金員を寄附することは,たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても,税理士会の目的の範囲外の行為である。憲法結果正解解説判例は,強制加入団体である税理士会が政党など政治資金規正法(以下「規正法」という。)上の政治団体に金員を寄附することが,税理士会の目的の範囲内の行為といえるかなどが問題となった事例において,「政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは,選挙における投票の自由と表裏を成すものとして,会員各人が市民としての個人的な政治的思想,見解,判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである」とし,「税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは,たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても,……税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない」としている(最判平8.3.19 南九州税理士会政治献金事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕39事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,主たる債務者から委託を受けた保証人が,主たる債務者に対して事前求償権を取得した後に当該保証人が免責行為によって事後求償権を取得した場合,これらの両求償権は同一の権利であるから,その消滅時効は,事前求償権が発生しこれを行使することができる時から進行する。民法結果正解解説判例は,主たる債務者から委託を受けて保証をした保証人(以下「委託を受けた保証人」という。)が,弁済その他自己の出捐をもって主たる債務を消滅させるべき行為(以下「免責行為」という。)をしたことにより,民法459条1項の規定に基づき主たる債務者に対して取得する求償権(以下「事後求償権」という。)は,免責行為をしたときに発生し,かつ,その行使が可能となるものであるから,その消滅時効は,委託を受けた保証人が免責行為をした時から進行するものと解すべきであり,このことは,委託を受けた保証人が,同460条各号所定の事由,又は主たる債務者との合意により定めた事由が発生したことに基づき,主たる債務者に対して免責行為前に求償をし得る権利(以下「事前求償権」という。)を取得したときであっても異なるものではないとしている(最判昭60.2.12 昭60重判民法1事件)。その理由として,同判決は,「事前求償権は事後求償権とその発生要件を異にするものであることは前示のところから明らかであるうえ,事前求償権については,事後求償権については認められない抗弁が付着し,また,消滅原因が規定されている(同法461条参照)ことに照らすと,両者は別個の権利であり,その法的性質も異なるものというべきであり,したがって,委託を受けた保証人が,事前求償権を取得しこれを行使することができたからといって,事後求償権を取得しこれを行使しうることとなるとはいえない」ことを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考潮見(プラクティス債総)651~652頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,従犯に対し,正犯者に言い渡される具体的宣告刑より重い刑が言い渡されることはあり得ない。刑法結果正解解説「従犯の刑は,正犯の刑を減軽する。」とされている(刑法63条)。「正犯の刑を減軽する」とは,正犯に対する法定刑に法律上の減軽(同68条以下)を施して従犯の処断刑を定めるという趣旨である。したがって,従犯に対し,正犯者に言い渡される具体的宣告刑より重い刑が言い渡されることもあり得る(大判昭13.7.19)。よって,本記述は誤りである。参考大谷(講義総)450頁。
基本刑法Ⅰ356~357頁。
条解刑法243頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,未決拘禁者が刑事施設内で特定の新聞を私費により定期購読することを同施設の長が制限することが許されるのは,その閲読を許すことにより刑事施設内の規律及び秩序の維持に明白かつ現在の危険を生ずる蓋然性が認められる場合に限られる。憲法結果正解解説判例は,未決拘禁者が私費で定期購読している新聞のある特定の記事について,刑事施設の長が全面的に抹消したことから,その抹消処分は当該未決拘禁者の知る権利を侵害するとして争われた事例において,新聞等の閲読の自由が憲法19条や同21条の規定の趣旨,目的からその派生原理として導かれるとした上で,被拘禁者の新聞等の閲読の自由を制限することが許されるためには,当該閲読を許すことにより監獄(現:刑事施設)内の「規律及び秩序が害される一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該新聞紙,図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり,かつ,その場合においても,右の制限の程度は,右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべき」としている(最大判昭58.6.22 よど号ハイジャック記事抹消事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕16事件)。したがって,同判決は,刑事施設の長が未決拘禁者の新聞等の閲読の自由を制限するための要件について,刑事施設内の規律及び秩序に明白かつ現在の危険を生ずる蓋然性が認められる場合に限られるとはしていない。よって,本記述は誤りである。
-
民法精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるとして,本人が,保佐開始の審判を請求した場合であっても,家庭裁判所は,請求者本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認めるときは,保佐開始の審判をすることができない。民法結果正解解説民法11条本文は,「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については,家庭裁判所は,本人……の請求により,保佐開始の審判をすることができる。」としている。もっとも,同条ただし書は,「第7条に規定する原因がある者については,この限りでない。」としている。本記述において,請求者である本人は,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認められており,同条に規定する原因がある者に当たる。したがって,家庭裁判所は,保佐開始の審判をすることができない。よって,本記述は正しい。参考我妻・有泉コメ65頁。
新注釈民法(1)517~518頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,相手方から急迫不正の侵害を受けた者が,相手方に対し専ら攻撃の意思で反撃を行った場合,正当防衛が成立する余地はない。刑法結果正解解説「防衛するため」の行為といえるために,防衛の意思が必要か否かについては学説上争いがあるが,判例は一貫して必要説に立っている(大判昭11.12.7等)。そして,防衛の意思の内容について,判例は明確な定義を示していないが,急迫不正の侵害を受けた者が「憤激または逆上して反撃を加えたからといって,ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」(最判昭46.11.16 刑法百選Ⅰ〔初版〕36事件)とし,「防衛の意思と攻撃の意思が併存している場合の行為は,防衛の意思を欠くものではない」としている(最判昭50.11.28 刑法百選Ⅰ〔第7版〕24事件)。もっとも,判例は,「攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情」があるとき(前掲最判昭46.11.16)や,「防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為」(前掲最判昭50.11.28)については,防衛の意思は認められないとしている。したがって,専ら攻撃の意思で反撃行為がなされたときには防衛の意思は認められず,正当防衛が成立する余地はない。よって,本記述は正しい。参考大谷(講義総)283~284頁。
井田(総)309~310頁。
高橋(総)287頁。
基本刑法Ⅰ187頁,189頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,市町村長は,原則として転入届を受理しなければならないが,地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合には,これを受理しないことが許される。憲法結果正解解説判例は,ある宗教団体の信者が転入届を政令指定都市内の区の区長に提出したが,区長が受理しなかったため,当該不受理処分の取消し及び国家賠償を請求した事例において,「住民基本台帳は,これに住民の居住関係の事実と合致した正確な記録をすることによって,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするものであるから」,区長は,転入届がされた場合には,その者に新たに当該区の区域内に住所を定めた事実があれば,法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されないとした上で,上告人(区長)の「地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合には,転入届を受理しないことが許される」という主張は「実定法上の根拠を欠く」としている(最判平15.6.26 地方自治百選〔第4版〕15事件)。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)297頁。
-
民法判例の趣旨に照らすと,債権を質権の目的とした場合,質権設定者は質権者に対し当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い,当該債権の放棄,免除,他の債務との相殺をすることができない。民法結果正解解説判例は,「債権が質権の目的とされた場合において,質権設定者は,質権者に対し,当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い,債権の放棄,免除,相殺,更改等当該債権を消滅,変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行うことは,同義務に違反するものとして許されない」としている(最判平18.12.21 民法百選Ⅰ〔第8版〕83事件)。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ116頁。
-
刑法判例の立場に従って検討した場合,代表取締役が,権限を濫用して自己の利益を図るために有価証券を作成した場合,有価証券偽造罪が成立する。刑法結果正解解説代表取締役や支配人が,権限を濫用して自己又は第三者の利益を図るために有価証券を作成した場合,代表取締役や支配人は,本人の営業に関し,自己の代表・代理名義又は本人名義を使用して手形等を作成する一般的権限を法律上当然に有しており,客観的には権限の範囲内の行為であるから,作成名義に偽りはなく有価証券偽造罪(刑法162条1項)は成立しない(大連判大11.10.20)。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)359頁。
基本刑法Ⅱ444頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例の趣旨に照らすと,酒類販売業の免許制は,酒類販売店の濫設に伴う酒類販売店相互間の過当競争によって招来されるであろう酒類販売店の共倒れから酒類販売店を保護するという積極目的に基づく規制である。憲法結果正解解説判例は,酒税法の定める酒類販売免許制度が憲法22条1項の定める職業選択の自由に違反するかが争われた事例において,「租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については,その必要性と合理性についての立法府の判断が,右の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するもので,著しく不合理なものでない限り,これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない」としている(最判平4.12.15 憲法百選Ⅰ〔第6版〕99事件)。したがって,同判決は,租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的を認定しているのであって,酒類販売店の共倒れから酒類販売店を保護するという積極目的を認定しているのではない。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例の趣旨に照らすと,離婚による財産分与には慰謝料を含めることもできるが,既になされた財産分与に慰謝料を含めた趣旨とは解されないか,又はその額及び方法において不十分と認められる場合には,別個に慰謝料を請求することができる。民法結果正解解説判例は,「裁判所が財産分与を命ずるかどうかならびに分与の額および方法を定めるについては,当事者双方におけるいっさいの事情を考慮すべきものであるから,分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であって,その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには,右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできる」とし,「財産分与として,右のように損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には,さらに請求者が相手方の不法行為を理由に離婚そのものによる慰藉料の支払を請求したときに,その額を定めるにあたっては,右の趣旨において財産分与がなされている事情をも斟酌しなければならないのであり,このような財産分与によって請求者の精神的苦痛がすべて慰藉されたものと認められるときには,もはや重ねて慰藉料の請求を認容することはできない」としつつ,「財産分与がなされても,それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか,そうでないとしても,その額および方法において,請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるものであるときには,すでに財産分与を得たという一事によって慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく,別個に不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求することを妨げられない」としている(最判昭46.7.23 民法百選Ⅲ〔第2版〕18事件)。よって,本記述は正しい。参考リーガルクエスト(親族・相続)98~99頁。
新基本法コメ(親族)87~88頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,深夜,自己が所有する無人の倉庫に放火しようと考え,ポリタンクに灯油を入れてライターを持って同倉庫に向かっていたところ,甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け,同倉庫に放火するに至らなかった。この場合,甲には,放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。刑法結果正解解説放火の罪の予備罪(刑法113条)は,現住建造物等放火罪(同108条)又は他人所有非現住建造物等放火罪(同109条1項)を犯す目的のある場合にのみ成立する。本記述において,甲が放火しようとしていたのは,自らが所有する無人の倉庫であり,自己所有の非現住建造物である。したがって,甲には,放火予備罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考条解刑法349頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例の趣旨に照らすと,現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。憲法結果正解解説判例は,夫婦が夫又は妻の氏を称すると定める民法750条が,憲法13条,14条1項,24条に反するかが争われた事例において,「氏は,個人の呼称としての意義があり,名とあいまって社会的に個人を他人から識別し特定する機能を有するものであることからすれば,自らの意思のみによって自由に定めたり,又は改めたりすることを認めることは本来の性質に沿わないもの」であり,また,「氏に,名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることからすれば,氏が,親子関係など一定の身分関係を反映し,婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは,その性質上予定されている」とした上で,「現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえ」ず,民法750条の規定は,「憲法13条に違反するものではない」としている(最大判平27.12.16 平28重判憲法7事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例の趣旨に照らすと,保証人が法人ではない場合において,主たる債務者が期限の利益を喪失したときは,債権者は,保証人に対し,その利益の喪失を知った時から2か月以内に,その旨を通知しなければならない。民法結果正解解説民法458条の3第1項は,主たる債務者が期限の利益を有する場合において,その利益を喪失したときは,債権者は,保証人に対し,その利益の喪失を知った時から2か月以内に,その旨を通知しなければならない,と規定する。そして,同項は,保証人が法人である場合には,適用されない(同458条の3第3項)。保証人が早期に支払をすることで,多額の遅延損害金の発生を防ぐことを可能とするものであり,個人の保証人を保護する趣旨である。よって,本記述は正しい。
なお,上記通知は,債権者において,主債務者の期限の利益喪失を知った時から2か月以内に保証人に到達することが必要であり,債権者が,上記通知をしなかった場合又は上記通知が2か月以内に保証人に到達しなかった場合には,債権者は,遅延損害金についての保証債務の履行の請求について制限を受けることとなる(同458条の3第2項)。参考潮見(プラクティス債総)623~624頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)133~134頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,オレンジジュースに睡眠薬の粉末及び麻酔薬を混入し,事情を知らない乙にこれを飲ませ,乙を意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状に陥らせた。乙が約6時間安静にするうちにその症状が完治した場合,甲には,傷害罪は成立しない。刑法結果正解解説傷害罪の「傷害」とは,被害者の健康状態を不良に変更し,その生活機能の障害を惹起することをいう(最決昭32.4.23 刑法百選Ⅱ〔第2版〕4事件)。判例は,本記述と同様の事例において,「被告人は,……被害者に対し,睡眠薬等を摂取させたことによって,約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ,もって,被害者の健康状態を不良に変更し,その生活機能の障害を惹起した」として,傷害罪の成立を認めている(最決平24.1.30 刑法百選Ⅱ〔第7版〕5事件)。したがって,甲には,傷害罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考井田(各)47頁。
基本刑法Ⅱ31~32頁。
条解刑法590頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法の規範内容が踏みにじられたり不当に変質させられたりしないようにする様々な国法上の工夫は,広く「憲法の保障」といわれるが,その代表的な方法や考え方に関して,憲法第99条で規定される憲法尊重擁護義務の主体として,国民が挙げられていないのは,国民に憲法に対する忠誠を要求することにより,国民の権利自由が侵害されることを恐れた結果であると考えることができる。憲法結果正解解説憲法99条は,「天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定しており,憲法尊重擁護義務の主体として国民を挙げていない。そして,同条の主体として国民を挙げていない点について,国民に憲法に対する忠誠を要求することにより,国民の権利自由が侵害されることを恐れた結果であるとする見解などがある。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)386頁。
佐藤幸(日本国憲法論)45~48頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)400頁。 -
民法交通事故による損害賠償に関して,加害者が一定額を支払うと約し,被害者がその余の請求を放棄する旨の和解がなされた場合,その後,和解当時予想できなかった後遺症が生じ,損害が拡大したときであっても,被害者は当該後遺症の損害について賠償請求をすることができない。民法結果正解解説判例は,「一般に,不法行為による損害賠償の示談において,被害者が一定額の支払をうけることで満足し,その余の賠償請求権を放棄したときは,被害者は,示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても,あるいは,それ以上の損害が事後に生じたとしても,示談額を上廻る損害については,事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である」とした上で,「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて,早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては,示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は,示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって,その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで,賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは,当事者の合理的意思に合致するものとはいえない」としている(最判昭43.3.15 民法百選Ⅱ〔第8版〕104事件)。同判決は示談契約の効力が問題となった事例であるが,被害者が一定額以上の損害賠償請求権を放棄したことが「譲歩」(民法695条)に当たるため,当該示談契約の法的性質は和解であると解される。したがって,同判決の採用した判断基準に従い,交通事故による損害賠償に関して和解がなされた場合であっても,その後,和解当時予想できなかった後遺症が生じ,損害が拡大したときは,当該後遺症の損害について賠償請求をすることができる。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)601~602頁。
我妻・有泉コメ1361~1362頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,盗品であることを知りながら,窃盗犯人から盗品を有償で譲り受けた者が,更にこれを運搬した場合,盗品等有償譲受け罪のほかに盗品等運搬罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,同一人が既に有償で取得した盗品を他に運搬することは,犯罪によって得たものの事後処分にすぎないのであって,刑法はかかる行為をも刑法256条2項によって処罰する法意でないことは明らかであるとしている(最判昭24.10.1)。したがって,盗品であることを知りながら,窃盗犯人から盗品を有償で譲り受けた者が,更にこれを運搬した場合,盗品等有償譲受け罪(同項)のみが成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)348頁。
大コメ(刑法・第3版)(13)749頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法地方公共団体の議会は,住民の代表機関であり,議決機関である点において国会と同じ性質を有しているため,国会が国権の最高機関であるのと同様に,地方自治権の最高機関たる地位にある。憲法結果正解解説地方公共団体の議会は,住民の代表機関であり,議決機関である点において国会と同じ性質を有している。しかし,地方公共団体の長は,住民により公選され,住民に対し直接責任を負うため(首長制),地方議会は執行機関たる長と独立対等の関係に立つとされる。したがって,国会が国権の最高機関であるのとは異なり,地方公共団体の議会は,地方自治権の最高機関たる地位にあるわけではない。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)373頁。
基本法コメ(憲法)421頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,建物の賃借人は,明確な合意のない限り,通常の使用及び収益によって生じた建物の損耗や建物の経年変化について原状回復義務を負わない。民法結果正解解説賃借人は,賃借物を受け取った後にこれによって生じた損傷がある場合において,賃貸借が終了したときは,その損傷を原状に復する義務を負う(民法621条本文)。賃借人が原状回復義務を負う「損傷」は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除いたものを指す(同条本文括弧書)。そして,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化について賃借人に原状回復義務を負担させる要件について,判例は,「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約……が明確に合意されていることが必要である」としている(最判平17.12.16 消費者法百選24①事件,平17重判民法8事件)。よって,本記述は正しい。参考中田(契約)396頁,404~405頁。
一問一答(民法(債権関係)改正)325頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,借金の返済に苦しんでいた甲は,別人を装って消費者金融会社から借入れを行うことを思い立ち,市役所職員乙に対し,虚偽の生年月日を記載した自己名義の住民異動届に,転入によって国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨を付記して提出するなどして,これを誤信した乙から国民健康保険被保険者証の交付を受けた。この場合,甲には,詐欺罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,文書の不正取得のうち,印鑑証明書や旅券など,単に証明の利益をもたらすにすぎない文書の不正取得については,詐欺罪の成立を否定している(大判大12.7.14,最判昭27.12.25)。しかし,保険医療機関に提示することにより医療費の負担軽減などの経済的利益を享受し得る国民健康保険被保険者証のように,財産的給付を取得し得る地位をもたらす文書を不正取得した事例においては,詐欺罪の成立を肯定している(最決平18.8.21)。したがって,甲には,詐欺罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)270~272頁。
基本刑法Ⅱ254頁。
条解刑法759頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例の趣旨に照らすと,憲法第26条第2項後段にいう「無償」とは,子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき,その対価を徴収しないことを定めたものであり,教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから,同項にいう無償とは,授業料不徴収の意味である。憲法結果正解解説判例は,「憲法26条2項後段の「義務教育は,これを無償とする。」という意義は,国が義務教育を提供するにつき有償としないこと,換言すれば,子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき,その対価を徴収しないことを定めたものであり,教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから,同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」としている(最大判昭39.2.26 教科書費国庫負担請求事件 憲法百選Ⅱ〔第6版〕A6事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法養親が夫婦である場合において,離縁時に養子が18歳であるとき,協議上の離縁をするには,家庭裁判所の許可が必要であり,かつ,夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き,夫婦が共にしなければならない。民法結果正解解説民法は,普通養子縁組の養親が夫婦である場合において,未成年者と離縁をするときは,夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き,夫婦共同離縁を原則とする旨規定している(同811条の2)。もっとも,協議離縁について,同811条1項は,「縁組の当事者は,その協議で,離縁をすることができる」と規定するのみであり,子が未成年者である場合であっても,離縁につき家庭裁判所の許可は要件とされていない。よって,本記述は誤りである。
なお,養子となる者が未成年者である場合,縁組の成立について家庭裁判所の許可が原則として必要とされている(同798条本文)。参考リーガルクエスト(親族・相続)158頁。
窪田(家族法)257頁。
新基本法コメ(親族)178頁,180~181頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,緊急避難の要件である「現在の危難」は,法益に対する侵害が現実に存在することを意味し,侵害が差し迫っているだけでは足りない。刑法結果正解解説緊急避難の要件である「現在の危難」には,法益侵害が現実に存在する場合のみならず,法益侵害の危険が切迫している場合も含まれる。判例は,正当防衛にいう「急迫」(刑法36条1項)とは,「法益の侵害が間近に押し迫ったことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味する」とした上で,緊急避難の要件である「現在の危難」についてもこれと同様に解するとしている(最判昭24.8.18 刑法百選〔初版〕11事件)。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)123頁,149頁。
基本刑法Ⅰ209頁。
条解刑法122頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与する場合,国会の議決に基づかなければならないが,この議決には,憲法上,衆議院の優越が認められている。憲法結果正解解説憲法8条は,「皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない。」と規定している。これは,皇室に戦前のように巨大な財産が集中するのは好ましくないと考え,皇室と国民の間の財産授受に国会のコントロールを加えようとするものである。もっとも,法律や予算の議決の場合と異なり,この議決には,憲法上,衆議院の優越は認められておらず,衆議院と参議院の意見の一致が必要である(同59条2項,60条2項参照)。よって,本記述は明らかに誤りである。参考芦部(憲法)53頁。
佐藤幸(日本国憲法論)524頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)144~145頁。
新基本法コメ(憲法)44~45頁。 -
民法判例の趣旨に照らすと,民法第94条第2項にいう「第三者」には,債権を他に仮装譲渡した者がその譲渡の無効を主張してその債権の弁済を求めた場合の債務者も含まれる。民法結果正解解説判例は,債権を他に仮装譲渡した者がその譲渡の無効を主張してその債権の弁済を求めた場合の債務者について, 債務者がその譲渡が虚偽であることを知っていたとしてもその譲受人に対し債務を負担することはなく,債務者が譲渡行為の目的たる債権につき法律上の利害関係を有するに至った者ということはできないとして,民法94条2項の「第三者」には当たらないとしている(大判昭8.6.16)。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)123頁。
-
刑法甲は,乙が居住する家屋に放火しようと考え,乙の留守中に同家屋に忍び込み,マッチで畳に火をつけた。しかし,乙がその直後に帰宅し,急いで消火したため,畳だけが焼損した。この場合,判例の立場に従って検討すると,甲には,現住建造物等放火罪(刑法第108条)の未遂罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,「建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには,該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とする」とした上で,「畳のごときは未だ家屋と一体となってこれを構成する建造物の一部といえない」として,畳を焼損するにとどまった場合には,現住建造物等放火罪の未遂罪(刑法112条,108条)の成立を認めている(最判昭25.12.14)。したがって,甲が乙所有の住居内の畳を焼損したとしても,甲には,現住建造物等放火罪の既遂罪は成立せず,現住建造物等放火罪の未遂罪が成立するにとどまる。よって,本記述は正しい。参考西田(各)317~318頁。
基本刑法Ⅱ366頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法国民主権の原理には,国家権力の正当性原理(正当性の契機)としての側面と国家権力の組織化原理(権力的契機)としての側面があり,この二つの側面を総合的に捉える見解によれば,国民主権の主体も二つの側面に対応して異なることになる。憲法結果正解解説国民主権の原理について,国家権力を正当化し権威付ける根拠は究極的に国民にあるという,国家権力の正当性原理(正当性の契機)としての側面と,国民が自ら直接に国の政治の在り方を終局的に決定するという,国家権力の組織化原理(権力的契機)としての二つの側面があるとし,これを総合的に捉える見解がある。この見解によれば,二つの側面に対応して,主権主体も二重化される。すなわち,前者における国民主権の主体は「全国民」であり,後者における国民主権の主体は,「有権者の全体」である。したがって,本記述のように主権概念を捉える見解によれば,二つの側面に対応して,国民主権の主体も異なることになる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)40~43頁。
佐藤幸(日本国憲法論)391頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)90~94頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)78頁。 -
民法取得時効に関して,判例に照らすと,Aが,Bからその所有する甲土地を譲り受け,引渡しを受けて占有を開始した後,BがCにも甲土地を譲渡し,Cへの所有権移転登記をした場合において,Aは,その後も甲土地の占有を継続し,甲土地の占有を取得した時から民法所定の時効期間を経過したときは,甲土地の所有権を時効取得することができる。民法結果正解解説判例は,不動産が売主から第一の買主に譲渡され,その登記がされない間に,その不動産が売主から「第二の買主に二重に売却され,第二の買主に対し所有権移転登記がなされたときは,……登記の時に第二の買主において完全に所有権を取得するわけであるが,その所有権は,売主から第二の買主に直接移転するのであり,売主から一旦第一の買主に移転し,第一の買主から第二の買主に移転するものではなく,第一の買主は当初から全く所有権を取得しなかったことになる」とし,「したがって,第一の買主がその買受後不動産の占有を取得し,その時から民法162条に定める時効期間を経過したときは,同法条により当該不動産を時効によって取得しうる」としている(最判昭46.11.5 民法百選Ⅰ〔第8版〕57事件)。よって,本記述は正しい。参考佐久間(総則)402~403頁。
-
刑法文書偽造の罪に関して,判例の立場に従って検討すると,甲は,運転免許証を持っていなかったため,行使の目的で,A県公安委員会が発行した乙の運転免許証の写真を自己の写真に貼り替え,生年月日を自己のものに変更した。この場合,甲には,有印公文書偽造罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「特定人に交付された自動車運転免許証に貼付しある写真及びその人の生年月日の記載は,当該免許証の内容にして重要事項に属するのであるから,右写真をほしいままに剥ぎとり,その特定人と異なる他人の写真を貼り代え,生年月日欄の数字を改ざんし,全く別個の新たな免許証としたるときは,公文書偽造罪が成立する」としている(最決昭35.1.12)。したがって,甲には,有印公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)444頁。
基本刑法Ⅱ400頁。
条解刑法433頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法住民に思想,意見等の情報を提供する公的な場である公立図書館は,そこで閲覧に供された図書の著作者にとっては,その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができるから,公立図書館の職員が著作者の思想・信条を理由とする不公正な取扱いによって既に閲覧に供された図書を廃棄することは,当該図書の著作者の人格的利益を侵害する。憲法結果正解解説判例は,公立図書館の職員が勝手に図書を廃棄したことから,当該図書の著作者が国家賠償請求訴訟を提起した事例において,住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場である公立図書館は,「そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる」から,「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは,当該著作者が著作物によってその思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない。そして,著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると,公立図書館において,その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は,法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であ」るとしている(最判平17.7.14 憲法百選Ⅰ〔第6版〕74事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合,残余の留置物によって担保される被担保債権の範囲は,残余の留置物に対応する部分の被担保債権の限度である。民法結果正解解説留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,留置物の全部についてその権利を行使することができる(不可分性 民法296条)。そして,同条は,留置物が可分である場合や複数の物である場合にも適用されると解されている。判例も,土地の宅地造成工事を請け負った債権者が造成工事の完了した土地部分を順次債務者に引き渡した事例において,「留置権者が留置物の一部の占有を喪失した場合にもなお右規定(注:民法296条)の適用があるのであって,この場合,留置権者は,占有喪失部分につき留置権を失うのは格別として,その債権の全部の弁済を受けるまで留置物の残部につき留置権を行使し得る」としている(最判平3.7.16 平3重判民法1事件)。したがって,残余の留置物によって担保される留置権の被担保債権の範囲は,残余の留置物に対応する部分の債権に割合的に限定(減縮)されず,原則として債権の全部に及ぶ。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決は,債権者が引渡しに伴って被担保債権の一部につき留置権による担保を失うことを承認した等の特段の事情がある場合には,例外的に被担保債権の範囲が限定されることを認めている。参考道垣内Ⅲ42頁。
我妻・有泉コメ507頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,銀行の預金・為替業務に従事する甲は,同行の為替担当係員乙に対して,あらかじめ偽造しておいた自己の口座宛ての振込依頼書を真正に作成されたもののように装い,他の正規の振込依頼書とともに回付して行使し,乙にその旨誤信させて,乙をして同行の為替端末機を操作させて振込入金を行わせ,自己の口座の預金残高を増加させた。この場合,甲には,電子計算機使用詐欺罪が成立する。刑法結果正解解説電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は,詐欺利得罪の補充類型であるから,コンピュータによる処理の途中に人が介在し,その人に対する「欺」く行為(同246条2項,1項)及びその者の処分行為が認められる場合には,電子計算機使用詐欺罪ではなく,詐欺利得罪が成立する。本記述では,甲は,自己が偽造した振込依頼書を利用して,乙をして正規の振込依頼であると誤信させ,その手続を行わせたことから,乙に対する「欺」く行為及び乙の処分行為が認められる。したがって,甲には,詐欺利得罪が成立し,電子計算機使用詐欺罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)274頁。
基本刑法Ⅱ264頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法の規範内容が踏みにじられたり不当に変質させられたりしないようにする様々な国法上の工夫は,広く「憲法の保障」といわれるが,その代表的な方法や考え方に関して,抵抗権は,その固有の意味において,国民による組織的な暴力・実力行使を伴うものであるとすると,実力の行使を公の武力の形でしか許さない現代の立憲的な憲法秩序の下では,多分に理念的な権利に属し,むしろ政治宣言としての意味を強く持つといえる。憲法結果正解解説抵抗権といわれるものの中には,①暴力の行使を伴わない受動的抵抗権,②暴力の行使を伴う能動的抵抗権,③現存の法理念を覆す攻撃的抵抗権の三つがあるとされる。抵抗権は,固有の意味では,②の能動的抵抗権を意味するところ,この意味における抵抗権は,国民による組織的な暴力・実力行使を伴うものであるから,実力の行使を公の武力の形でしか許さない現代の立憲的な憲法秩序の下では,抵抗権の行使を正当な反政府活動の手段として一般的に承認することはできず,その行使は極めて厳格な要件の下でのみ認めることができるにとどまる。その意味において,抵抗権は,多分に理念的な権利に属し,むしろ政治宣言としての意味を強く持つものといえる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)387~388頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)402~403頁。
大石(憲法講義Ⅱ)12~13頁。 -
民法土地の売買契約が第三者の詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は,同時履行の関係にある。民法結果正解解説判例は,第三者による詐欺(民法96条2項)を理由に,売主が売買契約を取り消した場合において,当事者双方の原状回復義務(同121条,121条の2第1項)につき,「右各義務は,民法533条の類推適用により同時履行の関係にある」としている(最判昭47.9.7)。よって,本記述は正しい。参考中田(契約)155頁。
我妻・有泉コメ1076頁。 -
刑法公務員が,請託を受けて賄賂を収受し,他の公務員の職務について働き掛けを行った場合,その働き掛けは,他の公務員の裁量判断に不当な影響を及ぼす程度のものでは足りず,違法なものでなければ,あっせん収賄罪(刑法第197条の4)は成立しない。刑法結果正解解説あっせん収賄罪(刑法197条の4)は,「他の公務員に職務上不正な行為をさせるように,又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたこと」が必要である。そして,職務上不正な行為をする,又は相当の行為をしなかったというのは,積極的又は消極的行為によりその職務に違反する一切の行為を意味する(大判大6.10.23)。判例は,「公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が同法(注:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)違反の疑いをもって調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,同委員会の裁量判断に不当な影響を及ぼし,適正に行使されるべき同委員会の告発及び調査に関する権限の行使をゆがめようとするものである」から,同条にいう「相当の行為をさせないようにあっせんをすること」に当たるとしている(最決平15.1.14 刑法百選Ⅱ〔第7版〕110事件)。よって,本記述は誤りである。参考基本刑法Ⅱ473~474頁。
条解刑法562頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法学問の自由には,学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とが含まれているが,憲法第23条は専ら大学における学問の自由を保障しているのであって,広く全ての国民に対して学問の自由を保障しているわけではない。憲法結果正解解説判例は,大学の構内で行われた演劇発表会に警察官が立ち入った行為が憲法23条に反しないかどうかが争われた事例において,「同条の学問の自由は,学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって,同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは,一面において,広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに,他面において,大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて,特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである」としている(最大判昭38.5.22 ポポロ事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕91事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法連帯債務者の一人に対する履行の請求によって生じた時効の完成猶予や更新の効力は,他の連帯債務者に対しても及ぶ。民法結果正解解説弁済その他債権者に満足を与える事由,自己の反対債権をもってする相殺,更改,混同を除く連帯債務者の一人について生じた事由は,債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思表示をした場合以外は,他の連帯債務者に対してその効力を生じない(民法441条)。したがって,連帯債務者の一人に対する履行の請求は,当事者に別段の合意がある場合を除き,他の連帯債務者に対してはその効力を生じない。よって,本記述は誤りである。参考潮見(プラクティス債総)569頁。
-
刑法緊急避難の要件である「やむを得ずにした行為」とは,当該避難行為をする以外にはほかに方法がなく,かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合をいう。刑法結果正解解説判例は,「やむを得ずにした行為」(刑法37条1項本文)とは,「当該避難行為をする以外には他に方法がなく,かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する」としている(最大判昭24.5.18)。よって,本記述は正しい。参考基本刑法Ⅰ210~211頁。
条解刑法124頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,憲法第51条の免責特権が保障されているとしても,国会議員が議院で行った質疑等において,個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があった場合には,当然に国の損害賠償責任が発生することになる。憲法結果正解解説判例は,国会議員が国会の質疑,演説,討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言について国の損害賠償責任が争われた事例において,「質疑等においてどのような問題を取り上げ,どのような形でこれを行うかは,国会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられている事柄とみるべきであって,たとえ質疑等によって結果的に個別の国民の権利等が侵害されることになったとしても,直ちに当該国会議員がその職務上の法的義務に違背したとはいえないと解すべきである。憲法51条は,……国会議員の発言,表決につきその法的責任を免除しているが,このことも,一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けているということができる」とした上で,「国会議員が国会で行った質疑等において,個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても,これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではな」いとしている(最判平9.9.9 憲法百選Ⅱ〔第6版〕176事件)。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決は,国の損害賠償責任が肯定されるためには,国会議員が,その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的を持って事実を摘示し,あるいは,虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど,国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とするとし,国の損害賠償責任が認められる可能性をかなり限定している。 -
民法建築途中の建前に第三者が材料を提供して独立の不動産である建物に仕上げた場合,当該建物所有権の帰属は,民法上の加工の法理によって決せられる。民法結果正解解説判例は,建物の建築工事請負人が建築途上においていまだ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに,第三者がこれに材料を供して工事を施し,独立の不動産である建物に仕上げた場合における当該建物の所有権が何人に帰属するかは,主たる動産の所有者に合成物の所有権の帰属を認める動産の付合の規定(民法243条)によるのではなく,むしろ,加工者が材料の一部を供した場合における加工の規定(同246条2項)に基づいて決定すべきとしている(最判昭54.1.25 民法百選Ⅰ〔第8版〕72事件)。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)189~190頁。
平野(物権)304~306頁。 -
刑法甲は,乙が居住する家屋に隣接する乙所有の無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,予想に反して乙居住の家屋に延焼した。この場合,甲には,延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。刑法結果正解解説刑法111条1項の延焼罪は,自己所有非現住建造物等放火罪(同109条2項)又は自己所有建造物等以外放火罪(同110条2項)を犯したときにのみ成立する。本記述において,甲が放火したのは乙所有の無人の倉庫であり,他人所有の非現住建造物である。したがって,甲には,延焼罪は成立せず,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考基本刑法Ⅱ387~388頁。
条解刑法347頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法集会の用に供される公共施設において,当該公共施設の管理者が,主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に当該公共施設の利用を拒むことは,憲法第21条の趣旨に反する。憲法結果正解解説最判平7.3.7(泉佐野市民会館事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕86事件)は,「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは,憲法21条の趣旨に反するところである」としている。よって,本記述は正しい。
なお,これはいわゆる「敵意ある聴衆の法理」という考え方であり,この考え方は,平穏な集会を行おうとしている者に対して一方的に実力による妨害がされる場合にのみ妥当し,集会に対する妨害行為が,施設を利用する側の違法な行為に起因して引き起こされる場合には,反対派の妨害行為による混乱のおそれを理由として施設の利用を拒むことも許されてよいというのが同判決の立場であるとの説明がなされている。参考平8最高裁解説(民事上)210頁。 -
民法保証に関して,判例の趣旨に照らすと,主たる債務者の債権者に対する債務の承認による時効の更新の効力は,保証人に対しては生じない。民法結果正解解説主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は,保証人に対しても,その効力を生ずる(民法457条1項)。したがって,債務の承認による時効の更新(同152条1項)の効力は,保証人に対しても生じる。よって,本記述は誤りである。参考潮見(プラクティス債総)633頁。
我妻・有泉コメ870~871頁。 -
刑法甲は,丙とけんかになり,丙の胸倉をつかみ顔面を多数回殴打したところ,丙がその場に倒れ込んだので,そのまま立ち去った。その直後,もともと丙に恨みを抱いていた乙は,偶然丙が倒れているのを発見し,丙の頭部を複数回蹴った。丙は,脳出血により死亡したが,死亡の原因となった傷害が,甲乙いずれの暴行により生じたかは不明であった。この場合,甲乙それぞれには,傷害罪が成立するにとどまる。刑法結果正解解説判例は,同時傷害の特例(刑法207条)の適用には,「各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること」と,「各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと」が必要であるとしている(最決平28.3.24 平28重判刑法6事件)。本記述において,甲は丙の顔面を多数回殴打し,乙は丙の頭部を複数回蹴っており,いずれも傷害結果を生じさせ得る危険性を包含する行為である。また,甲の暴行の直後に,乙が暴行しており,時間的・場所的近接性が認められるので,外形的には共同実行に等しいといえる。そして,判例は,傷害致死罪(同205条)にも同207条の適用を肯定している(最判昭26.9.20)。したがって,甲,乙には傷害致死罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)51頁。
基本刑法Ⅱ35~36頁。
条解刑法595頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法改正についての国民の承認には,「その過半数の賛成」が必要であり,この「過半数」の意味については,有権者総数,投票総数,有効投票総数のいずれの過半数であるかが争われているが,日本国憲法の改正手続に関する法律は,投票総数説を採用している。憲法結果正解解説憲法改正が成立するためには,国民投票の「過半数の賛成」を得ることが必要である(憲法96条1項後段)。ここでの「過半数」の意味については,①有権者総数,②投票総数,③有効投票総数のいずれの過半数かで学説が分かれている。そして,日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)126条1項は,「国民投票において,憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えた場合は,当該憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとする。」とし,国民投票法98条2項は「投票総数」を「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」と定義していることから,③説を採用したことになる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)407~408頁。
佐藤幸(日本国憲法論)37頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)410頁。
新基本法コメ(憲法)503~504頁。 -
民法売買の目的物が他人の物であるため,直ちにその物の所有権を取得することができないことを知りながら買主がその物の占有を開始した場合,その占有は所有の意思をもってする占有とはいえないから,取得時効は成立しない。民法結果正解解説取得時効の成立には,所有の意思をもってする占有が,民法所定の期間継続することが必要である(民法162条)。判例は,「占有における所有の意思の有無は,占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものであり,土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には,右売買が他人の物の売買であるため売買によって直ちにその所有権を取得するものではないことを買主が知っている事実があっても,買主において所有者から土地の使用権の設定を受けるなど特段の事情のない限り,買主の占有は所有の意思をもってするものとすべきであって,右事実は,占有の始め悪意であることを意味するにすぎない」としている(最判昭56.1.27)。よって,本記述は誤りである。参考我妻・有泉コメ315頁。
-
刑法勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は,面会者から密かに差し入れられた甲の房の合い鍵を使用して房の扉を開け,同拘置所から逃走した。この場合,甲には,加重逃走罪(刑法第98条)が成立する余地はない。刑法結果正解解説甲は,勾留状によって拘置所に勾留されている者であるから,「裁判の執行により拘禁された……未決の者」(刑法97条)に当たり,加重逃走罪の主体となる。そして,拘禁場等の損壊を手段とする加重逃走罪が成立するためには,拘禁場若しくは拘束のための器具を「損壊」して逃走することを要するところ,同罪における「損壊」とは,物理的損壊に限られると解されている(広島高判昭31.12.25)。本記述における甲は,面会者から密かに差し入れられた合い鍵を用いて房の扉を開けて逃走したのであり,扉ないし錠を損壊して逃走したのではない。したがって,甲に加重逃走罪が成立する余地はない。よって,本記述は正しい。参考基本刑法Ⅱ542頁。
条解刑法305~306頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第93条第2項にいう「住民」とは,地方公共団体の区域内に住所を有する者を意味すると解すべきであるから,同項は,我が国に在留する外国人に対して,地方公共団体の長,その議会の議員等の選挙の権利を保障したものである。憲法結果正解解説判例は,外国籍を有する者らが,居住地の選挙人名簿に登録されていなかったため,選挙管理委員会に対し,選挙人名簿に登録するよう異議の申出をしたところ,これを却下する決定を受けたため,同決定の取消しを求めた事例において,「憲法93条2項にいう「住民」とは,地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり,右規定は,我が国に在留する外国人に対して,地方公共団体の長,その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」としている(最判平7.2.28 憲法百選Ⅰ〔第6版〕4事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法売主が,目的物の引渡しの提供をした上,民法第541条の規定に従い相当期間を定めて代金の支払を催告した場合において,催告期間の経過後,解除権行使前に,買主から債務の本旨に従った弁済の提供を受けたときは,特段の事情がない限り,売主は,これを拒絶して解除権を行使することはできない。民法結果正解解説判例は,民法541条に従って相当の期間を定めて債務の履行を催告した場合において,催告期間内に履行がないとしても,そのことは,解除権を発生させるにとどまり,その解除権の行使がない間は,契約は,なお依然として存続するのが原則であって,その期間内に履行がないことの一事をもって当然解除されるべき特別の事情がない限り,債権者はなお債務の履行を請求することができると同時に,債務者もまたその債務を履行することができるのであるから,原則として,催告期間経過後,解除権行使前における債務の履行は,債権者においてこれを拒むことができず,既にその履行があったときは,解除権を行使することはできないとしている(大判大6.7.10 売買(動産)百選89事件)。よって,本記述は正しい。参考中田(契約)244頁。
我妻・有泉コメ1108頁。 -
刑法甲は,乙が郵便局に提出するために作成した転居届を破り捨てた。この場合,甲には私用文書毀棄罪が成立する。刑法結果正解解説私用文書等毀棄罪(刑法259条)の客体は,「権利又は義務に関する他人の文書」等である。そして,権利又は義務に関する文書とは,権利・義務の存否・得喪・変更を証明するための文書をいい,私文書偽造等罪(同159条)と異なり,単なる「事実証明に関する文書」を含まない。郵便局への転居届は,居所移転という事実証明に関する文書である(大判明44.10.13)。したがって,本記述において,甲が破り捨てた転居届は,「権利又は義務に関する他人の文書」に当たらず,甲には私用文書毀棄罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)302頁,394頁。
高橋(各)446~447頁,537頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例は,衆議院の小選挙区選挙において,候補者以外に候補者届出政党にも独自の選挙運動が認められているのは,選挙制度を政策本位,政党本位のものにするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものであると解されるのであって,十分合理性を是認し得るとしている。憲法結果正解解説判例は,衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認める公職選挙法の規定の合憲性が争われた事例において,「憲法は,政党について規定するところがないが,その存在を当然に予定しているものであり,政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素であって,国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから,国会が,衆議院議員の選挙制度の仕組みを決定するに当たり,政党の右のような重要な国政上の役割にかんがみて,選挙制度を政策本位,政党本位のものとすることは,その裁量の範囲に属することが明らかであるといわなければならない。そして,選挙運動をいかなる者にいかなる態様で認めるかは,選挙制度の仕組みの一部を成すものとして,国会がその裁量により決定することができる」とした上で,公職選挙法の規定によれば,「小選挙区選挙においては,候補者のほかに候補者届出政党にも選挙運動を認めることとされているのであるが,政党その他の政治団体にも選挙運動を認めること自体は,選挙制度を政策本位,政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものであると解されるのであって,十分合理性を是認し得る」としている(最大判平11.11.10 憲法百選Ⅱ〔第6版〕157②事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法更改後の債務について不履行がある場合には,債権者は,更改契約を解除することができるが,更改前の債務は復活しない。民法結果正解解説判例は,更改もまた1つの契約であるから,契約の解除に関する一般規定に従って解除することができ,契約の解除は,当該契約に基づく法律関係を遡及的に消滅させて,同契約締結以前の状態に復帰させる効力を有するものであって,更改に限って別異の取扱いをする理由は特にないから,更改契約が適法に解除された契約当事者間にあっては,更改によって生じた債務が消滅すると同時に更改前の債務関係が当然に復活するとしている(大判昭3.3.10)。よって,本記述は誤りである。参考基本法コメ(債総)236頁。
-
刑法甲は,夜間,Vを自動車後部のトランク内に監禁し,見通しのよい道路上に同車を停車させていたところ,同車に後方から乙の運転する自動車が,乙の居眠り運転という重大な過失行為により追突したため,その衝撃によりVは死亡した。この場合,Vの直接の死亡原因が乙車による追突により生じているから,甲の監禁行為とVの死亡の結果との間には因果関係がない。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている(最決平18.3.27 刑法百選Ⅰ〔第7版〕11事件)。したがって,甲の監禁行為とVの死亡の結果との間には因果関係が認められる。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)66頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法農業災害補償法の定める水稲耕作者の農業共済組合への当然加入制は,米の生産の確保と自作農の経営の保護を目的とするものであるところ,職業の遂行それ自体を禁止するものではなく,職業活動に付随して,その規模等に応じて一定の負担を課するという規制の態様や,共済掛金の一部国庫負担や政府による再保険といった制度の内容などに照らせば,著しく不合理であることが明白であるとはいえない。憲法結果正解解説判例は,水稲等の耕作の業務を営む者について農業共済組合への当然加入制を定める農業災害補償法の規定が憲法22条1項に違反するかが争われた事例において,農業災害補償法が当然加入制を採用した趣旨は,「国民の主食である米の生産を確保するとともに,水稲等の耕作をする自作農の経営を保護することを目的と」するものであるとした上で,「当然加入制は,もとより職業の遂行それ自体を禁止するものではなく,職業活動に付随して,その規模等に応じて一定の負担を課するという態様の規制であること,組合員が支払うべき共済掛金については,国庫がその一部を負担し,災害が発生した場合に支払われる共済金との均衡を欠くことのないように設計されていること,甚大な災害が生じた場合でも政府による再保険等により共済金の支払が確保されていること」などに照らすと,当然加入制の採用は,「公共の福祉に合致する目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまる措置ということができ,立法府の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であることが明白であるとは認め難い」として,憲法22条1項に違反しないとしている(最判平17.4.26 平17重判憲法8事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)236頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)480頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅱ)289頁。 -
民法16歳のAが,法定代理人の同意を得ることなくBとの間で10万円を借り入れる契約を締結し,受領した10万円を生活費として全額費消した場合において,当該契約締結から1か月後,Aの法定代理人が,AB間の当該契約を取り消したときは,Aは,Bに対し,借りた10万円を返還しなくてもよい。民法結果正解解説取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされる(民法121条本文)。ただし,制限行為能力者である未成年者(同20条1項参照)は,その行為によって現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う(同121条ただし書)。そして,判例は,制限行為能力者が,取り消すことができる法律行為により相手方から受領した金員をもって,自己の他人に対する債務を弁済し又は必要な生活費として支出したときは,制限行為能力者はその法律行為により現に利益を受けているものということができるとし,当該法律行為を取り消した以上,同条によりその弁済又は支出した金員を相手方に償還する義務を負うとしている(大判昭7.10.26 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕39事件)。したがって,本記述において,Aは,受領した10万円を生活費として全額費消しているから,Bに対してこれを返還する義務を負う。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)103~104頁,227頁。
-
刑法甲は,自宅の近隣で起こった窃盗事件について,捜査機関の取調べを受けた際,乙に刑事処分を受けさせる目的で,乙がその犯人である旨の虚偽の回答をした。この場合,甲には虚偽告訴等罪は成立しない。刑法結果正解解説刑法172条にいう「申告」は,自発的に行う必要があり,捜査機関等の取調べを受けて虚偽の回答をすることはこれに当たらない。したがって,甲には虚偽告訴等罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考山口(各)601頁。
山中(各)822頁。
大コメ(刑法・第3版)(8)423頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法皇位の継承につき世襲制を採用すること及び皇位継承の資格につき男系男子主義を採用することについて,憲法は何ら規定しておらず,専ら皇室典範の定めるところに委ねている。憲法結果正解解説憲法2条は,「皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する。」とし,皇位の継承につき世襲制を採用している。よって,本記述は誤りである。
なお,皇位継承の資格者については,憲法は定めておらず,皇室典範が「皇統に属する男系の男子」(同1条)の「皇族」(同2条柱書)が皇位を継承する(男系男子主義)旨定めている。参考芦部(憲法)46頁。
佐藤幸(日本国憲法論)512~514頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)113頁。 -
民法Aが所有する甲土地上に,権原なく乙建物を建築して所有することにより甲土地を不法占拠するBが,乙建物につき自己名義で所有権保存登記をした上で,乙建物を第三者Cに譲渡して引き渡した場合でも,Bが引き続き乙建物の登記名義を保有するときには,Aは,Bに対して建物収去土地明渡請求をすることができる。民法結果正解解説判例は,「土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには,現実に建物を所有することによってその土地を占拠し,土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである」が,「他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には,たとい建物を他に譲渡したとしても,引き続き右登記名義を保有する限り,土地所有者に対し,右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないものと解するのが相当である」としている(最判平6.2.8 民法百選Ⅰ〔第8版〕51事件)。その理由として,同判決は,「建物は土地を離れては存立し得ず,建物の所有は必然的に土地の占有を伴うものであるから,土地所有者としては,地上建物の所有権の帰属につき重大な利害関係を有するのであって,土地所有者が建物譲渡人に対して所有権に基づき建物収去・土地明渡しを請求する場合の両者の関係は,土地所有者が地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で,あたかも建物についての物権変動における対抗関係にも似た関係というべく,建物所有者は,自らの意思に基づいて自己所有の登記を経由し,これを保有する以上,右土地所有者との関係においては,建物所有権の喪失を主張できないというべきであるからである。もし,これを,登記に関わりなく建物の「実質的所有者」をもって建物収去・土地明渡しの義務者を決すべきものとするならば,土地所有者は,その探求の困難を強いられることになり,また,相手方において,たやすく建物の所有権の移転を主張して明渡しの義務を免れることが可能になるという不合理を生ずるおそれがある。他方,建物所有者が真実その所有権を他に譲渡したのであれば,その旨の登記を行うことは通常はさほど困難なこととはいえず,不動産取引に関する社会の慣行にも合致するから,登記を自己名義にしておきながら自らの所有権の喪失を主張し,その建物の収去義務を否定することは,信義にもとり,公平の見地に照らして許されない」ことを挙げている。したがって,本記述において,甲土地所有者Aは,自らの意思で乙建物の所有権保存登記を経由し,引き続き登記名義を保有するBに対し,建物収去土地明渡請求をすることができる。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)301~304頁。
川井(2)34~35頁。 -
刑法甲は,乙がV女に暴行を加え,強いて性交している際に,乙に気付かれることなく,共同加功の意思を持ってV女の足を押さえ付け,V女の反抗を著しく困難にした。この場合,甲には強制性交罪の共同正犯は成立しない。刑法結果正解解説判例は,相互に共同犯行の認識がなければ共同正犯は成立しないとして,いわゆる片面的共同正犯を否定している(大判大11.2.25)。本記述においては,甲乙間に意思の連絡が認められないため,甲には強制性交罪の共同正犯(刑法177条,60条)は成立しない。よって,本記述は正しい。参考条解刑法222頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法選挙に関して,判例は,衆議院議員選挙において採用されている拘束名簿式比例代表制は,選挙で決定された当選人数の中で各政党の比例名簿登載者の上位から順に当選人が決定されることになるから,直接選挙には当たらないが,憲法は,国会議員について直接選挙を明文で規定しておらず,当該方式を採用したことは国会の裁量の限界を超えるということはできないとしている。憲法結果正解解説判例は,公職選挙法が衆議院議員選挙において採用している拘束名簿式比例代表制が,選挙権を侵害し,直接選挙の原則に反するかどうかなどが争われた事例において,「政党等にあらかじめ候補者の氏名及び当選人となるべき順位を定めた名簿を届け出させた上,選挙人が政党等を選択して投票し,各政党等の得票数の多寡に応じて当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は,投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において,選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない。複数の重複立候補者の比例代表選挙における当選人となるべき順位が名簿において同一のものとされた場合には,その者の間では当選人となるべき順位が小選挙区選挙の結果を待たないと確定しないことになるが,結局のところ当選人となるべき順位は投票の結果によって決定されるのであるから,このことをもって比例代表選挙が直接選挙に当たらないということはできず,憲法43条1項,15条1項,3項に違反するとはいえない」としている(最大判平11.11.10 憲法百選Ⅱ〔第6版〕157①事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法占有保持の訴えは,妨害が発生した時から1年以内に提起しなければならない。民法結果正解解説占有保持の訴えは,妨害の存する間又はその消滅後1年以内に提起しなければならない(民法201条1項本文)。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)292頁。
川井(2)129~130頁。
基本法コメ(物権)79頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,目的物を盗品かもしれないと認識していたが,それでも構わないと思って有償で譲り受けた場合でも,盗品等有償譲受け罪の故意は認められる。刑法結果正解解説未必の故意とは,行為者が犯罪事実の実現を可能なものと認識し,これを認容している場合をいうところ,判例は,盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)は,盗品であることを知りながらこれを買い受けることによって成立するものであるが,その故意が成立するためには,買い受けようとするものが盗品であるとの確定的認識までは必要とされず,盗品であるかもしれないと思いながら,あえてこれを買い受ける意思があれば足りるとしている(最判昭23.3.16 刑法百選Ⅰ〔第7版〕41事件)。したがって,本記述の場合,盗品等有償譲受け罪の故意が認められる。よって,本記述は正しい。参考刑法総論講義案111~112頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第9条の解釈に関して,第1項で,放棄されている戦争とは侵略戦争であって,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項前段の「前項の目的を達するため」を,侵略戦争放棄という第1項の目的を達するためとする見解によると,自衛目的のための戦力は保持できることになるが,この見解に対しては,自衛のための戦力と侵略のための戦力は実際上区別できないとの批判が当てはまる。憲法結果正解解説憲法9条1項で,放棄されている戦争とは侵略戦争であって,自衛戦争は放棄されていないとし,同条2項前段の「前項の目的を達するため」の意味を,侵略戦争放棄という同条1項の目的を達するためとする立場に立つと,同条2項は,侵略のための戦力は保持せず(つまり,自衛のための戦力は保持できる。),また交戦権の否認は交戦国が持つ諸権利は認めないとの意味にとどまることになる。この見解に対しては,憲法自体に内閣構成員の資格としての文民規定(同66条2項)以外に戦争・軍隊を前提とする他の規定がないこと,自衛のための戦力と侵略のための戦力を実際上区別できないことなどの批判がある。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)56~58頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)164~167頁。
渋谷(憲法)72~73頁。 -
民法Aが所有する甲不動産をBが時効によって取得した場合,Bは,Aに対し,登記なくして甲不動産の所有権を時効取得したことを主張することができる。民法結果正解解説判例は,以下のように述べて,不動産の所有者であった者を「第三者」(民法177条)に当たらないとしている(大判大7.3.2)。すなわち,不動産物権の得喪及び変更の登記は,当事者以外の第三者に対抗する方法にすぎず,当事者並びにその一般承継人との間においては登記なくしてその効力を生ずることは,同176条及び同177条の規定に照らし明らかである。時効による不動産所有権の取得は原始取得であるため,時効によって不動産所有権を取得する者は当事者ではない。しかし,取得時効完成の時期においては,占有者が所有権を取得する結果,目的不動産の所有者たる者の所有権は消滅するため,時効完成当時の所有者は,その取得者に対する関係においては,あたかも伝来取得における当事者たる地位にあるものとみなすべきである。したがって,時効による不動産の所有権の取得につき,これを第三者に対抗するためには登記が必要であるが,時効完成の時期における所有者であった者に対しては,完全に所有権を取得するものであって,登記を必要としないとしている。したがって,本記述において,甲不動産を時効取得したBは,時効完成当時における所有者であったAに対しては,登記なくして甲不動産の所有権を時効取得したことを主張することができる。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅰ452頁。
佐久間(物権)108~109頁。
我妻・有泉コメ366頁。 -
刑法甲は,代金を支払う意思がないのに,覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を譲り受け,代金の支払請求を免れるために,同人を殺害した。甲には強盗殺人罪は成立しない。刑法結果正解解説強盗殺人罪(刑法240条後段)の主体である「強盗」とは,強盗罪の実行に着手した者をいうところ,強盗利得罪(同236条2項)は,暴行又は脅迫を用いて,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合に成立する。同罪の客体には,覚せい剤の代金請求権のような民事上不法な利益も含まれると解されている。また,判例は,覚せい剤の返還ないし代金の支払請求を免れるために覚せい剤の売主を殺害しようとしてこれを遂げなかった事例において,強盗殺人未遂罪(同243条,240条後段)の包括一罪を構成するとしている(最決昭61.11.18 刑法百選Ⅱ〔第7版〕39事件)。したがって,甲には強盗殺人罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山中(各)310頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法司法に関して,判例は,憲法は,一般的には国民の司法参加を許容しており,これを採用する場合には,適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,陪審制とするか参審制とするかを含め,その内容を立法政策に委ねているとする。憲法結果正解解説判例は,国民の司法参加を前提とする裁判員裁判の合憲性について,「憲法に国民の司法参加を認める旨の規定が置かれていないことは,所論が指摘するとおりである。しかしながら,明文の規定が置かれていないことが,直ちに国民の司法参加の禁止を意味するものではない。憲法上,刑事裁判に国民の司法参加が許容されているか否かという刑事司法の基本に関わる問題は,憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則,憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討して判断されるべき事柄である」とした上で,「国民の司法参加と適正な刑事裁判を実現するための諸原則とは,十分調和させることが可能であり,憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はなく,国民の司法参加に係る制度の合憲性は,具体的に設けられた制度が,適正な刑事裁判を実現するための諸原則に抵触するか否かによって決せられるべきものである。換言すれば,憲法は,一般的には国民の司法参加を許容しており,これを採用する場合には,上記の諸原則が確保されている限り,陪審制とするか参審制とするかを含め,その内容を立法政策に委ねていると解されるのである」としている(最大判平23.11.16 憲法百選Ⅱ〔第6版〕181事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法債務者が口頭の提供をしても債権者において弁済を受領しない意思が明確であると認められる場合であっても,債務者は,口頭の提供をしなければ,債務不履行の責任を免れない。民法結果正解解説判例は,「債務者が言語上の提供をしても,債権者が契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められる場合においては,債務者が形式的に弁済の準備をし且つその旨を通知することを必要とするがごときは全く無意義であって,法はかかる無意義を要求しているものと解することはできない。それ故,かかる場合には,債務者は言語上の提供をしないからといって,債務不履行の責に任ずるものということはできない」としている(最大判昭32.6.5 続百選〔第2版〕民法24事件)。よって,本記述は誤りである。参考中田(債総)315頁。
潮見(プラクティス債総)286頁。
川井(3)312頁。 -
刑法甲は,Vを殺害する旨を告知してVを脅迫した。この場合,Vが気丈な性格であったため現実には畏怖しなかったときであっても,甲には脅迫罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,脅迫罪(刑法222条1項)は,同項列挙の法益に対して危害を加える旨の告知をすることによって成立し,必ずしも告知された者が畏怖したことを必要としないとしている(大判明43.11.15)。したがって,Vが現実に畏怖しなくても,甲には脅迫罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)73頁。
条解刑法646頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法生存権を具体化する立法が存在しない場合には不作為の違憲確認訴訟を提起することができるとする具体的権利説は,憲法第25条第1項の権利内容は行政権を拘束するほどには明確ではないが,立法府を拘束するほどには明確であることを根拠とする。憲法結果正解解説生存権の法的性格における具体的権利説とは,憲法25条1項の権利内容は,行政権を拘束するほどには明確ではないが,立法府を拘束するほどには明確であり,その意味で具体的な権利を定めたものであり,国が同項を具体化する立法をしない場合には,立法不作為の違憲確認訴訟を提起することができるとする見解である。よって,本記述は正しい。
なお,この見解は同項を直接の根拠にして具体的な給付を裁判所に請求することまでを認めるものではないが,近時,言葉どおりの意味における具体的権利として,一定の場合に同項に基づいて具体的な給付を裁判所に請求することを認める見解も唱えられている。参考芦部(憲法)269~270頁。
佐藤幸(日本国憲法論)363~366頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)502~504頁。
安西ほか(憲法学読本)229~230頁。 -
民法条件及び期限に関して,判例の趣旨に照らすと,不能の条件を付した法律行為は,無効である。民法結果正解解説不能の停止条件を付した法律行為は,無効となる(民法133条1項)。不能条件とは,将来において実現することが社会通念上不可能である条件をいう。そして,停止条件付法律行為は,停止条件が成就した時からその効力を生じるところ(同127条1項),不能の停止条件が付されている法律行為は,条件が成就する可能性が否定されており,もはや効力が発生する余地がないため,法律上の行為として維持する必要性はないことから,同133条1項は当然のことを定めた規定である。これに対して,不能の解除条件を付した法律行為は,無条件となる(同条2項)。解除条件付法律行為は,解除条件が成就した時からその効力を失うところ(同127条2項),不能の解除条件が付されている法律行為は,条件の成就によって効力が否定されることはないから,無条件の場合と等しくなるのである。したがって,不能の条件を付した法律行為が全て無効となるわけではない。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)318頁。
基本法コメ(民法総則)203~204頁。
注解財産法(総則)640~641頁。 -
刑法刑務所の看守者である公務員甲は,18歳の被拘禁者乙女の承諾を得て,勤務時間中に同女にわいせつな行為をした。この場合,甲には特別公務員暴行陵虐罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条2項)の保護法益は,公務員の職務違反行為を処罰することであるとした上で,被害者の同意がある場合であっても,わいせつ行為や強制性交等が「陵辱若しくは加虐の行為」に該当するとしている(大判大15.2.25)。したがって,承諾の有無は本罪の成立に影響しないため,違法性は阻却されず,甲には特別公務員暴行陵虐罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考条解刑法551頁。
裁判例コンメンタール刑法第2巻366頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法インターネットの個人利用者による表現行為は,他の表現手段を利用した場合とは異なり,利用者は相互に情報の発受信に関して対等の地位に立ち,言論を応酬し合えるという従来の情報媒体とは著しく異なった特徴を有しているから,当該表現行為の被害者に対して応酬することを要求しても不当とはいえない特段の事情がある場合には,他の表現手段を利用した場合に比べて,より緩やかな要件で名誉毀損罪の成立を否定すべきである。憲法結果正解解説判例は,個人が,インターネット上に自らが開設したホームページにおいて,ある株式会社の名誉を毀損したとして起訴された事例において,「インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」としている(最決平22.3.15 平22重判憲法8事件)。その理由として,同決定は,「インターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもない」ことを挙げている。したがって,同決定は,名誉毀損罪の成否について,インターネット上での表現行為であっても,他の表現手段と同様の厳格度により判断すべきであるとしており,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきであるとはしていない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)188~189頁。
-
民法建物賃借人は,賃貸人に代位して,建物の不法占拠者に対し,直接自己に対してその明渡しをなすべきことを請求することができる。民法結果正解解説判例は,建物の賃借人が,不動産賃借権を被保全債権として,賃貸人たる建物所有者に代位して,不法占拠者に対し建物の明渡しを請求することを認めた上で,この場合においては,建物の賃借人が,「直接自己に対してその明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのを相当とする」としている(最判昭29.9.24)。直接建物賃借人の下への明渡しを認める理由として,学説は,建物賃借人が受領できないとすれば,建物賃貸人が受領しない場合に債権者代位権の目的を達成することができないということを挙げている。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)215頁。川井(3)135頁。
我妻・有泉コメ793頁。 -
刑法甲は,自動車保険を掛けた自己所有の自動車を海中に投棄した。この場合,甲には器物損壊罪が成立する。刑法結果正解解説器物損壊等罪(刑法261条)の客体は,「他人の物」であるから,自己の所有物は同罪の客体にはならない。また,自己の所有物に保険が掛けられていた場合に,その物を損壊したときは,他人の物を損壊したとする旨の規定もない(同262条参照)。したがって,甲には器物損壊罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。
なお,自己所有の非現住建造物に保険が掛けられていた場合に,これを焼損したときは,他人所有の非現住建造物等放火罪が成立する(同115条,109条1項)。参考山口(各)356頁,359~360頁。
条解刑法326~327頁,789頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法は,政教分離規定を設けるに当たり,国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの,と解すべきである。憲法結果正解解説判例は,市の主催する体育館の起工式が,神社の神職主宰の下,神式にのっとって挙行され,その費用が公金から支出されたことが,憲法20条3項,89条に違反するか否かが争われた事例において,「憲法は,政教分離規定を設けるにあたり,国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの,と解すべきである」としている(最大判昭52.7.13 津地鎮祭事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕46事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法成年被後見人が不動産の贈与を受けた場合,成年被後見人は,当該贈与契約を取り消すことができない。民法結果正解解説成年被後見人がした法律行為は,日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き,成年被後見人において取り消すことができる(民法9条,120条1項)。そして,不動産の贈与を受けることは,日常生活に関する行為とはいえないから,成年被後見人は,自らがした贈与契約を取り消すことができる。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)92~93頁。
我妻・有泉コメ58頁,253頁。 -
刑法甲は,偽造通貨をスーツケースの中に隠した上,中に入っているのは書類であると偽って,同スーツケースを自宅に配送するよう宅配業者乙に依頼して,同人にこれを引き渡した。この場合,甲には偽造通貨行使罪が成立する。刑法結果正解解説偽造通貨行使罪(刑法148条2項)にいう「行使」とは,偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことをいう(大判明37.5.13)。甲は,乙に対して自宅への配送の目的で偽貨を託しているにすぎず,これを流通に置いたとはいえない。したがって,甲には偽造通貨行使罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)352頁。
条解刑法414頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法思想・良心の自由に関して,判例は,公立高等学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有し,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものであるから,同校の校長が教諭に当該行為を命じても,当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではないとしている。憲法結果正解解説判例は,公立高等学校の教諭が,卒業式の際に,国歌斉唱時の起立斉唱行為を命ずる職務命令に従わなかったとして戒告処分を受けたことから,当該職務命令が憲法19条に反するとして争った事例において,「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである」とした上で,「起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人(注:原告)の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。……本件職務命令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。そうすると,本件職務命令は,これらの観点において,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできない」とし,「もっとも,上記の起立斉唱行為は,教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」としている(最判平23.5.30 憲法百選Ⅰ〔第6版〕40事件)。したがって,同判決は,学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求める職務命令は,対象者の思想・良心の自由に対する制約となり得るとしている。よって,本記述は誤りである。
-
民法借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が,建物の引渡しを受けてこれを使用している場合であっても,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるときは,建物の敷地について民法第612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたということはできないから,土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約を解除することはできない。民法結果正解解説判例は,借地上の建物が譲渡担保の目的とされた場合,その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り,当該建物の敷地の賃借権にも譲渡担保の効力が及ぶとしている(最判昭51.9.21)。そうすると,借地上の建物が譲渡担保の目的とされた場合,少なくとも形式上は,当該建物の所有権が譲渡担保権者に移転するので,敷地賃借権の無断譲渡に当たり,民法612条の土地賃貸借契約の解除事由となるのではないかが問題となる。この点について,判例は,「借地人が借地上に所有する建物につき譲渡担保権を設定した場合には,建物所有権の移転は債権担保の趣旨でされたものであって,譲渡担保権者によって担保権が実行されるまでの間は,譲渡担保権設定者は受戻権を行使して建物所有権を回復することができるのであり,譲渡担保権設定者が引き続き建物を使用している限り,右建物の敷地について民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたと解することはできない」とした上で,「しかし,地上建物につき譲渡担保権が設定された場合であっても,譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときは,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても,建物の敷地について民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当であり,他に賃貸人に対する信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情のない限り,賃貸人は同条2項により土地賃貸借契約を解除することができる」としている(最判平9.7.17 平9重判民法9事件)。その理由として,同判決は,「譲渡担保権者が建物の使用収益をする場合には,敷地の使用主体が替わることによって,その使用方法,占有状態に変更を来し,当事者間の信頼関係が破壊されるものといわざるを得ない」ことなどを挙げている。したがって,借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が,建物の引渡しを受けてこれを使用している場合であっても,建物の敷地について同612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたということはできないとする本記述は誤っている。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ313~314頁。
-
刑法甲は,乙に刑事処分を受けさせる目的で,乙が丙から現金を窃取した旨を捜査機関に告発した。この告発が,乙を陥れるために,甲の記憶に反してなされたものである場合には,たとえ客観的事実に合致していたとしても,甲には虚偽告訴等罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,虚偽告訴等罪(刑法172条)にいう虚偽の申告とは,「申告の内容をなすところの刑事,懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいう」としている(最決昭33.7.31参照)。したがって,本記述の告発は,客観的事実に反していないので,甲には虚偽告訴等罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)601~602頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第9条の解釈に関して,第1項で,放棄されている戦争とは侵略戦争であって,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解は,従来の国際法上の通常の用例によると,「国際紛争を解決する手段として」の戦争は,国家の政策の手段としての戦争と同義であり,こうした用例を尊重すべきであるということを根拠とする。憲法結果正解解説憲法9条の戦争放棄には,同条1項で「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付いている。従来の国際法上の用例に従えば,「国際紛争を解決する手段として」の戦争とは,国家の政策の手段としての戦争,すなわち侵略戦争である。本記述の見解は,これを尊重して,同項で,放棄されているのは侵略戦争であって,自衛戦争は放棄されていないとする。したがって,本記述の見解は,「国際紛争を解決する手段として」の戦争の意味については,従来の国際法上の用例を尊重すべきであるということを根拠の一つとしている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)56~57頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)164~166頁。 -
民法物権と債権の対比に関して,債権の時効取得が認められることはないが,物権の時効取得は認められる。民法結果正解解説時効により取得することができる権利は,所有権(民法162条)及び所有権以外の財産権(同163条)である。同条の「財産権」には不動産賃借権などの継続的給付を目的とする債権も含まれると解されており,判例も,不動産賃借権の時効取得を認めている(最判昭43.10.8 昭43重判民法2事件)。したがって,物権も債権も時効により取得することが認められる。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)397~398頁。
我妻・有泉コメ314頁,319頁。 -
刑法自らの過失によって危難を招いた場合であっても,緊急避難の要件である「現在の危難」に当たり,緊急避難が成立する余地がある。刑法結果正解解説判例は,いわゆる自招危難のうち,社会通念に照らしやむを得ないものとしてその避難行為を是認することができる場合に,緊急避難(刑法37条1項本文)の成立する余地を認めている(大判大13.12.12 刑法百選Ⅰ〔第7版〕32事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)159~160頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法各国の憲法の中には,憲法保障を直接の目的とする特別の規定を設ける例もある。日本国憲法が,明文規定を設けて,国民各自に対して憲法を尊重し擁護する義務を負わせているのは,その一つの例ということができる。憲法結果正解解説各国の憲法の中には,自らの保障を直接の目的とする特別の規定を置く例がある。日本国憲法の憲法尊重擁護義務(同99条)がその一例である。しかし,同条は,擁護義務者として国民を挙げていない。このように,同条から国民が除かれているのは,仮に国民が擁護義務者に含まれていると,それを根拠に権力の側から国民に対して憲法忠誠を要求することが許容され得ることになるため,それを防ぐ点にあると考えられる。よって,本記述は誤りである。参考野中ほか(憲法Ⅱ)400頁。
-
民法免除の意思表示には,条件を付すことができる。民法結果正解解説債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する(民法519条)。そして,免除には条件を付けることができると解されている。これは,債務者を特に不利益にすることがないからである。よって,本記述は正しい。
なお,免除に条件を付す一例としては,100万円の貸金返還請求訴訟における和解条項において,被告が原告に対して一定の期日までに80万円を支払った場合には,残額を免除する旨の条項を入れることが挙げられる。参考中田(債総)421頁。
潮見(新債権総論Ⅱ)340頁。 -
刑法信頼の原則は,他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当といえる場合に適用されるが,行為者自身に規範違反的行為がある場合においても,同原則は適用され得る。刑法結果正解解説信頼の原則とは,他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場合は,たとえ他人の不適切な行動と自己の行動が相まって法益侵害の結果を発生させたとしても,過失責任は問われないという法理をいう。そして,判例は,右折しようとした第1種原動機付自転車の運転手Aが,後方から高速度で進行してきたB運転の第2種原動機付自転車に自車を衝突させ,Bを死亡させた事例において,Aは,Bが交通法規を守り,速度を落として自車の右折を待って進行する等,安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足りるとして,信頼の原則を適用し,Aが右折時に当時の道路交通法34条3項に違反したことは,注意義務の存否に影響しないとしている(最判昭42.10.13 刑法百選Ⅰ〔第7版〕54事件)。よって,本記述は正しい。参考西田(総)272~273頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法裁判官が心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には,公の弾劾によらなくとも罷免されるが,その決定は裁判所の裁判によるものとされる。憲法結果正解解説憲法は,裁判官の罷免について,最高裁判所裁判官が国民審査によって罷免される可能性がある(同79条2項,3項)以外には,心身の故障のために職務を執ることができない場合と公の弾劾による場合という2つの場合に限定している(同78条前段)。このうち,前者については,心身の故障のために職務を執ることができなくなったとの口実のもとに,外部からの政治的圧力などによって恣意的に裁判官の罷免が決定されることを防ぐため,その決定は裁判所の裁判により行われる。そして,この手続については,裁判官分限法に定められている。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)617頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)245頁。
基本法コメ(憲法)360~361頁。 -
民法条件が成就することによって利益を受ける当事者が故意にその条件を成就させたときは,相手方は,その条件が成就しなかったものとみなすことができる。民法結果正解解説条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,相手方は,その条件が成就したものとみなすことができるが(民法130条),条件が成就することによって利益を受ける当事者が故意にその条件を成就させたときの規定はない。この点について,判例は,条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させた場合は,同条の類推適用により,相手方は条件が成就していないものとみなすことができるとしている(最判平6.5.31 民法百選Ⅰ〔第8版〕40事件)。よって,本記述は正しい。参考佐久間(総則)324頁。
-
刑法甲は,行使の目的で,印刷機器を用いて5千円札を偽造しようとしたが,印刷機器の操作を誤ったため,完成したものは,一般人が一見して真正な5千円札と誤認するには至らない程度のものであった。甲には通貨偽造罪の実行の着手が認められる。刑法結果正解解説通貨偽造罪(刑法148条1項)は,行使の目的で,日本国内で通用する貨幣等を「偽造」することによって成立するところ,「偽造」とは,権限のない者が通貨に似た外観のものを製作することをいい,製作された物が一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っていることが必要となる(大判昭2.1.28,最判昭25.2.28)。通貨を偽造する意思で偽造を開始したが,結果として,一般人をして真正な通貨と誤認させる程度にまで至らなければ,通貨偽造罪ではなく,通貨偽造未遂罪(同151条,148条1項)が成立する。本記述では,甲は,行使の目的で,印刷機器を用いて日本国内で通用する5千円札を偽造しようとしている。したがって,甲には通貨偽造罪の実行の着手が認められる。よって,本記述は正しい。参考山口(各)422~423頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法付随的違憲審査制の下では,裁判所は特定の事件の裁判の主文の判断に必要な限度でのみ違憲審査権を行使できるにすぎないから,刑事事件について,起訴の根拠となった法律の合憲性を被告人の行為の構成要件該当性より先に審査してはならない。憲法結果正解解説付随的違憲審査制とは,通常の裁判所が,具体的な訴訟事件を裁判する際に事件の解決に必要な限度で適用法条の違憲審査を行う方式である。そこで,訴訟において違憲の争点が適法に提起されている場合でも,付随的違憲審査制における事件性の要請から,適用法条の構成要件該当性の判断が先行すべきであるとの考え方もある(札幌地判昭42.3.29 憲法百選Ⅱ〔第6版〕170事件参照)。しかし,付随的違憲審査制においては,訴訟が適法に成立していることの確認が本案の争点の判断に先行するのが基本原則であり,そのために,法令が事件に適用される可能性の存在の確認は必要であるが,それ以上に,法律の合憲性を先に審査すべきであるとか,構成要件該当性の判断が先行しなければならないとかという結論にはならないといえる。すなわち,起訴の根拠となった法律の合憲性と被告人の行為の構成要件該当性のどちらを先に審査すべきかについては,付随的違憲審査制それ自体からは直ちに出てこない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)381~382頁。
佐藤幸(日本国憲法論)649~650頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)310~311頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)341~343頁。
高橋(憲法訴訟)194~195頁。
憲法百選Ⅱ〔第6版〕365頁。 -
民法雇用関係の先取特権は,最後の6か月間の給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。民法結果正解解説雇用関係の先取特権は,給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法306条2号,308条)。日用品の供給の先取特権と異なり(同306条4号,310条参照),雇用関係の先取特権においては,最後の6か月間の給料等に制限されていない。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ51~52頁,55頁。
-
刑法甲は,当初から代金支払の意思がなく所持金もないのに,旅館に宿泊し飲食した後,同旅館の従業員乙に対し,「自動車で帰宅する友人を駅まで送ってくる。」とうそを言い,乙からは「いってらっしゃいませ。」と言われ,宿泊等の代金を支払わずそのまま戻らなかった。甲には詐欺罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,無銭宿泊の事例において,最初から代金を支払うつもりがないのに,宿泊,飲食等した場合,その時点で1項詐欺罪(刑法246条1項)が既遂に達するものとしている(最決昭30.7.7 刑法百選Ⅱ〔第7版〕52事件)。よって,本記述は正しい。
なお,債務の支払を免れたことが2項詐欺罪(同条2項)に当たるためには,債権者を欺罔して債務免除の意思表示をさせることが必要であるところ,本記述において,従業員乙は,甲の宿泊代金債務を免除する意思表示はしておらず,甲に2項詐欺罪は成立しない。参考山口(各)254頁,258頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め,その執行を監督し,更にその人事に関与するなど,その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することを要すると解する見解は,憲法第89条後段の趣旨を私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとするところに求める立場と結び付く。憲法結果正解解説憲法89条後段の趣旨については,必ずしも明確ではなく,学説上も分かれている。本記述の見解は,同条後段の趣旨について,私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとするところに求める立場(自主性確保説)である。この見解は,同条後段の「公の支配」の意義について,国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め,その執行を監督し,更にその人事に関与するなど,その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することを要すると解する見解(厳格説)に立つとされる。これにより,国が財政的援助をする以上は事業の自主性を認めず,事業の自主性を認める以上は援助しないと憲法が割り切っていると解することになる。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)365~366頁。
佐藤幸(日本国憲法論)527~529頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)343~346頁。 -
民法契約上の債務の不履行があった場合に,債権者がその債務に関して強制執行をしない旨の当事者間の合意は,有効である。民法結果正解解説判例は,当事者間の強制執行をしないとの合意(不執行の合意)は,「債権の効力のうち請求権の内容を強制執行手続で実現できる効力(いわゆる強制執行力)を排除又は制限する法律行為と解されるので,これが存在すれば,その債権を請求債権とする強制執行は実体法上不当なものとなる」として,不執行の合意を適法な法律行為として認めている(最決平18.9.11 執行・保全百選〔第2版〕1事件)。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)67頁。
潮見(新債権総論Ⅰ)359頁。 -
刑法甲は,乙から金を借りる条件として児童ポルノを撮影したデータを送信するよう要求されたので,性的意図はなく単に金を得る目的で,7歳のV女に対して,同女の陰部を触るなどのわいせつな行為を行い,その際の同女の姿態を撮影した。甲には強制わいせつ罪は成立しない。刑法結果正解解説強制わいせつ罪(刑法176条)は,13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合,又は13歳未満の者にわいせつな行為をした場合に成立する。本罪については,故意のほかに,主観的違法要素として性的意図を要件とするかという問題があり,判例はかつては性的意図必要説に立っていた(最判昭45.1.29 刑法百選Ⅱ〔第7版〕14事件)。しかし,近時,判例変更が行われ,判例は本記述と同様の事例において,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきであり,故意に加えて性的意図があることを一律に同罪の成立要件とすることは相当でないとする判断を示した(最大判平29.11.29 平29重判刑法3事件)。すなわち,同判決は,「刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。したがって,そのような個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。しかし,そのような場合があるとしても,故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でな」いとした上で,本記述の事例においては,「行為そのものが持つ性的性質が明確な行為であるから,その他の事情を考慮するまでもなく,性的な意味の強い行為として,客観的にわいせつな行為であることが明らかであ」るとしている。したがって,本記述において,甲の行為は,客観的にわいせつな行為である以上,性的意図はなくとも,強制わいせつ罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)100~101頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法の人権保障規定は,専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間を直接規律することを予定するものではないから,私人間相互の私的支配関係において,個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害又はそのおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容し得る限度を超える場合,私的自治に対する一般的制限規定である私法の一般条項の適切な運用によって解決を図るほかない。憲法結果正解解説判例は,民間企業が入社試験の際に身上書及び面接において学生運動等の活動を秘匿する虚偽の申告をした者に対し本採用を拒否した行為の有効性が争いになった事例において,国又は公共団体を当事者としない私人間の法律関係において憲法の人権保障が及ぶかにつき,「私人間の関係においても,相互の社会的力関係の相違から,一方が他方に優越し,事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり,このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは,劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが,そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた,採用することはできない」とした上で,「私的支配関係においては,個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは,これに対する立法措置によってその是正を図ることが可能であるし,また,場合によっては,私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって,一面で私的自治の原則を尊重しながら,他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し,その間の適切な調整を図る方途も存するのである」としている(最大判昭48.12.12 三菱樹脂事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕10事件)。つまり,同判決は,私的支配関係における法的紛争の解決方法として,まずは,立法措置による是正を図ることが可能であることを示し,場合によっては,私法の一般条項を適切に運用することによって適切な調整を図ることも可能であることを示している。よって,本記述は誤りである。
-
民法共同相続人間で遺産分割協議が成立した場合に,共同相続人全員の合意によって,当該協議を解除することができるだけでなく,相続人の一人が当該協議で負担した債務を履行しないときには,その債権を有する他の相続人は,民法第541条に基づき当該協議を解除することもできる。民法結果正解解説判例は,「共同相続人の全員が,既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上,改めて遺産分割協議をすることは,法律上,当然には妨げられるものではな」いとしている(最判平2.9.27 家族法百選〔第5版〕96事件)。したがって,前段は正しい。一方,判例は,「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に,相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができない」としている(最判平元.2.9 民法百選Ⅲ〔第2版〕70事件)。その理由として,同判決は,「遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し,その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり,しかも,このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ,法的安定性が著しく害されることになる」ことを挙げている。したがって,後段は誤りである。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)601頁。
リーガルクエスト(親族・相続)328~329頁。 -
刑法裁判所は,特定の鑑定意見の一部を採用した場合であっても,責任能力の有無・程度については,当該鑑定意見の他の部分に事実上拘束されることなく,これを判断することができる。刑法結果正解解説判例は,「責任能力の有無・程度の判断は,法律判断であって,専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり,その前提となる生物学的,心理学的要素についても,上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である」ので,「専門家たる精神医学者の精神鑑定等が証拠となっている場合においても,鑑定の前提条件に問題があるなど,合理的な事情が認められれば,裁判所は,その意見を採用せずに,責任能力の有無・程度について,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる……そうすると,裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく,上記事情等を総合して判定することができるというべきである」としている(最決平21.12.8 刑法百選Ⅰ〔第7版〕35事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)272頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例は,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合,後者が別の目的に基づく規律を意図するものであるときは,国の法令と条例との間には何らの矛盾抵触はなく,条例が国の法令に違反する問題は生じ得ないとする。憲法結果正解解説判例は,公安条例と道路交通法の抵触の有無が争われた事例において,「条例が国の法令に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば,ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも,当該法令全体からみて,右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは,これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし,逆に,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも,後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり,その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや,両者が同一の目的に出たものであっても,国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく,それぞれの普通地方公共団体において,その地方の実情に応じて,別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは,国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく,条例が国の法令に違反する問題は生じえない」としている(最大判昭50.9.10 徳島市公安条例事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕88事件)。したがって,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合,後者が別の目的に基づく規律を意図するものであるときであっても,その適用によって前者の規定の意図する目的と効果を阻害するときは,国の法令と条例との間に矛盾抵触があり,条例が国の法令に違反する問題が生じ得る。よって,本記述は誤りである。
-
民法譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,更にその債権を譲り受けた転得者が,譲渡禁止の特約の存在を知らず,かつ,知らないことについて重大な過失がなかったときは,債務者は,転得者に対し,特約の存在を対抗することができない。民法結果正解解説債権譲渡は,原則として自由であるが(民法466条1項本文),当事者が債権譲渡を禁止する特約も有効である(同条2項本文)。もっとも,取引の安全に配慮し,同項ただし書は,「その意思表示は,善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。そして,判例は,本記述と同様の事例において,譲渡禁止特約のある債権を悪意の譲受人から譲り受けた転得者が特約の存在について善意である場合,債務者は特約の存在を対抗することができないとしている(大判昭13.5.14)。また,判例は,「民法466条2項は債権の譲渡を禁止する特約は善意の第三者に対抗することができない旨規定し,その文言上は第三者の過失の有無を問わないかのようであるが,重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから,譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であっても,これにつき譲受人に重大な過失があるときは,悪意の譲受人と同様,譲渡によってその債権を取得しえないものと解するのを相当とする」としている(最判昭48.7.19 民法百選Ⅱ〔第5版新法対応補正版〕27事件)。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)525頁,528頁。
川井(3)246頁。
我妻・有泉コメ907頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合,甲は,Aが所有する不動産について管理をするため,甲とAとの間の契約に基づき登記簿上の名義を甲名義にしていた。甲は,同不動産につきAから提起された所有権移転登記手続請求事件に応訴して,自己の所有権を主張し,虚偽のA名義の当該不動産の売渡約定証を証拠として提出した場合,甲に横領罪が成立する。刑法結果正解解説「横領」とは,自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得すること,すなわち,「不法領得の意思」を実現する一切の行為をいう。そこで,本記述において,相手方から提起された所有権移転登記手続請求事件に応訴して,偽造文書を用いて自己の所有権を主張・抗争することをもって,不法領得の意思を実現する行為があったといえるかが問題となる。応訴して請求棄却を求め,その理由として自己の所有権を主張するといった不法領得の意思を推知させるような行為があるからといって,横領罪が常に既遂に達するものではない。しかし,判例は,他人の建物を管理占有していた者が偽造文書を利用して建物所有者に対し自己の所有権を主張し,所有権移転登記を求める旨の民事訴訟を提起した事例(最判昭25.9.22),登記簿上自己が所有名義人となって預かり保管中の不動産につき,所有者からの所有権移転登記手続請求訴訟提起に対して応訴して自己の所有権を主張し,他人に虚偽の証言を依頼するなどして抗争した事例(最決昭35.12.27)において横領罪の成立を認めている。したがって,本記述においても不法領得の意思を実現する行為が行われたとして,甲に横領罪が成立する。よって,甲に横領罪が成立する。参考山口(各)306頁。
昭35最高裁解説(刑事)479~487頁。
大コメ(刑法・第3版)(13)614~615頁。
裁判例コンメンタール刑法第3巻425~426頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第21条第2項前段にいう「検閲」の禁止は,公共の福祉を理由とする例外を許容しない,絶対的禁止であるのに対し,検閲以外の表現行為に対する事前抑制は,表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法第21条の趣旨に照らし,厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容され得る。憲法結果正解解説判例は,税関検査が憲法21条2項前段の「検閲」に当たるかどうか等が争われた事例において,「憲法21条2項前段は,「検閲は,これをしてはならない。」と規定する。憲法が,表現の自由につき,広くこれを保障する旨の一般的規定を同条1項に置きながら,別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは,検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ,これについては,公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法12条,13条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたもの」であるとしている(最大判昭59.12.12 憲法百選Ⅰ〔第6版〕73事件)。他方,判例は,知事選の立候補予定者に対する厳しい批判を行った記事を掲載した雑誌の事前差止めが憲法21条に反するかどうかが争われた事例において,「表現行為に対する事前抑制は,新聞,雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ,公の批判の機会を減少させるものであり,また,事前抑制たることの性質上,予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く,濫用の虞があるうえ,実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって,表現行為に対する事前抑制は,表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし,厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない」としている(最大判昭61.6.11 北方ジャーナル事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕72事件)。したがって,判例によれば,検閲以外の表現行為に対する事前抑制は,原則として禁止されるが,例外的に許容される場合があることを認めている。よって,本記述は正しい。
-
民法隠匿によって占有している者は,善意の占有者であっても,占有物から生ずる果実を返還する義務を負う。民法結果正解解説善意の占有者は,占有物から生ずる果実を取得する(民法189条1項)。他方,悪意の占有者は,果実を返還し,かつ,既に消費し,過失によって損傷し,又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う(同190条1項)。この悪意の占有者に関する規定は,隠匿によって占有をしている者について準用されている(同条2項)。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)280~281頁。
川井(2)123頁。 -
刑法甲は,A宅に置いてあったA所有の腕時計を,自分の父親の所有物であると誤信し,自分が使おうと思ってこっそり自宅へ持ち帰った。甲とAとの間には親族関係がなかった場合,甲には窃盗罪は成立しない。刑法結果正解解説刑法244条1項及び2項は,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者について,刑の免除をし,その他の親族との間でこれらの罪を犯した場合にはこれを親告罪としたものである。判例は,刑法「244条1項は,親族間の一定の財産犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき,その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず,その犯罪の成立を否定したものではない」としており(最決平20.2.18 刑法百選Ⅱ〔第7版〕35事件),同条を処罰阻却事由と解している。同条の親族関係の錯誤については,同条を処罰阻却事由と解する以上,故意あるいは犯罪の成否には影響を及ぼさず,同条の適用は認められない。したがって,甲には窃盗罪(同235条)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法755~756頁。
大コメ(刑法・第2版)(12)445頁,447~448頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法老齢加算の廃止を内容とする保護基準の改定については,厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるが,その際,老齢加算の支給を受けていない者との公平に鑑みると,老齢加算を含めた生活扶助が支給されることを前提として現に生活設計を立てていた被保護者の期待的利益については配慮する必要はない。憲法結果正解解説判例は,生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた住民らが,老齢加算廃止を内容とする保護基準の改定により,生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため,この変更決定の取消しを求めた事例において,「生活保護法8条2項によれば,保護基準は,要保護者(生活保護法による保護を必要とする者をいう。)の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであるのみならず,これを超えないものでなければならない。そうすると,仮に,老齢加算の一部又は全部についてその支給の根拠となっていた高齢者の特別な需要が認められないというのであれば,老齢加算の減額又は廃止をすべきことは,同項の規定に基づく要請であるということができる。もっとも,同項にいう最低限度の生活は,抽象的かつ相対的な概念であって,その時々における経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり,これを保護基準において具体化するに当たっては,国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な,しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである……。したがって,保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際し,最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否かを判断するに当たっては,厚生労働大臣に上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきであ」り,「また,老齢加算の全部についてその支給の根拠となる上記の特別な需要が認められない場合であっても,老齢加算は,一定の年齢に達すれば自動的に受給資格が生じ,老齢のため他に生計の資が得られない高齢者への生活扶助の一部として相当期間にわたり支給される性格のものであることに鑑みると,その加算の廃止は,これを含めた生活扶助が支給されることを前提として現に生活設計を立てていた被保護者に関しては,保護基準によって具体化されていたその期待的利益の喪失を来すものであることも否定し得ないところである。そうすると,上記のような場合においても,厚生労働大臣は,老齢加算の支給を受けていない者との公平や国の財政事情といった見地に基づく加算の廃止の必要性を踏まえつつ,被保護者のこのような期待的利益についても可及的に配慮する必要があるところ,その廃止の具体的な方法等について,激変緩和措置を講ずることなどを含め,上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきである」としている(最判平24.4.2 行政百選Ⅰ〔第7版〕51②事件)。したがって,同判決は,老齢加算を含めた生活扶助が支給されることを前提として現に生活設計を立てていた被保護者に関しては,保護基準によって具体化されていたその期待的利益についても配慮する必要があるとしている。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(憲法Ⅱ)358頁。
平24最高裁解説(民事下)463~464頁。 -
民法Aは,亡Bから亡Bの所有していた甲土地の遺贈を受けたが,その旨の所有権移転登記をしていなかった。その後,亡Bの共同相続人の1人であるCの債権者Dは,甲土地についてCの相続分に相当する持分を差し押さえ,その旨の登記がされた。この場合であっても,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を亡Bから取得したことを,所有権移転登記なくして主張することができる。民法結果正解解説判例は,「不動産の所有者が右不動産を他人に贈与しても,その旨の登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず,所有者は全くの無権利者とはならないと解すべきところ……,遺贈は遺言によって受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示にほかならず,遺言者の死亡を不確定期限とするものではあるが,意思表示によって物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるところはないのであるから,遺贈が効力を生じた場合においても,遺贈を原因とする所有権移転登記のなされない間は,完全に排他的な権利変動を生じないものと解すべきである。そして,民法177条が広く物権の得喪変更について登記をもって対抗要件としているところから見れば,遺贈をもってその例外とする理由はないから,遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様,登記をもって物権変動の対抗要件とするものと解すべきである」としている(最判昭39.3.6 民法百選Ⅲ〔第2版〕74事件)。本記述では,Dは甲土地のCの相続分に相当する持分につき登記を備えているが,Aは登記を備えていないことから,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を主張することができない。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(親族・相続)386頁。
佐久間(物権)105~106頁。 -
刑法指名手配の対象となっている甲は,逃走中に生活費を得るために乙という偽名を用いてC会社に就職しようと考え,同社に提出する目的で,履歴書用紙に,乙という氏名,虚偽の生年月日,住所,経歴等を記載し,その氏名の横に「乙」と刻した印鑑を押した上,甲自身の顔写真を貼り付けた履歴書を作成した。甲には有印私文書偽造罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「私文書偽造の本質は,文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解されるところ……,これらの文書の性質,機能等に照らすと,たとえ被告人の顔写真がはり付けられ,あるいは被告人が右各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても,これらの文書に表示された名義人は,被告人とは別人格の者であることが明らかであるから,名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである」としている(最決平11.12.20 刑法百選Ⅱ〔第7版〕95事件)。したがって,本記述の甲には有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)459頁,469頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法下級裁判所の裁判官の任命は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が行うとされるが,指名過程の透明性を高め,国民の意見を反映させるため,国民的視野に立って多角的見地から意見を述べる機関として,規則により下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置されている。憲法結果正解解説下級裁判所の裁判官については,「最高裁判所の指名した者の名簿によつて,内閣でこれを任命する」(憲法80条1項本文前段)とされているが,最高裁判所による指名過程が必ずしも透明でなく,国民の意思が及び得ないとの指摘を受け,指名過程の透明性を高め,国民の意見を反映させるため,国民的視野に立って多角的見地から意見を述べる機関として,下級裁判所裁判官指名諮問委員会が,平成15年に司法制度改革の一環として,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則により設置された。当該委員会は,最高裁判所の諮問機関としてその諮問に応じ,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名することの適否や指名に関する事項を審議し,この結果に基づき最高裁判所に意見を述べることとされている。よって,本記述は正しい。
なお,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の意見を基に,最高裁判所が下級裁判所裁判官を指名するという運用がなされているが,最高裁判所の指名権を無にするような恣意的なものでない限り,内閣は指名された者の任命を拒否できると解されている。参考佐藤幸(日本国憲法論)603頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)289~290頁。 -
民法被保佐人が時効完成前の債務を承認するには,その保佐人の同意を得なければならない。民法結果正解解説時効の中断の効力を生ずべき承認をするには,相手方の権利についての処分につき行為能力があることを要しない(民法156条)。債務の承認(同147条3号)は,現に存在する権利を確認する行為であり,処分行為とは異なるためである。判例も,時効中断の効力を生じさせる承認は,相手方の有する権利の存在を認める観念の表示であり,準禁治産者(現:被保佐人)といえども単独ですることができ,その保佐人の同意を要しないことは,同156条の規定により明白であるとしている(大判大7.10.9)。したがって,被保佐人が時効完成前の債務を承認するには,その保佐人の同意を得る必要はない。よって,本記述は誤りである。参考四宮・能見(民法総則)469頁。
-
刑法甲は,V宅の居間の金庫に多額の現金が入っていることを知り,これを盗む目的で,Vの留守を見計らってV宅の裏口から侵入しようとしたところ,甲の予想に反して,Vが帰宅したため,慌てて逃走した。甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。刑法結果正解解説窃盗罪(刑法235条)の実行の着手(同43条本文)は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められる。具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,犯行の日時・場所等の諸般の事情を考慮することになるが,通常の住宅等への侵入窃盗の場合には,侵入しただけでは窃盗罪の実行の着手とは認められず,遅くとも財物の物色行為のあった時点で実行の着手が認められる(最判昭23.4.17)。本記述では,甲はV宅に侵入しようとしただけであるから,窃盗罪の実行の着手は認められない。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法724頁。
前田(各)324頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法付随的違憲審査制は,伝統的な司法の観念に立脚するものであり,個人の権利保護を第一の目的とする私権保障型の憲法保障制度であるから,事件・争訟として適切に裁判所に提起されている場合,その当事者は,特定の第三者の憲法上の権利を主張することは許されない。憲法結果正解解説付随的違憲審査制は,伝統的な司法の観念に立脚するものであり,個人の権利保護を第一の目的とする(私権保障型の憲法保障制度)。そのため,事件・争訟の当事者が特定の第三者の憲法上の権利を主張することは,原則として許されない。もっとも,違憲の主張をする者の利益の程度,援用される憲法上の権利の性格,違憲の主張をする者と第三者の関係,第三者が別の訴訟で自己の権利侵害につき違憲の主張をすることの可能性等の要素を考慮した上で,その主張を当事者にさせることが適切な状況があり,またそのことが第三者に実質的な不利益を与えない限り,その主張を認めてもよいとする等,これを認める見解が一般的である。判例も,憲法81条はこの付随的違憲審査制を規定するものであり(最大判昭27.10.8 警察予備隊違憲訴訟 憲法百選Ⅱ〔第6版〕193事件),当初,「他人の権利に容喙干渉」(最大判昭35.10.19)することは許されないとしたが,その後,これを認めている(最大判昭37.11.28 第三者所有物没収事件 憲法百選Ⅱ〔第6版〕194事件)。したがって,付随的違憲審査制から直ちに,事件・争訟の当事者が,特定の第三者の憲法上の権利を主張することが許されないということにはならない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)380頁。
佐藤幸(日本国憲法論)632~633頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)298~301頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)322~326頁。 -
民法日用品供給の先取特権の債務者は,規模,経営態様等のいかんを問わず,法人は含まれない。民法結果正解解説判例は,「民法306条4号,310条の法意は,同条の飲食品および薪炭油の供給者に対し一般先取特権を与えることによって,多くの債務を負っている者あるいは資力の乏しい者に日常生活上必要不可欠な飲食品および薪炭油の入手を可能ならしめ,もってその生活を保護しようとすることにあ」り,「かかる法意ならびに同法310条の文言に照らせば,同条の債務者は,自然人に限られ,法人は右債務者に含まれないと解するのが相当である」とした上で,「このような解釈は,法人の規模,経営態様等のいかんを問わず妥当する」としている(最判昭46.10.21 倒産百選〔第3版〕47事件)。その理由として,同判決は,「もし法人が右債務者に含まれると解するならば,法人に対する日用品供給の先取特権の範囲の限定が著しく困難になり,一般債権者を不当に害するに至ることは明らかである」ことを挙げている。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ55頁。
-
刑法甲は,乙が覚せい剤を密輸することを知りながら,同人に対して覚せい剤購入資金を交付したところ,乙は,これを用いて2回の密輸を行った。甲には,2個の覚せい剤取締法違反幇助の罪が成立し,両罪は併合罪となる。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「幇助罪は正犯の犯行を幇助することによって成立するものであるから,成立すべき幇助罪の個数については,正犯の罪のそれに従って決定されるものと解するのが相当である」としている(最決昭57.2.17 刑法百選Ⅰ〔第7版〕106事件)。その上で,同決定は,「幇助罪が数個成立する場合において,それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かについては,幇助犯における行為は幇助犯のした幇助行為そのものにほかならないと解するのが相当であるから,幇助行為それ自体についてこれをみるべきである」とした上で,「被告人の幇助行為は1個と認められるから,たとえ正犯の罪が併合罪の関係にあっても,被告人の2個の覚せい剤取締法違反幇助の罪は観念的競合の関係にあると解すべきである」としている。したがって,甲の幇助行為は覚せい剤購入資金を交付した行為1個であり,1個の行為が2個の罪名に触れる関係にあるから,両罪は観念的競合になる。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)410頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法内閣は,国会に対して「連帯して」責任を負う旨の規定は,国務大臣の単独責任を否定する趣旨ではないとされるが,憲法上国務大臣が辞職を義務付けられる場合として,衆議院が内閣の連帯責任を追及する,内閣不信任決議案の可決又は内閣信任決議案の否決がある。憲法結果正解解説憲法は,「内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。」(同66条3項)と定め,内閣の責任についての一般原則を示している。内閣は,総理大臣の下に一体となって政治を行う原則から,その責任も一体として負うことにしたものである。しかし,この連帯責任の規定は,内閣の構成員たる国務大臣の単独責任を否定する趣旨ではない。すなわち,各国務大臣の所管事項について,国会の信任を破るような行為があった場合には,内閣の連帯責任を問うこともできるし,その大臣の単独責任を問うこともできる。そして,憲法上国務大臣が辞職を義務付けられる場合として,衆議院が内閣の連帯責任を追及する,内閣不信任決議案の可決又は内閣信任決議案の否決がある(同69条)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)328~329頁。
佐藤幸(日本国憲法論)504~505頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)220~221頁。
新基本法コメ(憲法)373頁。 -
民法買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,その抵当権が買戻権の行使により消滅した場合,抵当権に基づく物上代位権の行使として,その買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。民法結果正解解説判例は,「買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,抵当権に基づく物上代位権の行使として,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる」としている(最判平11.11.30 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕87事件)。その理由として,同判決は,「買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては,買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはな」く,「また,買戻代金は,実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見ることができ,目的不動産の価値変形物として,民法372条により準用される304条にいう目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭に当たるといって差し支えない」ことを挙げている。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ151頁。
-
刑法甲は,A店での万引き事件の被疑者として取調べを受けていた際に,警察署の取調室内において,「Aの店は汚いのだから,商品に価値なんてないだろう。」などと発言した。取調室内には,警察官2名が在室していた。甲には名誉毀損罪が成立する。刑法結果正解解説「公然と」とは,摘示された事実を不特定又は多数人が認識し得る状態をいい(最判昭36.10.13),判例は,事実の摘示の相手方が特定・少数の場合でも伝播可能性がある場合には公然性を認めている(いわゆる伝播性の理論。最判昭34.5.7 刑法百選Ⅱ〔第7版〕19事件など)。しかし,警察官は公務員として職務上知ることのできた秘密を守らなければならない法律上の義務があるのみならず,捜査官としての職務に従事中であったことから,本記述の事例においては,甲の発言についての伝播性はないといえる。判例も,検事取調室内での名誉毀損行為について,同様の判断を示している(最決昭34.2.19)。したがって,甲に名誉毀損罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)260頁。
西田(各)123~124頁。
昭34最高裁解説(刑事)58~61頁。
条解刑法675頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第29条は,私有財産制度を保障しているのみではなく,社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するものである。憲法結果正解解説判例は,共有森林について2分の1以下の持分の共有者の分割請求を禁止する森林法186条(昭和62年法律第48号による削除前)が,憲法29条等に反し無効となるかが争われた事例において,「憲法29条は,1項において「財産権は,これを侵してはならない。」と規定し,2項において「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。」と規定し,私有財産制度を保障しているのみでなく,社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する」としている(最大判昭62.4.22 森林法共有林事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕101事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは,その判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる。民法結果正解解説善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは,その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされる(民法189条2項)。これは,敗訴し得るような本権の訴えが提起されたにもかかわらず,その時以後の果実を占有者に取得させることは不当だからである。したがって,悪意の占有者とみなされるのは,本権の訴えの提起の時からであり,その判決が確定した時からではない。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)280~281頁。
川井(2)122~123頁。
基本法コメ(物権)57頁。 -
刑法甲は,夜明け前の暗い高速道路を走行中,同方向に進行していた大型トレーラーを運転するAの運転態度に腹を立てたため,Aの車両(以下「A車」という。)を相応の交通量のある第3通行帯(追越し車線)に停止させ,A車から降りてきたAに暴行を加えた。甲が自車で走り去ってから7,8分後までAがその場にA車を停車させ続けたところ,後続車がA車に衝突し,後続車の運転手Vが死亡した。AがA車を直ちに発進させなかったことが,甲から暴行を受けた際にエンジンキーを紛失したと勘違いし周囲を探していたという事情によるものであった場合であっても,甲がA車を停止させた行為とVの死亡の結果との間には,因果関係がある。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,高速道路の第3通行帯(追越し車線)上に自車及びA車を停止させたという被告人甲の過失行為は,「後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有していたというべきである」とした上で,「本件事故は,被告人の上記過失行為の後,Aが,自らエンジンキーをズボンのポケットに入れたことを失念し周囲を捜すなどして,被告人車が本件現場を走り去ってから7,8分後まで,危険な本件現場に自車を停止させ続けたことなど,少なからぬ他人の行動等が介在して発生したものであるが,それらは被告人の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったといえる」として,甲の過失行為とVらの死傷との間には因果関係があるとしている(最決平16.10.19 平16重判刑法2事件)。したがって,甲がA車を停止させた行為とVの死亡の結果との間には,因果関係がある。よって,本記述は正しい。参考山口(総)66頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法税関検査は,関税徴収手続の一環にすぎず,網羅的・一般的な審査ではないから,憲法第21条第2項前段にいう「検閲」に当たらないが,ある表現物に対して税関長による輸入禁止処分がなされた場合,当該表現物に表された思想内容等は,我が国においては発表の機会を奪われ,これを受ける側の知る自由が制限されることになるから,事前規制そのものである。憲法結果正解解説最大判昭59.12.12は,「税関検査の結果,輸入申告にかかる書籍,図画その他の物品や輸入される郵便物中にある信書以外の物につき,それが3号物件(注:関税定率法21条1項3号(現:関税法69条の11第1項7号))に該当すると認めるのに相当の理由があるとして税関長よりその旨の通知がされたときは,以後これを適法に輸入する途が閉ざされること」になる結果,「当該表現物に表された思想内容等は,わが国内においては発表の機会を奪われることとなる。また,表現の自由の保障は,他面において,これを受ける者の側の知る自由の保障をも伴うものと解すべきところ……,税関長の右処分により,わが国内においては,当該表現物に表された思想内容等に接する機会を奪われ,右の知る自由が制限されることとなる。これらの点において,税関検査が表現の事前規制たる側面を有することを否定することはできない」が,「これにより輸入が禁止される表現物は,一般に,国外においては既に発表済みのものであって,その輸入を禁止したからといって,それは,当該表現物につき,事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また,当該表現物は,輸入が禁止されるだけであって,税関により没収,廃棄されるわけではないから,発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。その意味において,税関検査は,事前規制そのものということはできない」し,また,「税関検査は,関税徴収手続の一環として,これに付随して行われるもので,思想内容等の表現物に限らず,広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし,3号物件についても,右のような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず,思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではな」く,「税関検査は行政権によって行われるとはいえ,その主体となる税関は,関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であって,特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく,また,……思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであって,行政権の判断が最終的なものとされるわけではない」から,「3号物件に関する税関検査は,憲法21条2項にいう「検閲」に当たらない」としている。よって,本記述は誤りである。
-
民法共同相続が生じた場合,相続財産を構成する普通預金債権は,相続開始と同時に共同相続人各自の相続分に応じて当然に分割され,遺産分割の対象とならない。民法結果正解解説判例は,「共同相続された普通預金債権……は,……相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」としている(最大決平28.12.19 民法百選Ⅲ〔第2版〕66事件)。その理由として,同決定は,以下のように述べる。すなわち,遺産分割の仕組みは,被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的な公平を図ることを旨とするものであることから,一般的には,遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく,また,遺産分割手続を行う実務上の観点からは,現金のように,評価についての不確定要素が少なく,具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する。具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点においては,預貯金が想起されるが,預貯金は,預金者において確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産である。普通預金契約は,一旦契約を締結して口座を開設すると,以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約である。口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが,その結果発生した預金債権は,口座の既存の預金債権と合算され,1個の預金債権として扱われる。また,普通預金契約は預金残高が0になっても存続し,その後に入金が行われれば入金額相当の預金債権が発生する。このように,普通預金債権は,1個の債権として同一性を保持しながら,常にその残高が変動し得るものである。そして,この理は,預金者が死亡した場合においても異ならない。すなわち,預金者が死亡することにより,普通預金債権は共同相続人全員に帰属するに至るところ,その帰属の態様について,上記債権は,口座において管理されており,預金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預金契約を解約しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し,各共同相続人に確定額の債権として分割されることはない。そして,相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが,預金契約が終了していない以上,その額は観念的なものにすぎない。預金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され,その後口座に入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預金債権が成立すると解することは,預金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり,その合理的意思にも反する。よって,本記述は誤りである。参考リーガルクエスト(親族・相続)315~316頁。
-
刑法行為者が,他人を殺害する目的で毒薬を入手したものの,悔悟の念を生じたため,その殺害の実行を断念した場合でも,刑が免除されることはない。刑法結果正解解説判例は,予備罪については,中止犯の規定の準用を認めない(最大判昭29.1.20 刑法百選Ⅰ〔第7版〕72事件)。しかし,本記述の殺人予備罪(刑法201条)は,同条ただし書において,刑の任意的免除を認めている。したがって,その刑が免除される余地はある。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法580頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第92条は,地方公共団体の組織及び運営に関する事項については法律でこれを定めることとしているから,地方議会を諮問機関とすることは,必ずしも違憲ということはできない。憲法結果正解解説憲法92条は,「地方自治の本旨」に基づいた法律の制定を命じている。ここにいう「地方自治の本旨」とは,地方自治が住民の意思に基づいて行われる民主主義的要素をいう住民自治と,地方自治が国から独立した団体によってその意思と責任の下でなされる自由主義的・地方分権的要素をいう団体自治を指す。そして,地方議会を諮問機関とする法律を制定し,地方自治の権限をはく奪することは,国から独立した団体による地方自治を失わせるものであり,団体自治に反しているといえる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)367頁。
-
民法AB間の売買契約が詐欺を理由として取り消された場合,AB間で相互に返還されるべき給付は,同時履行の関係にある。民法結果正解解説判例は,売買契約が詐欺を理由に取り消された場合,売主・買主双方の原状回復義務は,民法533条の類推適用により同時履行の関係にあるとしている(最判昭47.9.7)。返還義務自体に着目すれば同時履行の関係を認めることが公平にかない,また,同時履行の抗弁を認めることで取消しによる清算の迅速を図ることができるためである。よって,本記述は正しい。参考川井(1)284頁。
昭47最高裁解説(民事)676頁。 -
刑法甲は,車で走行中,知り合いの乙女が歩いているのを発見し,強制性交の目的を秘して「家まで送ってあげる。」と声を掛けたところ,乙女は,これを信じて車に乗り込んだが,途中で違う道に入ったことに気付き,停車するよう求めた。この場合,甲がそれ以上走行を続けることを断念し,乙女を降車させたとしても,甲には監禁罪が成立する。刑法結果正解解説監禁罪(刑法220条後段)の「監禁」とは,一定の場所からの脱出を困難にして,移動の自由を奪うことをいう。判例は,行き先を偽りA地点でXを自動車に乗せ走行したところ,B地点でだまされたことに気付いたXが停車を求めたもののそのまま走行し,C地点でXが逃げ出したという事例において,「監禁」の「方法は,必ずしも……暴行又は脅迫による場合のみに限らず,偽計によって被害者の錯誤を利用する場合をも含む」として,A地点からの監禁罪の成立を認めている(最決昭33.3.19)。本記述では,甲は,乙女からの求めがあったところで降車させてはいるが,乙女をだまして乗車させ,走行を開始していたのであるから,既に甲には監禁罪が成立しているといえる。よって,本記述は正しい。参考山口(各)86~88頁。
西田(各)82~83頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法いわゆるビデオリンク方式によった上で,被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても,被告人は,証人の供述を聞き,自ら尋問することができ,また,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないことから,憲法第37条第2項前段が保障する被告人の証人審問権を侵害しない。憲法結果正解解説判例は,証人の遮へい,いわゆるビデオリンク方式による証人尋問を定める刑訴法の各規定(同157条の5,157条の6)が被告人の証人審問権(憲法37条2項前段)等を侵害するかどうかが争われた事例において,「証人尋問の際,……ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても,映像と音声の送受信を通じてであれ,被告人は,証人の供述を聞くことはでき,自ら尋問することもでき,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから,……被告人の証人審問権は侵害されていないというべき……である。したがって,刑訴法157条の3,157条の4(現:157条の5,157条の6)は,憲法37条2項前段に違反するものでもない」としている(最判平17.4.14 憲法百選Ⅱ〔第6版〕192事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法安全配慮義務違反の債務不履行によって死亡した被害者の遺族は,固有の慰謝料請求権を有しない。民法結果正解解説最判昭55.12.18は,被用者の遺族が使用者に対して,雇用契約上の安全保証義務(安全配慮義務と同義)違反を理由とする損害賠償等を請求した事例において,亡被用者「と被上告人ら(注:使用者)との間の雇傭契約ないしこれに準ずる法律関係の当事者でない上告人ら(注:被用者の遺族)が雇傭契約ないしこれに準ずる法律関係上の債務不履行により固有の慰藉料請求権を取得するものとは解しがたい」としている。その理由として,同判決の調査官解説は,安全配慮義務違背が債務不履行を理由として債権者が債務者の責任を追及するものであるという点を重視すると,契約の当事者でない者の固有の責任追及権は否定されるといえ,民法415条の規定の文言自体がこのことを明らかにしており,同711条類推適用の余地はないことを挙げている。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)118頁。
昭55最高裁解説(民事)420頁。 -
刑法受託収賄罪の「請託」とは,公務員に対し,職務に関して一定の不正な行為を行うことを依頼することをいい,正当な行為を行うことの依頼はこれに当たらない。刑法結果正解解説判例は,受託収賄罪(刑法197条1項後段)の「請託」とは,「公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することであって,その依頼が不正な職務行為の依頼であると,正当な職務行為の依頼であると」は問わないとしている(最判昭27.7.22 刑法百選〔新版〕60事件)。そのため,請託とは,職務に関して一定の不正な行為を行うことを依頼することに限られない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)623頁。
西田(各)526~527頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法人が自己の信仰生活の静ひつを他者の宗教上の行為によって害されたとして,そのことに不快な感情を持ったとしても,これを被侵害利益として直ちに損害賠償又は差止めを請求することができるとするならば,かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となる。憲法結果正解解説判例は,社団法人隊友会A県支部連合会と自衛隊A地方連絡部が共同して亡夫をA県護国神社に合祀申請(以下「本件合祀申請」という。)したことは,宗教上の人格権の侵害であるなどとして,亡夫の妻(被上告人)が,合祀手続の取消しなどを請求した事例において,「本件合祀申請は合祀の前提としての法的意味をもつものではな」く,「合祀申請が神社のする合祀に対して事実上の強制とみられる何らかの影響力を有したとすべき特段の事情」もないから,被上告人の「法的利益の侵害の成否は,合祀それ自体が法的利益を侵害したか否かを検討すれば足り……また,合祀それ自体は県護国神社によってされているのであるから,法的利益の侵害の成否は,同神社と被上告人の間の私法上の関係として検討すべき」であるとした上で,「私人相互間において……信教の自由の侵害があり,その態様,程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは,……法的保護が図られるべきである……。しかし,人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし,そのことに不快の感情を持ち,そのようなことがないよう望むことのあるのは,その心情として当然であるとしても,かかる宗教上の感情を被侵害利益として,直ちに損害賠償を請求し,又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば,かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは,見易いところである。信教の自由の保障は,何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して,それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。……原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは,これを直ちに法的利益として認めることができない」としている(最大判昭63.6.1 殉職自衛官合祀事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕47事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法債務者所有の不動産所有権の譲渡をもって代物弁済した場合,所有権移転登記及び現実の引渡しをしなければ,債務消滅の効力は生じない。民法結果正解解説代物弁済(民法482条)により債権が消滅するところ,同条の「給付をした」というためには,権利の移転に加え,第三者に対する対抗要件の具備が必要である。判例は,「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもって代物弁済する場合の債務消滅の効力は,原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず,所有権移転登記手続の完了によって生ずる」としている(最判昭40.4.30)。その理由として,同判決の調査官解説は,債務消滅の対価は,不動産所有権の完全な取得に尽きることを挙げている。したがって,債務消滅の効力を生じるには,所有権移転登記は必要であるが,それに加えて現実の引渡しまでは必要ない。よって,本記述は誤りである。参考中田(債総)387頁。
川井(3)332頁。
昭40最高裁解説(民事)110頁。 -
刑法甲は,確定判決によって刑務所に収容されている乙の友人であるが,刑務所を見学している際,乙を逃走させる目的で刑務官に暴行を加えたものの,騒ぎを聞きつけた他の刑務官に取り押さえられたため,乙を逃走させるに至らなかった。甲に逃走援助罪の既遂罪は成立しない。刑法結果正解解説逃走援助罪(刑法100条)は,逃走を容易にすべき行為を終了することによって,直ちに既遂に達し,被拘禁者が現実に逃走したことを要しない。したがって,甲が乙を逃走させる目的で刑務官に暴行を開始した場合,甲には同罪の既遂罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)479頁。
山口(各)574頁。
条解刑法310頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められているが,参議院で衆議院と異なった議決をした場合,又は参議院が衆議院の可決した条約を受け取った後,国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは,必ず両議院の協議会を開かなければならない。憲法結果正解解説条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められている(憲法61条・60条2項)。そして,参議院で衆議院と異なった議決をした場合には両議院の協議会を開かなければならない(国会法85条)が,参議院が衆議院の可決した条約を受け取った後,国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは,両議院の協議会を開くことなく,衆議院の議決が国会の議決となる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)300頁。
佐藤幸(日本国憲法論)441~442頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)88~89頁。 -
民法Aが罵声を浴びせるなどしてBを脅し,Bがこれに畏怖した結果その所有する甲土地をAに売却する旨の契約を締結した場合において,強迫を理由とする意思表示の取消しが認められるためには,Bが完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する。民法結果正解解説判例は,「民法96条にいう「強迫に因る意思表示」(現:「強迫による意思表示」)の要件たる強迫ないし畏怖については,明示若しくは暗黙に告知せられる害悪が客観的に重大なると軽微なるとを問わず,苟くもこれにより表意者において畏怖した事実があり且右畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的に存すれば足りるのであって,……完全に意思の自由を失った場合はむしろその意思表示は当然無効であり,民法96条適用の余地はない」としている(最判昭33.7.1 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕20事件)。したがって,強迫を理由とする意思表示の取消しが認められるためには,Bが完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要しない。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(総則)174頁,176~177頁。
-
刑法人を不法に監禁中に,監禁罪の法定刑を重くする法改正が行われて施行された場合,常に新法が適用される。刑法結果正解解説監禁罪(刑法220条後段)は継続犯と解されているところ,判例は,継続犯の実行行為継続中にその刑罰法規に変更があった事例において,「刑法6条による新旧両法対照の問題はおこらず,常に新法を適用処断する」としている(最決昭27.9.25)。よって,本記述は正しい。参考条解刑法12頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法放送事業者は,放送をした事項が真実でないことが判明した場合,放送法の規定により訂正放送等が義務付けられているが,これは,放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から,放送事業者に対し,自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって,被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではない。憲法結果正解解説判例は,放送事業者がした真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた者が,放送法4条1項の規定に基づく訂正放送等を求める私法上の権利を有するかが問題となった事例において,同「4条1項は,真実でない事項の放送について被害者から請求があった場合に,放送事業者に対して訂正放送等を義務付けるものである」とする一方で,「同項は,真実でない事項の放送がされた場合において,放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から,放送事業者に対し,自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって,被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではない」としている(最判平16.11.25 平16重判憲法8事件)。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)179~180頁。
-
民法甲土地の買主Aが所有権移転登記を経由する前に甲土地を転売した場合,Aは,売主Bに対して甲土地の所有権移転登記手続を請求することはできない。民法結果正解解説判例は,売買による所有権移転の登記請求権は,売買による所有権移転の事実に伴い必ず存在する義務であるとした上で,買主は,たとえ不動産を転売してその所有権を喪失したとしても,まず自己の所有権取得の登記を行い,その所有権取得を完全なものにして,その後,転得者に対して転売による所有権移転登記の義務を尽くすべきであって,転売により自己の登記請求権を失うものではないとしている(大判大5.4.1 不動産取引百選〔第2版〕41事件)。したがって,Aは,甲土地を転売した場合であっても,Bに対して所有権移転登記手続を請求することができる。よって,本記述は誤りである。参考佐久間(物権)51頁。
-
刑法甲は,確定判決によって刑務所に収容されている者であるが,逃走の目的で刑務所内の居房の窓に設置された鉄格子を損壊した時点で,刑務官に発見されたため,逃走行為に着手することができなかった。甲に加重逃走罪の未遂罪は成立しない。刑法結果正解解説判例は,「刑法98条のいわゆる加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によるものについては,逃走の手段としての損壊が開始されたときには,逃走行為自体に着手した事実がなくとも,右加重逃走罪の実行の着手がある」としている(最判昭54.12.25)。本記述において,甲は,逃走の目的で刑務所の窓の鉄格子を損壊した以上,加重逃走罪の実行の着手があったといえる。また,同罪は看守者の実力支配を脱した時に既遂に達するところ,甲は,逃走行為自体に及ばないうちに刑務官に発見されており,その実力支配を脱していない。したがって,甲には,同罪の未遂罪(同102条,98条)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)476頁。
山口(各)570頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法国は,教育の一定水準を維持しつつ,高等学校教育の目的達成に資するために,高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり,特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については,教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量には,おのずから制約が存する。憲法結果正解解説判例は,公立高校の教師が,文部省(現:文部科学省)による高等学校学習指導要領に定められた科目の目標及び内容を逸脱した指導を行った等の理由による懲戒免職処分の取消しを求めて訴えを提起した事例において,「国が,教育の一定水準を維持しつつ,高等学校教育の目的達成に資するために,高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり,特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については,教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存する」としている(最判平2.1.18 伝習館高校事件 憲法百選Ⅱ〔第6版〕141事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人が,事前求償権を被保全債権とする仮差押えをした場合,事前求償権の消滅時効だけでなく,事後求償権の消滅時効をも中断する。民法結果正解解説仮差押えは,時効の中断事由であるが(民法147条2号),時効中断の客観的範囲は定められておらず,解釈に委ねられている。そこで,保証人が事前求償権を被保全債権として仮差押えをすることにより,事後求償権の消滅時効も中断するかが問題となる。この点,判例は,信用保証協会が,信用保証委託契約上の事後求償権等に基づき,主たる債務者に対し,金員の支払を求めたところ,主たる債務者が事後求償権の消滅時効を主張した事例において,事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断するとしている(最判平27.2.17 平27重判民法5事件)。よって,本記述は正しい。参考潮見(プラクティス債総)652頁。
-
刑法甲は,恋慕する乙が冷淡なのに憤慨し,乙を困らせる意図で,乙の事務所から重要な業務書類が入ったかばんを持ち去り,2か月余りの間自宅に隠匿した。この場合,甲には乙を困らせる意図しかないので,甲には窃盗罪は成立しない。刑法結果正解解説窃盗罪(刑法235条)の成立には,主観的超過要素としての不法領得の意思が要求されており,判例によれば,それは権利者を排除し,他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用・処分する意思である(大判大4.5.21 刑法百選Ⅱ〔第6版〕29事件)。本記述の甲の行為は乙を困らせるためのものにすぎず,利用・処分意思がなく,不法領得の意思は認められない。したがって,本記述では,甲には窃盗罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考山口(各)197頁。
西田(各)170頁。
大谷(講義各)194~195頁,201頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第50条の定める不逮捕特権における「逮捕」とは,憲法第33条の「逮捕」と異なり,広く公権力によって身体の自由を拘束することを意味するから,刑事訴訟法上の逮捕,勾引,勾留をはじめ行政上の保護措置も含む。憲法結果正解解説憲法50条は,「両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。」として,議員の不逮捕特権を定めている。ここでいう「逮捕」とは,同33条の「逮捕」と異なり,広く公権力によって身体の自由を拘束することを意味し,刑訴法上の逮捕,勾引,勾留をはじめ行政上の保護措置(警察官職務執行法3条等)等も含むとされている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)307~308頁。
佐藤幸(日本国憲法論)470頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)102頁。 -
民法住宅用建物について,屋根及び周壁を有し土地に定着した一個の建造物として存在するに至れば,工事中であっても登記によってその建物に関する物権変動を第三者に対抗することができる。民法結果正解解説判例は,建物がその目的とする使用に適する構成部分を具備する程度に達しない限り,いまだ完成した建物と称することはできないが,建物として不動産登記法により登記をすることができるに至れば,当該有体物は既に動産の領域を脱して不動産の部類に入るとした上で,住宅用建物について,工事中であっても屋根及び周壁を有し土地に定着した一個の建造物として存在するに至れば,床及び天井を備えていなくても登記をすることができるとしている(大判昭10.10.1 民法百選Ⅰ〔第8版〕11事件)。そのため,住宅用建物が,工事により屋根及び周壁を有し土地に定着した一個の建造物として存在するに至れば,その建物は,「不動産」(民法86条1項)となり,登記によってその物権変動を第三者に対抗することができる(同177条)。よって,本記述は正しい。参考川井(2)4頁,42頁。
-
刑法甲は,委員に罵声を浴びせ,出入口を施錠して委員会室に立てこもるなどして,県議会の委員会の条例採決事務を妨害した。この場合,甲には威力業務妨害罪は成立し得ない。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,条例採決事務は強制力を用いる権力的業務ではないから,業務妨害罪における「業務」に当たることを理由として,威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するとしている(最決昭62.3.12 刑法百選Ⅱ〔第6版〕22事件)。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)159~160頁。
西田(各)140頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例は,憲法第40条の「抑留又は拘禁」の中には,無罪となった公訴事実に基づく抑留又は拘禁が含まれるが,不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁については,そのうちに実質上は,無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるとしても,その部分の抑留又は拘禁は,同条の「抑留又は拘禁」に包含されないとする。憲法結果正解解説判例は,ある公訴事実について無罪を言い渡された被告人が,当該公訴事実において,不起訴処分となった別の被疑事実の勾留中に取り調べられた事実が内容とされているとして,その勾留に対する刑事補償請求をしたことにつき,その可否が争われた事例において,「憲法40条は,「……抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたとき……」と規定しているから,抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となった場合は同条の補償の問題を生じない」とした上で,しかし,「憲法40条にいう「抑留又は拘禁」中には,無罪となった公訴事実に基く抑留または拘禁はもとより,たとえ不起訴となった事実に基く抑留または拘禁であっても,そのうちに実質上は,無罪となった事実についての抑留または拘禁であると認められるものがあるときは,その部分の抑留及び拘禁もまたこれを包含する」としている(最大決昭31.12.24 憲法百選Ⅱ〔第6版〕134事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする損害賠償を請求する場合には,使用者が負う損害賠償債務は,被用者が損害を受けた時から遅滞に陥る。民法結果正解解説判例は,被用者の遺族が使用者に対して,雇用契約上の安全保証義務(安全配慮義務と同義)違反を理由とする損害賠償等を請求した事例において,雇用契約上の安全保証義務違反を理由とする損害賠償請求は債務不履行に基づく損害賠償請求であると位置付けた上で,「債務不履行に基づく損害賠償債務は期限の定めのない債務であり,民法412条3項によりその債務者は債権者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥る」としている(最判昭55.12.18 労働百選〔第9版〕49事件,昭55重判民法9事件)。よって,本記述は誤りである。
なお,判例は,不法行為に基づく損害賠償請求(同709条)の場合,債務者が遅滞に陥る時期は損害の発生時であるとしている(最判昭37.9.4)。参考中田(債総)118頁。
昭55最高裁解説(民事)415頁。 -
刑法過失を基礎付ける注意義務の発生には,必ずしも法令の根拠を要しない。刑法結果正解解説判例は,「およそ人の生命・身体に危害を生ずるおそれある……業務に従事する者は,その業務の性質に照らし危害を防止するため法律上・慣習上若しくは条理上必要なる一切の注意をなすべき義務を負担する」としている(最決昭37.12.28)。したがって,慣習や条理も注意義務の根拠となり得る。よって,本記述は正しい。参考高橋(総)227頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第95条は,地方自治特別法を制定するのに必要とされる住民投票について,国会の議決に先立って行わなければならない旨を定めており,それを受けて,国会法及び地方自治法が,地方自治特別法を制定する際の具体的手続を定めている。憲法結果正解解説憲法95条は,「一の地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ,国会は,これを制定することができない。」と規定して,地方自治特別法の制定手続を法律に委ねている。そして,この規定の仕方からは,憲法95条は,国会の議決に先立ち住民投票で過半数の同意を要求しているように読めるものの,住民投票と国会の議決の時間的先後関係についてはどちらが先であっても構わないものと解されている。よって,本記述は誤りである。
なお,国会法67条は,「一の地方公共団体のみに適用される特別法については,国会において最後の可決があつた場合は,別に法律で定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票に付し,その過半数の同意を得たときに,さきの国会の議決が,確定して法律となる。」と規定し,国会の議決が先行する旨を定め,また,地方自治法も地方自治特別法の住民投票の手続について定めている(地方自治法261条,262条)。参考芦部(憲法)368頁。
佐藤幸(日本国憲法論)560頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)389頁。
宮沢コメ780頁。
新基本法コメ(憲法)500頁。 -
民法連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,詐欺を理由としてその代物弁済を取り消した場合,他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。民法結果正解解説取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされるため(民法121条本文),Aの代物弁済が詐欺を理由として取り消されれば,当該代物弁済の効力はさかのぼって消滅することになる。このように,代物弁済の効力がさかのぼって消滅すれば,他の連帯債務者は,再び弁済の義務を負うことになる。もっとも,エの解説で述べたように,詐欺による意思表示の取消しは,「善意の第三者」に対抗することができない(同96条3項)。仮に,他の連帯債務者が「善意の第三者」に当たるとすれば,取消しの遡及効が制限され,他の連帯債務者は,代物弁済による債務の消滅を債権者に対し主張できることになる。この点について,判例は,同項にいう「善意の第三者」とは,詐欺の事実を知らないで,すなわち,善意で新たに権利を取得した者をいうのであって,詐欺による他人間の法律行為により,自然に自己の債務を免れたような者は含まれないため,連帯債務者の一人が詐欺によって代物弁済をした場合における他の連帯債務者は,同項の「善意の第三者」に当たらないとしている(大判昭7.8.9)。よって,本記述は正しい。参考川井(1)188~189頁。
-
刑法化学肥料の製造を業とする株式会社甲は,過失によって,有毒物質が入った排水をA湾内に排出した。妊婦乙がこの排水によって汚染された魚介類を食べたところ,胎児丙に病変が生じ,丙は出生後に病気が進行して死亡した。この場合,丙は甲の実行行為時に胎児であったのであるから,甲には業務上過失致死罪は成立しない。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「現行刑法上,胎児は,堕胎の罪において独立の行為客体として特別に規定されている場合を除き,母体の一部を構成するものと取り扱われていると解されるから,業務上過失致死罪の成否を論ずるに当たっては,胎児に病変を発生させることは,人である母体の一部に対するものとして,人に病変を発生させることにほかならない。そして,胎児が出生し人となった後,右病変に起因して死亡するに至った場合は,結局,人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するから,……同罪が成立する」としている(最決昭63.2.29 刑法百選Ⅱ〔第7版〕3事件)。したがって,甲には業務上過失致死罪(刑法211条前段)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)24~26頁。
西田(各)25~27頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法政党は,憲法第21条第1項の保障する結社の自由を行使して結成され,活動する私的団体であるが,実際には国家機関の一部として活動しているという意味において,公的団体としての性格を有しているものといえる。憲法結果正解解説政党は,憲法21条1項の保障する結社の自由の行使として結成され,活動する私的団体であるが,政党は国家の政治的意思形成過程に深く関わっており,実際には国家機関の一部として活動しているという意味において,公的団体としての性格を有しているものといえる。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)417~419頁。
安西ほか(憲法学読本)260~261頁。
戸松(憲法)41~42頁。
市川(憲法)34頁。 -
民法袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)の所有権を取得した者は,当該袋地について所有権移転登記を具備しなければ,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の所有者やその利用権者に対して,その囲繞地について,公道に至るための通行権を主張することができない。民法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「袋地の所有権を所得した者は,所有権取得登記を経由していなくても,囲繞地の所有者ないしこれにつき利用権を有する者に対して,囲繞地通行権を主張することができると解するのが相当である」としている(最判昭47.4.14 民法百選Ⅰ〔第5版新法対応補正版〕56事件)。その理由として,同判決は,「民法209条ないし238条は,いずれも,相隣接する不動産相互間の利用の調整を目的とする規定であって,同法210条において袋地の所有者が囲繞地を通行することができるとされているのも,相隣関係にある所有権共存の一態様として,囲繞地の所有者に一定の範囲の通行受忍義務を課し,袋地の効用を完からしめようとしているためである。このような趣旨に照らすと,袋地の所有者が囲繞地の所有者らに対して囲繞地通行権を主張する場合は,不動産取引の安全保護をはかるための公示制度とは関係がない」ということを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考川井(2)151頁。
基本法コメ(物権)97頁。 -
刑法甲は,法令により拘禁された者を看守する者であり,被拘禁者乙の逃走を容易にする行為をしたが,乙が逃走する前に辞職し,乙が実際に逃走した時点で看守者の身分を有していなかった。甲に看守者等による逃走援助罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,法令により拘禁された者を看守又は護送する者が,被拘禁者の逃走を容易にする行為をした場合,逃走の事実が看守又は護送の任務解除後に発生したときでも,看守者等による逃走援助罪(刑法101条)の成立を認めている(大判大2.5.22)。したがって,逃走を容易にさせる行為をした時点で上記身分を有する以上,たとえ被拘禁者の逃走前に辞職していたとしても,甲には看守者等による逃走援助罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考条解刑法311頁。
大コメ(刑法・第3版)(6)324頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法弁護士資格を有する国会議員の所属する弁護士会が,当該議員が議院で行った発言を理由として,弁護士法上の懲戒責任を追及することは,免責特権を定めた憲法第51条に反せず,許される。憲法結果正解解説憲法51条は,「両議院の議員は,議院で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。」として,免責特権について規定している。これは,議院における議員の自由な発言や表決を最大限確保しようとすることにある。そして,ここでいう「責任」とは,一般の国民ならば当然負うべき法的責任をいい,損害賠償や名誉毀損といった民事上,刑事上の責任がこれに含まれることに加えて,弁護士資格を有する国会議員が弁護士法上負う懲戒責任もこれに含まれる。したがって,弁護士資格を有する国会議員の所属する弁護士会が,当該議員の議院における発言や表決などについて,弁護士法上の懲戒責任を追及することも憲法51条に反し,許されない。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)471~472頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)106頁。
注解憲法Ⅲ95頁,100頁。
新基本法コメ(憲法)332頁。 -
民法法律に規定された登記や引渡し以外には,物権変動の対抗要件は認められない。民法結果正解解説不動産である土地の一部を構成する立木の売買において,その公示の便宜を図るために明認方法という慣習上の対抗要件が認められている。判例も,樹木の皮を削って所有者名を墨書したこと(大判大10.4.14 民法百選Ⅰ〔初版〕62事件)等を,明認方法として認めている。よって,本記述は誤りである。参考川井(2)74頁,77頁。
-
刑法甲が,同時に同一場所において,無免許で,かつ,酒に酔った状態で自動車を運転した場合,無免許運転の罪と酒酔い運転の罪が成立し,両罪は観念的競合となる。刑法結果正解解説判例は,観念的競合(刑法54条1項前段)における「1個の行為」とは,法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で,行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価を受ける場合をいうとした上で,無免許運転の罪(道路交通法64条,117条の4第2号)と酒酔い運転の罪(同65条1項,117条の2第1号)の関係につき,「社会的見解上明らかに1個の車両運転行為であって……右両罪は刑法54条1項前段の観念的競合の関係にある」としている(最大判昭49.5.29 刑法百選Ⅰ〔第7版〕103事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)407~408頁。
西田(総)418頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法削除前の刑法第200条が,尊属殺人に関し,普通殺人と区別して特別の規定を設けること自体,個人の尊厳と人格価値の平等を基本的立脚点とする民主主義の理念と抵触するものとの疑いが極めて濃厚であるから,同条は,憲法第14条第1項に違反するといわざるを得ない。憲法結果正解解説判例は,削除前の刑法200条所定の尊属殺人罪で起訴された被告人が,同条は憲法14条1項に違反すると主張した事例において,「尊属に対する尊重報恩は,社会生活上の基本的道義というべく,このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は,刑法上の保護に値する」とし,「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして,このことをその処罰に反映させても,あながち不合理であるとはいえない」としながらも,「刑法200条は,尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において,その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え,普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ,憲法14条1項に違反して無効である」としている(最大判昭48.4.4 尊属殺重罰規定判決 憲法百選Ⅰ〔第6版〕28事件)。したがって,同判決は,削除前の刑法200条の規定が,尊属殺人に関し,普通殺人と区別して特別の規定を設けること自体が憲法14条1項違反としているのではなく,刑罰の加重の程度が極端であることを理由に同項違反としている。よって,本記述は誤りである。
-
民法債務者Bと引受人Cとの間で履行引受がされた場合において,Cが履行しないときは,Bは,Cに対し,債務不履行責任を追及することができる。民法結果正解解説履行引受とは,債務者と引受人との間の契約であり,引受人が債務者に対して,債務者の債務を弁済するなどして債務者を免責させる義務を負うものをいう。そこで,この義務を引受人が履行しない場合は,債務者に対する関係で債務不履行となり,債務者は,引受人に対し,債務不履行責任を追及することができる。そして,判例も債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)を認めている(大判明40.12.24)。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)578頁,582頁。
潮見(新債権総論Ⅱ)521~522頁。 -
刑法甲は,確定判決によって刑務所に収容されている者であるが,刑務官の隙を見て刑務所内の居房から脱出したものの,刑務所の敷地外に脱出する前に刑務官に発見され拘束された。甲に単純逃走罪の既遂罪は成立しない。刑法結果正解解説逃走罪は,拘禁から離脱する行為に着手した時に実行の着手が認められ,看守者の実力支配を脱した時に既遂に達する。したがって,刑務所内の居房から脱出したことにより同罪の実行の着手が認められるとしても,刑務所内にいる限りは看守者の実力支配内にあるといえ,逃走罪は既遂に達しない。よって,本記述は正しい。
なお,甲には,単純逃走未遂罪(刑法102条,97条)が成立する。参考西田(各)475頁。
山口(総)567頁。
条解刑法303頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第41条の「立法」の解釈について,国民の権利を直接制限し,義務を課する法規範の定立と理解する見解によると,行政組織に関する事項は,国民の権利を直接制限し義務を課するものではないため,命令で定めなければならないことになる。憲法結果正解解説憲法41条の「立法」を実質的意味の立法であるとし,その内容として,国民の権利を直接制限し,義務を課する法規範の定立と理解する見解がある。この見解によれば,行政組織に関する事項は,国民の権利を直接制限し,義務を課するものではないため,当該事項については法律の規定によることを要しないということになる。しかし,それは,行政組織に関する事項を法律によって定めることが同条の要請ではないという意味であって,当該事項について命令で定めなければならないことになるわけではない。よって,本記述は誤りである。
なお,本記述の見解に立ちつつ,法治主義の原則を採用して議会による行政の民主的統制を強化している憲法の趣旨や,官吏に関する事務を掌理するために「法律の定める基準」を要求している同73条4号の趣旨などから,少なくとも行政組織の大綱が法律で定められるべきであるとする見解もある。参考芦部(憲法)295~296頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)78~82頁。
戸波(憲法)364~366頁。
法セミ468号81~83頁。 -
民法主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人が弁済をしたことにより取得する事後求償権の消滅時効は,事前求償権を行使できる場合であっても,事前求償権を行使できる時からではなく,免責行為をした時から進行する。民法結果正解解説消滅時効は,「権利を行使することができる時」から進行するところ(民法166条1項),保証人の事後求償権(同459条1項後段)の「権利を行使することができる時」とはいつなのかが問題となる。この点,判例は,事前求償権(同項前段,460条)が時効により消滅したことによって事後求償権も時効により消滅したかが争われた事例において,事後求償権は,委託を受けた保証人が免責行為をしたときに発生し,かつ,その行使が可能となるものであるから,その消滅時効は,委託を受けた保証人が弁済その他自己の出捐をもって主たる債務を消滅させるべき免責行為をした時から進行し,このことは委託を受けた保証人が事前求償権を取得した場合であっても異ならないとしている(最判昭60.2.12 昭60重判民法1事件)。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)502頁。
潮見(新債権総論Ⅱ)718頁。 -
刑法広大な湖内で,同湖の一部を区切って錦鯉を養殖している者のいけすから逃げ出した錦鯉は,遺失物等横領罪における「占有を離れた他人の物」に当たらない。刑法結果正解解説遺失物等横領罪(刑法254条)の客体は,「占有を離れた他人の物」である。判例は,占有の客体が動物である場合,逃走や散逸のおそれがない程度に事実上支配されている場合に限り占有が認められるとするが(最決昭35.9.13など),当該動物に帰巣性があれば,当該動物が所有者の物理的支配外に出た場合であっても,所有者の動物に対する占有を認めている(大判大5.5.1,最判昭32.7.16など)。鯉には帰巣の習性が認められないため,これが広大な湖内に設置されたいけすから逃げ出した場合には,所有者の占有を離脱したものになると解されている。判例も,本記述と同様の事例において,広大な湖に逃げ出した鯉は所有者の占有を離脱したものであるとしている(最決昭56.2.20 刑法百選Ⅱ〔第2版〕57事件)。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)316頁。
西田(各)270頁。
条解刑法715~716頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法道路交通法上の規定に基づく警察官の呼気検査は,飲酒運転を防止することを目的としてアルコール保有の程度を調査するものであって,運転者から供述を得ようとするものではないから,これを拒んだ者を処罰する旨の道路交通法の規定は,憲法第38条第1項に違反しない。憲法結果正解解説判例は,酒気帯び運転のおそれがあるとして,警察官から,道路交通法上の呼気検査に応じるよう要求された者が,これを拒否したため,同法上の呼気検査拒否罪に問われた事例において,呼気検査の手続が憲法38条1項の禁止する「自己に不利益な供述」の強要に当たるか否かにつき,「憲法38条1項は,刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ,右検査は,酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって,その供述を得ようとするものではないから,右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は,憲法38条1項に違反するものではない」としている(最判平9.1.30 刑訴法百選〔第10版〕A9事件)。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)346頁。
渋谷(憲法)246~247頁。 -
民法債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において,債権者が故意に甲不動産に設定された抵当権を放棄することにより,その担保を喪失したときは,甲不動産の抵当権が放棄された後に乙不動産を譲り受けた者も,債権者に対し,その担保の喪失によって償還を受けることができなくなった金額の限度において抵当不動産によって負担すべき責任が当然に消滅したことを主張できる。民法結果正解解説本記述のような場合,債務者所有の甲不動産の抵当権が放棄された後に,物上保証人所有の乙不動産が第三取得者によって取得されていることから,この第三取得者が民法504条の免責を主張できるか否かが問題となる。判例は,「債務者所有の抵当不動産(以下「甲不動産」という。)と右債務者から所有権の移転を受けた第三取得者の抵当不動産(以下「乙不動産」という。)とが共同抵当の関係にある場合において,債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又は懈怠(注:過失)によりその担保を喪失又は減少したときは,右第三取得者はもとより乙不動産のその後の譲受人も債権者に対して民法504条に規定する免責の効果を主張することができるものと解するのが相当である。すなわち,民法504条は,債権者が担保保存義務に違反した場合に法定代位権者の責任が減少することを規定するものであるところ,抵当不動産の第三取得者は,債権者に対し,同人が抵当権をもって把握した右不動産の交換価値の限度において責任を負担するものにすぎないから,債権者が故意又は懈怠(注:過失)により担保を喪失又は減少したときは,同条の規定により,右担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった金額の限度において抵当不動産によって負担すべき右責任の全部又は一部は当然に消滅するものである。そして,その後更に右不動産が第三者に譲渡された場合においても,右責任消滅の効果は影響を受けるものではない」としている(最判平3.9.3 平3重判民法4事件)。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)373~375頁。
-
刑法甲は,乙がVに対して暴行を加えて傷害を負わせた後に,その現場に出くわし,その場で乙と共謀を遂げた上でVに対して更なる暴行を加えた。甲の共謀加担後の暴行が,共謀加担前に生じていた傷害を相当程度重篤化させるものであった場合,甲には共謀加担前の傷害も含めたVの傷害全てについて傷害罪の共同正犯が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,被告人は,共謀加担前に先行者が生じさせた傷害結果については,被告人の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後に傷害を引き起こすに足りる暴行によって被害者の傷害の発生に寄与したことについてのみ傷害罪の共同正犯としての責任を負うとしている(最決平24.11.6 刑法百選Ⅰ〔第7版〕82事件)。したがって,甲には共謀加担後に生じたVの傷害についてのみ傷害罪の共同正犯(刑法204条,60条)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)369頁,371頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例は,国又は地方公共団体が,課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてではなく,一定の要件に該当する全ての者に対して課する金銭給付は,その形式いかんにかかわらず,憲法第84条に規定する「租税」に当たるとしている。憲法結果正解解説判例は,憲法84条の「租税」の意味について,「国又は地方公共団体が,課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてでなく,一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は,その形式のいかんにかかわらず,憲法84条に規定する租税に当たる」としている(最大判平18.3.1 旭川市国民健康保険条例事件 憲法百選Ⅱ〔第6版〕203事件)。同判決は,主体を国及び地方公共団体に限定した上で,公権的課徴金性と非反対給付性の観点から,同条の「租税」の範囲を定めている。よって,本記述は正しい。民法判例によれば,負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与がなされ,受贈者が契約の趣旨に従い負担を履行した場合,贈与者は,特段の事情がない限り,死因贈与を撤回することができないが,負担付遺贈がなされ,そのことを知った受遺者が遺言者の死亡前に負担の内容を任意に実現した場合,遺言者は,遺贈を撤回することができない。民法結果正解解説判例は,「死因贈与については,遺言の取消(現:撤回)に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用される」としている(最判昭47.5.25 家族法百選〔第3版〕123事件)。その理由として,同判決は,「死因贈与は贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが,かかる贈与者の死後の財産に関する処分については,遺贈と同様,贈与者の最終意思を尊重し,これによって決するのを相当とするからである」としている。ただし,無制限に死因贈与の撤回を認めてよいかが問題となるも,判例は,「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては,贈与者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから,右贈与契約締結の動機,負担の価値と贈与財産の価値との相関関係,右契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右負担の履行状況にもかかわらず負担付死因贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り,遺言の取消(現:撤回)に関する民法1022条,1023条の各規定を準用するのは相当でない」としている(最判昭57.4.30 民法百選Ⅲ〔第2版〕86事件)。したがって,前段は正しい。これに対し,遺贈は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(同985条1項)ことからすると,遺言者の死亡前に遺言を撤回しても受遺者に何ら不利益をもたらさないのが通常である。また,負担は付款であり,条件ではないため,履行の有無は遺贈の効力に関係がない。これらのことに鑑みると,負担付遺贈がなされたことを知った受遺者が,遺言者の死亡前に負担の内容を任意に実現した場合であっても,遺言者は遺贈を撤回することができる(同1022条参照)。したがって,後段は誤りである。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)279~280頁。
リーガルクエスト(親族・相続)382頁,391~392頁。
新版注釈民法(28)278~280頁。刑法自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的が併存していても,本人の利益を図ることが決定的な動機ではなかったときは,「自己若しくは第三者の利益を図る目的」が認められ得る。刑法結果正解解説背任罪は,自己又は第三者の利益を図る目的(図利目的)又は加害目的の,少なくともいずれかを必要とする目的犯である。そして,判例は,主として自己又は第三者の利益を図る目的(図利目的)があれば,従として本人の利益を図る目的があっても背任罪の成立を認めている(最判昭29.11.5等)。また,判例は,自己又は第三者の利益を図る目的(図利目的)と本人の利益を図る目的が併存している場合には,本人の利益を図ることが決定的動機でなければ,図利目的が認められ得るとしている(最決平10.11.25 刑法百選Ⅱ〔第7版〕72事件)。同決定は,特別背任罪(会社法960条1項)の成否が問題となった事例であるが,図利目的は,同罪と背任罪(刑法247条)の共通の成立要件であり,同決定における考え方は,同罪にも当てはまるとされる。したがって,自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的が併存する場合,本人の利益を図る目的が決定的な動機ではなかったときは,「自己若しくは第三者の利益を図……る目的」が認められ得る。よって,本記述は正しい。参考リーガルクエスト(刑法各論)252~255頁。
山口(各)326~328頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第3章の人権規定は,法人についても性質上可能な限り適用されるが,信教の自由や学問の自由は,自然人である個人の精神的活動の自由であるから,法人には適用されない。憲法結果正解解説憲法第3章の人権規定は,法人についても性質上可能な限り適用される(最大判昭45.6.24 八幡製鉄事件 憲法百選Ⅰ〔第6版〕9事件等参照)。つまり,自然人に固有なものは法人には保障されないが,その他の人権規定は,法人固有の性格と矛盾しない範囲内で適用される。精神的活動の自由については,争いがあるが,宗教法人には信教の自由(同20条)が,学校法人には学問の自由(同23条)が保障されると考えられている。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)89~90頁。
佐藤幸(日本国憲法論)151~153頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)233~235頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅱ)31~33頁。 -
民法Aがその占有する時計をBに売却した場合において,占有改定により当該時計の占有をAがBに引き渡したとしても,Bは,即時取得により当該時計の所有権を取得することはできない。民法結果正解解説即時取得による所有権取得が認められるためには,動産の占有を開始したことが必要であるが(民法192条),その占有の取得方法について,判例は,「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し,かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもっては足らない」としている(最判昭35.2.11 民法百選Ⅰ〔第8版〕68事件)。したがって,占有改定による引渡し(同183条)がされているにすぎない本記述においては,Bは,即時取得により時計の所有権を取得することができない。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)146~152頁。
内田Ⅰ474~477頁。 -
刑法弁護士資格のない甲は,自己の氏名が乙弁護士会所属の丙弁護士と同姓同名であることを利用して,丙弁護士に成り済まし,甲を弁護士と信じていた者から弁護士報酬を請求する目的で,弁護士の肩書を付した丙の名義で弁護士報酬金請求に係る文書を作成した。この場合,甲には有印私文書偽造罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「私文書偽造の本質は,文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解されるところ……たとえ名義人として表示された者の氏名が被告人の氏名と同一であったとしても,本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式,内容のものである以上,本件各文書に表示された名義人は,乙弁護士会に所属する弁護士丙であって,弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかであるから,本件各文書の名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである」として,有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立するとしている(最決平5.10.5 刑法百選Ⅱ〔第7版〕94事件)。したがって,甲には有印私文書偽造罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(各)470~471頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法集会は,国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成,発展させ,また,相互に意見や情報等を伝達,交流する場として必要であり,さらに,対外的に意見を表明するための有効な手段であるから,憲法第21条第1項の保障する集会の自由は,民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない。憲法結果正解解説判例は,多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供される工作物の使用を禁止することができる旨定める特別立法(いわゆる成田新法)の合憲性が問題となった事例において,「現代民主主義社会においては,集会は,国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成,発展させ,また,相互に意見や情報等を伝達,交流する場として必要であり,さらに,対外的に意見を表明するための有効な手段であるから,憲法21条1項の保障する集会の自由は,民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない」としている(最大判平4.7.1 成田新法事件 憲法百選Ⅱ[第6版]115事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法根抵当権は,不特定の債権を担保するために成立するため,根抵当権設定時に被担保債権が成立している必要はないが,抵当権は,被担保債権なしに成立し得ないため,抵当権設定の時点で被担保債権が成立している必要がある。民法結果正解解説根抵当権は,不特定の債権を担保するために設定されるため(民法398条の2第1項),被担保債権との関係で,成立・存続・消滅における付従性がなく,根抵当権設定時に被担保債権が成立している必要はない。したがって、前段は正しい。他方,抵当権は成立において付従性の原則が妥当するため,被担保債権なくしては成立しない。もっとも,将来の債権や条件付債権についても,債権発生の基礎となる具体的な法律関係が存在する限り,被担保債権とすることができる。したがって,後段は誤りである。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ131頁,240頁。
内田Ⅲ393頁,477~478頁。
我妻・有泉コメ636頁。 -
刑法身の代金を得る目的で銀行の代表取締役を略取した者が,同代表取締役の近親者ではない同銀行の幹部に対して身の代金を要求した場合,同幹部が同代表取締役の安否を気遣っていたとしても,身の代金目的略取罪及び拐取者身の代金要求罪は成立し得ない。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,刑法225条の2における「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」には,「単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが,被拐取者の近親でなくとも,被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる」とした上で,「相互銀行の代表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは,被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者に当たる」としている(最決昭62.3.24 刑法百選Ⅱ[第7版]13事件)。したがって,本記述においても,身の代金目的略取罪及び拐取者身の代金要求罪は成立し得る。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)97~98頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法議院の自律権を確保するためには財政的基盤が必要であり,憲法は,両議院の経費は,独立して,国の予算に計上しなければならない旨規定している。憲法結果正解解説衆参両議院は,相互に独立して審議議決を行う機関であり,その前提として,他の機関や院の干渉を排除して行動できる自律権がある。この議院の自律権は,①自主組織権,②自律的運営権,③財政自律権の三つに大別できるところ,①自主組織権及び②自律的運営権については憲法上の規定が存在するものの(同58条1項、2項),③財政自律権については国会法に規定が存在するのみで(同32条),憲法は特に規定していない。よって,本記述は誤りである。参考佐藤幸(日本国憲法論)465頁。
-
民法債権者は,自己の債権を保全するため,その債務者に属する代位権につき債権者代位権を行使することができる。民法結果正解解説判例は,債権者が,債務者に代位してその債務者に属する代位権を行使することを認めている(大判昭5.7.14,最判昭39.4.17)。その理由として,両判決とも,民法上,同423条1項ただし書が,一身専属権について代位行使を禁じているほかは,代位の目的となる権利について何ら限定していないことを挙げている。よって,本記述は正しい。参考中田(債総)211頁。
昭39最高裁解説(民事)99~100頁。 -
刑法甲は,乙に恨みを抱き,乙が居住する家屋に放火して全焼させたが,放火した時点において,乙はたまたま外出中で同家屋内にいなかった。この場合,甲には現住建造物等放火罪(刑法第108条)が成立する。刑法結果正解解説判例は,刑法108条にいう「現に人が住居に使用」すること,すなわち現住性について,現に人の起臥寝食の場所として日常利用されていることをいい,必ずしも昼夜間断なく使用している必要はなく(大判大2.12.24),居住者がたまたま外出して一時その建物にいない場合でもよいと解している。したがって,本記述において,乙は,放火の時点でたまたま外出して家屋内にいなかったにすぎないから,当該家屋については現住性が認められ,当該家屋に火を放ち焼損させた甲には現住建造物等放火罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(各)318頁。
平9最高裁解説(刑事)217頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例は,条例は,住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的立法であり,実質的には法律に準じるものであるから,法律の授権がなくても条例に罰則を定めることができるとしている。憲法結果正解解説判例は,条例による罰則制定の可否が争われた事例において,「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく,法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで,このことは憲法73条6号但書によっても明らかである」としている。もっとも,法律の授権が不特定な白紙委任的なものであってはならないとした上で,「条例は・・・・・・公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にし,むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから,条例によって刑罰を定める場合には,法律の授権が相当な程度に具体的であり,限定されておればたりる」としている(最大判昭37.5.30 憲法百選Ⅱ[第6版]215事件)。したがって,同判決は,条例に罰則を定める場合には,法律による授権が必要であるという前提に立っている。よって,本記述は誤りである。
-
民法Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し,Aから甲土地を譲り受けたCは,AからCへの所有権移転登記をしなければ,甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することができない。民法結果正解解説判例は,民法177条の「第三者」の意義について,当事者又はその包括承継人以外の者で,不動産に関する物権の得喪及び変更の登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいうとしている(大連判明41.12.15 不動産取引百選[第3版]46事件)。そして,判例は,「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず,これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得る」としている(最判昭25.12.19 民法百選Ⅰ[第8版]62事件)。本記述において,Bは,Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているのであるから,不法占有者である。したがって,Cは,Bに対し,登記なくして乙建物の収去を請求することができる。よって,本記述は誤りである。参考川井(2)33頁。
-
刑法他人の助力を得て中止行為を行った場合には,中止犯が成立することはない。刑法結果正解解説判例は,中止犯(刑法43条ただし書)の成立には,行為者自らが結果発生を防止するか,又は,自ら防止したと同視するに足りる程度の努力を要求している(大判昭12.6.25)。したがって,行為者が他人の助力を得て中止行為を行ったとしても,自らが結果発生を防止するための積極的な努力をしていた場合には,中止犯の成立が認められる余地がある。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)299~300頁。
条解刑法181~182頁,348頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法判例は,憲法第9条第2項により保持が禁止される戦力とは,我が国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力を指し,外国の軍隊は,我が国に駐留するものであっても,ここにいう戦力には該当しないとしている。憲法結果正解解説判例は,正当な理由がなく米軍基地に侵入した者が,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法(以下「刑特法」という。)2条違反で起訴された事例において,アメリカ合衆国軍隊の駐留は,憲法9条2項前段の戦力を保持しない旨の規定に違反しており,刑特法2条は,憲法31条に違反して無効となるのではないかが問題となったところ,憲法9条2項「において戦力の不保持を規定したのは,わが国がいわゆる戦力を保持し,自らその主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためである・・・・・・。従って・・・・・・同条項がその保持を禁止した戦力とは,わが国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力をいうものであり,結局わが国自体の戦力を指し,外国の軍隊は,たとえそれがわが国に駐留するとしても,ここにいう戦力には該当しない」としている(最大判昭34.12.16 砂川事件 憲法百選Ⅱ[第6版]169事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法判例によれば,建物所有を目的とする土地の賃借人が,土地上に建物を建築したが,その建物について自らの意思で,土地の賃借人の家族名義で所有権保存登記をした場合であっても,土地の賃借人は,その後にその土地を取得した者に対して,借地権を対抗することができる。民法結果正解解説建物所有目的の借地権については,その土地につき登記がなくても,その土地上の建物につき保存登記がされていれば,第三者に対して対抗することができる(借地借家法10条1項)。もっとも,判例は,建物所有目的の土地の賃借人が,借地上に所有する建物につき,同居している長男の名義で所有権保存登記をした事例において,「地上建物を所有する賃借人が,自らの意思に基づき,他人名義で建物の保存登記をしたような場合には,当該賃借権者はその賃借権を第三者に対抗することはできない」としている(最大判昭41.4.27 民法百選Ⅱ[第8版]58事件)。その理由として,同判決は,他人名義の建物の登記によっては,自己の建物の所有権でさえ第三者に対抗できないものであり,建物につき自己名義の登記があることを前提として土地の賃借権の登記に代えようとした同項の法意に照らして,本記述のような場合は保護に値しないことを挙げている。したがって,借地上の建物について,自己名義ではなく家族名義の登記になっている以上,同項の適用はなく,土地の賃借人は,その後にその土地を取得した者に対して,借地権を対抗することができない。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)482頁。
内田Ⅱ231~232頁。
川井(4)236頁。 -
刑法甲は,わいせつな画像を不特定多数人にファクシミリで送信して,紙媒体で閲覧できる状態にした。この場合,甲にはわいせつ物頒布罪が成立する。刑法結果正解解説刑法175条における「電磁的記録」とは,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう(同7条の2)。そして,平成23年刑法改正において,ファクシミリでわいせつな画像等を送信する場合,頒布先においてそれが電磁的記録以外の形態による記録として存在するに至ることがあり得ることから,同175条1項後段の客体として,「その他の記録」を規定することとされた。また,「電子的記録」「その他の記録」の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう(最決平26.11.25 平27重判刑法7事件)。したがって,わいせつな画像を不特定多数人にファクシミリで送信して,紙媒体で閲覧できる状態にした甲の行為は,「その他の記録」の「頒布」に当たり,甲には,わいせつ物頒布罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考新基本法コメ(刑法)384頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法内閣は,憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから,たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても,その法律を執行しなければならない。憲法結果正解解説憲法第73条第1号は,内閣が「法律を誠実に執行」する旨定めている。「誠実に執行」とは,たとえ内閣の賛成できない法律であっても,法律の目的にかなった執行を行うことを義務付ける趣旨である。つまり,法律が違憲かどうかについては,国会の判断が内閣のそれに優先し,国会で合憲であるものとして制定した以上,内閣はその判断に拘束されるということである。したがって,内閣は,自らが違憲と判断する法律であっても,その法律を執行しなければならない。よって,本記述は正しい。
なお,最高裁判所が法律を違憲と判断した場合には,内閣はその法律の執行を停止することができると解されている。参考佐藤幸(日本国憲法論)497~498頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)205頁。 -
民法甲債権についてAがBのために質権を設定した場合,Aは,甲債権を自働債権,乙債権を受働債権として相殺することはできない。民法結果正解解説判例は,「債権が質権の目的とされた場合において,質権設定者は,質権者に対し,当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い,債権の放棄,免除,相殺,更改等当該債権を消滅,変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行うことは,同義務に違反するものとして許されない」としている(最判平18.12.21 民法百選Ⅰ[第8版]83事件)。これは,質権の設定は,設定者に対して質権の目的物の価値を減損する行為を禁じる効力を持つものなので,自働債権に質権が設定されると,自働債権が差し押さえられたのと同様に債権の処分の一種である相殺が禁止されるからである。したがって,甲債権にAがBのために質権を設定した場合,Aは,甲債権を自働債権,乙債権を受働債権として相殺することはできない。よって,本記述は正しい。参考道垣内Ⅲ116頁。
我妻・有泉コメ1002頁。 -
刑法名誉毀損罪が成立するためには,公然と事実の摘示が行われる必要があり,特定かつ少数人に事実を摘示した場合には,その者らを通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があったとしても,公然と事実の摘示が行われたとはいえない。刑法結果正解解説名誉毀損罪は,人の社会的評価を低下させる具体的な事実を公然と摘示することによって成立する。そして,「公然」とは,不特定又は多数人が認識できる状態をいうと解される(大判昭3.12.13,最判昭36.10.13 続刑法百選29事件等)。また,判例は,摘示の相手方が特定少数人であっても,伝播して間接的に不特定又は多数人が認識できるようになる場合には,公然性が認められるとしている(最判昭34.5.7 刑法百選[第7版]19事件)。したがって,特定かつ少数人に事実を摘示した場合でも,その者らを通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があったならば,公然と事実の摘示が行われたといえる。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法675頁。
山口(各)136~137頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法有罪判決を受けた刑事被告人に対し,裁判所に出廷させた証人の旅費,日当及び宿泊料を負担させることは,「刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反する。憲法結果正解解説判例は,憲法37条2項の法意と被告人の訴訟費用の負担が問題となった事例において,同項の「公費で自己のために,証人を求める権利を有するという意義は,刑事被告人は,裁判所に対して証人の喚問を請求するには,何等財産上の出損を必要としない,証人訊問に要する費用,すなわち,証人の旅費,日当等は,すべて国家がこれを支給するのであって,訴訟進行の過程において,被告人にこれを支弁せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために,充分に証人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であって,もっぱら刑事被告人をして,訴訟上の防禦権を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら,それは,要するに,被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において,その防禦権を充分に行使せしめんとするのであって,その被告人が,判決において有罪の言渡を受けた場合にも,なおかつその被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない」としている(最大判昭23.12.27)。したがって,有罪判決を受けた刑事被告人に対し,裁判所に出廷させた証人の旅費,日当及び宿泊料を負担させることは,同項に違反しない。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)251頁。
佐藤幸(日本国憲法論)344頁。
新基本法コメ(憲法)281頁。 -
民法代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権は,代位弁済者の債務者に対する求償権である。民法結果正解解説判例は,「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために,法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり,したがって,代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権として扱うべきものは,原債権であって,保証人の債務者に対する求償権でないことはいうまでもない。」としている(最判昭59.5.29 民法百選Ⅱ[第8版]36事件)。よって,本記述は誤りである。参考中田(債総)357~358頁。
-
刑法法律に規定のない事項に対し,これと類似の性質を有する事項に関する法規を適用して処罰することは許されない。刑法結果正解解説罪刑法定主義は,罰則を適用する場合,解釈により罰則において処罰の対象とされていると解される行為のみを処罰することを許容し,法律に規定のない事項に対し,これと類似の性質を有する事項に関する法規を適用して処罰することは許されない。(類推解釈の禁止 最判昭30.3.1 刑法百選[初版]2事件)。よって,本記述は正しい。
なお,罪刑法定主義は被告人の人権保護のための原則であることから,被告人に有利な類推解釈を行うことは許される。参考山口(総)13~14頁。
基本刑法Ⅰ21~23頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法酒類販売業の免許制は,酒類販売店の濫設に伴う酒類販売店相互間の過当競争によって招来されるであろう酒類販売店の共倒れから酒類販売店を保護するという積極目的に基づく規制である。憲法結果正解解説判例は,酒税法の定める酒類販売免許制度が憲法22条1項の定める職業選択の自由に違反するかが争われた事例において,「租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については,その必要性と合理性についての立法府の判断が,右の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するもので,著しく不合理なものでない限り,これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない」としている(最判平4.12.15 憲法百選Ⅰ[第6版]99事件)。したがって,同判決は,租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的を設定しているのであって,酒類販売店の共倒れから酒類販売店を保護するという積極目的を認定しているのではない。よって,本記述は誤りである。
-
民法請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,請負人が既に仕事の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,未完成部分に限り,契約を解除することができる。民法結果正解解説請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。したがって,前段は正しい。もっとも,判例は,「建物その他土地の工作物の工事請負契約につき,工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に右契約を解除する場合において,工事内容が可分であり,しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは,特段の事情のない限り,既施工部分については契約を解除することができず,ただ未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない」としている(最判昭56.2.17 不動産取引百選[第2版]107事件)。したがって,後段も正しい。よって,本記述は正しい。参考中田(契約)226頁。
内田Ⅱ274頁。
川井(4)300~301頁。 -
刑法殺人をするつもりでナイフを用意した者が,殺人の実行に着手する前に,後悔の念に駆られて翻意した場合,中止犯が成立する。刑法結果正解解説殺人をするつもりでナイフを用意した行為について,殺人予備罪(刑法201条)が成立するところ,判例は,「予備罪には中止未遂の観念を容れる余地」がないとして,予備罪について中止犯の規定の準用又は類推適用を認めない立場に立っている(最大判昭29.1.20 刑法百選Ⅰ[第7版]72事件)。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)303~304頁。
大塚(総)264頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法集会の用に供される公共施設において,当該公共施設の管理者が,主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に当該公共施設の利用を拒むことができるのは,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。憲法結果正解解説判例は,死亡した労働組合連合体の幹部について,合同葬を行うために,当該組合連合体が市の福祉会館(以下「本件会館」という。)の使用許可申請をしたところ,内ゲバ殺人である可能性がある旨の報道に照らして,当該組合連合体と対立する者らの妨害による混乱のおそれがあることなどを理由に不許可処分となったことから,当該組合連合体が市に対して国家賠償請求訴訟を提起した事例において,地方自治法「244条に定める普通地方公共団体の公の施設として,本件会館のような集会の用に供する施設が設けられている場合,住民等は,その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので,管理者が正当な理由もないのにその利用を拒否するときは,憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれがある」とした上で,「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,……公の施設の利用関係の性質に照らせば,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」としている(最判平8.3.15 上尾市福祉会館事件 地方自治百選[第4版]57事件,平8重判憲法6事件)。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)288頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)368頁。 -
民法元本確定後の根抵当権について,根抵当権者が利息や遅延損害金を請求する権利を有する場合,根抵当権者は最後の2年分についてのみ,その根抵当権の行使により,優先弁済を受けることができる。民法結果正解解説抵当権によって担保される被担保債権の範囲について,民法375条は,「利息その他の定期金」は満期となった最後の2年分(同条1項本文),遅延損害金についても最後の2年分(同条2項本文)に限定している。この趣旨は,後順位抵当権者や他の一般債権者の予測可能性を確保するというものである。根抵当権においても同様に,第三者の予測可能性の確保という趣旨は妥当するが,根抵当権においては極度額(同398条の2第1項,398条の3第1項)により被担保債権の範囲が定まるため,同375条1項の適用はない。よって,本記述は誤りである。参考道垣内Ⅲ162~163頁,243~244頁。
内田Ⅲ393頁,478頁。
我妻・有泉コメ647~648頁。 -
刑法責任能力の有無を判断する前提となる生物学的要素及びこれが心理学的要素に与えた影響について,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重すべきである。刑法結果正解解説判例は,「生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである」としている(最判平20.4.25 平20重判刑法4事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)273頁。
条解刑法152頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は,議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる趣旨のものであるから,各議院の下した議院資格に関する判断について,更に裁判所で争うことは認められていない。憲法結果正解解説憲法55条本文は,「両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。」として,資格争訟裁判について規定している。そして,同条は資格争訟裁判における議員の資格の有無の判断を専ら各議院の自律的な審査に委ねる趣旨としたものであり,かかる裁判は「日本国憲法に特別の定のある場合」に当たるため,裁判所は裁判をする権限を有しない(裁判所法3条1項)。したがって,各議院の下した議員資格に関する判断については,更に裁判所で争うことはできない。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)315~316頁。
佐藤幸(日本国憲法論)460~461頁。 -
民法判例によれば,特別の約定のない建物の賃貸借契約において,賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,同時履行の関係に立たないが,賃借人は,賃貸人に対し敷金返還請求権をもって建物につき留置権の成立を主張することができる。民法結果正解解説判例は,期間満了による建物の賃貸借終了に基づく建物明渡請求訴訟の事例において,特別の約定のない限り,建物の賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務が先履行であり,賃貸人の敷金返還債務とは同時履行の関係に立たないとしている(最判昭49.9.2 民法百選Ⅱ[第8版]65事件)。その理由として,同判決は,「敷金は,賃貸借の終了後家屋明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものであり,賃貸人は,賃貸借の終了後家屋の明渡がされた時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除してなお残額がある場合に,その残額につき返還義務を負担するもの」であること,「敷金契約は,……賃貸人が賃借人に対して取得することのある債権を担保するために締結されるものであって,賃貸借契約に附随するものではあるが,賃貸借契約そのものではないから,賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡義務と賃貸人の敷金返還債務とは,一個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものとすることはできず,また,両債務の間には著しい価値の差が存しうることからしても,両債務を相対立させてその間に同時履行の関係を認めることは,必ずしも公平の原則に合致するものとはいいがたい」ことなどを挙げる。したがって,前段は正しい。また,同判決は,「賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合にあっては,賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない」としている。したがって,後段は誤りである。よって,本記述は誤りである。参考中田(契約)156頁,412~414頁。
安永(物権・担物)456頁。 -
刑法甲は,乙の財布を自己のものとする目的で,乙に対し,社会通念上一般に相手方の犯行を抑圧するに足りない程度の暴行を加えたところ,乙が極度の小心者であったためにその反抗を抑圧されたことから,乙の反抗抑圧状態に乗じて同人から財布を奪った。この場合,甲には強盗罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,強盗罪と恐喝罪(刑法249条1項)の区別について,暴行又は脅迫が,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかという客観的基準によって決せられるのであって,具体的事案の被害者の主観を基準として,その被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかによって決せられるものではないとした上で,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫が加えられた場合において,強盗罪の成立を認めている(最判昭24.2.8)。したがって,本記述では,甲は,乙に対し,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行を加えたにすぎないから,当該暴行により乙がその反抗を抑圧されたとしても,甲には,強盗罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)217頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法政党が党員に対して行う処分は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる場合であっても,政党自身によってあらかじめ自律的に定められた規範にのっとって行われなければならないから,裁判所は,その限度でこれを司法審査の対象とすることができる。憲法結果正解解説判例は,政党の行った党員に対する除名処分に対して司法審査が及ぶかどうかが問題となった事例において,「政党に対しては,高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」とした上で,「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審判権は及ばないというべきであり,他方,右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても,右処分の当否は,当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし,右規範を有しないときは条理に基づき,適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり,その審理も右の点に限られる」としている(最判昭63.12.20 共産党除名処分事件 憲法百選Ⅱ[第6版]189事件)。したがって,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所は審査することができない。よって,本記述は誤りである。
-
民法動産の占有者がその占有を取得するに当たり,前主が無権利者であることを知らなかったが,権利者であることを疑っていた場合には,即時取得は認められない。民法結果正解解説判例は,民法192条にいう「善意」とは,「動産の占有を始めた者において,取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し」たことをいうとしている(最判昭26.11.27 売買(動産)百選46事件)。同判決の趣旨に照らせば,即時取得における悪意とは,前主が権利者であることを信じていなかったことをいうことになるから,無権利者であることを知っていた場合だけでなく,前主が権利者であることを疑っていた場合も悪意と扱われることになる。したがって,前主が権利者であることを疑っていた場合は,即時取得は認められない。よって,本記述は正しい。参考佐久間(物権)152頁。
類型別115~116頁。
問題研究140頁。 -
刑法市立病院の医師甲は,乙に頼まれ,乙が市役所に提出する診断書に虚偽の記載をした。この場合,甲には虚偽診断書作成罪が成立する。刑法結果正解解説虚偽診断書作成罪(刑法160条)は,私文書の無形偽造を例外的に処罰する規定であり,医師が主体となった場合に限り成立する身分犯である。もっとも,公務員たる医師がその資格に基づいて虚偽の診断書等を作成した場合には,虚偽公文書作成罪(同156条)として重く処罰されることになると解されている(最判昭23.10.23 刑法百選Ⅰ[初版]53事件)。したがって,甲は市立病院の医師であって公務員であるから,甲には虚偽公文書作成罪が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)471頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法両議院の会議及び両院協議会は公開が原則であるが,いずれも出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会とすることができる。憲法結果正解解説憲法57条1項は,「両議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。」と規定している。したがって,両議院の会議(本会議)は公開が原則であり,秘密会とするためには,出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要である。他方,両院協議会とは,両院の議決が異なる場合に,両院間の妥協を図るために設けられる協議機関であるところ,両院協議会はその性質上一切の傍聴が許されず(国会法97条),当然に秘密会となる。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)312頁。
佐藤幸(日本国憲法論)451頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)134~135頁。 -
民法土地の売買契約において,買主への所有権移転登記がされている場合,売主からの代金支払請求に対して,買主は,土地の引渡しとの同時履行を主張することはできない。民法結果正解解説判例は,不動産の売買において,所有権移転登記がされた場合,買主は,所有権の取得を第三者に対抗することができ,引渡しを受ける前であっても当該不動産を第三者に処分し得ることを理由として,特別の事情又は特約のない限り,買主は,所有権移転登記と同時に代金を支払わなければならず,売主が目的物を引き渡さないことを理由として代金の支払を拒むことはできないとしている(大判大7.8.14 不動産取引百選[第3版]22事件)。よって,本記述は正しい。参考川井(4)28頁。
-
刑法正当防衛に当たる暴行を加えた者が,当該暴行により相手方が更なる侵害行為に出る可能性がなくなったにもかかわらず,そのことを認識した上で,専ら攻撃の意思で新たな暴行に及んだ場合,両暴行が時間的・場所的に連続していたとしても,これらを全体的に考察して1個の過剰防衛の成立を認めることはできない。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,正当防衛に当たる暴行により転倒した相手方が,「被告人に対し更なる侵害行為に出る可能性はな」く,「被告人は,そのことを認識した上で,専ら攻撃の意思に基づいて」新たな暴行に及んでいるのであるから,新たな暴行が「正当防衛の要件を満たさないことは明らかである」とした上で,「両暴行は,時間的,場所的には連続しているものの,……その間には断絶があるというべきであって,急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに,その反撃が量的に過剰になったものとは認められない。そうすると,両暴行を全体的に考察して,1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当でな」いとしている(最決平20.6.25 刑法百選Ⅰ[第7版]27事件)。よって,本記述は正しい。参考西田(総)179~181頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法通信に関する情報は,通信の内容と,受発信者の住所,氏名,送信日時などの通信の存在自体に関する事実に分類されるところ,憲法第21条第2項後段の主要な目的が私生活の秘密の保護にあるとする見解によれば,前者のみならず後者の情報も,通信の秘密の保障を受ける。憲法結果正解解説通信の秘密の保障の主要な目的が私生活の秘密ないしプライバシーの保護にあると考える見解からは,通信の秘密の保障は,通信の内容だけではなく,受発信者の住所,氏名,送信日時など,通信の存在自体に関する事実にも及ぶものとされている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)221頁。
佐藤幸(日本国憲法論)320~321頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)397頁。
注解憲法Ⅱ85~86頁。 -
民法判例によれば,土地に設定された抵当権の効力は,土地上に抵当権設定当時から存在し,土地所有者が所有する石灯籠や取り外しのできる庭石には及ばない。民法結果正解解説判例は,抵当権設定当時から宅地の上に存在する石灯籠及び取り外しのできる庭石は宅地の従物であり,宅地の抵当権の効力は,抵当権設定当時に存在した従物に及ぶとしている(最判昭44.3.28 民法百選Ⅰ[第7版]82事件)。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ396頁。
-
刑法甲と乙は,Vに対する傷害を加えることを共謀した上,共同して,Vに対し手拳で殴打するなどの暴行を加えていたところ,Vの言動に激高した乙は,隠し持っていたナイフで,殺意をもってVの下腹部を突き刺し,Vを即死させた。この場合、甲には,殺人罪の共同正犯が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「殺人罪と傷害致死罪とは,殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで,その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから」殺意のなかった共犯者については,殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するとしている(最決昭54.4.13 刑法百選Ⅰ[第7版]90事件)。したがって,甲には,殺人罪の共同正犯は成立せず,傷害致死罪の共同正犯(刑法205条,60条)が成立するにとどまる。よって,本記述は誤りである。参考山口(総)364頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,教科書検定は,検定基準の各条件に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎず,憲法第23条に違反しない。憲法結果正解解説判例は,高校用日本史教科書を執筆したが,文部大臣(現:文部科学大臣)により検定不合格処分及び条件付検定合格処分を受けた者が,教科書検定の合憲性等を争った事例において,教科書検定制度が憲法23条に違反するとの主張について,「教科書は,教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,普通教育の場において使用される児童,生徒用の図書であって……学術研究の結果の発表を目的とするものではなく,本件検定は,申請図書に記述された研究結果が,たとい執筆者が正当と信ずるものであったとしても……旧検定基準(注:昭和33年文部省告示86号)の各条件に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない」とし,教科書検定は同条に反しないとしている(最判平5.3.16 第1次家永教科書事件上告審 憲法百選Ⅰ[第6版]93事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法不動産質権の存続期間は最長10年であり,設定行為によってもこれより長い期間を定めることはできない。民法結果正解解説民法360条1項に規定されている。これは,不動産質権者は,目的不動産を使用収益することができるとされているところ(同356条),不動産の用益権を長く所有者以外の者に委ねることは,不動産の効用を全うすることにならないと考えられたことによる。よって,本記述は正しい。参考川井(2)296頁。
我妻・有泉コメ565頁。
基本法コメ(物権)229~230頁。 -
刑法甲は,乙宅において乙に覚せい剤を注射し,それによって錯乱状態に陥った乙を乙宅に放置して立ち去ったところ,乙は数時間後に急性心不全のために死亡した。この場合,甲が乙が錯乱状態に陥った時点で直ちに救急医療を要請していれば,十中八九乙の救命が可能であったときは,甲には保護責任者遺棄致死罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,被害者が錯乱状態に陥った時点で「直ちに被告人が救急医療を要請していれば,……十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると,同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから,被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と……同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には,刑法上の因果関係がある」としている(最決平元.12.15 刑法百選Ⅰ[第7版]4事件)。したがって,甲には保護責任者遺棄致死罪(刑法219条,218条)が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(総)117頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法皇室が私有財産を持つことは禁止されていないから,皇室が皇室外から財産を譲り受ける場合,国会の議会を経る必要はない。憲法結果正解解説憲法88条前段は,「すべて皇室財産は,国に属する。」と規定しているが,同条の趣旨は皇室財政の自律を廃して民主化を図る点にあるから,皇室が私有財産を持つことまで禁止されているわけではない。もっとも,戦前のように皇室に巨大な財産が集中し,あるいは皇室と特定の者との不健全な結び付きが生じることを防止するため,同8条は,皇室の財産授受について国会の議決に基づかなければならないと定めており,民主的コントロールを及ぼすこととしている。したがって,皇室が皇室外から財産を譲り受ける場合,国会の議決が必要である。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)52~53頁。
佐藤幸(日本国憲法論)523~524頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)143~145頁。 -
民法判例によれば,外国の通貨で債権額を指定した場合,債権者は,債務者に対し,日本の通貨によって請求することができない。民法結果正解解説判例は,「外国の通貨をもって債権額が指定された金銭債権は,いわゆる任意債権であり,債権者は,債務者に対し,外国の通貨又は日本の通貨のいずれによって請求することもできるのであり,民法403条は,債権者が外国の通貨によって請求した場合に債務者が日本の通貨によって弁済することができることを定めるにすぎない」としている(最判昭50.7.15 国際私法百選[第2版]49事件)。したがって,債権者は,債務者に対し,日本の通貨によって請求することができる。よって,本記述は誤りである。参考川井(3)27頁。
-
刑法公文書が作成権限に基づいて作成されている限り,正規の手続によらなかったことを理由としては,公文書偽造罪は成立しない。刑法結果正解解説判例は,「公文書偽造罪における偽造とは,公文書の作成名義人以外の者が,権限なしに,その名義を用いて公文書を作成することを意味する」とした上で,市役所職員であった被告人が所定の申請書を提出せず,手数料も納付せずに自ら印鑑証明書を作成したという事例において,「被告人は,作成権限に基づいて……5通の印鑑証明書を作成したものというべきであるから,正規の手続によらないで作成した点において権限の濫用があるとしても,……公文書偽造罪をもって問擬されるべきではない」としている(最判昭51.5.6 刑法百選Ⅱ[第7版]90事件)。よって,本記述は正しい。参考条解刑法434頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法地方議会の議員に対する出席停止処分は,当該議員の議決権,発言権等の権利行使が奪われるのみならず,その名誉,信用などの人格的利益に関わる重大事項であるから,もはや議会の内部規律に基づく自治的措置に任せるべき問題とはいえず,当該処分の有効性については,裁判所による司法審査が及ぶ。憲法結果正解解説判例は,村議会議員が3日間の議会出席停止の懲罰決議を受けたのに対して,その無効の確認及び取消しを求めた事例において,「自律的な法規範をもつ社会ないし団体に在っては,当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ,必ずしも,裁判にまつを適当としないものがある」とした上で,除名処分については,過去の判例(最大判昭35.3.9)を引用し,「議員の除名処分の如きは,議員の身分の喪失に関する重大事項で,単なる内部規律の問題に止まらない」として,司法審査が及ぶとしたが,これに対して,出席停止処分については,「議員の権利行使の一時的制限に過ぎないもの」であるとして,議員の出席停止処分は,まさに議会の内部規律の問題として,自治的措置に任せるべきであるので,司法審査が及ばないものとしている(最大判昭35.10.19 憲法百選Ⅱ[第6版]187事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法居住用建物の賃借人が死亡した場合において,賃借人に相続人がいないときは,その賃借人と当該居住用建物に同居していた内縁の配偶者は,法定の期間内に当該居住用建物の賃貸人に反対の意思を表示したときを除き,賃借人から借家権を承継し,これを自己の居住権として主張することができる。民法結果正解解説居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において,賃借人と事実上の夫婦関係にあった同居者は,相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときを除き,建物の賃借人の権利義務を承継する(借地借家法36条1項)。そして,借家権を承継した同居者は,これを自己の居住権として主張することができる。よって,本記述は正しい。
なお,死亡した賃借人に相続人がいる場合には,当該相続人が賃借権を相続することになるが,判例は,賃借人と同居していた内縁の妻は,相続人の有する賃借権を援用できるとしている(最判昭42.2.21 民報百選Ⅱ[第5版新法対応補正版]65事件)。参考川井(4)272頁。 -
刑法甲は,乙を殺害した直後,乙が高価な腕時計を身に付けているのに気付き,売却して利益を得ようと考え,これを奪った。この場合,甲に乙の腕時計を奪取する意思が生じたのは乙の死亡後であり,死者である乙に占有を観念できない以上,甲には窃盗罪は成立しない。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると,被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して,他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから,右奪取行為は,占有離脱物横領ではなく,窃盗罪を構成する」としている(最判昭41.4.8 刑法百選Ⅱ[第7版]29事件)。したがって,甲には窃盗罪(刑法235条)が成立する。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)183頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,内閣総理大臣は,閣議にかけて決定された方針がない以上,内閣の明示の意思に反しないとしても,行政各部に対し指導,助言等の指示を与える権限を有しない。憲法結果正解解説判例は,内閣総理大臣が当時の運輸大臣(現:国土交通大臣)に対して航空会社に特定の航空機の選定購入を勧奨するよう働きかけた行為が内閣総理大臣の職務権限に属するか争われた事例において,「内閣総理大臣は,憲法上,行政権を行使する内閣の首長として(66条),国務大臣の任免権(68条),内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど,内閣を統率し,行政各部を統轄調整する地位にあるものである。そして,内閣法は,閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条),内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条),行政各部の処分または命令を中止させることができるものとしている(8条)。このように,内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには,閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと,流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため,内閣総理大臣は,少なくとも,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有する」としている(最大判平7.2.22 ロッキード事件丸紅ルート 憲法百選Ⅱ[第6版]180事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例によれば,借地上の建物を所有する土地の賃借人が,自らの意思に基づき,当該建物において賃借人と同居する家族の名義で建物の保存登記をした場合,土地賃借権の第三者に対する対抗力を認めることができる。民法結果正解解説借地権は,その登記がなくても,土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは,これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。もっとも,判例は,同項による土地賃借権の対抗要件について,「地上建物を所有する賃借権者が,自らの意思に基づき,他人名義で建物の保存登記したような場合には,当該賃借権者はその賃借権を第三者に対抗することはできない」としている(最大判昭41.4.27 民法百選Ⅱ[第7版]58事件)。その理由として,同判決は,他人名義の建物の登記によっては,自己の建物の所有権さえ第三者に対抗できないものであり,自己の建物の所有権を対抗し得る登記があることを前提として,これをもって土地賃借権の登記に代えようとする同項の法意に照らし,かかる場合は,同法の保護を受けるに値しないことを挙げている。したがって,たとえ同居する家族名義の建物保存登記がある場合でも,土地賃借権の第三者に対する対抗力は認められない。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅱ231~232頁。
川井(4)236頁。 -
刑法甲は,乙に対して,V方への住居侵入窃盗を唆したところ,乙は強盗の目的でV方に侵入し,在宅していたVに対して,財物奪取の目的で暴行を加えて,金品を強取した。この場合,甲には,V方への住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯が成立する。刑法結果正解解説判例は,教唆者が,住居侵入窃盗を教唆したところ,被教唆者が住居侵入強盗を行った事例において,「犯罪の故意ありとなすには……犯人が認識した事実と,現に発生した事実とが……犯罪の類型(定型)として規定している範囲において一致(符合)することを以て足る」とした上で,「Yの判示住居侵入強盗の所為が,Xの教唆に基いてなされたものと認められる限り,Xは住居侵入窃盗の範囲において,右Yの強盗の所為について教唆犯としての責任を負う」としている(最判昭25.7.11 刑法百選Ⅰ[第7版]89事件)。したがって,甲には,V方への住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯(刑法130条前段,235条,61条1項)が成立する。よって,本記述は正しい。参考山口(刑法)172頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法を直接実施するのは,国会の権限であるから,政令で憲法を直接実施することは認められないと一般に解されている。憲法結果正解解説内閣は,「憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。」(憲法73条6号本文)が認められているため,文言上は,内閣が憲法を直接実施するために政令を制定することができるかのように読める。しかし,立法権は原則として国会にあり(同41条),憲法を直接実施するのは,国会の権限であるから,同73条6号本文の「憲法及び法律」は,一体として読むべきであると解されている。したがって,政令で憲法を直接実施することは認められないと一般に解されている。よって,本記述は正しい。参考芦部(憲法)297頁。
野中ほか(憲法Ⅱ)210~211頁。
注解憲法Ⅲ18~19頁。
新基本法コメ(憲法)392頁。 -
民法判例によれば,被相続人の全財産の包括遺贈を受けた共同相続人の一人に対し,遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合において,遺留分権利者に帰属する権利は,遺留分割の対象となる相続財産としての性質を有する。民法結果正解解説判例は,「遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合,遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し,受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するところ……,遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない」としている(最判平8.1.26 家族法百選[第6版]99事件)。その理由として,同判決は,「特定遺贈の目的とされた特定の財産は……直ちに受遺者に帰属し,遺産分割の対象となることはなく,また,民法は,……遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者,受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえる」とし,「特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有」せず,包括遺贈は,「特定遺贈とその性質を異にするものではない」ことを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅳ520~523頁。
川井(5)238頁。 -
刑法責任主義の観点から,結果的加重犯の成立には,基本犯についての故意のほか,重い結果についての過失を要する。刑法結果正解解説判例は,夫が妻に暴行を加え,その結果妻をショック死させた事例において,「傷害罪の成立には暴行と死亡との間に因果関係の存在を必要とするが,致死の結果についての予見を必要としない」としている(最判昭32.2.26 刑法百選Ⅰ[第7版]50事件)。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法129頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法八幡製鉄事件判決(最高裁判所昭和45年6月24日大法廷判決,民集24巻6号625頁)は,会社が,政治的行為をなす自由を有するとしても,政治資金の寄附は政治の動向に影響を与えることに鑑みると,会社の政治資金の寄附は国民による寄附と別異に扱わなければならないとした。憲法結果正解解説本記述の最高裁判所判決(最大判昭45.6.24 八幡製鉄事件 憲法百選Ⅰ[第6版]9事件)は,「会社は,自然人たる国民と同様,国や政党の特定の政策を支持,推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する」とした上で,「政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり,会社によってそれがなされた場合,政治の動向に影響を与えることがあったとしても,これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」としている。よって,本記述は誤りである。
-
民法割賦金弁済契約において,債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合,債務者が割賦金の支払を1回怠ったときは,その時から残債務全額について当然に消滅時効が進行する。民法結果正解解説判例は,「割賦金弁済契約において,割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には,一回の不履行があっても,各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し,債務者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり,その時から右全額について消滅時効が進行する」としている(最判昭42.6.23 民法百選Ⅰ[第3版]48事件)。よって,本記述は誤りである。参考川井(1)371~372頁。
-
刑法公務員甲は,乙から,職務上何かと世話になった謝礼と併せて将来も好意ある取扱いを受けたいとの趣旨で現金を収受した。この場合,甲に単純収賄罪が成立することはあっても,受託収賄罪が成立することはない。刑法結果正解解説判例は,「「請託を受け」とは,将来一定の職務行為をすることの依頼を受けることを意味する」としている(最判昭30.3.17)。そうすると,何かと世話になった謝礼と併せて将来も好意ある取扱いを受けたいとの趣旨で現金を供与した場合,一定の職務行為の依頼があったとはいえないから,「請託」には当たらないことになる。したがって,甲に受託収賄罪(刑法197条1項後段)が成立することはない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)500頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法尊属殺重罰規定判決(最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決,刑集27巻3号265頁)は,尊属殺の法定刑は,それが死刑又は無期懲役刑に限られている点においてあまりにも厳しいものというべく,尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重といった立法目的のみをもってしては,これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり,合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することは到底できないとした。憲法結果正解解説本問の判決は,「尊属殺の法定刑は,それが死刑または無期懲役刑に限られている点……においてあまりにも厳しいものというべく,……立法目的,すなわち,尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみをもってしては,これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり,合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはとうていできない」としている。よって,本記述は正しい。
なお,同判決は,上記判示部分に続けて,削除前の「刑法200条は,尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において,その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え,普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ,憲法14条1項に違反して無効であるとしなければならず,したがって,尊属殺にも刑法199条を適用するのほかはない」としている。 -
民法判例によれば,扶養義務者が過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合における各自の分担額については,協調が調わない限り,家庭裁判所が,各自の資力その他一切の事情を考慮して審判によって定める。民法結果正解解説判例は,「扶養義務者の一人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に,過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合……,各自の分担額は,協議が整わないかぎり,家庭裁判所が,各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであって,通常裁判所が判決手続で判定すべきではない」としている(最判昭42.2.17 民法百選Ⅲ51事件)。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅳ301頁。
川井(5)134~135頁。 -
刑法私人である甲は,行使の目的で,虚偽の記載をした証明書発行申請書を提出し,情を知らない公務員をして内容虚偽の証明書を作成させた。甲は,作成権限のある公務員を利用して内容虚偽の公文書を作成させたので,甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,「刑法は,いわゆる無形偽造については公文書のみに限ってこれを処罰し,……公文書の無形偽造についても同法156条の他に特に公務員に対し虚偽の申立を為し,権利義務に関する公正証書の原本又は免状,鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法157条の処罰規定を設け,しかも右156条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない点から見ると公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない趣旨と解する」としている(最判昭27.12.25)。したがって,本記述の甲には,虚偽公文書作成罪(刑法156条)の間接正犯は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考山口(刑法)400頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法天皇が未成年のときや国事行為を自らすることができないと皇室会議で判定されたときには,当然に摂政が置かれる。憲法結果正解解説摂政(憲法5条,皇室典範16条)とは,天皇が未成年のときや重大な事故により国事行為を自ら行うことができない場合に,天皇に代わってその行為を行う法定代理機関である。摂政は,天皇の委任に基づく臨時代行(憲法4条2項)とは異なり皇室典範の定める原因が生じたときに法律上当然に設置される。したがって,天皇が未成年のときや重大な事故により国事行為を自らすることができないときには,当然に摂政が置かれる。よって,本記述は正しい。参考野中ほか(憲法Ⅰ)133~135頁。
-
民法契約により,承役地の所有者が,自己の費用で地役権者の地役権行使のために承役地に工作物を設ける義務を負担した場合であっても,承役地の所有者は,いつでも,地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで,当該義務を免れることができる。民法結果正解解説契約によって承役地の所有者が負担した地役権行使のために工作物を設ける義務は,いつでも,地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで,免れることができる(民法287条,286条)。これは,本来義務は放棄することができないが,地役権行使のために工作物を設ける義務は,いわば土地の所有者が負担するものであるから,土地の所有権を放棄して地役権者に移転することで,その義務を免れると考えられるためである。よって,本記述は正しい。参考我妻・有泉コメ503頁。
-
刑法甲は,わいせつな写真を外国で販売しようと考え,日本国内にある自宅においてこれらを保管した。甲にはわいせつ物有償頒布目的所持罪が成立しない。刑法結果正解解説判例は,「刑法175条の規定は,わが国における健全な性風俗を維持するため,日本国内において猥せつの文書,図画などが頒布,販売され,又は公然と陳列されることを禁じようとする趣旨に出たものである」とした上で,わいせつ物有償頒布目的所持罪(刑法175条2項)における「有償で頒布する目的」の意義について,「日本国内において販売する目的をいうものであり,したがって,猥せつの図画等を日本国内で所持していても日本国外で販売する目的であったにすぎない場合には」同罪は成立しないとしている(最判昭52.12.22 刑法百選Ⅱ[第5版]100事件)。したがって,甲には,わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考西田(各)400頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,法律の委任に基づいて条例で罰則を定めることも可能であるところ,条例は地方公共団体の議会によって制定される民主的立法であるから,行政府の制定する命令への罰則の委任が個別的・具体的なものでなければならないのとは異なり,条例への罰則の委任は一般的・包括的なもので足りる。憲法結果正解解説罰則を定める条例によって処罰された者が,当該条例は憲法31条に違反するとして争った事例において,判例は,「条例は,法律以下の法令といっても,上述のように,公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にし,むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから,条例によって刑罰を定める場合には,法律の授権が相当な程度に具体的であり,限定されておればたりると解するのが正当である」としている(最大判昭37.5.30 憲法百選Ⅱ[第6版]215事件)。つまり,条例への罰則の委任は,一般的・包括的なものでは足りず,相当な程度に具体的であり限定されたものでなければならない。よって,本記述は誤りである。
-
民法主たる債務の違約金についての定めがない場合には,保証債務に違約金についての定めをしても,その効力を生じない。民法結果正解解説保証人は,その保証債務についてのみ,違約金又は損害賠償の額を約定することができる(民法447条2項)。これは,保証債務は主たる債務と別個の債務であるし,このような約定は保証債務自体の拡張ではないから,保証債務の付従性にも反しないことに基づく。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ348頁。
川井(3)210頁。
我妻・有泉コメ837頁。 -
刑法病院を経営する甲は,A県立大学のB医局に属する医師を派遣してもらった謝礼として,A県立大学の臨床医学教室教授乙に500万円を交付した。この場合,乙がB医局の長であり,そこに属する医師の指導教育について権限を有し,また,その採用及び昇進についての実質的な決定権及びB医局と一定の関係を有する外部の病院への医師の派遣について最終的な決定権を有していたときは,B医局に属する医師の派遣は,乙の本来の職務である自己が属する臨床医学教室に属する医師の指導教育と密接に関連する行為であるから,甲には贈賄罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,本記述と同様の事例において,県立医大の教授であり,同大学付属病院救急外科部長でもあった者が,自ら指導教育する医師を被告人の経営する関連病院に派遣した行為は,「医師を教育指導するというその職務に密接な関係のある行為」に当たるとし,被告人が医師の派遣について便宜ある取り計らいを受けたことなどの謝礼等の趣旨の下に金員を供与した行為は贈賄罪(刑法198条)に当たるとしている(最決平18.1.23 平18重判刑法10事件)。したがって,甲に贈賄罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考西田(各)495頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法政見放送としての品位を損なう言動を禁ずる公職選挙法の規定は,テレビジョン放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響力を有していることに鑑み,そのような言動が放送されることによる弊害を防止する目的で政見放送の品位を損なう言動を禁止したものであるから,当該規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,法的に保護された利益とはいえない。憲法結果正解解説判例は,参議院議員選挙の立候補者が政見放送の録音・録画に際し,差別的用語を使用したため,放送事業者が当該部分の音声を削除して放送したところ,当該立候補者が政見をそのまま放送される権利が侵害されたとして損害賠償を求めた事例において,政見放送としての品位を損なう言動を禁ずる公職選挙法の規定は,「テレビジョン放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響力を有していることにかんがみ,そのような言動が放送されることによる弊害を防止する目的で政見放送の品位を損なう言動を禁止したものであるから,右規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,法的に保護された利益とはいえず,したがって,右言動がそのまま放送されなかったとしても,不法行為法上,法的利益の侵害があったとはいえない」としている(最判平2.4.17 憲法百選Ⅱ[第6版]162事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法質権設定者は,相当の担保を供すれば,質権の消滅を請求することができる。民法結果正解解説留置権については,債務者は相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができるが(民法301条),質権については,このような規定はない。留置権は,質権とは異なり法定担保物権であり,設定契約に基づいて成立するのではないため,その成立の際に債務者は,被担保債権額と目的物の価額との均衡を考慮に入れることができない。それゆえ,留置権においては,被担保債権額が目的物の価額に比して僅少になるという債務者に不利益な場合が質権に比して多く生じ得るため,同条が特に規定されたものである。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ507頁。
我妻・有泉コメ515頁。
注釈民法(8)76頁。 -
刑法甲は,自動車を利用して犯罪を行うに当たり,自己所有の実態を隠ぺいするために,自動車登録ファイルに新規登録する際に,乙が所有者であるかのような虚偽の登録をすることを企て,同自動車の所有者等が乙である旨の虚偽の内容を記載した登録申請書に必要な書類を添えて,情を知らない運輸局の自動車登録官をして自動車登録ファイルにその旨の不実の記録を作出させた。甲には電子計算機使用詐欺罪が成立する。刑法結果正解解説電子計算機使用詐欺罪の客体である「財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」とは,財産権の得喪・変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって,一定の取引場面において,それが作出されることにより事実上当該財産権の得喪・変更が生じるものであると解されている。本記述における自動車登録ファイルは,自動車の所有権関係を公証するものであり,その変更によって財産権の得喪・変更を生じないため,これに当たらないと解されている。したがって,甲には同罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考西田(各)216頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,地方自治体が課税権の主体となることは憲法上予定されているが,租税の賦課については国民の税負担全体の程度や国と地方との間ないし普通地方公共団体相互間の財源の配分等の観点からの調整が必要である。憲法結果正解解説判例は,税収の安定と法人課税における負担の公平性を図るため外形標準課税が導入されるまでの臨時的措置として繰越欠損金の額に相当する所得を課税標準として課税するとした神奈川県臨時特例企業税条例の違法性が争われた事例において,地方自治の本旨に従って憲法94条所定の事務を「行うためにはその財源を自ら調達する権能を有することが必要である」から,「地方公共団体は,地方自治の不可欠の要素として,……国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されている」ところ,「租税の賦課については国民の税負担全体の程度や国と地方の間ないし普通地方公共団体相互間の財源の配分等の観点からの調整が必要である」としている(最判平25.3.21 神奈川県臨時特例企業税事件 憲法百選Ⅱ[第6版]208事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法法学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が弁護士になった時に返済する。」と約束していたが,司法修習を経て進路変更し,検察官になった場合,Aは,Bに対する借入金の返済債務を免れる。民法結果正解解説本記述において,「弁護士になった時」との約束が履行期に条件を付けたものであれば,条件が成就しない限り履行期は到来せず,結局BはAに金銭を贈与したに等しいことになるから,Aは借入金返済債務を免れることになるが,履行期に期限(不確定期限)を付けたものであれば,期限の到来までただ返済が猶予されているにすぎず,Aはその債務を免れることはできないことになる。判例は,消費貸借契約における債務の履行期を債務者の出世の時とするのは,停止条件ではなく不確定期限であるとしている(大判明43.10.31,大判大4.3.24)。したがって,本記述においても,Aは,Bに対する借入金の返済義務を免れることができない。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅰ301~302頁。
川井(1)296~297頁。 -
刑法甲は,夜道を歩いているAに対し殺意をもって拳銃を発射したところ,銃弾がAの身体を貫通した後,Aの傍らを一緒に歩いていたBにも命中して,A及びBの両名を死亡させた。甲がAと共に歩いているBの存在を認識していなかった場合でも,甲にはA及びBに対する殺人罪が成立する。刑法結果正解解説判例は,「犯罪の故意があるとするには……犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく,両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる……から,人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上,犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも,右の結果について殺人の故意がある」として,およそ人を殺す意思で人の死亡の結果を生じさせた以上,認識していた犯罪事実について故意犯が成立するほか,発生した犯罪事実についても結果の数だけ故意犯が成立することを認めている(最判昭53.7.28 刑法百選Ⅰ[第7版]42事件)。したがって,甲にはA及びBに対する殺人罪(刑法199条)が成立する。よって,本記述は正しい。参考条解刑法142~143頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第82条第1項は,手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨であり,このような公開裁判の原則は傍聴の自由を内容として含んでいるものの,国民は,憲法第82条第1項を根拠に,裁判を傍聴することを権利として要求することはできない。憲法結果正解解説判例は,刑事訴訟規則215条の合憲性を争われた事例において,憲法82条1項は「手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨」としている(最大決昭33.2.17 北海タイムス事件 憲法百選Ⅰ[第6版]76事件)。また,判例は,一般の傍聴者が法廷でメモを取ることを禁止しながら,司法記者クラブ所属の報道記者に対してはこれを許可していた裁判長の措置の合憲性が争われた事例において,憲法82条1項は「各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより,傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも,いうまでもないところである」としている(最大判平元.3.8 レペタ事件 憲法百選Ⅰ[第6版]77事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法管理者は,本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときを除き,善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。民法結果正解解説管理者は,「本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは,悪意又は重大な過失があるのでなければ,これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」とする緊急事務管理の規定(民法698条)の反対解釈として,事務管理における管理者は,原則として,善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負うとされている。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅱ557~558頁。
川井(4)361~362頁。 -
刑法14歳に満たない者であっても,精神鑑定の結果,事物の是非善悪を弁識する能力やその弁識に従って行動する能力を成人と同程度に有していると認められた場合には,刑罰が科せられることがある。刑法結果正解解説14歳に満たない者の行為は,罰せられない(刑法41条)。これは,事物の理非善悪を弁識する能力やその弁識に従って行動する能力の有無にかかわらず,政策的に年齢による一律的処理をするものである。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法167頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,憲法第81条は「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定するが,「処分」には裁判所の判決も含まれる。憲法結果正解解説判例は,憲法81条の「処分」に裁判所の判決が含まれるか否かについて,「憲法第81條によれば,最高裁判所は,一切の法律,一切の命令,一切の規則又は一切の處分について違憲審査權を有する。裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく,個々の事件について具體的處置をつけるものであるから,その本質は一種の處分であることは言うをまたぬところである。法律,命令,規則又は行政處分の憲法適否性が裁判の過程において終審として最高裁判所において審判されるにかかわらず,裁判の憲法適否性が裁判の過程において終審として最高裁判所において審判されない筈はない。否,一切の抽象的規範は,法律たると命令たると規則たるとを問わず,終審として最高裁判所の違憲審査權に服すると共に,一切の處分は,行政處分たると裁判たるとを問わず,終審として最高裁判所の違憲審査權に服する」としている(最大判昭23.7.8 憲法百選Ⅱ[第6版]195事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法債権者の一人に対する弁済が詐害行為に当たるとして,他の債権者がその弁済を取り消して受益者に対して受け取った金銭の返還を請求した場合、受益者は,自己の債権額に応じた按分学についてもその返還を拒むことはできない。民法結果正解解説判例は,債権者の一人に対する弁済が詐害行為に当たるとして他の債権者から提起された詐害行為取消訴訟において,受益者が,取消債権者からの金銭支払請求に対して自己の債権額に対応する按分額の支払を拒絶することはできないとしている(最判昭46.11.19 民法百選Ⅱ[第7版]19事件)。その理由として,同判決は,按分額の支払を拒絶することを認めると,いち早く自己の債権につき弁済を受けた受益者を保護し,総債権者の利益を無視することになり,総債権者のために債務者の一般財産を保全するという詐害行為取消権の制度趣旨(民法425条参照)に反することになることを挙げている。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅲ329~330頁。
川井(3)165~166頁。 -
刑法弁護人が,偽造された証拠について,その事情を知りつつ裁判所にその取調べを請求した場合,証拠隠滅等罪は成立しない。刑法結果正解解説偽造又は変造された証拠の「使用」とは,偽造又は変造された証拠を真正の証拠として,裁判所や捜査機関に提供することをいうところ,判例は,弁護人が,被疑者の偽造した証拠をそれと知りながら検察官に提出してその取調べを請求する行為を,証拠隠滅等罪(刑法104条)の「使用」に当たるとしている(大判大7.4.20)。よって,本記述は誤りである。参考条解刑法317頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第1条は,天皇は,「日本国の象徴」である旨定めているから,天皇の行為が憲法に規定されている国事行為であるかどうかにかかわらず,その行為の効果は日本国に帰属することになる。憲法結果正解解説天皇は国家機関として国事行為を行い(憲法4条1項),その効果は日本国に帰属することになる。他方,天皇は,当然のことながら私人としての私的行為を行うことができ,その効果は天皇に帰属する。よって,本記述は誤りである。参考芦部(憲法)51頁。
野中ほか(憲法Ⅰ)136頁。 -
民法無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,賃借人と転借人との間で転貸借契約が締結された時から進行する。民法結果正解解説判例は,無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権(民法612条2項)は,転借人が,賃借人(転貸人)との間で締結した転貸借契約に基づき,当該土地について使用収益を開始した時から,その行使が可能となったものということができるから,その消滅時効は,転借人が転貸借契約に基づき土地の使用収益を開始した時から進行するとしている。(最判昭62.10.8 昭和62重判民法3事件)。よって,本記述は誤りである。参考川井(1)374頁。
我妻・有泉コメ331~332頁。 -
刑法横領罪の「占有」とは,物に対して事実上又は法律上の支配力を有する状態をいうところ,既登記不動産については,所有権登記名義人以外に,不動産を事実上支配している不動産の賃借人にも占有が認められる。刑法結果正解解説横領罪の「占有」は,事実上又は法律上物に対する支配力を有する状態をいい(大判大4.4.9),登録済みの不動産については,登録簿上所有者として表示されている者だけが占有者であり(大判明44.2.3),不動産の賃借人のように不動産を事実上支配しているにとどまる者には占有は認められない。よって,本記述は誤りである。参考高橋(各)360~361頁。
裁判例コンメンタール刑法第3巻397頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法夫婦同氏を定めた民法第750条について,夫婦同氏を受け入れられない者らの婚姻に事実上の制約が生ずるとしても,そのような事実上の制約は,婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものか否かを検討するに当たって,考慮すべき事項とはならない。憲法結果正解解説判例は,夫婦別姓を望む者にとって,夫婦同氏を定めた民法750条が憲法13条,14条1項,24条に反しないかが争われた事例において,民法750条の「規定は,婚姻の効力の一つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではない。仮に,婚姻及び家族に関する法制度の内容に意に沿わないところがあることを理由として婚姻をしないことを選択した者がいるとしても,これをもって,直ちに上記法制度を定めた法律が婚姻をすることについて憲法24条1項の趣旨に沿わない制約を課したものと評価することはできない。ある法制度の内容により婚姻をすることが事実上制約されることになっていることについては,婚姻及び家族に関する法制度の内容を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる」としている(最大判平27.12.16 平成28重判憲法7事件)。よって,本記述は誤りである。
-
民法期間の定めがある建物の賃貸借契約において,契約の更新がない旨を定めるためには,賃貸人は,賃借人に対し,賃貸借契約の締結に先立って,契約の更新がなく,期間の満了により契約は終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず,かかる説明をしなかったときは,借地借家法の法定更新の規定が適用される。民法結果正解解説定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは,建物の賃貸人は,あらかじめ,建物の賃借人に対し,契約の更新がなく,期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(借地借家法38条2項)。かかる説明を怠ったときは,契約の更新がないこととする定めは,無効となる(同条3項)。したがって,この場合,借地借家法の法定更新の規定が適用されることとなる。よって,本記述は正しい。
なお,判例は,同「条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する」としている(最判平24.9.13 平24重判民法9事件)。参考内田Ⅱ199頁。
川井(4)265頁。 -
刑法精神の障害があったとしても,それにより事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力が著しく減退していなければ,心神耗弱と認める余地はない。刑法結果正解解説判例は,心神耗弱(刑法39条2項)とは,精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力が著しく減退した状態をいうとしている(大判昭6.12.3 刑法百選Ⅰ[第4版]33事件)。よって,本記述は正しい。参考注釈刑法(1)615~616頁。
西田(総)280頁。
山口(刑法)134頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第35条は,令状に,捜索する場所及び押収する物を明示することを要求しているにとどまり,その令状が正当な理由に基づいて発せられたことを明示することまでは要求していない。憲法結果正解解説判例は,捜索差押許可状(刑訴法219条1項)における「捜索すべき場所」,「差し押さえるべき物」の記載が憲法35条1項の特定性の要件を満たすか,及び差押目的物の特定との関係で「罪名」に罰条を付記すべきかが争われた事例において,「憲法35条は,……令状に,捜索する場所及び押収する物を明示することを要求しているにとどまり,その令状が正当な理由に基づいて発せられたことを明示することまでは要求していない」としている(最大決昭33.7.29 憲法百選Ⅰ[第2版]101事件,刑訴法百選[第10版]A5事件)。よって,本記述は正しい。参考佐藤幸(日本国憲法論)325頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)293頁。
新基本法コメ(憲法)274頁。 -
民法定期預金の返還期限が当事者双方の利益のために定められている場合,銀行Aは,預金者Bに対し,期限までの利息を支払えば,期限の利益を一方的に放棄することができる。民法結果正解解説期限の利益は,原則として単独で放棄することができるが,これにより相手方の利益を害することはできない(民法136条2項)。もっとも,期限の利益の放棄により相手方が被る損害を賠償すれば,期限の利益を放棄することができると解されている。判例も,銀行は,預金者に期限までの利息を支払えば,期限の利益を一方的に放棄することができるとしている(大判昭9.9.15 民法百選Ⅰ[第3版]43事件)。したがって,本記述においても,銀行Aは,預金者Bに対し,期限までの利息を支払えば,期限の利益を一方的に放棄することができる。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅰ306頁。
川井(1)306頁。 -
刑法甲は,乙とVが殴り合いのけんかをしているのを見掛け,乙に肩入れして,「いっそのことVを叩きのめしてしまえ。」などと申し向けたところ,これにより乙は,犯罪意思を強固にして,Vの腹部を強く蹴るなどして同人に加療約1週間を要する胸腹部打撲の傷害を負わせた。この場合,甲には現場助勢罪が成立する。刑法結果正解解説本記述において,甲は,声援を送ることで乙に精神的な援助を与え,これによって,乙の実行行為の遂行を促進しているため,甲には傷害罪の幇助犯(刑法204条,62条1項)が成立する。そして,判例は,現場助勢罪(同206条)は,傷害の現場における単なる助勢行為を処罰するものであって,特定の正犯を幇助する幇助犯とは区別されるものであるとして,傷害罪の幇助犯が成立する場合には,現場助勢罪は成立しないとしている(大判昭2.3.28)。よって,本記述は誤りである。参考山口(各)48頁。
高橋(各)54頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,法律による具体化を予定しているところ,判例は,これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではないとしている。憲法結果正解解説判例は,郵便業務従事者によって,書留郵便物や特別郵便物が滅失・毀損された際の損害賠償額を制限していた郵便法旧68条,73条が,憲法17条に違反しないかが争われた事例において,同条の趣旨につき,「公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない」としている(最大判平14.9.11 郵便法違憲判決 憲法百選Ⅱ[第6版]133事件)。よって,本記述は正しい。
-
民法Aが,その所有する未登記の甲建物をBに譲渡した後,重ねて甲建物をCに譲渡した場合において,甲建物が未登記のままであるときは,先の譲渡が優先するから,Bは,Cに対し,甲建物の所有権の取得を対抗することができる。民法結果正解解説判例は,不動産の取得については,当該不動産が未登記であっても民法177条の適用があり,取得者は,その旨の登記を経なければ,取得後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,自己の権利の取得を対抗することができないとしている(最判昭57.2.18 不動産取引百選[第3版]36事件)。したがって,本記述において,甲建物が未登記のままであっても,先の譲渡が優先するのではなく,登記のないBは,Cに対してその所有権の取得を対抗することができない。よって,本記述は誤りである。参考川井(1)42頁。
判例コメ民法(3)65頁。 -
刑法甲が,Vが所有しているが現に居住していない家屋に放火したところ,同家屋は全焼し,延焼することを予期していなかったAの居住する家屋も延焼した場合,甲には延焼罪が成立する。刑法結果正解解説延焼罪(刑法111条)は,自己所有非現住建造物等放火罪(同109条2項)又は自己所有建造物等以外放火罪(同110条2項)を犯したときにのみ成立する。本記述において,甲が放火しているのは,V所有の家屋という他人所有の非現住建造物であり,甲はA宅に延焼させる意思はないことから現住建造物等放火罪の故意もない。したがって,甲には他人所有非現住建造物等放火罪が成立し,延焼罪は成立しない。よって,本記述は誤りである。参考基本刑法Ⅱ377頁。
条解刑法332頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法最高裁判所の判例によれば,特定事項についてこれを規律する国の法律と条例とが併存する場合,後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであるときは,国の法令と条例との間には何らの接触はなく,条例が国の法令に違反する問題は生じ得ない。憲法結果正解解説判例は,公安条例と道路交通法との抵触の有無が争点となった事例において,「条例が国の法令に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば,ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも,当該法令全体からみて,右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは,これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし,逆に,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも,後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり,その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや,両者が同一の目的に出たものであっても,国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく,それぞれの普通地方公共団体において,その地方の実情に応じて,別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは,国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく,条例が国の法令に違反する問題は生じえない」としている(最大判昭50.9.10 徳島市公安条例事例 憲法百選Ⅰ[第6版]88事件)。したがって,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合,後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであっても,その適用によって国の法令の規定の意図する目的と効果を阻害するときは,国の法令と条例との間に矛盾牴触があり,条例の規定は国の法令に違反することになり得る。よって,本記述は誤りである。
-
民法判例によれば,債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係にある。民法結果正解解説判例は,被担保債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続とは,前者が後者に対し先履行の関係にあり,同時履行の関係に立たないとしている(最判昭57.1.19)。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ526頁。
-
刑法多量に飲酒すると心神喪失の状態に陥る素質を有する者は,日頃から飲酒を控えるなどして他人に害悪を及ぼす危険を防止する義務があるから,同人がこの義務を怠った結果として心神喪失に陥って殺人行為に及んだ場合,自己の上記素質を自覚している限り,過失致死罪の罪責を免れない。刑法結果正解解説判例は,「多量に飲酒するときは……心神喪失の状態において他人に犯罪の害悪を及ぼす危険ある素質を有する者は居常右心神喪失の原因となる飲酒抑止又は制限する等前示危険の発生を未然に防止するよう注意する義務」があり,「心神喪失時の所為であったとしても……己れの素質を自覚していたものであり且つ……事前の飲酒につき前示注意義務を怠ったがためであるとするならば」過失犯の責任を免れないとしている(最大判昭26.1.17 刑法百選Ⅰ[第7版]37事件)。したがって,本記述においては過失致死罪が成立する。よって,本記述は正しい。参考条解刑法163~164頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法宗教法人に対する解散命令が確定したときは,精算手続が開始され,宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していた物も処分されることになるから,信者らが行ってきた宗教上の行為を法的に制約する効果を一定程度伴うことになる。憲法結果正解解説判例は,宗教法人法に基づく解散命令の合憲性が争われた事例において,「解散命令は,信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも,宗教法人の解散命令が確定したときはその精算手続が行われ……,その結果,宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから……,これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る」としている(最決平8.1.30 宗教法人オウム真理教解散命令事件 憲法百選Ⅰ[第6版]42事件)。したがって,宗教法人の解散命令の確定は,宗教上の行為の禁止・制約という法的効果を一切伴わず,礼拝施設など宗教上の行為の用に供していた宗教法人所有の財産を用いた宗教上の行為に支障が生じることはあり得るものの,これは事実上のものである。よって,本記述は誤りである。
-
民法AはBに対して甲土地を売却し引き渡したが,Bが弁済期経過後も代金を支払わなかったため,Aが,Bに対し,解除のための催告をするに当たり,Bが代金を催告から所定の期間内に支払わない場合には甲土地の売買契約を解除する旨の意思表示をすることは,単独行為に条件を付することになるため,許されない。民法結果正解解説単独行為に条件を付することは,相手方の地位を不安定にするため,原則として許されない(民法506条1項後段参照)。もっとも,判例は,単独行為であっても,解除の意思表示については,例外的に,契約当事者の一方が同541条の催告をするに当たり,所定の期間内に相手方が債務を履行しない場合には,改めて解除の意思表示をすることなく契約を解除する旨の停止条件付解除の意思表示も有効であるとしている(大判明43.12.9)。このような条件は,相手方の地位を不安定にしないからである。したがって,本記述においても,Aは,Bに対し,Bが代金を催告から所定の期間内に支払わない場合には甲土地の売買契約を解除する旨の意思表示をすることも許される。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅰ303頁。
川井(1)295~296頁。 -
刑法甲は,Aを債務者とする虚偽の支払督促を申し立ててAから金員を得ようと企て,Aから異議申立ての機会を奪うため,裁判所から発送された支払督促正本をAを装って郵便配達員から受領し,直ちに廃棄した。この場合,甲が同正本を受領した点について,甲に同正本を廃棄するだけの意思しかなかったときには,不法領得の意思を欠き,甲には詐欺罪は成立しない。刑法結果正解解説判例は,「郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について,廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかった場合には,支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできない」として,詐欺罪(刑法246条1項)の成立を否定している(最決平16.11.30 刑法百選Ⅱ[第7版]31事件)。したがって,甲に詐欺罪は成立しない。よって,本記述は正しい。参考リーガルクエスト(刑法各論)152頁。
西田(各)159頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法天皇は,憲法第99条により憲法尊重擁護義務を負っているため,内閣の助言に憲法に反する行為を求める内容が含まれる場合には,天皇としてはこの内閣の助言に基づく行為を拒否しなければならないことになる。憲法結果正解解説憲法第99条は,国務大臣,国会議員,裁判官などのほかに,天皇,摂政に対し憲法尊重擁護義務を課している。そこで,天皇に対する内閣の助言に憲法に反する行為を求める内容が含まれているとした場合,天皇は憲法尊重擁護義務を理由に,この内閣の助言に基づく行為を拒否することができるかが問題となり得るが,天皇は内閣の助言に応じることこそが,まさに憲法尊重擁護義務の内容であると解する立場からは,天皇は内閣の助言に従うべきであるとされる(同3条,4条1項参照)。よって,本記述は誤りである。参考安西ほか(憲法学読本)32~33頁。
リーガルクエスト(憲法Ⅰ)24~25頁。 -
民法不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,被害者又はその法定代理人が損害の発生を現実に認識し,かつ,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度に加害者を知った時から起算する。民法結果正解解説不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する(民法724条前段)。判例は,同条の「損害」を知った時の意義について,「民法724条は,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて,消滅時効の起算点に関して特則を設けたのであるから,……同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう」としている(最判平14.1.29 平14重判民法9事件)。また,判例は,同様に「加害者を知った時」の意義について,「民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは,同条で時効の起算点に関する特則を設けた趣旨に鑑みれば,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに,その可能な程度にこれを知った時を意味する」としている(最判昭48.11.16 民法百選Ⅱ[第7版]103事件)。よって,本記述は正しい。参考内田Ⅱ473~474頁。
川井(4)529~531頁。 -
刑法手形の割引を依頼された者が,割引によって得た金額を依頼者に引き渡すために保管中に,依頼者に対して有する金銭債権と相殺する意思でこれを自己の用途に費消した場合,横領罪の「不法領得の意思」が認められない。刑法結果正解解説判例は,横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは,「他人の者の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意志をいう」としているところ(最判昭24.3.8 刑法百選Ⅱ[第7版]65事件),相殺の意思を有する場合には,不法領得の意思は認められないとされている。裁判例は,本記述と同様の事例において,不法領得の意思を欠くとして,横領罪の成立を否定している(名古屋高判昭36.7.31)よって,本記述は正しい。参考高橋(各)377~378頁。
裁判例コンメンタール刑法第3巻418頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法再婚禁止期間を定めた改正前民法第733条第1項の規定の憲法適合性を検討するに当たっては,婚姻をするについての自由が憲法第24条第1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものであり,改正前民法第733条第1項の規定が婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっているという事柄の性質を十分考慮に入れる必要がある。憲法結果正解解説判例は,女性の再婚禁止期間を定めた改正前民法733条1項(以下「本件規定」という。)が憲法14条1項,24条2項に反しないか争われた事例において,「同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するもの」であり,本件規定が「婚姻制度に関わる立法として,婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている」という事柄の性質を「十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である」としている(最大判平27.12.16 平成28重判憲法6事件)。よって,本記述は正しい。参考曹時69巻5号235~236頁。
-
民法所有権に基づく返還請求訴訟において,被告が原告に対する債権を被担保債権とする留置権の抗弁を主張し,これが認められた場合であっても,当該被担保債権の消滅時効は中断しない。民法結果正解解説判例は,所有権に基づく株券返還請求訴訟上で,当該株券の費用償還請求権を被担保債権とする留置権の抗弁が主張された事例において,「被担保債権の債務者を相手方とする訴訟における留置権の抗弁は被担保債権につき消滅時効の中断の効力がある」としている(最大判昭38.10.30)。その理由として,同判決は,留置権によって単に目的物を留置する場合と異なり,「訴訟において留置権の抗弁を提出する場合には,留置権の発生,存続の要件として被担保債権の存在を主張することが必要であり,裁判所は被担保債権の存否につき審理判断をなし,これを肯定するときは,被担保債権の履行と引換に目的物の引渡をなすべき旨を命ずるのであるから,かかる抗弁中には被担保債権の履行さるべきものであることの権利主張の意思が表示されているものということができる」としている。よって,本記述は誤りである。
なお,同判決は,「固より訴訟上の留置権の主張は反訴の提起ではなく,単なる抗弁に過ぎないのであり,訴訟物である目的物の引渡請求権と留置権の原因である被担保債権とは全く別個な権利なのであるから,目的物の引渡を求むる訴訟において,留置権の抗弁を提出し,その理由として被担保債権の存在を主張したからといって,積極的に被担保債権について訴の提起に準ずる効力があるものということはできない」として,「請求」(民法147条1号)としてではなく,「催告」(同153条)としての中断の効力を認めている。参考内田Ⅰ321~324頁。
川井(1)332~333頁。 -
刑法犯行時の精神状態が心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは主として臨床精神医学的な判断であるから,裁判所は,複数の精神鑑定の意見のうちいずれを採用すべきかを選択することができるにとどまり,選択した精神鑑定の意見は全面的に採り入れなければならない。刑法結果正解解説判例は,「責任能力の有無・程度の判断は,法律判断であって,専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり,その前提となる生物学的,心理学的要素についても,上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である」として,「専門家たる精神医学者の精神鑑定等が証拠となっている場合においても,鑑定の前提条件に問題があるなど,合理的な事情が認められれば,裁判所は,その意見を採用せずに,責任能力の有無・程度について,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができ……,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく,上記事情等を総合して判定することができる」としている(最決平21.12.8 刑法百選Ⅰ[第7版]35事件)。したがって,裁判所は,精神鑑定の意見を採用しないこともできるし,採用した精神鑑定の意見を全面的に採り入れなければならないわけでもない。よって,本記述は誤りである。参考西田(総)282~284頁。
正解率
科目名
科目名 正解率
解答日・解答結果
設問
解答
-
憲法公立校の生徒が,信仰上の理由により,その通学する学校の定めた教育課程の履修を一部拒否する場合,学校側は生徒の信仰に配慮した代替措置を講ずる義務を生じるから,そのような代替措置を講ずることもないまま,信仰上の理由による当該科目の履修拒否ということを主たる理由として,原級留置や退学という重大な不利益処分をすることはできない。憲法結果正解解説判例は,公立の高等専門学校での剣道実技の履修を信仰上の理由から拒否したため最終的に退学処分を受けたことを争った事例において,「信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を,正当な理由のない履修拒否と区別することなく,代替措置が不可能というわけでもないのに,代替措置について何ら検討することもなく,体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて,原級留置処分をし,さらに,不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく,二年続けて原級留置となったため進級等規定及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成績の見込みがないと認められる者」に当たるとし,退学処分をしたという上告人の措置は,考慮すべき事項を考慮しておらず,又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き,その結果,社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく,本件各処分は,裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない」としている(最判平8.3.8 エホバの証人剣道拒否事件 憲法百選Ⅰ[第6版]45事件)。同判決は,一般論として,信仰上の理由による履修拒否の場合に,学校側としては,生徒の信仰に配慮した代替措置を講ずる義務が生じると判示しているのではなく,代替措置を講じることもないまま,信仰上の理由による剣道実技の履修拒否ということを主たる理由として,結果として原級留置,退学という重大な不利益処分をしたことが,本件において裁量権の濫用になると判断しているにすぎない。よって,本記述は誤りである。参考平8最高裁解説(民事)196~197頁。
-
民法共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象とならない。民法結果正解解説詐害行為取消権は,「債務者が債務者を害することを知ってした法律行為」を対象とするが(民法424条1項本文),「財産権を目的としない法律行為」は,その対象とならない(同条2項)。そして,判例は,「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象となり得る」としている(最判平11.6.11 民法百選Ⅲ68事件)。その理由として,同判決は,遺産分割協議は,相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について,その全部又は一部を,各相続人の単独所有とし,又は新たな共有関係に移行させることによって,相続財産の帰属を確定させるものであり,その性質上,財産権を目的とする法律行為であるといえることを挙げている。よって,本記述は誤りである。参考内田Ⅲ308頁。川井(3)156頁。
-
刑法新聞記者である甲による取材行為が国家公務員法上の守秘義務違反のそそのかし罪に該当したが,当該取材行為は,真に報道の目的からでたものであり,その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものであった。この場合,甲の取材行為の違法性は阻却される。刑法結果正解解説判例は,報道機関の取材行為に秘密漏示そそのかし罪(国家公務員法100条1項,109条12号,111条)が成立するかが問題となった事例において,「直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく,報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは,それが真に報道の目的からでたものであり,その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは,実質的に違法性を欠き正当な業務行為」であるとしている(最決昭53.5.31 外務省機密漏洩事件 刑法百選Ⅰ[第7版]18事件)。よって,本記述は正しい。参考山口(総)107~108頁。
西田(総)200頁。